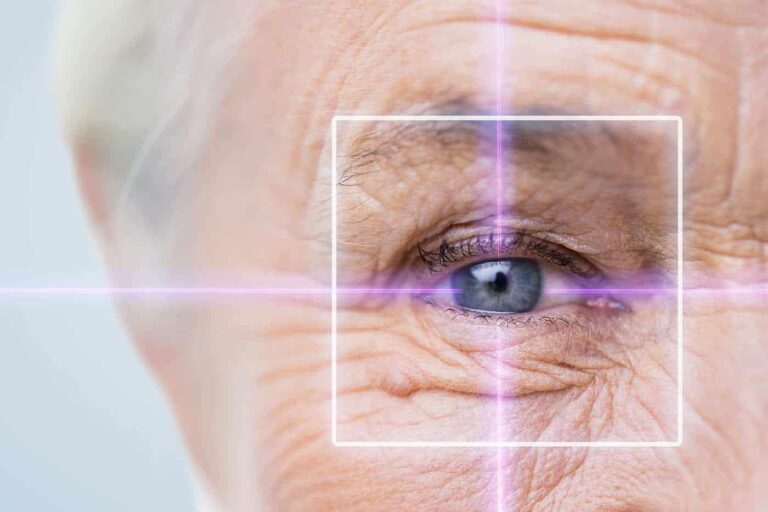眼の病気とは(構造・働き・加齢と疾患の関係)
「最近、手元が見えにくい」「目がかすむ」「もしかして病気だろうか」——目の不調は、私たちの生活の質(QOL)に直結するため、小さな変化でも大きな不安を感じるものです。この総合ガイドページは、そうした目の病気に関するあらゆる疑問や不安にお答えするために構築されています。
[cite_start]
この最初のセクションでは、すべての理解の基礎となる「目とはどのような器官か」について、深く掘り下げていきます。具体的には、目が持つ精密な構造と「見える」という驚くべき仕組み、そして多くの人が避けて通れない「加齢」が目にどのような影響を与え、なぜ様々な病気につながりやすくなるのかを、日本眼科学会や厚生労働省の示す見解に基づき、 [cite: 1] わかりやすく解説します。
本記事は医療情報を提供するものであり、個別の医療アドバイスではありません。症状がある場合は医療機関を受診してください。
目はなぜカメラに例えられるのか(角膜・水晶体・網膜の役割)
[cite_start]
眼科医や専門家が目の仕組みを説明するとき、よく「カメラ」に例えられます。これは、複雑な目の働きを直感的に理解する上で非常に分かりやすい比喩です。日本眼科学会の資料によれば、[cite: 1] 私たちの目(眼球)は、直径約24mmほどの小さな球体ですが、その中には最先端のカメラにも劣らない、驚くほど精密な部品が詰まっています。
まず、光が目に入ってくる最初の「窓」が角膜(かくまく)です。これはカメラの「レンズの表面(保護フィルターとレンズの一部)」にあたります。角膜は完全に透明でなければならず、ここで外から入ってきた光の大部分が屈折(光を曲げること)されます。この角膜のカーブが均一でなかったり、眼球の奥行き(眼軸長)とのバランスが崩れたりすると、ピントが合わなくなります。これが、乱視や近視といった屈折異常の主な原因の一つとなります。
角膜を通った光は、次に「絞り」の役割をする虹彩(こうさい)によって光の量が調節されます。これは日本人の多くが茶色い部分、いわゆる「黒目」と呼ばれる部分です。虹彩の中央にある穴が瞳孔(どうこう)です。明るい場所では虹彩が瞳孔を小さくし(光量を減らし)、暗い場所では大きく開いて(光量を増やし)、網膜に届く光の量を常に最適に保っています。
そして、カメラの「ピント調節レンズ」に相当するのが水晶体(すいしょうたい)です。日本眼科医会の説明にもある通り、 この透明なレンズは、その周りにある毛様体筋(もうようたいきん)という筋肉によって厚みを変え、遠くのものや近くのものに瞬時にピントを合わせます。この水晶体が加齢などによって白く濁ってしまう病気が、白内障です。
目の中の大部分を占めるのは、硝子体(しょうしたい)という透明なゼリー状の組織です。これは眼球の形を内側から支え、カメラの「暗箱(光が乱反射しないようにする空間)」の役割を果たします。光はこの硝子体を通過して、最終的にカメラの「フィルム(あるいはイメージセンサー)」にあたる網膜(もうまく)に到達します。
[cite_start]
網膜は、光を電気信号に変換するという非常に重要な役割を持つ、薄い神経の膜です。この膜には1億個以上の視細胞が敷き詰められています。特に、網膜の中心部にある黄斑(おうはん)は、最も感度が高く、私たちが物体の細部を認識したり、色を見分けたり、文字を読んだりするために使われる、視機能の「核」となる部分です。この黄斑部が障害されると、視力低下や物の歪みといった深刻な症状が現れます。網膜で変換された電気信号は、視神経(ししんけい)という100万本以上の神経線維の束(ケーブル)を通って脳に送られ、そこで初めて「見えた」と映像として認識されるのです。 [cite: 1]
加齢でまず落ちるのは“調節力”と“透明性”
「自分は若い頃、両目とも2.0だったから大丈夫」——そう思っていても、残念ながら加齢による目の変化は誰にでも訪れます。世界保健機関(WHO)も「人生のどこかの時点で誰もが少なくとも1つは眼の状態でケアを必要とする」と指摘しており、 視機能は加齢とともに様々な負荷が高まるものと世界的に認識されています。
最も多くの人が最初に自覚する加齢変化は、「ピント調節力の低下」、すなわち老視(ろうし)、一般に「老眼」と呼ばれる状態です。「老眼」と聞くとネガティブなイメージを持つかもしれませんが、これは水晶体のタンパク質が年齢とともに硬くなるために起こる生理的な現象です。若い頃は弾力性に富んでいた水晶体が硬くなるため、毛様体筋がどれだけ頑張って収縮しても、水晶体の厚みを十分に変えることができなくなります。その結果、近くのものにピントが合わなくなるのです。40代を過ぎた頃から「スマートフォンの文字が読みにくい」「レストランの薄暗い照明だとメニューが見えない」と感じ始めるのは、この調節力の低下が主な原因です。これは病気というより生理的な変化ですが、老視への適切な対処(老眼鏡の使用など)は、無理なピント合わせによる眼精疲労や頭痛を避け、生活の質を保つために非常に重要です。
もう一つの大きな変化は、「透明性の低下」です。カメラのレンズも長年使えば傷やくすみがつくように、目のレンズである水晶体も、数十年にわたって紫外線や体内の酸化ストレスにさらされることで、主成分であるタンパク質が徐々に変性し、透明性を失っていきます。これがゆっくりと進行した状態が白内障です。初期の段階では自覚症状はほとんどありませんが、徐々に「全体的にかすんで見える」「車のライトがやけにまぶしい」「色の区別がつきにくくなった」といった形で現れ始めます。
さらに、目の表面を守る「涙」にも変化が訪れます。涙は単なる水分ではなく、目の表面を滑らかにし、栄養を与え、細菌から守るバリア機能を持っています。しかし、加齢とともに涙の分泌量が減少したり、涙の蒸発を防ぐ「油層」の質が低下したりすることで、眼球の表面(角膜)が不安定になります。これが「目が乾く」「ゴロゴロする」「疲れやすい」「理由もなく涙が出る」といったドライアイ(乾き目)の症状を引き起こしやすくなります。これもまた、視界のかすみや疲れの原因となります。
アイフレイルとは?フレイルとの違いとセルフチェックの考え方
最近、日本の眼科領域で非常に重要視されているのが**「アイフレイル(Eye Frail)」**という概念です。これは、日本眼科学会などが中心となって提唱しているもので、「加齢に伴い眼の脆弱性(ぜいじゃくせい:もろさ)が増し、さまざまな要因が重なって視機能が低下した状態」を指します。
「フレイル」と聞くと、一般的に筋力や活力が低下した「虚弱」な状態(介護が必要になる手前の段階)を思い浮かべるかもしれません。アイフレイルもその考え方と同様に、「加齢による正常な目の衰え」と「明確な目の病気」の中間段階、あるいは病気の予備軍とも言える状態を示しています。この概念が非常に重要なのは、アイフレイルは「年だから仕方ない」と諦めるものではなく、**「早期に気づき、適切な介入(対策)をすれば、改善したり進行を抑制したりできる可逆的な段階」**を含むと定義されている点です。
なぜこの概念が今、強く提唱されているのでしょうか。それは、緑内障や加齢黄斑変性など、失明につながる可能性のある病気の多くが、初期段階では自覚症状に乏しく、気づいた時にはかなり進行しているケースが後を絶たないためです。「アイフレイル」という言葉で広く注意を喚起し、自覚症状がなくてもセルフチェックや定期検診を促すことが、将来の視機能低下や失明を防ぐための社会的な鍵となると考えられています。厚生労働省も、企業と連携して職場などでのアイフレイルチェックリストの活用を推進しており、 国民の健康課題として認識されています。
アイフレイルのセルフチェックには、以下のような項目が含まれます。もし一つでも当てはまるものがあれば、それは「年のせい」と自己判断せず、一度眼科で詳しい検査を受けるサインかもしれません。
- 以前と比べて、目が疲れやすくなった(パソコン作業などがつらいデジタル眼精疲労も含む)
- 新聞や本を読むとき、以前より強いメガネ(老眼鏡)が必要になった
- 物がかすんで見えることがある
- 明るい場所に出ると、以前よりまぶしく感じることが増えた
- 目が乾きやすい、または逆に涙が出やすい
- 両目で見ても、片方の目だけで見ても、見え方にあまり差がないか
これらの視力低下のサインに早く気づくことが重要です。また、日常的な紫外線対策(サングラスやUVカット眼鏡の使用)なども、目の脆弱化(特に白内障や黄斑変性)を防ぐために今日からできる重要な対策です。
加齢が引き金になりやすい代表的な目の病気の全体像
アイフレイルの状態、つまり「加齢によって目が脆弱になった状態」に気づかず、あるいは対策をせずに放置してしまうと、やがて本格的な眼疾患を発症するリスクが高まります。WHOの2019年の報告でも、 世界の視覚障害の主な原因は、未矯正の屈折異常(近視・老視など)、白内障、加齢黄斑変性、緑内障、糖尿病網膜症であり、そのほとんどが加齢や慢性疾患と強く関連しています。ここでは、特に加齢と関連が深い代表的な病気を概観します。
1. 白内障(Cataracts)
最も代表的な加齢性疾患です。前述の通り、水晶体のタンパク質が変性して濁る病気です。日本眼科医会も「加齢による変化がもっとも多い」と明記しており、 早い人では40代から始まり、80代を超えるとほとんどの人が何らかの白内障の状態にあるとされています。「かすむ」「まぶしい」「視力が落ちた」といった症状が生活に支障をきたすようになれば、手術が検討されます。幸い、現代では濁った水晶体を取り除き、人工の眼内レンズを挿入する手術が非常に安全に行われており、視力を取り戻すことが可能な病気の代表例です。
2. 緑内障(Glaucoma)
緑内障は、日本の成人の失明原因の第1位であり、非常に注意が必要な病気です。これは、何らかの理由で視神経(網膜からの情報を脳に送るケーブル)が障害を受け、視野(見える範囲)が徐々に欠けていく病気です。加齢とともに視神経自体が脆弱になったり、眼圧(目の内圧)の調節機能が低下したりすることが関与すると考えられています。緑内障の最も恐ろしい点は、病気がある程度進行するまで自覚症状がほとんどないことです。両目で見ていると、片方の目の視野が欠けていても脳が補完してしまうため、気づきにくいのです。「見える範囲が狭くなってきた」と本人が気づいた時には、すでに視神経の障害がかなり進行していることが多く、一度失われた視野は現代の医学では元に戻せません。だからこそ、緑内障の早期発見と治療開始が、視力を守るために極めて重要となります。
3. 加齢黄斑変性(Age-related Macular Degeneration: AMD)
欧米では歴史的に失明原因のトップですが、日本でも食生活の欧米化や高齢化に伴い急速に増加しています。これは、網膜の中心部である「黄斑」が、加齢による老廃物の蓄積や、それを処理しようとして発生する新生血管(新しくできる異常な血管)の影響で障害される病気です。黄斑は視機能の「中心」を担うため、ここが障害されると、「見たいものが歪んで見える」「中心が黒く暗く抜けて見える」といった、生活に直結する深刻な症状が現れます。厚生労働省の資料でも、 加齢黄斑変性は緑内障や糖尿病網膜症と並び、早期発見すべき病気として挙げられています。黄斑部の健康を保つことが、高齢期のQOLを維持するために不可欠です。
失明は高齢期に集中する―なぜ早期の眼底検査がすすめられるのか
「自分はまだはっきり見えているから大丈夫」—その考えが、目の健康において最も危険な落とし穴かもしれません。前述の緑内障や加齢黄斑変性、あるいは糖尿病の合併症である糖尿病網膜症といった、日本で失明につながる可能性のある病気の多くは、初期段階では自覚症状がほとんどないまま静かに進行します。
だからこそ、日本眼科学会や厚生労働省は、一致して「症状がなくても、40歳を過ぎたら定期的な眼科検診を」と強く呼びかけているのです。 特に重要なのが、眼底検査(がんていけんさ)です。これは、点眼薬で瞳孔を開き(または無散瞳カメラを使い)、瞳孔の奥にある眼底(網膜・視神経・血管)の状態を医師が直接観察する検査です。この検査によって、医師は網膜や視神経に緑内障や黄斑変性の初期異常が起きていないか、血管に動脈硬化や高血圧、糖尿病による変化(出血や詰まり)の兆候がないかを確認できます。これは、自覚症状が出るずっと前に、病気のサインを捉えることができるほぼ唯一の方法と言っても過言ではありません。
もちろん、すべての加齢変化が深刻な病気に直結するわけではありません。しかし、どれが「生理的な変化(アイフレイル)」で、どれが「病的な変化」の始まりなのかを、ご自身で見分けることは不可能です。例えば、失明に至る緊急疾患である網膜剥離の初期症状(飛蚊症:黒い点が飛ぶ)と、加齢による生理的な硝子体混濁(同じく飛蚊症)を、症状だけで区別することは困難です。
高齢期に視機能が低下すると、生活の質が著しく損なわれるだけでなく、転倒による骨折のリスク増加、認知機能の低下、社会的な孤立など、全身の健康にも連鎖的に悪影響を及ぼすことが知られています。40歳を過ぎたら、それは目の健康の「曲がり角」です。自分のため、そして大切な家族と将来の生活の質を守るために、定期的な眼科検診を「自分ごと」として捉え、習慣化することが何よりも大切です。
よくある質問(FAQ)
Q1: 年齢とともに見えにくくなるのは“老眼”だけですか?
A: いいえ。多くの人が最初に自覚するのはピント調節力の低下(老視)ですが、それだけではありません。加齢では同時に、水晶体の透明性低下(白内障の前段階)、涙の質と量の低下(ドライアイ)、網膜・視神経の脆弱化(緑内障や黄斑変性のリスク)など、複数の変化が重なって起こります。 日本眼科学会はこれらをまとめて「アイフレイル」と呼び、単なる老眼と片付けずに、早めのチェックを勧めています。
Q2: 40代で眼科検診を受ける意味はありますか?
A: 非常に大きな意味があります。緑内障や加齢黄斑変性は、40代から発症し始める方がいます。日本の行政資料(厚生労働省)でも、40歳以上の従業員にアイフレイルチェックや眼底検査を周知するよう求めており、 自覚症状の出にくいこれらの病気を早期発見するために、40歳は検診を開始する最適なタイミングとされています。
Q3: アイフレイルは病名ですか?
A: 病名ではありません。アイフレイルは、加齢によって目が弱くなった「状態」を指す言葉であり、病気の早期発見・早期介入を促すための“啓発用語”です。この段階で気づき、適切なセルフケアや治療を開始すれば、機能の回復や進行抑制が期待できる、というポジティブな側面を持っています。
Q4: 見えにくさが急に強くなったときはどうすればいいですか?
A: 「ゆっくりとした加齢変化」ではなく、「急な病的変化」の可能性が高いため、早急な(当日~翌日中の)眼科受診を強く勧めます。特に「視野の一部が黒く欠ける」「カーテンが降りてくる」「物がひどく歪む」「強い痛みを伴う」といった症状は、網膜剥離や急性緑内障発作、加齢黄斑変性の悪化など、緊急性の高い病気のサインである可能性があります。
受診の目安と症状別のサイン(視力低下・かすみ・痛み・充血・飛蚊症・視野欠損)
前のセクションでは、眼の基本的な構造や働き、加齢による変化について学びました。しかし、その繊細な眼に「いつもと違う」異常を感じたとき、「これはただの疲れなのか、それともすぐに病院へ行くべきなのか」と判断に迷い、不安になることは非常に多いでしょう。
このセクションでは、ご自身やご家族が判断するための一助として、受診の目安となる6つの代表的な症状(視力低下、かすみ、痛み、充血、飛蚊症、視野欠損)に焦点を当てます。どのような状態が危険なのか、その背後にどんな病気が隠れている可能性があるのかについて、厚生労働省の公式マニュアルやMayo Clinicなどの信頼できる医療機関の情報に基づき、詳しく、そして深く掘り下げて解説します。
受診を急ぐべき「緊急」のサイン(レッドフラグ)
まず最も重要なこととして、以下の症状が一つでも当てはまる場合は、自己判断で様子を見ず、直ちに(当日中または夜間・休日の場合は救急外来へ)眼科を受診してください。これらは、網膜剥離や、急性閉塞隅角緑内障など、治療が遅れると数時間から数日で深刻な視力障害や失明に至る可能性のある、非常に危険な疾患のサインです。
- 突然の急激な視力低下、または視野がカーテンのように欠ける感覚
- 強い目の痛みに加え、激しい充血、頭痛、吐き気、光がまぶしいといった症状を伴う
- 飛蚊症(黒い点や糸くずのようなものが見える)の数が突然、急激に増えた
- 飛蚊症の増加と同時に、閃光(暗い場所でピカッと光が見える「光視症」)を自覚する
- 化学薬品が目に入った、物が刺さった、強くぶつけたなどの明らかな外傷や異物感
- 片側の瞳孔がもう片方より明らかに大きい(瞳孔不同)
これらのサインは、時間との勝負です。迷わず専門医の診察を受けてください。
症状別に見る受診の目安
緊急サインには当てはまらないものの、注意が必要な症状について、その特徴と受診のタイミングを解説します。
視力低下(突然または徐々に)
突然の視力低下は上記の「緊急」サインに該当します。一方で、「最近、なんとなく見えにくい」といった緩やかな視力低下も注意が必要です。見逃してはいけない視力低下のサインとして、片目ずつ確認することが非常に重要です。私たちは普段、両目で見ているため、片方の視力が落ちていても、もう片方の健康な目が無意識に補ってしまい、異常の発見が遅れることがよくあります。ゆっくりとした視力低下であっても、白内障、緑内障、加齢黄斑変性、糖尿病網膜症などが静かに進行している可能性があるため、「年のせい」と自己判断せず、一度眼科で詳しい検査を受けることをお勧めします。
目のかすみ(霧視)
視界がぼやける、霧がかかったように見える原因は多岐にわたります。一時的な目の疲れ(眼精疲労)やドライアイでもかすみは生じますが、これらは通常、休息や点眼で改善します。しかし、かすみが数日たっても取れない場合や、痛み・充血を伴う場合は、角膜炎やぶどう膜炎(目の中の炎症)が疑われます。特に注意が必要なのは、かすみと同時に「電灯の光の周りに虹の輪が見える(虹視症)」症状がある場合です。これは、急性緑内障発作の危険な兆候である可能性があり、緊急の対応が必要です。
目の痛み(眼痛)
目の痛みの理由には、目の表面に原因があるものと、目の奥に原因があるものがあります。「ゴロゴロする」「しみる」「まばたきをすると痛い」といった表面的な痛みは、まつ毛やゴミなどの異物、ドライアイ、コンタクトレンズによる角膜の傷(角膜びらん)などが考えられます。一方で、目の奥が重く痛む、あるいは「えぐられるような激痛」の場合は、単なる眼精疲労だけでなく、前述の緑内障発作や視神経炎、あるいは副鼻腔炎など、より深刻な状態も疑われます。痛みが24時間以上続く、または視力低下を伴う場合は、速やかに受診してください。
目の充血
充血は最も一般的な症状の一つです。アレルギーやウイルスの感染による結膜炎(はやり目)が原因のことが多いです。また、痛みのないべったりとした充血(結膜下出血)は、見た目は派手ですが、多くの場合1〜2週間で自然に治癒します。しかし、Mayo Clinicなども警告するように、充血に「視力低下」「強い痛み」「まぶしさ」「色のついた目やに」を伴う場合は、単純な結膜炎ではなく、角膜潰瘍や強膜炎、ぶどう膜炎など、視力障害につながる病気の可能性があるため、緊急性が高まります。感染性の結膜炎が疑われる場合は、学校や仕事を休む必要があるかどうかの判断や、他人にうつさないための対策も必要です。
飛蚊症(ひぶんしょう)
目の前に黒い点や透明な糸くず、アメーバのようなものが飛んで見える症状です。多くは加齢によって眼球内の硝子体(しょうしたい)が濁る「生理的飛蚊症」であり、この場合は心配いりません。しかし、米国国立眼研究所(NEI)は、「数が急に増える」「閃光(光視症)を伴う」「視野の一部が欠ける」という3つの症状を、網膜剥離や網膜裂孔(網膜に穴が開くこと)の危険なサインとしています。これらは緊急のレーザー治療や手術が必要になるため、直ちに眼科を受診してください。
視野欠損(見える範囲が欠ける)
視野(見える範囲)が欠ける、または狭くなる症状は、最も重大なサインの一つです。「カーテンがかかったように一部が見えない」場合は網膜剥離が強く疑われ、緊急手術が必要です。また、厚生労働省のマニュアルでも、急激な視野欠損は視神経障害や網膜の血管閉塞など、治療が遅れると不可逆的な(元に戻らない)ダメージにつながる疾患の症状としています。特に緑内障は、自覚症状がないまま周辺の視野からゆっくりと欠けていくため、本人が気づいた時にはかなり進行しているケースが少なくありません。見え方に少しでも違和感があれば、検査を受けることが推奨されます。
市販の目薬で様子を見てよい期間は?
充血や軽いかすみ、疲れ目、かゆみなどに対して市販の目薬を使用する方も多いでしょう。非常に多くの種類があり、手軽に試せる一方で、いつまで使い続けてよいのかは知っておく必要があります。
厚生労働省の資料では、アレルギー用や抗菌性の点眼薬を含め、市販薬を5〜6日間使用しても症状が改善しない場合、または悪化する場合は、安易に自己判断で継続せず、眼科医や薬剤師に相談するよう推奨しています。
特に、充血を素早く取ることを目的とした「血管収縮剤」が含まれる目薬は、一時的に白目をきれいにしますが、長期連用すると薬が切れた際にリバウンドでかえって充血を悪化させることがあります。市販の目薬の正しい選び方を理解し、上記の「緊急サイン」がないことを確認した上で、期間を決めて使用することが重要です。
特に注意が必要な方(基礎疾患・小児・高齢者)
すべての人に共通するサインとは別に、特定の背景を持つ方は、より低いハードルで、より早期の受診が強く推奨されます。
- 糖尿病・高血圧の方: 国立国際医療研究センターは、糖尿病の方は自覚症状がなくても年1回以上の眼底検査を推奨しています。かすみや飛蚊症を自覚した時点では、糖尿病網膜症がかなり進行している可能性があるため、「早期」ではなく「直ち」の受診が必要です。高血圧による眼底(網膜の血管)への影響も、動脈硬化の進行を知る上で重要です。
- 特定の薬を服用中の方: ステロイド(内服・点眼)、抗不整脈薬(アミオダロン)、一部の抗がん剤や免疫抑制剤などは、副作用として眼圧上昇(緑内障)や角膜、網膜に影響を与えることが知られています。これらの治療中にかすみや視力低下が出た場合は、市販薬で様子を見ずに、必ず処方医と眼科医に相談してください。
- お子様の場合: 子供の視力低下は、本人がうまく症状を言葉で伝えられないことがあります。保護者の方が「目を細めて物を見る」「まぶしがる」「テレビに極端に近づく」「片目を閉じて見ている」「視線が合わない気がする」などの行動変化に気づいたら、弱視や斜視、先天性の疾患の可能性も考慮し、小児眼科を受診してください。
- 高齢者の場合: 「直線がゆがんで見える」「読んでいる文字の中心が暗く見える」といった症状は、加齢黄斑変性の代表的なサインです。早期の治療開始が視力維持に不可欠ですので、見え方の「質」の変化に注意してください。
よくある質問(FAQ)
Q1: 目が充血して市販の目薬をさしても治りません。何日続いたら眼科に行くべきですか?
A: 厚生労働省の資料では、充血やかゆみなどの症状が5〜6日間続いても改善しない場合は、市販薬の漫然とした使用を中止し、眼科医を含む専門家に相談することを推奨しています。もし強い痛みや視力低下、まぶしさなどを伴う場合は、5〜6日を待たずに直ちに受診してください。
Q2: 飛蚊症が急に増えて光が走るのですが、様子を見てもいいですか?
A: いいえ、様子を見るのは非常に危険です。それは網膜剥離やその前段階である網膜裂孔の典型的な初期症状である可能性が非常に高いです。米国国立眼研究所(NEI)なども、これらの症状が出た場合は直ちに眼科専門医に連絡するよう強く推奨しています。放置すると手術が困難になったり、失明に至る可能性があるため、すぐに受診してください。
Q3: 片目だけがかすんで見えるのですが、両目で見ると普通に見えるので急ぎませんか?
A: 急いで受診することを推奨します。片方の目の視力や視野に異常が出ても、もう片方の健康な目が情報を補ってしまうため、両目で見ていると異常に気づきにくいものです。しかし、その裏では網膜や視神経の重要な病気が進行している可能性があります。必ず片目ずつ見え方をチェックし、片方に異常を感じたら早めに眼科を受診してください。
Q4: 目が赤くて痛いのですが、内科でも診てもらえますか?
A: 目の痛みと充血が同時にある場合、角膜潰瘍や急性緑内障発作など、眼圧測定や細隙灯顕微鏡といった眼科専門の検査・処置が必要な病気が隠れています。厚生労働省のマニュアルでも「一刻も早い眼科専門医での対応が望まれる」とされており、まずは眼科を受診することを強く推奨します。夜間や休日で眼科が開いていない場合は、救急外来で眼科医の診察が可能か相談してください。
これらの症状に気づき、眼科を受診することを決めたら、次に「どんな検査をされるのだろう」という不安が出てくるかもしれません。次のセクションでは、視力検査や眼圧検査、眼底検査など、眼科で行われる基本的な検査の流れと、それぞれの検査で何がわかるのかについて詳しく解説していきます。
検査の流れと基本(視力・眼圧・眼底・OCT・蛍光眼底造影・角膜/視野検査)
前節では、「見えにくい」「痛い」「何かが飛んで見える」といった、目が発する様々なSOSサインについて詳しく見てきました。そうした不安を抱えて眼科を訪れるとき、「一体どんな検査をされるのだろうか」「痛い検査はないだろうか」と、多くの方が緊張されることでしょう。本セクションは、そうした不安を和らげるための一助となるものです。眼科で行われる基本的な検査の流れ、それぞれの検査が持つ目的、そして医師がそのデータから何を読み取ろうとしているのかを、一歩ずつ丁寧に解説していきます。なぜこの検査が必要なのかを理解することは、ご自身の目の状態を把握し、安心して治療に進むための大切な第一歩です。ここでは、眼科診療の土台となる「基本検査」から、より精密な診断に不可欠な「専門検査」まで、その役割と流れを紐解いていきます。
眼科初診でまず行う基本検査の流れ
眼科の診察室に入ると、多くの場合、まずいくつかの基本的な検査が順番に行われます。これは、医師が目の状態を多角的に、そして効率的に把握するための「標準的なルート」のようなものです。通常、まずは問診で自覚症状や既往歴を伺い、その後、視力検査、眼圧検査、そして細隙灯顕微鏡(さいげきとうけんびきょう)検査と呼ばれる診察が行われます。細隙灯顕微鏡は、医師が目の表面(結膜や角膜)から目の内部(水晶体や硝子体)までを拡大して直接観察する、眼科診療の核となる診察です。これらの基本検査は、いわば「目の健康診断」の基礎セットであり、ここでの所見が、さらに詳しい検査に進むべきかどうかの分かれ道となります。
例えば、眼鏡店でも視力を測ることはできますが、日本眼科学会が指摘するように、眼科での一連の検査は「病気を見逃さない」ことを最大の目的としています。単に近視や乱視の度数を調べるだけでなく、その視界のぼやけが、白内障や緑内障、網膜の病気といった治療が必要な疾患の初期症状でないかをふるい分ける(スクリーニングする)重要な役割を担っています。この基本フローで得られた情報(例えば「視力が出にくい」「眼圧が高い」「水晶体が濁っている」)に基づき、医師は「どの病気が疑わしいか」を絞り込み、次のステップとしてOCTや視野検査といった追加の精密検査を指示するのです。
視力・屈折検査でわかること/わからないこと
「C」のマーク(ランドルト環)や数字、ひらがなを使った視力検査は、眼科診療の「出発点」であり、最も基本的な情報源です。多くの方がご自身の「裸眼視力」(何も矯正しない状態での視力)を気にされますが、眼科医がそれ以上に重視するのが「矯正視力」(眼鏡やコンタクトレンズで矯正した状態での最高視力)です。なぜなら、この矯正視力の値が、目の健康状態を判断する大きな手がかりとなるからです。気球の絵などを見る「オートレフラクトメーター」という機械で近視や乱視の度数を測定した後、検査員がレンズを入れ替えながら矯正視力を測定します。
ここで最も重要なのが、この「矯正視力」がどこまで出るか、という点です。もし眼鏡やコンタクトレンズで適切に矯正して、視力が1.0(またはその年齢での期待値)まで良好に出る場合、見えにくさの原因は主に近視・遠視・乱視といった「屈折異常」や、調節力の低下(老眼)である可能性が高いと判断されます。しかし、どれだけ正確な度数で矯正しても視力が上がらない、あるいはかすみが取れない場合、それは単なる屈折異常の問題ではなく、光の通り道(角膜、水晶体)や、光を感じるフィルム(網膜)、情報を脳に送るケーブル(視神経)のどこかに、病的な異常が隠れている可能性を強く示唆します。この「矯正しても視力が上がらない」という所見こそが、医師が白内障、網膜疾患、緑内障などを疑い、次の精密検査(眼底検査やOCT)に進むかどうかの重要な判断材料となるのです。日本眼科学会も手引きで明言している通り、視力検査は単なる度数合わせではなく、眼疾患の発見につながる重要なプロセスであり、視力低下のサインを見逃さないことが、目の健康を守る上で極めて重要です。
眼圧検査の種類と正常値の考え方
「目に風を当てられる検査」として知られる眼圧検査は、多くの方が少し苦手とされるかもしれませんが、緑内障を早期に発見するために非常に重要な検査です。眼圧とは、眼球の内部の圧力のことで、目の形状を一定に保つための「タイヤの空気圧」のようなものです。この圧力が(その人の視神経が耐えられるレベルを超えて)高くなりすぎると、視神経が圧迫されて傷つき、視野(見える範囲)が徐々に欠けていく緑内障を引き起こす可能性があります。主流の検査方法は2種類あり、一つは空気を吹き付けて測定する「非接触式(ノンコンタクト)トノメトリー」、もう一つは点眼麻酔をして医師が直接器具を角膜に当てる「圧平式(ゴールドマン)トノメトリー」です。一般的には、まず非接触式でスクリーニングを行い、数値が高い場合や緑内障が強く疑われる場合に、より精密な圧平式で再測定することが多いです。
ここで知っておくべき最も重要な事実は、日本人に多い「正常眼圧緑内障」の存在です。これは、眼圧の測定値が一般的に「正常範囲」とされる21mmHg以下であるにもかかわらず、視神経が傷んで視野欠損が進行してしまうタイプです。日本眼科学会の緑内障診療ガイドラインでも、眼圧は緑内障の最も重要なリスク因子であるとしながらも、眼圧値だけを基準に診断しないよう注意喚起しています。眼圧は一日の中でも変動し、測定する時間帯によっても変わります。また、角膜の厚さによっても測定値は影響を受け、角膜が厚い人は実際より高く、薄い人は実際より低く出ることがあります。特にレーシックなどの屈折矯正手術を受けた方は角膜の厚さが変化しているため、その点を医師に申告することが正確な状態把握につながります。したがって、眼圧はあくまで診断材料の一つであり、後述する眼底検査(視神経の形状)や視野検査(機能の低下)と組み合わせて総合的に判断されます。
OCTと眼底造影の違いと使い分け
視力検査や眼底の診察で「目の奥(網膜)」に異常が疑われた場合、現代の眼科診療ではOCT(光干渉断層計)と蛍光眼底造影という2つの精密検査が中心的な役割を果たします。この二つは、しばしば混同されがちですが、目的と方法が全く異なります。OCTは「網膜のCTスキャン」のように構造(厚みや層)を調べる検査、眼底造影は「網膜の血管地図」のように血流(漏れや詰まり)を調べる検査、とイメージすると分かりやすいでしょう。
OCT(光干渉断層計)は、目に触れることなく、近赤外線を当てて網膜の断面図を撮影する検査です。検査は数分で終わり、痛みも眩しさもほとんどありません。この検査の登場により、これまで平面でしか捉えられなかった網膜を「立体的に」評価できるようになりました。これにより、黄斑浮腫(網膜のむくみ)の程度や、加齢黄斑変性における新生血管の活動性、緑内障による視神経線維の菲薄化(薄くなること)を、ミクロン単位の精度で数値化・画像化できます。非侵襲的であるため、治療効果の判定のために繰り返し行える点が最大の強みです。
一方、蛍光眼底造影(FAまたはIA)は、腕の静脈から造影剤(フルオレセインやインドシアニングリーン)を注射し、眼底カメラで連続的に撮影することで、網膜や脈絡膜の「血流」そのものを可視化する検査です。造影剤が血管を流れていく様子を捉えることで、血管が詰まっている場所、血液成分が漏れ出している場所、異常な新生血管の有無などを正確に特定できます。網膜出血を引き起こす糖尿病網膜症、網膜血管閉塞症、加齢黄斑変性のタイプ診断やレーザー治療の計画において、非常に重要な情報を提供します。ただし、造影剤を使用するため、ごく稀にアレルギー反応のリスクが伴います。そのため、最新の診療ガイドラインでは、特に加齢黄斑変性の経過観察などでは非侵襲的なOCTでの評価を優先する場面が増えており、造影検査は初回診断時や病状に大きな変化が疑われる際など、適応を慎重に判断して行われる傾向にあります。検査は、日本眼科学会の安全実施基準に基づき、アレルギー歴の確認や救急薬剤の準備のもとで万全の体制で行われます。
角膜・視野など追加で行う専門検査のタイミング
基本検査やOCT検査に加え、特定の状態をより深く評価するために、角膜検査や視野検査が追加されることがあります。これらの検査は全員に行われるわけではなく、疑われる病気や治療方針の決定に必要な場合に選択されます。
角膜検査は、目の最も外側にある透明な「窓」である角膜の形状や、その内側にある細胞(角膜内皮細胞)の健康状態を詳しく調べる検査です。例えば「角膜形状解析(トポグラフィー)」は、角膜の表面が歪んでいないか(不正乱視)や、円錐角膜という病気がないかを診断するために行われます。これは、安全なコンタクトレンズの処方、特にハードコンタクトレンズや、屈折矯正手術(レーシックやICL)の適応を判断する上で不可欠な検査です。また、「角膜内皮細胞検査」は、角膜の透明性を維持するために重要な細胞の数を測定し、白内障手術などの内眼手術を安全に行えるかを判断する材料となります。
一方、視野検査は、一点を注視したまま「見える範囲(上下左右の広さ)」と「見える感度」を測定する検査です。これは日本眼科学会も指摘するように、緑内障の診断と進行判定に必須の検査です。緑内障は、自覚症状がないままゆっくりと視野が欠けていく病気だからです。検査には、自動で光の感度を測定する「静的視野検査(ハンフリーなど)」と、光を動かしながら見える範囲の境界線を調べる「動的視野検査(ゴールドマンなど)」があり、病状に応じて使い分けられます。OCTが視神経の「構造の変化」(神経線維の薄さ)を捉えるのに対し、視野検査は「機能の変化」(実際に見えにくい範囲)を捉えます。この二つを定期的に組み合わせることで、緑内障の進行をより早期にかつ正確に把握することができます。また、網膜剥離の一部や、脳の病気(脳梗塞や脳腫瘍)によっても特有の視野欠損が起こることがあり、原因を切り分けるためにも重要な検査です。
よくある質問
Q1: 眼科の検査はどれくらい時間がかかりますか?
A: 検査内容によって大きく異なります。視力検査、眼圧検査、細隙灯顕微鏡での診察といった基本的な検査のみであれば、受付から会計まで30分から1時間程度で終わることが一般的です。ただし、目の奥(網膜)を詳しく調べるために散瞳(さんどう:目薬で瞳孔を開くこと)が必要な場合は、目薬が効くまでに20~30分、診察後に眩しさやピントが合うまで数時間かかるため、半日ほど余裕を見る必要があります。さらに蛍光眼底造影や複数の視野検査を行う場合は、検査自体に30分~1時間程度かかるため、合計で1~2時間以上になることもあります。検査内容は医師が症状や疑われる病気に応じて判断します。
Q2: OCTと蛍光眼底造影はどちらが詳しいのですか?
A: どちらが「詳しい」かは、知りたい情報によります。OCTは造影剤を使わず、網膜の「構造」や「厚み(むくみ)」を断層写真で見るのに非常に優れており、緑内障の神経線維の厚さや黄斑浮腫の程度の経過観察に威力を発揮します。一方、蛍光眼底造影は、造影剤を使って血管の「血流」や「漏れ・詰まり」をリアルタイムで見る検査です。糖尿病網膜症や網膜血管閉塞症、加齢黄斑変性の活動性を正確に診断するのに適しています。現在は、まず非侵襲的なOCTで評価し、治療方針の決定や初回診断のために造影検査を追加する、という使い分けが主流です。
Q3: 眼圧が正常でも視野検査をするのはなぜですか?
A: 非常に重要なご質問です。日本では、眼圧が正常範囲(21mmHg以下)であるにもかかわらず緑内障が進行する「正常眼圧緑内障」が、緑内障全体の7割以上を占めると報告されています。つまり、眼圧測定だけでは緑内障の多くを見逃してしまう危険性があります。そのため、緑内障診療ガイドラインでは、眼圧だけでなく、眼底検査で視神経の形状(構造)を確認し、さらに視野検査で実際に「見えにくい」範囲(機能)を確認することを診断基準としています。眼圧が正常でも、視神経の形に異常があったり、OCTで神経線維の減少が見られたりした場合は、視野検査で機能的な障害が出ていないかを確認する必要があるのです。
Q4: 造影検査は危険ではありませんか?
A: 蛍光眼底造影は、腕の静脈から造影剤を注射する医療行為であり、リスクがゼロではありません。最も多い副作用は、検査中の一時的な吐き気や、検査後の皮膚・尿の黄染(数日で消失)です。ごく稀(数万~数十万件に1件程度)に、アレルギー反応(じんましん、呼吸困難、血圧低下など)が起こる可能性があり、海外の医療機関でも安全管理の重要性が指摘されています。そのため、日本眼科学会の安全実施基準では、検査前に必ずアレルギー歴や喘息、心臓病、腎臓病などの有無を詳細に確認し、万が一の事態に備えて救急蘇生薬剤や設備を準備した上で、医師の厳重な監督下で行うよう定められています。不安な点は、検査前に必ず医師にご相談ください。
白内障(原因・症状・手術・術後ケア)
前節では、視力検査や眼底検査など、眼科で行われる基本的な検査の流れについて詳しく見てきました。そうした検査、特に中高年になってからの検診で最も多く見つかる代表的な眼の疾患が「白内障(はくないしょう)」です。
「白内障と診断されました」と告げられたとき、多くの方が「これは大変な病気なのでは?」「失明してしまうのではないか?」と大きな不安を感じるかもしれません。しかし、白内障は加齢とともに誰にでも起こり得る、いわば「眼の白髪」のようなものです。実際、世界保健機関(WHO)も、治療可能な失明原因の第一位として白内障を挙げており、適切に対処すれば視力を取り戻せる病気の代表です。
このセクションでは、白内障とは具体的にどのような状態なのか、なぜ起こるのか、どのような症状が出たら注意すべきか、そして最新の治療法である手術と術後のケアについて、深く掘り下げて解説します。視界がぼやける、かすむといった症状は他の病気の可能性もありますが、白内障特有の事情を理解することで、過度な不安を和らげ、適切な次のステップに進む助けとなるはずです。
白内障とは?水晶体が濁るメカニズムと主な種類
私たちの眼は、よく高性能なカメラに例えられます。その中でも「レンズ」の役割を果たしているのが「水晶体(すいしょうたい)」です。水晶体は直径約9mm、厚さ約4mmの透明な凸レンズ状の組織で、入ってきた光を集め、網膜(カメラのフィルムにあたる部分)にピントを合わせる重要な働きを担っています。
健康な水晶体は完全に透明で、光をきれいに透過させます。しかし、何らかの原因でこの水晶体の中身(主にタンパク質と水分)が変性し、白く濁ってしまう状態、これが「白内障」です。レンズが曇りガラスや、すりガラスのようになってしまうため、光がうまく網膜まで届かなくなったり、レンズの中で光が乱反射したりして、「見えにくい」「かすむ」といった症状が現れます。
白内障にはいくつかの種類がありますが、原因によって大きく分けられます。
- 加齢性白内障(かれいせい):
最も多いタイプで、白内障の原因の8割以上を占めます。主な原因は加齢による水晶体タンパク質の変性や酸化ストレスの蓄積です。個人差はありますが、60代で約70%、80代になるとほぼ100%の人に何らかの白内障の所見が見られるとされています。 - 併発白内障(へいはつ):
眼の他の病気(例:ぶどう膜炎、緑内障、網膜剥離など)や、全身の病気(例:糖尿病、アトピー性皮膚炎)に合併して発症します。また、ステロイド薬の長期使用によっても引き起こされることがあります。 - 外傷性白内障(がいしょうせい):
眼を強く打つなどの怪我によって水晶体が傷つき、濁るタイプです。 - 先天性白内障(せんてんせい):
生まれつき水晶体に濁りがあるタイプです。視力の発達を妨げ、弱視の原因となるため、このセクションで扱う加齢性とは異なり、早期の診断と治療(手術)が非常に重要になります。(詳細は「小児の眼疾患」のセクションで解説します)
このほか、喫煙(WHOはリスク因子として指摘)や、長期間にわたる強い紫外線の曝露(UVB)も、白内障の発症を早める危険因子として知られています。若い頃からサングラスや帽子で紫外線対策をすることは、将来の白内障予防につながる可能性があります。
白内障の具体的な症状:「かすみ」「まぶしさ」の正体
白内障の症状は、水晶体の「どこが」「どの程度」濁っているかによって、人それぞれ異なります。多くの場合、ゆっくりと進行するため、初期段階では自覚症状がないことも少なくありません。「なんとなく見えにくい」と感じていても、「年のせいだろう」と見過ごしてしまうケースが非常に多いのです。
しかし、進行するにつれて、以下のような特徴的な症状が現れます。これらの症状は、単なる視力低下とは異なる「見え方の質」の変化です。
- 視界がかすむ・ぼやける(霧視):
最も一般的な症状です。水晶体の濁りによって光がうまく透過できず、網膜に鮮明な像を結べなくなります。よく「すりガラス越しに見ているよう」「霧がかかったよう」と表現されます。眼鏡やコンタクトレンズの度数を変えても、このかすみは改善しません。 - 光をまぶしく感じる(羞明):
水晶体の中で光が乱反射するため、特に明るい場所でまぶしさを強く感じるようになります。具体的には、「晴れた日の屋外がまぶしくて目を開けていられない」「対向車のヘッドライトが異常ににじんで見える」「夜間の運転が怖くなった」といった症状が現れます。米国のメイヨー・クリニックも、この羞明を主要な症状の一つとして挙げています。 - 物が二重・三重に見える(単眼複視):
片方の目で見ても、物がダブって見えることがあります。これは、濁った水晶体の中を光が不規則に通るために起こります。 - 色の見え方が変わる:
水晶体の中心部(核)が濁るタイプ(核白内障)では、水晶体自体が黄色〜茶褐色に着色していきます。これにより、青系の色が認識しにくくなり、視界全体がセピア色、あるいは黄色っぽく見えることがあります。 - 一時的に近くが見やすくなる(近視化):
核白内障が進行すると、水晶体の屈折力(光を曲げる力)が強まり、一時的に近視の状態になることがあります。もともと遠視だった人が「最近、老眼鏡なしでも近くの文字が読めるようになった」と喜ぶことがありますが、これは「第二の視力(セカンドサイト)」と呼ばれる現象で、白内障が進行しているサインである可能性が高いです。
重要なことは、これらの症状は痛みや充血を伴わずに、ゆっくりと進行するのが典型的であるという点です。もし、急激な目の痛みや視力低下、強い充血がある場合は、白内障以外の病気(急性緑内障発作や角膜炎など)の可能性も考えられるため、速やかに眼科を受診する必要があります。
手術のタイミング:いつ決断すべきか?
「白内障と診断されたら、すぐに手術を受けなければならない」と考えている方も多いかもしれませんが、それは必ずしも正しくありません。白内障の進行は非常にゆっくりであることが多く、初期段階であれば、生活に支障がない限り、経過観察となるのが一般的です。
では、どのタイミングで手術を決断すべきなのでしょうか。その最も重要な判断基準は、「視力検査の数値(0.7や0.5など)ではなく、ご自身の日常生活にどれだけ支障が出ているか」です。
日本眼科学会も、手術の適応として「視力低下が本人の生活に支障をきたすこと」を第一に挙げています。例えば、以下のような不便を感じ始めたら、手術を検討するタイミングかもしれません。
- 車の運転、特に夜間の運転でヘッドライトがまぶしくて怖い。
- 標識や看板の文字がかすんで見えにくい。
- 新聞や薬のラベルなど、細かい文字が読みにくい。
- 料理をする際、手元がぼやけて不安。
- ゴルフのボールの行方や、テニスのボールが見えにくい。
- 人の顔がぼんやりして、表情がわかりにくい。
また、ご自身の生活上の不便がまだ少なくても、糖尿病網膜症や緑内障など、他の眼の病気を合併している場合、白内障の濁りで眼底の診察や治療(レーザーなど)が困難になることがあります。このようなケースでは、他の病気の管理のために、早めに白内障手術が勧められることもあります。
「点眼薬で白内障は治せますか?」という質問もよくいただきます。現在、日本で承認されている白内障治療用の点眼薬(ピレノキシン製剤など)は、あくまで水晶体のタンパク質変性を抑え、「進行を遅らせる」ことを目的としたものです。残念ながら、一度濁ってしまった水晶体を透明に戻す薬は、現在のところ存在しません。視力を根本的に回復させる唯一の治療法は、手術であるというのが世界の共通認識です。
白内障手術の標準的な流れと眼内レンズ(IOL)
「眼の手術」と聞くと、強い痛みや恐怖を感じるかもしれませんが、現在の白内障手術は技術が飛躍的に進歩しており、非常に安全性が高く、短時間で終わる手術の代表格となっています。多くの場合、点眼による局所麻酔で行われ、痛みを感じることはほとんどありません。
現在、世界的に標準となっているのは「超音波乳化吸引術(ちょうおんぱにゅうかきゅういんじゅつ)」という方法です。その流れは以下の通りです。
- 麻酔:まず、点眼薬による局所麻酔を行います。注射はしない施設がほとんどです。
- 切開:黒目(角膜)の端に、わずか2〜3mm程度の非常に小さな切開創を作ります。
- 水晶体の核の乳化・吸引:その小さな切開創から、超音波を発する細い器具を挿入します。超音波の振動で、硬く濁った水晶体の核を細かく砕き(乳化)、同時に吸引して取り除きます。このとき、水晶体が入っていた袋(水晶体嚢)は残しておきます。
- 眼内レンズ(IOL)の挿入:水晶体の中身が空になった水晶体嚢の中に、折りたたんだ人工のレンズ(眼内レンズ:Intraocular Lens, IOL)を挿入します。レンズは眼の中でゆっくりと広がり、元の水晶体の代わりにピントを合わせる役割を果たします。
手術時間は、症例にもよりますが10分〜20分程度です。日本では、厚生労働省の定める短期滞在手術として普及しており、全身状態に問題がなければ日帰り手術、あるいは1泊程度の入院で行うのが一般的です。
眼内レンズ(IOL)の選択
手術の際、自分の眼に入れる眼内レンズ(IOL)は、術後の「見え方の質」を大きく左右する重要な選択です。レンズには大きく分けて以下の種類があります。
- 単焦点眼内レンズ:ピントが合う距離が「一箇所」のみ(遠く、中間、または近く)のレンズです。日本の公的医療保険が適用されます。例えば「遠く」にピントを合わせた場合、遠くの景色は裸眼ではっきり見えますが、手元の新聞やスマートフォンを見るためには老眼鏡が必要になります。
- 多焦点眼内レンズ:ピントが「複数箇所」(例:遠くと近く)に合うように設計されたレンズです。眼鏡への依存度を減らすこと(老眼鏡をなるべく使わずに生活すること)を目的としています。これには、2焦点、3焦点、焦点深度拡張型(EDOF)など様々なタイプがあります。ただし、保険適用の単焦点レンズとの差額(先進医療や選定療養の費用)は、原則として自己負担となります。費用や特徴については別記事もご参照ください。
- トーリックレンズ:乱視を矯正する機能がついたレンズです。単焦点、多焦点それぞれにトーリックのオプションがあります。
どのレンズが最適かは、その人のライフスタイル(運転をよくするか、読書が好きか、スポーツをするかなど)、仕事、性格、そして費用に対する考え方によって全く異なります。(屈折矯正手術に関する詳細は、ICLやレーシックなどの屈折矯正手術のセクションでも触れますが)白内障手術は、自分の視力を「再設計」する大きなチャンスでもあります。医師とよく相談し、納得のいくレンズを選ぶことが重要です。
なお、白内障と緑内障を併発している場合、日本眼科学会の基準(2024年版)に基づき、白内障手術と同時に眼圧を下げるための小さな器具(眼内ドレーン)を挿入する低侵襲緑内障手術(MIGS)を同時に行うこともあります。
術後ケアと日常生活の注意点
手術が無事に終わっても、本当の視力回復はその後のケアにかかっています。手術でできた小さな傷口が完全にふさがり、眼の中の炎症が治まるまでの期間(通常1ヶ月程度)は、感染症を防ぐために非常に重要です。「手術は成功したのに、術後のケアを怠ったために感染症を起こして視力が落ちた」という事態を避けるため、医師の指示を厳守する必要があります。
国際的なガイドライン(NICE/NCBI)でも、術後フォローの目的は合併症の早期発見であると明記されています。特に重要な注意点は以下の通りです。
- 術後の点眼:
最も重要です。感染を防ぐための抗菌薬、炎症を抑えるためのステロイドや非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の点眼薬が処方されます。決められた回数を、決められた期間(自己判断で中断しない)、清潔な手で確実に行う必要があります。 - 眼の保護:
術後しばらくは、就寝時や外出時に保護用のメガネや眼帯を使用するよう指示されることがあります。これは、無意識に眼をこすったり、ぶつけたりするのを防ぐためです。 - 日常生活の制限:
「いつから洗顔・洗髪・入浴・化粧・飲酒・仕事・運動が可能か」は、手術の方法や術後の経過によって異なります。一般的に、術後数日間は、眼に直接水や石鹸が入らないように注意が必要です。重い物を持ったり、激しい運動をしたりすることも、眼圧が上がる可能性があるため制限されます。必ず医師の許可を得てから再開してください。 - 定期的な通院:
手術翌日、1週間後、1ヶ月後など、指定された日時に必ず診察を受けてください。眼圧測定、視力検査、傷口のチェック、炎症の程度の確認などが行われます。
手術後のケアや食事の注意点については、別の記事でも詳しく解説していますが、最も大切なのは「いつもと違う」と感じたら自己判断せず、すぐに医師に相談することです。
術後の合併症と「後発白内障」
現在の白内障手術は非常に安全性が高いとはいえ、100%リスクがないわけではありません。稀ではありますが、重篤な合併症が起こる可能性もあります。また、数ヶ月〜数年後に起こりやすい「後発白内障」という状態についても理解しておく必要があります。
緊急性の高い合併症(レッドフラグ)
術後数日から数週間の間に、以下のような症状が現れた場合は、緊急を要する合併症(特に急性術後眼内炎)の可能性があります。時間外や休日であっても、すぐに手術を受けた施設または救急外来に連絡してください。
- 急激な視力低下(「昨日より明らかに見えなくなった」)
- 強い眼の痛み、頭痛、吐き気(眼圧の急上昇や感染のサイン)
- 激しい充血、膿のような眼脂(めやに)
- 視野の一部が欠ける、黒いカーテンがかかったように見える(網膜剥離の可能性)
これらの初期症状を見逃さず、迅速に対応することが、視力を守る上で極めて重要です。
後発白内障(こうはつはくないしょう)
手術から数ヶ月、あるいは数年経ってから、「また視界がかすんできた」「まぶしくなってきた」と感じることがあります。これは「白内障の再発」ではなく、多くの場合「後発白内障」です。
白内障手術では、眼内レンズを入れるために水晶体の「袋(水晶体嚢)」を残します。この残した袋(特に後ろ側の膜)が、時間の経過ととも細胞の増殖などによって再び濁ってくるのが後発白内障です。これは手術の失敗ではなく、ある一定の確率(数%〜20%程度)で起こり得る現象です。
治療は非常に簡単で、手術室に入る必要はありません。外来で「YAGレーザー」という特殊なレーザーを使い、濁った袋の中心部に小さな穴を開けて光の通り道を再び作るだけです。痛みもなく、数分で終了し、すぐに視力は回復します。手術後の視力回復に疑問を感じたら、まずは後発白内障を疑って眼科を受診しましょう。
白内障に関するよくある質問(FAQ)
Q1: 白内障は点眼薬で治せますか?
A: いいえ。2025年現在、一度濁ってしまった水晶体を元の透明な状態に戻す点眼薬は存在しません。日本で処方される点眼薬は、あくまで「進行を遅らせる」ことを期待するものであり、視力を根本的に改善する治療法は手術のみとされています。
Q2: 視力がまだ0.7ありますが、手術はできますか?
A: 可能です。手術の適応は、視力検査の数値だけで決まるわけではありません。視力が0.7あっても、「対向車のライトがまぶしくて運転が怖い」「趣味のゴルフでボールが見えない」など、ご自身の生活における「見え方の質」の低下が著しく、不便を感じている場合は、手術の良い適応となります。
Q3: 白内障手術は日帰りが普通ですか?
A: はい。日本では技術の進歩と診療報酬制度(短期滞在手術)の整備により、多くの施設で日帰り手術、または1泊2日程度の入院で行われています。ただし、全身状態(重い糖尿病や心臓病など)や、ご自宅での術後ケアが難しい場合などは、数日間入院するケースもあります。
Q4: 手術後にしてはいけないことは何ですか?
A: 最も重要なのは「眼をこすらない」「眼に汚れた水や汗を入れない」「医師の指示なしに点眼をやめない」ことです。術後1週間程度は、洗顔や洗髪の方法に制限があります。また、重い物を持つ、激しい運動をする、飲酒するなども、傷口の回復や炎症に影響するため、指定された期間は避ける必要があります。
Q5: 手術しても、また白内障になりますか?(再発)
A: 手術で挿入した人工の眼内レンズ(IOL)自体が濁ることはありません。したがって、白内障が「再発」することはありません。ただし、前述の通り、手術から数ヶ月〜数年後にレンズを入れた袋が濁る「後発白内障」が起こることはあります。これは簡単なレーザー治療(手術は不要)で、すぐに視力を回復できます。
Q6: 糖尿病がありますが、白内障手術は安全ですか?
A: 血糖コントロールが良好であれば、多くの場合、安全に手術を行うことが可能です。ただし、糖尿病網膜症が進行している場合は、白内障手術が網膜症に影響を与える可能性も考慮し、手術のタイミングや方法(網膜症の治療を先に行うか、同時に行うかなど)を慎重に決定する必要があります。詳細は「糖尿病網膜症」のセクションも併せてご覧ください。
緑内障(視神経の障害・進行予防・点眼とレーザー治療)
前節では白内障について解説しましたが、ここでは日本における失明原因の第1位である「緑内障」について詳しく見ていきます。白内障が手術によって視力回復を目指せる病気であるのに対し、緑内障は一度失われた視野や視機能を取り戻すことができないため、「いかに進行を食い止めるか」が治療のすべてとなります。
多くの方が「緑内障=眼圧が高い病気」というイメージをお持ちかもしれませんが、実は日本では眼圧が正常範囲内であるにもかかわらず病気が進行する「正常眼圧緑内障」が大多数を占めます。このセクションでは、緑内障の本質である視神経の障害、進行予防の考え方、そして治療の柱となる点眼薬とレーザー治療について、日本の現状を踏まえて徹底的に解説します。
日本で最も多い「正常眼圧緑内障」とは?
緑内障とは、視神経と視野に特徴的な変化が生じ、治療によって眼圧を十分に下げることでその進行を抑制できる可能性のある慢性疾患です。日本緑内障学会の定義でも、この「眼圧下降による進行抑制」が治療の根幹であるとされています。(日本緑内障学会『緑内障診療ガイドライン(第5版)』参照)
健康診断などで「眼圧が正常(10〜21mmHg)なので大丈夫です」と言われた経験がある方も多いでしょう。しかし、ここに日本の緑内障診療における最大の落とし穴があります。日本の疫学調査(多治見スタディ)では、40歳以上の約5%(20人に1人)が緑内障であり、そのうちの実に7割以上が「正常眼圧緑内障(NTG)」であったことが判明しています。
つまり、日本人においては「眼圧が正常範囲内であっても、その人にとっての視神経の耐久力を超えていれば、視神経はゆっくりと傷んでいく」というケースが非常に多いのです。この事実は、なぜ日本人に正常眼圧緑内障が多いのか、その背景には欧米人とは異なる視神経の脆弱性や血流の問題などが関与していると考えられています。
視神経が傷むメカニズムと危険因子
緑内障による視神経の障害は、眼球の後ろにある視神経乳頭(視神経の束が眼球から脳へと向かう入り口)で起こります。眼圧などの要因によって視神経線維が圧迫されたり、血流障害が起きたりすることで、神経線維が少しずつ死滅していきます。その結果、視神経乳頭の「陥凹(かんおう)」と呼ばれるへこみが拡大し、それに伴って網膜の神経線維層が薄くなっていきます。これが「緑内障性視神経症(GON)」と呼ばれる特徴的な変化です。
視神経は情報を脳に送る電線のようなものですから、この電線が壊れると、その部分が担当していた視野(見える範囲)が欠けていきます。初期の緑内障では、視野の中心から少し外れた場所から欠け始めることが多く、両目で見ていると互いにカバーしてしまうため、自覚症状はほとんどありません。初期症状や危険因子を早期に知ることが、失明を防ぐために何よりも重要です。
緑内障の最大の危険因子は「高い眼圧」ですが、それ以外にも複数の因子が関わっています。
- 加齢: 40歳を超えると有病率が上昇します。
- 家族歴: 血縁者に緑内障の方がいるとリスクが上がります。
- 近視: 特に強度の近視は、視神経乳頭の構造が緑内障の変化に脆弱であるとされています。近視と緑内障リスクの関係については、多くの研究がその関連性を指摘しています。
- その他の因子: 角膜の薄さ、低血圧、血流障害(冷え性など)なども関与が疑われています。
進行予防の鍵:「ターゲット眼圧」という考え方
緑内障治療の目的は、失われた視野を取り戻すことではなく、残された視神経と視野を守り、生涯にわたって生活の質(QOL)を維持することです。現在、科学的に証明されている唯一確実な治療法は、「眼圧を下げること」です。
ここで重要なのが「ターゲット眼圧(目標眼圧)」という考え方です。これは、「その患者さんの視神経がそれ以上傷まないであろうと期待される眼圧レベル」を指します。正常眼圧緑内障の方であっても、現在の「正常範囲内」の眼圧から、さらに20~30%低いレベルまで眼圧を下げることで、進行リスクを有意に下げられることがわかっています。
ターゲット眼圧は、診断時の視野障害の程度、進行速度、年齢、危険因子などを考慮して、医師が個別に設定します。例えば、初期の緑内障であれば「元の眼圧から20%下降」、中等度以上であれば「30%以上の下降」といった具合です。治療を開始した後は、定期的に視野検査やOCT(光干渉断層計)検査で視神経の状態をチェックし、「進行が止まっているか」を評価します。もし進行が続くようであれば、ターゲット眼圧をさらに低く設定し直し、治療を強化していきます。緑内障に関する誤解を解き、正しい知識を持つことが治療の第一歩です。
治療の第一選択:点眼薬の種類と正しい使い方
ターゲット眼圧を達成するための治療として、まず最初に行われるのが「点眼薬(目薬)」による薬物療法です。緑内障の点眼薬には多くの種類があり、主に房水(目の中を循環する水)の産生を抑えるか、房水の排出を促進することで眼圧を下げます。
主な点眼薬の系統:
- プロスタグランジン(PG)関連薬: 房水の排出(ぶどう膜強膜流出路)を促進します。眼圧下降効果が最も強く、1日1回の点眼で済むため、第一選択薬として広く用いられます。
- β遮断薬: 房水の産生を抑えます。効果が強いためPG関連薬と並んで多用されますが、喘息や心臓病の方には使えない場合があります。
- 炭酸脱水酵素阻害薬: 房水の産生を抑えます。点眼薬と内服薬があります。
- α2受容体作動薬: 房水の産生抑制と排出促進の両方の作用を持ちます。
- Rhoキナーゼ(ROCK)阻害薬: 房水の排出(線維柱帯流出路)を促進する、比較的新しいタイプの薬剤です。
- 配合点眼薬: 作用の異なる2〜3種類の成分を1本に配合した薬です。複数の点眼薬が必要な場合に、さす回数を減らして負担を軽減するために用います。
緑内障治療は、生涯にわたる長期戦です。点眼を自己判断で中断してしまうと、眼圧が元に戻り、気づかないうちに病気が進行してしまいます。日常生活での注意点を守り、決められた回数を正しく継続することが最も重要です。複数の目薬を使う場合は、吸収を良くするため5分以上間隔をあけて点眼してください。
レーザー治療はいつ検討する?(SLT・虹彩切開)
点眼薬だけではターゲット眼圧を達成できない場合や、副作用で点眼の継続が難しい場合、あるいは点眼のし忘れ(アドヒアランス不良)が懸念される場合には、次のステップとしてレーザー治療が検討されます。緑内障治療は点眼、レーザー、手術と段階的に進めるのが一般的です。
主なレーザー治療:
- 選択的レーザー線維柱帯形成術(SLT):
開放隅角緑内障(正常眼圧緑内障を含む)に対して行われます。房水の排水口である「線維柱帯」に低出力のレーザーを照射し、細胞を活性化させることで排水をスムーズにし、眼圧を下げます。体への負担が少なく、外来で短時間に行え、繰り返し治療が可能な点がメリットです。点眼薬と同等の初期治療として選択されることも増えています。 - レーザー虹彩切開術(LPI):
主に閉塞隅角緑内障、またはそのリスクが高い「狭隅角」の方に行われます。虹彩(茶目)の端にレーザーで小さな穴を開け、房水の新たな通り道を作ることで、隅角が塞がってしまうのを防ぎます。急性緑内障発作の予防や治療に有効です。
レーザー治療で眼圧が十分に下がり、安定すれば、点眼薬の数を減らしたり、中止したりできる可能性もあります。ただし、効果が永続的でない場合もあり、定期的な経過観察は必須です。もしレーザー治療でも眼圧コントロールが不十分な場合は、最終的な手段として手術(線維柱帯切除術など)が必要となりますが、手術の詳細は別のセクションで解説します。
急性発作の危険サインと薬剤性の注意点
緑内障の多くはゆっくり進行し自覚症状が出にくいものですが、中には緊急の対応が必要なタイプがあります。それが「急性閉塞隅角緑内障(急性緑内障発作)」です。
これは、何らかの原因で房水の出口(隅角)が急激に塞がり、眼圧が40~50mmHg以上にまで急上昇する状態です。以下のような症状が突然現れた場合は、厚生労働省の注意喚起にもある通り、緊急事態です。数時間で視神経が深刻なダメージを受け、失明に至る危険があるため、夜間や休日でも直ちに眼科救急を受診してください。
- 突然の激しい目の痛み、充血
- 急激な視力低下、かすみ(「霧の中にいるよう」と表現される)
- 電灯の周りに虹のような輪が見える(虹視症)
- 激しい頭痛、吐き気、嘔吐(目の症状より頭痛が目立つこともあり、脳疾患と間違われることもある)
このような危険なかすみ目は、放置してはいけません。また、特定の薬剤がこの発作を引き起こす(薬剤性緑内障)ことも知られています。特に、遠視で隅角が狭い中高年女性は注意が必要です。市販のかぜ薬、抗アレルギー薬、睡眠薬、一部の抗うつ薬などに含まれる「抗コリン作用」を持つ成分が、瞳孔を開いて隅角を塞ぎ、発作の引き金になることがあります。緑内障と診断されている方や、眼科で「隅角が狭い」と指摘されたことがある方は、市販薬を購入する際も必ず医師や薬剤師にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q1: 眼圧が正常でも「緑内障です」と言われるのはなぜですか?
A: 日本人では、眼圧が統計上の正常範囲(10~21mmHg)にあっても、その人の視神経が耐えられるレベルよりは高く、結果として視神経障害が進行してしまう「正常眼圧緑内障」が最も多いタイプだからです。治療は、現在の眼圧を「正常だから安心」と考えるのではなく、そこからさらに20~30%下げて、視神経を守るための「ターゲット眼圧」を目指すことになります。
Q2: 緑内障の目薬は一生さす必要がありますか?
A: 緑内障は、高血圧や糖尿病と同じ慢性疾患であり、「完治」するものではありません。現在の治療は、あくまで「進行を遅らせる」ことが目的であり、一度失われた視野は元に戻りません。そのため、多くの場合、生涯にわたって眼圧をコントロールし続ける必要があり、点眼治療も継続することが原則となります。
Q3: 目薬をさしても眼圧が下がらないと言われました。次は何をしますか?
A: まず、点眼が正しく(回数、量、方法)できているかを確認します。その上で効果が不十分な場合、①別の作用を持つ点眼薬を追加する、②複数の成分が入った配合点眼薬に変更する、③レーザー治療(SLTなど)を行う、④手術を検討する、といったステップで治療を強化していきます。担当医と相談し、ご自身の病状とライフスタイルに合った方法を選択します。
Q4: 緑内障はどのくらいの頻度で検査に行けばいいですか?
A: 病気の進行度(病期)や、進行速度によって異なります。一般的には、病状が安定していれば、初期~中期の緑内障で数ヶ月~半年に1回程度の視野検査と、定期的な眼底・OCT検査を行うことが多いです。進行が速いと判断された場合や、治療法を変更した直後は、より短い間隔(1~3ヶ月ごとなど)で検査を行い、眼圧や視野の変化を慎重に評価します。
ドライアイ(原因・検査・人工涙液・マイボーム腺ケア)
前節までの緑内障や白内障といった特定の構造的疾患とは異なり、ここでは日本で約2,200万人が罹患しているとも言われる、非常に身近な「国民病」であるドライアイについて掘り下げていきます(日本眼科学会[1])。
多くの方が「目が乾く」「ゴロゴロする」「ショボショボする」といった不快感として認識していますが、ドライアイは単なる一時的な乾燥ではありません。日本の最新定義(2016年版)[2]では、「涙液層の安定性が損なわれ、自覚症状(眼不快感・視機能異常)を生じるもの」とされており、放置すると眼表面に傷がつく可能性のある慢性の疾患です。単なる不快感だけでなく、「目がかすむ」「光がまぶしい」「目がかゆい」といった多様な症状を引き起こします。このセクションでは、その原因から検査、そして日々のケアまでを詳しく解説します。
原因別に見るドライアイ:涙が少ないタイプと蒸発しやすいタイプ
ドライアイと一口に言っても、その原因は大きく二つに分けられます。自分がどちらのタイプに近いのかを知ることが、適切な対策の第一歩となります。
1. 涙液分泌減少型(Aqueous-deficient)
これは、文字通り「涙の蛇口」からの分泌量が不足している状態です。涙の量そのものが少ないため、目が乾きやすくなります。このタイプは、シェーグレン症候群のような自己免疫疾患(全身の分泌腺が障害される病気)や、特定の薬剤の副作用、加齢などによって引き起こされることがあります。
2. 蒸発亢進型(Evaporative)
こちらが現代の日本人において非常に多いタイプです。涙の量は十分に出ているにもかかわらず、「涙の蒸発を防ぐフタ」が機能不全を起こし、涙がすぐに乾いてしまう状態です。私たちの涙は、ただの水(水層)ではなく、その表面を薄い油(脂質層)が覆うことで蒸発を防いでいます。この「油のフタ」が不安定になる最大の原因が、マイボーム腺機能不全(MGD)です。
マイボーム腺とは、上下のまぶたの縁にある油の分泌腺です。ここが詰まったり、炎症を起こしたりすると、涙に必要な油が供給されず、涙はあっという間に蒸発してしまいます。そして、このMGDを引き起こす現代特有のリスク要因が、私たちの生活に潜んでいます。
- VDT(Visual Display Terminal)作業:
パソコンやスマートフォンを長時間見つめる作業です。問題は、画面に集中すると「まばたきの回数」が激減することです。まばたきは、涙を目の表面に均一に広げ、新しい油を分泌させる「ワイパー」の役割を果たします。まばたきが減れば、涙は乾き、油も行き渡りません。デジタル眼精疲労の多くは、この蒸発亢進型ドライアイを併発しています。 - コンタクトレンズの装用:
コンタクトレンズは、涙の層を分断し、涙の安定性を著しく低下させます。特にソフトレンズは、レンズ自体が水分を吸収(蒸発)するため、目の乾燥を助長します。また、レンズの縁がマイボーム腺の出口を物理的に塞ぐことも指摘されています。コンタクトレンズの種類を見直すことも治療の一環です。 - 環境要因と加齢:
エアコンの効いた乾燥した室内、加齢(特に閉経後の女性ホルモンの変動)も、涙の質と量に大きく影響します(MGDガイドライン[5])。
これらの要因が複雑に絡み合い、単なる目の疲れとは異なる、治療が必要な「病的な乾き」へと進行していきます。
ドライアイの検査:単なる「乾き」と「病気」を見分ける
「ドライアイかもしれない」と眼科を受診した際、医師はどのようにして「一時的な乾き」と「治療が必要なドライアイ」を区別するのでしょうか。多くの方が「検査は痛いのではないか」と不安に思われるかもしれませんが、ほとんどの検査は痛みがありません。医師は以下の検査を組み合わせて、涙の「量」「質」「安定性」、そして「結果としてのダメージ」を評価します。
- BUT(Tear Film Breakup Time:涙液層破壊時間)
これは涙の「質」と「安定性」を測る最も重要な検査です。フルオレセインという黄色の色素(点眼)で涙を染め、患者さんにまばたきを我慢してもらいます。涙が目の表面を均一に覆ってから、乾燥によって涙の層が「破壊」される(黒いスポットが現れる)までの時間を測定します。この時間が5秒未満の場合、涙が非常に不安定である(=蒸発亢進型)と診断されます(ドライアイ診療ガイドライン[3])。
- 角結膜染色検査(Staining)
これは、乾きによって目の表面(角膜や結膜)がどれだけ「傷ついているか」を可視化する検査です。BUTで使ったフルオレセイン色素は、細胞が剥がれたり、細胞同士の接着が緩んだりしている部分を染め出します。傷の範囲や場所を見ることで、ドライアイの重症度を判定します。この所見は、ドライアイ診断の確定(日本2016年基準[2])に不可欠です。
- シルマー試験(Schirmer Test)
これは涙の「量」を測る古典的ですが重要な検査です。目盛りのついた専用の細い濾紙(ろし)を下まぶたの端に5分間挿入し、どれだけの長さが涙で濡れるかを測定します。5分間で5mm未満の場合、涙の分泌量が少ない(=涙液分泌減少型)と判断されます。挿入時に多少の異物感を感じることがありますが、痛みはありません。
- マイボグラフィー(Meibography)
これは蒸発亢進型の原因となるMGDを診断するための「まぶたのレントゲン」のような検査です。まぶたの裏側から特殊な光を当てて、油を出すマイボーム腺の形を直接撮影します。健康な腺は白い線として整然と並んでいますが、MGDが進行すると、腺が詰まって途切れたり、炎症で変形したり、最終的には「脱落」して失われたりしている様子がはっきりとわかります。
これらの検査結果と、「目の奥の痛み」や「目のかゆみ」といった詳細な問診を組み合わせることで、医師はあなたのドライアイのタイプと重症度を正確に診断します。
治療の第一歩:人工涙液、処方点眼薬、涙点プラグ
ドライアイの診断がついた場合、治療は段階的に行われます。目標は、不快な症状を取り除くだけでなく、涙の層を安定させ、角膜の傷を修復することです。
1. 人工涙液(市販薬)とヒアルロン酸ナトリウム点眼
最も基本的な治療は、不足している涙を外から補うことです。ここで重要なのは、市販薬(OTC)と処方薬の違いを理解することです。
- 市販の人工涙液:軽度の乾きには有効ですが、防腐剤(ベンザルコニウム塩化物など)が含まれている製品が多いです。防腐剤は、頻繁に(1日5〜6回以上)使用すると、かえって角膜を傷つける可能性があります。頻繁に使う場合は、防腐剤の入っていない使い切りタイプの製品を選ぶべきです(Mayo Clinic[13])。
- 厚生労働省・日本眼科学会からの重要な注意喚起:
市販の点眼薬(ヒアルロン酸ナトリウム0.1%製剤など)を使用しても、1週間程度で症状が改善しない場合、自己判断で使い続けることは非常に危険です(厚生労働省[10])。その乾きは、角膜感染症や他の重篤な疾患のサインかもしれません(厚労省[11])。必ず眼科を受診してください。
2. 処方点眼薬(涙の質を改善する薬)
眼科で処方される薬は、単なる「潤滑剤」ではありません。涙の成分そのものを改善する「治療薬」です。
- ジクアホソルナトリウム(例:ジクアス®):涙の「水分」と「ムチン」の両方の分泌を促進します。ムチンは涙を目の表面に「糊付け」する役割があり、涙の安定性を高めます。
- レバミピド(例:ムコスタ®):主に「ムチン」の分泌を促進し、さらに角膜上皮の傷を修復する作用も持ちます。特にコンタクトレンズ装用者やMGD患者で低下しているムチン層の改善に役立ちます。
これらは、食事による栄養改善や目の体操といったセルフケアと並行して、治療の柱となります。
3. 涙点プラグ(涙の排水口にフタをする)
点眼薬を頻繁に使用しても症状が改善しない「涙液分泌減少型」の場合、この治療が非常に有効です。涙は目の表面を潤した後、目頭にある「涙点(るいてん)」という小さな排水口から鼻へと流れていきます。涙点プラグは、この排水口にシリコン製の小さなフタ(プラグ)を挿入し、涙が流れ出るのを物理的に防ぐ治療です。これにより、自分自身が分泌した貴重な涙を目の表面により長く留めることができます。挿入は外来で数分で完了し、痛みはほとんどありません。
蒸発亢進型の鍵:マイボーム腺ケア(MGD)の徹底
点眼治療を行っても「一時的に潤うが、すぐに乾く」と感じる場合、その根本原因は「油(脂質層)」にある可能性が高いです。蒸発亢進型ドライアイの大部分はMGDを伴っており、このMGDに対するケアこそが、治療の成否を分ける鍵となります。これは一度きりの治療ではなく、「歯磨き」のように毎日続けるべき「まぶたの生活習慣」です。
日本のMGD診療ガイドライン[5, 14]でも、以下のセルフケアが第一選択として推奨されています。
ステップ1:温める(温罨法 – おんあんぽう)
なぜ?:MGDで詰まっている油(マイボーム)は、常温では「固まったバター」や「ラード」のような状態です。これを「溶けたバター」のようにサラサラにする必要があります。研究によれば、油の融点(溶ける温度)は約32〜40℃であり、まぶたを40℃前後で5〜10分間温め続けることが最も効果的とされています(国内研究[16])。
どうやって?:市販のホットアイマスク、濡らして絞ったタオルを電子レンジで温めたもの(火傷に注意)などを使い、まぶたの上からじっくりと温めます。入浴中に温かいタオルを使うのも効果的です。
ステップ2:洗う(眼瞼清拭 – がんけんせいしき)
なぜ?:まぶたの縁には、溶け出した古い油、皮脂、化粧品の残り、細菌などが付着しています。これらがマイボーム腺の出口を再び塞いだり、炎症(まぶたのかゆみ)の原因になったりします。
どうやって?:温めた後、まぶた専用の洗浄剤(アイシャンプーなど)や、清潔な綿棒を使って、まつ毛の生え際を優しく拭き取ります。ゴシゴシこすらず、汚れを浮かせるように行います。このケアは、ものもらい(麦粒腫)や霰粒腫の予防にも直結します。
(ステップ3:押し出す – 医師の指導下で)
温めた後に清潔な指や綿棒でまぶたを軽く圧迫し、溶けた油を押し出すマッサージもありますが、強くやりすぎるとまぶたを痛めるため、最初は眼科で指導を受けることをお勧めします。
セルフケアで改善しない重症のMGDに対しては、近年、医療機関で「IPL(Intense Pulsed Light)」という特殊な光を照射して詰まりを改善させる治療も行われるようになっており、日本国内でもその有効性が研究されています(国内臨床研究[15])。
よくある質問(FAQ)
Q1: 単なる「目の乾き」と「ドライアイ」はどう違いますか?
A: 「目の乾き」は、例えばエアコンの効いた部屋に短時間いた時などに誰でも感じる「症状」です。一方、「ドライアイ」は、涙の質や量の異常が慢性的になり、目の表面に傷がつくなど、眼表面の恒常性が破綻した「病気」を指します。症状だけでは区別が難しく、厚生労働省や日本眼科学会[12]は、市販薬を1週間使っても改善しない、または視力低下などを伴う場合は、自己判断せずに眼科を受診するよう強く推奨しています。
Q2: ドライアイの検査は痛いですか?
A: ほとんどの検査に痛みはありません。BUTや染色検査は、まぶしさを感じることはあっても、点眼薬(色素)による痛みはほぼありません。シルマー試験は、濾紙をまぶたに挟むため数分間の異物感がありますが、強い痛みではありません。不安な点は、検査前に医師やスタッフに遠慮なく伝えてください。
Q3: 市販の人工涙液は1日に何回まで使っていいですか?
A: 製品のタイプによります。防腐剤が含まれている一般的なボトルタイプの点眼薬は、角膜への負担を考慮し、1日4〜6回程度までが目安です。もしそれ以上点眼しないと辛い場合は、ドライアイが進行しているか、防腐剤による角膜障害が起きている可能性があります。頻繁に点眼が必要な場合は、防腐剤の入っていない使い切りタイプの人工涙液を選び、根本的な治療について眼科医に相談してください(厚労省[10])。
Q4: まぶたを温めるとドライアイがよくなるのはなぜですか?
A: 現代人のドライアイの多く(蒸発亢進型)は、まぶたの縁にある「マイボーム腺」の油が詰まること(MGD)が原因です。この油は常温ではバターのように固まっていますが、40℃前後で温めることで溶け出し、涙の表面を覆う「油のフタ」として正常に機能するようになります(MGDガイドライン[5])。これにより、涙の蒸発が抑えられ、ドライアイの症状が根本的に改善します。
Q5: 目やに(めやに)も出ますが、ドライアイと関係ありますか?
A: 関係がある場合とない場合があります。ドライアイが原因で出る目やには、比較的「白く、糸を引くようなネバネバしたもの」が多いです。これは、涙の水分が蒸発し、ムチンなどの成分が濃縮されたものです。しかし、もし目やにが「黄色や緑色でドロっとしている」「朝、まぶたがくっついて開かない」という場合は、ドライアイではなく、次のセクションで解説する細菌性結膜炎などの感染症の可能性が高いです。この場合は直ちに眼科での治療が必要です。
結膜炎・角膜炎(感染性/アレルギー性・治療と予防)
前節のドライアイでも見られたように、「目が充血する」「ゴロゴロする」といった症状は非常によくある悩みですが、その原因は多岐にわたります。中でも「結膜炎」と「角膜炎」は、目の表面(前眼部)で起こる炎症性疾患の代表であり、多くの人が一度は経験するものです。
しかし、単に「目が赤い」といっても、その背景は大きく異なります。「結膜炎(けつまくえん)」は、まぶたの裏側と白目の表面を覆う「結膜」の炎症です。一方、「角膜炎(かくまくえん)」は、黒目の表面にある透明な「角膜」の炎症を指します。この二つは隣接していますが、その深刻度は全く異なります。角膜炎は結膜炎よりもはるかに重症であり、治療が遅れれば失明につながる可能性もある、緊急性の高い状態です。
目が赤くなったとき、多くの人が「これは人にうつるのか?」「市販の目薬で大丈夫か?」「仕事や学校は休むべきか?」といった不安に直面します。このセクションでは、こうした具体的な疑問に答えるため、感染性の結膜炎(ウイルス性・細菌性)、アレルギー性の結膜炎、そして最も注意すべき角膜炎について、その見分け方、適切な治療法、そして家庭や学校での予防策までを、日本の公的機関や最新の研究知見に基づき、深く掘り下げて解説します。痛みを伴う赤目には特に注意が必要です。
感染性結膜炎の種類と流行時期(流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎・プール熱)
[cite_start]
「結膜炎」と聞いて多くの人が最も心配するのは、「うつるかどうか」でしょう。特に感染力が非常に強く、公衆衛生上も重要視されているのが、主にウイルスによって引き起こされる感染性結膜炎です。日本では、厚生労働省が眼科定点把握疾患として「流行性角結膜炎」と「急性出血性結膜炎」を指定し、その流行状況を監視しています [cite: 1]。
これらのウイルス性結膜炎は、主に夏から秋にかけて流行のピークを迎えることが多かったのですが、近年は冬場にも報告が見られるなど、通年での注意が必要です。それぞれの特徴を理解しておくことが、迅速な対応と感染拡大の防止につながります。
流行性角結膜炎(EKC:Epidemic Keratoconjunctivitis)
通称「はやり目」とも呼ばれ、アデノウイルス(D種8, 37, 53, 54型など)によって引き起こされます。感染してから1〜2週間という長い潜伏期間の後、突然、強い充血、大量の目やに(水様性)、まぶたの裏にブツブツができる(濾胞性結膜炎)、耳の前にあるリンパ節の腫れや痛みといった症状が現れます。
この病気で最も恐ろしいのは、結膜炎の症状が治まりかけた頃(発症から1〜2週間後)に、角膜(黒目)に炎症が波及することです。角膜に「多発性角膜上皮下混濁」と呼ばれる小さな点状の濁りが残ることがあり、これが視界のかすみや視力低下の原因となります。この混濁は数ヶ月から、時には1年以上も残ることがあり、治療には眼科専門医によるステロイド点眼薬の管理が不可欠です。
ウイルス性結膜炎の全体像については、こちらの記事で詳しく解説しています。
咽頭結膜熱(PCF:Pharyngoconjunctival Fever)
通称「プール熱」として知られ、主にアデノウイルス(B種3, 7型など)が原因です。その名の通り、夏にプールの利用を通じて子供たちの間で流行することが多いですが、プールの水だけでなく、タオルや飛沫を通じても感染します。主な症状は、結膜炎(充血・目やに)に加えて、「発熱」と「喉の痛み(咽頭炎)」という三主徴を呈することです。
EKCほど強い目の症状が出ることは少ないですが、全身症状を伴うのが特徴です。学校保健安全法では、主要症状(発熱、咽頭炎、結膜炎)が消失した後も、さらに2日間が経過するまで登校停止と定められています。感染経路と予防策を正しく知ることが重要です。
急性出血性結膜炎(AHC:Acute Hemorrhagic Conjunctivitis)
エンテロウイルス70型やコクサッキーウイルスA24変異株などが原因で起こります。この病気は、潜伏期間がわずか1日程度と非常に短いのが特徴です。発症すると、強い目の痛み、ゴロゴロ感とともに、名前の通り「結膜下出血」を伴い、白目が真っ赤に出血します。その見た目の派手さから、患者さん自身も家族も非常に驚かれますが、この出血自体は時間とともに吸収されることがほとんどです。しかし、感染力が極めて強く、短期間で家庭内や職場内で爆発的に流行するため、厳重な感染対策が求められます。
細菌性結膜炎で抗菌薬点眼が必要なケース/不要なケース
目が赤くなり、特に「目やに」が多い場合、「細菌感染(ばいきん)ではないか?」と心配になるのは当然です。細菌性結膜炎は、黄色ブドウ球菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌など、身の回りに存在する細菌によって引き起こされます。
典型的な症状は、朝起きると目が開かないほどの、ネバネバとした黄色い膿性の目やにです。ウイルス性結膜炎が水様性の目やにやリンパ節の腫れを特徴とするのに対し、細菌性は膿性の目やにが鑑別のポイントとなります。多くの場合、片方の目から始まりますが、もう片方の目にうつることもあります。
こうした症状がある場合、治療には抗菌薬(抗生物質)の点眼薬が用いられます。これにより、原因となる細菌の増殖を抑え、回復を早めることができます。特に乳幼児や高齢者、免疫力が低下している方では、細菌が角膜炎や眼内炎など、より深刻な感染症に進展するのを防ぐためにも、抗菌薬点眼の適正な使用が重要です。
しかし、ここで非常に重要な問題があります。それは、日本では抗菌薬点眼が過剰に使用されているという指摘です。2025年に国立国際医療研究センター(NCGM)は、眼科領域における抗菌薬点眼、特にフルオロキノロン系点眼薬の使いすぎについて警告を発しました。
英国のNICE(英国国立医療技術評価機構)のガイドラインでは、細菌性結膜炎の多くは自然に治癒するため、抗菌薬なしでの経過観察も選択肢とされるのに対し、日本では「慢性結膜炎」といった曖昧な診断のもと、抗菌薬が長期にわたり処方されがちです。NCGMは、「抗菌薬を使っても症状が改善しない結膜炎」の背後には、アレルギー性結膜炎、薬剤性の角膜障害、あるいはドライアイなど、全く別の原因が隠れていることが多いと指摘しています。
したがって、以下の点を理解することが重要です。
- 抗菌薬が必要なケース: 明らかに膿性の目やにが多い、細菌性結膜炎が強く疑われる場合。
- 抗菌薬が不要(無効)なケース: 流行性角結膜炎や咽頭結膜熱などのウイルス性結膜炎(抗菌薬はウイルスに効きません)。アレルギー性結膜炎。
- 注意が必要なケース: 抗菌薬を数日間使用しても改善しない場合。これは「薬が弱い」のではなく、「診断が違う」可能性が高いサインです。漫然と使用を続けず、必ず眼科で再評価を受ける必要があります。
アレルギー性結膜炎と感染性との見分け方(2日ルール)
「目がかゆい!」— これはアレルギー性結膜炎の最も特徴的な症状です。感染性の結膜炎が「ゴロゴロする」「痛い」といった異物感が中心であるのに対し、アレルギー性は「耐えがたいほどの、強いかゆみ」が主訴となります。
アレルギー性結膜炎は、花粉(スギ、ヒノキなど)、ハウスダスト(ダニの死骸やフン)、動物のフケなどが原因(アレルゲン)となって引き起こされます。これらのアレルゲンが結膜に付着すると、免疫系が過剰に反応し、かゆみや充血、涙、水様の目やにといった症状が現れます。多くの場合、両方の目に同時に症状が現れ、くしゃみや鼻水といったアレルギー性鼻炎の症状を伴うことも少なくありません。
では、この「かゆみ」や「充血」が出たとき、市販の抗アレルギー点眼薬に頼っても良いのでしょうか? ここで知っておくべき重要な基準が、日本眼科学会が示している「2日ルール」です。
厚生労働省と日本眼科学会は、市販の抗アレルギー点眼薬(スイッチOTC薬)の使用について、以下のような見解を示しています。
- 使用して良いケース: 医師によって「季節性アレルギー性結膜炎(花粉症など)」と既に診断されており、その症状(かゆみ)を緩和するために短期的に使用する場合。
- 使用を中止し、眼科を受診すべきケース:
- 市販薬を2日間使用しても、症状(かゆみ・充血)が改善しない場合。
- 感染性結膜炎(ウイルス性・細菌性)や、その他の目の病気(麦粒腫、コンタクトレンズ合併症など)との区別がつかない場合。
- 強い目の痛み、視力低下、光過敏、あるいは膿性の目やにを伴う場合。
要するに、「ただのかゆみだからアレルギーだろう」と自己判断し、市販薬を漫然と使い続けることは非常に危険です。感染症や角膜炎といった、より深刻な病気を見逃すリスクがあるため、「2日使って効かなければ専門医へ」という原則を守ることが、あなたの目の健康を守る上で極めて重要です。
角膜炎を疑うサインとコンタクトレンズ使用時の注意
これまで解説してきた結膜炎とは一線を画す、非常に危険な状態が「角膜炎(かくまくえん)」です。角膜(黒目)は、光が目に入る入り口であり、視力にとって最も重要な組織の一つです。ここが炎症を起こすと、結膜炎とは比べ物にならないほど強い症状が現れ、恒久的な視力障害や失明につながる可能性があります。
角膜炎を疑うべき「レッドフラグ(危険なサイン)」は以下の3つです:
- 強い目の痛み(疼痛): 「ゴロゴロする」というレベルではなく、「ズキズキする」「刺すような」激しい痛みを伴います。
- 視力低下: 明らかに「見えにくい」「かすんで見える」。結膜炎では通常、涙や目やにで一時的にかすむことはあっても、持続的な視力低下は起こりにくいです。
- 羞明(しゅうめい): 「光が異常にまぶしく感じる」状態です。明るい場所に出ると目が開けられないほどの不快感を伴います。
これらの症状が一つでも当てはまる場合は、結膜炎だと思い込まず、直ちに眼科を受診してください。
角膜炎の最大の危険因子は、コンタクトレンズ(CL)の不適切な使用です。米国疾病予防管理センター(CDC)は、CLに関連する眼感染症の危険性について、2025年にも最新の警告を発しています。
コンタクトレンズ関連角膜炎
CL装用者が上記のレッドフラグを感じた場合、それは「ただの結膜炎」ではなく、視力を脅かす角膜炎である可能性を第一に考えなければなりません。
- 細菌性角膜炎: CLを装用したまま寝る、レンズの洗浄を怠る、といった行為で緑膿菌などに感染し、急速に進行します。治療には、非常に高頻度(時には15〜30分おき)の広域抗菌薬点眼が必要となります。
- 真菌性角膜炎: 細菌性よりは稀ですが、CLの不衛生な管理で発症することがあります。
- アカントアメーバ角膜炎: これが最も恐ろしい角膜炎の一つです。アカントアメーバは水道水やプール、土壌などに存在する原虫です。CLを水道水ですすいだり、CLをつけたままシャワーや水泳をしたりすることで感染します。激しい痛みを伴い、治療は数ヶ月に及び、角膜移植が必要となることもあります。
角膜炎の治療期間や予防法について、また安全なコンタクトレンズの選び方について、これらの記事も併せてお読みください。
家庭・学校での結膜炎予防:タオル共有・プール利用の注意点
感染性結膜炎、特にウイルス性のものは感染力が非常に強いため、個人での治療と並行して、「他人にうつさない」「他人からうつされない」ための感染予防策が不可欠です。感染予防の基本は、ウイルスや細菌が目に入る経路を断つことです。
家庭内・職場での感染予防
CDCやNHS(英国民保健サービス)が一貫して推奨する、最も重要な予防策は以下の通りです:
- 徹底した手洗い: ウイルスは感染者の涙や目やにに含まれます。目を触った手でドアノブや電灯のスイッチ、共用の物品(PC、電話など)を触ると、そこから第三者に感染が広がります。石鹸と流水で頻繁に手を洗うことが最も重要です。
- タオルの共用禁止: 家族間であっても、顔や手を拭くタオルは完全に分けてください。バスタオルも同様です。
- 枕カバーやシーツの分離: 感染者の寝具は別に洗濯し、日光でよく乾かします。
- 化粧品の共用禁止: アイライナーやマスカラなどを共有してはいけません。感染期間中に使用した化粧品は破棄することが望ましいです。
- 目を触らない: 無意識に目をこすったり触ったりする癖を意識的にやめます。
これらの対策は、自宅でのケアの基本となります。
学校・保育園・プール利用について
子供が集団生活を送る場では、特に厳格な管理が求められます。先述の通り、咽頭結膜熱(プール熱)は学校保健安全法に基づき、主要症状が消えてから2日間は登校(登園)停止です。流行性角結膜炎(はやり目)も同様に、医師が感染の恐れがないと判断するまで登校停止となります。
プール熱という名前から分かるように、プールの水やビート板、タオルを介して感染が広がりやすいため、流行時期のプール利用には特に注意が必要です。症状がある間のプール利用は絶対に避けてください。
市販の抗アレルギー点眼を使ってはいけないとき
ドラッグストアでは、目の充血やかゆみに対する様々な市販薬(OTC)が販売されており、非常に便利です。しかし、その手軽さゆえに、誤った使用が深刻な事態を招くこともあります。特に、「充血をとる」ことを謳った血管収縮剤配合の点眼薬の長期使用や、抗アレルギー点眼薬の不適切な使用には注意が必要です。
最後に、市販の点眼薬を使ってはいけない、あるいは直ちに使用を中止して眼科を受診すべき「危険なサイン」をまとめます。
- 強い目の痛み、光過敏、視力低下がある場合:
これは結膜炎ではなく、角膜炎やぶどう膜炎など、失明リスクのある深刻な病気のサインです。市販薬で様子を見ている場合ではありません。 - コンタクトレンズ装用者の充血・痛み:
前述の通り、角膜炎(特にアカントアメーバ)のリスクが極めて高い状態です。CLを外し、レンズも持参して直ちに眼科を受診してください。 - 市販の抗アレルギー薬を2日間使っても改善しない場合:
日本眼科学会が示す「2日ルール」です。アレルギーではなく、感染症やその他の病気の可能性があります。 - 膿性の(黄色くネバネバした)目やにが出る場合:
アレルギーではなく、細菌性結膜炎の可能性が高いです。抗アレルギー薬は無効であり、適切な抗菌薬による治療が必要です。 - 片方の目だけ症状が強い場合:
花粉症などのアレルギーは両目に起こることが多いため、片目だけの場合は感染症や異物、角膜炎などを疑う必要があります。
また、世界保健機関(WHO)は、世界的に最も多い感染性失明原因として「トラコーマ」を挙げています。これはクラミジアの一種による慢性的な結膜炎で、主に衛生環境の悪い地域で問題となります。トラコーマは、適切な治療がなければ角膜の混濁と失明を招きます。日本国内での発生は稀ですが、市販薬で治らない結膜炎の背景には、このように多様な原因があり得ることを知っておくべきです。
網膜疾患(網膜剥離・網膜静脈閉塞症・黄斑変性)
前節では、結膜炎や角膜炎といった、主に眼の「表面」で起こる炎症性のトラブルについて詳しく見てきました。このセクションでは、さらに眼の奥深く、カメラで言えば「フィルム」や「イメージセンサー」に相当する、光を感じるための最も重要な組織、網膜(もうまく)に焦点を当てます。
網膜は、私たちが物を見るために不可欠な、薄く繊細な神経の膜です。この組織に問題が生じると、視力に直接的かつ深刻な影響が及ぶことがあります。「急に視界の一部が欠けた」「黒いカーテンが下りてきたように見える」「中心が歪んで見える」— これらは、網膜が発している重大なSOSサインかもしれません。ここでは、特に緊急性が高い、あるいは中高年になってから発症しやすい代表的な3つの網膜疾患、「網膜剥離」「網膜静脈閉塞症」「黄斑変性」について、その兆候と対処の基本を深く掘り下げて解説します。
網膜剥離:「カーテンが下りる」緊急事態
「ある日突然、目の前に無数の黒い点や虫のようなもの(飛蚊症)が嵐のように現れた」「視界の端でピカピカと光が走る(光視症)」「そして、視野の一部が黒いカーテンで覆われたように見えなくなった」— これらは、網膜剥離(もうまくはくり)の典型的な症状です。これは、眼科領域における最も緊急性の高い疾患の一つであり、文字通り「時間との戦い」になります。
網膜剥離とは、眼球の内側に張り付いている網膜が、その土台である脈絡膜(みゃくらくまく)から剥がれてしまう状態を指します。網膜は脈絡膜から栄養を受け取っているため、一度剥がれてしまうと栄養が途絶え、光を感じる細胞(視細胞)が急速に機能を失い、数日のうちに死んでしまいます。一度死んでしまった視細胞は、残念ながら元に戻りません。だからこそ、一刻も早い治療が必要なのです。
最も一般的なタイプは、網膜に「裂け目(網膜裂孔)」ができ、そこから眼球内の水分(硝子体液)が網膜の裏側に入り込むことで発生する「裂孔原性網膜剥離」です。日本眼科学会も指摘する通り、特に近視が強い方や、過去に眼を強くぶつけたことがある方、アトピー性皮膚炎の方は、網膜が薄く弱くなっていることがあり、注意が必要です。剥離がまだ中心部(黄斑)に及んでいない(macula-on)うちに手術を受けることが、視力を守る上で極めて重要です。
治療は、原則として手術となります。主な方法には、眼球の外側からシリコンのスポンジを当てて裂け目を塞ぐ「強膜バックリング術」や、眼球内から直接剥がれた網膜を元に戻し、レーザーで焼き付けて固定する「硝子体手術」があります。米国国立眼研究所(NEI)も、これらの手術法の有効性と緊急性を強調しています。どの手術法を選択するかは、剥離の状態や裂孔の位置によって決まります。
- 飛蚊症の「急激な」増加:いつも見えている数個の浮遊物ではなく、突然「墨を流したよう」「タバコの灰が舞うよう」な大量の黒い点が出現した場合。
- 光視症:暗い場所で、視界の端(特に耳側)で稲妻のような光が走る場合。
- 視野欠損:視界の一部が、まるで黒いカーテンや影で覆われて見えない場合。これは網膜が剥がれている範囲を示しています。
これらの症状に一つでも気づいた場合は、「疲れているだけ」と自己判断せず、休日や夜間であっても直ちに眼科救急を受診してください。網膜剥離が治るかどうかは、この初動の速さにかかっています。網膜剥離の原因を理解することは、リスクを持つ方にとって重要であり、手術後の回復期間についても正しい知識を持つことが不安の軽減につながります。
網膜静脈閉塞症:高血圧・動脈硬化が引き起こす「眼の脳梗塞」
網膜剥離が「壁紙が剥がれる」物理的なトラブルだとすれば、網膜静脈閉塞症(もうまくじょうみゃくへいそくしょう)は、網膜の「排水管が詰まる」循環のトラブルに例えられます。これは、網膜から血液を運び出す静脈が何らかの原因で詰まり、血液や水分が網膜内に溢れ出してしまう病気です。脳梗塞や心筋梗塞が「動脈」の詰まりであるのに対し、これは「静脈」の詰まりであり、「眼の脳梗塞」とも呼ばれます。
なぜ静脈が詰まるのでしょうか。最も多い原因は、高血圧や動脈硬化です。日本眼科学会も解説している通り、網膜では動脈と静脈が交差している箇所があり、動脈硬化によって硬くなった動脈が、柔らかい静脈を上から圧迫して押しつぶし、血流をせき止めてしまうのです。そのため、この病気は50代以降の中高年、特に高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病を持つ方に多く発症します。
症状は、詰まった場所によって異なります。網膜全体の静脈が詰まる「網膜中心静脈閉塞症(CRVO)」では、視界全体が急激にかすみ、著しい視力低下をきたします。一方、枝分かれした静脈の一部が詰まる「網膜静脈分枝閉塞症(BRVO)」では、詰まった領域に対応する視野の一部が暗く見えたり、かすんだりします。BRVOはCRVOよりも頻度が高いとされています。
この病気の最大の問題は、溢れ出た水分が網膜の中心部である「黄斑」に溜まり、「黄斑浮腫(おうはんふしゅ)」を引き起こすことです。黄斑が水ぶくれ状態になると、物が歪んで見えたり、中心が暗く見えたりし、視力が著しく低下します。また、血流が悪い状態が続くと、網膜が酸欠になり、それを補おうと質の悪い新しい血管(新生血管)が生えてくることがあります。この新生血管が破れると、大規模な網膜出血や、治療が非常に困難な血管新生緑内障を引き起こす可能性があります。
治療は、黄斑浮腫を抑え、新生血管の発生を防ぐことが目的となります。国立国際医療研究センターなどの専門機関では、病態に応じて、黄斑浮腫を引かせるための抗VEGF薬の硝子体注射、血流の悪い部分をレーザーで凝固する「網膜光凝固術」、あるいは硝子体手術などが選択されます。同時に、高血圧や糖尿病など、根本原因となっている内科疾患の管理が不可欠です。片眼のかすみや視野の異常を感じたら、それは全身の血管からの警告サインかもしれません。
黄斑変性:日本の失明原因上位、加齢による「中心」の障害
これまで網膜「全体」に関わる剥離や、網膜の「血管」の詰まりについて見てきました。最後は、その網膜の中でも、私たちが物を見る上で最も重要な「中心部」である黄斑(おうはん)そのものが障害される病気、黄斑変性(おうはんへんせい)についてです。
黄斑は、直径わずか1.5〜2mmほどの小さな領域ですが、視力に最も関わる視細胞が密集しています。私たちが文字を読んだり、人の顔を認識したり、色の違いを見分けたりできるのは、すべてこの黄斑のおかげです。この「ピントの芯」とも言える部分が、主に加齢によってダメージを受けるのが「加齢黄斑変性」です。
「最近、カレンダーやタイルの直線が波打って見える(変視症)」「読みたい文字の中心だけが黒く抜けて読めない(中心暗点)」— こうした症状は、黄斑が正常に機能していないサインであり、非常に心配な兆候です。加齢黄斑変性は、欧米では失明原因の第1位であり、日本眼科学会も警鐘を鳴らしている通り、高齢化に伴い日本でも急増しており、緑内障、糖尿病網膜症に並ぶ主な失明原因の一つとなっています。
この病気には、大きく分けて2つのタイプがあります。一つは、黄斑の組織が加齢とともに徐々に萎縮していく「萎縮型」です。進行は比較的ゆっくりですが、根本的な治療法はまだ確立されていません。もう一つは、黄斑の下に質の悪い「新生血管」が生えてきて、出血や水漏れを起こす「滲出型(しんしゅつがた)」です。こちらは進行が非常に早く、数ヶ月から数年の単位で急激な視力低下をきたすため、早期の治療介入が不可欠です。
滲出型加齢黄斑変性は、かつては有効な治療法が少ない病気でしたが、近年、新生血管の活動を抑える「抗VEGF薬」を眼内に注射する治療法が登場し、多くの患者さんの視力を維持、あるいは改善できるようになりました。黄斑変性という病気の全体像を理解することは、早期発見の第一歩です。網膜の変性疾患は多岐にわたりますが、加齢黄斑変性は特に重要な疾患であり、その詳細な病型分類、抗VEGF療法の具体的なスケジュール、サプリメントの役割などについては、次節の「加齢黄斑変性(タイプ・抗VEGF療法・生活改善)」で専門的かつ深く掘り下げて解説します。
よくある質問 (FAQ)
Q1: 飛蚊症が急に増えたら必ず網膜剥離ですか?
A: 必ずしもそうとは限りません。加齢による生理的な硝子体の変化(後部硝子体剥離)でも飛蚊症は増えます。しかし、網膜に裂け目ができた際に、網膜の血管が切れて硝子体に出血すると、飛蚊症が「急激に」「大量に」発生することがあります。これが網膜剥離の前兆である可能性があり、日本眼科学会も、飛蚊症の急増や光視症を伴う場合は速やかな眼科受診を推奨しています。特に強度近視の方は網膜剥離のリスクが高いため、より注意が必要です。
Q2: 網膜静脈閉塞症は自然に治りますか?
A: 枝分かれした静脈が詰まる分枝型(BRVO)で、出血や浮腫が軽い場合は、自然に出血が吸収されて視力が回復することがあります。しかし、中心部である黄斑に浮腫が長引くと、視細胞がダメージを受けて視力が完全には戻らないことがあります。そのため、黄斑浮腫がある場合はレーザー治療や抗VEGF薬の注射が検討されます。専門機関での診断に基づき、経過観察で良いか、積極的な治療が必要かを判断することが重要です。
Q3: 加齢黄斑変性と黄斑浮腫は違いますか?
A: はい、異なります。加齢黄斑変性は、主に加齢によって黄斑の組織そのものが「変性(性質が変わってしまう)」する病気です(萎縮型と滲出型)。一方、黄斑浮腫は、黄斑が「浮腫(むくむ)」状態を指す言葉であり、網膜静脈閉塞症、糖尿病網膜症、ぶどう膜炎など、様々な原因によって引き起こされます。加齢黄斑変性(滲出型)でも新生血管から水漏れが起こるため、黄斑浮腫を伴うことがあります。
Q4: 網膜剥離は、どのくらい早く手術すれば視力が残せますか?
A: 視力を決定づける黄斑がまだ剥がれていない段階(macula-on)で手術を受けることが、最も視力予後が良いとされています。NEIや日本眼科学会は、この段階であれば「緊急手術」の対象であり、症状に気づいてから24時間〜数日以内といった、日単位での迅速な対応が推奨されます。黄斑が剥がれてしまった後(macula-off)でも手術は行いますが、中心視力の回復には限界が出ることがあります。
Q5: これらの網膜疾患を家で予防する方法はありますか?
A: 網膜剥離そのものを家庭で確実に予防する方法はほとんどありませんが、強度近視の方は眼を強くぶつけないよう注意することが挙げられます。一方、網膜静脈閉塞症や加齢黄斑変性(滲出型)は、生活習慣病と深く関連しています。国立国際医療研究センターも指摘するように、高血圧、糖尿病、脂質異常症の管理を内科医と連携してしっかり行うことが、発症や重症化の予防につながります。また、加齢黄斑変性には禁煙、紫外線対策、抗酸化物質(ルテインなど)の摂取が予防に役立つ可能性が示されています。バランスの取れた食事を心がけることも、眼の健康維持の基本です。
加齢黄斑変性(タイプ・抗VEGF療法・生活改善)
前節では網膜に起こりうる様々な疾患の概要を見てきましたが、ここでは特に高齢化社会において深刻な問題となっている「加齢黄斑変性(かれいおうはんへんせい, AMD)」について、深く掘り下げて解説します。「黄斑変性」という言葉を聞いて、多くの方が「失明してしまうのではないか」という強い不安を感じるかもしれません。その不安は当然のものです。なぜなら、この病気は私たちが物を見る上で最も重要な「中心視力」を脅かすからです。
加齢黄斑変性は、50歳を過ぎた頃から発症リスクが高まる、網膜の中心部「黄斑(おうはん)」の病気です。世界保健機関(WHO)も、高齢化が進む国々において主要な視覚障害の原因の一つとして認識しています。黄斑は、私たちが文字を読んだり、人の顔を認識したり、細かい作業をしたりするために使う、最も解像度の高い「ピントの芯」にあたる部分です。この重要な部分が加齢によってダメージを受け、物がゆがんで見えたり、中心が暗く見えたりする症状を引き起こします。
日本では食生活の欧米化などの影響もあり、患者数が増加傾向にあるとされています。しかし、知っておいていただきたいのは、この病気は「早期発見」と「適切な治療の継続」によって、視力の維持が十分に可能になってきているということです。このセクションでは、加齢黄斑変性の2つの主要なタイプ、日本人に特有の病型、そして最新の治療法である抗VEGF療法、さらに進行を遅らせるための生活改善について、日本眼科学会が2024年に改訂した最新の診療ガイドラインや国内外の研究知見に基づき、詳しく解説していきます。
加齢黄斑変性の2つのタイプ:ゆっくり進む「萎縮型」と急速な「滲出型」
加齢黄斑変性は、その進行の仕方によって大きく2つのタイプに分けられます。これは、病気の性質が全く異なるため、治療方針を決定する上で最も重要な分類です。
1. 萎縮型(いしゅくがた)
「萎縮型」は、黄斑の組織が加齢とともに徐々にすり減り、萎縮していくタイプです。道路のアスファルトがゆっくりと劣化していく様子を想像すると分かりやすいかもしれません。網膜色素上皮(もうまくしきそじょうひ)という網膜を支える重要な細胞や、光を感じる視細胞そのものが少しずつ機能を失っていきます。
- 症状の進行:進行は非常にゆっくりです。「最近、少し文字が読みにくくなった」「中心がやや暗く感じる」といった、ゆるやかな視力低下が特徴です。
- 治療:残念ながら、2025年現在、萎縮型によって失われた視機能を明確に回復させる治療法は確立されていません。海外では「地図状萎縮(GA)」と呼ばれる重度の萎縮型に対する新しい治療薬の研究が進んでいますが、日本国内での一般診療にはまだ時間を要します。
- 対策:そのため、萎縮型と診断された場合の基本方針は、「これ以上悪化させないこと」と「滲出型へ移行しないか見張ること」になります。具体的には、後述するサプリメント(AREDS2)の検討や生活習慣の改善、そして定期的な眼科受診が中心となります。
2. 滲出型(しんしゅつがた)
「滲出型」は、加齢黄斑変性の中でも特に警戒が必要なタイプです。これは、黄斑の下にある脈絡膜(みゃくらくまく)から、本来あってはならない異常な血管(脈絡膜新生血管、CNV)が発生する病態です。この新生血管は非常にもろく、血液の成分や水分(滲出液)が漏れ出したり、血管が破れて出血したりします。
- 症状の進行:このタイプは進行が非常に速いのが特徴です。新生血管から漏れ出た水分は、黄斑部を水ぶくれ(浮腫)のように腫れさせ、網膜の構造を急速に破壊します。そのため、「数日前から急に、カレンダーの線がゆがんで見える」「視野の中心に黒い影(中心暗点)が現れた」といった自覚症状が出やすいです。
- 治療:滲出型は、放置すれば数ヶ月から数年の単位で重篤な視力低下に至るため、日本眼科医会も「すぐに治療が必要」と警鐘を鳴らしています。治療の第一選択は、この異常な血管の活動性を抑える「抗VEGF療法」となります。
これら2つのタイプは、OCT(光干渉断層計)と呼ばれる網膜の断面図を見る検査で、多くの場合、明確に区別することができます。
日本人に見られる特徴:ポリープ状脈絡膜血管症(PCV)とは?
滲出型加齢黄斑変性の中には、さらにいくつかのサブタイプ(亜型)が存在します。その中でも、特に日本人を含むアジア人に非常に多く見られるのが「ポリープ状脈絡膜血管症(PCV)」と呼ばれるタイプです。
報告によれば、日本の滲出型AMDの患者さんのうち、実に30%から50%がこのPCVであるとされています。これは欧米の白人(数%程度)と比べて著しく高い割合です。
PCVとは、脈絡膜の血管網の先端が「ポリープ(こぶ)」のように膨らむ特徴を持つ病態です。この「こぶ」が破れて大規模な網膜下出血を起こしやすい、非常に厄介なタイプです。蛍光眼底造影検査(ICG造影)という特殊な検査を行うことで、このポリープ状の病変を特定することができます。
なぜ、このPCVをわざわざ区別するのでしょうか。それは、通常の滲出型AMD(典型AMDと呼ばれます)と比べて、後述する抗VEGF薬単独の治療に抵抗しやすい(効きにくい)場合があるからです。この「日本人に多いタイプは、欧米の標準治療がそのままでは効きにくいことがある」という事実が、日本の眼科治療における重要なポイントとなります。そのため、日本眼科学会の2024年ガイドラインでも、PCVは典型AMDとは分けて治療方針が検討されており、PDT(光線力学的療法)の併用が今なお重要な選択肢として位置づけられています。
滲出型AMDの標準治療:抗VEGF硝子体注射
「目に注射をする」——。この言葉を聞いただけで、強い恐怖心や抵抗感を覚えるのは当然のことです。しかし、この「抗VEGF硝子体注射(こうブイイージーエフしょうしたいちゅうしゃ)」こそが、滲出型加齢黄斑変性の治療を革命的に変え、多くの患者さんの視力を守ってきた現在の世界的な標準治療です。
まず、この治療が何を目指しているのかを理解することが大切です。滲出型の原因は、「VEGF(血管内皮増殖因子)」という物質が過剰に放出され、異常な新生血管の成長を促してしまうことにあります。抗VEGF薬は、このVEGFの働きを直接ブロックする薬剤です。この薬を目の中(硝子体)に直接注射することで、新生血管の活動性を鎮め、漏れ出た水分を減らし、網膜の腫れ(浮腫)を引かせることができます。
多くの方が心配される「痛み」については、どうでしょうか。注射の前には、点眼麻酔薬を何度も使用し、目の表面の感覚を徹底的に麻痺させます。そのため、実際に針が刺さる痛みを感じることはほとんどありません。多くの方が「何か押されるような感じ」「一瞬チクッとしたかもしれない」と表現される程度です。注射自体は数秒で終わります。術後の目の奥の痛みや感染症のリスクはゼロではありませんが、非常にまれです。
この治療は、病気の「根治」を目指すものではなく、病気の活動性を抑え込み「管理」する治療です。薬の効果は時間とともに薄れるため、一度の注射で終わりではなく、定期的に継続する必要があります。この「継続」こそが、視力を守るための最大の鍵となります。
治療の負担を減らす工夫:T&Eレジメンと薬剤の選択
「注射を継続する必要があると言われても、一体いつまで、何回打てばいいのか」——。これは、治療を受ける患者さんにとって最も切実な疑問であり、不安の種です。かつては「毎月1回、固定で注射する」方法や、「悪化したら注射する(PRN)」方法が取られていましたが、これらには通院負担や治療不足のリスクがありました。
現在、日本で主流となっているのは「Treat-and-Extend(T&E)レジメン」と呼ばれる方法です。これは、患者さん一人ひとりの状態に合わせて、治療の「負担」と「効果」のバランスを取る、非常に合理的な投与計画です。
- 導入期:まず、病気の活動性をしっかり抑え込むため、月1回の注射を3回程度連続して行います。
- 維持期(T&E):3回目の注射後、OCT検査で網膜の腫れが引いている(活動性が抑えられている)ことを確認します。もし良好であれば、次回の注射までの期間を「2週間」または「4週間」延長します(例:4週間隔→6週間隔へ)。
- 延長と短縮:次の診察時も良好であれば、さらに期間を延長します(例:6週間隔→8週間隔へ)。もし、途中で網膜に再び水が溜まるなど、病気が再燃した兆候が見られたら、その時点で間隔を短縮します(例:8週間隔→6週間隔へ)。
このように、T&Eレジメンは「その患者さんにとって、病気を抑え込める最長の間隔」を見つけ出していくオーダーメイドの治療法です。最終的に3〜4ヶ月に1回の注射で安定する方もいれば、8週間隔を維持する必要がある方もいます。大切なのは、自己判断で中断せず、医師と決めたスケジュールで治療を継続することです。また、近年ではより効果が長く持続する新しい薬剤(高用量製剤や二重特異性抗体など)も登場しており、注射の間隔をさらに延ばす試みが日本国内の臨床試験でも進められています。もし現在の治療の負担が大きいと感じる場合は、薬剤の変更(スイッチ)が可能か医師に相談することも選択肢の一つです。
日本で今も重要な選択肢:PDT(光線力学的療法)併用
抗VEGF療法が標準治療となる一方で、日本眼科学会の2024年ガイドラインでは、ある特定の条件下で「PDT(光線力学的療法)」を併用することが現在も有効な治療選択肢として明記されています。これは、欧米のガイドラインではPDTの優先順位が下がっていることと対照的であり、日本人の病型に合わせた重要な戦略です。
PDTが特に考慮されるのは、前述した「ポリープ状脈絡膜血管症(PCV)」や、抗VEGF薬単独では反応が乏しい(効果が出にくい)症例です。
PDTは以下のような手順で行われます。
- 光に反応する特殊な薬剤(ベルテポルフィン)を腕から点滴します。この薬剤は、異常な新生血管に集まりやすい性質を持っています。
- 薬剤が新生血管に集まったタイミングで、ごく弱い(熱を発生しない)特殊なレーザーを病変部に照射します。
- 光に反応した薬剤が活性化し、新生血管を「閉塞」させ、活動性を低下させます。
抗VEGF薬が「新生血管の活動性を”抑える”(水漏れを止める)」治療であるのに対し、PDTは「新生血管そのものを”詰まらせる”(蛇口を閉める)」治療であるとイメージすると良いでしょう。特にPCVの「ポリープ(こぶ)」の部分は、PDTによって閉塞させやすいことが知られています。
抗VEGF薬とPDTを併用することで、より強力に病気の活動性を抑え込み、結果として抗VEGF薬の注射回数を減らせる可能性があることが、日本の多くの臨床研究で示されています。失明を防ぐため、医師が造影検査の結果からPCVであると診断し、PDTの併用を提案した場合は、その利点とリスクについてよく説明を受けることが重要です。ただし、PDTは脈絡膜が薄い症例では萎縮を早めるリスクも指摘されており、適応は慎重に判断されます。
進行を遅らせる生活習慣:禁煙、食事、サプリメント(AREDS2)
加齢黄斑変性は「加齢」という避けられない要因に加え、「生活習慣」という修正可能な要因が深く関わっています。特に、病気の進行を遅らせるために、今日からできることがいくつかあります。
1. 禁煙(最も重要)
加齢黄斑変性の発症・進行において、米国国立眼研究所(NEI)が「最大の修正可能なリスク因子」として挙げているのが喫煙です。喫煙は網膜の酸化ストレスを著しく高め、黄斑の細胞にダメージを与えます。もし現在喫煙されている場合、禁煙することが、どのような高価な治療にも勝る、最も確実で効果的な自己対策となります。
2. 食事と栄養
黄斑部には「ルテイン」や「ゼアキサンチン」といった色素(カロテノイド)が高濃度に存在し、これらが有害な光から網膜を守る「天然のサングラス」のような役割を果たしています。これらを多く含む緑黄色野菜(ほうれん草、ケール、ブロッコリーなど)や、網膜の健康維持に役立つオメガ3脂肪酸(青魚など)を積極的に摂取することが推奨されます。いわゆる「地中海食」のような、抗酸化物質を多く含むバランスの取れた食事療法が理想的です。
3. サプリメント(AREDS2)
「AREDS(エイアールイーディーエス)2」と呼ばれる、米国の大規模臨床研究に基づいた特定のサプリメント(ビタミンC、E、亜鉛、銅、ルテイン、ゼアキサンチンを含む)があります。厚生労働省のeJIMサイトでも紹介されていますが、ここで非常に重要な注意点があります。このサプリメントは、健康な人が加齢黄斑変性を「予防」するために飲むものではありません。
このサプリが推奨されるのは、すでに「中等度以上の萎縮型AMD」と診断された人、または「片眼がすでに滲出型AMD」である人が、重度の段階へ「進行するリスクを抑制する」ためです。自分にサプリメントが必要かどうかは、必ず眼科医に病期(ステージ)を確認した上で判断してください。
4. 紫外線対策と全身管理
強い太陽光(特に紫外線)も網膜へのダメージとなるため、外出時にはUVカット機能付きのサングラスや帽子を着用することが勧められます。また、高血圧や脂質異常症といった心血管系のリスク管理も、目の血流を保つ上で重要と考えられています。
こんな症状が出たらすぐ眼科へ(自己チェックと受診の目安)
滲出型加齢黄斑変性は、時間との戦いです。治療が早ければ早いほど、良好な視力を維持できる可能性が高まります。そのため、異常を早期に発見する「自己チェック」が非常に重要です。
アムスラー格子(Amsler Grid)による自己チェック
日本眼科学会も推奨している、格子状の図(アムスラー格子)を使った簡単なセルフチェックがあります。以下の手順で、週に1回程度、明るい場所で行ってください。
- もし老眼鏡をお持ちなら、かけた状態で行います。
- 片方の目を手で隠し、もう片方の目で格子の中心にある黒い点を見つめます。
- 中心の点を見つめたまま、格子の線全体がまっすぐに見えるか、ゆがんだり、欠けたり、暗く見えたりする部分がないかを確認します。
- 反対側の目も同様に行います。
もし、線が波打って見えたり(変視症)、中心が暗く見えたり(中心暗点)した場合は、滲出型AMDを発症しているか、活動性が高まっているサインかもしれません。
緊急性の高い症状(レッドフラグ)
以下のような症状が現れた場合は、決して「疲れているだけ」「様子を見よう」と自己判断せず、数日以内に(できれば当日か翌日に)眼科専門医を受診してください。
- 急に、物がゆがんで見え始めた
- 急に、視野の中心部が暗く(黒く)見えるようになった
- 急に、中心部の視力が落ちて、文字が読めなくなった
また、すでに抗VEGF注射による治療を受けている方が、注射の後に急な目の痛み、強い充血、急激な視力低下を感じた場合は、まれな合併症である眼内炎の可能性があります。次の予約を待たず、すぐに治療を受けた施設に連絡してください。
よくある質問(FAQ)
Q1: 加齢黄斑変性になると、必ず失明するのですか?
A1: 「失明」という言葉に強い不安を感じるお気持ちはよくわかります。「加齢黄斑変性」は、かつては中途失明の主要な原因であり、治療法がなかった時代は緑内障などと並び恐れられていました。しかし、滲出型に対しては抗VEGF療法という非常に有効な治療法が登場しました。適切な時期に治療を開始し、根気強く継続することで、病気の活動性を抑え込み、実用的な視力を生涯にわたって維持できる患者さんが大多数です。ただし、2025年の海外報告でも示されているように、治療を自己判断で中断してしまうと、再び病気が活動的になり視力が低下するリスクがあります。医師との信頼関係のもと、治療を継続することが何よりも重要です。
Q2: 目への注射は、痛くないのでしょうか?
A2: 治療を受ける上で、最も不安な点だと思います。注射の前には、非常に強力な点眼麻酔薬を何度も使用し、目の表面の感覚をほぼゼロにします。そのため、多くの場合、針が刺さる「痛み」そのものは感じません。ただし、目が押されるような「圧迫感」や、薬液が入ってくる感覚、あるいは一瞬「チクッ」とした違和感を覚えることはあります。注射は数秒で終わります。ほとんどの患者さんが「思ったより痛くなかった」「怖がっていたのが損だった」と仰います。不安が強い場合は、事前に医師や看護師にその気持ちを伝えておくと、より丁寧に配慮してもらえるでしょう。
Q3: 萎縮型と診断されました。本当に何もすることがないのでしょうか?
A3: 萎縮型には「滲出型のような緊急の治療はない」という意味であり、「何もしなくていい」わけではありません。まず、萎縮型から滲出型へ移行する可能性があるため、アムスラー格子での自己チェックと、医師に指示された間隔(例:3ヶ月〜半年に1回)での定期的なOCT検査が不可欠です。また、病気の進行を遅らせる可能性がある生活習慣(禁煙、緑黄色野菜の摂取、紫外線対策)を徹底することが、今できる最も重要な「対策」となります。目の健康を守るために、サプリメント(AREDS2)の適応があるかどうかも含め、主治医とよく相談してください。
Q4: サプリメント(AREDS2)は飲んだほうがいいですか?
A4: AREDS2サプリメントは、研究によって「中等度以上の萎縮型」または「片眼が進行したAMD」の患者さんにおいて、進行リスクを抑制する効果が示されています。逆に言えば、ごく初期のAMDや、健康な目の方が「予防」のために飲んでも、明確な効果は証明されていません。高用量のビタミンや亜鉛を含むため、体質によっては合わない場合もあります。ご自身の病期がAREDS2の適応に該当するかどうか、まずは眼科専門医に診断してもらい、その上で摂取を検討してください。
糖尿病網膜症(進行段階・光凝固・硝子体手術・定期検査)
前節では加齢黄斑変性について見てきましたが、本節では、日本の中途失明原因の上位を占め、糖尿病患者さんにとって最大の懸念事項の一つである「糖尿病網膜症」について、深く掘り下げて解説します。
糖尿病と診断されたとき、多くの方は食事制限や血糖値のコントロールに意識が集中し、目のことは後回しになりがちです。しかし、日本糖尿病学会の2024年ガイドラインが「Aグレード」で強く推奨しているように、糖尿病と診断された時点(または疑われた時点)で、症状がなくても眼科を受診することが極めて重要です。
なぜなら、糖尿病網膜症の最大の恐怖は、重症化して「増殖網膜症」と呼ばれる段階に進むまで、自覚症状がほとんどない「沈黙の病気」であるためです。視力検査で1.0(20/20)と判定されても、網膜の血管は静かにダメージを受け続けている可能性があります。この「見えるから大丈夫」という誤解こそが、発見を遅らせる最大の原因となります。
なぜ症状がないまま進行するのか?「沈黙の病気」の正体
「症状がないのに、なぜ病気が進行するのか」と疑問に思うのは当然です。その答えは、網膜の構造にあります。
網膜は光を感じる神経の膜ですが、痛みを感じる神経(痛覚)はありません。そのため、高血糖によって網膜の毛細血管が傷つき、小さな出血(毛細血管瘤)が起きたり、血液の成分が漏れ出したりしても、初期段階では全く痛みを感じません。これが「単純網膜症」と呼ばれる第一段階です。
さらに病状が進み、血管が詰まって網膜の一部が酸素不足(虚血)になっても、その範囲が視界の中心である「黄斑(おうはん)」を避けていれば、視力低下のサインとして自覚することは困難です。症状が出るとすれば、血液の成分が黄斑に漏れ出してむくみを引き起こす「糖尿病黄斑浮腫」による視界のぼやけや、進行した段階での大出血による飛蚊症(黒い点が見える)などですが、これらは既に治療介入が急がれるサインです。
このように、糖尿病網膜症は「自覚症状が出た=かなり進行している」という特徴を持つため、唯一の防御策は、症状が出る前に眼科の「眼底検査」で網膜の血管を直接観察し、早期発見することなのです。これは、高血圧性網膜症などと同様に、全身の血管の状態を反映する「窓」としての役割も持っています。
進行段階と受診間隔の目安:4つのステージ
糖尿病網膜症は、その進行度によって大きく4つのステージに分類されます。そして、このステージこそが、眼科医が「次にいつ受診してください」と伝える間隔の根拠となります。ここでは、厚生労働省の公開資料などで示されている分類と、一般的な受診間隔の目安を解説します。
ただし、これはあくまで目安であり、血糖コントロールの状態、高血圧や腎症の合併、妊娠の有無などによって、医師は受診間隔を個別に調整します。
- ステージ1:網膜症なし
状態:糖尿病と診断されているが、眼底検査では網膜に異常が見られない状態です。
受診目安:年に1回程度。ただし、これは「もう大丈夫」という意味ではなく、「来年もチェックが必要」という意味です。 - ステージ2:単純(非増殖)網膜症
状態:網膜の毛細血管がもろくなり、小さな出血点(毛細血管瘤)や、血液成分の漏れ(硬性白斑)が見られる初期段階です。まだ自覚症状はありません。
受診目安:3~6ヶ月に1回程度。病変の進行が早まっていないか、黄斑浮腫が出てきていないかを監視します。 - ステージ3:増殖前網膜症
状態:血管が詰まる範囲が広がり、網膜が広範囲に酸素不足(虚血)に陥り始めた状態です。体は「危険だ」と判断し、酸素を補うために新しい血管(新生血管)を作ろうとする準備(SOS信号)を出し始めます。この段階でも自覚症状がないことが多いですが、失明へのカウントダウンが始まった非常に重要な時期です。
受診目安:1~2ヶ月に1回程度。レーザー治療(後述)のタイミングを慎重に見極める必要があります。 - ステージ4:増殖網膜症
状態:酸素不足を補おうと、網膜の表面や硝子体に向かって「新生血管」という、もろくて異常な血管が生えてきてしまった段階です。この新生血管は非常に弱いため、破れて硝子体出血という眼内の大出血を起こしたり、網膜を引っ張って牽引性網膜剥離を引き起こしたりします。ここまで来ると、急激な視力低下や失明の危険性が非常に高くなります。
受診目安:2週~1ヶ月に1回程度。レーザー治療や手術(後述)が必須となります。
治療の柱①:網膜光凝固(レーザー治療)の目的と限界
「レーザー治療」と聞くと、多くの方が視力を回復させる「レーシック」のような治療を想像するかもしれませんが、糖尿病網膜症に対するレーザー治療(網膜光凝固術)は、その目的が全く異なります。
最大の目的は、「視力の回復」ではなく、「失明の予防」です。日本眼科学会も解説している通り、この治療は「これ以上悪くしないため」に行われます。この点を誤解していると、治療後に「視力が良くならなかった」と不満を感じてしまうため、正しい理解が不可欠です。
では、具体的に何をしているのでしょうか。
増殖前~増殖網膜症(ステージ3~4)で、網膜が酸素不足に陥ると、「血管新生因子(VEGF)」というSOS信号物質が放出されます。これが新生血管を生やす原因です。レーザー治療(特に汎網膜光凝固:PRP)は、酸素不足に陥っている網膜の周辺部(視力にあまり関わらない部分)をレーザーで焼き固める治療です。
これにより、以下の2つの効果が期待できます:
- 酸素を必要とする網膜細胞の総量を減らし、網膜全体の酸素不足を緩和する。
- SOS信号(VEGF)を出す細胞自体を破壊し、新生血管の発生や成長を抑制する。
これは、いわば「船が沈まないように、重要でない積荷(網膜の周辺部)を捨てて、最も重要な操舵室(黄斑部=中心視力)を守る」という考え方です。そのため、治療の代償として、視力の回復は望めず、むしろ治療後しばらくは黄斑浮腫が悪化して一時的に見えにくくなったり、視野(見える範囲)が狭くなったり、夜間に見えにくく(夜盲)なったりすることがあります。しかし、これらは失明を防ぐための「トレードオフ」なのです。
治療の柱②:硝子体手術(進行した場合の最終手段)
もし、レーザー治療のタイミングを逃したり、レーザー治療を行っても病気の勢いが止まらなかったりした場合はどうなるでしょうか。その場合、「硝子体手術(しょうしたいしゅじゅつ)」という、より高度な眼科手術が必要となります。
日本眼科学会も、糖尿病網膜症を硝子体手術の主な適応疾患として挙げています。主な目的は以下の2つです:
- 硝子体出血の除去:
新生血管が破れて眼球の中(硝子体腔)が血液で満たされてしまうと、光が網膜に届かず、視力が急激に低下します。この溜まった血液を、手術器具で吸い出して取り除きます。 - 牽引性網膜剥離の治療:
新生血管が治る過程で「増殖膜」という線維性の膜(かさぶたのようなもの)を形成し、これが網膜を引っ張って剥がしてしまいます(牽引性網膜剥離)。この増殖膜を丁寧に剥がし、網膜を元の位置に戻します。
この手術は、眼球に開けた0.5mmほどの小さな穴から器具を挿入して行う、非常に繊細なものです。手術によって、出血で全く見えなかった視界が劇的に改善することもありますが、網膜自体が長期間ダメージを受けていた場合、手術後の回復には時間がかかり、視力が完全には戻らないことも少なくありません。また、手術後の生活にも一定の制限(うつ伏せ姿勢など)が必要となる場合があります。硝子体手術は「最後の砦」であり、ここまで進行させないことが何よりも重要なのです。
定期検査こそが最強の「お守り」:内科との連携
ここまで読んでいただいて明らかなように、糖尿病網膜症の治療は「早期発見・早期介入」に尽きます。レーザーや手術は、あくまで進行してしまった病気に対する「ダメージコントロール」に過ぎません。
本当の意味での「治療」は、内科での血糖・血圧・脂質のコントロールと、眼科での「定期検査」です。
厚生労働省の資料が強調するように、眼底検査は「体外から唯一、直接血管の状態を観察できる」貴重な検査です。内科医が血液検査の数値(HbA1cなど)で体の状態を把握するのに対し、眼科医は眼底検査で「血管が実際にどれだけダメージを受けているか」をその目で確認します。
この2つの情報が揃って初めて、あなたの糖尿病が今どのような状態にあるのかを正確に把握できます。内科と眼科は、糖尿病治療における「車の両輪」なのです。
「今日は忙しいから」「まだ見えているから」と眼科の受診を先延ばしにすることは、失明のリスクを自ら高めていることに他なりません。症状がないうちから定期的に眼科を受診することこそが、あなたの大切な目の健康を守る、最強の「お守り」となります。進行すると、新生血管緑内障という治療が困難な緑内障や、目の奥の激しい痛みを伴う合併症を引き起こす前に、必ず定期検診を継続してください。
よくある質問 (FAQ)
Q1: 糖尿病ですが、視力は1.0あります。眼科に行かなくていいですか?
A1: いいえ、絶対にいけません。糖尿病網膜症は、末期(増殖網膜症)になるまで自覚症状や視力低下がほとんどない病気です。日本糖尿病学会は、診断された時点での眼科受診をAグレード(強く推奨)としています。視力が良くても、網膜の血管はダメージを受けている可能性があります。
Q2: 受診間隔の目安(年1回→3~6か月→1~2か月)は絶対ですか?
A2: あれは、厚生労働省が2007年頃に示した標準的な目安であり、現在も大枠は変わりません。しかし、実際の間隔は、あなたの網膜症のステージだけでなく、血糖コントロールの状態(HbA1c)、血圧、腎症の有無、妊娠などを考慮して、眼科医が個別に決定します。目安より短くなることも、良好であれば長くなることもあります。
Q3: 網膜光凝固(レーザー治療)をすれば、視力は元に戻りますか?
A3: いいえ、戻りません。この治療の目的は「視力の回復」ではなく、「失明の予防(現状維持または進行を遅らせること)」です。日本眼科学会もこの点を明記しており、酸素不足の網膜を焼いて新生血管の発生を抑えるための治療です。むしろ、副作用として視野が狭くなることもありますが、失明を防ぐためには必要な治療です。
Q4: 硝子体出血があると言われました。すぐに手術が必要ですか?
A4: 出血の量や場所によります。少量の出血であれば自然に吸収されるのを待つこともありますが、数ヶ月しても吸収しない場合や、出血で網膜の状態が確認できない場合、あるいは牽引性網膜剥離を伴う場合は、硝子体手術が検討されます。放置せず、専門医と方針を相談してください。
Q5: レーザーではなく、注射(抗VEGF薬)だけで治せますか?
A5: 黄斑浮腫に対しては抗VEGF薬注射が第一選択です。しかし、増殖網膜症(PDR)そのものに対しては、海外の臨床研究では注射単独の良好な成績もありますが、日本ではまだ網膜光凝固(PRP)が標準治療とされています。理由として、レーザーは効果が永続的であるのに対し、注射は効果が一時的で頻回な通院と費用が必要となるためです。多くの場合、レーザーを基本とし、補助的に注射が併用されます。
視神経疾患(視神経炎・虚血性視神経症・視神経萎縮)
前節では、網膜の毛細血管が障害される「糖尿病網膜症」について詳しく見てきました。網膜という「スクリーン」が正常に光を受け取っても、その情報を脳に送る「メインケーブル」が損傷してしまえば、深刻な視力障害につながります。それが、今回解説する「視神経疾患」です。
視神経は、網膜で受け取った視覚情報を脳へ伝達する唯一の経路であり、約120万本もの神経線維の束でできています。この重要なケーブルが、炎症によって「火事」を起こしたり(視神経炎)、血流が途絶えて「梗塞」を起こしたり(虚血性視神経症)、あるいは様々な原因の結果として最終的に「枯れて」しまったり(視神経萎縮)するのが、これらの疾患群です。
これらの疾患は、緑内障や網膜疾患とは異なり、突然発症することも多く、患者さんの不安は計り知れません。本章では、視神経疾患の中でも代表的な3つの病態について、日本の大学病院の解説[3]や、Mayo Clinic[11]、米国国立医学図書館(NCBI)[14]などの最新の知見に基づき、その原因、症状、そして「回復の可能性」という最も重要な違いについて、深く掘り下げて解説します。
視神経炎とは|急に片眼がかすむ・痛むときに考える病気
「ある日突然、片方の目がかすんできた」「色合いがいつもと違って見える」「目を動かすと、目の奥が鈍く痛む」——このような恐ろしい症状は、視神経炎(Optic Neuritis)の典型的なサインかもしれません。これは、視神経ケーブルが炎症を起こし、腫れ上がってしまう状態です。
視神経は、電気コードを覆うビニールの被覆のように、「ミエリン鞘」という絶縁体で守られています。視神経炎の多くは、このミエリン鞘が何らかの原因で破壊され、神経が「ショート」してしまうことで発症します。炎症によって神経の信号伝達が妨げられるため、急激な視力低下や、視野の真ん中が見えにくくなる「中心暗点」、そして特に赤色などがくすんで見える「色覚異常」が起こります。また、約9割のケースで、目を動かすと痛み(眼球運動時痛)を伴うのが大きな特徴です[4, 10]。
では、なぜこのような炎症が起こるのでしょうか。多くの場合、兵庫医科大学病院の資料[4]などでも示されているように、原因が特定できない「特発性」も多いのですが、しばしば全身の自己免疫疾患と関連しています。特に重要なのが、中枢神経系の脱髄疾患である「多発性硬化症(MS)」や、「視神経脊髄炎スペクトラム障害(NMOSD)」です[1, 2, 3]。これらは、本来ウイルスなどから体を守るはずの免疫系が、自分自身の視神経や脊髄を攻撃してしまう病気です。そのため、眼科では視神経炎を診断した場合、血液検査で特殊な抗体(抗AQP4抗体や抗MOG抗体)を調べたり、MRIで脳や脊髄に他の病変がないかを確認したりすることが不可欠です[4]。
この病気の予後について、Mayo Clinicの解説[12]では、多くの場合、治療しなくても数週間から数ヶ月で視力は自然に改善する傾向があるとされています。しかし、特に症状が重い場合や、MS・NMOSDが疑われる場合、視力の回復を早める目的で、入院して高用量のステロイドを3日間ほど点滴する「ステロイドパルス療法」が行われるのが一般的です[4, 12]。米国国立眼研究所(NEI)[17]による過去の大規模研究では、飲み薬のステロイドだけでの治療は、かえって再発リスクを高める可能性があると報告されており、現在では推奨されていません。視神経炎は、適切な検査と治療によって「回復が見込める」視神経疾患の代表ですが、目の奥の痛みを伴う急な視力低下に気づいたら、決して放置してはいけません。
虚血性視神経症とは|50歳以降に多い“朝起きたら見えない”タイプ
視神経炎とは対照的な病態、それが「虚血性視神経症(Ischemic Optic Neuropathy)」です。これは、視神経が炎症で「燃える」のではなく、血流が途絶えて「梗塞(こうそく)」を起こす状態です。「目の心筋梗塞」や「視神経の脳梗塞」と例えると分かりやすいかもしれません。
この病気は、特に50歳以上の方に多く[13]、典型的な症状は「朝、目が覚めたら、片方の目が見えなくなっていた」というものです。視神経炎と決定的に違うのは、「痛みを伴わない」ことです[13]。また、視野全体が真っ暗になるというよりは、「視野の上半分(あるいは下半分)が、まるでカーテンが下りたように全く見えない」(水平半盲)という特徴的な症状が出ることがあります[5]。
なぜこのような「視神経の梗塞」が起こるのでしょうか。視神経(特に眼球とつながる部分である視神経乳頭)は、非常に細い血管によって栄養されています。この細い血管が、動脈硬化や血栓によって詰まってしまうのが原因です。そのため、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙といった、いわゆる生活習慣病のリスクファクターを持つ人に発症しやすいことがわかっています[13]。また、もともと視神経乳頭の構造が混み合っている「disc at risk」と呼ばれる形態の人も発症しやすいとされています。
この疾患で最も重要な点は、治療に関する厳しい現実です。千葉大学病院の治験解説ページ[5]や大阪大学病院の臨床研究資料[8]でも明記されている通り、残念ながら、発症してしまった直後に視力を回復させるための「確立された有効な治療法」は、現時点では存在しません[13, 16]。ステロイドやビタミン剤、血管拡張薬などが試みられることもありますが、その効果は限定的です。
したがって、この病気と診断された場合の医療の焦点は、「失われた視力を取り戻す」ことではなく、2つの重要な目標に移ります。第一に、側頭部の痛みや発熱などを伴う緊急性の高い「動脈炎性」のタイプ[16](巨細胞性動脈炎)を除外すること。第二に、そして最も重要なこととして、「もう片方の目」を全力で守ることです。NCBIの総説[13]によれば、約20%の人が5年以内に対側の目も発症するとされており、血圧、血糖、コレステロールの厳格な管理が、反対側の目の「梗塞」を防ぐために何よりも重要になります。
視神経萎縮とは|他の眼病の“あと”に起こる不可逆変化
視神経炎という「火事」、あるいは虚血性視神経症という「梗塞」。これらの激しいダメージ(あるいは緑内障のような慢性的な圧迫)が視神経に加わった結果、最終的に神経線維が死滅し、元に戻らない「傷跡」として残った状態——それが「視神経萎縮(Optic Atrophy)」です。
非常に重要なことですが、専門的な文献[15]でも強調されている通り、視神経萎縮は「それ自体が一つの病気」というよりも、「様々な病気の結果を示す臨床所見(サイン)」です[14]。健康な視神経乳頭は、豊富な血流を反映してピンク色をしていますが、萎縮を起こすと神経線維が失われ、血流も乏しくなるため、白っぽく「枯れた」ように見えます。
原因は多岐にわたります。前述の視神経炎や虚血性視神経症の後遺症のほか、緑内障による長年の圧迫、脳腫瘍などによる視神経の圧迫、外傷、特定の薬剤や中毒、あるいはレーベル病などの遺伝的な要因も含まれます。
この病態について、関西医科大学病院の解説[7]では「通常、回復することはありません」と明確に述べられています。一度死滅してしまった神経線維は、現在の医学では再生させることができないため、視神経萎縮による視力や視野の喪失は、残念ながら「不可逆的な変化」です。
したがって、治療の焦点は「萎縮そのものを治す」ことではなく、2点に絞られます。第一に、もし緑内障や腫瘍など、今もなお神経を圧迫し続けている「原因」が特定されれば、その原因を直ちに取り除くこと(例えば、緑内障手術で眼圧を下げるなど)。第二に、すでに萎縮が完了してしまっている場合は、残された視機能(ロービジョン)を最大限に活用し、生活の質(QOL)を維持・向上させるための「ロービジョンケア」へと移行することです。これには、拡大鏡や遮光眼鏡、音声読み上げソフトなどの活用が含まれます。
視神経炎と虚血性視神経症の違い|検査でどこを見ているのか
「突然、片目が見えにくくなった」と患者さんが訴えた時、眼科医の頭の中はフル回転しています。「炎症」なのか、「虚血」なのか、あるいは「網膜」の問題なのか。これを正確に見分けることが、予後を大きく左右するからです。医師が注目しているのは、「患者さん自身」「症状の性質」そして「画像検査」の3つの情報です。
- 患者さん自身(背景):年齢はいくつですか?(視神経炎は20〜40代に多い、虚血性視神経症は50歳以上に多い[13])高血圧や糖尿病の持病はありますか?(あれば虚血を強く疑う)過去にMSや自己免疫疾患を指摘されたことは?(あれば視神経炎を疑う)
- 症状の性質:痛みはありますか?(目を動かすと痛いなら視神経炎[10]、痛みが全くないなら虚血性視神経症[13])。発熱や、こめかみの痛み、食事の時に顎が痛むなどの全身症状はありませんか?(もしあれば、緊急で全身ステロイド治療が必要な「動脈炎性虚血性視神経症」[16]を最優先で疑います)
- 検査所見:眼底検査で視神経乳頭がどのように腫れているか、出血の有無などを確認します。さらに、OCT(光干渉断層計)[9]という検査で、視神経線維の厚さや、OCTアンギオグラフィーで乳頭周囲の毛細血管の血流が途絶えていないかを詳細に調べます。
決定的な鑑別には、多くの場合MRI(磁気共鳴画像)検査が不可欠です[4, 12]。視神経炎の場合、造影剤を使用すると、炎症を起こしている視神経が白く「光って」見えます。一方、虚血性視神経症(NAION)では、通常このような増強効果は見られません。MRIは同時に、視神経炎の原因となりうる多発性硬化症(MS)の病変が脳内に隠れていないか、あるいは腫瘍による圧迫がないかも確認できるため、非常に重要な検査です。
さらに、視神経炎が疑われ、特に両目に症状が出たり、脊髄炎を伴ったりするなど、NMOSD(視神経脊髄炎)[19]が疑われる場合は、血液検査で「抗AQP4抗体」や「抗MOG抗体」といった特殊な自己抗体を測定します[1, 2, 4]。これらの抗体が陽性であれば、MSとは異なる特別な治療(ステロイドや免疫抑制剤)が必要になるため、網膜剥離や黄斑変性といった他の眼科疾患とは異なる、神経内科との密接な連携が求められます。
すぐに受診すべき危険な視力障害のサイン
ここまで解説してきたように、視神経疾患は「様子を見ても良いもの」と「一刻を争うもの」が混在しています。以下の症状(レッドフラグ)に気づいた場合は、「そのうち治るだろう」と自己判断せず、直ちに眼科専門医を受診してください。
- 数時間から1〜2日の間に、片方の視力が急激に落ちた(視神経炎、虚血性視神経症の急性期)[4, 5]
- 目を動かすと、目の奥に鈍い痛みを感じる(視神経炎を強く示唆)[4, 10]
- 視野の「上半分」または「下半分」が、カーテンがかかったように突然見えなくなった(虚血性視神経症の典型)[5]
- 高齢者(特に60歳以上)で、急な視力低下と同時に、こめかみの痛み、発熱、物を噛むと顎が痛む・だるいといった全身症状がある(これは「動脈炎性虚血性視神経症」の可能性があり、失明を防ぐために緊急の全身ステロイド治療が必要です)[16]
- 両目の視力が急速に低下する、または片目の視力低下に続いて、もう片方の目も見えにくくなった(NMOSDなど、より重篤な病態の可能性)[1, 2]
その目の痛みや視力低下は、あなたの体が出している重要なSOSサインです。特に視神経の病気は、治療のタイミングが予後を大きく左右します。ためらわずに専門医の診断を受けてください。
よくある質問(FAQ)
Q1: 視神経炎は自然に治りますか?
A: 典型的な視神経炎の多くは、Mayo Clinicの解説[12]にもあるように、数週間から数ヶ月かけて自然に視力が改善する傾向があります。しかし、全員が完全に元通りになるわけではなく、特に背景にNMOSD[1, 2]などがある場合は、重い後遺症が残ることもあります。急性期にステロイドパルス療法[4, 12]を行うのは、この回復を早め、炎症を強力に抑え込むことで、できるだけ後遺症を残さないようにするためです。いずれにせよ、自然に治るかもしれないと様子を見ることは極めて危険であり、必ず精密検査が必要です。
Q2: 虚血性視神経症に効く薬はありますか?
A: 残念ながら、発症直後の非動脈炎性虚血性視神経症(NAION)に対して、視力を回復させることが科学的に証明された「確立された治療薬」は、現時点(2025年現在)ではありません[5, 13, 16]。治療の焦点は、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった全身の危険因子を厳格に管理し、もう片方の目に同じ発作が起きるのを予防することに置かれます。日本では大阪大学[8]などで「経角膜電気刺激」といった神経保護の臨床研究も進められていますが、まだ一般診療ではありません。
Q3: 視神経萎縮は元に戻せますか?
A: 一度「萎縮」してしまった(死滅してしまった)視神経線維を、現在の医学で元通りに「再生」させる方法は、残念ながらありません[7, 14]。これは、NEI(米国国立眼研究所)[18]などが再生医療の研究を進めている分野ではありますが、実用化には至っていません。したがって、視神経萎縮の治療とは、萎縮の原因となっている病気(緑内障の眼圧など)を管理して進行を食い止めること、そして、残された視機能を最大限に活かす「ロービジョンケア」を行うことが中心となります。
Q4: 視神経炎と緑内障の視野障害はどう違いますか?
A: どちらも視神経が障害されますが、性質が全く異なります。視神経炎は「急性」の発症で、数日のうちに見えにくくなり、目の痛みを伴うことが多く、視野は中心部(中心暗点)が欠けることが多いです。一方、緑内障の多く(開放隅角緑内障)は「慢性」で、何年もかけてゆっくりと進行し、痛みはなく、視野は周辺部(鼻側階段状など)から欠けていくため、末期になるまで自覚症状が出にくいという大きな違いがあります[7, 14]。
Q5: 視神経の病気はどの科を受診すればいいですか?
A: まず「目が見えにくい」という症状の入り口は、「眼科」です。眼科で詳細な眼底検査、OCT、視野検査などを行い、視神経に問題があるかどうかを診断します。その結果、視神経炎が強く疑われ、厚生労働省の資料[1]で定義されるような視神経脊髄炎(NMOSD)や多発性硬化症(MS)[2, 4]が原因として考えられる場合は、「神経内科」と密接に連携して、MRI検査やステロイド治療、その後の免疫抑制療法などを進めていくことになります。
ここまで、視神経という「ケーブル」そのものが障害される重篤な疾患について、炎症、虚血、そして萎縮という3つの側面から詳しく見てきました。次節では、より多くの人が日常的に経験する「ピントが合わない」という問題、すなわち近視、遠視、乱視、そして老視といった「屈折異常」について、その原因と最新の対処法を詳しく解説していきます。
近視・遠視・乱視・老視(原因・メガネ/コンタクト/手術)
前節では視神経に関わる疾患という、目の奥深くにある重要な構造の問題について見てきました。このセクションでは、それとは異なり、私たちにとって最も身近であり、世界中で何十億人もの人々が経験している「ピントが合わない」問題、すなわち屈折異常について、日本の最新のガイドラインや国際的な知見(WHOの2024年報告など)に基づき、深く掘り下げていきます。
「近視(近眼)」「遠視」「乱視」、そして40歳を過ぎればほぼ全ての人が経験する「老視(老眼)」。これらは病気というより「状態」ですが、放置すれば生活の質を著しく低下させ、特に子供の場合は学習や発達にも影響を与えかねません。「私の近視はどこまで進むのか」「子供の視力を守るにはどうすればいいのか」「レーシック手術は本当に安全なのか」といった不安や疑問は、多くの方が抱える切実なものです。この章では、それらの原因から、最も基本的な眼鏡(メガネ)、コンタクトレンズ、そして最新の屈折矯正手術に至るまでの選択肢を、一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。
屈折異常の基本:近視・遠視・乱視・老視とは?
私たちの目を高性能なカメラに例えるなら、「網膜(もうまく)」がフィルムやセンサーにあたります。外から入ってきた光が、目のレンズである「角膜(かくまく)」と「水晶体(すいしょうたい)」を通り、フィルムである網膜上に「ピッタリとピントが合う」状態が、いわゆる「正視(せいし)」です。屈折異常とは、このピントが網膜上からズレてしまう状態を指します。
近視(きんし)
最も多くの日本人が経験している屈折異常です。これは主に、眼球の奥行き(眼軸長:がんじくちょう)が正常よりも「長く」伸びすぎてしまうことで起こります。カメラで言えば、フィルムがレンズから遠すぎる位置にあるようなものです。その結果、ピントが網膜の「手前」で合ってしまい、遠くの景色がぼやけて見えます。近くのものは比較的よく見えます。日本の厚生労働省(e-ヘルスネット)も、多くの近視は眼軸長が伸びることによる軸性近視であると説明しています。一度伸びてしまった眼軸は元に戻すことができないため、特に成長期に「近視の進行をいかに抑制するか」が世界的な公衆衛生上の課題となっています(WHO MyopiaEd 2022)。近視のマネジメントについて詳しく知ることも重要です。
遠視(えんし)
近視とは逆に、眼軸長が「短い」か、または角膜や水晶体の光を曲げる力(屈折力)が弱すぎることが原因です。ピントが網膜の「後ろ」で合ってしまう状態です。遠視の方は、遠くを見るときも近くを見るときも、常に目のピント調節機能(調節力)を使い続けている状態になります。若い頃は、この調節力が強いため、無理やりピントを合わせることができてしまいます。そのため、「自分は目が良い」と誤解しているケースが少なくありません。しかし、水面下では常に目が頑張っているため、日本眼科学会も指摘するように、眼精疲労(目の疲れ)や頭痛、肩こりの原因となりやすいのが特徴です。子供の場合、強い遠視が見逃されると、ピントを合わせる訓練がうまくできず、「弱視」の原因になることもあるため注意が必要です。
乱視(らんし)
これは、ピントが合う「点」が一つではない状態です。多くの場合、角膜(黒目)の表面が、きれいな球形(サッカーボール型)ではなく、ラグビーボールのように歪んでいることが原因です。方向によって光の曲がり方が異なるため、ピントが2ヶ所以上にズレてしまいます。その結果、遠くも近くも関係なく、物が二重に見えたり、にじんだり、ぼやけたりします。例えば、夜間に信号の光が線のように伸びて見えるのは、乱視の典型的な症状の一つです。乱視の原因と治療法については、別の記事でさらに詳しく解説しています。
老視(ろうし)=老眼
これは、上記の3つとは根本的にメカニズムが異なります。「病気」ではなく、誰もが経験する「加齢による生理的な変化」です。カメラのオートフォーカス機能が衰えるようなものです。私たちの目のレンズ(水晶体)は、若い頃は非常に柔らかく、近くを見るときは「毛様体筋(もうようたいきん)」という筋肉が緊張して水晶体を厚くし、ピントを合わせています。しかし、日本眼科学会によると、40歳頃から水晶体そのものが硬くなり始め、毛様体筋がどれだけ頑張っても十分に厚くならず、ピント調節力が低下します。これが老視の正体です。よく「近視の人は老眼にならない」という俗説がありますが、これは誤りです。近視の人はもともとピントが手前に合っているため、メガネを外せば近くが見えるだけで、調節力が衰えるという変化自体は全ての人に平等に起こっています。老視(老眼)の最新治療については、こちらの記事も参照してください。
矯正の第一選択:眼鏡(メガネ)のすべて
屈折異常に対する最も安全で基本的、かつ長い歴史を持つ矯正手段が眼鏡です。その原理は非常にシンプルで、近視(ピントが手前)には光を広げる「凹レンズ(おうレンズ)」を、遠視や老視(ピントが後ろ)には光を集める「凸レンズ(とつレンズ)」を目(角膜)の前に置くことで、網膜上に正しくピントを結び直させます。
しかし、「ただ見えれば良い」という時代は終わりました。日本眼科学会が2025年に公開した「成人の視力検査および眼鏡処方に関する手引き」では、検査室で測定した「完全矯正値(最もよく見える度数)」が、必ずしもその人の「日常で快適な度数」とは限らないと強調しています。例えば、デスクワーク中心の人が完全矯正の遠くがよく見えるメガネをかけると、かえってPC画面でピント調節を使いすぎて疲れてしまうことがあります。運転用、PC作業用、読書用など、生活場面に合わせて度数を微調整することが、眼精疲労を減らす鍵となります。眼鏡による頭痛に悩む方は、このミスマッチが原因かもしれません。
老視(老眼)用メガネの多様化
老視が始まると、「近くの文字が見えにくい」という悩みが出てきます。最もシンプルな解決策は「単焦点近用眼鏡(いわゆる老眼鏡)」です。しかし、これでは手元は見えますが、少し顔を上げると遠くがぼやけてしまいます。そこで開発されたのが、1枚のレンズに複数の度数が入った「多焦点レンズ」です。
- 遠近両用レンズ(累進多焦点レンズ): レンズの上部で遠くを、下部で近くを見ることができます。境目がないため自然な見た目ですが、視線を上下に動かすコツが必要で、横を見ると歪みを感じやすい側面もあります。
- 中近両用レンズ(室内用・オフィスレンズ): 遠近両用よりも「中間距離(PC画面など)」と「手元(書類)」の視野を広く設計したレンズです。室内でのデスクワークや家事が多い方に適していますが、遠くの運転などには使えません。
どのレンズが最適かは、その人の生活スタイル(運転が多いか、PC作業がメインか、など)によって全く異なります。遠視の人は老視を早く自覚しやすく、近視の人はメガネを外せば近くが見えるため自覚が遅れるなど、元の屈折異常によっても最適な処方は変わってきます。
小児の近視進行抑制メガネ
近年、眼鏡の役割で最も注目されているのが「小児の近視進行抑制」です。これは単なる「視力矯正」ではなく、「治療的」な意味合いを持ちます。日本眼科学会が2025年に公開したガイドラインでは、特殊な設計の「近視管理用眼鏡(多分割レンズ)」が、低濃度アトロピン点眼やオルソケラトロジーと並んで、エビデンスのある近視進行抑制手段として位置づけられました。これは、レンズ中心でピントを合わせつつ、周辺部では特殊なレンズ(DIMS技術など)で「周辺部網膜ではピントを網膜の手前に結ばせる」ことで、「これ以上、眼軸が伸びる必要はない」という信号を脳に送り、眼軸の伸びを抑制しようとする最先端の技術です。子供の近視進行を本気で考えるならば、こうした新しい選択肢も眼科医と相談する価値があります。
コンタクトレンズの選択肢と安全性
コンタクトレンズは、眼鏡の「物が小さく(大きく)見える」「視野が狭まる」「運動時に不便」といったデメリットを解消し、素顔のまま快適な視界を得られる優れた矯正器具です。角膜の表面に直接乗せるため、光学的なメリットも大きいとされています。ハードタイプ、ソフトタイプ、使い捨てタイプなど多様な種類があり、老視に対応した「多焦点コンタクトレンズ」も広く使われています。
オルソケラトロジー(Ortho-K)
コンタクトレンズの中でも特殊な位置づけなのが「オルソケラトロジー」です。これは、夜寝ている間に特殊なデザインのハードコンタクトレンズを装用し、角膜の形状を平坦化させることで、日中は裸眼でもピントが合うようにする近視矯正法です。日本眼科学会の2017年ガイドラインでも屈折矯正の一手段として認められており、近年では小児の近視進行抑制効果(約30〜40%)にも注目が集まっています。ただし、角膜の形状を積極的に変える医療行為であるため、眼科専門医による厳格な管理と定期検査が不可欠です。オルソケラトロジーの安全性や費用については、こちらの解説をご覧ください。
最も重要な「安全性」:コンタクトレンズの鉄則
コンタクトレンズの利便性は、「正しいケア」という絶対的な責任と表裏一体です。この責任を軽視すると、失明につながる重篤な合併症を引き起こす可能性があります。米国国立眼研究所(NEI)や英国のMoorfields眼科病院などは、安全な使用法を繰り返し警告しています。
- 水道水の使用は厳禁: これが最も危険な行為の一つです。「少しだけなら」とレンズを水道水ですすいだり、保存ケースを水道水で洗ったりすることは絶対にあってはいけません。水道水には「アカントアメーバ」という微小な原虫が含まれている可能性があり、これがレンズと角膜の間で増殖すると、激しい痛みとともに角膜組織が「食べられて」しまう、治療が極めて困難な「アカントアメーバ角膜炎」を発症するリスクがあります。
- 装用したまま寝ない: 睡眠中はまぶたを閉じるため、角膜への酸素供給が著しく低下します。レンズを装用したまま寝ると、角膜は深刻な酸素不足(低酸素状態)に陥り、角膜のバリア機能が低下し、細菌に感染しやすい非常に脆弱な状態になります。
- 定期的なレンズ交換とケースの清掃: 決められた装用期間(1day, 2weekなど)を厳守し、レンズケースも専用のケア用品で正しく洗浄・乾燥させ、定期的に新しいものと交換することが感染予防の基本です。
「目が充血する」「ゴロゴロする」「痛い」といった症状が出た場合は、レンズの使用を直ちに中止し、眼科を受診してください。コンタクトレンズ使用者のための角膜炎予防ガイドも必ずお読みください。
屈折矯正手術(レーシック・SMILE等)の実際
「朝起きた瞬間から、鮮明な世界が広がる」——これは、屈折異常を持つ多くの人にとっての夢です。この夢をかなえる選択肢が、屈折矯正手術です。これは、主に角膜の形状をレーザーなどで変化させることで、目そのものが持つ屈折力を変え、網膜上にピントが合うようにする治療法です。一度手術を受けると元には戻せないため、非常に慎重な判断が求められます。
日本眼科学会が2024年に改訂した第8版ガイドラインでは、以下の手術法が主に挙げられています。
- LASIK(レーシック): 最も広く知られている方法です。角膜の表面に「フラップ」と呼ばれる薄いフタを作成し、それをめくって内部の角膜実質層にエキシマレーザーを照射し、角膜を削って形状を整え、フラップを元に戻します。回復が早いのが特徴です。
- PRK(ピーアールケー): フラップを作らず、角膜の一番上の上皮層を取り除き、直接レーザーを照射します。フラップがないため衝撃に強いとされますが、術後に痛みが出やすく、視力の回復に時間がかかる傾向があります。
- SMILE(リレックススマイル): 2023年に日本で承認された比較的新しい方法です。フェムト秒レーザーで角膜の内部に「レンチクル」と呼ばれる薄いレンズ状の切片を作成し、角膜のごく小さな切開創からそれを取り出します。フラップを作らないため、LASIKとPRKの長所を併せ持つと期待されています。
- ICL(有水晶体眼内レンズ): これはレーザーで角膜を削るのではなく、目の中に特殊なレンズを「挿入」する方法です。自分の水晶体は残したまま、虹彩の後ろに永久コンタクトレンズのようなものを固定します。角膜を削らないため、強度近視でレーシックが適応外となる人や、角膜が薄い人にも適応できる場合があります。ICLを含む屈折矯正手術の比較については、こちらをご覧ください。
手術の適応とリスク
これらの手術は「誰でも受けられる」わけではありません。日本眼科学会のガイドラインでは、原則として18歳以上で屈折度が安定していること、角膜の厚さが十分にあること、円錐角膜や重度のドライアイ、全身性の疾患(膠原病など)がないことなど、厳格な適応基準が定められています。また、英国NHSや米国Mayo Clinicなどの公的・専門機関は、手術に伴うリスクについても明確に言及しています。
一般的なリスクとしては、手術後に「期待した視力が出ない(低矯正・過矯正)」「一時的または長期的なドライアイが悪化する」「夜間に光がにじんで見える(ハロー・グレア)」「まれに感染症やフラップのズレ」などが挙げられます。また、手術で近視を矯正しても、加齢による「老視」は40代になれば必ず訪れます。その際、遠くが見えるように矯正しすぎると、今度は手元を見るための老眼鏡が早くから必要になるケースもあります。屈折矯正手術は、利便性という大きなメリットと、元に戻せないというリスクを天秤にかけ、専門医と十分に話し合った上で決定すべき重要な選択です。
手術後の生活で注意すべき点も確認しておきましょう。
このように、最も一般的な「ピントのズレ」である屈折異常には、その原因や年齢、生活スタイルに応じて、眼鏡から手術まで多様な解決策が存在します。しかし、視力の問題はこれだけではありません。特に小児期においては、屈折異常とは異なるメカニズムで視力の発達が妨げられる「弱視」や、両眼の視線が揃わない「斜視」といった、早期発見・早期治療が不可欠な疾患が存在します。次のセクションでは、こうした子供特有の目の疾患について詳しく見ていきます。
小児の眼疾患(弱視・斜視・先天白内障・先天緑内障)
前節では近視や乱視といった屈折異常について解説しましたが、お子様の目の問題には、さらに早期の対応が将来の視力を左右する、特有の疾患群が存在します。それは「見る力」そのものが発達している最中だからこそ起こる問題です。
大人の視力はすでに完成していますが、赤ちゃんの視力は生まれたときにはまだ未完成です。そこから様々なものを見て、触れて、脳の「視覚中枢」が刺激されることで、少しずつ「見る力」が育っていきます。この大切な発達期は「視覚感受性期」と呼ばれ、おおむね生後数か月から8歳頃まで続くとされています。
もし、この最も大切な時期に、何らかの原因で「鮮明な映像」が脳に届かない状態が続くと、脳はその目からの情報を処理することを諦めてしまい、視覚中枢の発達が止まってしまいます。これが「弱視(じゃくし)」です。弱視の恐ろしさは、感受性期を過ぎてから(例えば10歳になってから)慌てて原因を取り除いても、一度発達が止まった視力は完全には回復しない点にあります。
「うちの子はちゃんと見えているだろうか」というご両親の心配は、非常に重要です。このセクションでは、その感受性期に深刻な影響を与え、乳幼児健診などでの早期発見が不可欠とされる4つの主要な小児眼疾患(弱視、斜視、先天白内障、先天緑内障)について、日本の専門機関の見解に基づき、深く掘り下げて解説します。
子どもの視力はいつ完成する?視覚発達のタイムライン
「子どもの視力はいつ完成するのか」という問いは、多くの保護者が抱く疑問です。生まれたばかりの赤ちゃんの視力は、光がぼんやりわかる程度(0.01〜0.02程度)とされています。そこから、目で見たものが脳に伝わり、「これはお母さんの顔だ」「これはおもちゃだ」と認識する能力が急速に発達していきます。
一般的な発達の目安は以下の通りです:
- 生後3〜4か月:動くものを目で追う(追視)ようになり、色がぼんやりと認識できるようになります。この時期に目が合わない、追視をしない場合は注意が必要です。
- 生後6か月〜1歳:視力は0.1〜0.2程度に発達し、物の立体感や距離感が分かり始めます。
- 3歳:視力が0.5〜1.0程度に達する子が増えてきます。日本の3歳児健診で視力検査が重要視されるのは、この時期に弱視の兆候を発見するためです。厚生労働省の健診項目にも、視力検査や斜視の確認が標準的に組み込まれています。
- 6〜8歳(就学期):視機能はほぼ完成し、大人と同じ1.0〜1.2程度の視力を持つようになります。
このタイムラインで最も重要なのが、「感受性期(特に3歳頃まで)」に、両目から「クリアで、ズレのない」映像が脳に届き続けることです。もし片方の目が強い遠視でぼやけていたり、斜視で違う場所を見ていたりすると、脳は「見にくい方の目」からの情報を遮断(抑制)し、良い方の目だけで物を見ようとします。その結果、使われなかった方の目の視力発達が停止し、弱視が固定化してしまうのです。
ご家庭で視力低下のサインに気づくことも大切ですが、乳幼児健診は、症状が表に出にくい目の問題を早期に発見するための非常に重要な機会です。
弱視を放っておくとどうなる?9歳未満での治療が重要な理由
弱視(医学的にはAmblyopia)とは、眼鏡やコンタクトレンズを使っても視力が1.0まで出ない状態を指します。これは、眼球そのものに大きな病気がないにもかかわらず、前述の「視覚感受性期」に脳への適切な刺激が届かなかったために、視力の発達が止まってしまった状態です。「怠け目(Lazy eye)」とも呼ばれますが、決して本人が怠けているわけではありません。
弱視は、その原因によっていくつかのタイプに分類されます。
- 屈折異常弱視:
両目ともに非常に強い遠視や乱視があるために、常にピントが合わないぼやけた映像しか脳に届かず、両目の発達が遅れてしまうタイプです。子どもは「ぼやけた世界」が普通だと思っているため、自分から見えにくいとは訴えません。 - 不同視弱視(ふどうしじゃくし):
片方の目だけが強い遠視や乱視であるため、良い方の目ばかりを使い、悪い方の目の発達が抑制されてしまうタイプです。片目は良く見えているため、日常生活では問題ないように見え、発見が最も遅れやすい弱視の一つです。 - 斜視弱視:
片方の目が常に外側や内側を向いている(斜視)ため、両目からの映像がズレてしまい、脳が混乱します。その結果、脳がズレている方の目からの情報を遮断し、その目の視力が発達しなくなります。 - 形態覚遮断弱視:
先天白内障や角膜混濁、眼瞼下垂(まぶたが下がっている)などで、光そのものが網膜に届くのを妨げられる、最も重篤なタイプです。これは一刻も早い原因の除去(手術など)が必要です。
弱視治療の基本は、「感受性期が終わる前に、網膜に鮮明なピントを合わせ、脳にその映像を強制的に認識させる」ことです。小児弱視の治療は時間との戦いであり、日本眼科学会の手引きでも、調節麻痺薬を使った精密な検査に基づき、適切な眼鏡を処方することが強調されています。
「こんなに小さいのに眼鏡を?」と驚かれるかもしれませんが、この時期の眼鏡は、単によく見えるようにするためではなく、脳の視覚中枢を発達させるための「訓練器具」です。お子様が嫌がっても、根気強くかけさせ続けることが将来の視力につながります。さらに、不同視弱視や斜視弱視の場合は、良く見える方の目をアイパッチなどで意図的に隠し、悪い方の目を強制的に使わせる「遮閉訓練」を併用することがあります。これはお子様にとっても保護者にとっても大変な治療ですが、感受性期の間だけ集中して行うことで、視力の大幅な改善が期待できます。
弱視治療の最新情報に関心があるかもしれませんが、基本は眼鏡と遮閉であり、9歳未満であることが治療効果の鍵となります。子供の視力低下を見逃さないことが何より重要です。
乳児の斜視は自然に治る?受診すべき斜視の見分け方
斜視(しゃし)とは、両目の視線が同じ方向を向いていない状態を指します。片方の目がまっすぐ前を見ているのに、もう片方の目が内側(内斜視)や外側(外斜視)、あるいは上下(上下斜視)を向いてしまう状態です。
保護者の方から「時々、目が寄っている気がするが、自然に治りますか?」というご質問をよく受けます。確かに、生後間もない赤ちゃんは、まだ両目を協調させて使う能力が未熟なため、一時的に視線がズレて見えることがあります(偽斜視)。しかし、国立成育医療研究センターなどの専門機関は、生後3〜4か月を過ぎても持続する斜視は、自然に治る可能性が低く、専門的な評価が必要であるとしています。
斜視は単なる「見た目」の問題ではありません。放置すると、以下の2つの深刻な問題を引き起こします。
- 弱視の発症:
前述の通り、常にズレている方の目からの情報を脳が無視し続けるため、「斜視弱視」を発症します。 - 両眼視機能の喪失:
私たちは普段、左右の目でわずかに違う角度から物を見て、それを脳で合成することで「立体感」や「奥行き」を感じています。これが両眼視機能です。しかし、斜視があると、両目からの情報が違いすぎるため、脳が合成を諦めてしまいます。その結果、精密な立体感を得ることができなくなります。
小児に多い斜視には、以下のようなタイプがあります。
- 乳児内斜視:生後6か月以内に発症する、目の内側への大きなズレです。多くの場合、早期の手術が必要となります。
- 調節性内斜視:強い遠視が原因で、ピントを合わせようと過剰に目に力を入れた結果、目が内側に寄ってしまうタイプです。これはまず遠視用の眼鏡をかけることで治療します。
- 間欠性外斜視:普段はまっすぐですが、ぼーっとしている時や疲れた時に、片方の目が外側にズレるタイプです。ズレる頻度や角度によっては、手術が検討されます。
日本眼科学会は、斜視治療の目標を「視力確保(弱視予防)」「眼位の矯正」「両眼視機能の獲得」の3段階で示しています。治療はタイプに応じて、眼鏡、プリズム眼鏡、手術、あるいは視能訓練士による訓練が選択されます。斜視手術は、目の筋肉(外眼筋)の位置を付け替えることで、目の向きをまっすぐにするものです。近年では、スマートフォンの長時間使用による急性の内斜視も報告されており、生活環境への注意も必要です。斜視は物が二重に見える複視の原因ともなるため、早期の介入が推奨されます。
先天白内障の手術タイミングとその後のメガネ・コンタクト管理
「赤ちゃんの瞳が白く濁っている」「光を当てると白く光る気がする」——これは「白色瞳孔」と呼ばれ、小児眼科において最も緊急性の高いサインの一つです。その原因として最も多いのが「先天白内障」です。
白内障とは、目の中でレンズの役割をしている「水晶体」が濁る病気です。加齢による白内障が一般的ですが、生まれつき水晶体に濁りがある場合、それを先天白内障と呼びます。頻度は1万人に1〜2人程度とまれですが、視覚発達への影響は甚大です。
濁りが強ければ、光が網膜まで届きません。これは前述の「形態覚遮断弱視」の最も典型的な原因であり、発見が遅れれば、たとえ後で手術をしても、視力が全く発達しないままになってしまいます。そのため、国立成育医療研究センターなどの中核病院では、視力発達への影響が大きいと判断された場合、生後できるだけ早い時期(数週〜数か月以内)に全身麻酔下での手術を行います。
乳幼児の手術は、大人の眼内レンズを入れる手術とは異なり、濁った水晶体と硝子体の一部を切除する術式が取られることが多いです。なぜなら、乳児の眼球はまだ急速に成長しており、ピント(度数)が安定しないため、眼内レンズを入れる時期や度数決定が非常に難しいためです。
手術はゴールではなく、スタートです。水晶体という強力なレンズを取り除いた目は、非常に強い「遠視」の状態になります。そのままではピントが合わず弱視になってしまうため、術後すぐに「乳児用のコンタクトレンズ」または「分厚い眼鏡」による屈折矯正を開始しなければなりません。赤ちゃんにコンタクトレンズを装用させ、毎日洗浄・管理することは、保護者にとって計り知れない負担ですが、これが視力発達に不可欠です。さらに、片目だけの手術の場合は、健眼遮閉(アイパッチ)も必要になります。術後のケアは非常に長期間にわたりますが、専門医と二人三脚で取り組むことが重要です。
赤ちゃんの目が大きい・まぶしがるときに考える先天緑内障
緑内障は、日本の失明原因第1位として知られる病気ですが、その多くは中高年で発症するものです。しかし、まれに生まれつき眼圧(目の中の圧力)が高い「先天緑内障(小児緑内障)」があります。
大人の緑内障がゆっくりと視野を失っていくのに対し、小児の緑内障は症状の進行が早く、非常に重篤です。赤ちゃんの眼球はまだ組織が柔らかいため、高い眼圧に耐えられず、眼球全体が引き伸ばされて大きくなってしまいます。そのため、大人の緑内障とは全く異なる、以下のような特有のサインが現れます。
- 流涙(りゅうるい):いつも涙目であったり、涙が止まらなかったりする。
- 羞明(しゅうめい):異常に光をまぶしがる。明るい場所で目を開けられない。
- 眼瞼痙攣(がんけんけいれん):まぶたがピクピクと痙攣する。
- 角膜混濁・角膜径増大:「黒目」の部分が白っぽく濁ったり、通常より大きく見えたりする(牛眼)。
これらの症状は、眼圧上昇によって角膜(黒目)がむくんだり、角膜の内側の膜(デスメ膜)が裂けたり(Haab線条)することで起こります。緑内障は早期治療が不可欠であり、放置すれば角膜混濁や視神経の圧迫により、急速に視力を失います。
日本眼科学会のガイドライン(第5版)では、小児緑内障は他の全身疾患(マルファン症候群、ダウン症候群など)に伴って発症することもあると分類されています。診断は、全身麻酔下で眼圧測定、角膜径の測定、眼底検査などを行って確定します。
治療の第一選択は、点眼薬ではなく、早期の手術です。隅角(目の中の水の出口)を切開して房水の流れを良くする手術(隅角切開術など)が行われます。多くの場合、複数回の手術が必要になりますが、早期に眼圧をコントロールできれば、視力障害を最小限に食い止められる可能性があります。ただし、手術で眼圧が下がった後も、角膜混濁や強い近視・乱視による弱視化のリスクが残るため、先天白内障と同様に、生涯にわたる長期的な緑内障管理と弱視治療が必要です。
保険で使える「弱視等治療用眼鏡」と自治体の補装具費のちがい
弱視や斜視の治療で「眼鏡が不可欠」と説明されても、次に保護者の頭をよぎるのは経済的な負担です。特に子どもの眼鏡は、成長や視力の変化に合わせて1〜2年ごと、時には半年ごとに作り替える必要があり、その費用は決して安くありません。
この経済的負担を軽減するため、日本には公的な補助制度が用意されています。しかし、制度が2種類あり、どちらが使えるかは年齢や条件によって異なるため、混乱しやすい点でもあります。ここでその違いを明確にしておきましょう。
- 健康保険の「療養費」
- 対象:9歳未満の子ども
- 条件:医師が「弱視」「斜視」「先天白内障術後」の治療のために必要と判断し、処方した眼鏡であること。(いわゆる近視や乱視だけでは対象外)
- 内容:眼鏡店で全額を一度支払い、その後ご加入の健康保険(協会けんぽ、組合健保、国民健康保険など)に申請することで、かかった費用の7割(義務教育就学前は8割)が「療養費」として払い戻されます。
- 注意点:支給には上限額が定められています。また、5歳未満は前回の申請から1年以上、5歳以上は2年以上経過している必要があります。
- 自治体の「補装具費支給制度」(障害者総合支援法)
- 対象:年齢制限なし(ただし18歳未満が中心)
- 条件:身体障害者手帳(視覚障害)を持っている、または同等の状態(例:両眼の矯正視力が0.3未満など)と医師・自治体に判定された場合。
- 内容:原則として購入前に自治体(福祉課など)に申請し、「支給券」の交付を受けてから眼鏡を作成します。自己負担は原則1割ですが、世帯所得に応じた上限額があります。
日本眼科学会もこの制度の周知に努めています。多くの場合、まずは健康保険の「療養費」を利用することになります。申請には眼科医が記入した「治療用眼鏡等作成指示書」と、眼鏡店が発行した領収書が必要です。どの制度が利用できるか、どのような書類が必要かは、必ず事前に眼科の窓口や、お住まいの自治体の担当窓口にご確認ください。
眼鏡をかけないリスクは、大人の比ではありません。こうした制度を活用し、お子様がためらわずに治療用眼鏡を装用できる環境を整えることが、視力発達の鍵となります。
角膜疾患(円錐角膜・角膜変性・角膜移植)
前節では、お子さんの眼疾患について見てきました。本節で最初に取り上げる「円錐角膜」も、多くは10代の思春期に発症が確認される、若い世代と深い関わりのある疾患です。眼球の最も前面にある「角膜」は、一般に「黒目」と呼ばれる部分を覆う透明な組織で、光を取り込み屈折させる「窓」であり「メインレンズ」の役割を果たしています。実際、眼球全体の屈折力(ピント合わせの力)のうち約3分の2をこの角膜が担っており、その形状や透明性が視力に直結します。本節では、この角膜の形状や透明性が損なわれる代表的な疾患について、深く掘り下げて解説します。
円錐角膜とは?10代から始まる角膜のゆがみ
「最近、急に近視や乱視が進んだ気がする」「眼鏡やコンタクトレンズを新調しても、どうもスッキリ見えない」「片目で見ると、物が二重、三重に見える」——。もし10代後半から20代にかけてこうした自覚症状がある場合、それは単なる近視や乱視の進行ではなく、「円錐角膜(えんすいかくまく)」のサインかもしれません。
円錐角膜は、日本眼科学会によれば、角膜の中央部分が徐々に薄くなり、前方に円錐(えんすい)状に突き出てくる進行性の疾患です。450人から2,000人に1人程度と比較的まれで、男性にやや多いとされています。原因はまだ完全には解明されていませんが、遺伝的要因や、目を強くこする物理的な刺激が関与していると考えられています。
この疾患の厄介な点は、角膜が不規則に歪んでしまうため、通常のいわゆる「乱視」とは異なり、眼鏡や通常のソフトコンタクトレンズでは視力を十分に矯正できなくなる点にあります。進行すると、物が歪んで見えるだけでなく、強いまぶしさ(羞明)を感じることもあります。アトピー性皮膚炎などで目のかゆみを伴う人は、無意識に目をこすってしまい、進行を早めるリスクがあるため特に注意が必要です。
治療は、進行の程度によって段階的に行われます。
- 初期: 眼鏡やソフトコンタクトレンズで対応できる場合もありますが、乱視の進行が早い場合は専門的な検査が推奨されます。
- 中期: 角膜の歪みを矯正するため、ハードコンタクトレンズが第一選択となります。角膜の特殊な形状に合わせてレンズを処方する必要があり、専門的なフィッティング技術が求められます。様々なコンタクトレンズの種類の中でも、特に酸素透過性の高いハードレンズが用いられます。
- 進行抑制: 近年、「角膜クロスリンキング(CXL)」という治療法が注目されています。これは角膜にビタミンB2を点眼しながら紫外線を照射し、角膜のコラーゲン線維を強固にすることで、それ以上の進行を抑制する治療です。病気の「進行を止める」ことを目的とした治療であり、早期に発見し介入することが重要です。
- 進行期: コンタクトレンズの装用が困難になったり、角膜が極度に薄くなり穿孔(せんこう)の危険が出てきたり、急性水腫(角膜内に水が溜まり急激に白く濁る)を起こしたりした場合は、後述する角膜移植手術が検討されます。
若年者で乱視の症状が急速に進む場合は、「角膜トポグラフィー」という角膜の形状を精密に測定する検査を受けることが、早期発見の鍵となります。
フックス角膜内皮ジストロフィーと水疱性角膜症
円錐角膜が角膜の「形状」の異常であるのに対し、角膜の「透明性」と「機能」に関わる重大な疾患が「フックス角膜内皮ジストロフィー」です。これは50歳以降、特に女性に多く見られる遺伝性の疾患で、ゆっくりと進行します。
私たちの角膜の透明性は、角膜の一番内側にある「角膜内皮細胞」という細胞が、角膜内の水分量を常に一定に保つ「ポンプ」の役割を果たすことで維持されています。この内皮細胞は、一度死んでしまうと再生することができません。フックス角膜内皮ジストロフィーは、この大切な内皮細胞が加齢とともに変性し、徐々に減少していく病気です。
初期症状として非常に特徴的なのが、「朝起きた時が一番見えにくく、午後になると少しマシになる」というものです。これは、夜間にまぶたを閉じている間に水分が角膜内に溜まり(浮腫)、日中活動して瞬きをすることで水分が蒸発し、一時的に角膜の透明性が回復するためです。しかし病気が進行すると、ポンプ機能の低下が著しくなり、一日中視界がぼやけ、霧がかかったように見えるようになります。
さらに進行し、角膜上皮にまで水分が溜まると「水疱(すいほう)」ができ、これを「水疱性角膜症(すいほうせいかくまくしょう)」と呼びます。この状態になると、著しい視力低下だけでなく、水疱が破れた際に激しい痛み、充血、涙を伴います。フックス角膜内皮ジストロフィー以外にも、白内障手術や緑内障手術などの眼科手術、外傷などによって角膜内皮細胞が大きくダメージを受けた場合にも、水疱性角膜症は発症します。
治療は、初期には角膜の水分を蒸発させる高張食塩水の点眼などが用いられますが、根本的な治療にはならず、進行した場合は角膜移植(特に内皮移植)が必要となります。
角膜移植:日本の現状と種類(全層・内皮移植)
進行した円錐角膜や水疱性角膜症など、角膜の形状や透明性が不可逆的に損なわれ、他の治療法では視力回復が見込めない場合の最終的な治療選択肢が「角膜移植」です。これは、亡くなった方から提供された健康な角膜(ドナー角膜)と、患者さんの濁ったり歪んだりした角膜を交換する手術です。角膜移植の技術は大きく進歩しています。
ここで、日本の角膜移植医療における重要な現実をお伝えしなければなりません。それは、厚生労働省の報告にもあるように、日本では角膜移植を希望する患者数に対し、ドナー角膜の提供数が慢性的に不足しているという事実です。そのため、移植が必要と診断されても、アイバンクに登録し、移植の順番を待つ必要があるのが一般的です(緊急性の高い疾患を除く)。
角膜移植には、主に以下の術式があります。
- 全層角膜移植(PKP): 角膜全体をドナー角膜と交換する、最も歴史のある方法です。円錐角膜が極度に進行した場合や、角膜に深い傷や濁りがある場合に適応されます。
- 角膜表層移植(DALK): 角膜の大部分を交換しますが、患者さん自身の最も内側にある「角膜内皮細胞」を残す術式です。主に円錐角膜や角膜表層の混濁が適応で、内皮細胞を残せるため、拒絶反応のリスクを(理論上)減らせるメリットがあります。
- 角膜内皮移植(DSAEK, DMEK): フックス角膜内皮ジストロフィーや水疱性角膜症など、「内皮細胞」だけが障害されている場合に、その悪い層だけを剥がし、ドナー角膜の内皮細胞を移植する方法です。角膜の大部分は自分のものを使うため、傷口が小さく、視力回復が早く、拒絶反応のリスクも低いとされ、近年急速に普及しています。
移植手術は比較的安全性が高いとされていますが、それでも他人の組織を移植するため「拒絶反応」という最大のリスクが伴います。また、感染症、緑内障、縫合糸のトラブルなどの合併症もあり、術後は長期にわたる慎重な経過観察と、免疫抑制剤の点眼治療が不可欠です。術後の生活管理も視力を守る上で重要となります。
再生医療という新たな光と注意点
前述のドナー不足という深刻な問題を背景に、日本では角膜の再生医療研究が世界に先駆けて進められています。特に水疱性角膜症に対しては、培養した角膜内皮細胞を眼内に注入する治療法や、細胞シートを用いる方法などが日本眼科学会の基準のもとで臨床応用され始めています。これらはドナー角膜を必要としない、あるいはドナー角膜の使用を最小限に抑える画期的な治療法として期待されています。
しかし、角膜疾患で最も重要なことは、見逃してはいけないサインに気づくことです。以下の症状は、緊急性が高い可能性があります。
- 急激な視力低下と激しい目の痛み: 円錐角膜の急性水腫(角膜が破れて水が溜まる)、あるいは水疱性角膜症の水疱が破れた可能性があります。
- 角膜移植後の充血、痛み、視力低下: これは「拒絶反応」の典型的なサインです。拒絶反応は早期に治療を開始すれば抑えられる可能性が高いため、絶対に放置してはいけません。
これらの症状が出た場合は、様子を見るのではなく、直ちに手術を受けた病院や最寄りの眼科専門医を受診してください。視力低下を治せる可能性は、行動の早さにかかっています。
ぶどう膜炎(全身疾患との関連・免疫治療)
前節までで角膜など眼の表面に近い病気について見てきましたが、ここからは眼のさらに奥深く、内部で起こる炎症について解説します。「ぶどう膜炎」という言葉を初めて聞くと、多くの方は「眼の中に炎症が起きる」という事実に強い不安を感じるかもしれません。実際に、ぶどう膜炎は診断や治療が難しく、視力低下や失明の原因にもなり得る重要な疾患です。
そして、ぶどう膜炎の最も複雑な点は、それが単なる「眼の病気」ではなく、しばしば「全身の病気のサイン」として現れることです。免疫系が自分自身を攻撃してしまう自己免疫疾患が背景に隠れていることが少なくありません。そのため、治療は眼の炎症を抑えるだけでなく、全身の免疫状態をコントロールする「免疫治療」という専門的なアプローチが必要になります。このセクションでは、なぜぶどう膜炎が全身疾患と関連するのか、そしてどのような治療法が選択されるのかを、日本眼科学会のガイドラインや最新の知見に基づき、深く掘り下げていきます。
「ぶどう膜炎」とは?なぜ全身の病気と関係するのか
まず、「ぶどう膜」とは眼球の内側にある組織の総称で、前から「虹彩(こうさい:ひとみの色がついた部分)」、「毛様体(もうようたい:ピント調節を担う筋肉)」、「脈絡膜(みゃくらくまく:網膜に栄養を送る血管の豊富な膜)」の3つを指します。これらの組織は、まるでブドウの皮と実のように眼球を包み込んでいるため、この名前がついています。
ぶどう膜炎とは、文字通りこのぶどう膜に炎症が起きることです。ぶどう膜は眼球の中でも特に血管が豊富な場所です。これを「戦場」に例えるなら、血液は兵士(免疫細胞)を運ぶ「道路網」です。もし体全体で免疫システムに異常が起き、兵士が暴走して自分自身の体を攻撃し始めると(自己免疫疾患)、この道路網が張り巡らされたぶどう膜は、格好の攻撃対象となってしまうのです。これが、ぶどう膜炎が全身疾患と強く関連する最大の理由です。
ぶどう膜炎は、炎症が起きる場所によって、主に4つのタイプに分類されます(日本眼科学会ガイドラインに基づく分類)。
- 前部ぶどう膜炎:最も多く、虹彩や毛様体に炎症が起きます。目の痛み、充血、まぶしさ(羞明)、視界のかすみといった症状が出やすいのが特徴です。
- 中間部ぶどう膜炎:毛様体から網膜の周辺部(硝子体)にかけて炎症が起きます。痛みや充血は少なく、「飛蚊症(ひぶんしょう:虫が飛んでいるように見える)」やかすみ目を自覚することが多いです。
- 後部ぶどう膜炎:脈絡膜や網膜、視神経など、眼の奥深くに炎症が起きます。視力にとって最も重要な部分であり、かすみ目や視力低下、視野の異常(見えにくい部分がある)などが起こりやすいです。
- 汎ぶどう膜炎:上記のすべて(前部から後部まで)に炎症が及んでいる状態を指します。最も重篤なタイプとされます。
治療方針を決める上で最も重要なのが、そのぶどう膜炎が「感染性」か「非感染性」かを見極めることです。感染性(結核、梅毒、ヘルペスウイルス、サイトメガロウイルスなど)であれば、原因となる病原体を叩く抗生物質や抗ウイルス薬が治療の主役です。一方で「非感染性」の場合、その多くは免疫システムの異常による自己免疫疾患です。この場合、治療は正反対で、免疫の暴走を「鎮める」ための免疫治療が必要となります。このセクションでは、特にこの「非感染性」のぶどう膜炎と、その背景にある全身疾患、そして治療法に焦点を当てて解説します。
日本で特に多い「三大ぶどう膜炎」と全身疾患
ぶどう膜炎の原因は多岐にわたり、半数近くは原因不明(特発性)とも言われます。しかし、日本では古くから特定の全身疾患との関連が深いことが知られており、特に「ベーチェット病」「サルコイドーシス」「原田病」は「三大ぶどう膜炎」と呼ばれています。これらの病気は、眼科医がぶどう膜炎を診察した際に、必ず鑑別に挙げるべき重要な疾患です。
1. ベーチェット病(Behçet’s Disease)
「たかが口内炎」と見過ごされがちな、再発する口の中のアフタ性潰瘍。しかし、これがベーチェTット病の主要な症状の一つである可能性があります。ベーチェット病は、口腔粘膜の潰瘍、皮膚症状(ニキビのような発疹や、すねの赤いしこり)、外陰部の潰瘍、そして眼の症状を4つの主症状とする、全身性の炎症性疾患です(厚生労働省の特定疾患資料参照)。特に眼の症状は「眼発作」と呼ばれ、両眼に強い炎症(汎ぶどう膜炎)を繰り返し、急激な視力低下を引き起こします。この発作を繰り返すたびに網膜がダメージを受け、失明に至るリスクが高いため、非常に強力な免疫治療が必要となる代表的な疾患です。
2. サルコイドーシス(Sarcoidosis)
サルコイドーシスは、原因不明の「類上皮細胞肉芽腫(にくげしゅ)」という炎症細胞の塊が、全身のさまざまな臓器(特に肺やリンパ節)にできてしまう病気です。多くの場合、肺の病変は自覚症状がないまま健康診断の胸部X線写真で偶然発見されます。しかし、この肉芽腫が眼(ぶどう膜)にできると、黄斑浮腫や網膜の血管炎などを引き起こし、かすみ目や視力低下の原因となります。この病気も両眼に症状が出ることが多く、厚生労働省の資料でも、眼や心臓、神経に病変がある場合は積極的な治療対象となるとされています。
3. 原田病(Vogt-Koyanagi-Harada Disease)
原田病は、メラノサイト(色素細胞)に対する自己免疫疾患と考えられています。メラノサイトは皮膚や毛髪だけでなく、眼のぶどう膜や内耳にも存在します。そのため、原田病では両眼の強いぶどう膜炎(網膜の下に水が溜まる漿液性網膜剥離を伴うことが多い)と同時に、髄膜刺激症状(頭痛、発熱、首の硬直)、内耳症状(耳鳴り、めまい)、そして回復期に皮膚の白斑や脱毛が起こることが特徴です。この病気は、日本の公的資料でも示されている通り、発症後できるだけ早期に、十分な量の全身ステロイド治療を開始することが、視力予後を大きく改善させることが知られています。
診断へのアプローチ:なぜ眼科医が内科の検査を依頼するのか
「眼がかすむと言って眼科に来たのに、なぜ胸のレントゲンや採血をたくさん取るのだろう?」——ぶどう膜炎の診断プロセスでは、多くの患者さんがこのような疑問を抱きます。これは、眼科医が「眼に見えている炎症」の裏に隠れた「全身の根本原因」を探すための、非常に重要なステップなのです。
前述の三大ぶどう膜炎を例にとっても、その診断には眼科以外の検査が不可欠です。
- サルコイドーシスを疑えば、胸部X線写真やCTで肺のリンパ節の腫れを確認したり、血液検査でACEやリゾチームといった数値を測定したりします。
- ベーチェット病を疑えば、特徴的な皮膚症状や口腔内潰瘍の病歴を詳しく問診し、場合によってはHLA-B51という遺伝的な型を調べる血液検査を行います。
- 原田病を疑えば、頭痛や耳鳴りの有無を確認し、髄膜刺激症状が強ければ髄液検査を行うこともあります。
さらに、忘れてはならないのが日本特有の感染症、HTLV-1(ヒトT細胞白血病ウイルス1型)です。HTLV-1は、成人T細胞白血病(ATL)の原因ウイルスとして知られますが、厚生労働省の啓発資料にもあるように、ぶどう膜炎(HU)を引き起こすこともあります。特に九州や沖縄などの浸淫地域では、原因不明のぶどう膜炎の場合、このウイルスの抗体検査も重要となります。
このように、ぶどう膜炎の診断は、眼科医、内科医、膠原病科医、呼吸器科医、皮膚科医、感染症科医などが連携する「チーム医療」で行われます。目の充血やかすみといった症状の裏にある原因を突き止め、最適な治療法を見つけるためには、全身的な視点での精査が不可欠なのです。
非感染性ぶどう膜炎の免疫治療:段階的アプローチ
感染性ぶどう膜炎が除外され、「非感染性(自己免疫性)」と診断された場合、治療の柱は「免疫治療」となります。ここでの目標は2つあります。第一に、現在起きている炎症という「火事」を速やかに鎮火させること。第二に、炎症が再発しないように免疫システム全体をコントロールし、「火種」が再び燃え上がらないようにすることです。そして、このプロセス全体を通じて、治療薬による副作用を最小限に抑えることが求められます。
現在の治療は、米国国立眼研究所(NEI)なども示すように、炎症の重症度や部位に応じて段階的に治療を強化する「ステップアップ・アプローチ」が基本です。
ステップ1:ステロイド(局所・全身)
ステロイドは、炎症を抑える「強力な消防士」です。最も基本的かつ即効性のある治療薬です。
前部ぶどう膜炎であれば、まずはステロイドの点眼薬で治療します。しかし、炎症が眼の奥(中間部・後部)に及んでいる場合や、ベーチェット病の眼発作、原田病の初期など、炎症が非常に激しい場合は、点眼だけでは不十分です。この場合、プレドニゾロンなどの経口ステロイド(飲み薬)や、メチルプレドニゾロンの点滴(ステロイドパルス療法)といった「全身投与」を行い、体全体から強力に炎症を鎮圧します。
しかし、ステロイドには大きな問題があります。強力な反面、長期間・高用量で使用すると、さまざまな副作用を引き起こす可能性があるのです。眼局所では、緑内障(眼圧上昇)や白内障のリスクが上がります。全身的にも、糖尿病、高血圧、骨粗鬆症、易感染性(感染しやすくなる)などの副作用が懸念されます。そのため、治療の長期目標は「いかにステロイドを安全な量まで減らすか(あるいは中止するか)」になります。そこで登場するのが、次のステップです。
ステップ2:免疫抑制薬(ステロイド・スパリング)
ステロイドをなかなか減らせない(例えばプレドニゾロン10mg/日以下にできない)、あるいは減らすとすぐに炎症が再発してしまう——。このような場合に、ステロイドと併用して導入するのが「免疫抑制薬」です。これらはステロイドの副作用を減らす(sparing)目的で使われるため、「ステロイド・スパリング薬」とも呼ばれます。
これらの薬は、ステロイドよりもゆっくりと、しかし持続的に免疫システム全体の「過剰な興奮」を鎮める働きがあります。日本でベーチェット病の眼症状に対して古くから使われているシクロスポリンやタクロリムス、あるいはサルコイドーシスや小児のぶどう膜炎で使われるメトトレキサート(MTX)、アザチオプリンなどがこれにあたります。これらの薬を併用することで、ステロイドだけでは抑えきれなかった炎症をコントロールし、ステロイドの維持量を安全域まで減らしていくことを目指します。ただし、これらの薬剤にも腎障害や肝障害、血圧上昇などの副作用の可能性があるため、定期的な血液検査によるモニタリングが不可欠です。
ステップ3:生物学的製剤(分子標的治療)
ステップ2の免疫抑制薬を使ってもなお炎症がコントロールできない、最も重症な「難治性ぶどう膜炎」に対して使われるのが、最新の治療薬である「生物学的製剤」です。
従来の免疫抑制薬が免疫システム全体を広く浅く抑える「絨毯爆撃」だとすれば、生物学的製剤は炎症を引き起こす特定の「伝達物質(サイトカイン)」だけを狙い撃ちする「スマートミサイル」に例えられます。
特に、炎症の“親玉”の一つである「TNF-α」という物質をブロックする薬剤(抗TNF-α抗体)は、ぶどう膜炎治療に革命をもたらしました。代表的な薬剤であるアダリムマブ(ヒュミラ®)は、2016年にNEJM誌で発表された国際的な臨床試験(VISUAL I/II)において、ステロイドだけでは再発を繰り返す非感染性ぶどう膜炎患者さんの再発リスクを劇的に低下させることが証明されました。また、ベーチェット病に対してはインフリキシマブ(レミケード®)も高い有効性が示されています。
これらの薬剤は非常に強力ですが、免疫を抑える力も強いため、結核などの感染症を再活性化させるリスクがあります。そのため、投与前には結核のスクリーニング検査が必須であり、投与中も感染症には細心の注意が必要です。これらの治療は、ぶどう膜炎と免疫治療に精通した専門施設で行われることになります。
よくある質問(FAQ)
Q1:ぶどう膜炎はなぜ全身の病気と関係するのですか?
A:ぶどう膜(虹彩・毛様体・脈絡膜)は、眼球の中でも特に血管や免疫細胞が豊富な組織です。そのため、ベーチェット病、サルコイドーシス、原田病といった、全身の免疫システムが異常をきたす病気(自己免疫疾患)が起こると、その「戦場」になりやすいからです。眼は、全身の免疫状態を映し出す「窓」とも言えます。したがって、ぶどう膜炎の治療では、眼だけでなく全身の状態を調べることが不可欠です。
Q2:ステロイドの飲み薬をやめるとすぐ再発します。どうしたらいいですか?
A:それは、ステロイドが「火事」を一時的に消しているだけで、免疫の異常という「火種」が残っているサインかもしれません。非感染性ぶどう膜炎の多くは、ステロイド単独での長期コントロールが難しいことが知られています。この場合、医師はシクロスポリン、メトトレキサート、アザチオプリンといった免疫抑制薬(ステップ2)を追加し、ステロイドを安全な量まで減らしながら「火種」そのものをコントロールする治療(ステロイド・スパリング)を提案します。これらの治療法について、主治医とよく相談してください。
Q3:私はHTLV-1キャリアですが、ぶどう膜炎になりますか?
A:はい、その可能性があります。厚生労働省の資料によれば、HTLV-1キャリアの方のうち、生涯でぶどう膜炎(HU)を発症する方は0.1〜0.3%程度と報告されています。頻度は高くありませんが、日本では特にキャリアの方が多い地域(九州・沖縄など)では、原因不明のぶどう膜炎を診た場合に必ず考慮すべき原因の一つです。もしキャリアであることをご存知で、眼のかすみや飛蚊症が続く場合は、必ず眼科医にその情報(キャリアであること)を伝えてください。
Q4:生物学的製剤(ヒュミラ®など)は日本でも使えますか?
A:はい、使用可能です。アダリムマブ(ヒュミラ®)は、既存の治療で効果不十分な「非感染性」の中間部・後部・汎ぶどう膜炎に対して、日本でも保険適用が認められています。また、ベーチェット病に伴う難治性ぶどう膜炎に対してはインフリキシマブ(レミケード®)も使われます。ただし、これらは非常に専門的な薬剤であり、結核などの感染症リスク管理も必要なため、どの疾患のどの段階で導入するかは、ぶどう膜炎の治療経験が豊富な専門医(眼科医や膠原病内科医)の判断が不可欠です。すべての患者さんに使われるわけではなく、重症・難治例が主な対象となります。
眼瞼・涙道の病気(麦粒腫・霰粒腫・眼瞼下垂・涙道閉塞)
前節では、眼球の表面を覆う「角膜」の疾患について詳しく見てきました。しかし、目を守る機能は角膜だけが担っているわけではありません。まぶた(眼瞼)や涙の通り道(涙道)も、視機能を維持するために不可欠な組織です。
このセクションでは、日常生活で非常によく遭遇する、まぶたと涙道の4つの主要な病気——「麦粒腫(ものもらい)」「霰粒腫」「眼瞼下垂」「涙道閉塞」——に焦点を当てて、その原因、症状、そして日本の医療現場における標準的な対処法を深く掘り下げていきます。これらの多くは良性ですが、中には深刻な感染症や、全身の病気のサインが隠れていることもあります。どのような場合にセルフケアが可能で、どのような場合に専門医の診断が必要なのか、その見極めが重要です。
麦粒腫(ものもらい):痛みを伴うまぶたの「おでき」
朝起きたら、まぶたが赤く腫れていて、瞬きをするたびにズキンと痛む——。多くの方が「ものもらい」として知るこの症状は、医学的には麦粒腫(ばくりゅうしゅ)と呼ばれます。これは、まぶたの縁にある汗腺(あせのせん)やまつ毛の毛根、あるいはまぶたの内側にある脂を出すマイボーム腺に細菌(主に黄色ブドウ球菌)が感染することで起こる、急性の化膿性炎症です。
この「ものもらい」という通称から、「人からうつる」と誤解されることがありますが、麦粒腫は感染症ではありますが、結膜炎のように人から人へ簡単にうつるものではありません。多くの場合、疲労やストレス、免疫力の低下、あるいは目をこするなどして、まぶたの常在菌のバランスが崩れたときに発症します。
麦粒腫は、感染した場所によって二種類に大別されます。日本眼科学会によれば、まつ毛の根本付近の腺に感染したものを外麦粒腫、まぶたの深い部分にあるマイボーム腺に感染したものを内麦粒腫と呼びます。外麦粒腫はまぶたの表面近くが腫れるため分かりやすい一方、内麦粒腫はまぶたの裏側(結膜側)に膿がたまるため、初期には異物感や腫れぼったさが主で、赤みや痛みが後から強くなることもあります。
治療に関しては、日本では初期段階から細菌を抑えるための抗菌目薬や眼軟膏が処方されることが一般的です。炎症が強い場合は、抗生物質の内服薬が併用されることもあります。多くの場合は数日から1週間程度で、膿が自然に排出されるか吸収されて治癒に向かいます。しかし、膿が溜まって腫れがひどい場合は、眼科で小さく切開して膿を出す処置(切開排膿)が必要になることもあります。
国際的には、Mayo Clinicなどの医療機関では、まず清潔なタオルを使った温罨法(おんあんぽう:温めること)で腺の出口を開き、自然な排膿を促すことが推奨されることもあります。ただし、自己判断で針を刺したり、強く押して膿を出そうとしたりするのは絶対に避けてください。細菌が周囲に広がり、眼窩蜂窩織炎(がんかほうかしきえん)という重篤な感染症を引き起こす危険があります。麦粒腫を早く治す方法としては、いずれにせよまぶたを清潔に保ち、コンタクトレンズの使用を一時中断し、医師の指示に従うことが重要です。
霰粒腫:痛みのない「しこり」との違い
麦粒腫とは異なり、「まぶたにコロコロとしたしこりがあるけれど、赤みも痛みもない」という場合、それは霰粒腫(さんりゅうしゅ)である可能性が高いです。これは麦粒腫のような細菌感染ではなく、マイボーム腺の出口が詰まり、分泌された脂が腺内に溜まって慢性的な炎症(肉芽腫:にくげしゅ)を引き起こした状態です。
なぜ詰まるのか、その明確な原因は不明なことも多いですが、脂漏性体質(皮脂の分泌が多い体質)や、マイボーム腺機能不全(MGD)が背景にあると考えられています。麦粒腫が「急性のニキビ」だとすれば、霰粒腫は「慢性のしこり」と例えることができます。
霰粒腫の最大の特徴は、通常は痛みを伴わないことです。しかし、このしこりに細菌が感染すると「急性霰粒腫」となり、麦粒腫と見分けがつかないほど赤く腫れて痛むことがあります。この点が、両者の診断を時に難しくさせます。
日本眼科学会は、霰粒腫は自然に治癒することが少ないと説明しています。小さなしこりで違和感がなければ経過観察することもありますが、ある程度の大きさになって外見上の問題や、しこりが角膜を圧迫して乱視を引き起こすような場合は、治療が検討されます。
治療法にはいくつかの選択肢があります。初期段階では麦粒腫と同様に温罨法が試みられることがあります。炎症を抑えるためにステロイドの点眼や軟膏が使われたり、しこりに直接ステロイドを注射して縮小を図る方法もあります。しかし、これらの保存的治療で改善しない場合や、しこりが硬く大きい場合は、霰粒腫の外科的治療として、まぶたの裏側(または表側)を小さく切開し、内部の溜まった脂や肉芽組織を摘出する手術(霰粒腫摘出術)が行われます。これは通常、外来で局所麻酔下にて短時間で行われます。
特に高齢者で霰粒腫が何度も再発する場合や、非典型的な外観の場合は、まれに脂腺癌(しせんがん)などの悪性腫瘍との鑑別が必要になることもあります。痛みがなくても、しこりが続く場合は眼科を受診し、適切な診断を受けることが重要です。
眼瞼下垂:まぶたが下がる原因と生活への影響
まぶたのしこりとは別に、「最近、まぶたが重く感じる」「目が開けにくくなった」「顎を上げて物を見る癖がついた」といった悩みは、眼瞼下垂(がんけんかすい)のサインかもしれません。これは、上まぶた(上眼瞼)が正常な位置よりも下がってしまい、瞳孔(ひとみ)の一部が隠れてしまう状態を指します。
眼瞼下垂は、その原因によっていくつかのタイプに分類されます。日本眼科学会の解説によると、大きく分けて生まれつきの「先天性」と、成長してから発症する「後天性」があります。後天性の中で最も多いのが「腱膜性(けんまくせい)眼瞼下垂」です。これは、まぶたを持ち上げる筋肉(眼瞼挙筋)そのものの力は正常でも、その筋肉がまぶたの先端(瞼板)に付着する部分の「腱膜」が伸びたり、外れたりすることで起こります。主な原因は加齢による組織のゆるみですが、長期間のハードコンタクトレンズの使用、目を強くこする癖、白内障手術後などでも生じることが知られています。
また、日本眼科医会は、実際にはまぶたの位置は下がっていないのに、加齢によってまぶたの皮膚がたるんで覆いかぶさる「眼瞼皮膚弛緩症(がんけんひふしかんしょう)」も存在し、これを「偽眼瞼下垂(ぎがんけんかすい)」として区別しています。これらは治療法が異なるため、眼科での正確な診断が不可欠です。
眼瞼下垂は、単に「眠そうに見える」といった美容上の問題だけではありません。視野が狭くなる(特に上方)という機能的な問題を引き起こします。無意識のうちに眉毛を上げて目を開けようとするため、額にしわが寄り、慢性的な頭痛や肩こりの原因となることもあります。眼瞼下垂の治療は、主に手術となります。視野障害などの機能的な問題が確認されれば、健康保険の適用となります。手術では、伸びてしまった腱膜を修復・短縮したり、皮膚のたるみを除去したりします。
まぶたに関連する問題としては、他にも逆さまつげ(睫毛内反・眼瞼内反)があり、これも角膜を傷つける原因となるため、眼科での診断が推奨されます。
涙道閉塞:「涙もろい」のではなく「流れない」病気
まぶたの病気と並んで多いのが、「涙」に関するトラブルです。「悲しくないのに、いつも目が潤んで涙があふれる」「風にあたると涙が止まらない」といった症状は、一般に「涙目(なみだめ)」、医学的には流涙症(りゅうるいしょう)と呼ばれます。
流涙症の原因は二つあります。一つは、ドライアイやアレルギーなどで角膜が刺激され、涙の分泌が過剰になる場合。もう一つが、涙の分泌量は正常でも、その排水路である「涙道(るいどう)」が詰まってしまい、涙があふれ出てしまう場合です。後者が涙道閉塞(るいどうへいそく)または涙道狭窄(きょうさく)です。
日本眼科医会の解説によれば、涙は上まぶたの外側にある涙腺で作られ、目を潤した後、目頭にある「涙点(るいてん)」という小さな穴から吸い込まれます。その後、「涙小管(るいしょうかん)」、「涙嚢(るいのう)」を経て、「鼻涙管(びるいかん)」を通り、最終的に鼻の奥へと排出されます。この排水路のどこかが狭くなったり、詰まったりすると、涙は行き場を失い、目からあふれ出てしまうのです。
涙とともに出てくる目やにが続く場合、特に注意が必要です。涙道が詰まると、涙嚢の中で涙がよどみ、細菌が繁殖しやすくなります。これにより、目頭が赤く腫れて強い痛みを伴う「急性涙嚢炎(きゅうせいるいのうえん)」を引き起こすことがあります。涙嚢炎は、抗菌薬による治療と、涙道の閉塞を解除する処置が必要となる深刻な状態です。
涙道閉塞の原因は、日本眼科学会によると、新生児に多い「先天性鼻涙管閉塞」(多くは自然に開通)と、加齢や炎症によって後天的に狭くなる場合があります。診断は、眼科で涙点から生理食塩水を流し、鼻に通じるかを調べる「涙道通水検査」などによって行われます。
治療は、閉塞の程度や場所によります。軽度の狭窄であれば、涙道に細い管(ブジー)を通して広げたり、涙道内視鏡を使って詰まりを確認しながら開通させたりします。再閉塞を防ぐために、シリコン製のチューブを一定期間留置することもあります。これらの方法で改善しない重度の閉塞の場合は、鼻の骨を一部削って涙嚢と鼻腔を直接つなぐ新しいバイパスを作る「涙嚢鼻腔吻合術(るいのうびくうふんごうじゅつ、DCR)」という手術が検討されます。
すぐに受診すべき危険なサイン
これまで解説した4つの疾患は、多くの場合、緊急性は高くありません。しかし、中にはこれらの病気と似た症状で始まりながら、視力や、時には生命に関わる重篤な状態が隠れていることがあります。以下の「危険なサイン(レッドフラグ)」を見逃さないことが非常に重要です。
- 急速な腫れと発熱:まぶたの腫れが数時間から1日といった短時間で急速に広がり、まぶたがパンパンに腫れて目が開けられなくなる、強い痛み、高熱や悪寒を伴う場合。これは「眼窩蜂窩織炎(がんかほうかしきえん)」という眼球の周囲の組織に感染が広がった危険な状態の可能性があります。抗菌薬の点滴治療が直ちに必要です。単なる目の腫れと自己判断せず、直ちに眼科または救急外来を受診してください。
- 目頭の激しい痛みと腫れ:目頭(内眼角)が赤く硬く腫れ、押すと激しい痛みがあり、膿が出てくる、発熱を伴う場合。これは前述の「急性涙嚢炎」の典型的な症状です。涙嚢が破裂する危険もあり、早期の治療が必要です。
- 突然の眼瞼下垂と神経症状:片方のまぶたが「突然」下がってきた場合。特に、「物が二重に見える(複視)」「瞳孔の大きさが左右で違う」「激しい頭痛」を伴う場合は、脳動脈瘤の破裂や脳梗塞、重症筋無力症など、脳や神経の重大な病気が原因である可能性があります。これは単なる目の痛みとは異なり、様子を見るべきではありません。直ちに神経内科や脳神経外科、あるいは救急受診が必要です。
- 明らかな視力低下や眼球突出:まぶたの腫れだけでなく、明らかに視力が低下している、目が前に飛び出す感じがする、眼球の動きが悪いといった場合は、眼窩内の腫瘍や甲状腺眼症など、別の疾患を強く疑う必要があります。
手術が検討されるタイミングと次のステップ
危険なサインがない場合でも、まぶたや涙道の問題が生活の質(QOL)を著しく低下させることがあります。どのような場合に手術が検討されるのでしょうか。
霰粒腫では、保存的治療(温罨法や薬物治療)を一定期間行っても、しこりが残存し、外見上の問題となる場合や、角膜を圧迫して視機能に影響を与える場合に摘出術が検討されます。手術後のケアも重要ですが、通常は日帰りで対応可能です。
眼瞼下垂では、美容的な希望だけの場合は保険適用外となりますが、まぶたが瞳孔にかかり、視野が狭くなっていると客観的に判断された場合、機能回復のための手術(眼瞼挙筋腱膜前転術など)が保険適用で検討されます。
涙道閉塞では、流涙や目やにが頻繁で日常生活に支障をきたす場合、あるいは涙嚢炎を繰り返す場合に、積極的な治療が推奨されます。ブジーやシリコンチューブ留置術で改善しない場合は、前述のDCR手術が検討されます。これらの眼科手術は専門性が高いため、眼形成(がんけいせい)や涙道を専門とする眼科医への相談が望ましいでしょう。
このセクションでは、比較的頻度の高いまぶたと涙道の病気について解説しました。これらは多くの場合、適切に対処すれば視機能に大きな後遺症を残しません。しかし、眼球は非常にデリケートな器官であり、突然の「外傷」や「緊急疾患」には、全く異なる迅速な対応が求められます。次のセクションでは、化学物質が目に入った場合や、目を強く打った場合など、「眼外傷と緊急疾患」について詳しく解説します。
眼外傷と緊急疾患(化学損傷・外傷性網膜剥離・視力喪失の予防)
前節では、比較的慢性的な経過をたどるまぶたや涙道の病気について見てきました。しかしこのセクションでは、それとは全く対照的に、一刻を争う「眼の緊急事態」について解説します。
眼の外傷(ケガ)は、誰の身にも突然起こりうる、最も恐ろしい事態の一つです。化学薬品が目に入る、ボールが強く当たる、鋭利なもので突き刺さる——。突然の激しい痛み、出血、あるいは急激な視力低下に、パニックになるのは当然です。このような緊急時に、最初の数分、数時間がその後の視力を左右することがあります。ここでは、失明を防ぐために知っておくべき、最も重要な初期対応と、見逃してはならない危険なサインについて、国際的なガイドラインに基づき、深く掘り下げて解説します。
化学物質が目に入ったときの最初の1時間で何をするか
日常生活や職場で起こりうる眼外傷の中で、最も緊急性が高く、かつ初期対応が視力予後をほぼ決定づけるのが「化学眼外傷」です。台所の漂白剤、お風呂用洗剤、職場の洗浄剤、あるいはセメントや石灰が目に入った場合、その瞬間から角膜(黒目)の組織は破壊され始めます。
多くの方が「まず病院へ行かなければ」と焦りますが、化学眼外傷において、病院よりも優先されるべき絶対的な行動が一つだけあります。それは、「現場での、ただちの、大量の水による洗眼」です。
化学物質は、目に入った瞬間に組織の奥深くへと浸透していきます。米国のStatPearls(2023年更新)や2020年の国際的なレビューによれば、特に危険なのは、苛性ソーダ(排水管洗浄剤)、アンモニア水、セメント、石灰などの「アルカリ性」物質です。アルカリは組織のタンパク質を溶かしながら深部へ侵入し続けるため、酸性の物質(バッテリー液など)よりも重症化しやすい傾向があります。酸はタンパク質を凝固させ、それがバリアとなってある程度浸透を食い止めることがありますが、どちらにせよ深刻な事態であることに変わりはありません。
組織の破壊は、洗い流すまで止まりません。救急車を待つ間、あるいは病院へ向かう車中も、化学物質は角膜を溶かし続けます。だからこそ、現場での対応がすべてなのです。
- ただちに洗眼を開始する: 慌てず、しかし1秒でも早く、清潔な流水(水道水、シャワー、生理食塩水など)で目を洗い始めます。
- まぶたを強制的に開く: 痛みでまぶたを固く閉じてしまいがちですが、指でまぶたを大きく開き、結膜(まぶたの裏側)の隅々まで水が届くようにします。
- 十分な時間、洗い続ける: 最低でも15分から30分は洗い続ける必要があります。英国のNHS(国民保健サービス)は、重症例では「約1時間」の洗眼を推奨しています。アルカリ性の場合は、中和されるまでさらに時間が必要です。
- 洗眼しながら救急要請する: 可能であれば、他の人に救急車(119番)を呼んでもらいます。洗眼を中断して電話をかけるべきではありません。
- 原因物質を持参する: Mayo Clinicは、原因となった化学物質の容器やラベルを病院へ持参することを推奨しています。これにより、医師は適切な解毒剤や治療方針を迅速に決定できます。
この初期対応が不十分だと、角膜が混濁し、深刻な角膜炎や将来的な瘢痕化、失明につながる可能性があります。化学物質による目の痛みは、視力を失う警告サインなのです。
打撲やスポーツ外傷のあとに起こる“見えづらさ”は網膜剥離のサインかもしれない
スポーツ中のボール、事故での殴打、あるいはシャンパンのコルクが目に当たるなど、眼球への「鈍的外傷(打撲)」もまた、非常に危険な事態です。多くの場合、直後は強い痛みと視界不良がありますが、しばらくすると視力が回復したように感じることがあります。この「治ったかもしれない」という自己判断が、最も危険な落とし穴です。
眼球は、水風船のように柔らかい組織です。2013年の研究モデルによれば、強い衝撃が加わると、眼球は一瞬で前後に圧縮され、その直後に赤道部(横方向)へ激しく膨張します。この暴力的な変形が、眼球内部の繊細な組織を引きちぎることがあるのです。
外見上はアザや軽い出血しかなくても、眼球内部では以下のような深刻な損傷が隠れている可能性があります。
- 前房出血(ぜんぼうしゅっけつ): 角膜と虹彩(茶目)の間に血液が溜まる状態です。初期には軽微でも、数日後に再出血して視力を奪うことがあります。前房出血は安静が第一であり、医師の管理が必要です。
- 硝子体出血・網膜出血: 眼球の後方を満たす硝子体や、光を感じる網膜に出血が起こると、視界が急に暗くなったり、インクを垂らしたように見えたりします。これも緊急性の高い網膜出血の一つです。
- 外傷性網膜剥離(TrRD): 最も警戒すべき合併症です。打撲の衝撃で網膜に穴(裂孔)が開き、そこから水が入り込むことで網膜が剥がれてしまいます。
特に恐ろしいのは、この網膜剥離が「遅れてやってくる」ことです。1991年の古典的な研究(PubMed掲載)では、外傷後の網膜裂孔や剥離のうち、約30%は受傷後24時間以内に見つかりますが、約60%は6週間以内に診断されています。つまり、受傷当日に異常がなくても、数日後、数週間後に剥離が進行することがあるのです。
したがって、眼球に強い打撲を受けた場合は、その日のうちに視力が回復したとしても、必ず眼科を受診し、散瞳(瞳孔を開く薬)による詳細な眼底検査を受ける必要があります。そして、医師から「今は大丈夫でも、以下の症状が出たらすぐに来てください」と指示された「レッドフラグ(危険なサイン)」を覚えておくことが重要です。
外傷性網膜剥離のレッドフラグ(危険なサイン)
Mayo Clinicなどの医療機関は、以下の症状を緊急受診のサインとしています。
- 飛蚊症(ひぶんしょう)の急増: 目の前に黒い点やゴミのようなものが突然、大量に現れる。
- 光視症(こうししょう): 暗い場所で、目の端に稲妻のような光が走る。
- 視野欠損(しやけっそん): 視界の一部が、カーテンや影がかかったように見えなくなる。
外傷性網膜剥離(TrRD)の診断と治療タイミング
「網膜剥離」という言葉を聞くと、誰もが強い不安を感じるでしょう。これは、カメラで言えばフィルムにあたる網膜が、眼球の壁から剥がれてしまう状態であり、治療しなければ失明に至る病気です。外傷性網膜剥離(TrRD)は、2024年の最新レビュー(PubMed掲載)によれば、全網膜剥離の約10〜40%を占めるとされています。
診断は、まず「いつ、どのようなケガをしたか」という問診が極めて重要です。2016年のレビュー(PubMed掲載)では、外傷直後は出血などで眼内が濁り、網膜の観察が困難な場合があるため、診断が遅れるリスクが指摘されています。しかし、超音波検査や詳細な眼底検査により、網膜剥離の詳しい原因となっている特徴的な裂孔(網膜周辺部の断裂など)を見つけ出します。
「網膜剥離は治るのか」という問いに対して、答えは「はい、ただし緊急手術が必要です」となります。これは、次セクションで解説する眼科手術の中でも、特に緊急性の高いものの一つです。治療の目的は、剥がれた網膜を元の位置に戻し、裂孔をレーザーや冷凍凝固で塞ぐことです。
ここで重要になるのが「手術のタイミング」です。時間が経過しすぎると、網膜上に硬い瘢痕組織(増殖硝子体網膜症:PVR)が形成され、網膜をさらに強く引っ張り、手術が困難になります。2016年の研究(PMC掲載)や2017年の症例シリーズ(PMC掲載)では、受傷後7日以内の早期に手術(硝子体手術や強膜バックリング術)を行うことで、このPVRや術後感染症のリスクが低下する可能性が示唆されています。手術後の回復期間や手術後の生活にも影響するため、早期の診断と治療介入が非常に重要です。
保護眼鏡で防げる眼のケガ――CDCが示す予防の基本
これまでに述べてきた眼外傷の多くは、非常に悲劇的ですが、その大部分は「予防可能であった」という事実もまた、重く受け止める必要があります。
米国疾病予防管理センター(CDC)は、職場、家庭でのDIY、スポーツ活動中における保護眼鏡の着用が、失明を防ぐための最も効果的な手段であると明言しています。CDC/NIOSH(米国国立労働安全衛生研究所)の2025年の指針によれば、特に建設業、製造業、化学薬品の取り扱い、粉じんの多い作業、草刈り機や電動工具の使用時には、適切な個人用保護具(PPE)が不可欠です。
ここで絶対に誤解してはならないのは、「日常のメガネやコンタクトレンズは、安全ゴーグル(保護眼鏡)の代わりにはならない」という点です。CDCは明確に警告しています。なぜなら、通常のメガネは横からの飛来物を防ぐサイドシールドがなく、レンズの耐衝撃性も保証されていないため、強い衝撃でレンズ自体が割れて眼球を傷つける「二次災害」の原因にさえなりうるからです。
眼の健康を守るためには、TPOに応じた使い分けが必要です。日常の紫外線対策としてはUVカット眼鏡の選び方を知ることが重要ですが、工具を使ったり、化学薬品を扱ったりする際は、JIS規格やANSI規格に適合した耐衝撃性のある保護ゴーグルを着用する習慣が、あなたの視力を守ります。また、コンタクトレンズの安全な使用は感染予防には重要ですが、外傷予防には全く寄与しないことも知っておくべきです。
外傷と間違えやすい眼の緊急疾患
「突然、目が見えなくなった」「耐え難いほどの目の痛み」といった症状は、必ずしも外傷だけが原因とは限りません。ケガをしていなくても、外傷と同じか、それ以上に緊急性の高い「眼の病気」が存在します。これらは失明までの時間が極めて短いため、症状が外傷と似ている緊急疾患として知っておく必要があります。
- 急性閉塞隅角緑内障(きゅうせいへいそくぐうかくりょくないしょう):
「眼の緊急事態の王様」とも呼ばれます。眼球内の水の流れ道(隅角)が急に塞がり、眼圧が異常に高くなる状態です。激しい目の痛み、頭痛、吐き気、視力低下、光の周りに虹がかかって見える(虹視症)などの症状が特徴です。治療が遅れると数時間で視神経が回復不能なダメージを受けます。これは慢性的な緑内障とは異なり、即時のレーザー治療や手術が必要です。 - 網膜中心動脈閉塞症(もうまくちゅうしんどうみゃくへいそくしょう):
「眼の脳卒中」とも呼ばれます。網膜に栄養を送る中心動脈が詰まる病気です。特徴は「痛みは全くない」にもかかわらず、「突然、片方の目が真っ暗になる」ことです。発症から数時間以内に血流を再開させなければ、網膜の神経細胞が死んでしまい、視力が回復する見込みは極めて低くなります。 - 眼内炎(がんないえん):
眼球内部が細菌や真菌に感染し、重度の炎症を起こす状態です。目の手術後や注射後、あるいは外傷からの感染で発症します。急激な視力低下、激しい目の痛み、充血が特徴で、緊急の抗生剤投与や手術が必要です。
これらの病気は、外傷の有無にかかわらず、上記のような症状が出た時点で「ゴールデンタイム」が始まっていると考え、夜間や休日であっても救急外来を受診する必要があります。
よくある質問(FAQ)
Q1: アルカリ性の洗剤が目に入ったとき、何分くらい洗えばいいですか?
A: 可能な限りすぐに洗眼を始めてください。最低でも15分から30分は必要です。しかし、英国NHSは「約1時間」の継続を推奨しており、特にアルカリ性は組織への浸透が強いため、より長時間の洗眼が安全とされています(StatPearls 2023, Frontiers in Medicine 2020)。pH試験紙があれば、中性に戻るまで続けるのが理想です。洗眼を続けながら救急車を呼んでください。
Q2: 目をぶつけたあとに“ピカッ”と光が見えるのは危険ですか?
A: 非常に危険なサインです。外傷による衝撃で網膜が引っ張られている(硝子体牽引)可能性があり、外傷性網膜剥離の初期症状(光視症)であることが多いです(PubMed 1991, PubMed 2024)。視野が欠ける前兆である可能性が高いため、受傷当日か遅くとも翌日までに、必ず眼科で散瞳による眼底検査を受けてください。
Q3: 外傷性の網膜剥離はどのくらいで手術する必要がありますか?
A: 網膜剥離は緊急手術が必要な状態です。特に外傷性の場合、時間が経つと瘢痕化(PVR)が進み、手術が難しくなります。受傷後7日以内に手術を行うことで、このPVRや感染症のリスクが低下するという報告があります(PMC 2017, PMC 2016)。症状を自覚したら、できるだけ早く専門医の診断を仰ぐことが推奨されます。
Q4: 目のケガは眼科がない病院でも診てもらえますか?
A: 一次救急(ER)では、洗眼、疼痛コントロール、基本的な診察などの初期対応は可能です。しかし、網膜剥離や眼球の穿孔(穴が開くこと)が疑われる場合、専門的な診断と手術が必要となるため、最終的には眼科専門医のいる高次医療機関への速やかな搬送が推奨されます(大阪府危機管理対応指針 2025)。
Q5: 仕事で目をケガしないためには何をすればいいですか?
A: 米国CDC/NIOSHは、作業内容に合った適切な保護眼鏡(ゴーグル、フェイスシールド、JIS/ANSI規格適合品)を着用し、顔に正しくフィットさせることが最も重要であると強調しています。日常のメガネやコンタクトレンズは、飛来物や化学物質に対する十分な防護にはなりません(CDC 2024)。
眼科手術の種類(白内障・レーシック・硝子体・緑内障手術・角膜移植)
前節では、予期せぬ事故や化学物質による「眼外傷と緊急疾患」について詳しく見てきました。それらは一刻を争う対応が必要な状態です。対照的に、本節では、視機能の回復や維持、あるいは失明の予防を目的として「計画的に行われる眼科手術」に焦点を当てます。
「目にメスを入れる」と聞くと、多くの方が強い不安や恐怖を感じるかもしれません。しかし、現代の眼科手術は技術の進歩により、非常に精密で、多くの場合、局所麻酔による日帰りや短期入院で安全に行われています。ここでは、日本で最も一般的に行われている5つの主要な手術――白内障手術、レーシック、硝子体手術、緑内障手術、そして角膜移植――について、それぞれ「何のために」「どのようなこと」が行われるのかを、できるだけ分かりやすく、順を追って解説していきます。手術の目的は、視力を「取り戻す」ものから、「守る」ものまで様々です。正しい知識を持つことが、不安を和らげ、最適な治療を選択するための第一歩となります。
白内障手術の基本手順(超音波乳化吸引+眼内レンズ)
「最近、視界がかすむ」「光が妙にまぶしく感じる」といった症状で眼科を受診し、「白内障ですね、手術を考えましょう」と告げられた時の不安は計り知れません。多くの方が「目の手術」という言葉の響きに、痛みや失明のリスクを想像し、怖くなってしまうのは当然のことです。
しかし、まず知っておいていただきたいのは、白内障とは何かということです。これは、目の中にある「水晶体」という、カメラのレンズの役割を持つ組織が白く濁ってくる加齢現象の一種です。手術は、眼球そのものを取り出すようなものでは決してなく、この「濁ったレンズを新しい人工のレンズに入れ替える」治療です。現在、日本で行われている白内障手術は非常に洗練されており、安全性が高い治療法として確立されています。
[cite_start]
日本で標準的に行われているのは、日本眼科学会も解説している「超音波水晶体乳化吸引術(PEA)」と「眼内レンズ(IOL)挿入術」という方法です [cite: 1]。これは、厚生労働省の診療ガイドラインでも推奨されている標準的な術式です。
手術の流れを簡単に説明すると、以下のようになります。
- 麻酔:まず、点眼薬による局所麻酔を行います。これにより、手術中に痛みを感じることはほとんどありません。意識はありますが、リラックスしている間に終わります。
- 小さな切開:黒目と白目の境目(角膜)を、わずか2mm前後という非常に小さく切開します。この傷口は非常に小さいため、通常は縫合する必要がなく、自然にふさがります。
- 水晶体の乳化吸引:その小さな切開口から、超音波を発する細い器具を挿入します。この超音波の振動で、濁った水晶体(中身)を細かく砕きながら、同時に吸引して取り除きます。この時、水晶体が入っていた「袋(水晶体嚢)」は残しておきます。
- 眼内レンズ(IOL)の挿入:水晶体の中身がきれいになくなった後、残しておいた袋(水晶体嚢)の中に、折りたたんだ状態の人工の眼内レンズ(IOL)を挿入します。レンズは目の中でゆっくりと広がり、正しい位置に固定されます。
この一連の流れは、非常に短時間(多くの場合10分~20分程度)で終了します。挿入する眼内レンズには、ピントが1箇所に合う「単焦点レンズ」と、複数の距離にピントが合う「多焦点レンズ」などがあります。どのレンズがご自身のライフスタイルに合うか、また手術費用や保険適用がどうなるかは、医師とよく相談する必要があります。かつては、ぶどう膜炎など他の目の病気があると眼内レンズは挿入できない(禁忌)とされていましたが、厚生労働省の通知(2011年)にもあるように、手術技術の進歩により、現在では専門医の管理下で安全に手術が可能となっています。手術後のケアも非常に重要ですが、この手術によって、長年悩まされた「かすみ」が晴れ、明るい視界を取り戻すことができるのです。
屈折矯正手術(レーシック)の適応と最新ガイドライン
「メガネやコンタクトレンズのない生活を送りたい」——これは、近視や乱視に悩む多くの方にとっての長年の願いかもしれません。この願いを叶える選択肢の一つが、「屈折矯正手術」であり、その中で最も広く知られているのが「レーシック(LASIK)」です。
レーシックは、目の表面にある「角膜」という透明な組織の形をレーザーで変えることによって、光の屈折を調整し、ピントが網膜に合うようにする手術です。具体的には、まず「フラップ」と呼ばれる角膜の表面の薄いフタを作成し、それをめくります。次に、露出した角膜の内部組織に「エキシマレーザー」という特殊なレーザーを照射し、あらかじめ計算された通りに角膜のカーブを精密に削って形を変えます。最後に、めくったフラップを元の位置に戻して終了です。フラップは自然に接着するため、縫合は必要ありません。
この手術の魅力は、日本眼科学会も解説している通り、手術時間が非常に短く(両眼で数分~十数分)、局所麻酔で行え、術後比較的早く視力が回復することです。しかし、ここで非常に重要なことがあります。それは、「レーシックは誰でも受けられるわけではない」という点です。
日本眼科学会が2024年に公表した最新の「屈折矯正手術のガイドライン(第8版)」では、手術の適応について厳格な基準が示されています。例えば、以下のような方は原則としてレーシックを受けることができません。
- 角膜が薄い方(レーザーで削る十分な厚みがないため)
- 円錐角膜(角膜が前方に突出する病気)の方、またはその疑いがある方
- 遺伝性の角膜変性症がある方
- 重度のドライアイがある方
- 近視の度が強すぎる方(矯正できる範囲には限界があります)
また、手術の安全性についても正しく理解しておく必要があります。日本では過去に、一部の施設での滅菌管理が不十分だったために、術後に深刻な感染性角膜炎が集団発生した事例がありました。これを受け、厚生労働省はガイドラインの周知や安全管理の徹底を繰り返し通知しています。したがって、施設選びは非常に重要です。ガイドラインを遵守し、術前の適応検査を厳格に行い、衛生管理が徹底され、術後6ヶ月以上の長期的な経過観察を行ってくれる、信頼できる医療機関を選ぶ必要があります。
米国のMayo Clinicなどの医療機関も指摘している通り、術後にはドライアイの症状が出やすくなったり、夜間に光がにじんで見える「ハロー・グレア」を感じたりすることがあります。これらの多くは時間とともに改善しますが、一部残る可能性もあります。近視を根本的に治す魅力的な選択肢ですが、術後のケアや潜在的なリスクをすべて理解した上で、ご自身の適応を医師と慎重に相談することが不可欠です。
硝子体手術が選ばれる代表的な病気(網膜剥離・糖尿病網膜症など)
「硝子体(しょうしたい)手術」と聞いても、多くの方はそれがどのような手術なのか、すぐには想像がつかないかもしれません。硝子体とは、眼球の内部の大部分を占めている、卵の白身のような透明なゼリー状の組織です。この手術は、目の「奥深く」にある網膜(カメラのフィルムに相当)や硝子体自体に問題が起きた時に行われる、非常に繊細な手術です。
日本眼科学会が解説している通り、この手術は白目(強膜)にごく小さな穴(1mm以下)を3ヶ所開け、そこから極細の手術器具を挿入して行います。器具には、眼内を照らす照明、硝子体を切除するカッター、眼圧を保つための灌流液を入れるものなどがあります。
では、どのような病気でこの手術が選ばれるのでしょうか。代表的なものは以下の通りです。
- 網膜剥離:網膜が眼球の壁から剥がれてしまった状態です。硝子体手術で、網膜を引っ張っている硝子体組織を除去し、レーザーで網膜を焼き付けて(光凝固)、剥がれた網膜を元の位置に戻します。網膜剥離が治るかどうかは、時間との勝負でもあります。
- 糖尿病網膜症:糖尿病の合併症で網膜の血管が詰まったり、出血したりする病気です。国立国際医療研究センターの解説にもある通り、進行して硝子体に出血が充満した場合や、網膜が引っ張られる牽引性網膜剥離が起きた場合に、硝子体手術で出血や増殖膜を除去します。
- 黄斑円孔・黄斑前膜:物を見る中心である「黄斑」に穴が開いたり(円孔)、膜が張ったり(前膜)する病気です。手術で硝子体を除去し、原因となっている膜を非常に繊細な操作で剥がします。
- 眼外傷:目の中に異物が入った場合などにも行われます。
この手術で特に患者さんの負担となりうるのが、術後の体位制限です。網膜剥離などの手術では、網膜を内側から押さえるために、手術の最後に眼内に特殊なガスやシリコーンオイルを入れることがあります。このガスやオイルの浮力で網膜を正しい位置に押さえつけるため、英国NHSの解説などにもあるように、術後一定期間(数日~数週間)、「うつぶせ」や「横向き」など、決められた体位を保つ(体位保持)必要があります。これは非常に大変なことですが、網膜をしっかり接着させるために不可欠な処置です。術後の回復期間も含め、医師からの説明をよく理解し、協力することが治療の成功につながります。
緑内障で手術になるとき:眼圧を下げるための選択肢
緑内障と診断された方が手術を勧められた時、多くの方が「これで失った視野が戻るかもしれない」と期待を抱かれるかもしれません。しかし、ここで最も大切で、時に受け入れ難い事実をお伝えしなければなりません。それは、日本眼科学会も明確に述べている通り、緑内障手術の目的は「すでに見えなくなった視野を回復させること」ではなく、「眼圧を確実に下げることで、これ以上病気が進行するのを防ぐこと(進行予防)」であるという点です。
緑内障は、眼圧(目の中の圧力)によって視神経が圧迫され、視野(見える範囲)が徐々に欠けていく病気です。一度障害された視神経は、現在の医療では再生させることができません。そのため、治療の柱は「眼圧を下げること」の一点に尽きます。
治療は通常、まず眼圧を下げる点眼薬から始まります。1種類で不十分なら2種類、3種類と増やしたり、レーザー治療を行ったりします。しかし、日本緑内障学会の診療ガイドライン(第5版)にもあるように、薬物療法やレーザー治療を最大限行っても目標とする眼圧まで下がらない場合や、薬の副作用で治療が続けられない場合、あるいは発見時すでに視野障害がかなり進行している場合に、手術が選択されます。
緑内障手術の基本的な考え方は、目の中の水(房水)の「排水路」を新しく作るか、既存の排水路の流れを良くすることです。代表的な手術には以下のようなものがあります。
- 濾過(ろか)手術(トラベクレクトミー):現在、最も一般的に行われる手術の一つです。白目(強膜)の一部に小さな「フタ」のようなものを作り、そこから房水を結膜(白目の表面の膜)の下にじわじわと染み出させるバイパス(排水路)を新しく作ります。房水が染み出た部分は「濾過胞(ろかほう)」と呼ばれ、白目の上が少し盛り上がった状態になります。
- 緑内障治療用インプラント挿入術(チューブシャント手術):非常に細いチューブを目の中に挿入し、そのチューブを通って房水を目の後方にあるプレートへ導き、そこから吸収させる方法です。濾過手術が難しい症例や、過去の手術でうまくいかなかった場合などに行われます。
- 線維柱帯(せんいちゅうたい)切開術:房水の元々の排水口である「線維柱帯」という部分を切開して、房水の流れを良くする手術です。
緑内障で手術が必要と判断された場合、それは「これ以上視野を失わないための、次の一手」と捉えることが大切です。手術後も眼圧が安定するまで頻繁な診察が必要であり、生涯にわたる定期的な経過観察が欠かせません。
角膜移植の種類と日本での待機期間の実情
「角膜移植」は、病気や怪我によって透明性を失い、白く濁ってしまった「角膜」(黒目の部分)を、亡くなった方から提供された透明な角膜と交換する手術です。角膜が濁ると、すりガラスを通して物を見ているようになり、視力が著しく低下します。この濁りは、薬では元に戻すことができません。角膜移植は、そのような状態から再び光を取り戻すための、唯一の根本的な治療法です。
しかし、この手術には大きな課題があります。それは「ドナー角膜」の不足です。国立国際医療研究センター(NCGM)の解説にもある通り、日本ではアイバンクを介して角膜の提供を受けますが、提供数が需要に追いついておらず、緊急性の高くない場合、手術を受けるまでに1年以上待機することも珍しくありません。
この貴重なドナー角膜を最大限に活用するため、また、患者さんの負担を減らすため、手術技術も進歩しています。かつては角膜全体(全層)を交換する「全層角膜移植(PK)」が主流でしたが、現在では角膜の悪い部分だけを交換する「パーツ移植(層状角膜移植)」が主流になりつつあります。
- 全層角膜移植(PK):濁った角膜を円形に全層くり抜き、同じ大きさのドナー角膜を縫い合わせる方法です。
- 角膜内皮移植(DSAEK / DMEK):角膜の内側にある「角膜内皮細胞」という細胞層の機能不全(水疱性角膜症など)が原因の場合に行われます。自分の角膜の表面は残し、内皮細胞層だけをドナーのものと交換します。英国NHSや米国国立眼研究所(NEI)でも、この方法が標準的な治療として紹介されています。
- 深層前層角膜移植(DALK):円錐角膜など、角膜の内皮細胞は正常だが、実質層(中間層)に問題がある場合に行われます。内皮細胞を残して、表層~実質層だけを交換します。
パーツ移植の利点は、自分の健康な部分(特に内皮細胞)を残せる場合、術後の拒絶反応のリスクが低くなることです。手術後は、日本眼科学会誌の報告にもあるように、拒絶反応や感染症を防ぐために、長期にわたる点眼と定期的な診察が不可欠です。また、日本では、ドナー不足の課題を解決するため、培養した角膜内皮細胞を注入する再生医療の研究も進められています。角膜移植の世界は、技術革新が続いている分野なのです。
手術後すぐに眼科へ行くべき危険サイン(感染・眼圧上昇・拒絶反応)
無事に手術が終わり、ほっと一息つかれることと思います。しかし、眼科手術において、手術の成功と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「術後の管理」です。手術後の食事や生活習慣も大切ですが、それ以上に「異常の早期発見」が視力を守る鍵となります。
手術後の目は、傷口がふさがっておらず、非常にデリケートな状態です。万が一、合併症が起きた場合、対応が数時間遅れるだけで、取り返しのつかない視力低下につながる可能性があります。特に「感染」「急激な眼圧上昇」「拒絶反応(角膜移植の場合)」は危険です。以下に示すのは、手術の種類に関わらず共通する「レッドフラグ(危険なサイン)」です。これらの症状を感じたら、処方された点眼薬をさして様子を見るのではなく、「夜間や休日であっても」すぐに手術を受けた施設に連絡し、指示を仰いでください。
- 急激な視力低下・見え方の悪化:「昨日より明らかにぼやける」「視野の一部が黒いカーテンのように欠けて見える」「視界の中心が歪む」といった症状。術後の網膜剥離、黄斑部(黄斑)の障害、あるいは重篤な感染の可能性があります。
- 強い目の痛み・頭痛・吐き気:単なるゴロゴロ感とは異なる、我慢できないほどの目の痛みや、目の奥から頭にかけてのズキズキする痛み、吐き気を伴う場合。術後の炎症や出血による急激な眼圧上昇(緑内障発作に似た状態)が疑われます。
- 急に増えた充血と膿(うみ)のような目やに:目が真っ赤になり、ネバネバした黄色や緑色の目やにが大量に出る場合。これは「術後感染症(眼内炎)」の典型的なサインです。眼内炎は失明に至る最も危険な合併症の一つであり、一刻も早い治療(抗生物質の投与や再手術)が必要です。
- (角膜移植後)視力の再低下・光がまぶしい・角膜の濁り:一度は透明に見えていたのに、数週間~数年経ってから再び視力が落ちたり、光を異常にまぶしく感じたり、移植した角膜が白く濁ってきた場合。これは「拒絶反応」のサインかもしれません。早期に治療(ステロイドの点眼や内服)を開始すれば、多くの場合抑えることができます。
これらのサインは、体が発する緊急事態の警報です。「手術後だからこんなものだろう」「もう少し様子を見よう」という自己判断が、生涯の視力を左右することがあります。手術を担当した医師は、こうした万が一の事態に備えています。不安を感じたら、どんな些細なことでも、遠慮なく相談することがご自身の目を守る最善の方法です。
目と全身疾患の関係(糖尿病・高血圧・甲状腺・膠原病)
前節では、白内障手術やレーシックなど、眼そのものの問題を解決するための様々な手術方法について詳しく見てきました。しかし、眼のトラブルは、必ずしも眼だけに起因するわけではありません。古くから「眼は全身を映す鏡」と言われていますが、これは単なる比喩ではないのです。
なぜなら、眼球の奥にある「網膜」は、医師がメスを入れることなく、体内の微細な血管(細小血管)や神経の状態を直接観察できる唯一の場所だからです。そのため、ご自身ではまだ自覚症状がない段階でも、全身の病気の初期サインが眼底検査で発見されることは少なくありません。特に、生活習慣と深く関わる糖尿病や高血圧は、全身の血管にダメージを与え、それが網膜の血管にも如実に現れます。
このセクションでは、眼の健康がいかに全身の状態と密接に結びついているか、特に重要な「糖尿病」「高血圧」「甲状腺疾患」「膠原病(自己免疫疾患)」の4つの全身疾患に焦点を当て、それぞれの病気がどのように眼に影響を及ぼすのか、そしてなぜ眼科の定期受診が全身の健康管理において不可欠なのかを、深く掘り下げて解説します。
なぜ糖尿病になると「まず目」を診るのか
「糖尿病と診断された」「血糖値が高めだ」と指摘されたとき、多くの方が「失明するのではないか」という強い不安を感じます。その不安は決して大げさなものではなく、厚生労働省のe-ヘルスネットによれば、糖尿病網膜症は日本において成人の失明原因の上位を占め続けています。
糖尿病が眼に及ぼす最大の影響は、この「糖尿病網膜症」です。高血糖の状態が長く続くと、血液がドロドロになり、全身の微細な血管(細小血管)が傷つき、詰まっていきます。特に網膜は、光を感じるために酸素と栄養を大量に必要とするため、非常に細い血管が張り巡らされています。高血糖によってこれらの血管がダメージを受けると、血液の成分が漏れ出したり(黄斑浮腫)、出血(眼底出血)を起こしたり、最終的には血管が詰まってしまいます。
血管が詰まると、網膜は酸素不足に陥ります。すると体は、「新しい血管(新生血管)」を急いで作ることで酸素不足を補おうとします。しかし、この新生血管は非常に脆く、すぐに出血したり、かさぶたのような膜(増殖膜)を作ったりします。この膜が網膜を引っ張り、網膜剥離を引き起こすことがあり、これが失明の大きな原因となります。
糖尿病網膜症の最も恐ろしい点は、病気がかなり進行するまで自覚症状がほとんどないことです。「まだよく見えているから大丈夫」と自己判断し、眼科の検診を怠っている間に、網膜の血管は静かにダメージを受け続けます。視力の低下や目のかすみを自覚した時には、すでに深刻な状態(増殖網膜症)に陥っているケースも少なくないのです。だからこそ、厚生労働省や日本眼科学会は、糖尿病と診断されたら「症状がなくても」定期的に眼底検査を受けるよう強く推奨しています。
さらに、糖尿病の影響は網膜だけにとどまりません。高血糖は水晶体のタンパク質を変性させ、白内障の発症を早めることが知られています。また、新生血管が眼内の水の出口(隅角)を塞ぐことで眼圧が上昇し、治療が非常に難しい「血管新生緑内障」を引き起こすリスクもあります。これは通常の緑内障とは異なり、急速に進行することが特徴です。したがって、糖尿病の管理は、内科での血糖・血圧・脂質のコントロールと、眼科での定期的な眼底チェックが「車の両輪」として不可欠なのです。
高血圧が引き起こす眼底の変化と全身リスク
高血圧もまた、自覚症状がないままに全身の血管を蝕む「サイレントキラー」ですが、そのサインは網膜にも明確に現れます。眼科医が眼底検査で「高血圧性網膜症」を指摘することがありますが、これは「目の病気」であると同時に、「全身の血管が危険な状態にある」という警告サインでもあります。
高い圧力がかかり続けると、網膜の動脈は硬くなり(動脈硬化)、細くなっていきます。眼底検査では、動脈が静脈を圧迫している様子(交叉現象)や、血管の壁がもろくなって小さな出血を起こしているのが観察されます。さらに進行すると、血管が詰まって酸素不足になった部分に「綿花様白斑(めんかようはくはん)」と呼ばれるシミができたり、視神経がむくんだりします。
これらの眼底所見の重要性は、単に目の状態を示すだけではありません。米国立衛生研究所(NIH)の報告などによれば、網膜の変化の程度が重いほど、将来的に脳卒中や心筋梗塞といった命に関わる心血管イベントを発症するリスクが高いことが示されています。眼底は、脳や心臓の血管の状態を推測するための「窓」なのです。
また、高血圧と動脈硬化は、「網膜静脈分枝閉塞症」や「網膜中心静脈閉塞症」という、網膜の「血栓症」の強力な危険因子です。これは網膜の静脈が詰まってしまい、行き場を失った血液が大規模な眼底出血や黄斑浮腫を引き起こし、急激な視力低下を招く病気です。健康診断などで眼科医から「高血圧の疑いがある」と言われたら、それは「内科で全身の血管管理を始めてください」という重要なメッセージなのです。
甲状腺眼症(バセドウ病眼症)の特異的なサイン
糖尿病や高血圧が「血管」の問題として眼に現れるのに対し、甲状腺の病気、特にバセドウ病(Graves病)は「自己免疫」の問題として眼に特異的な症状を引き起こします。これを「甲状腺眼症(またはバセドウ病眼症)」と呼びます。
この病気の本態は、甲状腺を攻撃するのと同じ「自己抗体」が、間違って眼の周りにある組織(眼窩脂肪や、眼球を動かす筋肉である外眼筋)をも攻撃してしまうことにあります。日本眼科学会によると、この自己抗体による攻撃が炎症を引き起こし、組織が腫れたり(浮腫)、硬くなったり(線維化)します。
その結果、以下のような特徴的な症状が現れます。
- 眼球突出:眼の奥の脂肪や筋肉が腫れるため、眼球が前方に押し出されます。いわゆる「目が飛び出た」状態です。
- 眼瞼後退:まぶたの筋肉が緊張・収縮し、まぶたが吊り上がったようになり、驚いたような「きつい目つき」に見えることがあります。
- 複視(物が二重に見える):外眼筋が腫れて硬くなると、左右の眼の動きが連動しなくなり、物が二重に見えることがあります。特に上下や左右を見たときに顕著になります。
- 眼の奥の痛み・圧迫感:眼窩内の組織が腫れ上がるため、眼の奥が重苦しい、痛むといった症状が出ます。
- 視力低下・視神経障害:最も重篤な合併症として、腫れ上がった組織が視神経を圧迫し、視力や視野に障害が出ることがあります。これは緊急の治療を要する状態です。
重要なことは、これらの眼症状は、必ずしも甲状腺機能の異常(ホルモン値の亢進や低下)と一致して現れるとは限らない点です。国立国際医療研究センター病院の解説にもあるように、甲状腺の数値が薬で安定していても眼症が進行することもあり、逆に眼症状が先行してバセドウ病が見つかるケースもあります。まぶたの腫れや目の見え方に変化を感じたら、内分泌内科と連携して甲状腺眼症を専門とする眼科を受診することが極めて重要です。
膠原病(自己免疫疾患)が引き起こす眼の炎症と乾燥
膠原病(こうげんびょう)とは、本来自らを防衛するはずの免疫システムが異常をきたし、自分自身の正常な組織を攻撃してしまう「自己免疫疾患」の総称です。関節リウマチ、シェーグレン症候群、全身性エリテマトーデス(SLE)、ベーチェット病などがこれに含まれますが、これらの病気は眼にも多彩な症状を引き起こします。
最も代表的なものの一つが、シェーグレン症候群による重度のドライアイ(乾燥性角結膜炎)です。厚生労働省の資料にもある通り、これは自己抗体が涙腺や唾液腺を攻撃し、破壊することで、涙や唾液の分泌が極端に減少する病気です。単なる「目の乾き」とは異なり、涙の量が絶対的に不足するため、角膜(黒目)の表面が傷だらけになり、強い異物感、痛み、視力低下を引き起こします。市販の目薬では対応できず、専門的なドライアイ治療や、膠原病そのものの管理が必要です。
また、ベーチェット病のように、全身の血管に炎症を起こすタイプの膠原病では、眼球内部の「ぶどう膜」に強い炎症(ぶどう膜炎)を繰り返すことが特徴です。ベーチェット病によるぶどう膜炎は、かつては日本の失明原因の上位を占めるほど重篤なものでした。近年は生物学的製剤などの治療の進歩で視力予後が改善しましたが、依然として内科(リウマチ科)と眼科の緊密な連携による迅速な炎症コントロールが求められます。
関節リウマチ(RA)の患者さんでは、白目(強膜)に炎症が起きる「強膜炎」や「上強膜炎」が見られることがあります。特に「強膜炎」は、海外の報告によれば、眼球を動かすだけでも痛むほどの強い眼痛と充血を特徴とし、膠原病の活動性が高まっているサインである可能性が指摘されています。このように、原因不明のぶどう膜炎、頑固なドライアイ、痛みを伴う充血などが続く場合は、背景に膠原病が隠れていないか、血液検査を含めた全身的な精査が必要となることがあります。
このように、糖尿病、高血圧、甲状腺疾患、膠原病は、それぞれ異なるメカニズムで眼に深刻な影響を与えます。眼科医は、眼底や眼球の状態を見ることを通じて、これらの全身疾患の存在を疑い、内科やリウマチ科への受診を勧める「最初の砦」となることもあります。眼の健康を守ることは、全身の健康管理と表裏一体なのです。
これまで見てきた病気が、主に体内の「内的な」変化(血糖、血圧、免疫)によって引き起こられるのに対し、現代人の眼は、かつてないほどの「外的な」ストレスにもさらされています。次のセクションでは、まさに現代の生活習慣病とも言える「デジタル時代の眼健康」について詳しく見ていきます。
デジタル時代の眼健康(VDT症候群・ブルーライト・視疲労)
前節では、糖尿病や高血圧といった全身の疾患が、いかに眼の健康に深刻な影響を及ぼすかを見てきました。しかし現代社会において、私たちの目にはもう一つの、そして非常に日常的な負担がかかり続けています。それが、スマートフォン、PC、タブレットといったデジタル機器の長時間使用です。
「単なる目の疲れだろう」「病気というほどではない」——。そう感じている方が大半かもしれません。しかし、その日常的な疲れや不快感は、「VDT症候群(Visual Display Terminal Syndrome)」あるいは「デジタルアイストレイン」と呼ばれる、明確な原因とメカニズムを持つ症状群です。これは決して「気のせい」ではなく、私たちの目と体が発している重要なサインなのです。
このセクションでは、この現代病ともいえるデジタル機器による眼の健康問題について、そのメカニズムから、誤解されがちなブルーライトの真実、そして日本の厚生労働省が示す具体的な対策まで、深く掘り下げて解説します。
VDT症候群とは?スマホ・PCが引き起こす心身の不調
夕方になると決まって肩が石のように硬くなる。夕食の準備をする頃には、ズキズキとした鈍い頭痛が始まる。PCの画面を見ていると、目が乾いてしょぼしょぼし、ピントが合いにくくなる——。これらは、VDT症候群の典型的な症状です。
VDT症候群とは、デジタル画面(Visual Display Terminal)を使った作業を長時間続けることによって引き起こされる、目や体、心に現れる様々な症状の総称です。具体的には、以下のような症状が含まれます。
- 眼の症状:目の乾燥感(ドライアイ)、充血、かすみ、視力の一時的な低下、ピント調節がスムーズにいかない、光がまぶしく感じる。
- 身体的な症状:肩こり、首や背中の痛み、頭痛、腕や手のしびれ、めまい、倦怠感。
- 精神的な症状:集中力の低下、イライラ、不安感、睡眠障害。
なぜ、たかが画面を見るだけで、これほど多様な症状が出るのでしょうか。主な原因は二つあります。
第一に、「ピント調節筋(毛様体筋)の酷使」です。私たちの目は、本来、遠くを見ている時に最もリラックスしています。しかし、PCやスマホの画面(多くの場合30cm〜60cm)を見るとき、目の中にある「毛様体筋」という筋肉が緊張し、水晶体というレンズを厚くしてピントを合わせ続けます。これは、腕にダンベルを持ったまま、何時間もその姿勢をキープするようなものです。この持続的な緊張が、目の疲れや、時には目の奥の痛みとして現れるのです。
第二に、「不自然な姿勢(不良姿勢)」です。特にノートPCやスマートフォンを使う際、私たちは無意識のうちに画面を覗き込むように頭を前に突き出し、背中を丸めがちです(いわゆる「タートルネック姿勢」)。人間の頭はボーリングの球ほどの重さ(約5kg)があり、それを首や肩の筋肉だけで支えることになります。この不自然な姿勢が、慢性的な肩こりや首の痛み、緊張型頭痛の直接的な引き金となります。
なぜ画面を見るとまばたきが減るのか:ドライアイとの深刻な関係
「朝は調子が良いのに、午後になると目が乾いて砂が入ったようにゴロゴロする」。これはVDT症候群の中でも、特に「まばたきの減少」が引き起こす典型的な症状です。
このメカニズムは非常に単純です。私たちは普段、1分間に約15回〜20回まばたきをしています。このまばたきは、車のワイパーのように、目の表面に新鮮な涙(油層と水層のバランスが取れたバリア)を塗り広げ、目を潤し、保護する重要な役割を担っています。
ところが、研究によれば、PCやスマホの画面に集中している間、このまばたきの回数が無意識のうちに半分以下(1分間に5回〜7回程度)にまで激減することがわかっています。集中すればするほど、まばたきを忘れてしまうのです。
まばたきが減るとどうなるか。涙の「ワイパー」が動かないため、目の表面の涙は蒸発し放題になります。特に、エアコンが効いた乾燥したオフィス環境では、涙の蒸発はさらに加速します。その結果、涙のバリアが壊れ、目の表面(角膜)がむき出しになり、乾燥感、異物感、かすみといった不快な症状が現れます。
これが、VDT作業とドライアイ(乾き目)の密接な関係です。一時的な疲れ目であれば休息で回復しますが、この「まばたき減少による乾燥」が慢性化すると、角膜の表面に傷がつきやすい状態となり、治療が必要なドライアイへと進行してしまうことがあります。特に、コンタクトレンズを装用している人は、レンズが涙の安定性を妨げやすいため、より一層の注意が必要です。
ブルーライトは本当に目に悪い?最新の公的見解と睡眠への影響
「ブルーライトが網膜を傷つける」「ブルーライトカット眼鏡は必須だ」——。デジタル時代の目の健康において、最も話題になり、また最も誤解されがちなのが「ブルーライト」の問題です。多くの方が、「目に悪い光」として漠然とした不安を抱えているのではないでしょうか。ここで、科学的に何がわかっており、何がわかっていないのかを整理します。
まず知っておくべきは、ブルーライト(青色光)は太陽光にも豊富に含まれる、ごくありふれた光の一部であるという事実です。
誤解1:「網膜にダメージを与える」は本当か?
確かに、実験室レベルで、非常に強いブルーライトを特定の細胞に長時間照射し続けると、酸化ストレス(細胞のサビ)を引き起こす可能性があるという基礎研究は存在します。しかし、複数の国際的なレビュー(査読付き論文のまとめ)では、「私たちが日常的に使用するPCやスマートフォンの画面レベルの明るさや距離で、網膜に明確な障害を引き起こすという決定的な証拠は、現時点では乏しい」と結論付けられています。私たちの目には、角膜や水晶体といった、光をフィルタリングする自然の防御機能が備わっているためです。
事実:最大の問題は「睡眠と体内時計」への影響
では、ブルーライトは無害なのでしょうか。いいえ、そうではありません。現在、科学的に最も確かな問題として指摘されているのは、網膜へのダメージではなく、「睡眠の質と体内時計(概日リズム)への影響」です。
私たちの網膜には、「ipRGCs」という特殊な細胞があり、これはブルーライトを強く感知します。日中にこの光を浴びることは、脳に「今は昼だ、活動しろ」と指令を出し、私たちを覚醒させます。問題は、それを夜間に浴びた場合です。
夜、寝る前に強いブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼だ」と勘違いし、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を強力に抑制してしまいます(出典:厚生労働省 e-ヘルスネット)。これが、「ベッドでスマホを見ていたら目が冴えて眠れなくなった」という現象の正体です。睡眠の質が低下すれば、翌日の目のかすみや倦怠感、集中力低下にも直結します。
また、ブルーライトは他の色の光よりも散乱しやすいため、人によっては「まぶしさ(グレア)」や「ちらつき」を感じやすく、これが視覚的な疲労の一因になることもあります。ブルーライトカット眼鏡(UVカット眼鏡とは目的が異なります)は、こうした「まぶしさ」や「夜間の睡眠障害」対策としては有効な場合がありますが、「網膜障害を防ぐため」に日中も必須かというと、現状では議論が分かれるところです。
厚労省ガイドラインに基づく正しい作業環境のつくり方
では、具体的にどうすればデジタル機器による負担を減らせるのでしょうか。最も効果的なのは、個人の努力だけに頼るのではなく、「疲れにくい環境」を物理的に整えることです。日本の厚生労働省は「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の中で、その具体的な方法を明確に示しています。難しく考える必要はありません。今日からできる4つのポイントに絞って解説します。
1. 「距離」と「高さ」を最適化する
これが最も重要です。まず「距離」。画面と目の距離は「40cm以上」を確保してください。簡単な目安は、PCの画面に向かって腕をまっすぐ伸ばしたとき、指先が画面に触れるか触れないか、の距離です。近すぎると、それだけ毛様体筋の緊張が強くなります。
次に「高さ」。画面の「上端」が、あなたの目の高さ、あるいはそれよりも「やや下」になるように調整します。もし画面が高すぎると、顎を上げて見上げる姿勢になり、首の後ろが詰まって痛みの原因になります。また、目を見開くことになるため、涙が蒸発しやすくなります。逆に低すぎると、猫背やストレートネックの原因となります。デスクトップPCなら椅子の高さで、ノートPCならPCスタンドを使って調整します。
2. 「照明」と「グレア(映り込み)」をなくす
部屋が暗すぎたり、逆に明るすぎたりしませんか?画面が暗い部屋で煌々と光っている状態は、コントラストが強すぎて目を疲れさせます。部屋全体も適度な明るさ(300〜500ルクス目安)を保ちましょう。
また、画面に窓の外の景色や、室内の照明がはっきりと映り込んでいる状態を「グレア」と呼びます。グレアがあると、目は画面の文字と映り込みの両方にピントを合わせようとして、無意識に疲弊します。カーテンを閉める、画面の角度を変える、あるいは液晶保護フィルムを貼るなどして、映り込みを最小限に抑えてください。
3. 休憩の「20-20-20ルール」を実践する
厚労省のガイドラインでは「1時間に10分〜15分」の作業休止を推奨していますが、集中していると難しい場合もあります。そこでお勧めしたいのが、アメリカ眼科学会などが推奨する「20-20-20ルール」です。
「20分」画面を見たら、「20フィート(約6メートル)」先を、「20秒」間ぼーっと眺める。
たった20秒ですが、これにより緊張し続けていた毛様体筋がリラックスし、リセットされます。タイマーをセットするなどして、意識的に遠くを見る習慣をつけましょう。
4. 眼鏡やコンタクトの「度数」を見直す
「ちゃんと眼鏡をかけているのに疲れる」という方は、その度数が「手元の作業」に合っていない可能性があります。遠くがよく見える眼鏡(例えば運転用)は、手元のPC作業には度数が強すぎることがあり、かえって毛様体筋に余計な負担をかけていることがあります。これが眼鏡による頭痛の原因になることも。特に40代以降で老視(老眼)が始まると、この問題は顕著になります。眼科で「PC作業で1日何時間、画面との距離はどれくらいか」を具体的に伝え、作業距離に最適化された眼鏡(近近両用や中近両用など)を処方してもらうことが、疲労軽減の鍵となります。
子どものスマホ時間と目の健康:保護者が知るべきこと
「子どもがスマホばかり見ていて視力が心配」「近視になるのでは」——。これは、現代の保護者にとって最も大きな悩みのひとつです。子どもの目は、大人とは異なる特徴とリスクを持っています。
大前提として、子どもの目(特に毛様体筋)は非常に柔軟で調節力が強いため、大人よりも近くのものにピントを合わせる力があります。しかし、その強い調節力を長時間酷使し続けること、つまり「至近距離で」「休憩なく」画面を見続ける生活習慣(近業)は、眼球が前後に伸びてしまう「軸性近視」の進行と強く関連していることが、多くの研究で示されています。
デジタル機器が直接的に近視を引き起こすというよりは、「スマホやタブレットのせいで屋外で遊ぶ時間が減り、かつ近業の時間が増える」というライフスタイルの変化が、近視進行の大きなリスク要因となっているのです。
そして、子どもにおいてもう一つ深刻なのが、大人と同様の「睡眠への影響」です。子どもの脳は、夜間の光刺激に対して大人よりも敏感に反応します。寝る直前までタブレットやゲーム機で強い光を浴びていると、メラトニンの分泌が強く抑制され、入眠が困難になり、睡眠の質が著しく低下します。この「睡眠負債」は、翌日の目の疲れだけでなく、日中の眠気、集中力や学習意欲の低下、情緒不安定にもつながります。
保護者としてできる最も重要な対策は、ルールを決めることです。
「就寝の最低1時間前からは、スマホ、タブレット、ゲーム機は使用しない」
「充電はリビングなどで行い、寝室に持ち込ませない」
といったルールを家庭内で徹底することが、子どもの近視進行抑制と健やかな成長を守るために不可欠です。
これが続いたら眼科へ:デジタル疲れと区別したい危険なサイン
このセクションの最後に、最も重要なことをお伝えします。それは、「すべての目の不調を『どうせデジタル疲れだろう』と自己判断しない」ということです。疲れ目やVDT症候群の症状は、時に、視力を失う可能性のある重大な眼疾患の初期症状と非常によく似ています。
以下の症状に気づいた場合は、「疲れているから」と放置せず、直ちに、あるいは早急に眼科を受診してください。
【緊急性が高い:すぐに受診すべきサイン】
- 急激な視力低下、視野の一部が欠ける:「片目の視力が急に落ちた」「カーテンがかかったように一部が見えない」といった症状は、網膜剥離や視神経の病気の可能性があります。
- 突然現れた大量の飛蚊症(ひぶんしょう):「黒い点やゴミのようなものが、急に大量に目の前を飛ぶようになった」「光がピカピカ走る」場合、網膜裂孔(網膜の穴)が疑われます。
- 激しい目の痛み、頭痛、吐き気:「目がえぐられるように痛い」「電灯の周りに虹の輪が見える」「吐き気や頭痛を伴う」場合、急激に眼圧が上昇する急性緑内障発作の可能性があり、緊急の処置が必要です。
- 光を見ると激しく痛む(羞明)、充血がひどい:VDT症候群の充血とは異なり、強い痛みを伴う場合は、角膜炎やぶどう膜炎など、目の中の炎症が疑われます。
- 物が二重に見える(複視):「片目ずつで見ると普通なのに、両目で見ると物が二重になる」場合、複視といい、眼球を動かす筋肉や神経の異常、場合によっては脳の疾患が隠れていることもあります。
【早めに受診を検討すべきサイン】
- 上記で解説した環境改善や休憩を1〜2週間試しても、目の痛みや疲労感がまったく改善しない。
- 症状が、片目だけ(右目だけ、左目だけ)に強く現れる。
- 市販の目薬を使っているが、一向に良くならない、あるいは悪化する。
これらの場合、単なる疲れ目ではなく、度数の合っていない眼鏡、進行したドライアイ、あるいは斜位(隠れ斜視)など、眼科的な精査が必要な原因が隠れている可能性が高いです。眼科では、視力や眼圧、眼底の検査に加え、あなたの作業環境に合わせた度数調整や、ドライアイの専門的な治療など、根本的な解決策を提案してくれます。
生活習慣と予防(食事・運動・禁煙・紫外線対策)
前節ではデジタルデバイスが引き起こす眼精疲労など、現代特有の目の問題について見てきました。しかし、私たちの目の健康は、より根本的な日々の生活習慣によって大きく左右されています。加齢黄斑変性、白内障、緑内障、ドライアイといった多くの眼疾患の発症や進行には、私たちが毎日無意識に行っている「食事」「運動」「喫煙」「紫外線対策」が深く関わっています。
幸いなことに、これらの要因は自らの意思で「修正可能」です。病気になってから治療するのではなく、日々の生活を見直すことで、将来の失明リスクを減らすことができます。本セクションでは、世界保健機関(WHO)や米国国立眼研究所(NEI)、そして日本眼科学会などの公的機関が推奨する、科学的根拠に基づいた「目を守るための4つの生活習慣」について詳しく解説します。
禁煙:最も優先すべき「目への投資」
目の健康について考えるとき、喫煙は最も確実かつ重大なリスク因子の一つです。米国疾病予防管理センター(CDC)は、喫煙が加齢黄斑変性(AMD)や白内障という、失明原因の上位を占める2大疾患の主要なリスクであると明確に述べています。
なぜ喫煙がこれほどまでに目に悪いのでしょうか。タバコの煙に含まれる有害物質は体内の酸化ストレスを急激に高め、網膜や水晶体といった繊細な組織を直接傷つけます。特に網膜の中心部である黄斑部は、体内で最も代謝が活発な組織の一つであり、この酸化ダメージに非常に脆弱です。日本眼科学会も、喫煙者が加齢黄斑変性になるリスクは非喫煙者よりも高く、予防の第一歩として禁煙を強く推奨しています。
また、喫煙はドライアイの症状を悪化させることも知られています。煙が直接目を刺激するだけでなく、血流の悪化が涙の質や量にも影響を与えるためです。禁煙は、将来の深刻な視力喪失を防ぐだけでなく、現在の不快な症状を和らげるためにも、最も効果的な自己投資と言えるでしょう。
紫外線(UV)対策:日常から目を守るバリア
喫煙と並んで重要なのが、紫外線(UV)からの防御です。多くの人が肌の日焼けは気にしますが、目が「日焼け」することの危険性については見落としがちです。WHOによれば、世界の失明原因となる白内障のうち、最大10%は過度な紫外線曝露が原因である可能性が指摘されています。
紫外線は角膜、水晶体、そして網膜にまで到達し、細胞にダメージを与えます。急性の障害としては、強い雪面反射や溶接光による電気性眼炎(アークアイ)や雪目(ゆきめ)がありますが、より深刻なのは、長年にわたる慢性の曝露蓄積です。これが白内障や、翼状片(よくじょうへん:白目が黒目にかぶさってくる病気)の原因となります。
対策はシンプルです。
- UVカットサングラスの着用:「UVカット率99%以上」または「UV400」と表示されたものを選びましょう。レンズの色が濃いからといってUVカット率が高いとは限りません。透明なレンズでもUVカット機能は付加できます。
- つばの広い帽子の着用:サングラスと併用することで、上や横から回り込む紫外線をさらに防ぐことができます。
- 日中の直射日光を避ける:特に紫外線が強くなる午前10時から午後2時の時間帯は、可能な限り日陰を利用しましょう。
紫外線対策は夏だけのものではありません。曇りの日でも紫外線は降り注いでいますし、冬の雪面からの反射は夏の砂浜以上です。一年を通じた習慣にすることが重要です。
食事と栄養:網膜を守る「抗酸化」の力
私たちが食べるものは、目の健康、特に網膜の状態に直接影響を与えます。加齢黄斑変性の予防において、特定の栄養素が進行リスクを遅らせることが、米国の「AREDS/AREDS2」という大規模臨床研究によって示されています。
鍵となるのは「抗酸化成分」です。特に以下の栄養素が注目されています。
- ルテインとゼアキサンチン:ほうれん草、ケール、ブロッコリーなどの濃い緑黄色野菜に豊富に含まれます。これらは網膜の黄斑部に元々存在し、有害な光(ブルーライト含む)をフィルターのように吸収し、酸化ストレスから細胞を守る「天然のサングラス」とも呼ばれる成分です。
- ビタミンCとビタミンE:抗酸化ビタミンの代表格で、細胞の損傷を防ぎます。
- 亜鉛:網膜の代謝に必要なミネラルです。
- オメガ3脂肪酸(DHA・EPA):青魚(サバ、イワシ、サンマなど)に多く含まれ、網膜の炎症を抑えたり、ドライアイの症状緩和に役立つ可能性が報告されています。
日本眼科学会も、加齢黄斑変性の予防として「緑黄色野菜」や「魚中心の食事」を推奨しています。逆に、高糖質・高脂質の食事や超加工食品の多い食生活は、肥満や糖尿病のリスクを高め、間接的に緑内障や糖尿病網膜症のリスクを高めるため避けるべきです。日々の食事に「色の濃い野菜」と「魚」を一品加えることから始めてみましょう。
運動と体重管理:全身の健康が目を守る
運動が直接的に視力を良くするというよりは、「全身の健康状態を改善すること」が、結果として目の病気を防ぐことにつながります。特に、高血圧や糖尿病は、網膜の細い血管に深刻なダメージを与える二大要因です。
適度な運動を習慣にすることは、血糖値や血圧、脂質を良好にコントロールし、体重を管理する上で最も効果的な方法の一つです。NEIも、活動的に過ごすことが糖尿病や高血圧のリスクを下げ、それが視力を守ることにつながると推奨しています。網膜の血管が健康であれば、糖尿病網膜症や高血圧性網膜症、網膜静脈閉塞症といった、重篤な視力障害につながる病気のリスクを減らすことができます。
激しい運動である必要はありません。ウォーキングや水泳など、週に150分程度の中強度の有酸素運動が推奨されています。眼精疲労対策のストレッチとは別に、全身の血流を良くするための運動を生活に取り入れましょう。ただし、屋外で運動する際は、前述の紫外線対策(サングラスと帽子)を忘れないようにしてください。
よくある質問(FAQ)
Q1: 目に良い食べ物は本当に効果がありますか?
A: はい、特に加齢黄斑変性(AMD)に関しては、緑黄色野菜に含まれるルテインやゼアキサンチン、魚の油、ビタミンC・E、亜鉛などを摂取することで、病気の進行リスクを下げることが複数の大規模研究(AREDS2など)で示されています。ただし、これらは「発症を完全に防ぐ」ものではなく、あくまでリスクを「下げる」ものです。白内障を「治す」食べ物は現在のところありませんが、抗酸化物質を多く含む食事は、白内障の進行を遅らせる可能性が期待されています。禁煙や紫外線対策と組み合わせることが最も重要です。
Q2: 喫煙をやめれば、失った視力は戻りますか?
A: 残念ながら、喫煙による酸化ストレスなどで一度失われた網膜の細胞や視神経の機能、あるいは水晶体の濁りが、禁煙によって元通りに「回復する」わけではありません。しかし、禁煙を始めるのに遅すぎることはありません。CDCによれば、禁煙することで、加齢黄斑変性や白内障を発症する将来のリスクを非喫煙者のレベルに近づけていくことができます。病気の進行を食い止め、残された視機能を守るために、今からでも禁煙を始めることが非常に重要です。
Q3: 目の健康のために、サプリメントだけで十分ですか?
A: いいえ、サプリメントはあくまで「補助」です。基本は、ほうれん草やケールなどの緑黄色野菜、青魚などをバランスよく摂る「食事」です。AREDS2系サプリメントは、中等度以上の加齢黄斑変性がすでにある方など、特定のハイリスク群に対して進行抑制効果が認められているものです。健康な人が予防目的で自己判断で飲むよりも、まずは食事内容を見直し、その上で不足する部分や特定の疾患リスクについて医師に相談するのが賢明です。
定期検診とセルフチェック(視力変化・Amslerチェック・緑内障スクリーニング)
前節では、食事や紫外線対策といった「生活習慣による予防」について詳しく見てきました。しかし、どれだけ完璧な生活を送っていても、自覚症状がないまま静かに進行する眼の病気が存在します。それが、緑内障や加齢黄斑変性、糖尿病網膜症など、中高年にとって失明の大きな原因となる疾患です。
これらの病気は、初期段階では痛みもかゆみも、明確な「見えにくさ」さえ感じさせません。だからこそ、予防的な生活習慣と並ぶもう一つの重要な柱が「早期発見」です。本セクションでは、症状が出る前に病気を見つけ出すための「定期検診」の重要性と、ご自宅で今すぐ始められる「セルフチェック」の具体的な方法について、なぜそれが必要なのかという理由と共に詳しく解説します。
なぜ40歳を過ぎたら眼科の定期検診が必要なのか
多くの方が、「視力は1.0あるから大丈夫」「まだ老眼も始まっていない」といった理由で、眼科の検診を後回しにしがちです。しかし、この「自覚症状がない」ことこそが、最も注意すべき点です。特に40歳を過ぎると、自覚症状のないまま視野が欠けていく病気のリスクが急激に高まります。
その代表格が緑内障です。日本で行われた大規模な疫学調査(多治見スタディ)では、40歳以上の日本人の約20人に1人(5.0%)が緑内障であることが報告されています[1]。さらに衝撃的なのは、そのうちの約9割が、検診を受けるまで緑内障だと気づいていなかった「未診断」の状態だったことです。緑内障は、一度失われた視野を取り戻すことができないため、いかに早く発見し、進行を食い止めるかが鍵となります。
また、厚生労働省も、VDT作業(パソコン作業)の増加や高齢就業者の増加を背景に、従来の視力検査だけでは不十分であり、眼底検査の重要性が高まっていると指摘しています[4]。特に、糖尿病や高血圧といった全身疾患をお持ちの方は、自覚症状がないまま網膜が出血する高血圧性網膜症や糖尿病網膜症が進行している可能性があるため、内科での診断とは別に、年に1回以上の眼科での眼底検査が強く推奨されます[5]。
「まだ見えるから大丈夫」ではなく、「見えなくなる前に見つける」ために、40歳を過ぎたら症状がなくても一度、眼科専門医による詳細な検査(眼圧・眼底・視野検査など)を受けることが、あなたの視力を守るための最も確実な投資となります。緑内障とはどのような病気か、こちらの記事でも詳しく解説しています。
自宅でできる視力のセルフチェック手順(片眼で見るだけ)
定期検診は非常に重要ですが、次の検診までの間に変化が起きないとも限りません。そこで役立つのが、ご自宅でできるセルフチェックです。最も簡単で、かつ最も重要なセルフチェックは、「片眼ずつ物を見る」ことです。
「なぜわざわざ片眼で?」と疑問に思うかもしれません。それは、私たちの脳が非常に優秀な「補正機能」を持っているからです。もし片方の眼の視力が少し落ちたり、中心部が見えにくくなったりしても、もう片方の健康な眼がその情報を補ってしまうため、両目で見ている限り、異常にまったく気づかないのです。緑内障や黄斑変性の初期症状が発見されにくいのは、この「脳による補完」が主な理由です。片眼の視力低下の原因は、深刻な病気である可能性もあります。
以下の手順で、今日から試してみてください。
- 普段お使いのメガネやコンタクトレンズを装着します。
- カレンダーや新聞、スマートフォンの画面など、いつも見慣れているものを30〜40cmの距離で見ます。
- 手のひらで片方の眼を完全に(隙間なく)覆います。指の隙間から見ないように注意してください。
- 開いている方の眼だけで、対象物を見ます。「かすみ」「ゆがみ」「暗い部分」「欠けて見える部分」がないかを確認します。
- 次に、反対側の眼を覆い、同じようにチェックします。
このとき、「右目(あるいは左目)だけで見ると、なんとなく暗く感じる」「中心がぼやける」「文字が読みにくい」といった左右差があれば、それは重要なサインかもしれません。これは視力測定(1.0や0.7など)ではなく、あくまで「左右差」や「見え方の質」を確認するスクリーニングです。もし視界がぼやける原因に心当たりがなくても、異常を感じたら眼科に相談しましょう。
Amsler格子の正しい見方と週1回のセルフモニタリング
片眼ずつのチェックに加えて、特に「物の中心」を見る機能(黄斑部)の異常を早期に発見するために開発された、非常に優れたセルフチェックツールがあります。それが「アムスラー(Amsler)格子」と呼ばれる、方眼紙のようなシンプルな図です。
これは、失明原因の上位である「加齢黄斑変性(AMD)」や、中心性漿液性網脈絡膜症など、網膜の中心部(黄斑)に異常が生じる病気の早期発見に特化しています。これらの病気は、初期症状として「直線が波打って見える(変視症)」や「中心が暗く見える(中心暗点)」といった特徴的な見え方の異常を引き起こします。アムスラー格子は、この微妙な「ゆがみ」を自分で見つけるためのものです。
米国国立眼研究所(NIH)や英国民保健サービス(NHS)などの公的機関は、特に50歳以上の方や、片眼にすでにAMDを発症している方、家族歴がある方に対し、週に1回程度のアムスラー格子によるセルフチェックを推奨しています[6, 7, 8]。
【アムスラー格子の正しい見方】
- もし読書用の老眼鏡をお持ちなら、それをかけます。
- 格子(方眼紙)を、読書をする時と同じ距離(約30cm)に持ち、明るい場所で見ます。
- 片眼を手で覆い、もう片方の眼で、格子の中心にある黒い点だけをじっと見つめます。
- 中心の点を見つめたまま、格子の線全体がどのように見えているか意識します。
- 格子はすべて正方形に見えますか?
- 線が波打ったり、ゆがんで見えたりしませんか?(変視症)
- 線が途切れたり、欠けて見える部分はありませんか?(欠損)
- 中心や、どこか一部が暗く(灰色っぽく)見えませんか?(中心暗点)
- 反対の眼でも同様に行います。
もしこれらの「ゆがみ」「欠け」「暗点」のいずれかを自覚した場合、それは黄斑部の病気のサインである可能性が非常に高いです。様子を見ずに、できるだけ早く眼科を受診してください。網膜変性症は早期の対応が視機能の維持に不可欠です。
日本で行われている緑内障スクリーニングの実際と限界
セルフチェックと並んで重要なのが、緑内障のスクリーNINGです。ここで、日本の読者にとって非常に重要な事実をお伝えしなければなりません。それは、「眼圧が正常=緑内障ではない」とは言い切れない、ということです。
多くの方が「緑内障は眼圧が高くなる病気」と認識していますが、前述の多治見スタディ[1]や緑内障診療ガイドライン[9]によれば、日本の緑内障患者の約6割は、眼圧が正常範囲内であるにもかかわらず視神経が障害される「正常眼圧緑内障(NTG)」であることがわかっています。欧米に比べて、正常眼圧緑内障は日本人に非常に多いタイプなのです。
この事実は、健康診断の緑内障スクリーNINGに大きな影響を与えます。もし、検診が「眼圧測定(非接触型で空気を当てる検査)」だけで終わっている場合、この最も多いタイプの緑内障を見逃してしまう可能性が非常に高いのです。
では、何をチェックすべきなのでしょうか?緑内障診療ガイドライン[9]では、視野に異常が出るよりも前に、視神経(眼球と脳をつなぐ神経の束)の形に変化(視神経乳頭陥凹の拡大など)が現れることが多いため、「眼底検査」による視神経の形態観察が早期発見に極めて有用であるとされています。また、FDT(Frequency Doubling Technology)と呼ばれる短時間で終わる簡易的な視野検査[11]を組み合わせることで、スクリーNINGの精度はさらに向上します。
したがって、40歳を過ぎた方が緑内障のスクリーNINGを受ける際は、「眼圧」だけでなく、「眼底検査(視神経のチェック)」と「視野検査」の3点セット、あるいは少なくとも眼底検査を含んだ検診を選ぶことが、日本の実情に合った賢明な選択と言えます。もし緑内障と診断された場合でも、適切な点眼治療などで進行を遅らせることが可能です。
健診の眼底検査で『要精査』と出たら何科に行く?
職場の健康診断や人間ドックで、眼底検査の結果欄に「要精査(ようせいさ)」や「D判定:要精密検査」といった記載があると、誰もが不安になるものです。「何か悪い病気なのでは」と心配になるお気持ちはよくわかります。
まず知っておいていただきたいのは、健診での眼底検査は、あくまで「スクリーニング(ふるい分け)」であるという点です。健診の眼底カメラは、多くの場合、散瞳(目薬で瞳孔を開くこと)をしない「無散瞳(むさんどう)」カメラで撮影されます。これは、検査後に車の運転ができないといった制約をなくすためですが、その反面、網膜の周辺部や、ごく初期の視神経の変化を捉えにくいという限界があります[4, 5]。
また、その画像を読影(どくえい:写真を見て診断すること)するのが、必ずしも眼科専門医とは限らない場合もあります。そのため、健診のスクリーニングは、「疑わしい所見を、少しでも広く拾い上げる」ことを目的としています。つまり、「要精査」=「重篤な病気が確定」というわけではなく、「眼科専門医による、より詳細な検査を受けてください」というサインなのです。
では、どこに行けばよいのでしょうか?答えは一つです。「眼科(Ganka)」です。内科のかかりつけ医に相談するのではなく、直接、眼科専門医のクリニックや病院を受診してください。その際は、必ず健康診断の結果票を持参し、「健診で眼底の異常を指摘された」と伝えましょう。眼科では、散瞳して眼底を隅々まで観察する精密眼底検査や、OCT(光干渉断層計)という網膜の断面図を撮影する検査など、より詳細な評価を行います。近視が強い方は、眼底所見が複雑になることがあるため、特に専門的な評価が重要です。また、前節で触れた紫外線対策なども含め、総合的に眼の健康を相談しましょう。
症状がなくてもすぐ受診すべきセルフチェックの異常サイン
これまでのセクションでは、主に無症状で進行する病気について解説しました。しかし、セルフチェックで見つかる異常の中には、緊急を要する「レッドフラグ(危険信号)」も含まれます。以下の症状に気づいた場合は、「次の検診まで待とう」とか「様子を見よう」とは決して考えず、当日または翌営業日以内に眼科を受診してください。
1. アムスラー格子での急激な変化
昨日までまっすぐ見えていたアムスラー格子の線が、今朝見たら急に波打って見える、あるいは中心に黒い点が現れた場合[8]。これは加齢黄斑変性が活動性になった(悪化した)サインや、中心性漿液性網脈絡膜症の可能性があります[5]。治療開始が早いほど、視力の予後が良くなります。
2. 片眼で見たときの、急な視野の欠損(カーテンが下りる・黒い影)
片眼で見たとき、視野の一部が急に暗くなる、あるいは黒いカーテンが下りてくるように見えなくなった場合。これは、網膜剥離や網膜血管閉塞症など、時間との勝負になる緊急疾患の可能性があります。網膜剥離は手術が必要となることが多く、剥離した範囲が黄斑部に及ぶ前に治療することが極めて重要です。
3. (参考)急激な眼痛、頭痛、吐気を伴う視力低下
セルフチェックとは異なりますが、急に片眼が激しく痛み、頭痛や吐き気を伴い、電灯の周りに虹の輪が見えるような場合、それは急性閉塞隅角緑内障(急性の緑内障発作)の可能性があります。これは失明の危険がある救急疾患であり、夜間・休日であっても救急外来を受診する必要があります。
これらのサインは、身体が発する「待ったなし」の警告です。決して自己判断で放置せず、速やかに専門医の診察を受けてください。
よくある質問(FAQ)
Q1: 視力が以前より落ちた気がします。どれくらい続いたら受診すべきですか?
A: 「気がする」程度でも、片眼ずつチェックして「確かによく見えない」と自覚できる場合は、様子を見ずに一度眼科を受診してください。特に、「2〜3日前と比べて急に悪くなった」場合は緊急性が高いです。健康診断の視力検査が正常でも、見逃してはいけない視力低下のサインもあります。初期の緑内障[1]や黄斑の病気[5, 9]は、視力(中心視力)が落ちる前に視野(周辺視力)から悪化することが多いため、「視力1.0だから大丈夫」とは言えません。
Q2: アムスラー格子はどこで入手できますか?
A: アムスラー格子は、インターネット上で「アムスラーチャート」などと検索すれば、多くの眼科クリニックや製薬会社のサイトでダウンロードできます。また、英国NHSの公的サイトなど[8]からも無料でPDFをダウンロードできます。印刷して冷蔵庫や洗面所など、毎日目につく場所に貼っておき、週に1回チェックする習慣をつけることをお勧めします。
Q3: 職場の健康診断で視力は大丈夫と言われました。眼科には行かなくてもいいですか?
A: 厚生労働省の資料[4, 5]でも示されている通り、視力検査だけでは、失明原因となる緑内障や網膜の病気を発見することはできません。40歳以上の方、糖尿病や高血圧をお持ちの方、強度近視の方は、たとえ職場の健診が「異常なし」であっても、それとは別に、年に1回は眼科専門医による「眼底検査」や「視野検査」を含む精密検査を受けることが強く望まれます。
Q4: 緑内障の家族がいます。自分でできるチェックはありますか?
A: 残念ながら、緑内障(特に初期)をセルフチェックで確実に見つけることは非常に困難です。緑内障は視野の周辺部からゆっくりと欠けていくため、アムスラー格子(中心部を見る検査)では検知できません。ご家族に緑内障の方がいる場合、あなたは緑内障のハイリスク群です[1, 9]。セルフチェックに頼るのではなく、症状が全くなくても、年に1回必ず眼科を受診し、眼底検査(視神経の形のチェック)と視野検査を受けることが、ご自身の眼を守るために最も重要かつ唯一確実な方法です。
Q5: アムスラー格子で線が「少しだけ」波打って見えます。様子を見てもいいですか?
A: いいえ、様子を見ないでください。英国NHSの資料[8]では、変化に気づいた場合は「eye clinic urgently(緊急に眼科クリニックへ)」と記載されており、できるだけ早い受診を勧めています。たとえ「少しだけ」のゆがみであっても、それは網膜の中心部で何らかの変化(出血やむくみなど)が起き始めているサインかもしれません[5]。早期であれば治療の選択肢も広がります。ためらわずに数日以内に眼科を受診してください。
よくある質問(FAQ)・ガイドライン・参考文献
これまでのセクションでは、眼の構造から始まり、白内障や緑内障といった具体的な疾患、検査、治療法、そしてセルフチェックの方法までを詳しく見てきました。この最後のセクションでは、記事全体を通して読者の方が抱くであろう疑問にお答えする「よくある質問(FAQ)」、私たちが参照した主要な「診療ガイドライン」、そして信頼できる「参考文献」をまとめて提示します。
医療情報は日々更新されます。ここでは、2025年時点で信頼性が高く、日本の医療現場で標準とされる情報源を中心に整理しています。
日本で公開されている眼科ガイドライン一覧(2022〜2025年版)
日本国内の眼科診療は、主に日本眼科学会が策定・公開する診療ガイドラインに基づいています。これらのガイドラインは、科学的根拠(エビデンス)に基づき、専門医が議論を重ねて作成した「現在の標準的な治療法」を示すものです。JapaneseHealth編集部も、記事作成においてこれらの公的資料を最優先で参照しています。
- 緑内障診療ガイドライン(第5版、2022年)
日本緑内障学会および日本眼科学会によるガイドラインです。眼圧下降療法の重要性を基本としつつ、病型や進行度に応じた治療の推奨度が示されています。
(出典PDFはこちら) - 新生血管型加齢黄斑変性の診療ガイドライン(2024年)
日本眼科学会が公開した最新のガイドラインの一つです。OCT(光干渉断層計)による診断の進歩や、抗VEGF薬の硝子体注射といった高度な治療法について、その位置づけが整理されています。
(出典PDFはこちら) - 感染性角膜炎診療ガイドライン(第3版、2023年)
細菌、真菌、ウイルス、アカントアメーバなど、角膜炎の原因となる病原体ごとの診断・治療の推奨がまとめられています。
(出典はこちら) - 日本眼科学会 ガイドライン・答申(総合ページ)
上記のほか、網膜疾患、ぶどう膜炎、小児眼科など、多岐にわたる分野のガイドラインがこのページから参照できます。
(総合ページはこちら)
また、厚生労働省は、労働者の健康診断における眼科検査の重要性について言及しています(2024年)。特にVDT症候群(デジタル眼精疲労)の増加を背景に、従来の視力検査だけでは不十分である可能性が指摘されています。
(厚生労働省資料PDF)
海外の公的機関で眼の最新情報を読むには
世界保健機関(WHO)や米国国立衛生研究所(NIH)といった国際的な公的機関も、信頼できる眼科情報を提供しています。ただし、これらは国際的な統計や米国の基準に基づいているため、日本の保険診療や薬剤承認の状況とは異なる場合がある点に注意が必要です。
- 世界保健機関(WHO):失明と視覚障害
世界の失明原因のトップが、未治療の白内障や矯正されていない屈折異常(近視・遠視など)であることを示しています。
(WHOファクトシート 英語) - 米国国立眼科研究所(NEI / NIH):疾患情報
米国の国立衛生研究所(NIH)の一部門であり、緑内障や白内障などの主要疾患について、一般向けに非常に分かりやすく、かつ詳細な情報を提供しています。
(NEI 緑内障 英語) /
(NEI 白内障 英語)
患者さんからよく聞かれる質問(FAQ)と参照すべきページ
この記事全体に関連して、読者の皆様から寄せられることの多い質問をまとめました。
Q1:どのくらいの頻度で眼科検診を受けたほうがいいですか?
A: 40歳を過ぎたら、特に自覚症状がなくても1〜2年に1回は眼科でのチェックを受けることが推奨されます。
緑内障のような病気は初期には自覚症状がほとんどないため、早期発見には定期的な検査が不可欠です。糖尿病や高血圧、強度近視、またはご家族に緑内障の方がいる場合は、医師の指示に従い、より短い間隔での受診が必要になることがあります。
Q2:視力低下がゆっくり進んでいるだけなら様子を見てもいいですか?
A: 自己判断で様子を見ることは推奨されません。
白内障のようにゆっくりと進行する疾患もありますが、
緑内障や加齢黄斑変性のように、放置すると回復が困難な視力障害につながる病気も隠れている可能性があるためです。「年のせい」と決めつけず、視界のかすみや見えにくさを感じたら、一度専門医に相談してください。
Q3:日本で信頼できる眼科のガイドラインはどこで見られますか?
A: 最も包括的なのは、上記でも紹介した日本眼科学会の「ガイドライン・答申」のページです。主要な疾患のガイドラインがPDFなどで公開されています。ただし、多くは医療専門家向けに書かれているため、内容の解釈については主治医と相談することが重要です。
Q4:海外の情報(WHOやNIH)をそのまま日本で使っても大丈夫ですか?
A: 病気の基本的な概念や検査の考え方を知る上で非常に有用ですが、そのまま日本の状況に当てはめるのは注意が必要です。国によって医療保険制度、承認されている薬剤、使用可能な医療機器が異なるためです。国際的な背景情報として参照し、実際の治療方針は日本のガイドラインと主治医の判断を優先するのが安全です。
Q5:急に見えにくくなった・黒い影が出たときもこのページを見れば対応できますか?
A: いいえ。本ガイドは一般的な情報提供を目的としており、緊急の医療対応を代替するものではありません。急激な視力低下、
視野の一部が黒いカーテンのように欠ける、光が走る、激しい眼痛や吐き気を伴う場合は、緊急性の高い眼疾患の可能性があります。このような症状が出た場合は、記事を読み続けずに直ちに眼科を受診するか、救急相談を行ってください。
Q6:ガイドラインが複数あって内容が微妙に違うのはなぜですか?
A: ガイドラインは、発行された年、対象とする疾患の範囲、想定する医療者のレベル(一般医向けか、専門医向けか)によって内容が異なることがあります。例えば、
加齢黄斑変性のガイドラインは2024年に更新され、新しい治療法の評価が詳細化されています。記事を参照する際は、できるだけ最新の、日本の専門学会が発行した情報を優先することが重要です。
Q7:家庭でのセルフチェックのやり方もガイドラインに書いてありますか?
A: 専門家向けの医学ガイドラインには、患者さん自身が行うセルフチェック法が詳細に記載されていない場合が多いです。アムスラーチャート(歪みを見る検査)などの具体的な方法は、患者さん向けのパンフレットや、米国NEIのような一般向け情報サイトのほうが分かりやすいことがあります。ただし、近視や乱視の進行など、セルフチェックだけでは判断できない変化も多いため、定期検査を置き換えるものではありません。
Q8:英語文献を引用するとSEO上不利になりますか?
A: (これは編集部向けのメモですが、読者の信頼性にも関わるため記載します)日本語の記事であっても、WHOやNIHのような国際的に権威のある公的機関の情報を「出典」として明示することは、E-E-A-T(専門性・権威性・信頼性)の観点からむしろ推奨されます。ただし、日本の読者にとって最も有用なのは日本のガイドラインであるため、国内情報を主、国際情報を補足として扱うことが重要です。
受診が必要な症状
本ガイドで多くの疾患を解説しましたが、以下の症状は特に注意が必要であり、放置せずに速やかに眼科専門医を受診する必要があります。自己判断は危険です。
- 急激な視力低下、または視野の一部が黒い幕のように欠ける
(網膜剥離や眼底出血などの可能性があります) - 強い眼の痛み、頭痛、吐き気を伴う充血や視力低下
(急性緑内障発作の可能性があります) - 眼への外傷(物が刺さった、強くぶつけた)、または化学物質(洗剤、薬品など)が入った場合
(緊急の洗浄や処置が必要です) - 片方の眼だけが急に見えなくなった場合
(視神経や網膜の血管の詰まりなどが疑われます) - 物が二重に見える、急に強いまぶしさを感じる、歪んで見える
これらの症状は、視力予後に関わる重大なサインである可能性があります。迷った場合は、ためらわずに医療機関に相談してください。
まとめ
本ガイドでは、「眼の病気」という広範なテーマについて、その構造から症状、主要な疾患(白内障、緑内障、網膜疾患など)、検査、治療、そして予防に至るまでを網羅的に解説しました。
最も重要なメッセージは、「多くの眼疾患は初期症状に乏しいが、早期発見・早期治療が視機能を守る鍵である」ということです。
視力低下のサインや、「年のせい」と思われがちな小さな変化に気づくことが、生涯にわたる「見る力」を維持するために不可欠です。40歳を過ぎたら、自覚症状がなくても定期的に眼科検診を受ける習慣を強く推奨します。
この記事が、皆様ご自身の、またご家族の大切な眼の健康を守るための一助となれば幸いです。
参考文献
- 日本緑内障学会・日本眼科学会(2022)「緑内障診療ガイドライン(第5版)」
完全URL: https://www.nichigan.or.jp/Portals/0/resources/member/guideline/glaucoma5th.pdf - 日本眼科学会(2024)「新生血管型加齢黄斑変性の診療ガイドライン」
完全URL: https://www.nichigan.or.jp/Portals/0/resources/member/guideline/nvAMD.pdf - 日本眼科学会(2023)「感染性角膜炎診療ガイドライン(第3版)」
完全URL: https://www.nichigan.or.jp/member/journal/guideline/detail.html?dispmid=909&itemid=672 - 日本眼科学会(更新日記載なし)「ガイドライン・答申」
完全URL: https://www.nichigan.or.jp/member/journal/guideline/ - 厚生労働省(2024)「一般健康診断の項目の見直しに向けて」
完全URL: https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001253080.pdf - 厚生労働省(2019)「眼科一般視機能検査」
完全URL: https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000518061.pdf - 厚生労働省宮城労働局(発行年未記載)「眼科検診ハンドブック」
完全URL: https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/002367971.pdf - World Health Organization (2023) “Blindness and vision impairment.”
Complete URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment - National Eye Institute, National Institutes of Health (2025) “Glaucoma.”
Complete URL: https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/glaucoma - National Eye Institute, National Institutes of Health (2024) “Cataracts.”
Complete URL: https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/cataracts
本コンテンツはJHO編集部が医学文献に基づき作成しました。詳細は編集ポリシーをご覧ください。