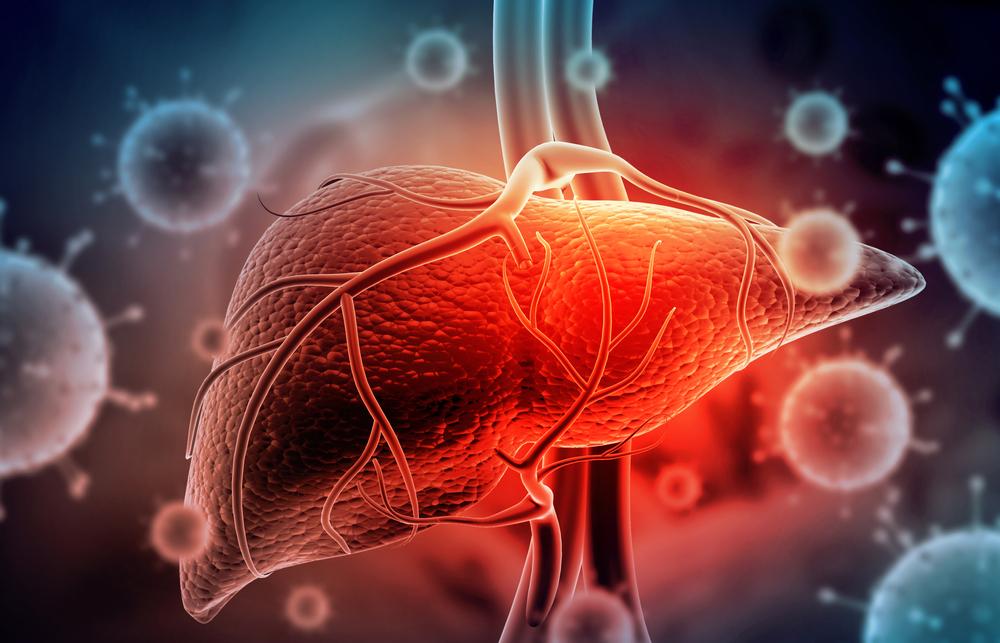消化器疾患とは(臓器と主症状の総論)
「胃が痛い」「お腹を下した」「胸やけがする」——こうした不快な症状は、誰もが一度は経験する身近なものです。しかし、これらが「消化器疾患」のサインであると聞くと、多くの人が漠然とした不安を感じるかもしれません。「消化器」とは具体的にどの臓器を指すのか、どのような仕組みで不調が起こるのか、不安や疑問は尽きないでしょう。
消化器系は、私たちが生きていくために不可欠な「栄養の摂取・消化・吸収・排泄」を担う、巨大で精密なシステムです。それは単なる「胃」や「腸」だけではなく、口から始まり肛門に至るまでの長い管(消化管)と、それを助けるサポート役の臓器(肝臓、胆嚢、膵臓)が連携して働いています。
このセクションでは、消化器疾患という広範なテーマを理解するための「地図」として、まず消化器系全体の構造と各臓器の役割を解説し、その後、どのような症状(SOSサイン)がどの臓器の問題を示唆するのか、その全体像(総論)を詳しく見ていきます。
本記事は医療情報の提供を目的としており、個別の診断や治療に代わるものではありません。ご自身の症状について不安がある場合は、自己判断せず、必ず医療機関を受診してください。
消化器はどの臓器から成る?——消化管+肝・胆・膵の役割
消化器系は、大きく二つのグループに分けられます。食べ物の通り道である「消化管」と、消化を助ける「肝臓・胆嚢・膵臓」です。これらがオーケストラのように連携し、複雑な消化・吸収プロセスを実行しています。
1. 食べ物の通り道「消化管」
消化管は、口から肛門まで続く一本の長い「管」であり、場所によって異なる役割を担っています。
- 食道:口から入った食べ物を胃へと運ぶ通路です。
- 胃:強力な胃酸と消化酵素で食べ物をドロドロに溶かし、殺菌します。食べ物を一時的に貯蔵する役割も持ちます。胃の詳しい機能や位置については、こちらの記事で解説しています。
- 小腸(十二指腸・空腸・回腸):全長6〜7メートルにも及ぶ主要な消化・吸収の場です。ここで膵液や胆汁と混ざり合い、栄養素が細かく分解・吸収されます。
- 大腸(盲腸・結腸・直腸):小腸で吸収されなかったものから水分を吸収し、便を形成します。また、膨大な数の腸内細菌が棲んでおり、免疫機能にも深く関わっています。
- 肛門:便を体外へ排出する出口です。
この一連の流れは、米国国立糖尿病・消化器・腎臓病研究所(NIDDK)も解説するように、自律神経によって精密に制御されています。
2. 消化を助ける「肝臓・胆嚢・膵臓」
消化管の外側にありながら、消化・吸収に不可欠な物質を供給する臓器です。
- 肝臓:体内で最大の臓器であり、「人体の化学工場」とも呼ばれます。栄養素の代謝、有害物質の解毒、そして脂肪の消化に必要な「胆汁」の生成など、500以上の機能を担っています。症状が出にくい「沈黙の臓器」としても知られています。肝臓の重要性については、こちらをご覧ください。
- 胆嚢・胆道:胆嚢は、肝臓で作られた胆汁を一時的に貯蔵し、濃縮する袋状の臓器です。食事をすると収縮し、胆道(胆管)を通じて胆汁を十二指腸に送り出します。
- 膵臓:食べ物(炭水化物、タンパク質、脂質)を分解するための強力な消化酵素(膵液)を分泌します。同時に、血糖値を調節するインスリンなどのホルモンを分泌する内分泌機能も持つ、重要な臓器です。膵臓の働きは非常に多岐にわたります。
主症状の全体像:体のSOSサインを読み解く
消化器疾患は、これらの臓器のどこかに問題が起こることで発症します。多くの場合、体は不調を「症状」というSOSサインとして私たちに伝えます。ここでは、代表的な症状と、それらがどの臓器に関連しているかを解説します。
- 腹痛(お腹の痛み):
最も一般的ですが、痛む場所によって原因が異なります。「キリキリ」「シクシク」「ズキズキ」といった痛みの性質や、食前・食後などのタイミングも重要な手がかりです。痛む場所から原因を探る方法も参考にしてください。- 上腹部(みぞおち)の痛み:胃や十二指腸の問題(胃炎、胃潰瘍、機能性ディスペプシアなど)が考えられます。
- 右上腹部の痛み:肝臓、胆嚢、胆管の問題(胆石症、胆嚢炎など)が疑われます[4]。
- 左下腹部の痛み:大腸(S状結腸など)の問題(憩室炎、便秘、過敏性腸症候群など)が考えられます。
- 胸やけ・呑酸(どんさん):
胃酸が食道へ逆流することで起こる症状です。食道の炎症(逆流性食道炎)が主な原因です。詳細は胃食道逆流症(GERD)の解説をご覧ください[1]。 - 吐き気・嘔吐:
胃腸炎などの感染症、食中毒、胃潰瘍、腸閉塞、さらには機能性ディスペプシアなど、原因は非常に多岐にわたります[2, 7, 8]。 - 下痢:
世界保健機関(WHO)は「1日に3回以上の水様便」を下痢と定義しています[16]。急性の場合は感染性胃腸炎が多く、慢性の場合は過敏性腸症候群(IBS)や炎症性腸疾患(IBD)なども考慮されます。最も注意すべきは脱水症状です。下痢の原因と対策について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。 - 便秘:
大腸の運動機能の低下や、便意を我慢することなどで起こります。多くは機能性便秘ですが、大腸がんなどが隠れている可能性もゼロではありません。便秘の包括的な知識も重要です[2, 17]。 - 血便・黒色便(下血):
これらは消化管のどこかから出血しているサインであり、**緊急性の高い症状**です。- 鮮血便(真っ赤な血):肛門(痔など)や直腸からの出血が疑われます。
- 暗赤色便(レンガ色):大腸の奥からの出血(憩室、炎症、腫瘍など)が考えられます[10, 11]。血便の原因は多岐にわたります。
- 黒色便(タール便):胃や十二指腸など、上部消化管からの出血が疑われます。血液が胃酸で酸化されて黒くなります[7]。
- 吐血(血を吐く):食道や胃からの大量出血を示唆し、英国民保健サービス(NHS)などが警告するように、直ちに医療機関を受診する必要があります[14]。
- 黄疸(おうだん):
皮膚や白目が黄色くなる症状です。これは血液中のビリルビンという色素が増えるためで、肝臓の機能低下(肝炎など)や、胆道が詰まる(胆石、腫瘍など)ことで起こります[15]。米国疾病予防管理センター(CDC)もC型肝炎の症状として挙げています。 - 嚥下障害(えんげしょうがい):
食べ物が飲み込みにくい、つかえる感じがする症状で、食道の病気(食道炎、食道がん、アカラシアなど)が疑われます[1]。 - 消化不良・腹部膨満感:
胃もたれや、お腹が張る感じは、消化不良や機能性ディスペプシア(FD)などでよく見られます[2]。
なぜ症状が起こるのか?(機能と構造の破綻)
消化器疾患の症状は、大きく分けて「機能的な問題」と「器質的な問題」の二つによって引き起こされます。この二軸で考えると、ご自身の不調が理解しやすくなります。
1. 機能的な問題(機能性疾患)
これは、内視鏡(胃カメラ)やエコー検査などで臓器を調べても、潰瘍や炎症、がんといった目に見える「形(構造)の異常」が見つからないにもかかわらず、症状が続いている状態を指します。いわば、臓器の「働き(機能)」や「制御」に問題が生じている状態です。
代表的なものに、胃もたれやみぞおちの痛みが続く「機能性ディスペプシア(FD)」や、下痢と便秘を繰り返す「過敏性腸症候群(IBS)」があります。これらは、消化管の運動異常、知覚過敏、ストレス、生活習慣、腸内細菌叢の乱れなど、複数の要因が絡み合って発症すると考えられています[2, 12]。
2. 器質的な問題(器質的疾患)
これは、検査によって明らかな「形(構造)の異常」が確認できる状態です。
- 炎症:胃酸による「逆流性食道炎」、ピロリ菌や薬剤による「胃炎」、ウイルスや細菌による「感染性胃腸炎」など。
- 潰瘍:胃や十二指腸の粘膜が深くえぐれた「胃潰瘍」「十二指腸潰瘍」。
- 腫瘍:「食道がん」「胃がん」「大腸がん」などの悪性腫瘍や、「大腸ポリープ」などの良性腫瘍[6, 10]。
- 結石:胆嚢や胆管に石ができる「胆石症」[4]。
- 出血・穿孔:潰瘍や憩室から出血したり、穴が開いたりする状態。
これらの器質的疾患は、機能性疾患と異なり、放置すると進行したり、時には命に関わる合併症(大出血や穿孔)を引き起こしたりする可能性があるため、早期の診断と適切な治療が不可欠です。
よくある質問 (FAQ)
Q1: 胸やけと胃痛はどう違いますか?
A: どちらも上腹部の不快感ですが、性質が異なります。「胸やけ」は、胸のあたりが焼けるような、熱い感じがする症状で、主に胃酸が食道に逆流すること(GERD)で起こります[1]。一方、「胃痛」は、みぞおち(心窩部)の痛みや重苦しさ、早期飽満感(すぐにお腹がいっぱいになる)などを指し、機能性ディスペプシア(FD)や胃潰瘍などで見られます[2]。ただし、両方の症状が同時に出ることもあり、自己判断は困難です。
Q2: 血便や黒色便を見つけたら、少し様子を見ても良いですか?
A: いいえ、様子見は推奨されません。米国NIDDKも指摘するように、血便や黒色便は消化管のどこかから出血しているサインです[13]。痔のように比較的軽微なものから、胃潰瘍、大腸憩室出血、大腸がんなど、緊急の治療が必要な疾患まで原因は様々です[7, 14]。特に黒色便や吐血は、速やかに医療機関(消化器内科または救急外来)を受診してください。
Q3: 下痢は、1日に何回以上出たら「下痢」と判断しますか?
A: 世界保健機関(WHO)は、「1日に3回以上の水様便(形のない水のような便)」を下痢と定義しています[16]。ただし、回数以上に重要なのは「状態」です。水様便が続く、水分が摂れない、ぐったりしている、おしっこの回数が極端に減った、といった場合は脱水が強く疑われるため、回数に関わらず早めに受診してください。
Q4: 黄疸(皮膚や白目が黄色い)が出たら、どの科を受診すればよいですか?
A: 消化器内科または肝臓内科が第一選択です。黄疸は、肝炎、肝硬変、胆石、胆道がん、膵臓がんなど、肝・胆・膵系の重大な病気のサインである可能性が高いです[15]。特に、尿の色が濃い(褐色尿)、便の色が白っぽい(灰白色便)といった症状を伴う場合は、胆汁の流れが滞っている(胆汁うっ滞)可能性があり、早急な受診が必要です。
Q5: 冬場に家族内で嘔吐や下痢が次々とうつった場合、何を疑いますか?
A: 冬季に集団発生する嘔吐・下痢症の多くは、「ノロウイルス」などのウイルスによる感染性胃腸炎が最も疑われます[8, 9]。非常に感染力が強いため、家庭内でも感染が広がりやすいのが特徴です。治療は対症療法(整腸剤や吐き気止め)が中心となりますが、乳幼児や高齢者は脱水になりやすいため、経口補水液などでこまめに水分補給を行うことが最も重要です。また、手洗いの徹底と、嘔吐物や便の適切な処理(次亜塩素酸ナトリウムでの消毒)が感染拡大防止の鍵となります。
受診の目安・救急の赤旗サイン(吐血・下血・激痛・黄疸・脱水)
消化器の症状には、腹痛、下痢、便秘など、日常生活でよく経験するものも多く含まれます。前節で概説したように、その範囲は非常に広いものです。しかし、「いつものこと」と自己判断してしまうことには大きな危険が伴います。消化器疾患の中には、一刻を争う救急治療が必要なもの、あるいは生命に関わる重大な病気のサインであるものが存在するからです。
このセクションでは、消化器症状における**「赤旗サイン(Red Flags)」**、すなわち**直ちに医療機関を受診すべき、あるいは救急車(119番)を要請すべき危険な兆候**について、日本の救急受診ガイドライン(例:東京消防庁「救急受診ガイド」など)や国際的な医療機関(NIDDK、NHSなど)の基準に基づき、詳しく解説します。これらのサインを知っておくことは、ご自身やご家族の命を守るために不可欠です。
吐血と下血(消化管出血のサイン)
消化管のどこかから出血しているサインは、最も緊急性の高い赤旗サインの一つです。出血を目にすることは非常に不安な経験ですが、その色や形状が重要な手がかりとなります。
- 吐血(とけつ):口から血を吐くことです。これには2つの主要なパターンがあります。
- 鮮紅色(せんこうしょく)の吐血:鮮やかな赤色の血を吐く場合。これは、食道や胃からの活動的な出血(例:食道静脈瘤の破裂、重度の潰瘍)を示唆し、極めて危険な状態です。
- コーヒー残渣様(コーヒーざんさよう)の嘔吐:米国国立糖尿病・消化器・腎臓病研究所(NIDDK)も指摘するように、吐物がコーヒーの残りかすのように黒褐色である場合。これは、胃の中で血液が胃酸と混ざり、酸化して黒くなったことを意味します。胃潰瘍や胃炎からの出血でよく見られますが、これも緊急の評価が必要です。
- 下血(げけつ):肛門から血が出ることです。これも色によって出血部位を推測できます。
- 黒色便(こくしょくべん)またはタール便:NIDDKや英国国民保健サービス(NHS)が警告するように、便が海苔の佃煮やイカスミのように真っ黒で、コールタールのように粘り気がある場合。これは主に上部消化管(胃や十二指腸)からの出血を示します。血液が腸を通過する間に消化・変性した結果です。吐血と同様に緊急性が高いサインです。
- 鮮血便(せんけつべん):便に鮮やかな赤い血が混じる、または排便時に出血する場合。痔(じ)が原因であることも多いですが、血便の原因には大腸ポリープ、大腸憩室炎、炎症性腸疾患(IBD)、あるいは大腸がんなども含まれます。特に大量の出血や持続する出血は救急受診が必要です。
判断のポイント:
吐血(鮮血・コーヒー残渣様を問わず)、または黒色便が確認された場合は、**量に関わらず直ちに救急外来を受診するか、119番通報を検討してください**。これらは、ピロリ菌感染に関連する胃潰瘍や十二指腸潰瘍、あるいは肝硬変などに伴う食道静脈瘤の破裂など、生命を脅かす可能性のある状態のサインです。特に、めまい、ふらつき、冷や汗、動悸、意識が遠のく感じなど、ショック症状を伴う場合は迷わず救急車を呼んでください。
経験したことのない激しい腹痛(急性腹症)
「お腹が痛い」という症状は最も一般的ですが、その「痛み方」が重要です。いつもの胃痛や腹痛とは明らかに違う、以下のような特徴を持つ痛みは「急性腹症(きゅうせいふくしょう)」と呼ばれ、緊急手術が必要な病気の可能性があります。
- 突然発症した、立っていられないほどの激痛
- 痛みがどんどん強くなり、持続する(波があるが、痛みがゼロにならない)
- お腹を軽く押すだけで激痛が走る(圧痛)、押した手を離すときに響く(反跳痛)
- お腹が板のように硬くなる(筋性防御)
- 発熱、嘔吐、冷や汗を伴う
NHSは、胃潰瘍の穿孔(穴が開くこと)や重度の胃腸炎などで見られる「突然の激しい腹痛」を緊急事態としています。これらは、胃や腸に穴が開いて内容物が腹腔内に漏れ出す「消化管穿孔」や、虫垂炎(盲腸)、腸閉塞(腸が詰まる)、急性膵炎など、緊急の処置や手術を必要とする病気のサインです。
判断のポイント:
「我慢できないほどの激しい腹痛」や「いつもと違う尋常ではない腹痛」を感じた場合は、**絶対に自己判断で様子を見たり、鎮痛剤を飲んだりしないでください**。鎮痛剤で痛みが一時的に和らぐと、診断が遅れる可能性があります。直ちに救急外来を受診するか、119番通報してください。
黄疸(皮膚や目の黄染)
黄疸(おうだん)は、血液中のビリルビンという黄色い色素が増加し、皮膚や、特に**眼球結膜(目のしろ目)**が黄色く染まる状態を指します。新生児では生理的な黄疸がよく見られますが、NHSが強調するように、成人に新たに出現した黄疸は、ほぼ常に何らかの病的な原因が隠れています。
黄疸は、肝臓自体の機能障害(例:急性肝炎、アルコール性肝障害、肝硬変)か、肝臓で作られた胆汁(ビリルビンを含む)の通り道である胆管が詰まること(例:総胆管結石、胆管がん、膵臓がん)によって引き起こされます。
特に以下の症状を伴う黄疸は、「閉塞性黄疸(へいそくせいおうだん)」の可能性があり、緊急性が高まります。
- 淡色便(たんしょくべん)または白色便:便が白っぽい、またはクリーム色になる(胆汁が腸に流れず、便が色づかないため)。
- 濃褐色尿(のうかっしょくにょう):尿の色が紅茶やウーロン茶のように濃くなる(行き場を失ったビリルビンが尿中に排出されるため)。
- 全身の強いかゆみ:ビリルビン関連物質が皮膚に蓄積するため。
判断のポイント:
成人が黄疸に気づいた場合、特に上記のような便や尿の色の変化、かゆみを伴う場合は、**可及的速やかに(通常は当日~翌日中に)医療機関を受診してください**。激しい腹痛や高熱を伴う場合(急性胆管炎など)は、救急受診が必要です。
重度の脱水(嘔吐・下痢が続く場合)
急性胃腸炎(感染症や食中毒)による嘔吐や下痢はありふれた症状ですが、それによって引き起こされる「脱水」は、特に乳幼児や高齢者において生命を脅かすことがあります。米国疾病予防管理センター(CDC)は、ノロウイルスやロタウイルス感染症における脱水の危険性を警告しています。
重度の脱水を示すサインには以下のようなものがあります。
- 水分を全く受け付けない、または飲んでもすぐに吐いてしまう
- 尿がほとんど出ない、または色が非常に濃い
- 口の中や舌がカラカラに乾いている
- (小児の場合)泣いても涙が出ない、目が落ちくぼんでいる
- 立ち上がると強いめまいやふらつきがする(起立性低血圧)
- ぐったりしている、呼びかけへの反応が鈍い(意識障害)
軽度の脱水であれば、自宅での経口補水液(ORS)による水分・電解質補給が基本です。世界保健機関(WHO)や日本の厚生労働省も、スポーツドリンクではなく、適切な塩分・糖分バランスの経口補水液の使用を推奨しています。
判断のポイント:
経口補水液を試みても水分摂取が追いつかない(嘔吐・下痢が激しすぎる)場合や、上記のような重度の脱水サイン(特に「ぐったりしている」「尿が半日以上出ていない」)が見られる場合は、**点滴による急速な水分補給が必要**です。医療機関を受診してください。意識障害がある場合は、直ちに119番通報が必要です。
特に注意が必要な状況(高齢者・基礎疾患・内服薬)
同じ症状であっても、その人の背景によって緊急度が変わることがあります。特に以下の状況に当てはまる方は、より早期の受診判断が求められます。
- 高齢者(65歳以上)および乳幼児:予備能力が低く、脱水や出血の影響が急速に現れやすいため、大人の下痢や嘔吐であっても早めに医療機関に相談してください。
- 肝硬変などの基礎疾患がある方:肝硬変の方は食道静脈瘤のリスクがあり、わずかな吐血や黒色便でも緊急事態です。
- 妊娠中の方:脱水や感染症が胎児に影響する可能性があるため、早めの対応が必要です。
- 抗凝固薬・抗血小板薬を内服中の方:NHSは、抗凝固薬(ワーファリン、エリキュース、イグザレルトなど)や抗血小板薬(バイアスピリン、クロピドグレルなど)を飲んでいる方の消化管出血は、重症化しやすいため**少量でも直ちに医師に連絡・受診**するよう強く推奨しています。
よくある質問(FAQ)
Q1: 吐いた物がコーヒーのかすのようでした。様子を見ても良いですか?
A: いいえ、様子を見るべきではありません。それは胃の中で出血した血液が胃酸で黒く変色した「コーヒー残渣様嘔吐」と呼ばれるサインです。活動的な出血を示している可能性があり、NHSなどの公的機関も**直ちに救急受診**が必要としています。
Q2: 便が黒い(タール便)が出ました。緊急ですか?
A: はい、**緊急性が高い**状態です。黒色便(タール便)は、主に胃や十二指腸からの出血(上部消化管出血)を示唆します。出血源を特定し、止血処置が必要になる場合があるため、**速やかに救急外来を受診してください**。
Q3: 大人の黄疸はどのくらい急いで受診すべきですか?
A: **至急の受診が必要です**。成人の黄疸は、肝炎、胆道閉塞、あるいは腫瘍など、重篤な肝胆膵疾患のサインであることが多いためです。特に腹痛や発熱、淡色便(白い便)を伴う場合は、その日のうちに医療機関を受診してください。
Q4: 下痢と嘔吐で脱水が心配です。スポーツドリンクではダメですか?
A: 軽度の脱水予防には役立ちますが、すでに脱水が疑われる場合や嘔吐・下痢が激しい場合は、スポーツドリンクでは塩分(電解質)が不足し、糖分が多すぎることがあります。厚生労働省やWHOは、電解質バランスが最適化された**経口補水液(ORS)**を推奨します。それでも水分が摂れない、またはぐったりしてきた場合は、点滴が必要なため医療機関を受診してください。
Q5: 血液をサラサラにする薬(抗凝固薬)を飲んでいます。少し血便が出ただけですが、受診すべきですか?
A: はい、**少量であっても直ちに医師に連絡し、受診してください**。抗凝固薬や抗血小板薬を内服中の方は、一度出血が始まると自然に止血しにくく、急速に重症化するリスクがあります。自己判断は非常に危険です。
診断と検査の流れ(血液・便検査/腹部エコー・CT/MRI/内視鏡・生検)
前節の「受診の目安」で解説したような深刻な症状(赤旗サイン)に気づき、不安を抱えて医療機関を訪れたとき、医師はまず「何が起こっているのか」を突き止めるための診断プロセスを開始します。消化器疾患の診断は、パズルのピースを一つひとつ集めて全体像を明らかにする作業に似ています。単一の検査で全てがわかることは稀であり、問診や身体診察から得られた情報をもとに、血液検査、便検査、画像検査、そして内視鏡検査を段階的に、あるいは組み合わせて進めていきます。
このプロセスは、患者さんにとっては不安や緊張を伴うものかもしれません。「痛い検査をされるのではないか」「何が見つかるのだろうか」という心配は当然のことです。このセクションでは、消化器疾患の診断において、どのような検査が、どのような目的で、どのような順序で行われるのか、その標準的な流れと各検査の役割を詳しく解説します。検査の内容を事前に理解しておくことは、不安を和らげ、安心して診断に臨むための第一歩となります。
まず何を調べる?初期検査としての血液検査
診察室で医師が最初に行う「一次評価」の中心となるのが血液検査です。これは、体内の状態を映し出す「ダッシュボード」のようなもので、医師は体のどこで「警報」が鳴っているのかを把握します。採血は日常的な検査に感じられるかもしれませんが、ここから得られる情報は、次に行うべき検査の方向性を決める上で極めて重要です。
- 炎症反応(CRPなど):CRP(C反応性たんぱく)は、体内で炎症や組織の破壊が起きると上昇する数値です。細菌感染による腸炎や胆嚢炎、膵炎などで顕著に高値を示すことがあります。ただし、これは「火事が起きている」ことは教えてくれますが、「どこで、何が原因の火事か」までは特定できません。そのため、他の検査と組み合わせて判断されます。
- 肝胆道系酵素(AST, ALT, γ-GTなど):肝臓や胆道に問題があると、特定の酵素が血液中に漏れ出します。ASTやALTの上昇は主に肝細胞の障害を、ALPやγ-GTの上昇は胆汁の流れが悪い「胆汁うっ滞」(胆石など)を示唆します。
- 膵酵素(アミラーゼ, リパーゼ):みぞおちから背中にかけての激しい痛みがある場合、膵臓の酵素を測定します。特に急性膵炎の診断において、アミラーゼよりもリパーゼの方が感度・特異度ともに高いとされ、診断に非常に有用です。
- 貧血(ヘモグロビン):立ちくらみや倦怠感がある場合、貧血の有無(ヘモグロビン値)を確認します。貧血があれば、吐血や黒色便がなくとも、消化管のどこか(胃潰瘍、大腸がん、ポリープなど)から慢性的に出血している可能性を考え、内視鏡検査の必要性が高まります。
便検査の使い分け:見えない出血から感染症まで
血液検査が体「内部」の状態を反映するのに対し、便検査は消化管を「通過」してきたものの情報を直接教えてくれます。特に大腸の病気や感染症の診断において重要な役割を果たします。
- 便潜血検査(FIT):健康診断で広く行われる検査で、便に混じった目に見えない微量な血液(ヒトのヘモグロビン)を検出します。この検査が陽性となった場合、多くの人が「もう一度検査して確認したい」と考えがちですが、日本のガイドラインでは便潜血の再検査は推奨されていません。陽性の場合は、痔などの良性疾患が原因であることも多いですが、大腸がんやポリープの可能性を否定するために、全大腸内視鏡検査(大腸カメラ)による精密検査が必須とされます。
- 便中カルプロテクチン(FC):慢性的・反復的な下痢や腹痛に悩んでいる場合に非常に有用な検査です。これは腸管の粘膜で炎症が起きると便中に増えるタンパク質を測定します。この数値が高い場合、潰瘍性大腸炎(UC)やクローン病といった炎症性腸疾患(IBD)が強く疑われます。一方、過敏性腸症候群(IBS)では炎症は起きないため、この数値は上昇しません。これにより、不要な内視鏡検査を避け、IBSとIBDの鑑別診断を進める大きな助けとなります。
- 便培養・PCR検査:突然の激しい下痢、嘔吐、発熱など、いわゆる「食あたり」や感染性胃腸炎が疑われる場合に行います。便培養でサルモネラ菌やカンピロバクターなどの細菌を特定し、PCR検査でノロウイルスやロタウイルス、寄生虫などを迅速に検出します。
- ピロリ菌検査:胃もたれや胃の不快感が続く場合、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染を調べます。現在も感染しているか(現感染)を調べるには、尿素呼気試験(UBT)や便中抗原検査が最も信頼性が高いとされています。血液抗体検査は「過去に感染した」ことも反映してしまうため、除菌後の判定や初回の現感染診断には適さない場合があります。
画像検査の第一歩:腹部超音波(エコー)検査
血液検査や便検査が「間接的」な情報であるのに対し、次に行うのは臓器の形や状態を「直接見る」画像検査です。その第一選択肢(ファーストライン)となるのが、腹部超音波(エコー)検査です。
これは、体表からプローブ(探触子)を当て、超音波の反響を利用して内臓を映し出す検査です。放射線被曝の心配がなく、安全で、ベッドサイドでも行えるため、特に右季肋部(右のあばら骨の下)の痛みや、みぞおちの痛みを訴える患者さんへの初期評価として非常に優れています。
超音波検査が最も得意とするのは、胆嚢内の胆石や、胆嚢が腫れている胆嚢炎の診断です。また、肝臓の脂肪蓄積(脂肪肝)の程度や、肝臓・膵臓・腎臓の腫瘍の有無をスクリーニングするのにも用いられます。
ただし、超音波は空気(腸内ガス)や骨、厚い脂肪に弱いという弱点があります。そのため、肥満度が高い方や、腸内ガスが多い状態では、膵臓の奥深くや総胆管が明瞭に見えないことがあります。医師が超音波で十分な情報が得られないと判断した場合や、より深刻な病態(穿孔、膿瘍、重症膵炎など)を疑う場合には、次のステップであるCTやMRI検査へと進みます。
CTとMRI/MRCP:より詳細な「断面図」
超音波検査で評価が困難だった場合や、より深刻な病態、あるいは腫瘍の広がりを精密に評価する必要がある場合、CT検査やMRI検査が選択されます。
- CT検査(Computed Tomography):X線を使って体を輪切りにした詳細な「断面図」を得る検査です。特に「急性腹症(急激な腹痛)」の診断における主役であり、虫垂炎(盲腸)、憩室炎、腸閉塞、あるいは膵炎の重症度評価(壊死や膿瘍の有無)に絶大な力を発揮します。また、がんのステージング(周囲の臓器への広がりやリンパ節転移の評価)にも不可欠です。
- MRI検査(Magnetic Resonance Imaging):強力な磁気と電波を使って体の断面を映し出す検査で、放射線被曝がないのが大きな利点です。CTが骨や空気の描出に優れるのに対し、MRIは筋肉や脂肪、胆汁や膵液などの「水成分」を含む軟部組織の描出に優れています。
- MRCP(磁気共鳴胆管膵管撮影):これはMRIの技術を応用し、胆管と膵管だけを「仮想的」に映し出す特別な撮影法です。胆汁や膵液は画像上で白く光るため、造影剤や内視鏡を使うことなく、総胆管結石の有無や、胆管・膵管の狭窄・拡張を非侵襲的に(体を傷つけずに)評価できます。
特に胆道系・膵臓の診断において、このMRCPの登場は大きな変革をもたらしました。かつては診断のためにERCP(後述)という内視鏡検査が必要でしたが、MRCPや超音波内視鏡(EUS)によって、侵襲的な検査を診断目的で行う必要性が大幅に減少しました。これは日本消化器病学会のガイドラインなどでも推奨されている、現在の標準的な考え方です。
最終診断の鍵:内視鏡(胃カメラ・大腸カメラ)と生検
画像検査が臓器の「形」や「位置関係」を外側から見るのに対し、内視鏡検査は消化管の「内側(粘膜)」を直接カメラで観察する検査です。そして、診断を確定させる上で最も重要な「生検(組織採取)」を行えることが最大の特徴です。
- 上部消化管内視鏡(EGD / 胃カメラ):胸焼け、胃痛、黒色便などの症状がある場合に行われます。口または鼻から細いカメラを挿入し、食道・胃・十二指腸の粘膜を詳細に観察します。これにより、胃潰瘍や逆流性食道炎、胃がんなどを発見します。健康診断のバリウム検査で異常を指摘された場合の精密検査としても行われます。
- 下部消化管内視鏡(CS / 大腸カメラ):便潜血陽性、血便、長引く下痢、便秘などの症状がある場合に行われます。肛門からカメラを挿入し、直腸から盲腸までの全大腸を観察します。
- 生検(病理組織診断):内視鏡検査の核心は「生検」にあります。「赤くなっている」「ただれている」「盛り上がっている」といった所見をカメラで確認するだけでは、「炎症」なのか「がん」なのかを100%確定することはできません。疑わしい病変部からごく小さな組織片を採取し、それを顕微鏡で詳細に調べる「病理診断」こそが、多くの消化器疾患における最終診断(確定診断)となります。
- 治療との一体化:特に大腸カメラは、診断と治療を同時に行える利点があります。検査中にがん化する可能性のあるポリープを発見した場合、その場で切除(ポリペクトミー)することが可能です。
検査の安全性と心の準備(鎮静・前処置)
これまでに多くの検査を解説してきましたが、特に内視鏡検査に対しては、「苦しい」「怖い」といった強い不安を感じる方が少なくありません。しかし、現代の医療では、これらの検査をできるだけ安全かつ快適に受けていただくための工夫が進んでいます。
鎮静剤の使用について
多くの施設では、患者さんの希望に応じて鎮静剤(静脈麻酔)を使用します。これは全身麻酔とは異なり、うっすらと眠っているような、あるいはリラックスした「ウトウト」した状態で検査を受ける方法です。特に嘔吐反射が強い方や、大腸が長く検査に時間がかかりそうな方、不安が非常に強い方には有効です。ただし、鎮静剤には呼吸抑制などのリスクも(稀ですが)伴うため、高齢の方や呼吸器・循環器に持病がある方では、安全性を最優先に投与量を調整したり、厳重な監視下で行ったりします。
また、検査の質と安全性を確保するためには「前処置」が極めて重要です。胃カメラの場合は検査前の絶食、大腸カメラの場合は検査前に腸内を空にするための下剤(腸管洗浄剤)の服用が必要です。特に大腸カメラの下剤は、量が多くて大変だと感じる方も多いですが、腸がきれいになっていなければ、小さな病変が見逃される原因となります。医師の指示通りに、確実な前処置を行うことが、精度の高い検査につながります。
血液をサラサラにする薬(抗血栓薬)を内服中の方は、生検やポリープ切除の際に出血のリスクが高まるため、検査前に必ず主治医(処方医)と内視鏡医に申告してください。検査のために薬をいつから休薬すべきか、あるいは休薬せずに検査可能か、専門的な判断が必要となります。
CTの造影剤アレルギーや腎機能、MRIの体内金属(ペースメーカーなど)や閉所恐怖症など、各検査には個別の注意点もあります。不安な点は事前に医師や看護師に確認し、安心して検査に臨める状態を整えることが大切です。
胃・十二指腸の病気(胃炎・ピロリ菌・胃潰瘍・機能性ディスペプシア)
前節では、消化器疾患を診断するための様々な検査(血液検査、内視鏡、画像診断など)の流れについて詳しく見てきました。検査を受ける際、多くの方が「一体、自分の胃はどうなっているのだろうか」「深刻な病気が見つかったらどうしよう」と大きな不安を感じます。その不安はごく自然なことです。
ここでは、その検査によって診断されることが多い、最も身近な上部消化管の病気、すなわち「胃」と「十二指腸」の主要な疾患について、その原因から最新の治療法までを深く掘り下げて解説します。胃がどのような臓器で、どのような働きをしているかを知ることは、これらの病気を理解する第一歩です。「胃痛」と一口に言っても、その背景にはさまざまな状態が隠されています。
胃炎(急性・慢性):すべての不調の始まり
「胃炎(いえん)」は、おそらく最もよく聞く胃の病名の一つでしょう。これは、胃の粘膜(胃の内側を覆うデリケートな層)に炎症が起きている状態を指します。胃炎は、その経過から「急性胃炎」と「慢性胃炎」に大別されます。
- 急性胃炎:アルコールの飲み過ぎ、刺激物の過剰摂取、鎮痛剤(NSAIDs)の服用、ストレスなどが引き金となり、急激な胃痛、吐き気、胃もたれを引き起こします。原因がはっきりしていることが多く、その原因を取り除くことで速やかに改善することが多いのが特徴です。
- 慢性胃炎:症状がはっきりしないまま、炎症が長期間にわたってじわじわと続く状態です。多くの場合、慢性胃炎の最大の要因はヘリコバクター・ピロリ菌の感染です。この状態が続くと、胃の粘膜が萎縮(いしゅく:薄く痩せてしまうこと)し、胃がんのリスクが高まることが知られています。
その他にも、鎮痛剤(NSAIDs)の長期服用による「薬剤性胃炎」や、自身の免疫が胃を攻撃してしまう「自己免疫性胃炎」(悪性貧血の原因となる)など、原因は多岐にわたります[8]。胃炎と診断された場合、その原因を特定し、適切な食事療法や生活習慣の改善を行うことが、より深刻な病気(胃潰瘍など)への進行を防ぐ鍵となります。
ヘリコバクター・ピロリ:胃がんの最大のリスク因子
ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)は、胃の強い酸性環境の中で生息できる特殊な細菌です。多くの場合、幼少期に感染し、一度感染すると自然に排除されることはほとんどありません。この菌が、前述の慢性胃炎、そして胃潰瘍・十二指腸潰瘍、さらには胃がんの発生に深く関わっています。
世界保健機関(WHO)の専門組織である国際がん研究機関(IARC)は、ピロリ菌を「確実な発がん因子」として分類しており、ピロリ菌の感染経路や胃がんとの関連性は世界中で研究されています[9]。幸いなことに、ピロリ菌は「除菌治療」(抗菌薬と胃酸分泌抑制薬を1週間服用する)によって高い確率で排除することが可能です。
日本では、2013年から「ピロリ菌感染胃炎」に対する除菌治療が健康保険の適用となりました。ただし、保険適用を受けるためには、「まず上部消化管内視鏡(胃カメラ)検査を受け、慢性胃炎であることを確認すること」が原則となっています[4]。内視鏡を行わずに血液検査や呼気検査だけで「陽性」と診断されても、保険診療での除菌は原則できないため、この点は特に注意が必要です。除菌治療の成功率は高く、一次除菌(最初の治療)で80〜90%、二次除菌(薬を変えた2回目の治療)まで含めると累積で98%程度が成功すると報告されています[6]。ピロリ菌検査の必要性や費用について不安がある場合は、消化器内科で相談しましょう。
胃・十二指腸潰瘍:粘膜が深くえぐれた状態
胃炎が粘膜表面の「ただれ」だとすれば、潰瘍(かいよう)は粘膜がさらに深くえぐれ、下の筋層まで達してしまった「穴」のような状態です。これが胃にできれば胃潰瘍、十二指腸(胃の出口のすぐ先にある臓器)にできれば十二指腸潰瘍と呼ばれます。
潰瘍の二大原因は、「ピロリ菌感染」と「非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)」です[1]。特に、ロキソニン®︎やボルタレン®︎などの鎮痛剤や、心臓・脳血管疾患の予防でアスピリン(バイアスピリン®︎など)を服用している方は、潰瘍のリスクが高くなります。
潰瘍の症状は、空腹時や夜間に悪化するみぞおちの痛みが典型的ですが、潰瘍の危険なサインを見逃さないことが重要です。最も危険な合併症は「出血」と「穿孔(せんこう)」です。
- 出血:潰瘍が血管を破ると出血します。吐血(真っ赤な血、またはコーヒーかす様)や、下血(タール便と呼ばれる真っ黒な便)として現れます。これは緊急の内視鏡による止血が必要です。
- 穿孔:潰瘍が胃や十二指腸の壁を貫通し、穴が開いてしまう状態です。突然の激しい腹痛(「ナイフで刺されたよう」と表現される)が特徴で、緊急手術が必要な腹膜炎を引き起こします。胃穿孔は命に関わる状態です。
治療は、強力な胃酸分泌抑制薬(PPIや、近年登場したP-CABと呼ばれる薬)が中心です[1]。ピロリ菌がいれば除菌治療を、NSAIDsが原因であれば可能な限り中止するか、P-CABなどの予防薬を併用します。未治療の場合、1年以内の再発率は非常に高い(胃で60%、十二指腸で85%)と報告されており[6]、原因の根本治療がいかに重要かがわかります。
機能性ディスペプシア(FD):検査で異常がないのに続く不調
「胃が痛むし、もたれる。すぐに満腹になって食べられない。だから内視鏡検査を受けたのに、『どこも悪くない、きれいな胃です』と言われた。」——これは、消化器内科で最もよく聞かれる悩みの一つです。このように、胃もたれや膨満感などの症状が続いているにもかかわらず、内視鏡検査などで潰瘍やがんのような器質的(目に見える)な異常が見つからない場合、「機能性ディスペプシア(Functional Dyspepsia: FD)」と診断されます。
これは決して「気のせい」や「怠け」ではありません。FDは、胃の「機能」に問題が生じている状態です[12]。具体的には、
- 食べた後に胃がうまく膨らまない(適応性弛緩障害)
- 食べ物を十二指腸へ送り出す動きが悪い(胃排出遅延)
- 胃や十二指腸がわずかな刺激に過敏になっている(内臓知覚過敏)
- ストレスや不安などの心理社会的要因
などが複雑に関与していると考えられています[2]。
治療は段階的に行われます。まず、生活習慣や食事の指導、ピロリ菌検査(陽性なら除菌)が行われます。それでも改善しない場合、第一選択薬として胃酸分泌抑制薬(PPI/P-CAB)が使われます[11]。次に、胃の動きを改善する消化管運動機能改善薬(アコチアミドなど)が試されます。これらで効果が不十分な場合、胃の知覚過敏を抑える目的で、ごく少量の抗うつ薬や抗不安薬が非常に有効な場合があります[7]。FDは完治が難しい場合もありますが、症状をコントロールし、うまく付き合っていくための治療法が確立されつつあります。
十二指腸炎:胃酸とピロリ菌の影響
十二指腸は胃のすぐ先にあり、胃から送られてきた食物と、膵液や胆汁が混ざり合う場所です。この十二指腸の粘膜が、胃酸やピロリ菌、薬剤などによって炎症を起こした状態が「十二指腸炎」です。
症状は胃炎や胃潰瘍と似ており、みぞおちの痛みや不快感、胃もたれなどが主です。十二指腸炎の治療は、基本的に胃炎や潰瘍に準じます。胃酸分泌抑制薬で粘膜を保護し、ピロリ菌がいれば除菌を行います。ストレスや食事の影響も受けやすいため、生活習慣の見直しも重要です。このセクションで解説した胃と十二指腸の病気は、互いに密接に関連しています。次のセクションでは、さらに上流にある「食道」の病気について見ていきましょう。
食道の病気(逆流性食道炎・食道炎・バレット食道 の基礎)
前のセクションでは、消化の要である「胃」の不調について詳しく見ました。食べ物が胃に達する前に必ず通過する、のどと胃をつなぐ「パイプ」が食道です。この食道は、胃酸のような強力な酸に対する防御機能を持っていないため、非常にデリケートな臓器です。
「胸が焼けるように熱い」「酸っぱいものがこみ上げてくる」「食べ物がつかえる感じがする」——こうした症状は、食道が何らかのダメージを受けているサインかもしれません。このセクションでは、食道の病気の中でも特に頻度の高い「逆流性食道炎(GERD)」、その他の「食道炎」、そして検診などで指摘されると不安になる「バレット食道」の基礎知識について、その原因と対策を分かりやすく解説します。
GERD(胃食道逆流症)と逆流性食道炎:胸やけの正体
「GERD(ガード)」や「逆流性食道炎」という言葉はよく耳にしますが、その違いを正確に理解されている方は少ないかもしれません。まず、この混乱しやすい用語から整理しましょう。
GERD(胃食道逆流症)とは、胃の中身(主に胃酸)が食道に逆流することによって、不快な症状(胸やけなど)や合併症が起きている「状態」全体を指す、非常に広い概念です。日本の診療ガイドライン[1]でも、この広い定義が採用されています。
このGERDは、内視鏡(胃カメラ)で見たときの食道の状態で、大きく2つのタイプに分けられます。
- 逆流性食道炎(びらん性GERD):内視鏡で見たときに、食道粘膜に「びらん」と呼ばれるただれや傷がハッキリと確認できるタイプです。これは胃酸による「火傷」が目に見える状態です。
- 非びらん性GERD(NERD):胸やけや呑酸(どんさん:酸っぱいものが上がってくる感じ)などの症状は確かにあるのに、内視鏡で見ても食道粘膜はキレイで、びらんが見当たらないタイプです。日本ではGERD患者さんの半数以上がこのNERDであるとも言われており、「見た目」だけでは判断できない難しさがあります。
では、なぜ逆流は起こるのでしょうか。通常、食道と胃のつなぎ目には、下部食道括約筋(LES)という筋肉の「フタ」があり、食べ物が通過するとき以外は胃の内容物が逆流しないよう、ギュッと閉じています[1, 2]。しかし、加齢、肥満による腹圧の上昇、食生活(高脂肪食やアルコール[4])、姿勢(猫背)など、さまざまな理由でこの「フタ」の機能が低下すると、胃酸が食道へと逆流しやすくなるのです。
主な症状は「胸やけ」や「呑酸」ですが、それだけではありません[1, 2]。
- のどの違和感(イガイガする、詰まった感じ)
- 慢性的な咳(特に夜間や早朝)
- 声のかすれ(嗄声)
- 胸の痛み(心臓の病気と間違われることも)
このように、一見すると逆流とは関係なさそうな症状(食道外症状)として現れることもあり、耳鼻咽喉科や呼吸器内科を受診しても原因がわからなかった場合、実はGERDが根本的な原因であることも珍しくありません。
食道炎の多様な原因:逆流だけではない食道の炎症
食道が炎症を起こす原因は、胃酸の逆流だけではありません。もし「逆流症の薬を飲んでいるのに、症状が良くならない」「特に飲み込むときに痛む」といった場合は、他の原因も考える必要があります[3]。
- 好酸球性食道炎(EoE):これは近年、日本でも注目されている病気で、胃酸とは関係なく、「好酸球」という種類のアレルギー細胞が食道粘膜に集まることで炎症が起こります[11]。主な原因は食物アレルギー(小麦、乳製品、卵など)と考えられており、胸やけよりも「食べ物がつかえる」「飲み込みにくい(嚥下障害)」といった症状が特徴です[11, 12]。アカラシアなど他の嚥下障害との鑑別も重要です。
- 薬剤性食道炎:特定の薬剤(骨粗しょう症の薬、一部の抗生物質や鎮痛剤など)が食道粘膜に張り付き、そこで溶け出すことで強い炎症を起こすことがあります[13]。特に、寝る直前に薬を飲んだり、少ない水で飲んだりすると、薬が食道に留まりやすくなるため危険です。薬を飲むときは、必ずコップ一杯程度の十分な水で、上体を起こしたまま飲むことが予防になります。
- 感染性食道炎:健康な人では稀ですが、免疫力が低下している状態(ステロイド治療中、化学療法中、糖尿病、HIV感染症など)では、カンジダ(真菌)やウイルス(ヘルペスなど)が食道で増殖し、炎症を起こすことがあります[3]。この場合、強い「嚥下時痛(飲み込むときの痛み)」が特徴です。
バレット食道:無症状の“変化”とサーベイランスの重要性
健康診断や人間ドックの内視鏡検査で、「バレット食道(Barrett’s esophagus)の疑い」と指摘され、不安に思われる方も多いでしょう。これは一体どのような状態なのでしょうか。
バレット食道とは、長期間にわたって胃酸の逆流にさらされ続けた結果、食道の粘膜が「もう耐えられない」と判断し、胃酸に強い胃の粘膜(円柱上皮)に「変身」してしまった状態(化生)を指します[6]。本来、食道粘膜は「扁平上皮」という皮膚のような細胞でできていますが、これが胃の粘膜に置き換わってしまうのです。
この「変身」自体は、体を守るための防御反応の一種であり、バレット食道そのものには通常、症状はありません[6]。問題は、この「変身した粘膜」が、非常に稀ではありますが、将来的に「食道腺がん」という特殊なタイプのがんの発生母地(がんの発生しやすい場所)になる可能性があることです[6, 10]。
日本では、欧米に比べてこのバレット食道から発生する食道腺がんの頻度は低いとされてきました[4]。しかし近年、食生活の欧米化やピロリ菌感染率の低下(胃酸分泌が活発になるため)に伴い、逆流性食道炎の患者さんが増え、それに伴ってバレット食道、そしてバレット食道がんも増加傾向にあると指摘されています[5]。
ここで強調したいのは、「バレット食道=がん」では決してない、ということです。がん化のリスクは一般の人よりは高いものの、年間の発生率は全体として見れば低いとされています[6, 10]。
最も重要なのは、この状態を放置せず、「サーベイランス(経過観察)」、つまり定期的な内視鏡検査を受けることです[7, 10]。胃の検診などで偶然見つかることも多いため、指摘された場合は、医師の指示に従い、1〜3年に1回など、推奨された間隔で内視鏡検査を受け、粘膜の状態をチェックし続けることが、がんの早期発見・早期治療に繋がります。
治療の基本戦略:生活改善と薬物療法
逆流性食道炎(GERD)の治療の基本は、「逆流を減らすこと」と「逆流した胃酸の攻撃力を弱めること」の2本柱です。
1. 生活習慣の改善(逆流を減らす)
薬を飲む前に、あるいは薬と並行して、まず取り組むべき最も重要な対策です[2]。これらを行わずに薬だけを飲んでも、根本的な解決にはなりにくいです。
- 食後すぐに横にならない:特に夕食後、最低でも2〜3時間は横になるのを避ける[2]。胃に物が入ったまま横になると、物理的に逆流しやすくなります。
- 就寝時の工夫:就寝中の逆流を防ぐため、枕だけでなく上半身全体が持ち上がるよう、ベッドの頭側を高くする(頭側挙上)[2]。
- 食事内容の見直し:高脂肪食、チョコレート、アルコール、炭酸飲料、柑橘類、香辛料などは、胃酸の分泌を増やしたり、LESを緩めたりすることが知られています[2, 4]。
- 減量と服装:肥満は腹圧を上げ、逆流の最大のリスク因子の一つです。体重を減らすだけで劇的に改善することがあります。また、ベルトやコルセットでお腹をきつく締めるのも避けましょう。
- 禁煙:喫煙はLESを緩める作用があります[2]。
2. 薬物療法(胃酸の攻撃力を弱める)
生活改善と並行して、胃酸の分泌を強力に抑える薬が治療の主役となります。
- プロトンポンプ阻害薬(PPI):長年にわたり、逆流性食道炎治療の第一選択(ゴールドスタンダード)とされてきた薬です[1, 2]。胃酸分泌を強力に抑制し、食道のびらんを治癒させます。
- P-CAB(カリウムイオン競合型アシッドブロッカー):日本では「ボノプラザン(製品名:タケキャブ)」として知られる、比較的新しい強力な胃酸分泌抑制薬です[8]。PPIよりも効果発現が速く、より強力に胃酸を抑えるため、重症の食道炎や、PPIでは効果が不十分だった場合(難治性GERD)の切り札として、日本の臨床現場で広く使われています[1, 9]。
- その他の薬剤:軽症の場合はH2ブロッカー(例:ガスター)が使われることもあります。また、アルギン酸塩(例:アルロイドG)は、胃の内容物の表面に「いかだ」のような層を作って逆流を防ぐ働きがあります[2]。
重症の合併症である食道狭窄(食道が狭くなる)や、薬物療法に抵抗する重度の逆流、あるいは肝硬変などに伴う食道静脈瘤といった特殊な病態については、内視鏡的治療や外科手術(噴門形成術[2]やLINX[16]など)が必要となる場合もあります。
食道の病気は、食後の不快感など、生活の質(QOL)に直結するものが多くあります。しかし、その多くは適切な診断と治療、そして生活習慣の見直しによって、大きく改善することが可能です。気になる症状があれば、自己判断で我慢せず、専門医に相談することが大切です。
ここまで、消化管の「上流」にあたる胃、十二指腸、そして食道について見てきました。次のセクションでは、食べ物の旅の「下流」にあたる、小腸・大腸の病気(下痢、便秘、IBSなど)について詳しく解説していきます。
小腸・大腸の病気(下痢・便秘・IBS・IBD・憩室・ポリープ)
前節では、食べ物が最初に通過する食道の病気について見てきました。ここでは、消化と吸収、そして排泄という生命維持に不可欠な役割を担う、長く複雑な「小腸」と「大腸」の病気について詳しく解説します。
小腸は栄養素の大部分を吸収する場所であり、大腸は主に水分を吸収して便を形成する場所です。これらの臓器に問題が生じると、下痢や便秘といった日常的な不調から、生活の質(QOL)を著しく低下させる過敏性腸症候群(IBS)、さらには長期的な管理が必要となる炎症性腸疾患(IBD)や、がん化のリスクを伴う大腸ポリープまで、多岐にわたる病気が発生します。
お腹の不調は「よくあること」と見過ごされがちですが、その背景には重要なサインが隠れていることも少なくありません。このセクションでは、機能的な問題(IBSなど)と器質的な問題(IBD、ポリープなど)を整理し、それぞれの病気の特徴、受診の目安、そして治療の基本的な考え方について、日本のガイドラインに基づきながら深く掘り下げていきます。ご自身の症状を理解し、適切な対応をとるための一助となれば幸いです。
便通異常の基礎:下痢・便秘の違いと警告サイン
私たちの健康状態を映す鏡とも言える「便通」。その異常である下痢と便秘は、多くの人が経験する最も一般的な消化器症状の一つです。しかし、「たかが下痢」「いつもの便秘」と軽視することはできません。これらは時に、重大な病気の初期症状である可能性もあるのです。
下痢(げり)とは
下痢は、便の水分量が異常に増加し、液状または泥状の便(軟便〜水様便)が頻繁に排出される状態を指します。医学的には、便の水分量が正常(約70-80%)を超え、90%以上になると定義されます。この状態は、腸が水分を十分に吸収できないか、あるいは腸管内に水分が過剰に分泌されることによって引き起こされます。
- 急性下痢(4週未満):多くはウイルスや細菌による感染性腸炎(食中毒)が原因ですが、これについては本ガイドの別セクション「消化器の感染症・食中毒」で詳述します。
- 慢性下痢(4週以上):4週間以上続く下痢は、感染症以外の原因、例えば後述するIBS(過敏性腸症候群)やIBD(炎症性腸疾患)など、器質的な病気を疑う必要があります。
下痢が続くと、水分と共に電解質(ナトリウムやカリウムなど)も失われ、脱水症状を引き起こす危険があります。特に高齢者や乳幼児は注意が必要です。
便秘(べんぴ)とは
便秘は、「排便回数が週に3回未満」という定義が広く知られていますが、実際には回数だけの問題ではありません。日本内科学会や関連ガイドラインでは、「便が硬くて排出しにくい」「強くいきまないと出ない」「排便後も便が残っている感じ(残便感)がある」「お腹が張って苦しい」といった、排便に伴う苦痛や不快感を慢性的に感じる状態を指します。
便秘は、大腸の動き(蠕動運動)が鈍くなる「弛緩性便秘」、ストレスなどで腸が過度に緊張する「痙攣性便秘」、便が直腸に達しても便意が起こらない「直腸性便秘」などに分類されます。慢性的な便秘は、生活習慣や食事内容が深く関わっていますが、大腸がんや腸閉塞など、腸の「通り道」が物理的に狭くなる器質的な病気が原因であることもあります。
受診を急ぐべき「警告症状(赤旗サイン)」
下痢や便秘が続く場合、以下の「警告症状(アラームサイン)」が一つでも当てはまれば、単なる機能不全ではなく、器質的な病気(IBD、大腸がん、重度の憩室炎など)の可能性を疑い、速やかに消化器内科を受診する必要があります。
- 血便・粘血便・黒色便:便に血が混じる、粘液と血が混じる、あるいはイカ墨のように黒い便が出る。血便は消化管からの出血を示す最も重要なサインです。
- 原因不明の体重減少:食事制限や運動をしていないのに、半年で体重が5%以上減少する。
- 発熱を伴う腹痛や下痢:38度以上の熱が続く場合。
- 夜間に症状で目覚める:特に夜間の下痢や腹痛で目が覚めるのは、機能性疾患(IBSなど)では比較的まれとされます。
- 40歳以上で初めて発症した便通異常:それまで快便だった人が、40歳を過ぎて急に慢性的な下痢や便秘になった場合。
- 貧血の進行:健康診断などで貧血を指摘された、あるいは立ちくらみや息切れがある。
これらのサインを見逃さず、早期に「診断と検査の流れ」に進むことが、重篤な疾患の早期発見・早期治療につながります。
IBS(過敏性腸症候群):診断の考え方と病型別の概観
「検査をしても『特に異常なし』と言われるのに、お腹の痛みや下痢・便秘がずっと続いている」。これは、過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome: IBS)の患者さんが抱える典型的な悩みです。IBSは、前述したような警告症状や器質的な病気(がん、炎症など)がないにもかかわらず、腹痛や腹部の不快感、そしてそれに伴う便通異常(下痢や便秘)が慢性的に続く機能性の疾患です。
この病気の根本には、単なる腸の問題だけでなく、脳と腸の間の情報伝達がうまくいかなくなる「脳腸相関」の異常が関わっていると考えられています。ストレスを感じるとお腹が痛くなる、というのはまさにこの脳腸相関の働きによるものです。IBSの患者さんでは、腸が通常よりも過敏な状態(内臓知覚過敏)になっており、わずかな刺激(食事、ガス、ストレスなど)でも痛みとして感じやすくなっています。
IBSの診断と分類
IBSの診断は、「Rome基準」などの国際的な診断基準に基づいて行われます。基本的には「腹痛が排便によって和らぐ」「腹痛と共に排便の回数や便の形状が変わる」といった特徴が、一定期間(例:過去3ヶ月のうち月に4日以上)続く場合に疑われます。IBSは機能性ディスペプシア(胃の不調)と合併することも少なくありません。
最も重要なのは、これが「除外診断」であるという点です。つまり、血液検査や便検査、場合によっては内視鏡検査(大腸カメラ)などを行い、IBDや大腸がん、感染症といった他の病気ではないことを確認した上で、初めてIBSと診断されます。
IBSは、その主な症状によって以下の4つのタイプ(病型)に分類され、治療法が異なります。
- 下痢型(IBS-D):慢性的または反復する腹痛と共に、頻繁に軟便や水様便を伴うタイプ。「通勤電車が怖い」「会議中にお腹が鳴ったらどうしよう」といった強い不安感を伴うこともあります。
- 便秘型(IBS-C):腹痛と共に、硬い便や兎糞状(コロコロした便)の便秘を伴うタイプ。強くいきまないと出ない、残便感が強いといった特徴があります。
- 混合型(IBS-M):下痢と便秘の両方を交互に繰り返すタイプ。症状の予測が難しく、対応に苦慮することが多いです。
- 分類不能型(IBS-U):上記のいずれにも明確に当てはまらないタイプ。
治療の基本的な考え方
IBSの治療は、一つの特効薬で治すというよりも、多角的なアプローチを組み合わせて症状をコントロールし、生活の質を改善することを目指します。
- 生活習慣・食事指導:規則正しい生活、十分な睡眠、適度な運動が基本です。食事については、特定の食品(高脂肪食、アルコール、カフェインなど)が症状を悪化させることがあります。近年では「低FODMAP(フォドマップ)食」と呼ばれる、特定の糖質を制限する食事法が有効な場合があることが知られています(詳細は「栄養・食事」のセクションで解説します)。
- 薬物療法:病型に合わせて薬を選択します。腸の動きを調整する薬、便の水分量を調節する薬(便秘型にはリナクロチドなど、下痢型にはラモセトロンなど)、腸内フローラのバランスを整えるプロバイオティクス(整腸剤)などが用いられます。
- 心理社会的アプローチ:ストレスが大きな要因である場合、認知行動療法(CBT)やリラクゼーション法が有効なこともあります。
IBSは命に関わる病気ではありませんが、患者さんの苦痛は深刻です。「気のせい」で済ませず、消化器専門医と相談しながら、自分に合った管理方法を見つけていくことが重要です。
IBD(炎症性腸疾患):潰瘍性大腸炎とクローン病
IBSが「機能性」の疾患であったのに対し、**炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease: IBD)**は、腸に明確な「炎症」や「潰瘍(かいよう:粘膜がえぐれること)」が起こる「器質性」の疾患です。原因不明の慢性的な炎症が続く自己免疫疾患の一種と考えられており、日本では難病(指定難病)に認定されています。
IBDは主に「潰瘍性大腸炎(UC)」と「クローン病(CD)」の二つに大別されます。どちらも20代〜30代の若年層での発症が多く、症状が落ち着いている「寛解期」と、悪化する「再燃期」を繰り返すことが特徴です。寛解期をいかに長く維持するかが治療の鍵となります。
潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis: UC)
潰瘍性大腸炎は、その名の通り、大腸の粘膜に炎症が起こる病気です。
難病情報センターによると、炎症は直腸から始まり、肛門側から奥に向かって連続的に広がるのが特徴です(クローン病のように飛び飛びにはなりません)。炎症が及ぶ範囲によって、直腸炎型、左側大腸炎型、全大腸炎型に分類されます。
主な症状は、血便、粘血便(血液と粘液が混じった便)、持続する下痢、腹痛です。重症化すると、発熱、体重減少、貧血などを伴うこともあります。また、長期にわたり全大腸炎型を患っている場合、大腸がんの発生リスク(Colitis-associated Cancer)が通常より高まるため、症状が落ち着いていても定期的な内視鏡検査(サーベイランス)が不可欠です。潰瘍性大腸炎が疑われる症状が見られたら、早期に専門医を受診することが寛解導入への近道です。
クローン病(Crohn’s Disease: CD)
クローン病は、潰瘍性大腸炎と異なり、口腔から肛門までの消化管のあらゆる部位に炎症が起こりうる病気です。特に小腸の末端部(回腸末端)と大腸が好発部位です。
難病情報センターの解説では、炎症が粘膜の浅い層にとどまるUCと違い、CDの炎症は腸の壁全層(粘膜下層から漿膜まで)に及ぶ「全層性炎症」であることが特徴です。また、炎症は非連続性(病変と正常な部分が飛び飛びに存在する「スキップ病変」)です。
主な症状は、腹痛、下痢、体重減少、発熱、全身倦怠感などです。UCと比べて血便の頻度は低いとされます。炎症が深層に及ぶため、腸が狭くなる「狭窄(きょうさく)」や、腸に穴が開いて他の臓器とつながってしまう「瘻孔(ろうこう)」、肛門周囲に膿がたまる「肛門周囲膿瘍」といった合併症を起こしやすいことも特徴です。狭窄や瘻孔が進行した場合、内科的治療だけでは管理が難しく、外科手術(腸管切除など)が必要となることもあります。
IBD治療の概観
IBDの治療は、まず炎症を抑えて寛解状態に導き、その状態をできるだけ長く維持すること(寛解維持)を目標とします。診断は内視鏡検査と生検(組織を採取して調べること)が基本となります。
治療薬は、炎症の強さや範囲、病型(UCかCDか)に応じて段階的に選択されます。
日本消化器病学会のIBD診療ガイドラインでは、以下のような薬剤が病態に応じて使用されます(個々の薬剤の詳細は「治療」のセクションで触れます)。
- 5-ASA製剤:腸の炎症を抑える基本的な薬(主にUCで使用)。
- ステロイド:強い抗炎症作用があり、活動期(再燃期)に寛解導入のために使用される。
- 免疫調整薬:免疫反応を抑えることで、ステロイドの減量や寛解維持に使用される。
- 生物学的製剤(抗体医薬):炎症を引き起こす特定の物質(TNF-αなど)をピンポイントで抑える強力な薬。寛解導入および維持に用いられます。
大腸憩室症・憩室炎:重症度で変わる治療の考え方
大腸憩室(けいしつ)とは、大腸の壁の一部が外側に向かって袋状に突出した「くぼみ」のことです。この憩室が多数存在している状態を「大腸憩室症」と呼びます。これは病気というよりも、加齢や食生活(食物繊維の不足)などによって生じる大腸の状態変化であり、特に症状がなければ(無症候性)、治療の必要はありません。日本の成人では、年齢と共に増加し、80歳以上では半数以上に見られるとも言われています。
問題となるのは、この憩室が炎症や出血を起こした場合です。
大腸憩室炎(けいしつえん)
憩室炎は、この「くぼみ」に便などが詰まり、細菌が感染して炎症が起きた状態です。主な症状は、腹痛(多くは左下腹部、ただし日本人では右側も多い)、発熱、吐き気などです。時に便通異常を伴うこともあります。
治療法は、その重症度によって大きく異なります。
英国NICEガイドラインなどでは、合併症のない軽症の憩室炎(痛みが軽く、発熱も高くない、腹膜刺激症状がない)の場合、抗菌薬(抗生物質)を必ずしも必要とせず、食事制限(絶食または流動食)と安静、経過観察で改善することがあるとされています。
しかし、以下のような重症・合併症例では、入院による点滴治療(抗菌薬、補液)が必要です。
- 痛みが非常に強い、高熱が続く
- 炎症が周囲に波及し、膿瘍(膿のたまり)を形成している
- 憩室が破れて穴が開く「穿孔(せんこう)」を起こし、腹膜炎を合併している
穿孔や大きな膿瘍の場合、ドレナージ(管を入れて膿を出す)や緊急手術(腸管切除)が必要となることもあります。憩室炎の診断と管理は、腹部CT検査などで炎症の程度を正確に評価することが鍵となります。
憩室出血
憩室内の血管が破れることで起こる出血です。腹痛を伴わず、突然、大量の新鮮血(真っ赤な血)が便として排出されるのが特徴です。多くは自然に止血しますが、出血量が多い場合は内視鏡(大腸カメラ)による止血術や、入院による管理が必要となります。
大腸ポリープ:切除とサーベイランスの基本
「健康診断の便潜血検査で陽性が出た」「大腸カメラを受けたらポリープがあると言われた」。このような経験をされた方も多いかもしれません。大腸ポリープは、大腸の粘膜がイボのように盛り上がったものです。
ポリープが見つかったときに最も心配なのは、「それががんではないか」「がんになるのではないか」という点でしょう。大腸ポリープにはいくつかの種類があり、すべてが危険なわけではありません。
ポリープの種類とがん化のリスク
ポリープは、その組織のタイプ(病理)によって大きく分類されます。
- 腺腫(せんしゅ):これが「前がん病変」と呼ばれる、将来的に大腸がんになる可能性のあるポリープです。腺腫の段階で切除することが、大腸がんの予防に直結します。
- 過形成性ポリープ:多くは小型で、がん化のリスクは非常に低いと考えられています。通常、治療の対象とならないことも多いです。
- 鋸歯状(きょしじょう)病変:近年注目されているタイプで、ギザギザした形状が特徴です。これらの一部(特にSSA/Pと呼ばれるタイプ)は、腺腫とは異なる経路でがん化するリスクがあり、切除の対象となります。
直腸ポリープを含むこれらの病変は、早期の段階では自覚症状がほとんどありません。そのため、症状がなくても定期的に検診を受けることが重要です。
ポリープの切除(内視鏡治療)
大腸ポリープ、特に腺腫や鋸歯状病変は、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)の際にそのまま切除することができます。これは「ポリペクトミー」と呼ばれます。小さなポリープはその場で切除(コールド・スネア・ポリペクトミーなど)できますし、ある程度大きなものでも内視鏡的粘膜切除術(EMR)という手技で切除可能です。これにより、開腹手術をすることなく、がんを予防できます。
切除後のサーベイランス(経過観察)
ポリープを切除したら「終わり」ではありません。
日本消化器病学会の大腸ポリープ診療ガイドラインでは、ポリープの数、大きさ、病理診断(腺腫かどうか、異型度(がん化の度合い)はどうか)に基づいて、次回の内視鏡検査を受けるべき間隔(サーベイランス間隔)が推奨されています。
例えば、リスクの低い小さなポリープ1個であれば5年後かもしれませんが、リスクの高いポリープ(大きい、数が多い、異型度が高い)であれば1年後、といった具合です。
便潜血検査で陽性となった場合は、これらの病変が存在する可能性があるため、必ず精密検査(大腸内視鏡検査)を受けるようにしてください。
よくある質問 (FAQ)
Q1: IBS(過敏性腸症候群)は、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を受けないと診断できませんか?
A: 必ずしもそうとは限りません。IBSの診断は、基本的に患者さんの症状の聞き取り(問診)と、国際的な診断基準(Rome基準など)に基づいて行われます。
日本の診療ガイドラインや
NICEガイドラインでも、前述した「警告症状(赤旗サイン)」(血便、体重減少、発熱、40歳以上の新規発症など)がなく、症状が典型的なIBSのものであれば、血液検査や便検査などで他の病気を除外した上で、内視鏡検査なしにIBSと臨床診断(症候学的診断)することが可能です。ただし、警告症状が一つでもある場合や、検診の便潜血検査で陽性が出た場合、あるいは治療への反応が悪い場合には、大腸がんやIBDなど他の器質的疾患を除外するために内視鏡検査が強く推奨されます。
Q2: 潰瘍性大腸炎(UC)とクローン病(CD)の最も大きな違いは何ですか?
A: どちらも慢性的な腸の炎症(IBD)ですが、最も大きな違いは「炎症が起こる場所」と「炎症の広がり方」です。
潰瘍性大腸炎(UC)は、炎症が大腸だけに限定され、直腸から連続的(つながって)に広がります。炎症は粘膜の浅い層が中心です。
一方、クローン病(CD)は、口から肛門までの消化管のあらゆる場所(特に小腸と大腸)に起こり得ます。炎症は非連続的(飛び飛び)に発生し、腸の壁の深い層まで及ぶことが特徴です。これにより、UCでは血便が、CDでは狭窄や瘻孔といった合併症が起こりやすいという違いにもつながります。
Q3: 大腸憩室炎になったら、必ず抗菌薬(抗生物質)が必要ですか?
A: いいえ、必ずしも必要ではありません。
英国NICEガイドラインなど近年の知見では、重症度によって対応が分かれます。腹痛が軽度で、発熱もないか微熱程度、血液検査での炎症反応も低く、CT検査などで膿瘍や穿孔といった合併症がない「非合併症性の軽症憩室炎」の場合は、抗菌薬を使用せず、絶食や流動食などの食事制限と安静、対症療法(鎮痛薬など)だけで改善することが多いとされています。ただし、高熱がある、痛みが強い、合併症がある「重症例」や、免疫力が低下している患者さんには、入院の上で抗菌薬の点滴治療が必要です。自己判断はせず、医師が重症度を評価した上での判断に従うことが重要です。
Q4: 大腸ポリープは、見つかったらすべて切除する必要がありますか?
A: すべてを切除する必要はありませんが、「将来がんになる可能性のあるポリープ」は原則として切除が推奨されます。
日本のガイドラインに基づき、切除が推奨されるのは主に「腺腫」と「鋸歯状病変」です。これらは大きさに関わらず、がん化のリスクがあるため、内視鏡的に切除することが大腸がんの予防につながります。一方で、「過形成性ポリープ」は、特に直腸にできる小型のものはがん化のリスクが極めて低いため、切除せずに経過観察とすることが一般的です。ただし、ポリープの種類を肉眼だけで100%判断するのは難しいため、最終的には医師の判断(生検や拡大内視鏡による評価)によります。
Q5: 普段と違う下痢や便秘が続きます。どのタイミングで病院に行くべきですか?
A: 症状の程度と「警告症状」の有無で判断します。以下の場合は、早急に消化器内科を受診してください。
- 血便(真っ赤な血、粘液と混じった血、黒い便)が出る
- 発熱(38度以上)と激しい腹痛を伴う
- 原因不明の体重減少(半年で5%以上)がある
- 40歳以上で、今までにない便通異常(下痢や便秘)が急に始まり、2週間以上続く
- 夜中に腹痛や下痢で目が覚めることが頻繁にある
これらはIBSのような機能性疾患ではなく、IBD、大腸がん、重度の憩室炎など、精密検査が必要な器質的疾患のサイン(警告症状)である可能性が高いためです。これらのサインがなくても、市販薬を試しても症状が改善しない、日常生活に支障が出ている場合も、一度専門医に相談してください。
肝臓の病気(脂肪肝・B/C型肝炎・肝硬変・アルコール関連障害)
前節では、食べ物の消化・吸収の最終段階を担う小腸・大腸の病気について解説しました。本節では、消化器系の中でも「体内の化学工場」とも呼ばれる最も重要な臓器の一つ、肝臓に焦点を当てます。
肝臓は、栄養素の代謝、有害物質の解毒、胆汁の生成など、生命維持に不可欠な500以上の機能を担う「沈黙の臓器」です。自覚症状が出にくいため、健康診断などで肝機能の数値(ALTやASTなど)の異常を指摘されて初めて、不安を感じる方が非常に多いのが特徴です。ここでは、現代の日本において特に問題となる主要な肝疾患―脂肪肝(MASLD)、B型・C型肝炎、肝硬変、そしてアルコール関連肝障害―について、その原因、最新の治療法、そして生活上の注意点を深く掘り下げて解説します。
脂肪肝(MASLD)とは:NAFLDとの違いと最新定義
健康診断で「脂肪肝」と指摘された経験はありますか?これは、肝臓に中性脂肪が過剰に蓄積した状態(肝細胞の30%以上)を指します。かつて脂肪肝は「お酒の飲み過ぎ」が主な原因と考えられていましたが、近年、お酒をほとんど飲まない人にも同様の脂肪肝が急増していることが問題視されています。
この「お酒を飲まない人の脂肪肝」は、以前はNAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)と呼ばれていました。しかし2023年以降、国際的なコンセンサスにより、この病態が肥満、2型糖尿病、脂質異常症といった「代謝異常」と強く関連していることを明確にするため、MASLD(代謝機能障害関連脂肪性肝疾患)という新しい呼称に移行しつつあります。
重要なのは、MASLDは単なる「脂肪が溜まった状態」ではないという点です。MASLDの新しい定義では、この代謝異常が病気の中心にあると位置づけられました。MASLDの一部は、肝臓に炎症や線維化(組織が硬くなること)を引き起こすMASH(代謝機能障害関連脂肪肝炎、旧NASH)へと進行します。MASHを放置すると、肝硬変や肝がんへと進展するリスクがあるため、早期の対策が不可欠です。
MASLDの治療の基本は、薬物療法ではなく、その根本原因である代謝異常の改善、すなわち生活習慣の修正です。脂肪肝を改善するための食事戦略としては、総摂取カロリーの制限、バランスの取れた栄養摂取が中心となります。特に、体重の7〜10%の減量が肝臓の脂肪量と炎症を劇的に改善させることが多くの研究で示されています。軽度の脂肪肝(ステージ1)であっても、それは体からの重要な警告サインであり、将来のMASHへの進行を防ぐための第一歩と捉えることが重要です。
B型肝炎(HBV):核酸アナログ製剤による生涯管理
B型肝炎は、B型肝炎ウイルス(HBV)の感染によって引き起こされる肝臓の炎症です。日本では、かつて母子感染(出産時の母親から子供への感染)が主な感染経路でしたが、1985年からの母子感染防止事業と、2016年からの乳児への定期接種(ワクチン)により、国立感染症研究所の報告によれば、小児の新たなキャリア発生は劇的に減少しました。
しかし、成人においては性交渉などによる水平感染のリスクが依然として存在します。HBV感染は、急性肝炎で終わる場合と、ウイルスが体内に留まり続ける「キャリア」と呼ばれる慢性状態になる場合があります。A型やC型肝炎との違いを理解することも大切です。
慢性B型肝炎の治療目標は、ウイルスの完全排除(完治)ではなく、ウイルスの増殖を強力に抑制し、肝炎を鎮静化させ、肝硬変や肝がんへの進行を防ぐことです。日本肝臓学会のB型肝炎治療ガイドラインによれば、現在の標準治療は「核酸アナログ製剤」(エンテカビル(ETV)、テノホビル(TDF/TAF)など)と呼ばれる経口薬(飲み薬)です。
この薬はウイルスの増殖をDNAレベルで抑え込み、肝機能(ALT値)を正常化させます。<多くの患者さんでは生涯にわたる服薬が必要となりますが、正しく服用を続けることで、肝硬変や肝がんのリスクを大幅に低下させることが可能です。「B型肝炎は治るのか」という疑問に対しては、「機能的治癒(ウイルス量が検出限界以下でHBs抗原が陰性化)」という状態を目指すことはありますが、核酸アナログによる「生涯管理」が基本となります。また、感染予防にはB型肝炎ワクチンの接種が最も効果的です。
C型肝炎(HCV):DAA治療で「治癒」を目指す時代
C型肝炎は、C型肝炎ウイルス(HCV)の感染による肝臓の炎症です。かつては血液製剤や注射器の使い回しなどで感染が広がりました。B型肝炎と異なり、C型肝炎は慢性化率が非常に高く(70%以上)、放置すると高い確率で肝硬変、肝がんへと進行するため、非常に恐れられていました。
しかし、C型肝炎治療は2014年以降、劇的な変革を遂げました。かつての標準治療であったインターフェロン(注射薬)は、副作用が強く、治療効果も限定的でした。これに対し、新しく登場した「直接作用型抗ウイルス薬(DAA)」は、経口薬(飲み薬)でありながら、世界保健機関(WHO)の報告でも示されている通り、95%以上という極めて高い確率でウイルスを排除(治癒)できるようになったのです。
DAAによる治療期間は、ウイルスの型や肝臓の状態にもよりますが、多くの場合8週間から12週間です。副作用もインターフェロン時代に比べて格段に少なく、高齢者や合併症を持つ方でも安全に治療が受けられるようになりました。C型肝炎の最新治療と公的支援については、日本のガイドラインでも詳細に定められており、医療費助成制度も充実しています。
ただし、DAA治療でウイルスが消えた(SVR:持続的ウイルス陰性化)後も、注意が必要です。特に、治療開始時点ですでに肝臓の線維化が進行していた(肝硬変に近い)方は、ウイルスが消えた後でも肝がんが発生するリスクが残ります。そのため、治療後も定期的な肝臓のサーベイランス(超音波検査など)を継続することが肝癌診療ガイドラインでも強く推奨されています。また、ウイルス排除後も、肝臓をいたわる食事療法を心がけることが望ましいです。
肝硬変:進行抑制と合併症管理の重要性
肝硬変(かんこうへん)は、上記のB型肝炎、C型肝炎、MASH(脂肪肝炎)、アルコール性肝障害などが長期間続くことによって、肝臓全体が硬く線維化し、その機能が著しく低下した「肝臓病の終末像」とも言える状態です。肝硬変と診断されると、多くの方が深刻な不安を覚えます。
肝硬変の診療で重要なのは、まず「代償性」か「非代償性」かを見極めることです。
- 代償性肝硬変: 肝臓は硬くなっているものの、まだかろうじて機能が保たれている状態。自覚症状は乏しいことが多いです。
- 非代償性肝硬変: 肝臓の機能が破綻し、様々な合併症が出現した状態。予後(病気の見通し)が厳しくなります。
肝硬変のステージ分類を理解し、自分の状態を把握することが治療の第一歩です。
治療の目標は、原因疾患(B型・C型肝炎、MASLD、禁酒など)の治療を継続し、非代償性への進行を防ぎ、合併症を早期に発見・治療することです。肝硬変診療ガイドライン2020で特に重視されているのが、以下の合併症管理です。
- 腹水: 肝臓でアルブミン(タンパク質)が作れなくなり、お腹に水が溜まる状態。塩分制限や利尿薬で管理します。腹水の管理はQOL(生活の質)に直結します。
- 食道・胃静脈瘤: 肝臓が硬くなると、血液が肝臓を通りにくくなり、食道や胃の静脈に迂回してこぶ(静脈瘤)を作ります。これが破裂すると命に関わる大出血(吐血・下血)となるため、内視鏡で定期的に監視し、予防的治療(結紮術など)を行います。食道静脈瘤の治療は予防が鍵です。
- 肝性脳症: 肝臓で解毒されるはずのアンモニアなどが脳に達し、意識障害や異常行動を引き起こします。食事(タンパク質制限は昔の話で、現在はむしろ筋肉減少を防ぐため適正な摂取が推奨されます)や薬剤で管理します。
また、肝硬変は肝がんの最大のリスク因子であり、定期的なサーベイランス(超音波検査と腫瘍マーカー)が不可欠です。
アルコール関連肝障害(ALD):国の飲酒ガイドラインと断酒
アルコール関連肝障害(ALD)は、長期間の過度な飲酒によって引き起こされる肝臓の障害の総称です。病態は、アルコール性脂肪肝から始まり、炎症を伴うアルコール性肝炎、そして最終的にはアルコール性肝硬変へと進行します。
「どのくらいの飲酒量が危険なのか」という疑問は非常に重要です。厚生労働省が2024年に公表した「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」では、疾患リスクを高める飲酒量として、1日あたりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性で20g以上と示されています(純アルコール20gは、ビール中瓶1本、または日本酒1合に相当)。
ただし、これはあくまで目安であり、アルコールの影響には大きな個人差があります。特に、MASLD(脂肪肝)の原因となる肥満や代謝異常がある人が飲酒をすると、肝障害のリスクが相乗的に高まることが知られています。
アルコール関連肝障害の治療で、唯一かつ最も重要なことは「断酒(だんしゅ)」です。アルコール性脂肪肝や、軽度のアルコール性肝炎の段階であれば、断酒によって肝臓は劇的に改善する可能性があります。しかし、一度肝硬変にまで進行してしまうと、断酒をしても肝臓が元に戻ることはありません。アルコール性肝炎は、重症化すると短期間で命を落とす危険な病態(重症アルコール性肝炎)となることもあり、専門的な治療と断酒の継続的な支援(専門外来や自助グループなど)が不可欠です。
肝臓は、その機能が低下してもなかなか症状を出さないため、問題が表面化した時にはすでに深刻な状態になっていることも少なくありません。次節では、肝臓と密接に関連し、消化を助ける胆道(胆嚢)と膵臓の病気について解説します。
胆道・膵臓の病気(胆石・胆嚢炎・胆管炎・膵炎・外分泌不全)
前節では「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓の病気について解説しました。本セクションでは、その肝臓と密接に関連し、消化と吸収に不可欠な役割を担う「胆道(胆嚢・胆管)」と「膵臓」の病気について掘り下げます。
これらの臓器の病気は、ある日突然、激しい腹痛や発熱として現れることが多く、迅速な対応が求められる緊急性の高い状態(急性胆嚢炎、急性胆管炎、急性膵炎など)から、慢性的に消化不良や栄養障害を引き起こす状態(慢性膵炎、膵外分泌不全)まで多岐にわたります。特に、診断と治療のタイミングが予後を大きく左右するため、日本の診療ガイドライン(JSGE/TG18)や最新の国際的なエビデンスに基づいた理解が不可欠です。[1, 3]
胆石症と急性胆嚢炎
「胆石」と聞くと、多くの方がご存知かもしれません。これは主にコレステロールが固まったもので、肥満、女性、妊娠、加齢などがリスクとされています。[1] 重要なのは、胆石があるだけでは必ずしも症状が出るとは限らない点です。「無症候性胆嚢結石」と呼ばれるこの状態は、胆石症の多くを占め、原則として手術はせず経過観察となります。(日本消化器病学会 胆石症GL 2021)[1]
しかし、この石が胆嚢の出口(胆嚢管)に詰まると、胆汁の流れが滞り、細菌感染を伴う「急性胆嚢炎」を引き起こします。[3] 症状は、典型的には食後のみぞおちから右上腹部にかけての激しい痛みや発熱です。診断は、腹部超音波検査が第一選択となります。[1, 9]
急性胆嚢炎と診断された場合、日本のガイドライン(TG18)に基づく重症度評価が行われ、多くの場合、入院中に早期の腹腔鏡下胆嚢摘出術(LC)が推奨されます。[3, 4, 11] これは、在院日数を短縮し、胆嚢炎の再発を防ぐためです。[11, 12] 現在は腹腔鏡下手術が主流ですが、癒着が強い場合などには開腹手術が選択されることもあります。重症で手術リスクが高い場合は、まず胆嚢ドレナージ(PTGBDなど)で炎症を抑えることもあります。[3]
急性胆管炎と総胆管結石
胆嚢結石が胆嚢管を通過して、さらに下流の「総胆管」に詰まると、事態はより緊急性を増します。これが「総胆管結石」です。[1] ここで細菌感染が加わると「急性胆管炎」となり、これは胆嚢炎よりも重篤化しやすい病態です。
発熱、黄疸、腹痛(シャルコーの三徴)が揃うと典型的ですが、高齢者では症状が揃わないこともあります。重症化すると意識障害やショック(レイノルズの五徴)を来たし、命に関わります。[3, 4] 診断では、総胆管結石の存在をEUS(超音波内視鏡)やMRCP(MRI)で確認します。[1]
治療の鍵は「時間」です。TG18ガイドラインでは、重症の急性胆管炎は24時間以内、中等症でも48時間以内の緊急胆道ドレナージ(内視鏡的ドレナージ:ERCP/ENBDなど)が強く推奨されています。[3, 4] ドレナージで炎症を鎮静化させた後、内視鏡的に結石を除去し(ESTなど)、最終的には胆石の供給源である胆嚢を摘出することが、再発予防の基本戦略となります。[1]
急性膵炎(胆石性とアルコール性)
膵臓は、強力な消化酵素を分泌する重要な臓器です。急性膵炎は、この膵臓が自ら分泌した酵素によって自己消化を起こし、激しい炎症を生じる病気です。二大原因は「胆石」と「アルコール」です。[10] アルコール性肝障害と同様、アルコールの長期多飲が膵臓に直接的なダメージを与えます。症状は、背中に突き抜けるような激しい上腹部痛と嘔吐が特徴です。
診断は、①特徴的な腹痛、②血液中の膵酵素(アミラーゼやリパーゼ)の上昇、③画像所見(CTなど)のうち2項目以上を満たすことで行われます。[10]
急性膵炎の初期治療で最も重要なのは輸液です。かつては「積極的(アグレッシブ)輸液」が推奨されていましたが、2022年のNEJMに掲載されたWATERFALL試験により、過剰な輸液はむしろ有害事象を増やすことが示されました。[6] 現在では、過度の輸液を避けた「中等量・目標指向」の輸液戦略が安全で推奨されています。[6]
原因が胆石の場合(胆石性膵炎)、胆管炎や胆道閉塞を合併していれば早期のERCPが、そうでなくても、PONCHO試験が示すように、入院中に早期の胆嚢摘出を行うことが再発予防に極めて有効です。[7, 10] 重症例では経腸栄養が優先され、予防的な抗菌薬投与は推奨されません。[10]
慢性膵炎と膵外分泌不全(PEI)
急性膵炎が治癒可能な可逆的な炎症であるのに対し、慢性膵炎は、主に長期間のアルコール摂取などによって膵臓が線維化し、機能が不可逆的に失われていく病気です。(日本消化器病学会 慢性膵炎GL 2021)[2]
膵臓の機能が低下すると、消化に必要な「膵酵素」の分泌が不足します。これが「膵外分泌不全(PEI)」です。[8] PEIになると、特に脂肪の消化吸収が著しく障害されます。その結果、「脂肪便」(便が白っぽく、水に浮き、油が漏れ出るような便)や、慢性的な下痢、体重減少、脂溶性ビタミンの欠乏といった栄養障害を引き起こします。[8] 診断は、便中エラスターゼ-1検査(便中の膵酵素を測定)などで簡便に評価できます。[8]
治療の柱は、不足した消化酵素を食事のたびに補う「膵酵素補充療法(PERT)」です。[2, 8] 慢性膵炎の管理には、厳格な禁酒と栄養指導が不可欠です。[2]
消化器の感染症・食中毒(胃腸炎・ノロ/ロタ・寄生虫の基礎)
前節まで、胆道や膵臓といった特定の臓器の慢性的な疾患について詳しく見てきました。本節では、視点を大きく変え、私たちの日常生活に最も身近で、かつ突然襲いかかってくる「外からの脅威」——すなわち消化器の感染症と食中毒について、その基礎から徹底的に解説します。突然の嘔吐や止まらない下痢に襲われたとき、多くの方が「いったい何が原因なのか?」「何か悪いものを食べたか?」「家族や職場でうつしてしまうのではないか?」と、強い不安と焦燥感に駆られます。特に、体力の弱い小さなお子様やご高齢の家族が同じ症状を呈した場合、その心配は計り知れません。
これらの急性胃腸炎は、目に見えないウイルス、細菌、あるいは寄生虫によって引き起こされます。それぞれの敵には特徴があり、感染経路も、対処法も、予防策も異なります。本節では、これらの敵の正体を正しく理解し、科学的根拠に基づいた予防策と、万が一の時のための適切な初期対応(セルフケア)を学ぶことで、その漠然とした不安を「具体的な行動」に変えるための知識を深めていきます。
ウイルス性胃腸炎の主役:ノロウイルスとロタウイルス
急性胃腸炎の多くはウイルスが原因であり、特にノロウイルスとロタウイルスはその代表格です。これらのウイルスは細菌とは異なり、食品の中で増殖するのではなく、ごく少量が食品や環境、人を介して体内に入ることで爆発的に感染を広げます。
ノロウイルス:冬の流行と強力な感染力
毎年冬になると「ノロウイルスによる集団感染」のニュースが報じられるように、ノロウイルスは日本の冬季における感染性胃腸炎の最大の原因の一つです(国立感染症研究所のサーベイランス[2])。多くの方が「カキなどの二枚貝」を感染源として連想しますが、実際には感染者の糞便や嘔吐物が乾燥し、そこに含まれるウイルスが埃と共に舞い上がり、それを吸い込むこと(飛沫感染・塵埃感染)や、汚染された手で触れたドアノブなどを介した接触感染(環境感染)も非常に多いのが特徴です。
ノロウイルスの最も恐ろしい点は、その「強力な感染力」です。わずか10〜100個程度のウイルス粒子で感染が成立すると言われています。これは、感染者の嘔吐物(数百万〜数億個/g)や糞便(数億〜数百億個/g)が、いかに危険な感染源であるかを示しています。さらに、ノロウイルスは「エンベロープ」という脂質の膜を持たないため、一般的なアルコール手指消毒剤が効きにくいという厄介な性質を持っています。
したがって、ノロウイルス対策の基本は「物理的な除去」と「化学的な不活化」です。
- 手洗い:アルコール消毒が効きにくいため、何よりも「石けんと流水による物理的な手洗い」が最も重要です。指の間、爪の先まで30秒以上かけて丁寧に洗い流すことが推奨されます。
- 環境消毒:ドアノブ、手すり、トイレのレバーなど、手が頻繁に触れる場所の消毒が必須です。この時、アルコールではなく「次亜塩素酸ナトリウム」(家庭用塩素系漂白剤)を適切な濃度(汚染がひどい場所は1000〜5000 ppm、通常の環境表面は200 ppm程度)に薄めて使用する必要があります(米国CDCの推奨[9])。嘔吐物を処理する際は、使い捨ての手袋とマスクを着用し、外側から内側へ静かに拭き取り、広範囲を塩素系消毒剤で覆うように消毒します。
ノロウイルスに感染した場合の症状は、感染性の原因として典型的なもので、突然の激しい嘔吐と水様性の下痢、腹痛、軽度の発熱を伴いますが、通常1〜3日程度で自然に回復します。しかし、乳幼児や高齢者は脱水症状を起こしやすいため、後述する水分補給が極めて重要になります。
ロタウイルス:乳幼児の重症化とワクチンによる予防
ロタウイルスは、ノロウイルスと並ぶ乳幼児の急性胃腸炎の主要な原因ウイルスです。特に生後6ヶ月から2歳の乳幼児が感染すると重症化しやすく、激しい嘔吐と「米のとぎ汁」や「白っぽいレモンのような」と表現される特徴的な水様性下痢を繰り返し、急速に脱水症状が進行することがあります。かつては、乳幼児が冬場に脱水症で入院する最大の原因でした。
しかし、この状況は日本において大きく変わりました。2020年10月からロタウイルスワクチンが定期接種化されたのです(厚生労働省[4])。これは飲むタイプの生ワクチンで、生後14週6日までに初回接種を完了することが推奨されています[7]。このワクチンの普及により、ロタウイルス胃腸炎による重症化や入院は劇的に減少しました。ロタウイルスもノロウイルス同様、アルコール消毒が効きにくいため、感染対策の基本は石けんによる手洗いと次亜塩素酸ナトリウムによる環境消毒です。
細菌性食中毒と寄生虫:見えざる敵への対策
ウイルス以外にも、細菌や寄生虫が食中毒の原因となります。食中毒は、ウイルスのように「食品に付着した」ものだけでなく、細菌のように「食品の中で増殖した」ものを食べることでも発生します。日本の食中毒統計では、カンピロバクターやサルモネラといった細菌が常に上位を占めています(厚生労働省[8])。
細菌性食中毒の基本(サルモネラ、カンピロバクター)
細菌性食中毒は、ウイルス性と比べて高熱や激しい腹痛、時には血便を伴うことが多いのが特徴です。
- カンピロバクター:鶏肉の生食や加熱不十分(鶏わさ、鶏レバー刺しなど)が主な原因です。潜伏期間が2〜7日と比較的長いのが特徴で、発熱、腹痛、下痢を引き起こします。
- サルモネラ:卵やその加工品、食肉などが原因となりやすいです。高熱と腹痛、下痢が主症状です。
- 腸管出血性大腸菌(EHEC, O-157など):牛肉の生食(ユッケ、レバ刺し)や加熱不十分なハンバーグ、あるいは汚染された野菜から感染することがあります。激しい腹痛と血便が特徴で、特に小児や高齢者では溶血性尿毒症症候群(HUS)という重篤な合併症を引き起こす危険があります。
細菌性食中毒の予防は、「つけない」(手洗いや器具の使い分け)、「増やさない」(低温保存)、「やっつける」(中心部までの十分な加熱)という食中毒予防の三原則が基本となります。後述しますが、細菌が原因であっても、多くの場合は抗菌薬(抗生物質)を使わずに自身の免疫力と対症療法で回復します。
アニサキスとその他の寄生虫
寄生虫も消化器症状の原因となります。日本で最も注意が必要なのはアニサキスです。
- アニサキス:サバ、アジ、イカ、サンマなどの魚介類に寄生している線虫です。魚介類を生で食べた後、数時間から十数時間後に、みぞおちや腹部に「キリで刺すような」と表現される激しい急性腹痛と嘔吐を引き起こします。これはアニサキスが胃や腸の壁に突き刺さることによる物理的な刺激と、アレルギー反応が複合して起こると考えられています。
最大の注意点は予防法です。アニサキスは一般的な料理で使う程度の酢(しめ鯖など)、塩、醤油、わさびでは死滅しません。予防するには「加熱(70℃以上、または60℃で1分以上)」または「冷凍(-20℃で24時間以上)」が必須です(厚生労働省[3])。アニサキス症が疑われた場合、内視鏡で虫体を確認し、摘出するのが最も確実な治療法となります。 - その他の寄生虫:海外渡航歴や特定の食品摂取に関連して、ジアルジア(ランブル鞭毛虫)やアメーバ赤痢、クリプトスポリジウムなども下痢症の原因となります。ジアルジアは脂っこい便(脂肪性下痢)や腹部膨満、アメーバ赤痢はイチゴゼリー状の粘血便が特徴とされますが、診断には便検査や血液検査が必要です。
治療の原則:脱水対策と抗菌薬の適正使用
原因がウイルスであれ細菌であれ、急性胃腸炎の治療で最も重要な原則は共通しています。それは「失った水分と電解質を補うこと」であり、そして「不要な薬を使わないこと」です。
最優先事項:経口補水療法(ORS)の役割
嘔吐や下痢で最も怖いのは「脱水症」です。特に乳幼児や高齢者は、体内の水分バランスが崩れやすく、急速に重症化することがあります。この時、「水分なら何でもいい」と考えるのは間違いです。水だけを大量に飲んでも体液が薄まってしまいますし、スポーツドリンクやジュースは糖分が多すぎて、かえって下痢を悪化させる(浸透圧性下痢)可能性があります。
ここでの主役は「経口補水液(ORS: Oral Rehydration Solution)」です。ORSは、ブドウ糖と電解質(ナトリウム、カリウムなど)が、腸から最も効率よく吸収されるように最適化された「飲む点滴」です。薬局などで市販されています。ORSを常温で、一度にがぶ飲みするのではなく、スプーンやコップで少量ずつ(5〜10分おきに一口ずつ)頻回に摂取するのがコツです。正しい水分補給が、重症化を防ぐ鍵となります。
また、世界保健機関(WHO)[19]は、特に開発途上国の小児の急性下痢症に対して、ORSと並行して「亜鉛」の補充(10〜14日間)を強く推奨しています。亜鉛は腸の粘膜の修復を助け、下痢の期間を短縮し、再発を予防する効果があるとされています[8]。
抗菌薬(抗生物質)は本当に必要か?
下痢や発熱があると、「早く治したいから抗生物質(抗菌薬)が欲しい」と考える方がいるかもしれません。しかし、急性下痢症の治療において、抗菌薬の出番は非常に限定的です。
その理由は以下の通りです:
- 原因の大半はウイルス:前述の通り、急性胃腸炎の多くはノロウイルスやロタウイルスが原因であり、抗生物質はウイルスには全く効果がありません。
- 細菌性でも自然治癒が基本:健康な成人の場合、サルモネラやカンピロバクターによる胃腸炎も、抗菌薬を使用しなくても自身の免疫力で数日以内に自然に回復することがほとんどです(NCGM抗菌薬適正使用の手引き[5])。
- かえって悪化する危険性:腸管出血性大腸菌(O-157など)の場合、不適切な抗菌薬の使用が菌を刺激し、かえってHUSなどの重篤な合併症のリスクを高めることが知られています。
- 副作用と耐性菌のリスク:抗菌薬は、病原菌だけでなく腸内の「善玉菌」まで殺してしまいます。その結果、抗生物質関連下痢症や、クロストリディオイデス・ディフィシル(CD)腸炎といった、より深刻な腸炎を引き起こすことさえあります。また、不必要な使用は薬剤耐性(AMR)菌を生み出す原因ともなります。
抗菌薬が推奨されるのは、海外渡航後の重症な下痢(旅行者下痢症の一部)、赤痢、コレラ、あるいは免疫不全者の重症感染など、ごく限られた場合です(厚労省マニュアル[6])。自己判断で過去にもらった抗菌薬を飲むことは、絶対に避けるべきです。
よくある質問(FAQ)
Q1: ノロウイルスにアルコール消毒は効きますか?
A: 効果は限定的です。ノロウイルスはアルコールへの抵抗性が強いため、アルコール手指消毒剤だけでは不十分とされています。予防の基本は、石けんと流水による「物理的な手洗い」を徹底することです。環境(ドアノブ、トイレ、床など)の消毒には、アルコールではなく「次亜塩素酸ナトリウム」(家庭用塩素系漂白剤)を1000〜5000 ppmの濃度に薄めて使用することが強く推奨されます[9]。
Q2: 子どもが胃腸炎のとき、まず何をすべきですか?
A: 最優先事項は「脱水予防」です。市販の「経口補水液(ORS)」を、スプーンやスポイトを使い、少量(5〜10mL程度)ずつ、5〜10分おきに根気よく与え続けてください。一度にたくさん飲ませると嘔吐を誘発することがあります。また、WHO[8]は小児の下痢症に対して「亜鉛」の補充(10〜14日間)を推奨しており、回復を早める効果が期待できます。
Q3: どのような場合に病院へ行くべきですか?
A: 以下の「赤旗サイン」が見られる場合は、脱水症や重篤な感染症の可能性があるため、速やかに医療機関を受診してください(英国NHS[18])。
- 尿が半日以上出ていない、あるいは色が濃く量が極端に少ない
- 口の中や舌がカラカラに乾いている、泣いても涙が出ない
- ぐったりしていて反応が鈍い、呼びかけにこたえにくい
- 血便や黒色便、激しい腹痛が持続する
- 39℃以上の高熱が続く
- 嘔吐が激しく、経口補水液(ORS)すら全く受け付けない
特に乳幼児、高齢者、妊娠中の方、基礎疾患(糖尿病、免疫不全など)がある方は、重症化しやすいため、早めの受診が賢明です。受診すべき危険なサインを見逃さないことが重要です。
Q4: 急性下痢症に抗生物質は必要ですか?
A: ほとんどの場合、不要です。急性下痢症の多くはウイルス性であり、抗生物質は効きません。軽症の細菌性胃腸炎(サルモネラ、カンピロバクターなど)も、多くは自然に治癒します[5]。自己判断で抗生物質を飲むと、腸内細菌のバランスを崩して回復を遅らせたり、耐性菌を生み出したりするリスクがあるため、医師の診断に基づかない使用は避けてください。
Q5: アニサキスは酢や醤油で防げますか?
A: 防げません。アニサキスは酢、塩、醤油、わさびなど、一般的な調味料に対する抵抗力が非常に強いです。しめ鯖でアニサキス症が起こるのもこのためです。アニサキスを予防する確実な方法は、「加熱(70℃以上、または60℃で1分以上)」または「冷凍(-20℃で24時間以上)」のどちらかです[3]。新鮮な魚介類であっても、生で食べる際は注意が必要です。
栄養・食事・サプリの実践(低FODMAP・経口補水・肝疾患の食事・サプリ安全性)
前節で解説した消化器感染症や食中毒のように、急激な下痢や嘔吐に見舞われた際の水分補給から、過敏性腸症候群(IBS)や肝疾患といった慢性的な症状管理まで、「栄養と食事」は消化器疾患の治療において極めて重要な役割を果たします。薬物治療と並行し、あるいはそれ以上に、日々の食事が症状を左右することも少なくありません。
しかし、情報が溢れる中で「何を食べ、何を避けるべきか」を自己判断するのは困難です。このセクションでは、科学的根拠に基づき、特に重要ないくつかの食事療法とサプリメントの安全性について、その実践方法と注意点を詳しく解説します。
低FODMAP(フォドマップ)食:IBS症状管理の実践
お腹の張り、腹痛、下痢や便秘を繰り返す過敏性腸症候群(IBS)の症状に悩む人にとって、「低FODMAP食」は有効な選択肢の一つです。FODMAPとは、小腸で吸収されにくい特定の糖質(発酵性オリゴ糖、二糖類、単糖類、ポリオール)の頭文字を取ったものです。これらが高FODMAP食品として腸に達すると、腸内細菌によって発酵し、ガスが発生したり、腸を刺激したりして、お腹の張りやガスの問題を引き起こすと考えられています。
多くのシステマティックレビューやメタ解析で、低FODMAP食がIBSの症状(腹痛、膨満感など)を有意に改善することが示されています。[3] しかし、重要なのは、これが「生涯続ける食事法ではない」という点です。低FODMAP食は、以下の3段階で進めるのが基本です。[3, 6]
- 導入期(制限期):まず4〜8週間、高FODMAP食品を厳格に制限し、症状が改善するかどうかを見極めます。
- 再導入期(チャレンジ期):症状が改善したら、高FODMAP食品を少量ずつ試し、どの食品が自分に合わないのか(耐性)を特定します。
- 個別化期(維持期):自分に合わないと特定された食品のみを避け、他の食品は可能な限り摂取する、個別化された食事を続けます。
このプロセスは非常に複雑であり、自己流で行うと栄養不足を招いたり、不必要な食品除去で腸内細菌叢(腸内フローラ)に悪影響を与えたりする可能性があります。[6] そのため、英国NICE(国立医療技術評価機構)のガイドラインなどでは、一般的な食事指導で改善しない場合に、管理栄養士などの専門家の指導の下で低FODMAP食を試すことが推奨されています。[2]
ORS(経口補水液):脱水時の命綱
食中毒や感染性腸炎の管理において、最も警戒すべきは下痢や嘔吐による「脱水症」です。この脱水症の予防と治療の基本となるのが「経口補水療法(Oral Rehydration Therapy)」であり、そのために用いられるのがORS(Oral Rehydration Solution:経口補水液)です。
ORSは、単なる水分ではなく、ナトリウム(Na)とブドウ糖(グルコース)が特定の比率で配合されています。これは、腸が水分を吸収する際に、ナトリウムとブドウ糖がセットで運ばれる「共輸送体」という仕組みを利用するためです。このバランスが崩れていると、水分は効率よく吸収されません。
ここで大きな誤解が生じやすいのが、「スポーツドリンク」との違いです。一般的なスポーツドリンクは、脱水時の下痢や嘔吐時の水分補給には不向きです。[1, 9] なぜなら、ORSに比べてナトリウム濃度が低く、糖濃度(浸透圧)が高すぎるため、かえって腸に負担をかけ、下痢を悪化させる可能性があるからです。
WHO(世界保健機関)/UNICEF推奨の低浸透圧ORSの組成:[4, 5, 7]
- ナトリウム(Na):75 mmol/L
- ブドウ糖(グルコース):75 mmol/L
- 浸透圧:245 mOsm/L
日本では、この基準に基づいた市販のORS(OS-1など)が薬局で入手可能です。特に乳幼児や高齢者は脱水が急速に進行するため、食中毒の応急処置としてORSを常備し、早期に受診することが推奨されます。[1, 9] また、WHOは小児の下痢に対し、ORSと共に「亜鉛」の補充を推奨しています(罹病期間の短縮、便量の減少)。[7, 8]
肝疾患の栄養療法:脂肪肝から肝硬変まで
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、症状が出にくい一方で、栄養代謝の中心的な役割を担っています。肝疾患の進行度によって、必要とされる栄養療法は大きく異なります。
1. 脂肪肝(NAFLD/MASLD)の食事
非アルコール性脂肪肝(NAFLD、最近ではMASLDとも呼ばれる)の治療の根幹は、体重減少です。米国国立糖尿病・消化器・腎疾患研究所(NIDDK)などによれば、体重の7〜10%を減量することで、肝臓の脂肪蓄積や炎症が有意に改善することが示されています。[10] 食事パターンとしては、野菜、果物、全粒穀物、良質な脂質(オリーブオイルや魚)を中心とする「地中海食」が支持されており、特に砂糖や果糖(清涼飲料水など)の過剰摂取を制限することが重要です。[11] 脂肪肝の食事改善は、体重管理と糖質制限が鍵となります。
2. 肝硬変の食事:誤解と真実
肝硬変が進行すると、かつては「たんぱく質制限」が指導されることもありましたが、現在の考え方は大きく異なります。肝硬変患者は、エネルギー消費が亢進し、筋肉が分解されやすい「サルコペニア(筋肉減少症)」のリスクが非常に高い状態です。[12, 13]
そのため、たんぱく質を制限するどころか、十分なたんぱく質(1.2〜1.5 g/kg/日)とエネルギー(25〜35 kcal/kg/日)を確保することが推奨されます。[12] 特に重要なのが「就寝前軽食(Late Evening Snack: LES)」です。夜間の空腹時間が長くなると、体は筋肉を分解してエネルギー源としてしまいます。就寝前にBCAA(分岐鎖アミノ酸)製剤や軽食(200kcal程度)を摂ることで、この筋肉分解を防ぎ、栄養状態を改善します。[12, 13]
一方で、肝硬変による腹水がある場合は、塩分制限(6 g/日未満)が厳格に求められます。[12] また、アルコールが肝臓に及ぼす影響が原因の場合は、絶対的な禁酒と、チアミン(ビタミンB1)などの微量栄養素の補充が不可欠です。[12] C型肝炎の食事療法など、原因疾患に応じた対応も求められます。
サプリメントの安全性:肝障害と薬物相互作用のリスク
「天然由来だから安全」「健康食品だから副作用はない」という考えは、非常に危険な誤解です。実際には、サプリメントや健康食品が原因で深刻な「薬物性肝障害(DILI)」を引き起こすケースが報告されています。
日本の医薬品医療機器総合機構(PMDA)も、薬物性肝障害の原因として健康食品やサプリメントを挙げており、注意を喚起しています。[14, 15] 例えば、高濃度のカテキンを含む緑茶抽出物や、ウコン(ターメリック)などは、米国NIHのデータベース(LiverTox)でも肝障害の事例が報告されています。[16] 2024年に日本で大きな問題となった「紅麹」関連製品についても、摂取中止と受診勧告が公的に通知されています。[17, 18]
また、肝障害だけでなく「薬物相互作用」も重大なリスクです。代表例はセントジョーンズワート(セイヨウオトギリソウ)で、多くの医薬品(免疫抑制薬、抗凝固薬、経口避妊薬など)の代謝を早め、その効果を著しく低下させることが知られています。[19] 肝臓サプリメントの安全性は保証されておらず、ビタミンAの過剰摂取が肝毒性を引き起こすこともわかっています。[20]
特に肝機能障害のリスクがある人や、既に医薬品を服用している人は、サプリメントを使用する前に必ず主治医や薬剤師に申告し、相談することが絶対的な原則です。[14, 15]
食事と栄養に関するよくある質問
Q1: 低FODMAP食はどのくらいの期間続けますか?
A: 厳格な制限期間(導入期)は、原則として4〜8週間です。症状が改善したら、必ず「再導入期」に移行し、どの食品が自分に合わないかを特定します。生涯にわたり全ての高FODMAP食品を除去し続けることは、栄養不足や腸内環境の偏りを招く可能性があるため推奨されません。[2, 3]
Q2: 下痢の時、スポーツドリンクは経口補水液(ORS)の代わりになりますか?
A: いいえ、原則として代わりにはなりません。ORSはWHOの基準に基づき、ナトリウムとブドウ糖が水分の吸収に最適なバランス(浸透圧245 mOsm/Lなど)で調整されています。[4, 5] スポーツドリンクはナトリウムが不足し、糖分が多すぎるため、脱水時の水分補給には不向きです。
Q3: 脂肪肝を改善するには、具体的に何キロ痩せれば効果がありますか?
A: 多くの研究で、現在の体重の7〜10%を減量することで、肝臓の脂肪蓄積や炎症(肝炎)が有意に改善すると報告されています。[10] 例えば体重80kgの人であれば、5.6kg〜8kgの減量が具体的な目標となります。
Q4: 肝硬変になると、たんぱく質は制限すべきですか?
A: いいえ、これは過去の誤解です。肝性脳症のリスクが極めて高い特殊な場合を除き、現代の栄養学ではたんぱく質の制限は推奨されません。むしろ、筋肉の減少(サルコペニア)を防ぐため、体重1kgあたり1.2〜1.5gの十分なたんぱく質を摂取し、さらに「就寝前軽食(LES)」で補うことが推奨されます。[12, 13]
Q5: サプリメントや漢方薬は安全ですか?
A: 安全とは限りません。医薬品との相互作用(例:セントジョーンズワート)[19]、特定の成分の過剰摂取による肝毒性(例:ビタミンA)[20]、あるいは製品そのものによる肝障害(例:一部の緑茶抽出物、ウコン、紅麹など)[14, 16, 17]のリスクが知られています。特に漢方薬などの併用を考えている場合や、既に肝疾患の治療を受けている場合は、摂取前に必ず主治医に相談してください。
生活習慣と予防(アルコール/喫煙・ワクチン・ピロリ除菌・健診の活用)
前章では、日々の食事や栄養素が消化器の健康にどう影響するかを見てきました。しかし、消化器疾患のリスクを管理し、長期的な健康を守るためには、食事と同じくらい、あるいはそれ以上に重要な「生活習慣」と「予防医療」への取り組みが存在します。
それが、アルコールや喫煙との向き合い方です。さらに、現代医療では、病気になる前にリスクそのものを取り除く「一次予防」や、症状が出る前に病気を発見する「二次予防」が非常に進歩しています。具体的には、特定のウイルスから身を守るワクチン接種、胃がんの最大のリスク因子であるピロリ菌の除菌、そして定期的ながん検診や肝炎ウイルス検査の受検です。これらは「運が悪ければ病気になる」という受動的な考え方から一歩進み、「自ら行動してリスクを回避する」ための具体的な戦略です。この章では、科学的根拠に基づき、日本国内の制度(保険適用や公的助成)も踏まえながら、あなたが今すぐ実行できる予防策を一つひとつ詳しく解説していきます。
アルコールとの向き合い方:適正飲酒の目安とリスク
お酒との付き合い方は、消化器の健康を考える上で避けて通れないテーマです。「自分はどれくらい飲んでいるのか」を客観的に把握するために、まずは「純アルコール量」で換算する方法を知っておきましょう。純アルコール量(g)は、「飲酒量(mL) × アルコール度数(%) × 0.8(アルコールの比重)」で計算されます。例えば、ビール500mL(アルコール度数5%)なら約20g、日本酒1合180mL(15%)なら約22g、ストロング系チューハイ500mL(9%)なら約36gが目安です。
日本の厚生労働省が示す「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」では、生活習慣病のリスクを高める飲酒量を、1日あたりの純アルコール量で男性40g以上、女性20g以上としています[3]。女性や高齢者はアルコールの分解能力が低い傾向があるため、より少ない量が目安とされています。もしご自身の飲酒量がこの基準を超えている場合、まずはこの量以下に抑える「節酒」を心がけることが、健康への重要な第一歩となります。
しかし、特に「がん予防」という観点では、近年さらに厳しい見解が国際的に示されています。衝撃的かもしれませんが、世界保健機関(WHO)は2022年に、「がんに関しては、安全な飲酒量は存在しない」と明言しています[16]。アルコールそのものと、その代謝物であるアセトアルデヒドは、食道、肝臓、大腸など多くの消化器がんの確実な発がん物質であり、飲む量が増えれば増えるほどリスクは直線的に上がります。日本のガイドラインが示す目安は、あくまで「生活習慣病全体のリスクが明らかに高まる閾値」であり、「がんリスクがゼロになる量」ではないことを、私たちは知っておく必要があります。
アルコールの害はがんだけではありません。アルコールは膵臓にも大きな負担をかけ、急性膵炎や慢性膵炎の主要な原因となります[20]。また、アルコール性肝炎や肝硬変のリスクは広く知られています。最近の研究では、アルコールが腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスを崩すことも指摘されており、消化管全体の健康に多角的な悪影響を及ぼします。可能であれば飲酒量をゼロに近づける「断酒」が最も望ましく、それが難しい場合でも、まずは休肝日を週に2日以上設ける、飲む量を減らすといった具体的な行動変容が求められます。急な断酒が困難な場合や、アルコール依存(中毒)が疑われる場合は、専門の医療機関への相談が不可欠です。
喫煙が消化器に与える深刻な影響と禁煙治療
アルコールと並んで、消化器疾患の強力なリスク因子となるのが喫煙です。喫煙は肺がんのイメージが強いかもしれませんが、WHOによれば、胃がん、膵臓がん、大腸がん、食道がんなど、消化器系の多くのがんのリスクを確実に高めます[17]。
特に深刻なのは、アルコールとの「相乗効果」です。IARC(国際がん研究機関)の報告によれば、飲酒と喫煙の両方の習慣があると、特に食道扁平上皮がんのリスクが、どちらか一方だけの場合の数倍~数十倍にまで跳ね上がることが示されています[18]。これは「1+1=2」ではなく、「1+1が5にも10にもなる」という恐ろしい関係です。飲酒と喫煙が肝臓に与える複合的影響も甚大であり、消化器の健康を考える上で、この二つを同時に断つことの重要性はいくら強調してもしすぎることはありません。
がんだけではありません。喫煙は、難病指定されている炎症性腸疾患(IBD)の一つであるクローン病の発症リスクを高め、さらに診断後の病気の経過を悪化させることが科学的に証明されています[19]。クローン病と診断された患者さんにとって、禁煙は治療の第一歩として強く、厳しく推奨されます。
「やめたいけれど、自分の意志だけではやめられない」というのが、ニコチン依存症の難しさです。しかし、現在は意志の力だけで禁煙する時代ではありません。日本では、ニコチン依存症と診断され、特定の基準(1日の喫煙本数×喫煙年数が200以上など)を満たせば、禁煙治療が健康保険の適用となります[15]。貼り薬(ニコチンパッチ)や飲み薬(バレニクリンなど)の助けを借りて、医療機関の医師や看護師のサポートを受けながら、より楽に、より確実に禁煙に取り組むことができます。近年普及している加熱式たばこや電子たばこも、健康へのさまざまな悪影響が懸念されており、紙巻きたばこと同様に禁煙が推奨されます。
消化器疾患を防ぐワクチン(B型肝炎・A型肝炎・ロタウイルス)
特定のウイルス感染は、急性胃腸炎や、慢性肝炎、さらには肝がんといった深刻な消化器疾患を引き起こします。幸いなことに、これらのうちいくつかはワクチンによって予防、あるいは重症化を防ぐことが可能です。
- B型肝炎(HBV)ワクチン:
日本では2016年10月から、乳児(0歳児)に対する定期接種となりました[10]。したがって、これ以降に生まれたお子さんは原則として接種済みです。しかし、それ以前に生まれた方は、基本的に未接種の可能性があります。B型肝炎ウイルスは主に血液や体液を介して感染し、成人での感染は一過性が多いものの、免疫力が低い乳幼児期に感染すると持続感染(キャリア)となりやすく、将来的に肝硬変や肝がんの最大のリスクとなります。成人であっても、医療従事者、B型肝炎キャリアの家族がいる方、透析患者さん、海外渡航者など、感染リスクが高いと考えられる場合は、任意でのワクチン接種が強く推奨されます。
- A型肝炎(HAV)ワクチン:
A型肝炎は、ウイルスに汚染された水や食べ物(特に生の魚介類など)を口にすることから感染します[13]。B型やC型肝炎と異なり慢性化することはまれですが、急性の肝障害を引き起こし、高齢者や肝臓に持病がある方では劇症化して命に関わることもあります。日本では定期接種ではありませんが、A型肝炎の流行地域(特にアジア、アフリカ、中南米など)へ渡航する方[21]、飲食店の従事者、または基礎疾患として慢性肝疾患を持つ方には、任意での接種が推奨されます。
- ロタウイルスワクチン:
乳幼児期に激しい嘔吐や下痢を引き起こす「感染性胃腸炎」の最も主要な原因ウイルスです。特に生後6ヶ月から2歳頃までに初感染すると重症化しやすく、脱水症状で入院が必要になることも少なくありません。この重症化を防ぐため、日本では2020年10月から、乳児への定期接種(飲むタイプのワクチン)が開始されました[12]。これにより、ロタウイルスによる重症胃腸炎での入院患者数が激減することが期待されています。
胃がん予防の鍵:ピロリ菌除菌の保険適用と重要性
日本の胃がんの発生原因の90%以上は、ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)の持続感染によるものであることが、今や常識となっています。ピロリ菌に一度感染すると、多くの場合、生涯にわたって胃の中に棲み続け、慢性的な胃炎(慢性活動性胃炎)を引き起こします。この慢性的な炎症が数十年の経過を経て、胃粘膜の萎縮(萎縮性胃炎)、腸上皮化生(胃粘膜が腸のようになる変化)へと進展し、最終的にその一部ががん化すると考えられています。
この胃がんへの連鎖を断ち切る最も強力な手段が、ピロリ菌を薬で除去する「除菌治療」です。除菌治療は、主に2種類の抗生物質と胃酸を強力に抑える薬の3剤を、1週間服用するというシンプルなものです。
かつて、この除菌治療は胃潰瘍や十二指腸潰瘍など、特定の病気と診断された場合のみ保険適用でした。しかし、ピロリ菌感染こそが胃がんの最大の原因であるというエビデンスが蓄積された結果、胃がん予防の重要性が広く認識され、2013年からは「内視鏡検査(胃カメラ)で慢性胃炎と診断された」場合にも、ピロリ菌感染の検査と除菌治療が保険適用となりました[7]。これは、日本の胃がん対策における歴史的な大転換点と言えます。
この保険適用拡大後、除菌治療を受ける人は爆発的に増え、その効果は既に出始めています。厚生労働省の資料によれば、胃がんによる死亡率が約10%減少したと報告されており、その要因の一つとして除菌治療の普及が大きく貢献したと考えられています[8]。もちろん、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の再発予防にも絶大な効果があります。
ピロリ菌は主に幼少期(主に5歳頃まで)に、衛生環境が整備されていなかった時代の井戸水や、保菌者であった親からの口移しなどを介して感染すると考えられています。そのため、衛生環境が劇的に改善された現代の若い世代では感染率が非常に低くなっています。しかし、中高年層ではまだ高い感染率が続いています。ご自身の胃の健康と将来の胃がんリスクを知るため、一度もピロリ菌の検査(呼気検査、血液検査、便中抗原検査など)を受けたことがない方は、まず検査を受けることを強くお勧めします。ただし、一つ重要な注意点として、除菌に成功しても胃がんのリスクが完全にゼロになるわけではありません。特に胃粘膜の萎縮が進んでから除菌した場合、リスクは残ります。そのため、除菌成功後も、定期的な胃カメラ検査は必ず継続してください。
がん検診と肝炎ウイルス検査:早期発見のための行動計画
ワクチンやピロリ菌除菌が、病気の「原因」そのものを取り除く「一次予防」であるのに対し、もし病気が発生してしまっても、それを症状が出る前のごく早期の段階で発見し、負担の少ない治療で治癒を目指す対策が「二次予防」、すなわち「検診」です。消化器領域において、科学的根拠に基づき死亡率を減少させる効果が証明されている検診は、胃がんと大腸がんの検診、そして肝炎ウイルス検査です。
厚生労働省の指針に基づき、日本の各市区町村は「対策型検診」として以下のがん検診を公費(無料または一部自己負担)で実施しています[4]。
- 大腸がん検診:
対象は40歳以上の方で、頻度は年に1回です。検査方法は「便潜血検査(FIT)」と呼ばれる、便に微量の血液が混じっていないかを調べる簡単な検査です[6]。これは、大腸がんやポリープがあると、便が通過する際に表面からわずかに出血することがあるためです。もし「陽性(要精密検査)」と判定された場合、それは「=大腸がん」という意味ではありません。痔など良性の病気で陽性になることも多々あります。しかし、その陽性の原因を突き止めるため、症状がなくても必ず精密検査(通常は大腸内視鏡検査=大腸カメラ)を受けてください。早期の大腸がんや、がん化する可能性のあるポリープは、この検診が発見のきっかけとなることが非常に多いのです。
- 胃がん検診:
対象は50歳以上の方で、頻度は2年に1回です[5]。検査方法は、自治体によって異なり、「胃X線検査(バリウム検査)」または「胃内視鏡検査(胃カメラ)」のどちらかを実施します。どちらの方法も一長一短ありますが、胃カメラは粘膜の微細な変化を直接観察できる利点があります。特に前述のピロリ菌除菌歴がある方は、胃がんのリスクがゼロにはならないため、定期的な胃カメラ検査の継続が強く推奨されます。
さらに、がん検診とは別に、肝炎ウイルス検査も「二次予防」として極めて重要です。B型肝炎ウイルス(HBV)やC型肝炎ウイルス(HCV)は、感染しても自覚症状がないまま何十年もかけて肝臓内で静かに炎症を引き起こし、肝硬変や肝がんに進行します。「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓は、症状が出た時には手遅れになっていることも少なくありません。日本では「一生に一度は肝炎ウイルス検査」をスローガンに、多くの自治体で無料または非常に安価な血液検査が提供されています[11]。過去に肝炎ウイルス検査を受けた明確な記憶がない方は、職場の健診や市区町村の窓口に問い合わせて、ぜひ一度検査を受けてください。早期に感染を発見できれば、現在はウイルスの活動を強力に抑える、あるいは(C型肝炎の場合は)体内から排除する効果的な治療法が開発されています。
食中毒と感染症の基本予防
ワクチンや検診と並び、日々の生活で実践できる最も基本的な予防策が、衛生管理です。特にノロウイルスやA型肝炎ウイルスによる食中毒や感染性胃腸炎は、基本的な「つけない・ふやさない・やっつける」の原則でリスクを大幅に減らすことができます。
- 手洗い(つけない):
特にノロウイルスは、一般的なアルコール消毒が効きにくいという厄介な特徴があります。そのため、A型肝炎[13]と同様に、石けんを使い、流水でウイルスを物理的に洗い流す「手洗い」が最も重要です。調理の前、食事の前、トイレの後、おむつ交換の後などは、指の間や手首まで意識して徹底的に洗いましょう。
- 加熱(やっつける):
ノロウイルス[14]やA型肝炎ウイルスは熱に弱いため、食品を加熱することが有効な対策です。特に感染源となりやすいカキなどの二枚貝や、井戸水、海外からの輸入食品などは、生食を避け、中心部までしっかり加熱(目安として85〜90℃で90秒以上)することが推奨されます。
- 消毒(やっつける):
万が一、家族内などで感染者が発生した場合、嘔吐物や便が触れた可能性のある床やドアノブは、そのまま放置すると感染源となります。これらの場所は、次亜塩素酸ナトリウム(家庭用の塩素系漂白剤を薄めたもの)を使って適切に消毒する必要があります。
生活習慣と予防に関するよくある質問(FAQ)
Q1: 日本の「適正飲酒」の基準は?結局、飲んでも良いのですか?ゼロが望ましいですか?
A: 厚生労働省のe-ヘルスネットなどによれば、あくまで「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」の目安として、1日あたりの純アルコール量で男性40g、女性20gとされています[1, 2]。しかし、WHOはがん予防の観点から「いかなるレベルの飲酒も安全とは言えない」と明言しています[4, 16]。健康への影響を最小限にしたい、特にがんのリスクを下げたいと考えるならば、飲酒量はゼロに近づける(禁酒する)ことが最も望ましい選択です。現在飲んでいる方は、まずは目安量以下に減らす「節酒」から始めることが現実的な第一歩です。
Q2: 喫煙は消化器がんやクローン病に具体的にどう影響しますか?
A: 喫煙は胃がん、膵臓がん、大腸がん、食道がんなど、多くの消化器がんの確実なリスク因子です[17]。特に飲酒と喫煙が重なると、食道がんのリスクは足し算ではなく掛け算(相乗効果)で急上昇します[18]。また、クローン病においては、発症リスクを高めるだけでなく、診断後の病状を悪化させ、再燃(症状が再び悪くなること)や手術のリスクを高めることがわかっています[19]。そのため、クローン病患者さんの禁煙は、薬物治療と同等に重要な「治療」の一環と位置づけられています。
Q3: 大人のB型肝炎(HBV)ワクチンは、どのような人が受けるべきですか?
A: 日本では2016年10月以降に生まれた赤ちゃんは、全員が定期接種の対象です[9, 10]。しかし、それ以前に生まれた方は、基本的に未接種の可能性があります。成人で接種が推奨されるのは、医療従事者、救急隊員、HBVキャリアの家族やパートナーがいる方、血液製剤を頻繁に使用する方(透析患者さんなど)、特定の地域へ渡航する方[21]など、感染(血液・体液曝露)のリスクが高い方です。ご自身が該当するか不明な場合は、医師にご相談ください。
Q4: なぜノロウイルスワクチンは実用化されていないのですか?
A: ノロウイルスには非常に多くの遺伝子の型(インフルエンザの型が毎年変わるのと似ています)があり、一つのワクチンで全ての型を防ぐことが技術的に非常に難しいことが一因です。また、感染防御に必要な免疫の仕組みも複雑です。そのため、2025年現在、日本国内で承認・実用化されたノロウイルスワクチンはありません[14]。予防は、石けんによる手洗い、食品の十分な加熱、感染者の嘔吐物の適切な処理(次亜塩素酸ナトリウムによる消毒)といった地道な衛生対策が中心となります。
Q5: ピロリ菌を除菌すれば、もう胃がん検診(胃カメラ)は受けなくても良いですか?
A: いいえ、それは大きな誤解です。除菌治療は胃がんのリスクを大幅に下げますが、ゼロにはなりません。特に、胃の粘膜の萎縮(老化)が進んでから除菌した場合、萎縮が進んでいなかった人と比べると、胃がんの発生リスクは残ってしまいます。除菌が成功したからこそ、残ったリスクを管理するために[8]、定期的な胃内視鏡(胃カメラ)検査を継続することが非常に重要です。
Q6: 胃がん・大腸がん検診は何歳から、どのくらいの頻度で受けるべきですか?
A: 厚生労働省が推奨する「対策型検診」(市区町村が実施)の基準は以下の通りです[4]:
- 大腸がん検診:40歳以上の方が対象で、年に1回、便潜血検査(2日法)を受けます[6]。
- 胃がん検診:50歳以上の方が対象で、2年に1回、胃X線(バリウム)検査または胃内視鏡(胃カメラ)検査のどちらかを受けます[5]。(※実施方法は自治体により異なります)
これらはあくまで最低限の推奨ラインです。ご自身の家族歴(血縁者にがんの方が多いなど)や、ピロリ菌除菌歴、ポリープの既往などに応じて、医師と相談の上で、より早い年齢から、あるいはより頻繁に検査(特に内視鏡検査)を行う「任意型検診」を選択することも重要です。
症状別早見表と自己管理(腹痛・吐き気/嘔吐・下痢・便秘・血便)
これまでのセクションでは、消化器系の様々な疾患やその予防法について詳しく見てきました。しかし、実際に「お腹が痛い」「急に吐き気がする」といった症状が現れたとき、私たちは不安に駆られます。それは単なる食べ過ぎなのか、それとも重大な病気のサインなのか。このセクションでは、最も一般的な5つの消化器症状(腹痛、吐き気・嘔吐、下痢、便秘、血便)に焦点を当て、「まず家庭で何をすべきか」という自己管理(セルフケア)と、「どのタイミングで病院へ行くべきか」という受診の目安(レッドフラグ)を、国内外の医療ガイドラインに基づき、具体的かつ詳細に解説します。
消化器の症状は、体が発する重要なシグナルです。このガイドが、あなたの不安を和らげ、適切な初期対応と冷静な判断を下すための一助となることを目指します。まずは、5大症状の要点をまとめた早見表からご覧ください。
主要5症状の自己管理と受診の目安(早見表)
これはあくまで初期対応の目安です。ご自身の症状が表の「直ちに救急」に少しでも当てはまる、あるいは「いつもと違う、何かおかしい」と感じる場合は、自己判断せずに医療機関に相談してください。
| 症状 | 自己管理の要点 | 受診の目安(数日以内) | 直ちに救急(当日) |
|---|---|---|---|
| 腹痛 | 安静にし、水分を少量ずつ補給。脂っこいもの、香辛料、アルコールを避ける。痛みが落ち着けば消化の良いものから再開。 | 痛みが持続・悪化する、発熱や嘔吐を伴う、便秘や下痢が数日続く。 | 突然の激痛、腹部が硬く、押したり動いたりすると響く、吐血(コーヒー残渣様)、黒色タール便や大量の血便、排便・放屁が全くない。 |
| 吐き気・嘔吐 | 経口補水液(ORS)を小さじ1杯ずつ5分おきなど、少量頻回で開始。吐き気が治まれば徐々に増量。固形物は無理しない。 | 1~2日経っても水分がまともに取れない、体重減少、発熱や腹痛が続く。 | 吐血(鮮血やコーヒー残渣様)、尿が半日以上出ない、めまいや失神、妊娠中で水分が全く取れない。 |
| 下痢 | 最優先は脱水補正。経口補水液(ORS)を早期から少量頻回で。食事は無理せず、整腸を心がける。自己判断での抗菌薬は不要。 | 2~3日経っても改善しない、発熱や腹痛が続く、海外渡航歴がある。 | 血液の混じった下痢(血便)、高度の脱水症状(強い喉の渇き、尿がほぼ出ない、ぐったりしている)、意識が朦朧とする。 |
| 便秘 | 食物繊維と十分な水分、適度な運動。排便トレーニング(朝食後など毎日決まった時間にトイレに座る)。市販薬は短期使用に留める。 | 生活介入で改善しない、腹痛や吐き気が悪化する、薬剤(オピオイド等)が原因と疑われる。 | 血便、原因不明の体重減少、貧血、激しい腹痛や嘔吐を伴う便秘(腸閉塞の疑い)。 |
| 血便 | トイレットペーパーに付く程度の少量なら安静・補水。硬い便の後に肛門が痛む場合は裂肛も考慮。 | 繰り返す、または持続する少量の血便。3週間以上続く便通の変化(便秘と下痢を繰り返すなど)。 | 黒色タール便(メレナ)、鮮血の多量・持続的な出血、吐血を伴う、激しい腹痛やショック症状(冷や汗、めまい)。 |
腹痛:場所と痛みの種類で考える
「腹痛」と一口に言っても、その原因は様々です。キリキリする胃の痛み、下腹部の鈍痛、差し込むような激痛など、感じ方は多岐にわたります。多くは一時的な消化不良やストレスによるものですが、中には緊急を要する病気が隠れていることもあります。
家庭での初期対応(セルフケア)
腹痛を感じたら、まずは無理をせず安静にすることが基本です。可能であれば楽な姿勢で横になり、衣服のベルトなどを緩めて腹部を圧迫から解放します。
- 水分補給:脱水を防ぐため、白湯や経口補水液を少量ずつ、ゆっくりと摂取します。冷たすぎる飲み物や、胃酸分泌を促すコーヒー、炭酸飲料は避けましょう。
- 食事:痛みが強い間は無理に食べる必要はありません。落ち着いてきたら、お粥やうどん、すりおろしたリンゴなど、消化が良く胃腸に負担をかけないものから再開します。脂っこい食事、香辛料の強い食事、アルコールは、消化管を刺激し症状を悪化させるため厳禁です。
- 市販薬:胃痛の原因がストレスや食べ過ぎとはっきりしている場合は、市販の胃腸薬が助けになることもあります。しかし、痛みの原因が不明な場合に自己判断で鎮痛薬(特にNSAIDs)を使用すると、胃潰瘍を悪化させたり、虫垂炎などの重大な病気の兆候を隠してしまったりする危険があるため、慎重であるべきです。
危険な腹痛(レッドフラグ)
以下の症状は、腹膜炎、消化管穿孔、腸閉塞、あるいは大動脈解離など、生命に関わる状態を示唆している可能性があります。痛む場所に関わらず、直ちに救急外来を受診するか、救急車を要請してください。
- 突然発症した、立っていられないほどの激痛:「バットで殴られたような」「引き裂かれるような」と表現される痛み。
- 動くと響く痛み:歩いたり、咳をしたり、ベッドの上で寝返りをうつだけで腹部全体に響くような痛み。腹膜炎(腹部の内側を覆う膜の炎症)のサインです。
- 吐血や黒色便を伴う:消化管のどこかで大量に出血しています。
- 便やガスが全く出ない(排便・放屁停止):腸閉塞(イレウス)が強く疑われます。
吐き気・嘔吐:最優先は「脱水」の回避
嘔吐は、体が有害なものを排出しようとする防御反応ですが、非常に体力を消耗します。繰り返す嘔吐で最も恐ろしいのは「脱水症」です。特に乳幼児や高齢者は、急速に脱水が進むため、水分補給が追いつかないと感じたら早期の受診が必要です。
水分補給(経口補水)の正しい方法
「水分を摂らなければ」と焦って水をがぶ飲みすると、その刺激で胃がさらに収縮し、再び嘔吐してしまう悪循環に陥ります。嘔吐時の水分補給には、医療用の経口補水液(ORS)が最適です。これは、水分と電解質(ナトリウムやカリウム)を最も効率よく吸収できるバランスで調整されています。
正しい飲ませ方(セルフケアの鍵):
- 最後の嘔吐から30分ほど待ち、胃を休ませます。
- 経口補水液を、ティースプーン1杯(約5ml)またはペットボトルのキャップ1杯分だけ口に含ませ、ゆっくり飲み込んでもらいます。
- 5分間待ち、吐き気が誘発されないことを確認します。
- 再びティースプーン1杯分を飲ませます。
- これを1時間ほど続け、吐かなければ、1回に飲む量を徐々に(例:15ml→30ml)増やしていきます。
この「少量頻回」が、胃を刺激せずに水分を腸まで届けるための最も重要なテクニックです。
危険な嘔吐(レッドフラグ)
食中毒やウイルス性胃腸炎による嘔吐は通常1~2日で改善しますが、以下は緊急のサインです。
- 吐血(鮮血)、または「コーヒー残渣様」の嘔吐:「コーヒー残渣(ざんさ)」とは、胃酸によって酸化され黒く変色した血液のことで、胃や十二指腸からの出血を示します。
- 激しい頭痛や意識障害を伴う:くも膜下出血や髄膜炎など、頭蓋内の問題である可能性があります。
- 重度の脱水症状:半日以上尿が出ない、泣いても涙が出ない(乳幼児)、ぐったりして呼びかけに反応が鈍い、めまいや失神。
- 妊娠中の激しい嘔吐(重症妊娠悪阻):水分や食事が全く取れず、体重が減少し始めた場合は、点滴による水分・栄養補給が必要なため、産婦人科を受診してください。
下痢:止めることより「出す」ことと「補う」こと
急性下痢の多くは、ウイルスや細菌を体外に排出しようとする防御反応です。そのため、自己判断で下痢を無理に止めると、かえって病原体の排出を遅らせ、回復を妨げる可能性があります。
セルフケアの優先順位
下痢の際も、嘔吐と同様に最優先事項は脱水補正です。下痢便とともに失われる水分と電解質を、経口補水液(ORS)で補い続けます。嘔吐がなければ、飲める範囲で少量ずつ頻回に摂取しましょう。
注意:止痢薬(下痢止め)の自己判断は推奨されない
「下痢を止めたい」という理由で市販の止痢薬(ロペラミドなど)を使いたくなるかもしれませんが、日本の国立国際医療研究センター(NCGM)などが監修する「抗微生物薬適正使用の手引き」では、急性下痢に対する止痢薬の使用は科学的根拠に乏しく、推奨されていません。
特に、発熱や血便を伴う場合(細菌性腸炎の可能性)に止痢薬を使用すると、腸の動きを止めてしまい、毒素の排出が遅れ、症状が重篤化する危険性があるため禁忌とされています。まずは経口補水液による水分補給に専念してください。
出典: 国立国際医療研究センター「抗微生物薬適正使用の手引き 第三版」(2024年)
感染対策(ノロウイルスなど)
感染性の下痢(特にノロウイルスやロタウイルス)は、家庭内や施設内で容易に感染拡大します。
- 手洗い:石鹸と流水で徹底的に洗い流します。アルコール消毒はノロウイルスには効きにくいため、石鹸での物理的な洗浄が最重要です。
- 吐瀉物・排泄物の処理:使い捨ての手袋、マスク、エプロンを着用し、ペーパータオルで静かに拭き取ります。拭き取った後は、家庭用塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)を薄めたもので広範囲を消毒します。
便秘:生活習慣の改善と薬剤の正しい知識
便秘は非常に多くの人が悩む症状です。「毎日排便がないと便秘」と思われがちですが、排便の頻度には個人差があり、「3日に1回でもスムーズに出れば問題ない」場合もあれば、「毎日出ていても強くいきまなければならない、残便感がある」場合は便秘とされます。大切なのは回数よりも「快適な排便習慣があるか」です。
セルフケアの4本柱
便秘治療の基本は、薬ではなく生活習慣の改善です。
- 食物繊維:野菜、果物、海藻、キノコ類など、水溶性と不溶性の両方の食物繊維をバランスよく摂取します。
- 水分:便を柔らかくするために、1日1.5リットル以上を目安に十分な水分を摂ります。
- 運動:ウォーキングなど、腸の動きを活発にするための適度な運動を習慣にします。
- 排便トレーニング:最も重要な習慣です。人間の腸は朝食後に最も活発に動きます(胃結腸反射)。便意がなくても、朝食後に必ず10〜15分トイレに座る時間を確保し、体に排便のリズムを覚えさせます。
市販薬の注意点:酸化マグネシウムの安全性
市販薬でよく使われる酸化マグネシウムは、便を柔らかくする比較的安全な薬とされています。しかし、特に注意が必要なケースがあります。
高マグネシウム血症のリスク:
- 腎機能が低下している方や高齢者は、マグネシウムを体外に排出する能力が落ちています。
- このような方が酸化マグネシウムを長期間・大量に服用し続けると、体内にマグネシウムが蓄積し、「高マグネシウム血症」を引き起こすことがあります。
- 初期症状は、吐き気、筋力低下、眠気、立ちくらみなどで、重篤化すると呼吸抑制や意識障害に至ることもあります。
自己判断での長期連用は避け、必要最小限の使用に留め、症状が出た場合は直ちに服薬を中止し医師に相談してください。
出典: PMDA「酸化マグネシウム製剤 適正使用に関するお願い」(2020年)
血便・黒色便:最も見逃してはならないサイン
便に血が混じることは、消化管のどこかから出血しているという明確なサインです。その色と形状によって、出血部位と緊急性が大きく異なります。
色の見分け方と緊急度
「血便」と聞くと赤い血を想像しますが、医学的には黒い便も血便の一種であり、むしろ緊急性が高い場合があります。
- 鮮血(真っ赤な血):
- トイレットペーパーに付着する、便器に数滴垂れる:多くは痔核(いぼ痔)や裂肛(きれ痔)など、肛門付近からの出血です。緊急性は低いことが多いですが、繰り返す場合は大腸がんなどの除外も必要です。
- 便全体に混じる、大量に出る:大腸からの出血(憩室出血、虚血性腸炎、IBD、がんなど)の可能性があり、緊急の評価が必要です。
- 黒色タール便(メレナ):
- 緊急事態(救急受診)です。
- これは、胃や十二指腸など、上部消化管からの出血(胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんなど)を示します。血液が胃酸と反応し、鉄が酸化されることで、海苔の佃煮やイカスミのように真っ黒でネバネバした便になります。
- 少量でも黒色便が出た場合は、体内で持続的に出血している可能性があり、貧血が急速に進行する危険があるため、直ちに医療機関を受診してください。
健康診断の便潜血検査で陽性となった場合も、目に見える出血がなくても消化管のどこかから微量に出血しているサインですので、必ず精密検査(大腸内視鏡など)を受けてください。
症状に関するよくある質問(FAQ)
Q1: 下痢や嘔吐のとき、スポーツドリンクではダメですか?
A: 経口補水液(ORS)が最適です。スポーツドリンクは、日常の水分補給には良いですが、下痢や嘔吐によって失われるナトリウム(塩分)の量が少なく、糖分が多すぎます。医学的な脱水補正には、WHO(世界保健機関)などが推奨する電解質バランスの経口補水液(ORS)を使用してください。緊急時は、湯冷まし1リットルに砂糖40g(大さじ4.5杯)、食塩3g(小さじ半分)を溶かしたもので代用できます。
Q2: 下痢が辛いので、市販の下痢止めを飲んでもいいですか?
A: 日本の医療ガイドラインでは、自己判断での使用は推奨されていません。特に、細菌性腸炎(O-157など)による血便や発熱がある場合、下痢止めは腸の動きを止め、毒素の排出を妨げ、症状を重篤化させる危険があります。まずは水分補給に専念し、症状が続く場合や血便がある場合は速やかに受診してください。
Q3: 便秘症ですが、毎日排便がないと異常ですか?
A: いいえ、排便の頻度には個人差があります。「毎日1回」は理想であって必須ではありません。週に3回程度でも、スムーズに苦痛なく排便でき、残便感がなければ「正常範囲」とされます。回数にこだわるよりも、食物繊維、水分、運動、排便トレーニングといった生活習慣を見直すことが重要です。
Q4: 真っ黒い便が出たら、何科を受診すべきですか?
A: 直ちに救急外来を受診してください。イカスミや海苔の佃煮のような真っ黒なタール便(メレナ)は、胃や十二指腸からの出血(上部消化管出血)が強く疑われる緊急のサインです。出血量が多いとショック状態になる危険があります。かかりつけ医を探すのではなく、救急対応が可能な病院(消化器内科医が常駐またはオンコールで対応できる病院)に向かうべきです。
Q5: 妊娠中で吐き気が強く、水も飲めません。どうすればいいですか?
A: 速やかに産婦人科を受診してください。これは「つわり」だからと我慢してはいけません。水分が全く取れない、尿が極端に少ない、体重が妊娠前から減少しているといった状態は「重症妊娠悪阻(じゅうしょうにんしんおそ)」という治療が必要な状態です。母体と胎児の健康を守るため、点滴による水分・栄養補給が必要かどうか、医師の診察を受けてください。
参照ガイドライン・FAQ・用語集
これまでのセクションで、消化器系のさまざまな症状、検査、治療法、そして具体的な症状別の対処法について詳しく見てきました。しかし、健康に関する情報は日々更新されており、「自分の症状について、もっと専門的な情報を知りたい」「医師の説明で出てきた用語が分からない」といった疑問や不安が残ることもあるでしょう。
この最後のセクションは、そうした皆様の「もっと知りたい」という声に応えるための「参照ハブ」です。本ガイド全体で依拠した国内外の信頼できる公的ガイドラインへの案内、消化器疾患に関するよくある質問(FAQ)、そして理解を深めるための重要な用語集をまとめました。また、本ガイドの締めくくりとして、緊急受診が必要な危険なサイン(レッドフラグ)と、全体の要点を再度確認します。
日本の公式ガイドライン一覧:JSGE/JSH/MHLWの一次情報ハブ
医療情報を探す上で最も重要なのは、その情報が「どこから」発信されたか、つまり信頼できる「一次情報」であるかを確認することです。特に日本国内の医療においては、各分野の専門学会や厚生労働省が発行するガイドラインが、診療の根幹となります。
ここでは、本ガイドで主軸とした日本の主要な消化器系ガイドラインと公的サイトをご紹介します。これらは主に医療専門家向けに書かれていますが、多くのガイドラインでは患者さん向けの解説資料も同時に公開されています。
- 日本消化器病学会(JSGE): 多くの消化器疾患(胃炎、胃潰瘍、IBD、胆石症など)の診療ガイドラインを作成しています。JSGEのガイドライン一覧ページでは、専門家向けの全文PDF(例:消化性潰瘍診療GL2020)だけでなく、「患者さんとご家族のための胃食道逆流症(GERD)ガイド(2023年版)」のように、非常に分かりやすく書かれた患者さん向けの資料も提供されています。関連情報としてピロリ菌除菌と胃潰瘍予防に関する最新の知見もご覧ください。
- 日本肝臓学会(JSH): B型肝炎やC型肝炎、肝硬変といった肝疾患の専門ガイドラインを発行しています。特に治療法は日進月歩であり、C型肝炎治療ガイドライン(2025年 第8.4版)のように、最新の治療薬に対応するために頻繁に更新されています。日本の肝炎対策と予防に関する包括的なガイドも併せてお読みいただくことをお勧めします。
- 厚生労働省(MHLW): がん検診や感染症対策など、国民衛生の根幹に関わる指針を定めています。例えば、大腸がん検診や胃がん検診のガイドライン(2023年)は、検診の対象年齢や検査方法の基準となっています。
- 国立感染症研究所(NIID): 食中毒やウイルス性胃腸炎(ノロウイルスなど)の流行状況や病原体に関する最新の科学的知見を提供しています。感染症発生動向調査(IDWR)は、国内の感染症流行を把握するための重要な情報源です。
これらの情報源は、ご自身の状態を客観的に理解し、医師とのコミュニケーションを深めるための強力なツールとなります。ご自身の疾患に関連する項目を、ぜひ一度確認してみてください。
NICE・WHOの参照ポイント:一次診療と公衆衛生の視点
日本のガイドラインと合わせて、国際的な医療機関の指針を参照することは、ご自身の状態を多角的に理解する上で非常に役立ちます。国によって医療制度や承認されている薬剤が異なるため、すべてが日本に当てはまるわけではありませんが、特に「初期対応」や「生活指導」において優れた知見を提供しています。
- NICE(英国国立医療技術評価機構): 英国の一次診療(かかりつけ医)向けのガイドラインが充実しており、実践的で具体的なのが特徴です。例えば、GERD/ディスペプシア(CG184)やIBS(NG106)のガイドラインは、どのような症状があれば専門医に紹介すべきか、といった基準が明確です。IBSや機能性ディスペプシア(FD)でお悩みの方は、こうした国際的な基準も参考になります。
- WHO(世界保健機関): 公衆衛生の世界的な基準を示しています。特に下痢症に関するファクトシートで推奨されているORS(経口補水液)の使用原則は、世界共通の標準治療です。脱水症状の危険性と正しい水分補給の方法を理解し、家庭での初期対応を学ぶ上で不可欠な情報源です。
- NIH/NIDDK(米国国立衛生研究所/国立糖尿病・消化器・腎疾病研究所): 患者さん向けの教育資料が非常に豊富で、疾患の定義、症状、検査、一般的な管理方法について、平易な言葉で解説されています。
消化器疾患に関するよくある質問(FAQ)
ここでは、消化器疾患に関して患者さんから寄せられることの多い質問と、それに対する専門的な回答をまとめました。
Q:最新の日本のガイドラインは、どのくらいの頻度で改訂されますか?
A:疾患や治療法の進歩の速さによって異なりますが、多くの主要なガイドラインはおよそ5年前後で見直されます。例えば、B型肝炎やC型肝炎の治療は新薬の登場により劇的に進歩しているため、日本肝臓学会(JSH)のガイドラインはより短い間隔で更新される傾向にあります(例:C型肝炎GLは2025年に第8.4版が公開)。ご自身の疾患の最新情報を知るには、各学会の公式サイトを定期的に確認することが最も確実です。
Q:下痢や嘔吐がある時、スポーツドリンクではダメですか?
A:緊急時や軽度の水分補給であれば、スポーツドリンクも役立ちます。しかし、嘔吐や下痢によって失われるのは水分だけでなく、ナトリウムやカリウムといった「電解質」が大量に失われます。スポーツドリンクは糖分が多く電解質が少ない傾向があり、WHOが推奨するORS(経口補水液)とは組成が異なります。ORSは、腸から最も効率よく水分と電解質を吸収できるように設計されています。ひどい下痢や嘔吐が続く場合は、スポーツドリンクではなく、薬局などで入手できるORSを選ぶことが強く推奨されます。
Q:ピロリ菌は全員検査して除菌した方が良いのですか?
A:これは非常に重要な質問です。ピロリ菌感染は胃がんの強力なリスク因子であり、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の主な原因です。そのため、胃潰瘍や十二指腸潰瘍と診断された方、特定の胃炎(内視鏡検査で確認)がある方などは、保険適用で検査・除菌治療が強く推奨されます。一方で、厚生労働省は、症状のない方全員に一律で検査(集団スクリーニング)を行うことについては、利益と不利益(例:薬剤の副作用、耐性菌の出現)を考慮し、慎重な立場を取っています。まずは胃がん検診などを受け、ご自身の胃の状態を知り、医師と相談することが第一歩です。
Q:患者向けの分かりやすい資料はどこにありますか?
A:前述の通り、日本消化器病学会(JSGE)が発行している「患者さんとご家族のためのガイド」シリーズ(GERDや慢性膵炎など)が、Q&A形式で非常に分かりやすく、信頼性も高いため最もお勧めです。また、米国のNIDDKのサイトも、基本的な知識を得るのに役立ちます。
用語集:知っておきたい消化器のキーワード
医師の説明や診断書で目にする専門用語について、その意味を分かりやすく解説します。
- GERD(胃食道逆流症)
- 「ガード」と呼ばれます。胃酸を含む胃の内容物が食道に逆流し、胸やけ(胸の焼けるような不快感)や「呑酸(どんさん)」(酸っぱいものがこみ上げてくる感じ)を引き起こす疾患です。逆流性食道炎は、この逆流によって食道に炎症(ただれ)が起きた状態を指します。
- FD(機能性ディスペプシア)
- 「エフディー」と呼ばれます。胃カメラ(内視鏡)検査などで調べても、胃潰瘍やがんのような明らかな異常(器質的疾患)が見つからないにもかかわらず、胃もたれ、早期飽満感(すぐにお腹がいっぱいになる)、みぞおちの痛みといった不快な症状が続く状態を指します。胃の運動機能や知覚過敏が関係していると考えられています。
- IBS(過敏性腸症候群)
- 「アイビーエス」と呼ばれます。FDと同様に、大腸カメラ(内視鏡)などで検査をしても明らかな異常がないにもかかわらず、腹痛や腹部の不快感を伴い、下痢や便秘などの便通異常が長く続く疾患です。「下痢型」「便秘型」「混合型」などのタイプに分類されます。ストレスが症状を悪化させる一因となることも知られています。
- IBD(炎症性腸疾患)
- 「アイビーディー」と呼ばれます。これはIBSとは全く異なり、腸に「器質的な」炎症が起こる慢性の疾患です。主に「潰瘍性大腸炎」と「クローン病」の二つを指します。潰瘍性大腸炎は主に大腸の粘膜に炎症が起こり、血便や下痢が続きます。クローン病は口から肛門までの消化管のあらゆる場所に炎症が起こりうる疾患で、腹痛や体重減少などがみられます。どちらも国の難病に指定されています。
- ORS(経口補水液)
- 「オーアールエス」と読みます。下痢や嘔吐、高熱などで失われた水分と電解質(ナトリウム、カリウムなど)を、最も効率よく体内に吸収できるように科学的に設計された飲み物です。前述の通り、糖分が中心のスポーツドリンクとは異なり、脱水症状の治療と予防に用いられます。
- 血便/黒色便(メレナ)
- 血便は、便に血液が混じることです。鮮やかな赤色(鮮血便)の場合は、痔や大腸など、肛門に近い場所からの出血が疑われます。一方、黒色便(メレナ)は、イカスミや海苔の佃煮のようなドロッとした真っ黒い便のことで、胃や十二指腸など、肛門から遠い場所で出血し、血液が胃酸によって黒く変色したことを示します。どちらも消化管出血の重要なサインです。
受診が必要な症状(緊急性の高いレッドフラグ)
消化器系の症状の多くは、安静や食事療法で改善しますが、中には命に関わる危険な病気のサインが隠れていることがあります。以下のような「レッドフラグ(危険な兆候)」が見られる場合は、自己判断せず、速やかに医療機関を受診してください。
「これくらいで救急車を呼んでいいのだろうか」とためらう気持ちは分かりますが、特に下記の症状は、迅速な対応が予後を大きく左右します。
- 突然の激しい腹痛: これまでに経験したことのないような、立っていられないほどの激しい腹痛が突然始まった場合。特に、お腹全体が板のように硬くなっている場合は、胃や腸に穴が開く消化管穿孔(せんこう)や、腸閉塞、重篤な膵炎などの可能性があります。
- 吐血(血を吐く)または黒色便(メレナ): 胃や食道からの大量出血(胃潰瘍、食道静脈瘤破裂など)が疑われます。イカスミのような真っ黒い便(黒色便)は、上部消化管出血のサインです。
- 持続する鮮血便(真っ赤な血便): 痔によるものも多いですが、大腸憩室からの出血や虚血性腸炎、大腸がんなど、大腸からの大量出血の可能性もあります。
- 黄疸(おうだん): 白目や皮膚が黄色くなる状態です。腹痛や発熱を伴う場合は、胆石が詰まる急性胆管炎など、緊急の処置が必要な場合があります。肝臓の機能が急激に悪化している(急性肝炎など)サインでもあります。
- 水分が全く取れない嘔吐・下痢と、重い脱水症状: WHOが警告する重度の脱水(ぐったりしている、尿がほとんど出ない、意識がもうろうとしている)は、点滴による急速な水分・電解質の補給が必要です。特に高齢者やお子さんは脱水が急速に進行するため、注意が必要です。
これらの症状以外でも、「いつもと違う」「何かおかしい」と感じた場合は、ためらわずに医療機関(日中はかかりつけ医、夜間・休日は救急外来)に相談してください。
まとめ:ご自身の「消化器」と向き合うために
この総合ガイドでは、消化器疾患の基本的な仕組みから、具体的な症状、検査、さまざまな疾患(胃、腸、肝臓、膵臓など)、そして食事や予防法に至るまで、幅広く解説してきました。
最もお伝えしたい重要なメッセージは以下の3点です。
- 症状は「我慢しない」: 腹痛、胸やけ、下痢、便秘といった日常的な症状は、体が発する重要なサインです。「いつものこと」と我慢せず、特に症状が続く場合や悪化する場合は、専門医に相談することが早期発見の第一歩です。
- 「検査」を正しく理解する: 血液検査や内視鏡検査は、診断を確定し、適切な治療方針を決めるために不可欠です。検査の目的や流れを理解することで、不安を和らげ、積極的に健康管理に取り組むことができます。
- 「生活習慣」が最大の予防薬: 多くの消化器疾患は、バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙、節度ある飲酒といった日々の生活習慣が、消化器の健康を守る最も強力な予防策です。
私たちの体は非常に複雑ですが、正しい知識を持つことは、漠然とした不安を「具体的な行動」に変える力を持っています。このガイドが、皆さんとそのご家族がご自身の消化器の健康と向き合い、より良い毎日を送るための一助となれば幸いです。
本コンテンツはJHO編集部が医学文献に基づき作成しました。詳細は編集ポリシーをご覧ください。