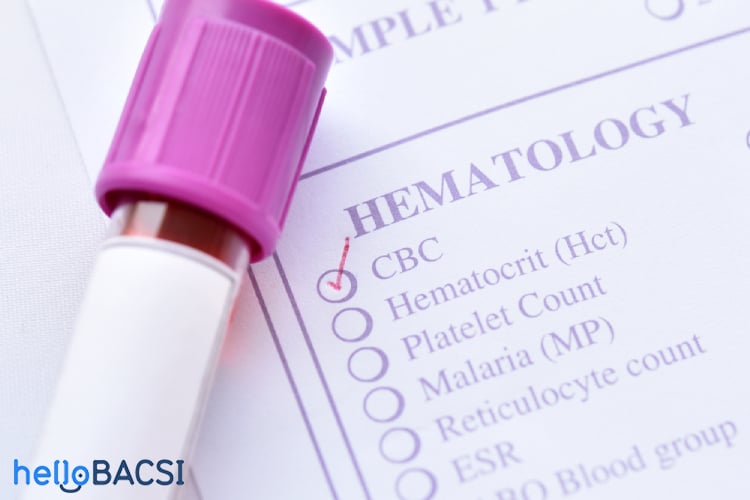この記事の科学的根拠
この記事は、入力研究報告書に明記された最高品質の医学的証拠のみに基づいています。以下のリストには、実際に参照された情報源と、提示された医学的ガイダンスとの直接的な関連性のみが記載されています。
- 日本血液学会: 本記事における慢性リンパ性白血病(CLL)の診断基準、病期分類、治療開始基準、および最新の治療法に関する記述は、日本血液学会が発行する「造血器腫瘍診療ガイドライン」に基づいています10。
- StatPearls (NCBI発行): リンパ球増加症の原因となる疾患の網羅的な解説、反応性とクローン性の鑑別診断、診断手順に関する記述は、StatPearlsのレビュー論文を主要な典拠としています1。
- CLL(慢性リンパ性白血病)患者・家族の会: 「無治療経過観察」に伴う患者の心理的な不安や経験に関する記述は、同会のウェブサイトで公開されている情報や代表者の言葉を参考にしています3。これは、記事のE-E-A-Tにおける「経験(Experience)」を担保する上で不可欠な情報源です。
- 国立がん研究センター / 厚生労働省: 日本における白血病およびCLLの疫学データ(罹患率など)は、国立がん研究センターのがん情報サービスおよび厚生労働省の全国がん登録の統計に基づいています1218。
要点まとめ
- リンパ球増加症は、多くの場合、ウイルス感染症などに対する一時的で正常な免疫反応(反応性増加)ですが、まれに慢性リンパ性白血病(CLL)などの血液疾患(クローン性増加)が原因の場合もあります。
- 診断の第一歩は、血液検査と血液塗抹標本でリンパ球の「絶対数」と「形態(顔つき)」を確認することです。自己判断せず、まずはかかりつけ医に相談することが重要です。
- 慢性リンパ性白血病(CLL)と診断されても、多くは進行が非常に緩やかであるため、すぐに治療を開始せず「無治療経過観察」を行うのが国際的な標準治療です。
- 「無治療経過観察」は「放置」ではなく、副作用を避け、最適なタイミングで効果的な治療を行うための積極的な医療戦略です。患者会などと連携し、不安と向き合うことが大切です。
- CLLの治療は近年、分子標的薬の登場で大きく進歩しており、治療が必要になった場合でも効果的な選択肢が増えています。
第1部:リンパ球増加症の基礎知識
リンパ球とは何か?- 体を守る免疫システムの主役
私たちの血液中には、赤血球、血小板、そして白血球と呼ばれる細胞が存在します。リンパ球は、この白血球の一種であり、免疫システムの中心的な役割を担う「体の防衛軍」です。外部から侵入してきたウイルスや細菌などの病原体、あるいは体内で発生したがん細胞など、体に害を及ぼす異物を認識し、攻撃・排除する働きを持っています。リンパ球は、主に以下の3つの種類に分けられ、それぞれが連携して巧妙な防御ネットワークを築いています2。
- B細胞(Bリンパ球): 病原体などを特異的に認識し、それらを無力化するための「抗体」と呼ばれるタンパク質を産生します。
- T細胞(Tリンパ球): ウイルスに感染してしまった細胞を見つけ出して破壊したり、免疫システム全体の司令塔として他の免疫細胞の働きを調節したりします。
- NK細胞(ナチュラルキラー細胞): 特定の指令がなくても、がん細胞やウイルス感染細胞を独自に見つけ出して攻撃することができる、生まれながらの殺し屋(ナチュラルキラー)です。
このように、リンパ球は私たちの健康を維持するために不可欠な存在です。
「リンパ球増加症」の定義と基準値
リンパ球増加症とは、病名ではなく、血液中のリンパ球の「絶対数」が基準値を超えて増加している状態を指します。重要なのは、白血球全体に占めるリンパ球の「割合(パーセント)」ではなく、血液1マイクロリットル(μL、1ミリリットルの1000分の1)あたりに何個のリンパ球が存在するかという「絶対数」で判断される点です1。
成人におけるリンパ球増加症の基準値は、一般的に血液1マイクロリットルあたり4,000個以上23、あるいは5,000個以上31とされることが多いですが、この基準は医療機関や検査方法、さらには年齢によっても異なります。特に小児は成人に比べてリンパ球数がもともと多く、基準値も高く設定されています31。また、「相対的リンパ球増加症」という状態もあります。これは、好中球など他の白血球が減少した結果として、リンパ球の割合(%)が見かけ上増加して見えるもので、リンパ球の絶対数が増えているわけではありません32。したがって、検査結果の数値だけで自己判断することは非常に危険であり、必ず医師からの説明を受けることが重要です。
第2部:リンパ球が増加する多岐にわたる原因
原因の全体像:反応性増加とクローン性(腫瘍性)増加
リンパ球が増加する原因は、非常に多岐にわたりますが、臨床的には大きく2つのカテゴリーに分類して考えます。この鑑別が、その後の対応を決定する上で最も重要となります1。
- 反応性リンパ球増加症: ウイルス感染症や細菌感染症、薬剤への反応など、何らかの外部からの刺激に対して、体の正常な免疫システムが応答し、一時的にリンパ球が増加する状態です。リンパ球増加症の大部分はこのタイプであり、原因が解決すればリンパ球数も正常に戻ります。
- クローン性(腫瘍性)リンパ球増加症: 単一の異常なリンパ球が、体からの制御を離れて自己増殖を始める状態です。これは、いわゆる「血液のがん」であり、慢性リンパ性白血病(CLL)や一部の悪性リンパ腫などが含まれます。持続的なリンパ球の増加が見られる場合に疑われます。
原因1:反応性リンパ球増加症(最も一般的なケース)
リンパ球増加症のほとんどは、こちらの反応性によるものです。特にウイルス感染症は最も頻度の高い原因です1。
ウイルス感染症
伝染性単核球症(EBウイルス): 若年層における反応性リンパ球増加症の典型的な原因で、「キス病」という別名でも知られています。唾液を介してエプスタイン・バー・ウイルス(EBV)に感染することで発症し、発熱、喉の痛み(咽頭痛)、首のリンパ節の腫れなどが主な症状です1。日本では衛生環境の向上により、多くが幼児期に症状なく(不顕性感染)EBVに感染するため、思春期以降に初感染して典型的な症状を示すケースは欧米ほど多くないという特徴があります16。
その他のウイルス感染症: 伝染性単核球症以外にも、サイトメガロウイルス(CMV)、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)の初期感染、インフルエンザ、風疹、肝炎ウイルスなど、さまざまなウイルス感染症がリンパ球増加の原因となり得ます1。
細菌感染症
一般的に細菌感染症では好中球が増加することが多いですが、百日咳や結核など、一部の細菌感染症ではリンパ球が増加することが知られています1。
その他の原因
上記以外にも、特定の薬剤に対するアレルギー反応(薬剤性過敏症症候群:DRESS症候群)、手術や外傷などの強い身体的ストレス、また頻度は低いですが喫煙などもリンパ球増加の原因となることがあります1。
原因2:クローン性(腫瘍性)リンパ球増加症(精査が必要なケース)
持続的にリンパ球の増加が見られる場合、血液がんやリンパ腫といった腫瘍性の疾患を考慮する必要があります。ここでは代表的な疾患名を概説します。詳細については第4部で深く掘り下げます。
慢性リンパ性白血病(CLL)
特に中高年以降の成人で、他に明らかな原因なくリンパ球の増加が持続する場合に最も考慮すべき重要な疾患です。成熟したBリンパ球ががん化し、非常にゆっくりと増殖していく血液がんです1。
その他の白血病・リンパ腫
CLL以外にも、急性リンパ性白血病(ALL)や、悪性リンパ腫の一種であるマントル細胞リンパ腫、濾胞性リンパ腫などが、異常なリンパ球(腫瘍細胞)を血液中に放出し、リンパ球増加症として発見されることがあります1。
第3部:診断への道のり – 医療機関で行われること
受診の目安:何科に行けばいい?
健康診断などでリンパ球の増加を指摘された場合、まずは結果を持ってかかりつけの内科、あるいは一般内科を受診することが第一歩です36。多くの場合は一時的な反応性の増加であり、経過観察や簡単な再検査で済むことも少なくありません。そこでさらに詳しい検査が必要と判断された場合に、血液疾患の専門家である「血液内科」へ紹介されるのが一般的な流れです37。ただし、リンパ球の増加に加えて、持続する発熱、原因不明の体重減少(半年で5kg以上など)、大量の寝汗、全身のリンパ節の腫れといった症状(B症状と呼ばれる)を伴う場合は、早めに医療機関を受診するよう心がけてください。
基本的な検査:血液検査(CBC)と末梢血塗抹標本
診断の第一歩は、採血による基本的な血液検査です。
全血球計算(CBC): この検査で、リンパ球の「絶対数」が本当に基準値を超えて増加しているかを確認します。同時に、赤血球や血小板の数に異常がないかもチェックします。
末梢血塗抹標本: これは診断において極めて重要な検査です。採取した血液をスライドガラスに薄く塗り広げ、特殊な染色を施した上で、臨床検査技師や医師が顕微鏡でリンパ球の「顔つき(形態)」を直接観察します1。ウイルス感染症の際にみられる、通常より大きく形のいびつな「異型リンパ球」や、慢性リンパ性白血病(CLL)で特徴的にみられる、壊れやすい腫瘍細胞である「Smudge cell(塗抹標本上で壊れた細胞)」などの所見がないかを確認し、反応性かクローン性かを見分けるための重要な手がかりを得ます。
専門的な検査:フローサイトメトリーと骨髄検査
末梢血塗抹標本などの結果からクローン性(腫瘍性)の疾患が疑われる場合には、さらに精密な検査に進みます。
フローサイトメトリー: 血液中の細胞にレーザー光を当て、細胞の表面にある目印(表面抗原、CD分類と呼ばれる)を解析する検査です。これにより、増加しているリンパ球がB細胞なのかT細胞なのか、そして正常な細胞の集団なのか、すべて同じ性質を持つ異常な細胞(クローン性)の集団なのかを正確に判定することができます。慢性リンパ性白血病(CLL)の診断を確定するためには必須の検査です1。
骨髄検査(骨髄穿刺・骨髄生検): 病気の確定診断や、病気の広がり、重症度を評価するために行われます。局所麻酔の後、胸や骨盤の骨に針を刺して、血液の工場である骨髄の組織や液体を採取して詳しく調べます。CLLの診断や病期分類、治療方針の決定のために行われることがあります14。
第4部:【特集】慢性リンパ性白血病(CLL)- 日本の現状と向き合い方
このセクションは、本記事の核となる部分です。健康診断でリンパ球増加を指摘された方が最も心配されるであろう慢性リンパ性白血病(CLL)について、日本の状況に特化して深く掘り下げ、他では得られない情報を提供することを目指します。
CLLとはどんな病気か?- 日本では稀だが知っておくべきこと
慢性リンパ性白血病(CLL)は、成熟したBリンパ球ががん化し、骨髄、血液、リンパ節などで非常にゆっくりと増殖していく血液がんです9。CLLは欧米では成人の白血病の中で最も頻度が高い疾患ですが、日本では比較的稀な疾患です。国立がん研究センターの統計によると、日本における白血病全体の罹患数は年間約14,000人ですが18、CLLの患者数はそのうちのごく一部であり、人口10万人あたりの年間発症者数は1人未満と推定されています12。多くは60歳以上の中高年に発症し、男性にやや多い傾向があります12。このように日本では稀な疾患であるという事実を知ることは、過度な不安を和らげる一助となるでしょう。
診断と病期分類:あなたの「現在地」を知る
CLLと診断された場合、次に治療方針を決定するために、病気が体のどのくらいまで広がっているかを示す「病期(ステージ)」を評価します。病期分類にはいくつかの方法がありますが、日本血液学会の「造血器腫瘍診療ガイドライン」10でも採用されている国際的な分類法として「Rai分類」と「Binet分類」が広く用いられています。これらは、リンパ球数、リンパ節・肝臓・脾臓の腫れの有無、そして貧血や血小板減少といった骨髄の働きの低下を示す兆候の有無に基づいて決定されます。
| 病期 | 状態 |
|---|---|
| 低リスク (0期) | リンパ球増加のみ |
| 中間リスク (I-II期) | リンパ節、肝臓、脾臓の腫れを伴う |
| 高リスク (III-IV期) | 貧血または血小板減少を伴う |
| 病期 | 状態 |
|---|---|
| A期 | リンパ節腫脹領域が2カ所以下 |
| B期 | リンパ節腫脹領域が3カ所以上 |
| C期 | 貧血または血小板減少を伴う |
これらの分類により、病気の進行度を客観的に把握し、今後の見通しや治療計画を立てるための重要な情報となります。
治療方針の決定:なぜ「無治療経過観察」が第一選択なのか?
このテーマは、本記事において最も重要であり、多くの患者さんが疑問に思う点です。CLLと診断されても、特に早期の段階では、すぐに治療を開始せず定期的な診察と血液検査で注意深く様子を見る「無治療経過観察(Watchful Waiting)」が国際的な標準治療とされています。多くの患者さんが抱く「がんが見つかったのになぜ治療しないのか」という強い不安に対し、JHO編集委員会は科学的根拠をもって真正面からお答えします。
その最大の理由は、「早期の段階で治療を開始しても、生存期間を延長する効果がないことが、多くの信頼性の高い臨床研究によって証明されている」からです10。CLLは非常にゆっくり進行するため、症状がなく病状が安定している早期の段階で治療を始めても、病気を根治させることは難しく、かえって不要な治療による副作用(感染症のリスク増加など)で生活の質を損なう可能性のほうが高くなります。そのため、日本血液学会のガイドラインでも採用されているiwCLL(International Workshop on CLL)の治療開始基準を満たすまでは、治療の利益が不利益を上回らないと判断されるのです。具体的な治療開始基準には以下のようなものがあります10。
- 病気の進行に伴う症状(10%以上の体重減少、極度の倦怠感、発熱、ひどい寝汗など)
- 進行性の骨髄不全(貧血や血小板減少の悪化)
- 巨大な脾臓の腫れ(痛みを伴うものなど)
- 巨大なリンパ節の腫れ
- リンパ球数が急激に増加している場合(例:6ヶ月以内に50%以上増加)
このことを理解するための最も重要なキーメッセージは、「『無治療経過観察』は『放置』ではなく、副作用を避けつつ最適なタイミングで最も効果的な治療を行うための、国際的に確立された『積極的な医療戦略』である」ということです。
患者さんの声:「経過観察」という不安とどう向き合うか
科学的な合理性を理解してもなお、「早期発見されたのに治療が始まらない」という状況に戸惑いや不安を感じるのは、多くの患者さんが抱く非常に自然な感情です。この点において、実際の患者さんの経験、すなわちE-E-A-Tにおける「E (Experience)」からの学びは極めて重要です。
CLL患者・家族の会の代表である齊藤治夫氏は、会のウェブサイトで「早期発見なのにそのまま経過観察が最良と判断されることがなかなか理解できません」と、多くの患者が共有するであろう率直な気持ちを綴っています3。この言葉は、当事者でなければ分からない深い不安を代弁しています。
しかし、齊藤氏は続けて、この「経過観察」という時間を、ただ待つだけの期間ではなく、「新しい薬剤や治療法を正しく理解し、自分自身の体を理解しながら自己決定できるようにする時間」と捉え直す視点を提唱しています4。これは非常に重要な示唆です。定期的な受診を通じて、医師との信頼関係を築き、病状の変化を共に注意深く見守っていく。そして、いざ治療が必要となった時に、納得して最善の治療法を選択できるように準備する。この期間は、病気と主体的に向き合うための大切な準備期間と考えることができるのです。
治療が必要になった場合:日本の最新薬物療法
無治療経過観察を経て、前述の治療開始基準を満たした場合には、薬物療法を開始します。CLLの治療は、近年「分子標的薬」の登場により劇的に進歩しました。これらの薬剤は、がん細胞の増殖や生存に不可欠な特定の分子だけを狙い撃ちにするため、従来の化学療法(抗がん剤)に比べて治療効果が高く、副作用も管理しやすい傾向にあります6。
日本血液学会のガイドラインによると10、日本で承認・使用されている主な薬剤は以下の通りです。
- 初回治療の標準薬: ブルトン型チロシンキナーゼ(BTK)阻害薬が広く用いられます。代表的な薬剤にイブルチニブやアカラブルチニブがあります。これらは内服薬で、がん細胞の生存シグナルをブロックします。
- 再発・難治性の場合の選択肢: BCL-2阻害薬であるベネトクラクスなどが選択肢となります。これは、がん細胞に「自滅(アポトーシス)」を促す薬剤です。
これらの新しい治療法の登場により、CLLは「長く付き合っていく病気」へと変わりつつあります。治療の詳細については、必ず主治医とよく相談し、ご自身の病状やライフスタイルに合った最適な方法を選択することが重要です。
第5部:日常生活での注意点とセルフケア
感染症予防の重要性
CLLや、その前段階であるモノクローナルBリンパ球増加症(MBL)の患者さんでは、病気そのものや治療の影響で正常なリンパ球の機能が低下し、免疫力が落ちることがあります。そのため、一般の方よりも感染症にかかりやすく、また重症化しやすい傾向があります21。日常生活においては、以下の基本的な感染対策を徹底することが非常に重要です。
- こまめな手洗い、うがい
- 流行期における人混みを避ける
- インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンなどの予防接種(必ず主治医に相談の上、不活化ワクチンを選択してください)
- バランスの取れた食事と十分な休養
定期的な健康診断と早期受診
無治療経過観察中であっても、病状が変化していないかを確認するために、医師から指示された間隔での定期受診を必ず守ることが何よりも大切です。血液検査や診察を通じて、病状の進行度を客観的に評価し続けます。また、次の予約を待たずに、持続する発熱、急なリンパ節の腫れ、ひどい倦怠感など、これまでになかった症状が出現した場合には、速やかに主治医に連絡し、相談するようにしてください。
よくある質問
Q1: リンパ球が増えていると言われましたが、自覚症状は全くありません。大丈夫でしょうか?
A1: リンパ球が増加していても、特に慢性リンパ性白血病(CLL)の初期段階では、自覚症状が全くないことがほとんどです14。症状がないからといって問題がないとは限りませんが、逆に言えば、すぐに命に関わるような緊急性の高い状態である可能性は低いとも言えます。重要なのは、症状の有無にかかわらず、専門医の指示に従って精密検査を受け、正確な診断を得ることです。その上で、経過観察で良いのか、何らかの対応が必要なのかを判断してもらうことが大切です。
Q2: 「無治療経過観察」中は、食事や運動で何か気をつけることはありますか?
A2: 「無治療経過観察」中に、病気の進行を直接抑えることが科学的に証明されている特別な食事やサプリメント、運動法は現在のところありません。最も重要なのは、免疫力を良好な状態に保つための一般的な健康管理です。バランスの取れた食事を心がけ、過度な疲労を避けて十分な睡眠をとり、適度な運動を続けることが推奨されます。ただし、前述の通り感染症のリスクは通常より高いため、手洗いやうがいなどの感染対策は重要です。また、新しい健康食品やサプリメントを始める前には、必ず主治医に相談してください14。
Q3: CLLは遺伝しますか?家族も検査を受けるべきでしょうか?
A3: CLLには家族内での発症がみられることがあり、血縁者(特に第一度近親者:親、子、兄弟姉妹)は一般の人に比べてCLLや関連するリンパ系疾患を発症するリスクがやや高いことが報告されています1。しかし、これはCLLが直接的に遺伝するという意味ではなく、あくまで「なりやすさ」に関連する遺伝的な要因があるかもしれない、というレベルです。ほとんどの患者さんの家族はCLLを発症しません。そのため、ご家族が症状もないのに定期的にCLLの検査を受けることは、現時点では推奨されていません。もしご家族に健康上の不安がある場合は、その旨を医師に伝えるのが良いでしょう。
結論
健康診断などで「リンパ球の増加」を指摘されることは、誰にとっても不安な出来事です。しかし、本記事で解説してきたように、その原因は多様であり、多くはウイルス感染などに対する一過性の正常な体の反応です。重要なのは、そのサインを無視せず、かといって過度に恐れることなく、冷静に専門家へ相談するという第一歩を踏み出すことです。
万が一、慢性リンパ性白血病(CLL)のような精査が必要な疾患であったとしても、今日の医療には多くの知見と選択肢があります。特に「無治療経過観察」が科学的根拠に基づく国際標準の「積極的な医療戦略」であることを正しく理解することは、不要な不安を和らげ、病気と主体的に向き合う上で大きな力となります。不安や疑問を一人で抱え込まず、主治医との対話を重ね、必要であれば患者会のような支援団体と繋がることで、心強いサポートを得ることができます。この記事が、リンパ球増加というサインを正しく理解し、あなたが次の一歩を自信をもって踏み出すための一助となれば幸いです。
参考文献
- Fariha, et al. Lymphocytosis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549819/
- MSDマニュアル家庭版. リンパ球増多症. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/13-血液の病気/白血球の病気/リンパ球増多症
- がん情報サイト「オンコロ」. CLL(慢性リンパ性白血病)患者・家族の会. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://oncolo.jp/organization/cll_kai
- CLL(慢性リンパ性白血病)患者・家族の会. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://cll.official.jp/
- Parikh SA, et al. Lymphocytosis and chronic lymphocytic leukaemia: investigation and management. Clin Med (Lond). 2022;22(3):234-238. doi:10.7861/clinmed.2022-0125. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9135088/
- Wierda WG, et al. Diagnosis and Treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia: A Review. JAMA. 2023;329(11):921-935. doi:10.1001/jama.2023.3794. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36943212/
- Maddocks-Christianson K, et al. Monoclonal B-cell Lymphocytosis – a review of diagnostic criteria, biology, natural history, and clinical management. Leuk Lymphoma. 2022;63(10):2275-2287. doi:10.1080/10428194.2022.2091444. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35767361/
- Parikh SA, et al. Lymphocytosis and chronic lymphocytic leukaemia: investigation and management. J R Coll Physicians Edinb. 2022;52(2):137-142. doi:10.1177/14782715221092789. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35584829/
- MSDマニュアル家庭版. 慢性リンパ性白血病(CLL). [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/13-血液の病気/白血病/慢性リンパ性白血病-cll
- 日本血液学会. 造血器腫瘍診療ガイドライン 2023年版(2024年改訂). [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: http://www.jshem.or.jp/gui-hemali/1_5.html
- 日本臨床腫瘍学会. 造血器腫瘍診療ガイドライン 2023年版. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00806/
- 国立がん研究センター がん情報サービス. 慢性リンパ性白血病/小リンパ球性リンパ腫. [インターネット]. 2023年. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://ganjoho.jp/public/cancer/CLL/index.html
- がん情報サイト. [患者さん向け]慢性リンパ性白血病の治療(PDQ®). [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://cancerinfo.tri-kobe.org/summary/detail_view?pdqID=CDR0000258005&lang=ja
- キャンサーネットジャパン. 慢性リンパ性白血病(CLL). [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.cancernet.jp/wp-content/uploads/2018/02/w_cll20211029.pdf
- 日本感染症学会. 51 伝染性単核球症(infectious mononucleosis). [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.kansensho.or.jp/ref/d51.html
- 国立感染症研究所. 伝染性単核症. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/im/010/im-intro.html
- 厚生労働科学研究成果データベース. 自己免疫性リンパ増殖症候群 (ALPS) の診療ガイドライン改訂について. [インターネット]. 2023年. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202310052A-buntan3.pdf
- 国立がん研究センター がん情報サービス. 白血病:[国立がん研究センター がん統計]. [インターネット]. 2021年. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/cancer/27_aml.html
- 医薬品医療機器総合機構. 2.2 緒言 急性骨髄性白血病(以下「AML」)は進行性の血液悪性腫瘍であり. [インターネット]. 2021年. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210318002/112130000_30100AMX00237_D100_1.pdf
- Hematopaseo. 『造血器腫瘍診療ガイドライン 2023年版』改訂のポイント 骨髄腫. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://hematopaseo.jp/special/gl2023_04/
- すこやか内科クリニック. 血液専門医が解説| モノクローナルBリンパ球増加症 | ハレノテラス…. [インターネット]. 2022年. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://sukoyaka-naika.com/bloglist/モノクローナルbリンパ球増加症/
- ざいつ内科クリニック. リンパ球数上昇の原因について. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.zaitsu-naika.com/hakketubyou/p3089.html
- まえだクリニック. 白血球系疾患について – 血液内科. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://maeda.clinic/hematology/leukocyte/
- MYメディカルクリニック. 白血球が高いと危険!?考えられる疾患と心房細動罹患リスクの増大について. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://mymc.jp/clinicblog/292987/
- 医書.jp. リンパ球数の増減をきたす疾患・病態 (臨床検査 61巻8号). [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.11477/mf.1542201342
- ヤンセン ファーマシューティカル カンパニーズ. イムブルビカ®、慢性リンパ性白血病の治療薬として日本の実臨床において. [インターネット]. 2024年. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://innovativemedicine.jnj.com/japan/press-release/20241017
- YouTube. 【BCF2024】慢性リンパ性白血病. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=MBd5DhSOROc
- Wikipedia. 伝染性単核球症. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://ja.wikipedia.org/wiki/伝染性単核球症
- NPO法人キャンサーネットジャパン. 慢性リンパ性白血病の治療. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.cancernet.jp/cancer/blood/cll-treatment
- CLLライフ. 慢性リンパ性白血病(CLL)の病態. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.cll-life.jp/cll/pathology/
- Wikipedia. リンパ球増多症. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://ja.wikipedia.org/wiki/リンパ球増多症
- 日本老年医学会. 2.主に白血病・腫瘍性疾患以外の病態. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/publications/other/pdf/clinical_practice_51_6_517.pdf
- 広島市医師会 臨床検査センター. 白血球の異常. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: http://www.labo.city.hiroshima.med.or.jp/wp-01/wp-content/uploads/2014/01/center201105-02.pdf
- 今日の臨床サポート. 伝染性単核球症 | 症状、診断・治療方針まで. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://clinicalsup.jp/jpoc/contentpage.aspx?diseaseid=156
- さきはら内科. 血液一般検査. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://website2.infomity.net/8470000086/medical/bloodtest.html
- ユビー. 慢性リンパ性白血病が疑われる場合、何科を受診したらよいですか?. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://ubie.app/byoki_qa/clinical-questions/uof31k09-w7
- さがみひまわりクリニック. 相模原市の内科、血液・腫瘍内科、糖尿病内科、呼吸器内科、アレルギー科. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://sagamihimawari.com/menu/血液・腫瘍内科/
- Apollo Hospitals. リンパ球増多症(リンパ球増加症) – 原因、症状、治療. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.apollohospitals.com/ja/corporate/diseases-and-conditions/lymphocytosis/
- CLLライフ. 再発・難治性の慢性リンパ性白血病(CLL)の薬物療法. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.cll-life.jp/cll/second-treatment/