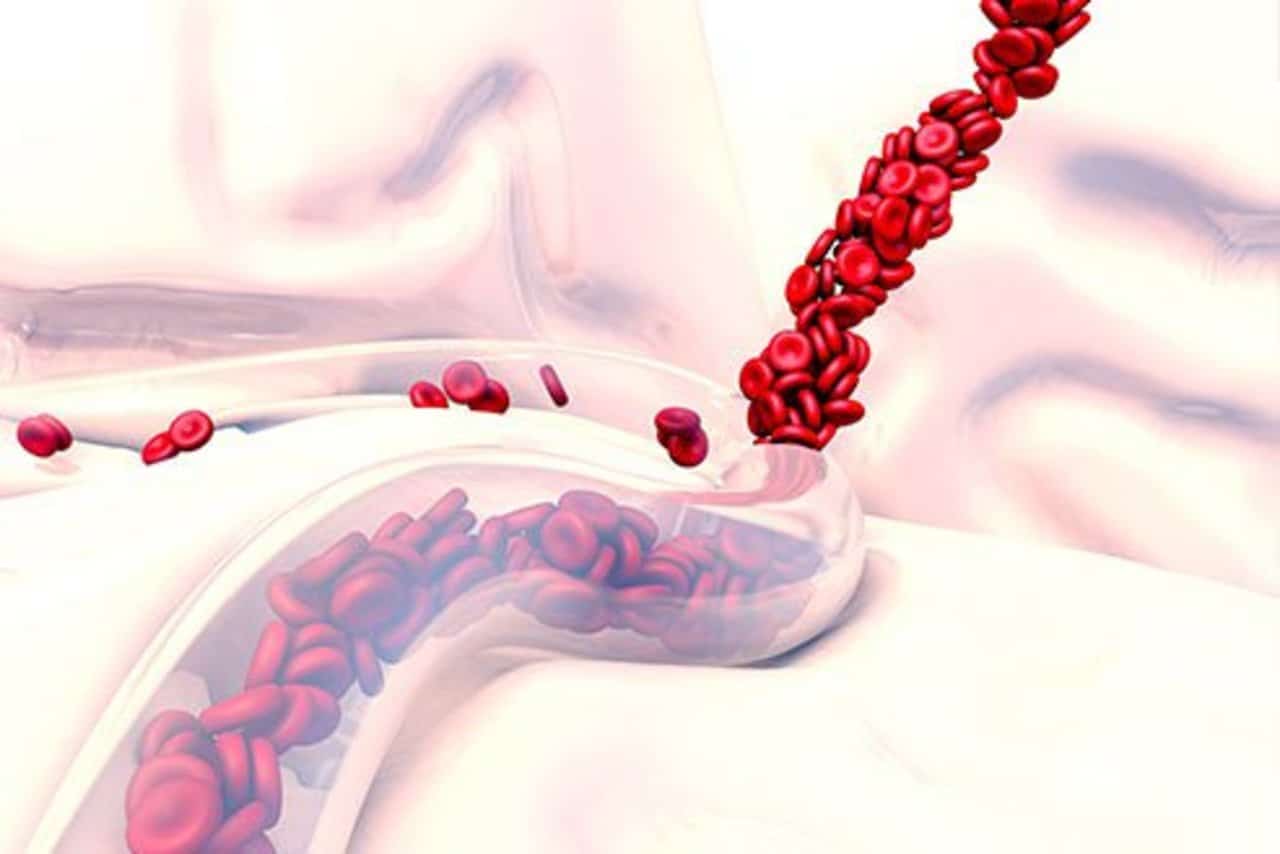要点まとめ
- 内出血には、自然に治る「あざ」から、生命を脅かす「脳出血」や「消化管出血」まで様々な種類が存在します。
- 「経験したことのない激しい頭痛」や「突然の片側麻痺」、「吐血・下血」は、直ちに救急車を呼ぶべき危険なサインです1。
- 原因は外傷だけでなく、高血圧や動脈瘤といった疾患、さらには「血液をサラサラにする薬」の服用も大きく関わっています2。
- 治療は原因と部位によって異なり、血圧管理から内視鏡手術、開頭手術まで多岐にわたります。最新の診療ガイドラインに基づいた迅速な対応が鍵となります27。
- 最大の予防策は、高血圧などの生活習慣病の管理と定期的な健康診断です。特に薬を服用中の方は、自己判断での中断は絶対に避けるべきです。
はじめに:その「内出血」、本当に大丈夫ですか?
「内出血」と聞くと、多くの人が机の角に足をぶつけてできる青あざを思い浮かべるかもしれません。しかし、その言葉が指し示す範囲は非常に広く、単なる「あざ」から、一刻を争う生命の危機に直結する病態まで、その深刻度は天と地ほども異なります。厚生労働省が発表した令和4年(2022年)の人口動態統計によれば、日本国内だけで年間33,480人もの人々が「脳内出血」で命を落としています13。これは、内出血が決して他人事ではない、重大な健康問題であることを示しています。
この記事では、JAPANESEHEALTH.ORG編集部が、どこにでも見られる「皮下出血(あざ)」から、緊急性の高い「頭蓋内出血」や「消化管出血」まで、内出血に関するあらゆる情報を網羅的に解説します。危険なサインの見分け方、多岐にわたる原因、そして日本国内の主要な学会が定める最新の診療ガイドラインに基づいた専門的な治療法、さらには日常生活で実践できる予防策まで、あなたの疑問と不安を解消するための知識を、科学的根拠に基づいて提供することをお約束します。
第1部:内出血の基礎知識 ― 種類とメカニズム
1.1. 内出血とは何か?― 体の中で何が起きているのか
内出血とは、医学的には「血管が損傷し、血液が血管の外にある体組織や体腔(たいくう)に漏れ出す状態」と定義されます。私たちの体には、出血が始まると自動的にそれを止める「止血」という精巧なシステムが備わっています。まず、損傷部位に血小板が集まってきて傷口を塞ぐ「一次止血」が起こり、続いて血液中の凝固因子と呼ばれるタンパク質群が連鎖的に働き、フィブリンという強固な網を形成して血餅(けっぺい)を作り、出血を完全に止める「二次止血」が完了します6。内出血が問題となるのは、この止血メカニズムが破綻したり、血管の損傷が大きすぎたりして、出血がコントロールできなくなった場合です。
1.2. 内出血の分類:場所による危険度の違い
内出血は、血液が漏れ出した場所によって、その危険度と緊急性が全く異なります。全身のどこでも起こりうる可能性がありますが、大きく分けると以下のようになります。
- 皮下出血(あざ): 最も一般的で、多くの人が経験するタイプの内出血です。皮膚の下の毛細血管が破れて出血します。原因は主に打撲などの軽い外傷で、通常は時間の経過とともに治癒します。出血直後は青紫色ですが、ヘモグロビンが分解される過程で緑色、黄色へと変化し、1〜2週間で消えていきます5。基本的な対処法は、安静(Rest)、冷却(Icing)、圧迫(Compression)、挙上(Elevation)を組み合わせたRICE処置です。
- 筋肉内出血: スポーツ外傷や肉離れなどで、筋肉内の比較的太い血管が損傷して起こります。皮下出血よりも腫れや痛みが強く、出血量が多い場合は、筋肉が硬い筋膜に覆われた区画(コンパートメント)の内圧が異常に上昇し、神経や筋肉への血流が途絶えて組織が壊死する「コンパートメント症候群」という重篤な状態に陥るリスクがあります。
- 関節内出血: 関節の中に出血がたまる状態です。血友病などの血液凝固異常を持つ患者さんで特によく見られますが、重度の捻挫や骨折でも起こります。放置すると、血液成分が関節軟骨を破壊し、関節の変形や機能障害につながる可能性があります。
- 生命を脅かす内出血:
- 頭蓋内出血: 頭蓋骨の内部で起こる出血の総称で、最も危険なタイプの一つです。脳の実質内で起こる「脳出血」や、脳を覆うくも膜の下で起こる「くも膜下出血」などが含まれます1。
- 胸腔内出血(血胸): 肺や心臓が収められている胸腔内に血液がたまる状態です。交通事故などの強い外傷や、大動脈瘤の破裂、肺がんなどが原因となります3。
- 腹腔内出血: 腹部の内臓を収める腹腔内への出血です。肝臓や脾臓といった血液が豊富な臓器(実質臓器)の損傷、子宮外妊娠の破裂、腹部大動脈瘤の破裂などが原因となります3。
- 消化管出血: 食道、胃、十二指腸、小腸、大腸といった消化管の内部で起こる出血です。胃潰瘍や大腸がんなどが主な原因です7。
第2部:危険なサインを見逃さない ― 症状からリスクを判断する
2.1. これが出たらすぐ病院へ!― 緊急性の高い危険な症状
以下に示す症状は、生命に関わる危険な内出血を示唆する可能性があります。一つでも当てはまる場合は、絶対に自己判断せず、ためらわずに救急車(119番)を呼んでください。
2.2. 「ただの不調」に隠れた内出血のサイン
すべての内出血が、上記のような劇的な症状を示すわけではありません。特に、消化管などで少量ずつの出血が慢性的に続いている場合、以下のような見過ごされがちな症状として現れることがあります。
- 原因不明の極度の疲労感、倦怠感
- めまい、立ちくらみ(貧血の進行による)
- 軽い運動や階段を上るだけでの息切れ、動悸
- 長引く原因不明の筋肉痛や関節痛
これらの症状は他の多くの疾患でも見られるため、内出血と結びつけるのは難しいかもしれません。しかし、これらの症状が続く場合、特に後述するような内出血のリスク因子(高血圧、抗血栓薬の服用など)を持つ人は、内出血の可能性も念頭に置き、一度医療機関に相談することを推奨します。
第3部:なぜ起こるのか?― 内出血の多様な原因
3.1. 外傷:直接的な血管の損傷
内出血の最も分かりやすい原因は、交通事故、高所からの転落、スポーツ中の激しい衝突といった物理的な衝撃による血管の損傷です。日本救急医学会などが策定した「外傷初期診療ガイドライン JATEC™」では、このような高エネルギー外傷の場合、外見上の傷がなくても体内に深刻な出血が起こっている可能性を常に考慮し、迅速な評価(Primary Survey)を行うことの重要性が強調されています3。特に、大腿骨(太ももの骨)や骨盤の骨折は、その周囲に太い血管が走行しているため、単独でも1〜2リットル以上の大量出血を引き起こし、出血性ショックに至る危険性が高いことで知られています6。
3.2. 疾患:血管や血液の異常が引き起こす内出血
外傷がなくても、体内の病的な変化が原因で内出血は起こります。
- 高血圧: 脳出血の最大の危険因子です1。持続的に高い血圧にさらされることで、脳の深部にある細い動脈の壁がもろくなり(リポヒアリノーシスという状態)、最終的に破綻してしまうことが主な原因です。日本脳卒中学会の「脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕」では、高血圧の厳格な管理が脳出血予防の根幹であるとされています2。
- 動脈瘤: 血管の壁が風船のように膨らんだ「こぶ」のことです。脳の動脈にできた脳動脈瘤が破裂すると「くも膜下出血」を、腹部の大動脈にできた腹部大動脈瘤が破裂すると、腹腔内に致死的な大出血を引き起こします。
- 血液の病気:
- 消化器疾患: 胃・十二指腸潰瘍、大腸憩室(腸壁の一部が外側に飛び出したもの)からの出血は、消化管出血の一般的な原因です。また、炎症性腸疾患(IBD)や、胃がん・大腸がんといった悪性腫瘍も、出血の原因となり得ます。日本消化器内視鏡学会のガイドラインでは、これらの疾患に対する内視鏡を用いた診断と治療の重要性が示されています4。
- その他の疾患: 糖尿病による高血糖状態が長く続くと、全身の血管がもろくなります。また、多発血管炎性肉芽腫症(GPA)20などの膠原病に伴う血管炎では、血管そのものが炎症を起こして破れやすくなります6。
3.3. 薬剤:医薬品が原因となる内出血
特定の病気の治療のために服用している薬が、内出血のリスクを高めることがあります。特に注意が必要なのが、「血液をサラサラにする薬」として知られる抗血栓薬です。
- 抗凝固薬: ワルファリンや、直接経口抗凝固薬(DOACs:プラザキサ、イグザレルト、エリキュース、リクシアナなど)が含まれます。これらは血液中の凝固因子が働くのを妨げ、血栓ができるのを防ぎます。心房細動による脳梗塞予防などに使われます。
- 抗血小板薬: アスピリンやクロピドグレル(プラビックス)などが代表的です。これらは血小板が固まるのを防ぎ、心筋梗塞や脳梗塞の再発予防に用いられます。
これらの薬を服用している人は、血が固まりにくくなっているため、転倒などの比較的軽い外傷でも、通常より大きな内出血や、重篤な頭蓋内出血を起こすリスクが高まります2。一方で、近年の研究では、DOAC服用者はワルファリン服用者に比べて頭蓋内出血のリスクが低いことも報告されています2。その他、長期間のステロイド剤の使用や、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬:ロキソニン、イブプロフェンなど)の服用も、胃の粘膜を荒らして消化管出血のリスクを高めることが知られています。
第4部:専門医による診断と治療 ― 最新の医療アプローチ
4.1. 診断:いかにして出血源を見つけるか
内出血が疑われる場合、医師は原因と出血部位を特定するために、様々な検査を迅速に行います。
- 問診と身体診察: どのような症状がいつから始まったか、頭をぶつけたりしなかったか、既往歴、そして特に抗血栓薬などの服用薬の情報を詳しく聴取します19。意識レベルの評価や、麻痺の有無、腹部の診察なども行われます。
- 画像検査:
- CT(コンピュータ断層撮影): 放射線を用いて体の断面を撮影する検査です。特に頭蓋内出血や、外傷による腹腔内・胸腔内の出血を迅速に診断するのに非常に有用です。
- MRI(磁気共鳴画像): 磁気を利用して体の内部を詳しく見る検査です。CTよりも小さな脳出血や、古い出血の痕跡を見つけるのに優れています。
- 超音波(エコー)検査: 腹部の内出血をベッドサイドで迅速に評価するFAST(Focused Assessment with Sonography for Trauma)や、心臓の周囲への出血の評価などに用いられます。
- 血管造影検査: カテーテルを血管内に挿入し、造影剤を注入しながらX線撮影を行う検査です。出血している血管そのものを特定でき、同時に後述するIVR治療に移行することも可能です。
- 血液検査: 貧血の程度(ヘモグロビン値)を調べて出血量を推定したり、血小板の数や凝固機能(PT-INR, APTTなど)を評価して、出血しやすい状態にあるかどうかを確認します。
4.2. 治療:出血を止め、命を救う
内出血の治療は、原因、部位、そして患者さんの全身状態によって大きく異なります。目標は、出血を迅速に止め、失われた血液を補い、生命を救うことです。
- 初期対応(救急): 意識や呼吸、循環が不安定な場合は、まずそれらを安定させることが最優先です。点滴による輸液や、失われた血液を補うための輸血が行われます。日本麻酔科学会などが定める「危機的出血への対応ガイドライン」では、大量出血時には赤血球だけでなく、血漿(FFP)や血小板もバランス良く輸血することの重要性が示されています16。
- 脳出血の治療:
- 血圧管理: 「脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕」では、急性期の血圧管理が極めて重要とされています。血圧が高いと血腫(血のかたまり)が増大するリスクがあるため、点滴薬を用いて収縮期血圧を速やかに140mmHg未満に下げることが強く推奨されています12。このガイドライン作成委員会の委員長は富山大学の黒田敏教授、脳出血班の班長は徳島大学の髙木康志教授が務めています2。
- 外科治療: 血腫が大きい場合や、血腫によって脳が強く圧迫されて意識障害が進行する場合には、手術が検討されます。頭蓋骨を開けて直接血腫を取り除く「開頭血腫除去術」や、小さな穴から内視鏡を挿入して血腫を吸引する、より低侵襲な「内視鏡下血腫除去術」などがあります1211。
- 消化管出血の治療:
- 外傷性出血の治療:
- IVR(カテーテル治療): Interventional Radiologyの略で、血管造影の手技を応用した治療です。足の付け根などから細いカテーテルを血管内に進め、出血している血管まで到達させ、そこを塞栓物質(金属コイルやゼラチンスポンジなど)で詰めて止血します。開腹手術に比べて体への負担が少ない利点があります。
- 外科手術: IVRでの止血が困難な場合や、複数の臓器に損傷がある場合は、開胸・開腹手術による直接的な止血が必要となります。重傷で状態が不安定な場合には、まず生命を救うための最小限の処置(ガーゼによる圧迫など)のみを行い、一度ICUで状態を安定させてから再度根本的な手術を行う「ダメージコントロール手術」という戦略がとられることもあります3。
第5部:予防と再発防止 ― あなたができること
5.1. 生活習慣の改善によるリスク管理
特に脳出血や生活習慣病に関連する内出血は、日々の生活を見直すことでそのリスクを大幅に下げることができます。
| リスク因子 | 具体的な対策 | 根拠・目的 |
|---|---|---|
| 高血圧 | ・減塩(1日6g未満が目標) ・野菜や果物を多く摂る ・定期的な有酸素運動(ウォーキングなど) ・医師から処方された降圧薬を正しく服用する |
脳出血の最大のリスク因子である血圧を正常範囲に保つことが最も重要です2。 |
| 糖尿病・高血糖 | ・バランスの取れた食事、適切なカロリー摂取 ・定期的な運動 ・血糖値の自己管理と定期的な受診 |
高血糖による血管の脆弱化を防ぎます6。 |
| 喫煙 | ・禁煙する(禁煙外来の活用も有効) | 喫煙は血管を収縮させ、動脈硬化を促進するため、内出血のリスクを高めます。 |
| 過度の飲酒 | ・節度ある適度な飲酒を心がける(または禁酒) | 大量の飲酒は血圧を上昇させ、肝機能障害による出血傾向を招く可能性があります。 |
5.2. 定期検診と服薬管理
年に一度の健康診断は、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病を早期に発見し、重大な内出血につながる前に対処するための絶好の機会です。また、抗血栓薬(血液をサラサラにする薬)を服用している方は、それがあなたの命を守るために必要な薬であることを理解し、絶対に自己判断で中断しないでください。他の医療機関を受診する際や、歯科治療を受ける際、薬局で市販薬を購入する際には、必ず抗血栓薬を服用していることを医療従事者に伝えてください19。
第6部:治療後の生活と患者さんの声
リハビリテーション
特に脳出血の後には、麻痺や言語障害(失語症)などの後遺症が残ることが少なくありません。機能回復のためには、早期からのリハビリテーションが極めて重要です。理学療法士(PT)による歩行訓練、作業療法士(OT)による日常生活動作の訓練、言語聴覚士(ST)による嚥下(飲み込み)や会話の訓練などを、個々の状態に合わせて行います。
患者が直面する現実
治療を終えて退院した後も、多くの患者さんやそのご家族は様々な困難に直面します。公益社団法人日本脳卒中協会が2020年に発表した「脳卒中を経験した当事者(患者・家族)の声」という調査報告書では、多くの患者さんが「退院後のリハビリの場の不足」や「社会復帰や就労に関する情報不足」、「後遺症、特に失語症によるコミュニケーションの困難」といった切実な悩みを抱えていることが浮き彫りになりました914。このような「生の声」は、内出血という病気が、単に一時の治療で終わるのではなく、その後の人生にも長く影響を及ぼしうることを私たちに教えてくれます。
支援情報
一人で悩みを抱え込む必要はありません。日本には、患者さんやご家族を支援するための様々な団体や窓口があります。
- 公益社団法人 日本脳卒中協会: 脳卒中に関する正しい知識の普及や、患者・家族への支援活動を行っています14。
- 一般社団法人 全国膠原病友の会: 膠原病患者さんのための情報交換や相談活動を行っています15。
- その他、疾患ごとや地域ごとに様々な患者会が存在します。お住まいの地域の保健所や、病院の医療相談室などで情報を得ることができます。
よくある質問 (FAQ)
Q1: ぶつけてもいないのに、足にあざがよくできます。大丈夫でしょうか?
Q2: 血液をサラサラにする薬(抗血栓薬)を飲んでいますが、転んで頭を打ちました。症状はありませんが、病院に行くべきですか?
A2: はい、必ずすぐに医療機関を受診してください。抗血栓薬を服用している方は、血が固まりにくいため、軽い打撲でも頭蓋内でじわじわと出血が広がる「慢性硬膜下血腫」などを起こすリスクが通常より高くなります。受傷直後は無症状でも、数週間から数ヶ月経ってから頭痛や麻痺などの症状が現れることがあります。頭を打った場合は、症状がなくても脳神経外科などの専門医の診察を受けることが極めて重要です。
Q3: 内出血の治療費はどのくらいかかりますか?
A3: 治療費は、内出血の種類、重症度、行われる治療(内視鏡、カテーテル、手術など)、入院期間によって大きく異なります。日本では公的医療保険が適用されますが、それでも自己負担額が高額になることがあります。しかし、「高額療養費制度」を利用すれば、1ヶ月の医療費の自己負担額が所得に応じた上限額を超えた場合に、その超過分が払い戻されます。詳しくは、病院の医療ソーシャルワーカーや、ご加入の健康保険組合にご相談ください。
Q4: 脳出血の後遺症で、リハビリはいつまで続けるべきですか?
A4: 脳卒中後の機能回復は、一般的に発症後3〜6ヶ月が最も著しいとされていますが、その後も緩やかに回復は続きます。リハビリテーションに「終わり」はなく、維持期・生活期においても、身体機能を維持・向上させ、より良い生活を送るために継続することが大切です。介護保険サービスを利用した通所リハビリや訪問リハビリなど、様々な選択肢があります。日本脳卒中協会の調査でも、退院後の継続的なリハビリの重要性と、その場の確保が課題として挙げられています10。
結論
内出血は、軽いあざから命を脅かす深刻な状態まで、非常に幅広い病態を含む言葉です。最も重要なことは、その多様性を理解し、特に危険なサインを見逃さず、迅速に行動することです。突然の激しい頭痛や麻痺、胸腹部の激痛、意識の変化といった症状は、ためらわずに専門医療の助けを求めるべきサインです。一方で、内出血の多くは、高血圧をはじめとする生活習慣病と深く関連しており、日々の健康管理が最大の防御策となります。定期的な健康診断を受け、医師の指導のもとで適切な治療を続けることが、あなたの未来の健康を守ることに繋がります。この記事が、内出血という複雑な問題に対するあなたの理解を深め、ご自身と大切な人の体を守るための一助となれば幸いです。不安な症状があれば、決して自己判断せず、速やかに医療専門家にご相談ください。
免責事項この記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的アドバイスに代わるものではありません。健康上の問題や症状がある場合は、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- HOKUTO. 脳出血 | ガイドライン(鑑別・症状・診断基準・治療方針). [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://hokuto.app/erManual/nwa0bxKArGqGhEjVUpGw
- 日本脳卒中学会. 脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕. [インターネット]. 2023 [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://www.jsts.gr.jp/img/guideline2021_kaitei2023.pdf
- 日本外傷学会, 日本救急医学会. 外傷初期診療ガイドライン JATEC™(改訂第6版). 東京: へるす出版; 2021.
- 医書.jp. 上部消化管出血. 消化器内視鏡. 2022;34(4). [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.24479/endo.0000000141
- リハサク. 内出血(あざ)を早く治す方法とは?内出血する原因や皮膚色の変化・要注意な病気も解説. [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://rehasaku.net/magazine/body/internalbleeding-healquickly/
- スギ薬局. 【医師監修】内出血の原因は?気になる病気の可能性や対処法…. [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://www.sugi-net.jp/sugi-channel/1100
- 日本消化器内視鏡学会. 非静脈瘤性上部消化管出血における内視鏡診療ガイドライン(第2版). Gastroenterological Endoscopy. 2024;66(7):1515-1541. [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://www.jstage.jst.go.jp/article/gee/66/7/66_1515/_html/-char/ja
- 日本消化器内視鏡学会. ガイドライン・提言. [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://www.jges.net/content/guideline
- 日本脳卒中協会. 脳卒中を経験した当事者 (患者・家族)の声. [インターネット]. 2020 [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://www.jsa-web.org/wp-content/uploads/2020/07/kanja_report2020.pdf
- 厚生労働省. 脳卒中患者・家族の実情調査 (中間報告). [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/001016278.pdf
- 日本神経治療学会. Ⅲ.脳出血. [インターネット]. 2009 [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://www.jsnt.gr.jp/guideline/img/nou2009_03.pdf
- ヨクミテ. 身に覚えのないあざの原因は?女性や高齢者に多い皮膚病を解説. [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://www.yoku-mite.care/symptoms/bruise/
- 厚生労働省. 令和4年(2022) 人口動態統計月報年計(概数)の概況. [インターネット]. 2023 [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai22/dl/gaikyouR4.pdf
- 日本脳卒中協会. 患者・家族委員会アンケート調査報告書「脳卒中を経験した当事者(患者・家族)の声」. [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://www.jsa-web.org/citizen/4019.html
- 一般社団法人全国膠原病友の会. [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://kougentomo.xsrv.jp/
- 日本麻酔科学会, 日本輸血・細胞治療学会. 危機的出血への対応ガイドライン. [インターネット]. 2017 [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://anesth.or.jp/files/pdf/kikitekiGL2.pdf
- サントリーウエルネス. 内出血の原因は?気が付かないうちに内出血している場合のおもな原因を解説. [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://www.suntory-kenko.com/column2/article/9350/
- 日本救急医学会. 対側損傷. [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://www.jaam.jp/dictionary/dictionary/word/0315.html
- MedicalNote. 覚えのないあざ:医師が考える原因と対処法|症状辞典. [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://medicalnote.jp/symptoms/%E8%A6%9A%E3%81%88%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%82%E3%81%96
- 慶應義塾大学病院 KOMPAS. 多発血管炎性肉芽腫症(granulomatosis with polyangiitis: GPA). [インターネット]. [引用日: 2025年6月18日]. Available from: https://kompas.hosp.keio.ac.jp/contents/000617.html