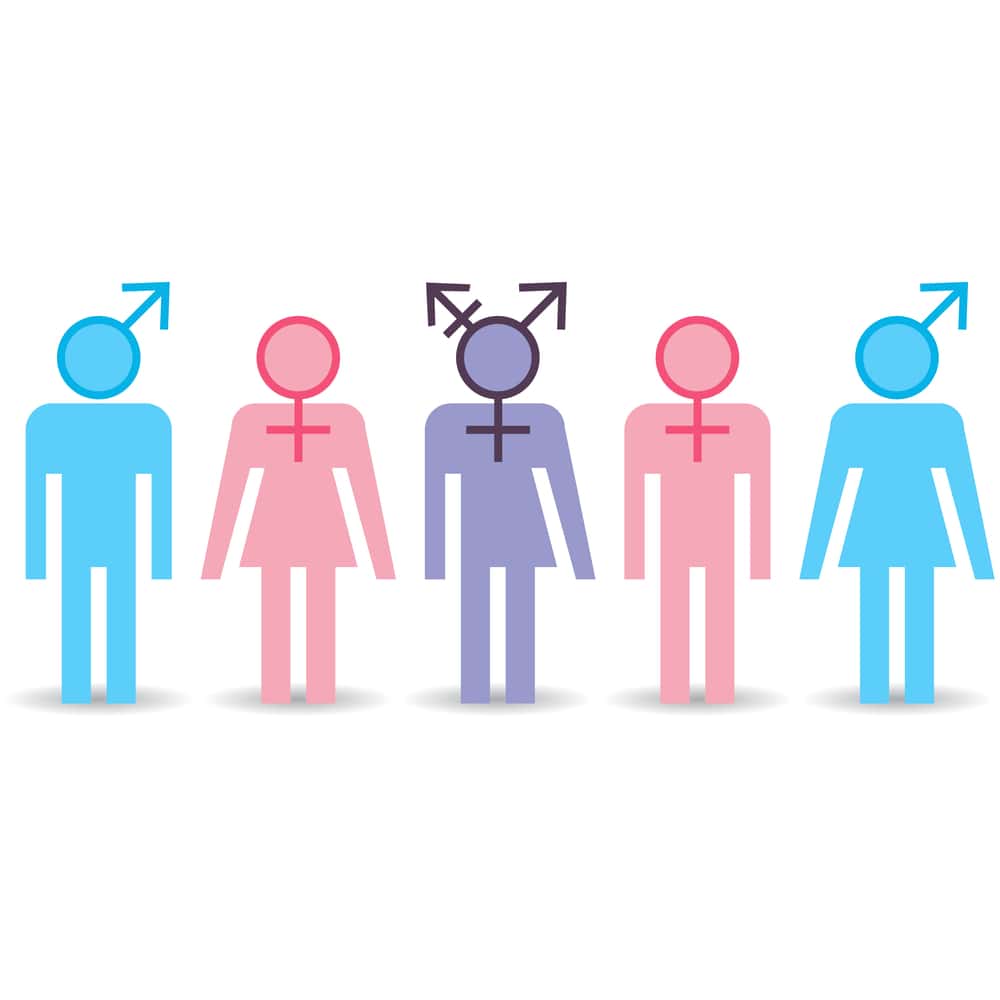本記事の監修医と信頼性について
この記事は、JAPANESEHEALTH.ORGの厳格な編集方針に基づき、精神科専門医の監修のもと作成されています。当サイトは、読者の皆様に最も信頼性の高い医療情報をお届けするため、世界的な医学研究、専門機関のガイドライン、そして日本国内の公的データを根拠とすることを徹底しています。全ての情報源は記事末尾の参考文献リストに明記し、完全な透明性を確保しています。
要点まとめ
- 性自認とは、自身の性別を内的にどう認識しているかという「こころの性」であり、出生時に割り当てられた生物学的性や、誰を好きになるかという性的指向とは独立した概念です。
- 世界保健機関(WHO)は最新の国際疾病分類(ICD-11)で、「性同一性障害」という言葉を廃止し、病気ではないことを示す「性別不合」という用語を採択しました。これは、性自認の多様性を尊重する世界的な流れを反映しています。
- 日本では、2023年10月に最高裁判所が、性別変更に生殖能力をなくす手術を求める法律の規定を違憲と判断しました。これは、日本の法制度が国際的な人権基準に近づくための歴史的な一歩です。
- 性自認と社会との不一致から生じる精神的苦痛(性別違和)は、うつ病や不安障害のリスクを高めることが研究で示されています。これは個人の問題ではなく、社会的な障壁や偏見が引き起こす健康格差です。
- 悩みを抱える当事者やその家族のために、日本には法務相談、医療、カウンセリング、コミュニティ支援など、専門的な相談窓口や支援団体が多数存在します。
性自認と子どもの支え方
「生物学的な性と違うかもしれない」「自分は男でも女でもない気がする」といったお子さんの言葉を聞いたとき、驚きや戸惑い、不安を感じる保護者の方は少なくありません。インターネットやSNSからさまざまな情報が流れてくる一方で、何が正しい知識なのか分からず、「どう関わるのが良いのか」と悩んでしまうことも多いでしょう。この記事のテーマである性自認(こころの性)は、とても個人的で繊細な問題だからこそ、間違った対応で傷つけてしまうのではないかという心配も自然な感情です。
このガイドでは、性自認という概念を整理しつつ、お子さんやご家族が直面しやすい悩みへの向き合い方を、医療的・法的・社会的な観点から丁寧に補足していきます。まずは、性自認そのものを「病気」ではなく、人間の多様性の一部として理解することが出発点になります。そのうえで、年齢や発達段階に応じた関わり方や、専門家への相談のタイミングを掴んでいくと、不安は徐々に整理されていきます。性自認に限らず、お子さんの健康全般についての基礎知識を押さえておきたい場合は、乳児期から思春期まで幅広いテーマを体系的に解説した小児科の総合ガイドも、全体像をつかむ助けになるでしょう。
性自認を理解するうえで大切なのは、「からだの性(生物学的性)」「こころの性(性自認)」「好きになる相手の性(性的指向)」が別々の軸である、という基本を押さえることです。思春期に入ると、二次性徴による体の変化や、周囲との比較、恋愛感情の芽生えなどが重なり、「自分は何者なのか」という問いが自然と強まります。この時期に、性やからだについての情報が不足していたり、偏見を含むメッセージだけを受け取ってしまうと、「自分はおかしいのではないか」という誤解につながり、性自認の揺らぎが必要以上に苦しいものになりがちです。思春期の体・心・人間関係を科学的に整理した思春期の性教育に関する完全ガイドに目を通しておくと、性自認の話題も含めて、親子で共通の土台を持ちながら対話しやすくなります。
実際にお子さんから性自認に関する打ち明け話があったときに、最初の一歩として最も重要なのは「否定も決めつけもしないで、まずは聴く」姿勢です。「そんなはずはない」と押さえつけたり、「あなたはトランスジェンダーなんだね」と急いでラベルを貼ったりする必要はありません。本人が何に困っているのか、どんな場面でつらさを感じているのかを、時間をかけて一緒に言葉にしていく過程そのものが、安心感につながります。性やからだについて年齢に応じた説明をする方法や、学校・友人との関係にどう配慮するかといった実践的なポイントは、思春期特有のからだの変化を扱った解説を併せて読むことで、見た目の悩みと性の自己イメージの結び付きも含め、より具体的に考えやすくなります。
次のステップとして大切なのは、性自認そのものだけでなく、「心と生活全体」を一緒に見守ることです。学校に行きづらくなっていないか、食事や睡眠のリズムが大きく乱れていないか、以前好きだったことへの興味を失っていないかなど、小さなサインの積み重ねが、メンタルヘルスの変化を示していることがあります。性別違和が強まり、うつ病や不安症、自傷行為などが重なる前に、早めに専門家につなぐことが負担を軽くする鍵です。思春期の心の不調のサインや、医療機関への相談の目安を整理した思春期の健康完全ガイドを参考にしながら、お子さんの変化を一緒に振り返ってみてください。
一方で、性自認に悩むお子さんを支える際に、避けたい対応もあります。「治してあげる」「男らしく(女らしく)させる」といった目的で、本人の意思に反して服装や髪型、しぐさを矯正しようとすると、自己否定感や孤立感が深まりやすくなります。また、本人の同意なく学校や親戚などにカミングアウトを強要したり、逆に「絶対に誰にも言ってはいけない」と過度に秘密扱いしたりすることも、安心して相談できる場を狭めてしまう要因になりがちです。この記事で紹介されているような法的支援窓口や相談機関と連携しながら、家庭では「どんな気持ちでも話していい場所」であることを、言葉と行動で示していくことが大切です。
性自認に関する悩みは、短期間で白黒つけられるものではなく、時間をかけて少しずつ輪郭が見えてくることが多いテーマです。保護者や周囲の大人が「正しい知識」と「ゆっくり見守る姿勢」の両方を持つことで、お子さんは自分のペースで安心して考え続けることができます。すべてを完璧に理解していなくても、「あなたの味方でいたい」というメッセージは必ず届きます。この記事と関連するガイドを手がかりに、性自認について学びながら、目の前のお子さんが自分らしく生きていける環境づくりを、一歩ずつ進めていきましょう。
第1部:基本概念の医学的定義
「性自認」を正確に理解するためには、まず関連する基本的な言葉の医学的定義を一つひとつ丁寧に確認することが不可欠です。これらの概念はしばしば混同されますが、それぞれが個人のアイデンティティを構成する異なる側面を示しています。
1.1. 性自認(Gender Identity)とは? —「こころの性」の科学
性自認とは、自分自身の性別をどのように感じ、認識しているかという、深く内的な自己感覚のことです1。これは、出生時に割り当てられた性別(Sex Assigned at Birth)と一致することもあれば、異なることもあります。性自認は、男性、女性、その両方、どちらでもない、あるいは流動的であるなど、非常に多様です。この内的な感覚は、他者から見える服装や行動、すなわち「性表現(Gender Expression)」とは必ずしも一致しません。アメリカ精神医学会(APA)は、この概念の核心を次のように定義しています。
性自認とは、人が自らを男性、女性、または他の性別として経験する、個人の内的な感覚を指す。(中略)性自認は、出生時に割り当てられた性別とは異なる場合がある12。
重要なのは、性自認が単なる「選択」や「思い込み」ではなく、個人のアイデンティティの根幹をなす、深く根差した感覚であるということです。
1.2. 生物学的性(Sex Assigned at Birth)とは?
生物学的性、より正確には「出生時に割り当てられた性別」とは、生まれた時の外性器の形状、染色体、性ホルモンといった生物学的な特徴に基づいて、医師や家族によって判断される分類です3。一般的には男性または女性の二つに分けられますが、生物学的な性は必ずしも明確な二元論で割り切れるものではありません。例えば、染色体、性腺、または性器の形状が典型的な男女の定義に当てはまらない「インターセックス(性分化疾患)」の人々も存在します。
1.3. 性的指向(Sexual Orientation)とは? —「好きになる性」
性的指向とは、どの性別の人に恋愛的、感情的、あるいは性的に惹かれるか、という「惹かれる対象の性」を指します3。これには、異性を好きになる「異性愛(ヘテロセクシュアル)」、同性を好きになる「同性愛(ゲイ、レズビアン)」、複数の性別を好きになる「両性愛(バイセクシュアル)」、誰にも性的魅力を感じない「無性愛(アセクシュアル)」、相手の性別に関わらず惹かれる「全性愛(パンセクシュアル)」など、多様な形があります。
最も重要な区別点は、性自認と性的指向が完全に独立した二つの異なる軸である、ということです。例えば、性自認が女性で、男性に惹かれる人(シスジェンダーの異性愛女性)もいれば、性自認が女性で、女性に惹かれる人(トランスジェンダーのレズビアン、またはシスジェンダーのレズビアン)もいます。ある人の性自認を知っても、その人の性的指向を推測することはできません。それは、ある人の身長を知っても、その人の目の色が分からないのと同じなのです。
第2部:国際的な診断基準と日本の現状 —「性同一性障害」から「性別不合」へ
性自認に関する医学的な理解は、この数十年で大きく進化しました。かつて「精神疾患」と見なされていた状態は、現在では個人の多様性の一側面として捉え直されています。この変化の中心にあるのが、国際的な診断基準の改訂です。
2.1. 世界の標準:WHOの「性別不合(Gender Incongruence)」
2019年に世界保健機関(WHO)が採択し、2022年1月に発効した最新の国際疾病分類第11版(ICD-11)は、この分野における歴史的な転換点となりました5。ICD-11では、これまで「性同一性障害」として「精神及び行動の障害」の章に分類されていた状態が削除され、代わりに「性の健康に関連する状態」という新しい章に「性別不合(Gender Incongruence)」という概念が導入されたのです4。
この変更は「脱病理化(de-pathologization)」と呼ばれ、トランスジェンダーであることがそれ自体病気や障害ではないという、国際的な医学界のコンセンサスを公式に示すものです。WHOは、性別不合を「個人の経験する性別(性自認)と、割り当てられた性別との間に、顕著で持続的な不一致がある状態」と定義しています4。この分類の目的は、診断名をつけてスティグマ(社会的な烙印)を押すことではなく、ホルモン療法や外科的処置など、必要な医療ケアへのアクセスを保証することにあります。
2.2. 米国精神医学会:DSM-5の「性別違和(Gender Dysphoria)」
アメリカ精神医学会(APA)が発行する精神疾患の診断・統計マニュアル第5版(DSM-5)では、「性別違和(Gender Dysphoria)」という用語が用いられています12。これはWHOの性別不合と密接に関連しますが、より「苦痛」の側面に焦点を当てた概念です。
DSM-5によれば、性別違和とは、自身の経験する性別と割り当てられた性別との不一致の結果として生じる、臨床的に意味のある重大な苦痛や、社会的・職業的機能の障害を指します12。ここでの極めて重要な区別は、トランスジェンダーであること自体が性別違和なのではなく、その不一致によって引き起こされる「苦痛」が診断の対象となる、という点です。トランスジェンダーやジェンダー多様性を持つ人の中には、この種の苦痛を経験せず、幸せに暮らしている人も多くいます。彼らは医学的な診断や介入を必要としません。
2.3. 日本における「性同一性障害」という用語の背景
国際的には「性別不合」や「性別違和」が標準となりつつある一方で、日本のメディアや行政、さらには医療現場でも、依然として「性同一性障害(Gender Identity Disorder, GID)」という言葉が広く使われています2,13。この「用語のギャップ」は、多くの混乱を生んでいます。
日本でこの古い用語が存続している主な理由は、それが法律の名称に明記されているためです。2004年に施行された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(通称:特例法)は、戸籍上の性別変更の要件を定めていますが、その法律名自体が「性同一性障害」という診断名に基づいています。したがって、法的な手続きを進める上では、この診断名が依然として必要不可欠となっているのが現状です。しかし、これが世界的な医学的コンセンサスからは時代遅れの見解であるという事実を理解しておくことは、現在の日本の状況を正確に把握する上で非常に重要です。
第3部:日本における法的・医療的プロセス
性自認に関する個人の歩みは、社会の法制度や医療システムと密接に関わっています。特に日本では、近年、この分野において大きな変化が起きています。
3.1. 【2023年最新】最高裁判決の衝撃:何が変わったのか?
本記事における最も重要な最新情報の一つが、2023年10月25日に日本の最高裁判所が下した歴史的な決定です。最高裁大法廷は、戸籍上の性別を変更するために、生殖能力を永続的に欠く状態にする手術(事実上の不妊手術)を義務付けていた特例法の規定(4号要件)について、個人の身体的完全性を侵害し、憲法に違反するとの判断を下しました6。
この決定は、長年にわたり国内外の人権団体や医学専門家から批判されてきた非人道的な要件を撤廃するものであり、日本のトランスジェンダーの人々の人権を保障する上で画期的な一歩です。世界トランスジェンダー・ヘルス専門家協会(WPATH)も、この判決を歓迎する声明を発表しています7,22。この判決により、今後は身体への大きな負担となる手術を受けることなく、戸籍上の性別を変更できる道が開かれました。これは、個人の意思と自己決定権を尊重する社会への大きな前進と言えます。
3.2. 戸籍上の性別変更:現在の要件と今後の展望
最高裁の違憲判決後も、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」に定められた他の要件は依然として存在します。2024年現在の主な要件は以下の通りです。
- 18歳以上であること。
- 現に婚姻をしていないこと。
- 現に未成年の子がいないこと。
- 性別の取扱いの変更を求める性別の性器に係る部分に近似する外観を備えていること(外観要件)。
このうち「外観要件」については、その合憲性を巡る議論が続いており、最高裁は審理を高等裁判所に差し戻しています。今後、この要件についても司法判断が示される可能性があり、日本の法制度は引き続き変化の過程にあると言えます。
3.3. 日本における医療的移行(ジェンダー・アファーミング・ケア)
ジェンダー・アファーミング・ケアとは、個人の性自認を肯定し、尊重することを目指す医療的アプローチの総称です。これには、心理的サポートからホルモン療法、外科的治療まで、幅広い選択肢が含まれます。日本における典型的なプロセスは、日本産科婦人科学会などのガイドラインに沿って進められますが、その内容はWPATHが示す国際的なケア基準(SOC8)に近づきつつあります10,13,23。
- 心理的カウンセリング: 精神科医や臨床心理士によるカウンセリングを通じて、本人の性自認や性別違和の状況を確認し、医療的移行に関する情報提供と意思決定の支援を行います。
- ホルモン療法: 身体的特徴を自認する性に近づけるため、ホルモン剤(男性ホルモンまたは女性ホルモン)の投与を行います。これは、WPATHのSOC8において、性別違和を軽減するために医学的に必要かつ効果的な治療法として推奨されています10。
- 外科的選択肢: 胸部の手術(乳房切除術や豊胸術)や、性別適合手術(性器の手術)など、様々な外科的選択肢があります。これらの手術は、本人の希望と医学的な適応に基づいて、慎重に検討されます。
これらのケアは、かつてのような「美容目的」や「選択的なもの」という見方とは異なり、性別違和による精神的苦痛を和らげるために「医学的に必要なケア」である、というのが現代の国際的なコンセンサスです10,17。
第4部:メンタルヘルスと社会的課題
性自認について語る上で、メンタルヘルスの問題は避けて通れません。トランスジェンダーやジェンダー多様性の人々が経験する精神的な困難は、個人の資質によるものではなく、社会的な環境が大きく影響しています。
4.1. 統計データが示す現実:日本のLGBTQ+とメンタルヘルス
数々の信頼できる調査が、LGBTQ+の人々、特にトランスジェンダーの人々が深刻なメンタルヘルスの格差に直面していることを明らかにしています。
- 認定NPO法人虹色ダイバーシティが2023年に実施した大規模調査「nijiVOICE 2023」によると、日本のトランスジェンダー男性の48.1%、トランスジェンダー女性の45.0%が、過去1年間に精神的な不調(うつ、不安障害など)を経験したと回答しています。これはシスジェンダー(異性愛者)の男性(16.3%)や女性(22.7%)と比較して著しく高い割合です9。
- 2024年に発表されたノンバイナリー(男女の枠に当てはまらない性自認を持つ人)の若者を対象とした国際的なメタ分析では、彼らがシスジェンダーの若者よりも高い割合でうつや不安症状を経験し、トランスジェンダーの若者と同等の高い自傷行為率を示すことが報告されています16。
これらのデータが示すのは、彼らが本質的に精神的に弱いということでは断じてありません。むしろ、日常的に直面する差別、偏見、いじめ、家族からの拒絶、医療へのアクセスの困難さといった「マイノリティ・ストレス」が、精神的健康を蝕む大きな原因となっているのです。この問題は、個人の治療だけでなく、社会全体の理解と変革を必要としています。
4.2. 子供と若者の性自認:親と社会ができるサポート
自分の子どもがジェンダーの多様性について打ち明けたとき、多くの親は戸惑い、どうサポートすればよいか悩むかもしれません。株式会社電通の「LGBTQ+調査2023」では、当事者の7割以上が「アライ(支援者)はもっと増えるべき」と考えているのに対し、非当事者で「アライになりたい」と考える人は約4割に留まり、意識の差(アライ・ギャップ)が存在することが示唆されています19。
しかし、研究は一貫して、家族や社会からの受容的で肯定的なサポートが、若者の精神的健康にとって極めて重要であることを示しています。WPATHのケア基準第8版の「子ども」と「思春期」に関する章でも、家族のサポートが良好な予後につながる最も強力な要因の一つであると強調されています11。拒絶的な態度が自殺念慮やうつ病のリスクを劇的に高める一方で、肯定的な関わりはそれらのリスクを大幅に低減させることがわかっています15。
ご家族・支援者の方へ:サポートのためのヒント
- 話を聴き、信じる:本人が打ち明けてくれたことを尊重し、まずはその気持ちを真摯に受け止めましょう。「気のせいだ」と否定せず、本人の感覚を信じることが第一歩です。
- 学び続ける:この記事のような信頼できる情報源から、性自認について学びましょう。知識は不安を減らし、より良いサポートにつながります。
- 名前と代名詞を尊重する:本人が望む名前や代名詞(彼、彼女など)を使うことは、その人の存在を肯定する強力なメッセージになります。間違えても、謝って訂正すれば大丈夫です。
- 専門家と繋がる:一人で抱え込まず、ジェンダーを専門とする医師、カウンセラー、あるいは支援団体に相談しましょう。あなた自身のサポートも大切です。
第5部:支援と情報を求めるあなたへ(リソース集)
性自認に関する悩みや疑問を抱えている当事者、ご家族、そして支援者のために、日本国内には信頼できる相談窓口や支援団体が数多く存在します。一人で悩まず、これらのリソースを活用してください。
5.1. 専門家による相談窓口(医療・心理)
ジェンダー問題に特化した医療機関やカウンセリングサービスは全国に存在します。お住まいの地域の「ジェンダークリニック」や、LGBTQ+のカウンセリングを専門とする臨床心理士を探すことが、第一歩となります。
5.2. 法的支援と相談窓口
戸籍上の性別変更や、職場での差別など、法的な問題に直面した際には、専門家の助けが不可欠です。
- 日本弁護士連合会 – LGBTQ相談窓口: 全国の弁護士会が設置する、LGBTQ+関連問題に特化した法律相談窓口のネットワークです。無料または低額で相談できる場合が多く、専門的なアドバイスを受けることができます8。
5.3. コミュニティと支援団体
同じような経験を持つ人々と繋がったり、安全な場所で情報を得たりすることは、大きな支えになります。
- プライドハウス東京レガシー: 日本初の常設大型LGBTQ+センターで、安全な居場所の提供や情報発信を行っています14。
- 認定NPO法人ReBit(リビット): LGBTQ+の若者支援に特化し、教育現場への出張授業やキャリア支援などを通じて、多様性を尊重する社会の実現を目指しています21。
- 特定非営利活動法人SHIP: 関東圏を中心に、ゲイ・バイセクシュアル男性やトランスジェンダーの人々が集えるコミュニティセンターを運営しています14。
- よりそいホットライン: 厚生労働省の補助事業で、24時間365日、誰でも無料で利用できる電話相談窓口です。ガイダンスに従って専門回線を選ぶことで、性的マイノリティに関する悩みを専門の相談員に話すことができます20。
これらは数あるリソースの一部です。厚生労働省や法務省のウェブサイト、地域の自治体の人権担当部署なども、さらなる情報を提供しています18。
よくある質問 (FAQ)
トランスジェンダーであることは精神疾患ですか?
いいえ、精神疾患ではありません。世界保健機関(WHO)は最新の国際疾病分類(ICD-11)において、トランスジェンダーであることを病気や障害のリストから除外し、「性別不合」として性の健康に関連する状態の章に再分類しました4。これは、トランスジェンダーであることが人間の多様性の一部であり、それ自体が治療の対象ではないという、国際的な医学界の明確なコンセンサスを反映したものです。ただし、自身の性自認と社会から認識される性別との不一致により著しい精神的苦痛を感じる場合(性別違和)、その苦痛を和らげるための医療的・心理的サポートが提供されることがあります。
結論
性自認は、私たち一人ひとりのアイデンティティの根幹をなす、深く個人的な感覚です。それは、生物学的な特徴や、誰に惹かれるかという性的指向とは明確に区別されるべきものです。国際社会では、性自認の多様性を尊重し、かつての病理的な見方から脱却する動きが標準となっています。2023年の最高裁判決に見られるように、日本の法制度もまた、この世界的な人権基準に沿う形で、大きな変革の時代を迎えています。
統計が示すように、社会的な無理解や偏見は、当事者のメンタルヘルスに深刻な影響を及ぼす健康問題です。この課題を乗り越えるために最も重要な鍵は、私たち一人ひとりが正確な知識を身につけ、共感と受容の心を持つことです。この包括的なガイドが、読者の皆様にとって、性自認への理解を深め、より多様で思いやりのある社会を築くための一助となることを心から願っています。
免責事項この記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的アドバイスに代わるものではありません。健康上の問題や症状がある場合は、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- Wikipedia. Gender identity. [インターネット]. [2025年6月19日引用]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_identity
- 厚生労働省. Ⅱ.職場と性的指向・性自認をめぐる現状. [インターネット]. [2025年6月19日引用]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/000625158.pdf
- 島根県. 性的指向・性自認(LGBT等). [インターネット]. 人権. [2025年6月19日引用]. Available from: https://www.pref.shimane.lg.jp/life/jinken/jinken/lgbtq/
- World Health Organization. Gender incongruence and transgender health in the ICD. [インターネット]. [2025年6月19日引用]. Available from: https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/gender-incongruence-and-transgender-health-in-the-icd
- Merck Manuals Professional Version. Gender Incongruence and Gender Dysphoria. [インターネット]. [2025年6月19日引用]. Available from: https://www.merckmanuals.com/professional/psychiatric-disorders/gender-incongruence-and-gender-dysphoria/gender-incongruence-and-gender-dysphoria
- LGBT法連合会. 【声明】性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の3条1項4号規定を憲法違反と判断する最高裁判所の決定について. [インターネット]. 2023. [2025年6月19日引用]. Available from: https://lgbtetc.jp/news/2931/
- gid.jp. 2023年(令和5年)10月25日、性同一性障害特例法の手術要件に関する意見表明. [インターネット]. 2023. [2025年6月19日引用]. Available from: https://gid.jp/opinion/opinion2023111101/
- 日本弁護士連合会. LGBTQに関する相談窓口. [インターネット]. [2025年6月19日引用]. Available from: https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/other/lgbtq.html
- Nijiiro Diversity. Japan LGBTQ+ Survey of Work and Life “nijiVOICE 2023”. [インターネット]. 2024. [2025年6月19日引用]. Available from: https://nijibridge.jp/wp-content/uploads/2024/03/20240225nijiVoice2023_ENG.pdf
- Coleman E, Radix AE, Bouman WP, Brown GR, de Vries ALC, Deutsch MB, et al. Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, Version 8. Int J Transgend Health. 2022;23(sup1):S1-S259. doi: 10.1080/26895269.2022.2100644. Available from: https://www.wpath.org/publications/soc8
- World Professional Association for Transgender Health. SOC8 Chapters. [インターネット]. [2025年6月19日引用]. Available from: https://wpath.org/publications/soc8/chapters/
- American Psychiatric Association. What Is Gender Dysphoria?. [インターネット]. [2025年6月19日引用]. Available from: https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria
- 日本産婦人科医会. (2)性同一性障害の診療の流れ. [インターネット]. [2025年6月19日引用]. Available from: https://www.jaog.or.jp/note/(2)性同一性障害の診療の流れ/
- 認定NPO法人 虹色ダイバーシティ. LGBTQ 支援団体リスト. [インターネット]. [2025年6月19日引用]. Available from: https://nijiirodiversity.jp/649/
- American Psychological Association. APA Resolution on Gender Identity Change Efforts. [インターネット]. 2015. [2025年6月19日引用]. Available from: https://www.apa.org/about/policy/resolution-gender-identity-change-efforts.pdf
- Busoni FM, Griesi D, Tascini G, Michelone C, Crescentini C, Fabbro F. Mental health of non-binary youth: a systematic review and meta-analysis. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2024;18(1):53. doi: 10.1186/s13034-024-00735-w. Available from: https://www.researchgate.net/publication/384768792_Mental_health_of_non-binary_youth_a_systematic_review_and_meta-analysis
- McCool ME, Zwickl S, Hughto JMW, Turban JL. Interventions for Gender Dysphoria and Related Health Problems in Transgender and Gender-Expansive Youth: A Systematic Review of Benefits and Risks to Inform Practice, Policy, and Research. JAMA Netw Open. 2024;7(5):e2411531. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.11531. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40109385/
- 厚生労働省. 性的マイノリティに関する理解増進に向けて~厚生労働省の取組. [インターネット]. [2025年6月19日引用]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index_00007.html
- Dentsu Inc. Dentsu Conducts LGBTQ+ Survey 2023. [インターネット]. 2023. [2025年6月19日引用]. Available from: https://www.group.dentsu.com/en/news/release/001047.html
- 社会的包摂サポートセンター. 性的指向(好きになる性)や性自認(自分の認識する性別)に関してお悩みの方へ. [インターネット]. よりそいホットライン. [2025年6月19日引用]. Available from: https://www.since2011.net/yorisoi/n4/
- 認定NPO法人ReBit. [インターネット]. [2025年6月19日引用]. Available from: https://rebitlgbt.org/
- World Professional Association for Transgender Health. WPATH Public Statements. [インターネット]. [2025年6月19日引用]. Available from: https://wpath.org/resources/public-statements/
- 日本女性心身医学会. 性同一性障害. [インターネット]. 一般のみなさまへ. [2025年6月19日引用]. Available from: https://www.jspog.com/general/details_83.html