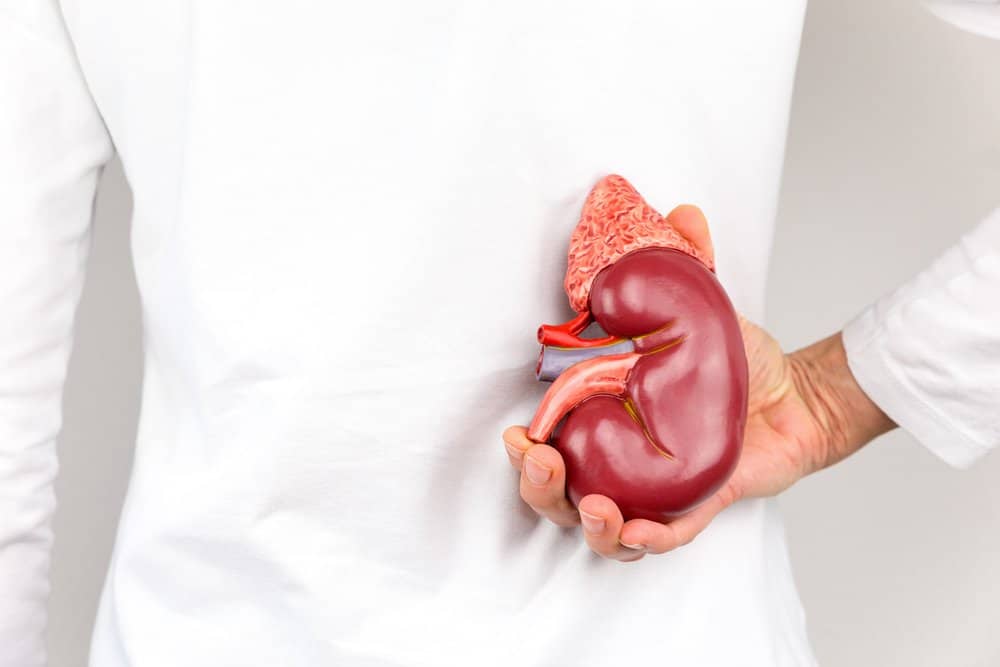本記事の科学的根拠
この記事は、引用されている最高品質の医学的証拠にのみ基づいています。以下に示すリストには、実際に参照された情報源のみが含まれており、提示された医学的ガイダンスとの直接的な関連性も記載されています。
- 厚生労働省: 日本における慢性腎臓病(CKD)の公衆衛生上の課題、透析医療の現状、および食事療法に関する公的データや指針は、同省の報告書に基づいています。
- 日本腎臓学会 (JSN): CKDの定義、病期分類、食事療法基準、および薬物療法に関する日本の臨床診療ガイドラインの主要な情報源です。本記事は、特に『エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023』を重要な根拠としています。
- 日本透析医学会 (JSDT): 日本の慢性透析療法の患者数や統計に関する年次報告は、同学会の調査データに基づいています。
- 日本泌尿器科学会 (JUA) および 日本癌治療学会 (JSCO): 腎がんの診断と治療に関する指針は、これらの学会が作成・参照する診療ガイドラインに基づいています。
- KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes): CKDの管理に関する国際的な視点と比較を提供するための、国際的な診療ガイドラインの情報源です。
要点まとめ
- 腎臓は背中側の腰のあたりに左右一対ある、握りこぶし大の臓器です。老廃物の排泄だけでなく、体液バランス、血圧、ホルモン産生など生命維持に不可欠な多様な機能を担っています。
- 慢性腎臓病(CKD)は日本の成人の7〜8人に1人が罹患する「国民病」ですが、初期症状がほとんどないため「沈黙の臓器」と呼ばれます。
- CKDの管理では、食塩制限(1日6g未満)と、病期に応じたたんぱく質・カリウムの管理が基本となります。
- 近年の薬物療法では、SGLT2阻害薬が糖尿病の有無にかかわらず、CKDの進行を抑制する中心的な薬剤として位置づけられています。
- 気になる症状がある場合や、健康診断で腎機能の異常を指摘された場合は、自己判断せず、かかりつけ医や専門医に相談することが極めて重要です。
第1章 腎臓:解剖学的および生理学的構造
腎臓の機能を理解するためには、まずその物理的な構造、すなわち肉眼レベルの解剖から顕微鏡レベルの機能単位に至るまでの精緻な設計を把握することが不可欠です。
1.1 肉眼解剖学:正確な位置、寸法、および構造的特徴
腎臓は後腹膜腔に位置する一対の臓器であり、脊柱を挟んで左右対称に配置されています4。具体的には、腰部のやや上方、背中側にあり、一般的には上部腰椎の高さに位置します5。肝臓の存在により、右腎は左腎よりもわずかに低い位置にあるのが通常です。形状は特徴的な「そら豆」の形をしており6、大きさは成人で握りこぶし大、長径約11cm、短径約5cm、重量は1個あたり約150gです4。この比較的小さな臓器に、心臓が1分間に送り出す血液の約4分の1という膨大な量が流れ込んでいる事実は、その代謝活動の高さと生命維持における重要性を物語っています7。
腎臓の内部構造は、血液の濾過と尿の生成・排泄という機能に最適化されています。最外層は腎被膜という線維性の膜で覆われ、その内側には皮質と髄質が存在します。髄質には腎錐体と呼ばれる円錐状の構造があり、ここで生成された尿は腎杯を経て腎盂に集められ、尿管へと送り出されます8。
1.2 ネフロン:腎臓の微細な機能単位
腎臓の構造的・機能的な基本単位はネフロンと呼ばれ、片方の腎臓に約100万個も存在します8。この無数のネフロンが、血液から尿を生成する一連のプロセスを担っています。
1.2.1 糸球体
ネフロンの始点は糸球体であり、これは毛細血管が毛糸の玉のように絡み合った構造体です9。糸球体は高圧のフィルターとして機能し、血液中の水分、老廃物(尿素、クレアチニンなど)、電解質、ブドウ糖といった小分子を濾し出します8。この段階で濾過された液体は「原尿」と呼ばれ、その量は健常な成人で1日に約150リットルにも達します8。一方で、赤血球やタンパク質のような大きな分子は濾過されず、血液中に留まります10。
1.2.2 尿細管
糸球体で生成された原尿は、次に長く曲がりくねった尿細管へと送られます8。ここが、体にとって必要な物質と不要な物質を最終的に選別する極めて重要な場所です。原尿に含まれる水分と、ブドウ糖、アミノ酸、電解質といった必須成分の約99%が、尿細管の壁を通して選択的に血液中へ再吸収されます8。同時に、血液中に残った一部の老廃物や薬物などが、能動的に尿細管内へ分泌(排泄)されます9。この精緻な再吸収と分泌のプロセスを経て、最終的に1日に約1.5リットルの尿が生成され、体外へ排泄されるのです11。
腎臓が持つこの膨大な数のネフロン(両腎で約200万個)は、非常に大きな機能的予備能を意味します。この予備能があるために、一部のネフロンが障害を受けても、残りのネフロンがその機能を代償し、体全体の恒常性は維持されます。しかし、これは諸刃の剣でもあります。かなりの数のネフロンが機能を失うまで自覚症状が現れないため、疾患の早期発見が困難になるという側面を持つのです。腎臓のこの解剖学的・生理学的設計そのものが、CKDが「沈黙の臓器」と呼ばれる所以であり、集団レベルでの検診や早期発見の取り組みが極めて重要となる理由です。
第2章 腎臓の多面的な機能:濾過を超えて
腎臓の役割は、単に老廃物を濾過して尿を作ることだけに留まりません。体内の内部環境を精緻に制御し、生命活動に不可欠なホルモンを産生するなど、その機能は極めて多岐にわたります。
2.1 排泄機能:老廃物の除去と尿の生成
前章で詳述した通り、腎臓の最もよく知られた機能は、体内の代謝活動によって生じる尿素やクレアチニンといった老廃物や、過剰に摂取された塩分などを血液中から除去し、尿として体外へ排泄することです4。この機能が低下すると、体内に毒素が蓄積し、尿毒症と呼ばれる状態を引き起こします。
2.2 恒常性維持機能:体内の精緻なバランス調整
腎臓は、体内の内部環境を常に一定に保つ「恒常性(ホメオスタシス)」の維持において中心的な役割を担います。
- 体液量の調節:尿の量を増減させることで、体内の水分量を厳密に調節します。これにより、脱水や、過剰な水分貯留による浮腫(むくみ)を防いでいます12。この働きは、体内の水分量を管理するダムに例えられることがあります12。
- 電解質バランスの調節:血液中のナトリウム、カリウム、カルシウム、リンといった電解質の濃度を、尿中への排泄量を調整することで一定に保ちます8。これらの電解質は、神経の伝達や筋肉の収縮など、生命活動の根幹に関わるため、そのバランス維持は極めて重要です。
- 酸塩基平衡の調節:体内の代謝活動で生じる酸を尿中に排泄し、重炭酸イオンを再生産することで、血液のpHを生命維持に適した弱アルカリ性の狭い範囲内に維持しています9。
2.3 内分泌機能:ホルモン産生の中枢
腎臓は、全身の機能を調節する重要なホルモンを産生・分泌する内分泌器官でもあります。
- 血圧調節(レニン):血圧が低下すると、腎臓はレニンというホルモンを分泌します。レニンは、血圧を上昇させ体液量を保持する「レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系(RAAS)」と呼ばれる一連のホルモン反応の引き金となります12。これは、高血圧がCKDの主要な原因かつ結果であることと密接に関連しています。
- 赤血球産生の促進(エリスロポエチン):腎臓は、骨髄に働きかけて赤血球の産生を促すエリスロポエチン(EPO)というホルモンを産生します12。CKDが進行し、このホルモンの産生が低下すると、貧血(腎性貧血)が引き起こされます。
- 骨の健康維持(活性型ビタミンD):腎臓は、食事から摂取されたり皮膚で産生されたりした不活性なビタミンDを、腸管からのカルシウム吸収に必須の活性型ビタミンDへと変換する最終段階を担います8。この機能が失われると、骨がもろくなるなどの骨・ミネラル代謝異常(MBD)が生じます。
これらの多様な機能は相互に関連しており、腎機能の低下は単一の問題ではなく、全身にわたる深刻な影響を及ぼします。以下の表は、腎臓の主要な機能を整理し、その機能不全がもたらす臨床的な帰結をまとめたものです。
| 機能カテゴリー | 具体的な機能 | 主要なメカニズム/ホルモン | 機能不全による影響 |
|---|---|---|---|
| 排泄機能 | 老廃物の除去 | 糸球体濾過、尿細管分泌 | 尿毒症 |
| 恒常性維持機能 | 体液量の調節 | 糸球体濾過、尿細管再吸収 | 浮腫、高血圧 |
| 電解質バランスの調節 | 尿細管再吸収・分泌 | 高カリウム血症、高リン血症 | |
| 酸塩基平衡の調節 | 酸の排泄、重炭酸の再生産 | 代謝性アシドーシス | |
| 内分泌機能 | 血圧調節 | レニン | 高血圧 |
| 赤血球産生の促進 | エリスロポエチン | 腎性貧血 | |
| 骨代謝の調節 | 活性型ビタミンD | 骨・ミネラル代謝異常 |
第3章 機能が低下する時:日本における慢性腎臓病(CKD)
腎臓の正常な生理機能から、その機能が慢性的に低下する病態、すなわち慢性腎臓病(CKD)へと焦点を移します。CKDは、日本の公衆衛生における最も重要な課題の一つです。
3.1 CKDの定義と病期分類:現代の臨床的枠組み
CKDは、「尿蛋白などの腎障害を示唆する所見」または「糸球体濾過量(GFR)が60 mL/分/1.73m²未満」のいずれか、あるいは両方が3ヵ月以上持続する状態と定義されます13。腎機能の評価には、血清クレアチニン値、年齢、性別から算出される推算糸球体濾過量(eGFR)が広く用いられます14。日本では、日本人向けに作成されたeGFR推算式(JSN eGFR)の使用が推奨されています15。また、筋肉量などの影響でクレアチニン値の信頼性が低い場合には、シスタチンCを用いたeGFRの測定が有用です16。
CKDの重症度は、腎機能低下の程度を示すGFR(G1〜G5)と、腎障害の程度を示すアルブミン尿(A1〜A3)の2つの指標を組み合わせた「重症度分類(ヒートマップ)」によって評価されます。この分類は、将来の末期腎不全への進行リスクや心血管疾患の発症リスクを予測するために極めて重要です15。なお、日本腎臓学会の2023年版ガイドラインでは、ステージG5の定義が、より臨床実態を反映する形で「高度低下〜末期腎不全」へと変更されました15。
| GFR区分 (mL/分/1.73m²) | アルブミン尿(mg/g・Cr) | ||
|---|---|---|---|
| 正常域 (A1) <30 |
微量アルブミン尿 (A2) 30~299 |
顕性アルブミン尿 (A3) >300 |
|
| 正常または高値 (G1) ≥90 |
低リスク | 中等度リスク | 高リスク |
| 正常または軽度低下 (G2) 60~89 |
低リスク | 中等度リスク | 高リスク |
| 軽度~中等度低下 (G3a) 45~59 |
中等度リスク | 高リスク | 極めて高リスク |
| 中等度~高度低下 (G3b) 30~44 |
高リスク | 極めて高リスク | 極めて高リスク |
| 高度低下 (G4) 15~29 |
極めて高リスク | 極めて高リスク | 極めて高リスク |
| 末期腎不全 (G5) <15 |
極めて高リスク | 極めて高リスク | 極めて高リスク |
| 出典: 日本腎臓学会の分類に基づき作成。色の濃さはリスクの高さを示します。 | |||
3.2 「国民病」の疫学:患者統計と高齢化の影響
日本におけるCKDの患者数は極めて多く、推定で約1,300万〜1,480万人と報告されています12。これは、日本の成人人口の7〜8人に1人が罹患していることを意味し、まさに「国民病」と呼ぶにふさわしい規模です。しかし、この膨大な推定患者数に対し、実際にCKDの治療を受けている患者数は、2023年の調査で62万9,000人と、大きな隔たりがあります17。この「診断と治療のギャップ」は、CKDが初期段階では無症状であるという「沈黙の臓器」の特性を如実に示しており、未診断の患者が膨大に存在することを示唆しています。
CKDの有病率は、日本の急速な高齢化と密接に関連しています18。高齢者における有病率は特に高く、国内の高齢者の4人に1人、75歳以上では3人に1人がCKDに罹患しているとの報告もあります19。透析導入患者の平均年齢も年々上昇しており、2021年には71.09歳に達しています20。末期腎不全に至り透析が必要となる患者の原疾患として最も多いのは糖尿病性腎症であり、全体の39.5%を占めます3。高血圧性腎硬化症がこれに続きます。この事実は、CKDが単独の腎疾患というよりも、糖尿病や高血圧といった生活習慣病の蔓延と、社会全体の高齢化という2つの大きな潮流が交差する点で発生する、より広範な公衆衛生問題の川下にある病態であることを示しています。
3.3 末期腎不全(ESKD)への道:日本の透析医療の現状
CKDが進行し、腎機能が生命を維持できないレベルまで低下すると、腎代替療法(透析療法または腎移植)が必要となります。日本透析医学会の報告によると、日本の慢性透析患者数は近年約34万人台で推移しており、2023年末時点では343,508人でした21。これは国民362人に1人が透析を受けている計算になります21。一方で、毎年新たに透析療法を開始する患者(新規透析導入患者)は、年間約38,000人〜40,000人という高い水準で推移しています1。この膨大な新規導入患者数を抑制することは、日本の医療政策における喫緊の課題です。厚生労働省は、2028年までに年間新規透析導入患者数を35,000人以下に減少させるという具体的な数値目標(KPI)を掲げています1。この目標設定の背景には、患者のQOL(生活の質)の維持向上に加え、透析医療に伴う莫大な経済的負担があります。透析医療費は1人あたり月額約40万円と非常に高額であり1、国家医療費全体に与える影響も大きいのです。
第4章 CKDの包括的管理:ガイドラインに基づくアプローチ
CKDの管理は、病気の進行を抑制し、合併症を予防・治療し、患者のQOLを維持することを目的とします。その治療戦略は、食事療法と薬物療法を両輪とし、国内外の診療ガイドラインに基づき、個々の患者の病期や状態に応じて個別化されます。
4.1 管理の礎:食事療法
食事療法は、すべてのCKD患者にとって不可欠な非薬物的介入であり、治療の一環として位置づけられています22。その目的は、腎臓への負担を軽減し、病状の進行を遅らせ、体液・電解質異常や高血圧といった合併症を管理することにあります。
4.1.1 食塩制限:腎臓および心血管保護のための普遍的指令
CKD患者における食塩摂取量の制限は、病期にかかわらず最も基本的な指導項目です。日本腎臓学会および日本高血圧学会は、高血圧を合併するCKD患者に対し、1日6g未満の食塩摂取を強く推奨しています23。この制限は、血圧の低下、体液貯留(浮腫)の改善、そして心臓への負担軽減に繋がり、腎保護および心血管保護効果が期待されます23。しかし、厚生労働省の令和元年国民健康・栄養調査によると、日本人の平均食塩摂取量は男性で10.9g、女性で9.3gと、目標を大幅に上回っており、このギャップを埋めるためには具体的な工夫が不可欠です24。実践的な減塩方法として、出汁のうま味や酢・香辛料を活用する、漬物や加工食品を避ける、麺類の汁は飲まない、醤油やソースは「かける」のではなく「つける」ようにするなど、多角的なアプローチが推奨されています24。
4.1.2 たんぱく質管理:栄養と腎負荷の繊細なバランス
たんぱく質は必須栄養素である一方、その代謝産物は腎臓から排泄されるため、過剰摂取は腎臓に負担をかけます23。そのため、日本腎臓学会の食事療法基準では、GFRの低下に伴い、段階的にたんぱく質制限を強化することが推奨されています。具体的には、ステージG3aでは標準体重1kgあたり0.8〜1.0g/日、ステージG3b〜G5(保存期)では0.6〜0.8g/日を目安とします2325。一方で、血液透析患者では透析によってアミノ酸などが失われるため、逆に標準体重1kgあたり0.9〜1.2g/日の十分なたんぱく質摂取が必要です26。
4.1.3 進行したCKDにおけるカリウムとリンの管理
腎機能がさらに低下すると、カリウムとリンの排泄能力も低下し、これらの摂取制限が必要となります。
カリウム(K):高カリウム血症は致死的な不整脈を引き起こす危険があるため、ステージG3b以降の患者ではカリウム制限が開始されます。目標値は、G3bで2,000mg/日以下、G4〜G5では1,500mg/日以下が目安です23。果物や野菜などに多く含まれるため、「茹でこぼし」や「水にさらす」といった調理の工夫が重要となります24。
リン(P):高リン血症は骨・ミネラル代謝異常や血管の石灰化を促進します。進行したCKDでは食事制限に加え、腸管からのリン吸収を阻害するリン吸着薬の使用が必要となることが多いです25。
4.1.4 栄養不良を防ぐための十分なエネルギー確保
たんぱく質制限を行う上で、最も注意すべき点の一つがエネルギー不足です。エネルギーが不足すると、体は自らの筋肉を分解してエネルギー源とするため、栄養状態が悪化し、かえって腎臓に負担をかけることになります23。したがって、CKDの食事療法では、標準体重1kgあたり25〜35kcal/日の十分なエネルギーを確保することが極めて重要であり23、そのために低たんぱく質米飯のような治療用特殊食品の活用が有効な選択肢となります27。
| CKDステージ | エネルギー (kcal/kg標準体重/日) | たんぱく質 (g/kg標準体重/日) | 食塩 (g/日) | カリウム (mg/日) |
|---|---|---|---|---|
| G1, G2 | 25~35 | 過剰摂取を避ける (≤1.3) | <6 | 制限なし |
| G3a | 25~35 | 0.8~1.0 | <6 | 制限なし |
| G3b | 25~35 | 0.6~0.8 | <6 | ≤2,000 |
| G4, G5 (保存期) | 25~35 | 0.6~0.8 | <6 | ≤1,500 |
| G5D (血液透析) | 30~35 | 0.9~1.2 | <6 | ≤2,000 |
| 出典: 日本腎臓学会の情報を統合して作成2328。これらは基準であり、個々の患者の状態に応じ医師・管理栄養士の指導のもと調整が必要です。 | ||||
4.2 薬物療法:現代の治療戦略
食事療法と並行して、CKDの進行抑制と合併症管理のために様々な薬物療法が行われます。
4.2.1 血圧管理
高血圧はCKDの最大の進行因子の一つです。レニン・アンジオテンシン系(RAS)阻害薬(ACE阻害薬やARB)は、尿蛋白を有するCKD患者の第一選択薬とされてきました15。国際的なKDIGOガイドライン2024年版では、忍容性があれば収縮期血圧120mmHg未満という厳格な目標が提案されています16。
4.2.2 新たなパラダイム:SGLT2阻害薬と包括的な心腎保護
SGLT2阻害薬は、もともと2型糖尿病治療薬として開発されましたが、その後の大規模臨床試験で、血糖降下作用とは独立した強力な腎保護効果および心血管保護効果が示され、CKD治療に革命をもたらしました。現在では、蛋白尿を有する非糖尿病性のCKD患者にも強く推奨されるようになり15、CKD治療の中心的役割を担う薬剤へと変貌を遂げています16。
4.2.3 合併症の管理
腎性貧血には赤血球造血刺激因子製剤(ESA)やHIF-PH阻害薬が、代謝性アシドーシスには炭酸水素ナトリウムが用いられます15。また、心血管疾患リスクを低減するため、KDIGOガイドラインでは透析を受けていない50歳以上のCKD患者の多くにスタチン系薬剤が推奨されています16。
4.3 グローバルな視点:JSNガイドラインとKDIGOガイドラインの比較
CKD診療はエビデンスに基づいており、日本のJSNガイドラインと国際的なKDIGOガイドラインには多くの共通点があります。特に、SGLT2阻害薬を広範なCKD患者に推奨する点は、世界的なコンセンサスとなっています15。一方で、たんぱく質摂取量(JSNはより段階的な制限を推奨23、KDIGOは高齢者のフレイルを考慮しより寛容16)や降圧目標(KDIGOはより厳格16)など、ニュアンスの違いも見られます。これは、エビデンスの解釈や対象集団の特性、医療制度の違いを反映している可能性があり、グローバルなエビデンスを日本の超高齢社会というローカルな文脈にどう最適化していくかという課題を示しています。
第5章 その他の腎疾患とその症状
CKD以外にも、腎臓には様々な疾患が存在します。
5.1 痛みの症状:腎臓における痛みの起源
腎臓に関連する痛みは、主に腎臓を覆う膜である「腎被膜」が急激に引き伸ばされることによって生じます29。典型的な原因は尿路結石症で、結石が尿の流れを塞ぎ、腎盂の内圧が急上昇することで脇腹から背中にかけての激痛(疝痛発作)を引き起こします29。また、細菌感染による急性腎盂腎炎では、腎臓の腫れによって持続的な鈍痛や叩打痛が生じます29。
5.2 悪性腫瘍:腎がん治療ガイドラインの概要
腎がんの治療は、日本泌尿器科学会が作成する『腎癌診療ガイドライン』に基づいて行われます30。腫瘍が腎臓内に留まっている限局性腎がんの治療の基本は手術であり、近年は腹腔鏡や手術支援ロボットを用いた低侵襲手術が主流です30。他の臓器に転移した転移性腎がんに対しては、免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬を中心とした薬物療法が標準治療となっています30。がん治療の進歩に伴い、抗がん剤による腎障害も問題となっており、日本腎臓学会や日本癌治療学会などが合同で「がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン」を作成しています13。
第6章 日本の腎臓病学の未来:研究とイノベーション
CKDという国民病に立ち向かうため、日本では国家レベルでの大規模な研究プロジェクトが推進されています。
6.1 ビッグデータの役割:日本腎臓病総合レジストリ(J-CKD-DB)からの洞察
CKDの膨大な患者数と診断ギャップという課題に対応するため、日本腎臓学会は厚生労働省の支援を受け、全国規模の包括的なCKD臨床効果情報データベース「Japan Chronic Kidney Disease Database (J-CKD-DB)」の構築を進めています31。このプロジェクトは、全国の参加医療機関の電子カルテから臨床データを自動的に抽出し、巨大なデータベースを構築するものです31。J-CKD-DBは、このビッグデータを活用して、日本のCKD患者における疾患の自然歴や予後を解明し、様々な治療法の有効性を実臨床環境で評価することを目的としています31。最近では、このデータベースから蛋白尿とミネラル代謝異常の関連性など、具体的な研究成果が報告され始めています32。この取り組みは、将来の診療ガイドライン改訂や医療政策立案の礎となり、厚生労働省が掲げる「新規透析導入患者の減少」という目標達成に貢献することが期待されます。
結論
本報告書は、腎臓が単なる尿生成器官ではなく、体液バランス、血圧、造血、骨代謝を司る、生命維持に不可欠な多機能臓器であることを示しました。しかし、その機能的予備能の高さゆえに、機能低下は「沈黙」のうちに進行し、日本ではCKDが深刻な国民病となっています。この背景には、社会の高齢化と、糖尿病や高血圧といった生活習慣病の蔓延があります。CKDの臨床管理は、食事療法を基本とし、近年ではSGLT2阻害薬の登場によって薬物療法のパラダイムが大きく転換しました。国内外のガイドラインは常に進化していますが、その推奨を日本の超高齢社会の実情にどう適合させていくかという課題も存在します。腎臓病学の未来は、J-CKD-DBのような大規模データベースを活用した、より早期の診断と個別化医療の推進にかかっています。未診断の膨大な患者をいかに早期に発見し、介入に繋げるか。これらの課題解決には、ビッグデータから得られる日本独自のリアルワールドエビデンスが不可欠です。腎臓病学は、今後ますます、プライマリケア、糖尿病学、循環器学、公衆衛生学との連携を深め、生活習慣病という上流からCKDという下流までを包括的に管理する、統合的な医療体系へと発展していくことが求められます。
参考文献
- 厚生労働省. 腎疾患対策の取組について [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/001005972.pdf
- 厚生労働省. 令和7年度慢性腎臓病(CKD)重症化予防のための 診療体制構築及び多職種連携モデル事業 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001390794.pdf
- 日本生活習慣病予防協会. CKD(慢性腎臓病) | 生活習慣病の調査・統計 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://seikatsusyukanbyo.com/statistics/disease/ckd/
- ソニー損保. クレアチニンっていったい何? 腎機能の状態の把握や改善に役立てよう [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.sonysonpo.co.jp/md/i_hch015.html
- 東大阪病院. 腎臓とは?(働き、代表的な腎臓疾患) | 透析に関すること [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.yurin.or.jp/artificial_dialysis/artificial_dialysis1/7052.html
- バイエル薬品. 「腎臓」はこんな臓器 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.ckd45.jp/ja/kidney/about
- Spotlight On Heart Failure. 心臓と腎臓の働きを知っていますか [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.spotlightonheartfailure.jp/voice/02.html
- 日本腎臓財団. 腎臓って何をするところ? [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: http://www.jinzouzaidan.or.jp/jinzou/
- 腎援隊. よくわかる基礎知識|腎臓の機能とは [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://jinentai.com/ckd/tips/1.html
- 日本腎臓学会. 1.腎臓の構造と働き-一般のみなさまへ [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://jsn.or.jp/general/kidneydisease/symptoms01.php
- キッセイ薬品工業株式会社. 腎臓の働き~透析療法とは? | 透析について考える | ~笑顔でいきいき~ 透析”新”ライフ [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.kissei.co.jp/dialysis/about_dialysis/cure.html
- 中外製薬株式会社. じん臓 | からだのしくみ | からだとくすりのはなし | 患者さん・一般の皆さま [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.chugai-pharm.co.jp/ptn/medicine/karada/karada012.html
- 日本腎臓学会. がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン 2022 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://jsn.or.jp/medic/data/guidelines2022.pdf
- 偕行会グループ. 腎臓のおはなし|お役立ち情報|偕行会グループの透析医療 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.kaikou.or.jp/touseki/useful/kidney.html
- ケアネット. 『エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023』改訂のポイント … [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.carenet.com/news/general/carenet/56794
- 育児する医師のブログ. 【内科医なら知っておきたい】KDIGOのCKDガイドライン2024の … [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://ikuji-doctor.com/kdigo-ckd-guideline-2024/
- 日本生活習慣病予防協会. 慢性腎臓病(CKD)の治療を受けている総患者数は [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://seikatsusyukanbyo.com/statistics/2025/010842.php
- 日本腎臓学会. 第 14 章 高齢者 CKD [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://jsn.or.jp/data/gl2023_ckd_ch14.pdf
- ケアネット. 国内高齢者の4人に1人、75歳以上では3人に1人がCKD [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.carenet.com/news/general/hdnj/59754
- 腎援隊. よくわかる基礎知識|日本における透析の現状 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://jinentai.com/dialysis/tips/1_1.html
- 日本透析医学会. わが国の慢性透析療法の現況 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://docs.jsdt.or.jp/overview/file/2023/pdf/2023all.pdf
- 日本医療政策機構. 【HGPI政策コラム】(No.55)―腎疾患対策推進プロジェクトより―「慢性腎臓病(CKD)の治療の継続において患者視点で求められていること(食事療法編)」 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://hgpi.org/lecture/column-55.html
- 協和キリン株式会社. 毎日の食事で気をつけること|知ろう。ふせごう。慢性腎臓病(CKD) [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.kyowakirin.co.jp/ckd/prevention/pre3.html
- ニチレイフーズ. 1日の塩分摂取量目安は?減塩目標や無理なく食事の塩分をコントロールする方法を解説 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://wellness.nichirei.co.jp/contents/detail/6
- 日本腎臓学会. 慢性腎臓病に対する食事療法基準2014年版 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://cdn.jsn.or.jp/guideline/pdf/CKD-Dietaryrecommendations2014.pdf
- 日本透析医学会. 慢性透析患者の食事療法基準 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.jsdt.or.jp/tools/file/download.cgi/1229/%E6%85%A2%E6%80%A7%E9%80%8F%E6%9E%90%E6%82%A3%E8%80%85%E3%81%AE%E9%A3%9F%E4%BA%8B%E7%99%82%E6%B3%95%E5%9F%BA%E6%BA%96287-291.pdf
- キッセイ薬品工業株式会社. 慢性腎臓病の食生活を助ける低たんぱく食品「ゆめごはん」 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://healthcareinfo.kissei.co.jp/lp/yumegohan/
- キッセイ薬品工業株式会社. これだけは知っておきたい食事管理のポイント | 透析レシピ [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.kissei.co.jp/dialysis/recipe/point.html
- 日本泌尿器科学会. 腎臓のあたりが痛む | 【一般のみなさま】 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.urol.or.jp/public/symptom/13.html
- 日本癌治療学会. 腎がん | がん診療ガイドライン [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: http://www.jsco-cpg.jp/kidney-cancer/
- J-CKD-DBプロジェクト. J-CKD-DBプロジェクトについて [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://j-ckd-db.jp/about/
- J-CKD-Database. J-CKD-Database [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://j-ckd-db.jp/
- Weblio辞書. 「腎臓(ジンゾウ)」の意味や使い方 わかりやすく解説 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.weblio.jp/content/%E8%85%8E%E8%87%93
- Boehringer Ingelheim. 腎疾患をとりまく現状 | べーリンガープラス [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://pro.boehringer-ingelheim.com/jp/medical/professional-development/situation-surrounding-kidney-disease
- 厚生労働省. ӡ㕴ӢӨ ቯตෟᅸӡ㕼㖄㕽ӢӨ [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316478.pdf
- 日本腎臓財団. 慢性腎臓病(CKD)予防<食事編> [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: http://www.jinzouzaidan.or.jp/jinzou/jinzou_6.html
- 腎援隊. 慢性腎臓病の食事療法 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://jinentai.com/ckd/tips/5_3.html
- 赤羽もりクリニック. 腎臓病に良い食べ物で腎機能の低下を防ぐための3つの基礎知識 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://akabanejinzonaika.com/kidney-food
- ひまわり医院(内科・皮膚科). 腎臓にいい食べ物と悪い食べ物について【玉ねぎ・にんにく・コーヒー】 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://soujinkai.or.jp/himawariNaiHifu/kidney-food/
- 松本泌尿器科クリニック. 腎臓の痛み、背中や腰が痛む [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://matsucli-suita.com/%E8%85%8E%E8%87%93%E3%81%AE%E7%97%9B%E3%81%BF%E3%80%81%E8%83%8C%E4%B8%AD%E3%82%84%E8%85%B0%E3%81%8C%E7%97%9B%E3%82%80
- いしむら腎泌尿器科クリニック. 背中や腰が痛む(腎臓の痛み) [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://ishimura.clinic/%E8%83%8C%E4%B8%AD%E3%82%84%E8%85%B0%E3%81%8C%E7%97%9B%E3%82%80
- 小田泌尿器科. 背中・腰が痛い原因は腎臓の病気? [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.oda-hinyoukika.com/back-pain/
- 日本癌治療学会. がん診療ガイドライン [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: http://www.jsco-cpg.jp/
- 日本癌治療学会. 「がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン2022」発行のお知らせ [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.jsco.or.jp/news/detail.html?itemid=220&dispmid=767&TabModule830=0
- 日本癌治療学会. ガイドライン・刊行物 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.jsco.or.jp/about/guideline.html
- J-CKD-Database. ホーム [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: http://j-ckd-db.sakura.ne.jp/
- 国立保健医療科学院. 腎臓病データベースの拡充・連携強化と包括的データベースの構築 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/26973
- 大阪大学腎臓内科. J-CKD-DB研究 [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/kid/kid/studyPlan/sp201712.html
- 協和キリン株式会社. 腎臓ってどんな働きをしている?|知ろう。ふせごう。慢性腎臓病(CKD) [インターネット]. [2025年6月20日引用]. Available from: https://www.kyowakirin.co.jp/ckd/working/index.html