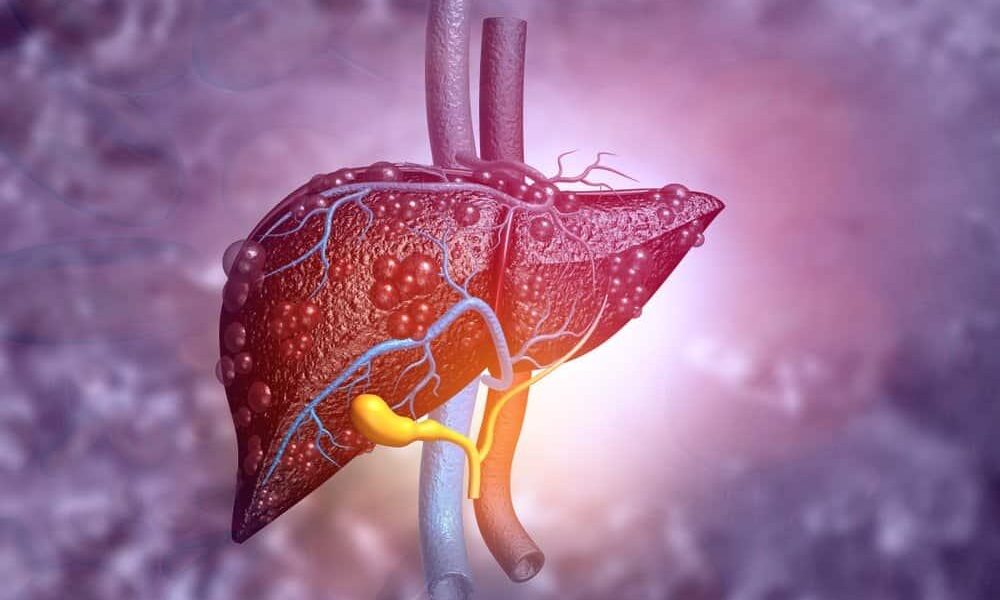この記事の科学的根拠
この記事は、入力された研究報告書で明示的に引用されている最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下は、参照された実際の情報源と、提示された医学的指導との直接的な関連性を示したリストです。
- 日本肝臓学会・日本消化器病学会: 本記事における診断、治療、合併症管理に関する主要な推奨事項は、両学会が共同で策定した「肝硬変診療ガイドライン2020」23に基づいています。これは日本の肝疾患診療における基幹的な指針です。
- 厚生労働省: 肝炎治療費助成制度や国の肝炎対策に関する記述は、厚生労働省が公開している公式情報5を参照しており、患者様が利用可能な公的支援の正確性を担保しています。
- 兵庫医科大学 / 日本肝臓学会による全国調査: 日本における肝硬変の成因動向(アルコール性の増加、ウイルス性の減少)に関するデータは、最新の全国調査結果18に基づいており、現代日本の医療状況を正確に反映しています。
- 患者さんとご家族のための肝硬変ガイド 2023: 食事療法や日常生活の注意点など、患者様目線での具体的なアドバイスは、専門家が患者様とそのご家族のために作成したこのガイド4の内容を基に構成されています。
要点まとめ
- 肝硬変という病気自体は、風邪のように人から人へうつる(感染する)ことは一切ありません。
- しかし、肝硬変の主な原因であるB型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスは、血液や体液を介して感染する可能性があります。
- 日本では現在、ウイルス性肝炎による肝硬変は減少し、アルコールや生活習慣病(非アルコール性脂肪性肝炎 NASH)が原因の肝硬変が増加しています。
- 肝硬変には症状がほとんどない「代償期」と、黄疸や腹水などの症状が現れる「非代償期」があります。早期発見が極めて重要です。
- 原因疾患の治療、適切な食事療法、生活習慣の改善により、肝硬変の進行を食い止め、合併症を管理することは十分に可能です。
肝硬変と感染リスク解説
「肝硬変は他の人にうつるのでは…?」という不安から、家族との食事や入浴、スキンシップまで躊躇してしまう方も少なくありません。特に、小さな子どもや高齢の家族がいると、「自分が原因で病気にさせてしまうのでは」という罪悪感に近い思いを抱くこともあります。こうした不安はとても自然なものですが、正しい知識がないまま怖がり続けると、必要のない距離まで生まれてしまいます。このボックスでは、その不安を整理し、「どこまで気をつければよいのか」を具体的にイメージできるようにしていきます。
記事本編でも強調されているように、肝硬変そのものは風邪のように人から人へうつる病気ではなく、あくまで長年の肝障害の結果として肝臓が硬くなった「状態」です。一方で、その背景にあるB型・C型肝炎ウイルスなどは血液や体液を介して感染しうるため、「肝硬変はうつらないが、原因ウイルスはうつる可能性がある」という区別が大切になります。消化管や肝臓の病気全体の位置づけや、合併症との関係をより広い視点から整理したい場合は、消化器疾患の総合ガイドも合わせて読むことで、現在の自分の状態をより立体的に理解しやすくなります。
本記事が示すように、肝硬変の背景には大きく①B型・C型肝炎などのウイルス性、②長期の多量飲酒によるアルコール性、③肥満や糖尿病などに伴う非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD/NASH)、④自己免疫性肝疾患など、複数の原因があります。そのうち「人から人へうつる」可能性があるのはB型・C型肝炎ウイルスで、主に血液や一部の体液を介して感染します。具体的には、出産時の母子感染、性交渉、注射器の共有、不十分に消毒された器具によるピアスやタトゥー、カミソリや歯ブラシの共有などが問題になります。A・B・Cそれぞれの肝炎の違い、症状、感染経路、治療と公的支援の全体像を系統立てて確認したい場合は、A型・B型・C型肝炎の完全ガイドで、感染の仕組みと対策を整理しておくと安心です。
不安を減らすための第一歩は、「自分や家族がウイルスに感染しているのかどうか」をはっきりさせることです。本記事でも紹介されているように、肝機能検査や肝炎ウイルス検査は、会社や自治体の健診、あるいは医療機関での個別検査として受けることができます。特に家族にB型・C型肝炎を原因とする肝硬変の方がいる場合、ご自身も同じウイルスに感染していないか一度血液検査で確認しておくとよいでしょう。検査の種類や結果の読み方、公費助成の仕組みまで含めて具体的にイメージしたいときは、B型肝炎検査の完全ガイドを参考にしながら、主治医と相談して検査のタイミングを決めると具体的な行動につなげやすくなります。
次のステップとして重要なのが、「これから感染を防ぐために何をするか」を家族単位で考えることです。本記事が述べるように、日常生活の中での食器の共有や入浴、握手・ハグなどで肝炎ウイルスがうつることはありませんが、血液が付着しうるカミソリ・歯ブラシ・爪切りなどは共有を避ける必要があります。また、B型肝炎には有効なワクチンがあり、未感染の家族が将来も安心して過ごす上で大きな支えになります。接種スケジュールや費用、助成制度を詳しく知りたい場合は、大人のB型肝炎ワクチン完全ガイドを読み、主治医と話し合いながら自分や家族に合った予防計画を立てていくとよいでしょう。
一方で、ウイルスが原因であっても、適切な治療によりウイルス量を抑えたり排除できれば、肝硬変の進行を緩やかにし、合併症のリスクを下げることができます。本記事やガイドラインが示すように、C型肝炎には飲み薬中心の直接作用型抗ウイルス薬(DAA)、B型肝炎にはウイルスの増殖を抑える薬があり、日本では公的な医療費助成制度も整えられています。B型・C型肝炎治療の選択肢と助成制度を俯瞰したいときには、現代肝炎治療の包括的ガイドが役立ちます。また、すでに肝硬変が進行して腹水が目立ってきた場合には、塩分制限や利尿薬などによる管理が重要になるため、肝硬変による腹水の完全ガイドを参考にしながら、日々の食事や体調観察のポイントを押さえておくと安心です。
肝硬変は「うつる病気」ではありませんが、その陰にはB型・C型肝炎や生活習慣など、きちんと向き合うべき原因が存在します。大切なのは、恐怖心だけで行動を止めてしまうのではなく、「どの部分が本当に注意すべきリスクなのか」を理解したうえで、検査・治療・予防策を一つずつ進めていくことです。この記事と関連ガイドを手がかりに、主治医や家族と率直に話し合いながら、ご自身と大切な人の肝臓を守るための一歩を踏み出していきましょう。
【結論】肝硬変は「うつらない」。しかし、本当の注意点は別にあります
多くの方が最も心配されるこの疑問に、まず明確にお答えします。肝硬変そのものが、風邪やインフルエンザのように咳やくしゃみ、あるいは食器の共有などで人から人へうつる(感染する)ことは絶対にありません8。肝硬変は感染症ではなく、長期間にわたる肝臓へのダメージの結果として肝臓が硬くなってしまう「状態」を指す病名です。
しかし、ここで非常に重要な注意点があります。それは、「肝硬変の原因となるウイルスは、人から人へうつる可能性がある」ということです8。肝硬変の二大原因は、B型肝炎ウイルス(HBV)とC型肝炎ウイルス(HCV)の持続的な感染です。これらのウイルスは主に血液を介して感染します。したがって、「肝硬変はうつらないが、その引き金となる特定のウイルスは感染しうる」と正しく理解することが、ご自身と周囲の人々を守るために極めて重要になります。
肝硬変の「原因」となるウイルスの正しい知識:B型・C型肝炎の感染経路と予防法
肝硬変を引き起こす可能性のあるB型肝炎ウイルスとC型肝炎ウイルスについて、その感染経路と予防法を正確に理解しておくことが不可欠です。
詳細な感染経路
両ウイルスともに主な感染経路は血液です。具体的な感染リスクは以下の通りです。
- B型肝炎ウイルス (HBV): 感染力が比較的強く、血液だけでなく一部の体液を介しても感染します。主な経路は、出産時の母子感染(垂直感染)、ウイルス保持者との性交渉、注射器の共有、消毒が不十分な器具を使ったタトゥーやピアスの穴あけ、カミソリや歯ブラシの共有(水平感染)などです89。
- C型肝炎ウイルス (HCV): 主に血液を介して感染します。過去には輸血による感染が問題となりましたが、現在では検査体制が確立され、そのリスクはほぼありません。現代における主な感染源は、薬物使用時の注射器の共有、不衛生な状態でのタトゥーやピアスの施術などです8。性交渉や母子感染のリスクはHBVに比べて低いとされていますが、ゼロではありません。
日常生活での感染リスクは?
多くの方が不安に感じる日常的な接触について、新潟大学歯学総合病院肝疾患相談センターなどの専門機関は、以下のような行為では感染しないことを明示しています10。
- 同じお皿の料理を食べる、鍋をつつく
- お風呂やプールに一緒に入る
- 握手やハグ
- 咳やくしゃみ
これらの行為でウイルスがうつる心配はありません。過度に恐れる必要はなく、正しい知識を持つことが偏見や差別を防ぐことにも繋がります。
予防こそが最大の防御
ウイルスの感染を防ぐためには、以下の対策が非常に有効です。
- ワクチン接種: B型肝炎には極めて有効なワクチンがあります11。現在、日本の子供たちは定期接種の対象となっています。ウイルス保持者のパートナーなど、感染リスクのある方は積極的にワクチンを接種することが推奨されます。残念ながら、C型肝炎に対するワクチンはまだありません。
- 性交渉: コンドームを正しく使用することが、B型肝炎の感染予防に効果的です10。
- 血液が付着しうる物品の共有を避ける: カミソリ、歯ブラシ、爪切りなど、血液が付着する可能性のある身の回り品の共有は絶対に避けてください9。
- 衛生管理: タトゥーやピアスを入れる際は、器具が適切に消毒・交換されているか、信頼できる施設で確認することが重要です。
表1: B型肝炎とC型肝炎の比較
| 特徴 | B型肝炎 (HBV) | C型肝炎 (HCV) | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 主な感染経路 | 血液・体液 | 主に血液 | 8 |
| 感染力 | 比較的強い | 比較的弱い | 9 |
| 慢性化率 | 感染年齢による (乳幼児期は高い) | 高い (約70%) | 11 |
| ワクチン | あり (有効) | なし | 11 |
| 主な予防法 | ワクチン接種、コンドーム使用 | 血液接触の回避、衛生管理 | 10 |
そもそも肝硬変とは?「沈黙の臓器」が発するサイン
肝臓が硬くなるメカニズム
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、非常に高い再生能力を持っています。しかし、ウイルス、アルコール、肥満などの原因によって長期間にわたり炎症(肝炎)が続くと、肝細胞の破壊と再生が繰り返されます。この修復過程で、コラーゲンなどの線維組織が蓄積し、次第に肝臓全体が硬く、ゴツゴツとした状態に変化します。これが「線維化」であり、線維化が進行しきった状態が肝硬変です1。硬くなった肝臓は、正常な機能を十分に果たせなくなります。
代償性肝硬変と非代償性肝硬変
肝硬変の進行度を理解する上で、この二つの段階を知ることは非常に重要です。日本肝臓学会もこの分類を診療の基本としています15。
- 代償性肝硬変 (Compensated): 病気の初期段階です。まだ残っている正常な肝細胞が、機能しなくなった部分を補って(代償して)働いているため、肝臓全体の機能は何とか保たれています。このため、自覚症状はほとんどないか、あっても全身の倦怠感や食欲不振といった軽微なものが多く、病気に気づかないことも少なくありません15。
- 非代償性肝硬変 (Decompensated): 病気が進行し、残った肝細胞だけでは肝臓の機能を維持できなくなった段階です。この段階になると、黄疸(おうだん)、腹水(ふくすい)、浮腫(ふしゅ、むくみ)、肝性脳症といった、生命を脅かす可能性のある深刻な症状や合併症が現れてきます15。
日本における肝硬変の原因の変化:ウイルス性の減少と「非ウイルス性」の増加
かつて、日本の肝硬変の最大の原因はC型肝炎ウイルスでした。しかし、画期的な治療薬の登場と国の肝炎対策事業の推進により、ウイルス性肝炎を原因とする肝硬変は著しく減少しています。その一方で、現代の日本ではアルコールや生活習慣病に起因する肝硬変が増加しており、その原因構成は大きく変化しています。
兵庫医科大学と日本肝臓学会が主導した最新の全国調査によると、2023年時点での肝硬変の成因は、アルコール性(35.4%)が最も多く、次いでC型肝炎(23.4%)、そして非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)を含む非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)が16.1%と急増しています18。これは、生活習慣の変化が肝臓の健康に直接的な影響を与えていることを示す重要なデータです。
主な原因をまとめると以下のようになります。
- ウイルス性: B型肝炎、C型肝炎。依然として重要な原因ですが、治療の進歩により減少傾向にあります13。
- アルコール性: 長期間にわたる過度の飲酒。アルコールの代謝産物であるアセトアルデヒドが肝細胞を直接傷つけます。専門家によると、男性の場合、日本酒換算で毎日3~5合を20年以上飲み続けると高いリスクがあるとされています13。
- 非アルコール性脂肪性肝炎 (NASH): 肥満、2型糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病(メタボリックシンドローム)に関連して発症します。飲酒習慣がない人にも起こる「脂肪肝」が進行したもので、現代の新たな脅威として注目されています1。
- 自己免疫性・その他: 自己免疫性肝炎(AIH)や原発性胆汁性胆管炎(PBC)など、自身の免疫システムが肝臓を攻撃してしまう病気も原因となります1。
肝硬変の具体的な症状と合併症
肝硬変が進行すると、肝機能の低下に伴い、体に様々なサインが現れます。これらのサインを見逃さないことが重要です。
- 初期症状: 最もよく見られるのは、原因不明の全身倦怠感や食欲不振です。これらは他の病気でも見られるため、見過ごされがちです15。
- 皮膚のサイン: 胸や肩のあたりに、クモが足を広げたような形の赤い血管腫(くも状血管腫)が現れたり、手のひらが異常に赤くなる(手掌紅斑)ことがあります14。
- ホルモン異常のサイン: 肝臓はホルモンの代謝にも関わっているため、機能が低下すると男性でも胸が女性のように膨らむ(女性化乳房)や、精巣が萎縮するなどの症状が見られることがあります14。
- その他の重要な症状: 白目や皮膚が黄色くなる黄疸、足がつりやすくなるこむらがえり、血を固める成分を作れなくなることで血が止まりにくくなる出血傾向(血小板減少)などがあります1。
生命を脅かす三大合併症
非代償期に入ると、特に注意すべき3つの深刻な合併症があります。
- 腹水・浮腫: 肝臓で作られるアルブミンというタンパク質が減少することで、血管内の水分が漏れ出し、お腹に水が溜まったり(腹水)、足がむくんだり(浮腫)します14。
- 肝性脳症: 本来肝臓で解毒されるはずのアンモニアなどの有害物質が脳に達し、精神神経症状を引き起こします。初期には昼夜逆転や判断力の低下、進行すると羽ばたくような手の震え(羽ばたき振戦)が見られ、最終的には昏睡状態に陥ることもあります1。
- 食道・胃静脈瘤: 肝臓が硬くなることで、門脈という血管の圧力が異常に高まります(門脈圧亢進)。これにより、血液が本来のルートを通れず、食道や胃の細い血管へ迂回します。この迂回路の血管がこぶのように膨らんだものが静脈瘤です。非常に破裂しやすく、一度破裂すると大量出血(吐血・下血)を起こし、命に関わります1。
肝硬変の進行を防ぐために:正しい予防と治療法
肝硬変にならないための予防法(一次予防)
肝硬変を未然に防ぐためには、その原因を作らないことが最も重要です。
- ウイルス肝炎対策: B型肝炎ワクチンを接種する、血液を介した感染機会(カミソリの共有など)を徹底して避けることが基本です20。
- アルコール対策: 適度な飲酒量を守り、休肝日を設けることが大切です。すでに肝臓に問題がある場合は、禁酒が原則となります20。
- 生活習慣病対策: 肥満やNAFLDを防ぐため、バランスの取れた食事と定期的な運動を心がけましょう20。
- 定期的な健康診断: 会社の健康診断や住民健診を必ず受け、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、血小板数などの肝機能の数値に異常がないかを確認することが、早期発見の鍵です1。
肝硬変と診断された後の治療法(二次・三次予防)
肝硬変と診断された場合、治療の目標は「原因を取り除き、進行を食い止め、合併症を管理し、生活の質(QOL)を維持すること」になります。「患者さんとご家族のための肝硬変ガイド 2023」でも強調されているように、一度硬くなった肝臓を完全に元に戻すことは困難ですが416、適切な治療で病気の進行をコントロールすることは可能です。
- 原因疾患への治療: これが治療の根幹です。
- 合併症への対症療法:
- 肝移植: 他の治療法では効果がなく、末期の肝不全に至った場合の唯一の根治療法として考慮されます29。
肝硬変と向き合うための食事療法と生活の工夫
肝硬変の管理において、薬物治療と並んで食事療法は非常に重要な役割を果たします。ここでは、すぐに実践できる具体的なポイントを解説します。
食事療法の基本原則
日本肝臓学会のガイド21や多くの専門家27が推奨する基本は、「バランスの良い食事を1日3食規則正しく、よく噛んで食べること」です。特に、肝硬変の患者様はエネルギーを消費しやすい状態にあるため、十分なカロリーを摂取することが重要です。
病状に応じた食事のポイント
食事内容は、肝硬変の進行度(代償期か非代償期か)や合併症の有無によって調整する必要があります。
- 代償期: 基本的に厳しい制限はありません。筋肉量を維持するために、良質なタンパク質(体重1kgあたり1.0〜1.2gが目安)をしっかり摂り、バランスの良い食事を心がけます16。
- 非代償期: 合併症に応じた制限が必要になります。
専門家が推奨する2つの重要な栄養療法
近年の研究で、以下の2つの栄養療法が肝硬変患者様の予後改善に有効であることが分かっています21。
- LES (Late Evening Snack / 就寝前の補食): 肝硬変の肝臓は糖分(グリコーゲン)を十分に蓄えられないため、夜間にエネルギー不足に陥り、自身の筋肉を分解してエネルギー源にしてしまいます。これを防ぐため、就寝前に炭水化物を中心とした200kcal程度の軽い食事(おにぎり1個、ロールパン2個など)を摂ることが推奨されています21。
- BCAA (分岐鎖アミノ酸) の補充: BCAAは筋肉でアンモニアの処理に使われたり、エネルギー源として利用されたりするため、肝硬変では不足しがちです。BCAA製剤を補充することで、血液中のアルブミン値を改善したり、筋肉量の維持、生活の質の向上に繋がることが報告されています21。
表2: 肝硬変の合併症別・食事の注意点早見表
| 合併症 | 控えるべきもの | 積極的に摂りたいもの | ポイント | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 腹水・浮腫 | 塩分、水分の過剰摂取 | カリウムを多く含む野菜 | 出汁や香辛料で風味付け | 1 |
| 肝性脳症 | 動物性タンパク質の過剰摂取 | 植物性タンパク質、食物繊維、BCAA | 規則正しい便通を保つ | 27 |
| 食道静脈瘤 | 硬い・鋭い・刺激の強い食品 | 柔らかく消化の良い食品(うどん等) | よく噛んでゆっくり食べる | 27 |
| 鉄過剰(C型肝炎由来) | 赤身肉、レバー、鉄サプリメント | 鉄分の少ない食品 | 特にHCV由来の肝硬変で注意 | 31 |
運動と睡眠
- 運動: 筋肉が減少する「サルコペニア」は予後を悪化させるため、無理のない範囲での適度な運動(ウォーキングなど)が重要です4。
- 睡眠: 睡眠障害はよく見られますが、安易な睡眠薬の使用は肝性脳症を誘発する危険があるため、主治医への相談が不可欠です。長時間の昼寝は避けましょう21。
公的支援と相談窓口
肝硬変の治療は長期にわたることが多く、医療費の負担も大きくなります。日本では、患者様を支えるための様々な公的支援制度が整備されています。
- 医療費助成制度: 厚生労働省は国の肝炎対策の一環として、高額な治療費に対する助成制度を設けています5。
- 肝炎治療特別促進事業: B型・C型肝炎の抗ウイルス治療(インターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療、インターフェロンフリー治療)にかかる医療費を助成します。
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業: 入院・通院にかかる医療費の自己負担額が月額1万円(上位所得者は2万円)に軽減されます。
- 重症化予防推進事業: 肝炎ウイルスの陽性者を対象に、定期的な検査費用の一部を助成します。
これらの制度の詳細は、お住まいの都道府県や市区町村の保健担当窓口、またはかかりつけの医療機関にご確認ください。
- 相談窓口: 経済的な問題だけでなく、病気に関する様々な悩みを相談できる窓口があります。
一人で抱え込まず、これらの制度や窓口を積極的に活用することが、安心して治療を続ける上で非常に大切です。
よくあるご質問 (Q&A)
Q1: 肝硬変は治りますか?
A: 一度硬くなってしまった肝臓の組織を、完全に元の柔らかい状態に戻すことは現代の医療では困難です。しかし、治療の目標は「治癒」だけではありません。原因となっている病気(ウイルス性肝炎やアルコールなど)を治療し、適切な食事療法や生活習慣を続けることで、病気の進行を止め、あるいは遅らせ、合併症を防ぎ、現状の肝機能を長く維持することは十分に可能です16。
Q2: 家族が肝硬変です。私は何をすべきですか?
A: まず、ご家族の肝硬変の原因がウイルス性(特にB型またはC型肝炎)であるかを確認してください。もしウイルス性が原因の場合、ご自身も同じウイルスに感染していないか、血液検査を受けることが重要です。特にB型肝炎はワクチンで効果的に予防できますので、未接種の場合は医師に相談しましょう11。また、塩分制限などの食事療法はご家族の協力が不可欠です。病気への正しい理解を持ち、精神的、身体的に患者様をサポートしてあげることが何より大切です。
Q3: 肝硬変になると、寿命はどのくらいですか?
A: この質問に一概にお答えすることはできません。予後は、肝硬変の原因、重症度(代償期か非代償期か)、合併症の有無、治療への反応性など、多くの要因によって大きく異なるからです。症状のない代償性の段階で発見され、原因除去や適切な管理を続ければ、健康な人と変わらない生活を長く送ることも可能です15。最も重要なのは、悲観的にならず、主治医とよく相談し、治療と自己管理を粘り強く続けることです。
Q4: 肝臓に良いというサプリメントはありますか?
A: 「肝臓に良い」と謳われるサプリメントや健康食品は数多くありますが、自己判断での摂取は非常に危険です。特定の成分の過剰摂取が、かえって肝臓に負担をかけ、薬物性肝障害を引き起こすケースも報告されています13。どのようなサプリメントであっても、摂取する前には必ず主治医や管理栄養士に相談してください。
結論
本記事を通して、肝硬変に関する重要なポイントを解説してきました。最後に、最も大切なメッセージを改めてお伝えします。
- 肝硬変そのものは「うつらない」。しかし、原因となるウイルスは「うつる」可能性がある。この正しい区別が、不要な不安と本当のリスク管理の第一歩です。
- 日本の肝硬変の主役は、ウイルスからアルコールや生活習慣病へと移り変わっています。これは、誰にとっても肝臓の健康が無関係ではないことを意味します。
- 肝臓は「沈黙の臓他の臓器」。症状が出たときには、病気はかなり進行している可能性があります。定期的な健康診断による早期発見が何よりも重要です。
- たとえ肝硬変と診断されても、絶望する必要はありません。原因への適切な治療と生活習慣の改善により、病気の進行をコントロールし、より良い生活を長く続けることは可能です。
この記事を読んで、少しでもご自身の肝臓の健康に不安を感じた方は、決してためらわないでください。お近くの専門医療機関(消化器内科・肝臓内科)を受診し、まずは肝炎ウイルス検査を含む血液検査を受けることを強くお勧めします。それが、あなた自身とあなたの大切な人の未来を守るための、最も確実な行動です。
免責事項本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的アドバイスに代わるものではありません。健康に関する懸念や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- 青葉台かなざわ内科・内視鏡クリニック. 肝硬変 [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://kanacli.jp/%E8%82%9D%E7%A1%AC%E5%A4%89
- 日本肝臓学会. 肝硬変診療ガイドライン(2020年11月) [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://www.jsh.or.jp/lib/files/medical/guidelines/jsh_guidlines/kankouhen2020_AR_v2.pdf
- 日本消化器病学会・日本肝臓学会. 肝硬変診療ガイドライン 2020(改訂第3版) [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://www.jsge.or.jp/committees/guideline/guideline/pdf/kankouhen2020_re.pdf
- 日本消化器病学会. 患者さんとご家族のための肝硬変ガイド 2023 [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://www.jsge.or.jp/committees/guideline/disease/pdf/kankouhen_2023.pdf
- 厚生労働省. 肝炎総合対策の推進 [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kanen/index.html
- 日本病院会. 肝炎対策基本法について [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://www.hospital.or.jp/site/news/file/4645553359.pdf
- e-Gov法令検索. 肝炎対策基本法 [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097
- 太陽生命. 肝硬変とは?症状や原因などの基礎を知ろう! [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://www.taiyo-seimei.co.jp/net_lineup/taiyo-magazine/illness/003/index.html
- 安藤おなかクリニック. 肝硬変は治る?進行を防ぐには?症状や原因・治療法を解説|岐阜・胃と大腸の内視鏡 [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://www.ando-naikaonaka.jp/cirrhosis/
- 新潟大学歯学総合病院肝疾患相談センター. [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://www.nuh.niigata-u.ac.jp/liv/about/
- オトナのVPD. B型肝炎(肝臓がん、肝硬変) [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://otona.know-vpd.jp/vpd/hapatitis_b.html
- 岩井グループ. B型肝炎・C型肝炎について|内科 [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://www.iwai.com/group/shokai/naika-kanen.php
- MYメディカルクリニック. 肝硬変とは?症状や診断方法について解説|渋谷・大手町… [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://mymc.jp/clinicblog/166634/
- 肝炎情報センター. 肝硬変 [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://www.kanen.jihs.go.jp/cont/010/kankouhen.html
- 千住・胃と腸のクリニック. 肝硬変の症状とは?予防法や内視鏡検査・治療法などについて解説 [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://www.senju-ge.jp/media/liver-cirrhosis-symptom
- あすか製薬. 肝硬変の治療 – 肝臓の病気 [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://www.aska-pharma.co.jp/kansikkan/disease/14.html
- ナース専科. 肝硬変の病態生理や治療、看護計画について解説 [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://kango-oshigoto.jp/media/article/3644/
- 兵庫医科大学. わが国の肝硬変の成因はアルコール性がトップに:慢性肝疾患の… [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://www.hyo-med.ac.jp/research/activity/performance/210/
- MYメディカルクリニック. [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://mymc.jp/clinicblog/166634/#:~:text=%E8%82%9D%E7%A1%AC%E5%A4%89%E3%81%AE%E4%B8%BB%E3%81%AA%E5%8E%9F%E5%9B%A0,%E5%8C%96%E3%81%97%E3%81%A6%E7%A1%AC%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- 中村まさし内科クリニック. 肝硬変 [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://nakamuramasashi.com/%E8%82%9D%E7%A1%AC%E5%A4%89
- 日本肝臓学会. 肝硬変ガイド [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://www.jsh.or.jp/lib/files/citizens/hbv/guideline_cirrhosis_of_the_liver.pdf
- ユビー. 肝硬変ではどのような症状がありますか? [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://ubie.app/byoki_qa/clinical-questions/7lxgatdesmx8
- ウチカラクリニック. 肝硬変・肝臓がんの危険な症状とは?原因や治療法は?【医師解説】 [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://uchikara-clinic.com/media/cirrhosis/
- MYメディカルクリニック. [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://mymc.jp/clinicblog/166634/#:~:text=%E8%82%9D%E7%A1%AC%E5%A4%89%E3%82%92%E4%BA%88%E9%98%B2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%82%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E7%9A%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
- ユビー. 肝硬変はどのくらいの期間で治りますか?治療を開始してから治るまでの流れを教えてください。 [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://ubie.app/byoki_qa/clinical-questions/pn1r_0yjb2o2
- Eisai. 慢性肝炎,肝硬変はどうやって治療する?|知る [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://patients.eisai.jp/kanshikkan-support/know/liverdisease-treatment.html
- リペアセルクリニック. 肝硬変の食事で気をつけることは?食べてはいけないものやおすすめ献立を医師が解説 [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://fuelcells.org/topics/32751/
- 配食のふれ愛. 肝硬変の原因や治療法、食事療法について [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://www.h-fureai.com/column/care-food-for-liver-cirrhosis
- リペアセルクリニック. 肝硬変の治療法を合併症別に現役医師が解説|治る時代がやってくる!? [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://fuelcells.org/topics/32681/
- Eisai. 食事療法の考え方|食べる|エーザイの肝疾患サポートサイト [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://patients.eisai.jp/kanshikkan-support/eat/diettherapy.html
- 熊本中央病院. 肝臓病の食事|診療科のご案内 [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://kumachu.kkr.or.jp/rn2024/department/other/nutrition/tab4-7.html
- Eisai. 肝硬変患者さんの栄養状態|食べる|エーザイの肝疾患サポートサイト [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://patients.eisai.jp/kanshikkan-support/eat/nutrition.html
- 厚生労働省 肝炎対策国民運動事業. 国の対策と現状の課題 | 知って、肝炎 [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://www.kanen.org/about/taisaku/
- 障害者職業総合センター NIVR. 肝硬変 [インターネット]. [引用日: 2025年6月20日]. Available from: https://www.nivr.jeed.go.jp/option/nanbyo/55.html