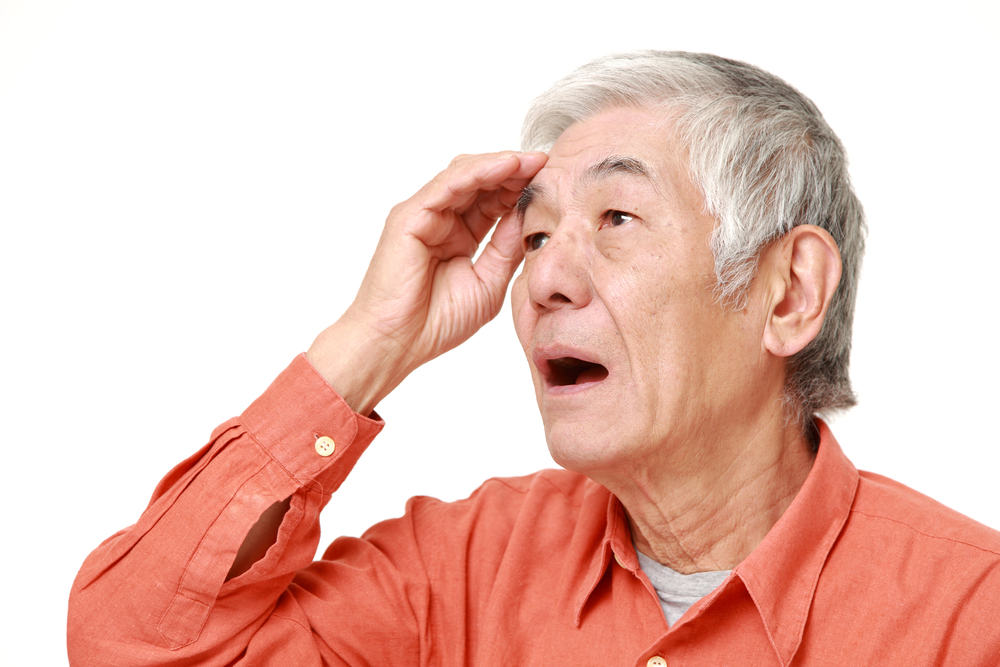この記事の科学的根拠
この記事は、引用されている研究報告書で明示された、最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下は、参照された実際の情報源と、提示された医学的ガイダンスとの直接的な関連性を示したものです。
- 世界保健機関(WHO)およびランセット委員会: 認知症の危険因子と予防戦略に関する記述は、世界保健機関(WHO)のガイドラインおよび権威ある医学雑誌ランセットの2020年報告書に基づいています。これらは、生活習慣の改善が認知症予防に重要であるという科学的コンセンサスを形成しています12。
- 日本神経学会および厚生労働省: 日本国内における診断基準、標準的治療法、および公的支援制度に関する情報は、日本神経学会が発行した「認知症疾患診療ガイドライン2017」および厚生労働省の「認知症施策推進大綱(新オレンジプラン)」に基づいています34。これらは、日本の医療現場における権威ある指針です。
- 国立長寿医療研究センター(NCGG): 日本独自の予防プログラム「コグニサイズ」に関する記述や、加齢による物忘れと認知症の違いに関する解説は、日本の高齢者医療研究を牽引する国立長寿医療研究センター(NCGG)の知見に基づいています5。
- 医薬品医療機器総合機構(PMDA)および製薬企業報告: アルツハイマー病の最新治療薬「レカネマブ」に関する効果、対象、副作用などの詳細な情報は、日本の医薬品承認機関であるPMDAの審査報告書および製薬企業の公式発表に基づいています6。
要点まとめ
- 加齢による物忘れは体験の一部を忘れるのに対し、認知症は体験全体を忘れる傾向があり、日常生活への影響の有無が重要な判断基準となります。
- 物忘れの原因は多様で、治療可能なもの(ビタミン欠乏、甲状腺機能障害など)も含まれるため、早期の正確な診断が極めて重要です。
- 最新治療薬「レカネマブ」は、早期アルツハイマー病の進行を遅らせる効果が示されており、治療に新たな希望をもたらしていますが、適応対象は限定的です。
- ランセット委員会の報告によれば、高血圧管理や運動、社会的交流など12の要因を管理することで、認知症の危険性の約40%を低減できる可能性があります1。
- 日本には、「コグニサイズ」のような独自の予防運動や、地域包括支援センターを通じた手厚い公的支援体制が存在します。
物忘れと認知症の不安に向き合うヒント
最近、物忘れが増えたと感じると「これは単なる加齢なのか、それとも認知症の始まりなのか」と心配になりますよね。ご自身だけでなく、ご家族の言動の変化に気づきながらも、どこまでが年相応の変化なのか判断に迷う方も多いと思います。「このまま進行してしまったらどうしよう」「病院に行くべきか分からない」と、不安だけが大きくなってしまうことも少なくありません。
“`
そこでこのミニガイドでは、加齢による自然な物忘れと、病的な認知症による物忘れの違い、考えられる原因、診断や治療、予防の考え方をコンパクトに整理します。まずは「何が心配で、どこから行動を始めればよいのか」をイメージできるようになることが目的です。脳や神経の病気全体の中で、ご自身の物忘れをどう位置づければよいか悩んだときは、JAPANESEHEALTH.ORGが体系的にまとめた脳と神経系の病気 完全ガイドもあわせて読むと、全体像をつかみやすくなります。このボックスをきっかけに、不安を少しずつ具体的な「次の一歩」に変えていきましょう。
物忘れの背景には、「年齢とともに誰にでも起こる生理的な変化」だけでなく、アルツハイマー病などの変性性認知症、脳梗塞などによる脳血管性認知症、さらにはビタミン欠乏や甲状腺機能低下症、正常圧水頭症、薬の副作用、うつ病や強いストレス、睡眠不足といった治療可能な要因まで、さまざまな原因が存在します。加齢による物忘れは「体験の一部を忘れる」が、認知症では「体験そのものをすっぽり忘れてしまう」ことが多く、日常生活への支障の有無が大きな目安になります。「もしかして認知症?」と感じたときにどのようなサインに注意すべきかは、早期発見のサインと家族ができる一歩で丁寧に整理されています。こうした情報も参考にしながら、「様子を見る」で終わらせず、必要なときにきちんと相談することが大切です。
行動の第一歩としては、物忘れのせいで約束を何度も忘れてしまう、財布や鍵を探し回ることが増えた、慣れた家事や仕事の段取りが極端に悪くなった…といった「日常生活への影響」が出てきたタイミングで、まずかかりつけ医に相談するのがおすすめです。そのうえで、必要に応じて「物忘れ外来」や脳神経内科、老年科など専門の外来を紹介してもらう流れが一般的です。専門医のもとでは、問診や神経心理検査(長谷川式認知症スケールやMMSEなど)、神経学的診察、血液検査、CT・MRIといった画像検査を組み合わせて、原因を一つひとつ丁寧に確認していきます。アルツハイマー病が疑われる場合、最近では血液検査やPETなどのバイオマーカー検査が診断の精度向上に役立つようになってきました。こうした検査の具体的な内容や受診先の選び方は、アルツハイマー病の診断ガイドでより詳しく確認できます。
検査の結果、早期アルツハイマー病と診断された場合には、近年登場したレカネマブのような疾患修飾薬が「進行を遅らせる」選択肢として検討されます。レカネマブは、アルツハイマー病の原因物質とされるアミロイドβの中でも毒性の高いプロトフィブリルを標的とし、脳内から除去することで症状の悪化スピードを抑えることが示されています。ただし、アミロイドβの蓄積がバイオマーカーで確認されていること、病期が軽度認知障害〜軽度のアルツハイマー型認知症に限られること、定期的なMRIによる副作用チェックが必要であることなど、適応条件はかなり限定的です。一方で、従来からある対症療法薬や、認知リハビリテーション、運動療法、回想法・音楽療法などの非薬物療法を組み合わせることで、日々の暮らしの質を高めることも大切です。アルツハイマー病そのものの全体像や、最新の治療・予防法については、アルツハイマー病の全体像と最新治療を参照すると理解が深まるでしょう。
また、「認知症」と聞くと一方向に進行するイメージを持ちがちですが、正常圧水頭症のように、原因に的確にアプローチすれば歩行障害や物忘れが大きく改善しうる「治せる認知症」もあります。特に、最近よく転ぶ・歩幅が小さくなったといった歩行障害に、尿のトラブルや物忘れが組み合わさっている場合には、正常圧水頭症(iNPH)の可能性も含めて専門医に評価してもらうことが重要です。診断がついた後の暮らし方や介護の工夫、公的な支援制度について知りたいときには、日本の認知症介護 完全ガイドが、家族の負担を一人で抱え込まないための道しるべになります。自己判断で「もう手遅れだ」と諦めてしまう前に、治療や支援の可能性を専門家と一緒に確かめていきましょう。
物忘れや認知症は、誰にとっても身近で不安の大きなテーマですが、「年のせいだから」と決めつけず、原因を確かめ、必要なサポートにつなげることで、将来の選択肢は大きく変わります。加齢による自然な変化なのか、治療や支援の対象となる状態なのかを早めに見極めることが、ご本人とご家族の安心につながります。今日できる小さな一歩――生活習慣の見直しや、相談先をメモしておくことからで構いません――を積み重ねながら、希望を持ってこの課題に向き合っていきましょう。
“`
もしかして認知症?加齢による物忘れとの決定的な違いとは
物忘れは誰にでも起こりうる現象ですが、その背景には単なる老化現象と、病的な認知症の初期症状という、二つの可能性があります。この二つを区別することは、不安を解消し、適切な対応をとるための第一歩です。国立長寿医療研究センターなどの専門機関によると、最も決定的な違いは「忘れている内容」と「日常生活への影響」にあります78。
加齢による物忘れは、体験の一部を忘れることが特徴です。例えば、「昨日の夕食に何を食べたかは思い出せないが、夕食を食べたこと自体は覚えている」といった具合です。多くの場合、ヒントがあれば思い出すことができ、忘れていること自体に自覚があります。これは脳の生理的な老化に伴うもので、日常生活に大きな支障をきたすことは稀です。
一方、認知症による物忘れは、体験の全体をすっぽりと忘れてしまう傾向があります。例えば、「夕食を食べたこと自体を覚えていない」という状態です。そのため、ヒントを与えても思い出すことが困難で、しばしば物忘れの自覚が乏しくなります。時間や場所が分からなくなる(見当識障害)、段取り良く物事を進められない(実行機能障害)といった他の認知機能の低下を伴い、次第に日常生活に支障をきたすようになります。
| 特徴 | 加齢による物忘れ | 認知症による物忘れ |
|---|---|---|
| 忘れる範囲 | 体験の一部(例:夕食の献立) | 体験の全体(例:夕食を食べたこと自体) |
| 自覚 | 「忘れてしまった」という自覚がある | 忘れたこと自体の自覚がないことが多い |
| ヒントによる想起 | ヒントがあれば思い出せる | ヒントがあっても思い出せないことが多い |
| 日常生活への影響 | ほとんどない | 支障が出てくる(約束を忘れる、物の管理ができない等) |
| 進行 | 年齢相応で、進行は緩やか | 時間とともに症状が進行する |
もしご自身やご家族の物忘れが、単に物事を思い出すのに時間がかかるというレベルを超え、日常生活に影響を及ぼし始めている場合は、専門家への相談を検討することが重要です。
物忘れの多様な原因:脳の病気から生活習慣、精神的要因まで
「物忘れ」と聞くと、すぐにアルツハイマー病などの認知症を連想しがちですが、その原因は非常に多岐にわたります。中には治療によって改善・回復可能なものも含まれているため、自己判断せずに原因を正確に突き止めることが極めて重要です9。
脳の病気に起因するもの
物忘れの最も深刻な原因は、脳自体の病変です。これには以下のようなものが含まれます。
- 変性性認知症:アルツハイマー病、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症など、脳の神経細胞が徐々に壊れていく病気です。
- 脳血管性認知症:脳梗塞や脳出血など、脳の血管の病気によって神経細胞がダメージを受け、認知機能が低下します。
- その他:脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、脳炎なども物忘れの原因となり得ます。
治療可能な原因(Treatable Dementia)
特筆すべきは、「治る認知症」とも呼ばれる一群の原因です。これらは早期に発見し、適切な治療を行えば、認知機能の回復が期待できます1011。
- ビタミン欠乏症:特にビタミンB1、B12、葉酸の欠乏は、認知機能の低下を引き起こすことが知られています。
- 甲状腺機能低下症:甲状腺ホルモンの不足により、全身の代謝が低下し、物忘れや無気力といった症状が現れます。
- 正常圧水頭症:脳室に脳脊髄液が過剰にたまり、脳を圧迫する病気です。物忘れ、歩行障害、尿失禁が三主徴とされています。
全身状態や精神的要因
脳の直接的な病気でなくても、心身の状態が記憶力に影響を及ぼすことがあります。
- うつ病・ストレス:強いストレスやうつ状態は、集中力や注意力を低下させ、結果として物忘れ(仮性認知症)を引き起こすことがあります。
- 薬の副作用(多剤服用):特に高齢者において、複数の薬を服用(ポリファーマシー)している場合、薬の相互作用や副作用によって認知機能が低下することがあります。
- 睡眠不足や疲労:十分な睡眠がとれていないと、記憶の定着が妨げられ、日中の注意力も散漫になります。
このように、物忘れの原因は一つではありません。だからこそ、「年のせい」と片付けずに、医療機関で原因を特定することが、その後の人生の質を大きく左右するのです。
専門医による診断プロセス:いつ、何科を受診すべきか?
物忘れが気になり始めたとき、早期に正確な診断を受けることは、将来の治療計画や生活設計の鍵となります。特に、アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」のような新しい治療法は、ごく早期の段階でなければ適応とならないため、診断の重要性はかつてなく高まっています。
受診の目安と診療科
「いつ、どの病院に行けばよいのか」は多くの方が悩む点です。受診を検討すべき目安は、「物忘れによって日常生活や仕事に支障が出始めたとき」です。例えば、約束を頻繁に忘れる、物の置き場所が分からず探し回ることが増えた、慣れた作業の段取りが悪くなった、といった具体的な変化がサインとなります9。
受診先としては、まず「かかりつけ医」に相談するのが第一歩です。その上で、専門的な検査が必要と判断された場合、以下の診療科を紹介されることが一般的です。
- 脳神経内科
- 精神科・心療内科
- 老年科
- 物忘れ外来(専門外来)
標準的な診断の流れ
専門外来では、日本神経学会の診療ガイドラインなどに沿って、多角的な検査が行われます310。
- 問診:本人および家族から、いつから、どのような症状があるか、日常生活の変化、既往歴、服薬状況などを詳しく聞き取ります。
- 神経心理検査:長谷川式認知症スケール(HDS-R)やミニメンタルステート検査(MMSE)などを用いて、記憶力、見当識、計算能力、言語能力といった認知機能を客観的に評価します。
- 神経学的診察:体の麻痺や感覚の異常、歩行の状態などを調べ、脳の他の病気の可能性を探ります。
- 血液検査:前述の治療可能な原因(ビタミン欠乏、甲状腺機能障害など)を除外するために行います。
- 脳画像検査:CTやMRIを用いて、脳の萎縮の程度や脳梗塞の有無、脳腫瘍などの器質的な異常がないかを確認します。
最新の診断技術:バイオマーカー検査
近年の診断における大きな進歩は、アルツハイマー病の原因物質であるアミロイドβの蓄積を直接可視化・測定するバイオマーカー検査です。新薬「レカネマブ」の適応を判断するために不可欠な検査となっています12。
- アミロイドPET検査:アミロイドβに結合する特殊な薬剤を注射し、PETカメラで撮影することで、脳内のアミロイド蓄積を画像として捉えることができます。
- 脳脊髄液検査:腰椎穿刺によって脳脊髄液を採取し、その中に含まれるアミロイドβやタウタンパクの濃度を測定します。
これらの先進的な検査により、症状がまだ軽微な軽度認知障害(MCI)の段階でも、その原因がアルツハイマー病によるものかを高い精度で診断できるようになりました。これにより、より早期からの介入が可能となっています。
認知症の最新治療法:新薬レカネマブから非薬物療法まで
かつて認知症、特にアルツハイマー病は「進行を止められない病」と考えられていましたが、近年の研究開発により、その流れは大きく変わりつつあります。疾患の根本原因に働きかける新薬の登場は、治療に革命的な変化をもたらし、新たな希望を生み出しています。
疾患修飾薬「レカネマブ」の登場
2023年に日本で承認された「レカネマブ(製品名:レケンビ®)」は、アルツハイマー病の治療における画期的な薬剤です6。これは、従来の症状を緩和する対症療法薬とは異なり、病気の進行そのものに影響を与える「疾患修飾薬」として初めて明確な効果が示されました。
- 作用機序:レカネマブは、アルツハイマー病の脳内に蓄積し、神経細胞を傷害する原因物質と考えられている「アミロイドβ」の中でも、特に毒性が高いとされるプロトフィブリルに選択的に結合し、脳内から除去します13。
- 効果:臨床試験において、レカネマブは18ヶ月間の投与で、プラセボ(偽薬)と比較して臨床症状の悪化を27%抑制することが示されました14。これは病気の進行を遅らせることを意味し、患者さんが自立した生活をより長く送れる可能性を示唆します。
- 対象患者:この薬の対象は非常に限定的です。アミロイドPETや脳脊髄液検査でアミロイドβの蓄積が確認された、症状がまだ軽度な「早期アルツハイマー病」(軽度認知障害(MCI)および軽度の認知症)の患者さんに限られます14。
- 注意点:アミロイド関連画像異常(ARIA)と呼ばれる、脳浮腫や脳微小出血などの副作用が報告されており、投与には定期的なMRI検査による慎重なモニタリングが必要です10。
従来の対症療法薬
現在も、記憶障害や問題行動といった認知症の中核症状や周辺症状を緩和するために、複数の薬剤が使用されています。これらは病気の進行を止めるものではありませんが、患者さんと介護者の生活の質を維持する上で重要な役割を果たします。
非薬物療法の重要性
薬物療法と並行して、非薬物療法も認知症治療の重要な柱です。これらは認知機能の維持や精神的な安定に寄与します。
- 認知リハビリテーション:失われた機能を取り戻すのではなく、残された機能を最大限に活用するための訓練を行います。
- 運動療法:定期的な運動は、認知機能の維持だけでなく、気分の改善や転倒予防にも繋がります。
- 回想法や音楽療法:昔の写真や音楽を用いて過去の記憶を呼び覚まし、精神的な安定やコミュニケーションの活性化を図ります。
最新の治療は、薬物療法と非薬物療法を組み合わせ、患者さん一人ひとりの状態に合わせて個別化されたアプローチをとることが主流となっています。
【科学的根拠に基づく】認知症リスクを減らす予防戦略 (WHOガイドライン準拠)
認知症は、発症してから治療するだけでなく、発症する前の「予防」が極めて重要であるという考え方が、世界の共通認識となっています。2020年に医学雑誌ランセットに掲載された画期的な報告では、12の修正可能な危険因子を管理することで、世界中の認知症のうち約40%が予防または発症を遅らせることが可能であると結論付けています1。これらの知見は、世界保健機関(WHO)のガイドラインにも反映されており2、私たちの生活習慣がいかに脳の健康に重要であるかを示しています。
WHOとランセット委員会が示す12の危険因子と対策
以下に、科学的根拠に基づいた12の危険因子と、今日から実践できる具体的な予防戦略を解説します。
| 危険因子 | 具体的な予防戦略と解説 |
|---|---|
| 1. 高血圧 (中年期) | 血圧を定期的に測定し、正常範囲(収縮期130mmHg未満が目標)に保つ。必要であれば医師の指導のもと降圧薬を服用する15。高血圧は脳の微小な血管にダメージを与え、認知機能低下の大きな原因となります。 |
| 2. 難聴 (中年期) | 聴力の低下を感じたら、専門医に相談し、必要に応じて補聴器を使用する。聴覚からの情報入力が減ることは、脳への刺激を減少させ、社会的孤立にも繋がります。 |
| 3. 頭部外傷 | 自転車乗車時のヘルメット着用や、転倒予防策(手すりの設置など)を講じ、頭部への衝撃を避ける。 |
| 4. 過度のアルコール摂取 | 飲酒量を減らす。WHOは週に21単位(ビール大瓶約10.5本)以上の飲酒を危険としています。節度ある飲酒を心がけることが重要です。 |
| 5. 肥満 (中年期) | 適正体重を維持する。バランスの取れた食事と定期的な運動が基本となります。 |
| 6. 喫煙 | 禁煙する。喫煙は血管を傷つけ、脳卒中や心臓病のリスクを高めることで、間接的に認知症のリスクも高めます16。 |
| 7. うつ病 | 気分の落ち込みが続く場合は、専門家に相談し、適切な治療を受ける。うつ病は認知症の危険因子であると同時に、初期症状である可能性もあります。 |
| 8. 社会的孤立 | 家族や友人との交流を保ち、趣味の会やボランティア活動などに参加する。人とのコミュニケーションは脳にとって重要な刺激です。 |
| 9. 運動不足 | WHOは週に150分以上の中等度の有酸素運動(早歩きなど)を推奨しています17。運動は脳の血流を改善し、神経細胞の成長を促します。 |
| 10. 大気汚染 | 汚染の激しい場所での長時間の活動を避けるなど、可能な範囲で対策を講じる。 |
| 11. 低学歴 | 生涯学習を続ける。新しいことを学ぶ、読書をする、楽器を演奏するなど、知的好奇心を持ち続けることが「認知予備能」を高めます。 |
| 12. 糖尿病 | 血糖値を適切に管理する。糖尿病は血管にダメージを与え、アルツハイマー病のリスクを高めることが知られています。 |
特に、健康的な食事パターンは重要です。魚、野菜、果物、豆類を多く含む地中海式食事や、伝統的な和食は、認知症予防に有益である可能性が示唆されています1819。これらの戦略は、一つひとつが独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。健康的な生活習慣を総合的に実践することが、脳の健康を守るための最も効果的な方法なのです。
日本の取り組み:認知症予防運動「コグニサイズ」と地域包括ケア
世界的な予防戦略の流れの中で、日本は独自の優れたプログラムと、きめ細やかな社会支援システムを構築してきました。これらは、科学的知見を日本の実情に合わせて応用したものであり、国民一人ひとりが実践できる具体的な選択肢を提供しています。
日本発の予防運動「コグニサイズ」
国立長寿医療研究センター(NCGG)が開発した「コグニサイズ」は、認知症予防を目的とした日本独自の画期的な運動プログラムです520。
- 定義と目的:コグニサイズは、「コグニション(認知)」と「エクササイズ(運動)」を組み合わせた造語です。運動を行いながら、同時に計算やしりとりなどの認知課題(頭の体操)を行う「デュアルタスク(二重課題)」が基本となります。これにより、脳の活動を活発化させ、認知機能の維持・向上を目指します21。
- 具体的な運動例(コグニステップ):
- 足踏みをしながら、1から順番に数を数えます。
- 「3の倍数」のときだけ、声を出さずに手を叩きます。(例:「1、2、(パン!)、4、5、(パン!)、7…」)
- 慣れてきたら、ステップの仕方を変えたり、課題を難しくしたりします(例:前に進みながら、後ろに下がりながら行う)。
このプログラムの優れた点は、特別な器具を必要とせず、楽しみながら安全に実践できることです。全国の自治体や介護施設などで広く導入が進んでいます22。
社会全体で支える:新オレンジプランと地域包括支援センター
日本政府は、厚生労働省を中心に「認知症施策推進大綱(新オレンジプラン)」を掲げ、認知症の人やその家族が地域で安心して暮らせる社会の構築を目指しています4。この計画は、「予防」と「共生」を両輪として推進しています。
- 地域包括支援センター:このシステムの拠点となるのが、全国の市町村に設置されている「地域包括支援センター」です。高齢者の健康、福祉、介護に関する総合的な相談窓口であり、無料で利用できます。認知症に関する悩み相談、専門医療機関の紹介、介護保険サービスの利用支援など、様々なサポートを提供してくれます。物忘れに悩んだら、まずここに相談することが非常に有効です4。
- 認知症サポーター:「認知症サポーター」は、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者です。特別な養成講座を受けることで誰でもなることができ、地域社会における偏見をなくし、支援の輪を広げる上で重要な役割を担っています。
これらの日本の取り組みは、医学的なアプローチだけでなく、社会全体で認知症という課題に向き合おうとする姿勢の表れであり、世界からも注目されています。
よくある質問
20代や30代で物忘れがひどいのは病気ですか?
若い世代での物忘れは、一般的にアルツハイマー病などの変性性認知症である可能性は非常に低いです。多くの場合、仕事の多忙さによるストレス、睡眠不足、うつ状態、注意力の散漫などが原因と考えられます9。まずは生活習慣を見直し、十分な休息をとることが重要です。しかし、症状が改善しない、あるいは他の神経症状(頭痛、めまい、体のしびれなど)を伴う場合は、稀な病気の可能性も否定できないため、一度、脳神経内科や心療内科の受診をお勧めします。
新薬レカネマブは誰でも使えますか?
いいえ、誰でも使えるわけではありません。レカネマブの投与対象は非常に厳密に定められています。まず、アミロイドPET検査や脳脊髄液検査によって、脳内にアルツハイマー病の原因とされるアミロイドβが蓄積していることが確認される必要があります。さらに、病気の進行度が「軽度認知障害(MCI)」または「軽度のアルツハイマー型認知症」という、ごく早期の段階にある患者さんに限られます。中等度以上に進行した患者さんには効果が確認されておらず、適応となりません14。
認知症の予防に最も効果的なことは何ですか?
家族が認知症かもしれないと思ったら、まず何をすべきですか?
まずは、ご本人の自尊心を傷つけないように配慮しながら、変化について穏やかに対話する機会を持つことが大切です。その上で、かかりつけ医、またはお住まいの地域の「地域包括支援センター」に相談することをお勧めします4。地域包括支援センターは、専門医療機関の紹介や、今後の生活に関する公的サービスの情報提供など、初期段階で必要なサポートを包括的に行ってくれる心強い味方です。
結論
物忘れと認知症は、多くの人々にとって不安の種ですが、正しい知識を持つことで、その向き合い方は大きく変わります。加齢による自然な変化と病的な症状を区別し、多様な原因の中から治療可能なものを見逃さず、早期に専門家へ相談することが極めて重要です。近年、レカネマブのような画期的な治療薬が登場し、病気の進行を遅らせることが現実的な目標となりました。しかし、その恩恵を受けられるのは、ごく早期に診断された一部の患者さんに限られます。
だからこそ、私たち一人ひとりが今すぐに取り組める「予防」の価値は計り知れません。運動、食事、生活習慣病の管理、そして社会とのつながり。これらの地道な努力が、脳の健康を守る最も確かな礎となります。日本には、コグニサイズのような優れたプログラムや、地域包括支援センターという頼れる相談窓口も整備されています。
認知症は確かに困難な課題ですが、もはや一方的に進行を待つだけの病気ではありません。科学的根拠に基づいた知識で武装し、予防に努め、最新の医療や社会の支援システムを積極的に活用することで、私たちは希望を持ってこの課題に立ち向かうことができるのです。この記事が提供する情報が、あなた自身とあなたの大切な人の未来を守るための、確かな一歩となることを心から願っています。
免責事項本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的アドバイスを構成するものではありません。健康に関する懸念や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet. 2020;396(10248):413-446. doi:10.1016/S0140-6736(20)30367-6
- World Health Organization. Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines. Geneva: World Health Organization; 2019. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789241550543
- 日本神経学会. 認知症疾患診療ガイドライン2017. 医学書院; 2017. Available from: https://www.neurology-jp.org/guidelinem/nintisyo_2017.html
- 厚生労働省. 認知症施策推進大綱について. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html
- 国立長寿医療研究センター. コグニサイズとは. Available from: https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/27-4.html
- エーザイ株式会社. 抗アミロイドβプロトフィブリル抗体「レカネマブ」について、日本において早期アルツハイマー病に係る適応で新薬承認を申請. ニュースリリース. 2023. Available from: https://www.eisai.co.jp/news/2023/news202307.html
- 国立長寿医療研究センター. 認知症臨床研究・治験の推進. Available from: https://www.ncgg.go.jp/hospital/ictr/crnd/general/general03.html
- 朝日生命. 加齢による物忘れと認知症の違いは?物忘れの予防と対処法. Available from: https://anshinkaigo.asahi-life.co.jp/activity/ninchisho/column1/05/
- ユビー. 物忘れの場合、何科を受診したらよいですか?また、病院を受診する目安はありますか?. Available from: https://ubie.app/byoki_qa/clinical-questions/symptom/b6u0c-owsz5
- かめいメンタル・メモリークリニック. 認知症(もの忘れ)の原因や症状、治療. Available from: https://www.kamei-mental.com/column/dementia.html
- 両国はらクリニック. もの忘れ外来. Available from: https://ryogoku-haracl.com/forgetfulness/
- 日本精神神経学会. 認知症に関する脳脊髄液・血液バイオマーカー情報の適正使用指針(改訂版). 2023. Available from: https://www.jspn.or.jp/modules/advocacy/index.php?cat_id=11
- 前澤クリニック. 今日の健康(8月)認知症の新薬. Available from: https://maezawa-clinic.jp/wp/wp-content/uploads/230902_ninchisho.pdf
- HOKUTO. 【更新】レカネマブ正式承認、 添付文書の注意点 ~アルツハイマー病治療はどう変わる?. 2023. Available from: https://hokuto.app/post/SB9SXR5hzH85Hin6Usfs
- 西記念ポートアイランドリハビリテーション病院. 認知症リスクを下げる生活習慣 WHOガイドラインから. Available from: https://nishi.kcho.jp/data/media/nishi/page/annai/shinryoka/nintisyo/pdf02.pdf
- メディカル・ケア・サービス株式会社. 【WHO推奨】認知症リスク低減のためのポイント|身体活動. Available from: https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/dementia/35636
- MCBI. WHOが推奨している12項目. Available from: https://mcbi.jp/lifestyle/preventive-measures/who-risk-reduction/
- 公益財団法人体力つくり指導協会. 今日からはじめよう! 認知症予防はカラダづくりから. Available from: https://www.health-net.or.jp/syuppan/leaflet/pdf/ninchiyobou.pdf
- Cog-selfcheck. WHO認知症予防ガイドラインとは。 認知症予防に役立つ情報をまとめて解説. Available from: https://cog-selfcheck.jp/column/s77/
- 岡崎市民病院 認知症疾患医療センター. コグニサイズについて. Available from: https://www.okazakihospital.jp/dementia/dementia/cognicise/
- DK ELDER SYSTEM. 〈プレミアムコンテンツ〉コグニサイズ. Available from: https://dk-eldersystem.com/contents/koguni.html
- みんなの介護. 【認知症予防】コグニサイズとは?具体例とやり方・意味を解説!. Available from: https://www.minnanokaigo.com/guide/dementia/prevention/cognicise/