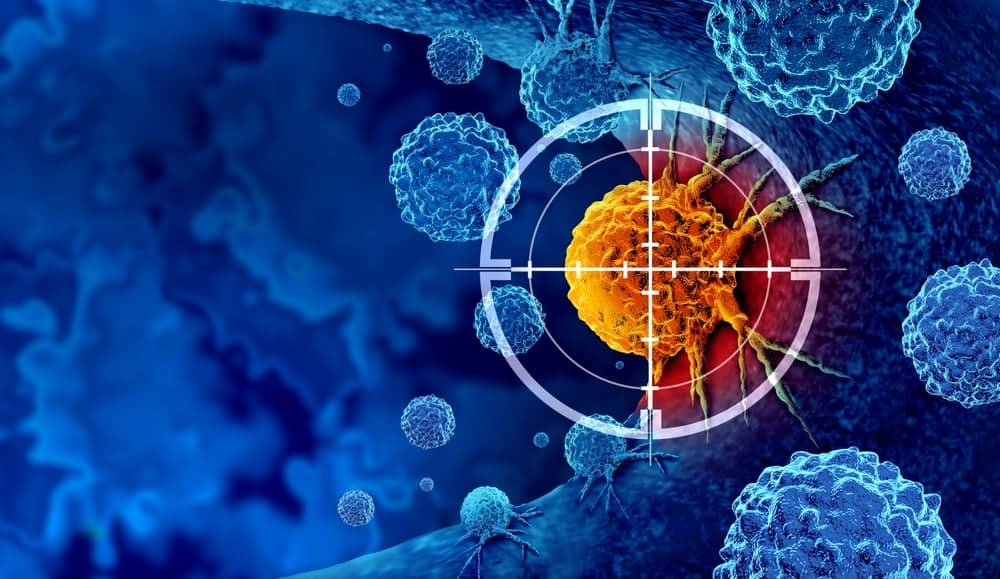本記事の科学的根拠
この記事は、入力された研究報告書で明示的に引用されている最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下のリストには、実際に参照された情報源のみが含まれており、提示された医学的ガイダンスとの直接的な関連性も示されています。
- 全国がんセンター協議会(全がん協): 本記事におけるステージ4のがん種別5年相対生存率に関するデータは、全国がんセンター協議会が公開する「全がん協生存率調査」の公式統計に基づいています。4
- 日本臨床腫瘍学会(JSMO)など: 骨転移、肝転移、脳転移、肺がんの標準治療に関する指針は、日本臨床腫瘍学会、日本肝胆膵外科学会、日本脳腫瘍学会、日本肺癌学会などが発行する各部位の診療ガイドラインに準拠しています。9101118
- 厚生労働省(MHLW): 診断早期からの緩和ケアの重要性に関する記述は、日本政府のがん対策推進基本計画の方針に基づいています。14
- 国立がん研究センター(NCC): 緩和ケアやがんゲノム医療に関する日本の制度や利用方法についての具体的な情報は、国立がん研究センターが運営する「がん情報サービス」および「がんゲノム情報管理センター(C-CAT)」の公開情報に基づいています。1519
要点まとめ
- 「余命」は個人の予測不能な寿命であり、医学では統計的指標である「予後」「生存率」を用いて全体像を把握します。日本の公式データでは、多くのがんで生存率が改善傾向にあります。
- 転移がんの治療は、複数の専門家が連携する「集学的治療」が基本であり、その方針は「キャンサーボード」で決定されるのが標準的です。
- 骨・脳・肝・肺など転移した部位ごとに、日本の各学会が作成した「診療ガイドライン」が存在し、科学的根拠に基づく標準治療が定められています。
- 「緩和ケア」は終末期医療ではなく、がんと診断された時から治療と並行して行うべき苦痛を和らげるための重要なケアです。
- 「がんゲノム医療」は、遺伝子情報を基に最適な治療法を探す新しい選択肢であり、日本の指定病院で保険診療として受けることが可能です。
転移がんと予後の理解
「転移」という言葉を告げられた瞬間、多くの方が「自分の余命はあとどれくらいなのか」「これからどんな治療が待っているのか」といった不安に押しつぶされそうになるかもしれません。インターネットで断片的な情報を調べるほど、かえって怖さが増してしまい、何を信じれば良いのか分からなくなることもあります。まずは、その戸惑いや恐怖は決してあなただけのものではなく、誰もが通るごく自然な感情であることを知ってください。そして、感情と同じくらい大切なのが、「今の状態を冷静に理解するための正しい地図」を手に入れることです。
“`
この地図づくりに役立つのが、日本の公的データや診療ガイドラインに基づいた情報です。転移があっても、がんの種類や広がり方によって治療の選択肢や見通しは大きく変わりますし、「余命」という曖昧な言葉ではなく、「予後」や「生存率」といった統計を使って全体像を捉えることで、不安を少しずつ知識へと変えていくことができます。がん全体の仕組みやステージ、検診、標準治療の位置づけを俯瞰したいときは、まずはがん・腫瘍疾患の総合ガイドを入り口に、「自分の病状がこの中のどこに当てはまるのか」を整理するところから始めてみましょう。
転移がんの「予後」を理解するうえで重要なのは、「一人ひとりの寿命そのものを当てることはできないが、多くの患者さんのデータから全体の傾向を知ることはできる」という視点です。例えば、日本のがん統計で広く用いられる5年相対生存率は、「同じような状態で診断された人たちが、どのくらいの割合で5年後も生きているか」を示す指標であり、あなた個人への宣告ではなく、あくまで道しるべに過ぎません。また、同じステージIVであっても、乳がんや前立腺がんのように長期生存が期待できるものもあれば、早期から慎重な対応が必要ながん種もあります。さらに、どの臓器に転移しているかによって症状や生活への影響も変わります。たとえば骨に転移した場合の痛みや末期症状、生活への支障については、骨転移がんの生存期間のような部位別の情報を見ると、より具体的にイメージしやすくなるでしょう。
具体的な一歩としてまず大切なのは、「自分のがんの全体像」を主治医と一緒に整理することです。原発巣の種類、ステージ、転移している臓器の数や場所、全身状態やこれまで受けてきた治療歴などを洗い出すことで、今どのような選択肢が現実的なのかが見えてきます。そのうえで、「原発巣ごとに転移が見つかった場合、どのくらいの生存期間が報告されているのか」「オリゴメタスターシス(少数転移)の段階であれば、局所療法を組み合わせる余地があるのか」といったポイントを確認していきます。原発巣別の統計やオリゴ転移に対する最新の考え方を知りたいときには、肺転移がんの生存期間のような記事も手がかりになります。数字を見るのは怖いかもしれませんが、「今いる場所を知る」ことが、これからの方針を一緒に決めていく出発点になります。
次のステップとして重要なのが、「自分に合った治療戦略を、チーム医療の中で組み立てること」です。転移がんの標準的な考え方では、手術・薬物療法・放射線治療・緩和ケアなどを組み合わせた集学的治療が中心となり、その方針はキャンサーボードと呼ばれる多職種カンファレンスで検討されることが推奨されています。特に肝臓のような臓器では、「切除できるかどうか」「局所療法や肝動注療法を組み合わせる余地があるか」といった専門的な判断が必要になります。肝転移に焦点を当てた治療パラダイムや日本の医療体制の特徴について深く知りたい場合は、転移性肝がんの治療戦略のような解説を読みながら、主治医に「自分の場合、この選択肢は考えられるのか」と一つずつ確認していくことが大切です。
同時に忘れてはいけないのが、「治療そのもの」と「生活の質を守るケア」を並行して進めるという視点です。痛みや息苦しさ、倦怠感、食欲低下といった症状は、我慢すべきものではなく、診断の早い段階から緩和ケアチームに相談することで、薬物療法やリハビリ、心理的サポートなど多角的に和らげることができます。また、標準治療が一通り終わった後も、がんゲノム医療という新しい選択肢が開ける場合があります。日本の制度のもとで行われるがん遺伝子パネル検査や、その結果を踏まえた治験・分子標的薬などの可能性については、がん遺伝子パネル検査とゲノム医療の情報も参考にしながら、「自分は対象になるのか」を主治医に相談してみてください。
転移がんという現実は、確かに重く感じられるかもしれません。しかし、予後や生存率のデータを「運命の宣告」としてではなく、「自分と医療チームが一緒に進むための地図」として捉え直すことで、見えてくる景色は少しずつ変わっていきます。今すぐすべてを理解する必要はありませんが、「自分の状態を整理する」「信頼できる情報源を押さえる」「医療者と率直に話す」という小さなステップを一つずつ積み重ねることが、これからの時間を納得して過ごすための力になります。この先の道のりを、恐怖だけでなく希望も抱きながら歩んでいけるよう、本稿で得た視点をあなたとご家族の対話に役立てていただければ幸いです。
“`
1. 「余命」から「予後」へ:生存率データを正しく理解する力
がんの転移を告げられたとき、多くの方が最初に知りたいと願うのは「自分の余命はあとどれくらいなのか」ということかもしれません。しかし、この問いに対して、医師が明確な数字で答えることはありません。それは決して希望がないからではなく、医学的な誠実さの表れなのです。
1.1. なぜ医師は「余命」を断言しないのか?
「余命」という言葉は、一個人の残された寿命を指しますが、これを正確に予測することは現代医学をもってしても不可能です。がんの進行速度、治療への反応、体力や精神状態など、無数の要因が複雑に絡み合うため、同じ種類、同じステージのがんであっても、その後の経過は一人ひとり全く異なります。そのため、医師は不確かな予測で患者さんを縛るのではなく、より客観的で科学的な指標を用います。それが「予後」と「生存率」という考え方です。
「予後」とは病気の経過についての医学的な見通しを指し、「生存率」はその見通しを具体的な数値で示した統計データです。これらは、あなた個人に下された「宣告」ではなく、過去の多くの患者さんのデータを基にした、あくまで全体的な傾向を示す「地図」のようなものだと理解することが重要です。この地図を手にすることで、私たちは自分が今どこにいるのかを客観的に把握し、これから進むべき道を冷静に考えることができるようになります。
1.2. 5年相対生存率とは?日本の公式データが示す希望
がんの統計でよく用いられるのが「5年相対生存率」です。これは、がんと診断された人のうち、5年後に生存している人の割合が、日本人全体の5年後の生存率と比べてどのくらいかを示す数値です。がん以外の原因(例えば、心臓病や事故など)で亡くなる影響を取り除いているため、がんそのものが生命に与える影響をより正確に評価できます。4
ここで、日本の最も信頼性の高いデータの一つである、全国がんセンター協議会(全がん協)の「全がん協生存率調査」を見てみましょう。この調査は、日本のがん診療の現状を正確に反映しています。以下は、主な癌腫におけるステージIV(転移がある状態)と診断された場合の5年相対生存率です。4
表1:日本の主要がんにおけるステージIVの5年相対生存率(データ源:全がん協)
がんの種類 5年相対生存率(ステージIV) 乳がん(女性) 43.5% 前立腺がん 66.7% 大腸がん 18.7% 3 胃がん 7.0% 肺がん 5.3% 注:これらの数値は統計データであり、個人の予後を示すものではありません。最新のデータについては公式サイトをご確認ください。
この表から分かるように、ステージIVと一括りに言っても、がんの種類によって生存率は大きく異なります。特に乳がんや前立腺がんでは、転移があっても半数近い、あるいはそれ以上の方が5年後も生存しており、がんと共に長く生きていく「慢性疾患」としての一面が見えてきます。また、大腸がんや他のがんにおいても、数字は決してゼロではありません。そして最も重要なことは、これらのデータはあくまで過去の治療成績の集計であり、医学は日進月歩で進歩しているという事実です。今日あなたが受けられる治療は、この統計が基になった数年前の治療よりも進化している可能性が高いのです。データは冷静に受け止めつつも、それが未来を決定づけるものではないという希望を持つことが、治療への第一歩となります。
2. 治療の基本方針:集学的治療とキャンサーボードの役割
転移がんの治療は、単一の治療法で立ち向かうのではなく、様々な専門家が知恵を結集して最適な戦略を練る「総力戦」です。この考え方を「集学的治療」と呼びます。これは、手術、薬物療法(化学療法、ホルモン療法、分子標的薬、免疫療法など)、放射線治療といった複数の治療法を、患者さん一人ひとりの状態に合わせて最適に組み合わせるアプローチです。
この集学的治療の司令塔となるのが、「キャンサーボード(Cancer Board)」です。これは、外科医、腫瘍内科医、放射線治療医、病理診断医、看護師、薬剤師など、がん治療に関わる様々な分野の専門家が一堂に会し、一人の患者さんの診断や治療方針について議論する会議のことです。日本のがん診療連携拠点病院などでは、このキャンサーボードの設置が標準となっており1、一人の医師の判断だけでなく、多角的な視点から最も質の高い治療方針が検討されます。治療方針は、がんが最初に発生した「原発巣」の種類、転移している場所と数、そして患者さんご自身の全身状態や希望などを総合的に考慮して決定されます。
3. 【部位別】日本の診療ガイドラインに基づく標準治療
ここからは、転移が起こりやすい主要な部位(骨、脳、肝、肺)ごとに、日本の各専門学会が作成した「診療ガイドライン」に基づいて、どのような治療が標準的に行われているのかを具体的に解説します。これらのガイドラインは、数多くの臨床研究の結果を基に、現時点で最も効果的で安全と考えられる治療法を推奨する、日本の医師たちの「教科書」です。
3.1. 骨転移:生活の質(QOL)を守るための最新アプローチ
骨への転移で最も重要な治療目標は、生命予後の改善はもちろんのこと、患者さんの「生活の質(Quality of Life, QOL)」を維持・向上させることです。骨転移は、痛み、病的骨折、脊髄圧迫による麻痺などを引き起こし、日常生活に深刻な影響を及ぼす可能性があるためです。
この領域では、日本臨床腫瘍学会(JSMO)が中心となって作成した『骨転移診療ガイドライン(改訂第2版)』が治療の根幹をなします。912 このガイドラインが示す現代的なアプローチの核心は、「多職種による同時並行的な介入」です。かつてのように一つずつ治療を試すのではなく、以下の4つの柱を早期から同時に進めることが推奨されています。
- 局所療法:痛みのある部位や骨折リスクの高い部位に放射線を照射し、症状を和らげ、がん細胞を叩きます。
- 薬物療法(全身療法):骨を強くし、骨折などの合併症(骨関連事象)を防ぐ「骨修飾薬」(ビスホスホネート製剤やデノスマブなど)を投与します。もちろん、がんそのものに対する化学療法や免疫療法も並行して行います。
- リハビリテーション:理学療法士などが関わり、筋力低下を防ぎ、安全な動作を指導することで、QOLの維持を目指します。
- 包括的管理:痛み止め(医療用麻薬など)による症状緩和、栄養指導、精神的サポートなど、あらゆる側面から患者さんを支えます。
また、同ガイドラインでは、これらの治療を効果的に進めるために「骨転移キャンサーボード」の設置が推奨されており、整形外科医、放射線治療医、腫瘍内科医などが密に連携する体制の重要性が強調されています。9 ご自身の状況でどのようなサポートが受けられるか、担当の医療チームにぜひご相談ください。
3.2. 脳転移:腫瘍の数と大きさで決まる治療戦略
脳への転移は、頭痛、吐き気、麻痺、けいれんなど、多彩な神経症状を引き起こす可能性があります。治療法の選択は、転移した腫瘍の数、大きさ、場所、そして原発がんの種類によって大きく左右されます。
日本脳腫瘍学会と日本脳神経外科学会が共同で作成した『転移性脳腫瘍診療ガイドライン(2024年版)』は、その名の通り、この分野における最新かつ最も信頼性の高い指針です。11 このガイドラインは、腫瘍の数に応じて非常に明確な治療戦略を示しています。
表2:日本のガイドラインに基づく脳転移の治療選択(要約)
腫瘍の数 推奨される主な治療法 解説 1個 手術 または 定位放射線治療(SRT) 腫瘍が大きく、周囲の脳を圧迫している場合は手術が優先されることが多い。小さい場合はSRTが良い選択肢となる。 2~4個 定位放射線治療(SRT) 複数の腫瘍をピンポイントで狙い撃ちできるSRTが標準。正常な脳へのダメージを最小限に抑えることを目指す。 5個以上 全脳放射線治療(WBRT) または 薬物療法 腫瘍が広範囲に散らばっている場合、脳全体に放射線をかけるWBRTが検討される。近年は、認知機能への影響を避けるため、効果が期待できる薬剤があれば薬物療法が優先される傾向にある。 注:上記は一般的な指針であり、実際の治療法は患者個々の状態に応じて総合的に判断されます。11
「定位放射線治療(Stereotactic Radiotherapy, SRT)」は、ガンマナイフやサイバーナイフといった機器を用い、多方向から放射線を病巣に集中させることで、周囲の正常な脳組織への影響を極力抑えながら、高い線量を腫瘍に照射する先進的な技術です。この治療法の進歩により、かつては治療が困難であった複数個の脳転移に対しても、QOLを保ちながら治療を行うことが可能になってきています。
3.3. 肝転移:切除可能かどうかの判断基準
肝臓は、多くの消化器がんや乳がんなどが転移しやすい臓器です。肝転移の治療において、最も根治(がんを完全に取り除くこと)が期待できる方法は、今も昔も「外科的切除」です。しかし、全ての患者さんが手術を受けられるわけではありません。
日本肝胆膵外科学会(JSHBPS)が示す『転移性肝がん診療ガイドライン』では、手術が可能かどうかを判断するための詳細なアルゴリズムが提示されています。102 その基準は、主に以下の要素によって決まります。
- 腫瘍の数と場所:転移巣が肝臓の片葉に留まっているか、主要な血管から離れているかなど。
- 肝臓以外の転移の有無:他の臓器に制御不能な転移がないこと。
- 残存する肝臓の機能:手術後に残る肝臓が、生命を維持するのに十分な機能を持つと予測されること。
これらの条件を満たさない「切除不能」と判断された場合でも、治療の選択肢がなくなるわけではありません。ラジオ波焼灼療法(RFA)のように、針を刺して熱でがんを焼き固める局所療法や、肝臓に栄養を送る動脈に直接抗がん剤を流し込む肝動注化学療法、そして全身に作用する薬物療法(化学療法や分子標的薬など)を組み合わせることで、がんの進行を抑え、症状を緩和することを目指します。
3.4. 肺転移:オリゴメタスターシスという考え方
肺もまた、様々な種類のがんが転移しやすい臓器です。肺に転移が見つかった場合、基本的には薬物療法が治療の中心となります。しかし、近年「オリゴメタスターシス(Oligometastasis)」という概念が注目されています。
これは、「転移しているけれども、その個数が少なく(オリゴ)、特定の臓器に限局している」状態を指します。日本肺癌学会の『肺癌診療ガイドライン2024年版』などでも、このような状態に対する積極的な局所治療の意義が議論されています。18 オリゴメタスターシスと考えられる場合、薬物療法と並行して、転移巣に対する手術や定位放射線治療といった「根治を目指す局所療法」を行うことで、長期的な生存が期待できる患者さんがいることが分かってきました。また、肺転移に伴って胸水(肺の外側に水が溜まる状態)が溜まり、呼吸困難などの症状が出ている場合には、胸水を抜いたり、胸膜癒着術を行ったりすることで、症状を劇的に改善させることができます。これもQOLを維持するための重要な治療です。
4. 治療と並行する重要な支え:日本の医療制度を最大限に活用する
最先端の治療を受けることと同様に、治療に伴う身体的・精神的な苦痛を和らげ、自分らしい生活を維持することも極めて重要です。日本の医療制度には、そのための強力な支援システムが整備されています。
4.1. 診断時から始まる「緩和ケア」:痛みを我慢しない権利
「緩和ケア」と聞くと、「もう治療法がない終末期の医療」というイメージを持つ方がいまだに少なくありません。しかし、これは大きな誤解です。現代のがん医療において、緩和ケアは「がんと診断されたその時から、治療と並行して行われるべき、あらゆる苦痛を和らげるためのケア」と定義されています。
この考え方は、厚生労働省が策定する「がん対策推進基本計画」にも明確に示されている日本政府の方針です。14 痛み、吐き気、だるさといった身体的な苦痛だけでなく、不安や落ち込みといった精神的な苦痛、仕事や経済的な問題といった社会的な苦痛に対しても、専門家チームが早期から介入し、支援を行います。国立がん研究センターの「がん情報サービス」によると、緩和ケアは、がん診療連携拠点病院などの専門外来や、緩和ケアチーム、一般病棟、そして在宅医療など、様々な形で受けることが可能です。1516 痛みや辛さを我慢する必要は全くありません。QOLを高く保つことは、治療を継続するための力にもなります。「緩和ケアについて詳しく知りたい」と、ぜひ主治医や看護師、がん相談支援センターに伝えてください。
ご自身の状況で緩和ケアをどのように活用できるか、担当の医療チームまたはお近くのがん相談支援センターにぜひご相談ください。
4.2. 未来への扉「がんゲノム医療」:知っておくべきこと
標準的な治療法が効かなくなった、あるいは終了してしまった場合でも、まだ希望が閉ざされたわけではありません。その次の一手として近年急速に発展しているのが「がんゲノム医療」です。
これは、患者さんのがん組織を用いて、がん細胞の増殖に関わる遺伝子の変化(変異)を一度に多数調べる「がん遺伝子パネル検査」を行い、その結果に基づいて最適な治療薬(主に分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬)を探し出す、いわば「個別化医療」の最先端です。1719
日本では、国立がん研究センターに設置された「がんゲノム情報管理センター(C-CAT)」が中心となり、全国のがんゲノム医療中核拠点病院・連携病院で、保険診療としてこの検査と治療を受けることができます。21 一般的には、標準治療が終了した(または終了が見込まれる)固形がんの患者さんなどが対象となります。この検査によって、自分のがんに特有の遺伝子変異が見つかれば、それに対応する薬剤の治験に参加できる可能性も開かれます。がんゲノム医療は、全ての人に効果的な治療が見つかるわけではありませんが、未来への新たな扉を開く可能性を秘めた重要な選択肢です。
ご自身ががん遺伝子パネル検査の対象となる可能性があるか、主治医にお尋ねください。
5. 未来への展望:日本の最新研究がもたらす希望
がんとの闘いは、絶え間ない研究開発の歴史です。そして日本は、その最前線で世界をリードする多くの研究成果を生み出しています。転移がんの治療成績は、これらの研究によって着実に向上しており、未来はさらに明るいものになると期待されています。
例えば、関西医科大学の小林久隆教授が開発した「光免疫療法」は、がん細胞にだけ結合する薬剤を投与した後、特殊な光を照射してがん細胞をピンポイントで破壊する、全く新しい原理の治療法です。13 これは「第5のがん治療法」とも呼ばれ、すでに一部のがんで承認され、応用範囲の拡大が期待されています。また、国際的な研究では、特定の遺伝子変異(マイクロサテライト不安定性-高、MSI-High)を持つ進行大腸がんにおいて、免疫チェックポイント阻害薬であるペムブロリズマブが著しい効果を示すことが、権威ある医学雑誌New England Journal of Medicineで報告されています。20
さらに、2025年2月には国立がん研究センターから画期的な発表がありました。これまで治療の大きな壁であった免疫療法の「耐性」(薬が効かなくなること)のメカニズムを解明し、その耐性を克服する可能性のある併用療法を発見したという報告です。8 このように、基礎研究の成果が、明日の新しい治療法へと繋がっていくのです。絶望する必要はありません。科学の進歩は、希望の光を灯し続けています。
結論:希望を胸に、納得のいく治療選択をするために
転移がんという診断は、あまりにも重い現実かもしれません。しかし、本稿で見てきたように、そこから先の道筋は決して一つではありません。予後というものは統計であり、個人の運命を決定づけるものではないこと。治療の選択肢は、日本の最高水準のガイドラインに基づき、科学的根拠を持って体系化されており、今この瞬間も進歩し続けていること。そして、治療そのものだけでなく、痛みや不安を和らげる緩和ケア、未来を拓くがんゲノム医療といった、あなたを支えるための包括的な医療システムが日本には存在すること。これらの知識が、暗闇を照らす一筋の光となることを願っています。最も大切なのは、正しい情報を力に変え、ご自身の医療チームと深く対話し、納得のいく治療を選択していくことです。この記事が、そのための第一歩となることを、JHO編集部一同、心から祈っています。
免責事項この記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言に代わるものではありません。健康上の懸念がある場合や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- がんの骨への転移と日常生活 – サバイバーシップ [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://survivorship.jp/bone-metastasis/about/index.html
- 転移性肝がん:肝臓の病気と治療 | 東京科学大学病院肝胆膵外科 [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.tmd.ac.jp/grad/msrg/liver/cancer03.html
- 大腸がんの余命や生存率は?ステージ別に解説 | がん遺伝子医療専門… [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.g-cg.jp/column/colon_3.html
- 全がん協部位別臨床病期別5年相対生存率. 全国がんセンター協議会 [インターネット]. [引用日: 2025年5月11日]. Available from: http://www.zengankyo.ncc.go.jp/etc/
- 癌が転移した場合の生存率は低いのでしょうか? | がん末期の治療相談はクリニックC4 [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://cccc-sc.jp/cancer/survival-rate.html
- ステージⅣ、および再発の“がん”とは? – 免疫療法コンシェルジュ [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://wellbeinglink.com/treatment-map/stage4/
- 末期がん(癌ステージ4)でもあきらめない先進治療と病院の選び方 [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.cancertx-negiup.com/
- 免疫チェックポイント阻害薬と自然免疫応答を活性化する薬剤との… 国立がん研究センター [インターネット]. 2025年2月14日 [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2025/0214/index.html
- 日本臨床腫瘍学会. 骨転移診療ガイドライン(改訂第2版). 南江堂, 2022. [Mindsガイドラインライブラリ]. Available from: https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00756/
- 日本肝胆膵外科学会. 転移性肝がん診療ガイドライン. 2021. [Mindsガイドラインライブラリ]. Available from: https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00673/
- 日本脳腫瘍学会, 日本脳神経外科学会. 転移性脳腫瘍診療ガイドライン (2024年版). [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: http://www.jsn-o.com/guideline2024/metabraintumor2024.html
- 【解説】骨転移診療ガイドライン改訂版に示された新たな診療方針 – HOKUTO [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://hokuto.app/post/vucpK8OYzzMBXXT5K7fR
- がんだけをピンポイントに壊す「第5の治療法」光免疫療法 – 先進医療.net [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.senshiniryo.net/column_a/39/index.html
- 緩和ケア – 厚生労働省 [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_kanwa.html
- 緩和ケア:[国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ] [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/relaxation/index.html
- 緩和ケア|地域がん診療連携拠点病院 – 日本赤十字社医療センター [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.med.jrc.or.jp/visit/cancer/palliativecare/tabid/786/Default.aspx
- がんゲノム医療 もっと詳しく:[国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ] [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/genomic_medicine/genmed02.html
- 日本肺癌学会. 肺癌診療ガイドライン -悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む- 2024年版 第8版. 金原出版. Available from: https://www.kanehara-shuppan.co.jp/books/detail.html?isbn=9784307204866&no=4&pc_mode_set=1
- がんゲノム医療とがん遺伝子パネル検査|国立がん研究センター が… [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://for-patients.c-cat.ncc.go.jp/
- Andre T, et al. Pembrolizumab in Microsatellite-Instability–High Advanced Colorectal Cancer. New England Journal of Medicine. 2020;383:2207-2218. doi:10.1056/NEJMoa2017699.
- 【地域別】がんゲノム医療を受けられる施設 [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://gan-genome.jp/hospital/facilities.html