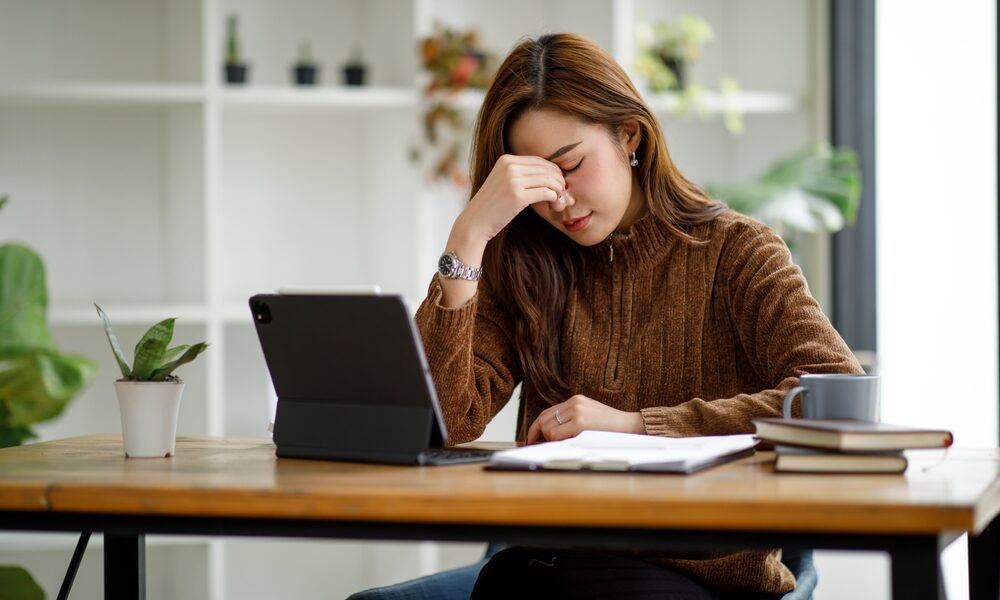この記事の科学的根拠
本記事は、提供された調査報告書に明示的に引用されている最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下に示すリストは、実際に参照された情報源と、提示された医学的指針への直接的な関連性を示したものです。
- 日本医師会: VDT症候群の症状、原因、およびその分類に関する指針は、日本医師会が公表した情報に基づいています328。
- 厚生労働省 (MHLW): 職場におけるVDT作業の労働衛生管理に関する具体的な基準(作業時間、作業環境、健康管理など)は、厚生労働省の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に準拠しています29。
- 米国検眼協会 (AOA): デジタル眼精疲労の定義、症状、および20-20-20ルールのような実践的な予防策に関する国際的な視点は、米国検眼協会の勧告を参考にしています17。
- 経済産業省 (METI): 眼精疲労対策を企業の戦略的投資と位置づける「健康経営」の概念および「健康経営優良法人」認定制度に関する記述は、経済産業省が主導する枠組みに基づいています4956。
- 各種学術論文 (PMC/PubMed掲載): デジタル画面の特性、瞬きの質の低下、ドライアイとの関連性、および各種対策の有効性に関する詳細な科学的知見は、査読済みの国際的な医学論文から得られたものです4514。
要点まとめ
- VDT症候群は単なる「疲れ目」とは異なり、目、筋骨格系、精神神経系にまで影響を及ぼす医学的な状態です。放置すると生産性の低下に直結します。
- 厚生労働省は、作業時間管理(1時間ごとに10~15分の休憩)、作業環境管理(照明やグレア対策)、健康管理(定期健康診断)などを含む詳細な予防ガイドラインを定めています。
- 個人レベルで実践できる「20-20-20ルール」や意識的な瞬き、適切な目薬の使用は即時的な効果が期待できますが、根本的な解決には企業の取り組みが不可欠です。
- ブルーライトカット眼鏡の有効性には科学的根拠が乏しく、学会も推奨していません。それよりも、ディスプレイの品質改善や人間工学に基づいた作業環境の整備が重要です。
- 眼精疲労対策は、経済産業省が推進する「健康経営優良法人」の認定基準に明記されており、従業員の健康を守ることは、企業のブランド価値と競争力を高める戦略的投資と位置づけられています。
デジタル眼精疲労の解決ガイド
夕方になると目の奥がズキズキ痛み、肩や首が石のように凝り固まってしまう。デスクワーク中心の現代において、多くの人が「ただの疲れ」と我慢していますが、それは身体が発している限界のサインかもしれません。デジタル機器との付き合い方を見直さなければ、その不調は慢性化し、仕事のパフォーマンスや日常生活の質を大きく下げる原因となります。
しかし、この現代病とも言えるVDT症候群は、適切な知識と環境調整によって十分に予防・改善が可能です。まずは目の健康全体を俯瞰し、眼の病気に関する包括的なガイドを参照することで、自分の症状が単なる疲れなのか、治療が必要な段階なのかを正しく理解することから始めましょう。
眼精疲労の根本的な解決には、なぜ目が疲れるのかというメカニズムを知ることが重要です。画面を見続けることによるピント調節機能の酷使や、姿勢の悪さが複合的に絡み合っています。目の疲れの根本原因と対策を深く理解し、自分の作業環境に潜むリスクを取り除くことが第一歩です。
次に、デジタル作業中に激減する「瞬き」への対策が不可欠です。瞬きが減ると涙が蒸発し、ドライアイが悪化することで眼精疲労が加速します。ドライアイの正しい対処法を実践し、目の表面を常に潤った状態に保つことが、長時間のデスクワークを乗り切るための鍵となります。
また、凝り固まった目の筋肉をほぐすアクティブなケアも取り入れましょう。「20-20-20ルール」などの休憩法に加え、効果的な目の体操と回復法を日常のルーチンに組み込むことで、疲労の蓄積を防ぎ、ピント調節機能を正常に保つことができます。
見落としがちなのが、眼鏡やコンタクトレンズの度数が作業距離に合っていないケースです。遠くがよく見える眼鏡でパソコン作業をすることは、目に過度な負担をかけ、頭痛の原因にもなります。眼鏡が引き起こす頭痛の原因を知り、デスクワーク専用の眼鏡を検討するなど、道具の最適化も忘れてはいけません。
デジタル機器はもはや手放せませんが、それに振り回されて健康を害する必要はありません。環境を整え、正しいケアを習慣化することで、快適な視界と高いパフォーマンスを維持することは可能です。今日からできる小さな変化で、あなたの大切な目を守り抜きましょう。
VDT症候群の深刻な実態:単なる「疲れ目」ではない医学的課題
VDT症候群の深刻さを正しく理解するためには、日常的に使われる言葉と医学的な定義を区別し、この症候群が持つ多面的な性質を把握することが不可欠です。
「疲れ目」と「眼精疲労」の決定的な違い
日常生活において、「疲れ目(つかれめ)」と「眼精疲労(がんせいひろう)」は混同されがちですが、医学的には明確な違いがあります。「疲れ目」は、目を酷使した後に起こる一時的な生理的状態で、十分な睡眠や休息によって完全に回復します1。一方、「眼精疲労」すなわちVDT症候群は、休息や睡眠をとっても目の痛み、かすみ、頭痛といった症状が回復せず、持続的または反復的に現れる病的な状態を指します1。この違いを強調することは、VDT症候群が単なる不快感ではなく、真剣な対策を必要とする健康問題であることを伝える上で極めて重要です。
VDT症候群がもたらす三つの側面からの影響
VDT症候群は目に限定される問題ではなく、労働者の心身全体に影響を及ぼします。医学的な研究では、その症状が主に三つのカテゴリーに分類されています3。
- 眼症状: 最も一般的で認識しやすい症状群です。ドライアイ、目の奥の痛み、充血、目のかすみ、一時的な視力低下、異物感などが含まれます3。
- 筋骨格症状: コンピューター作業中に長時間同じ姿勢を保つことで、首や肩、背中のこりや痛み、腕のだるさ、さらには不適切なキーボード操作による指のしびれといった症状が現れます2。これは反復性緊張損傷(Repetitive Strain Injury)の一種と見なすことができます。
- 精神・神経症状: 絶え間ない集中と視覚的ストレスは神経系にも影響を及ぼし、緊張型頭痛、めまい、原因不明のいらいら感や不安感、食欲不振、睡眠障害などを引き起こします。重症化すると抑うつ状態に至ることもあり、これは脳の持続的なストレスが自律神経のバランスを乱すことによって生じます38。
| 症状の分類 | 具体的な症状 | 概要 |
|---|---|---|
| 眼症状 | ドライアイ、眼精疲労、目の痛み、充血、かすみ目、光への過敏、異物感 | 目の酷使と乾燥により、眼球表面および調節機能に直接関連する症状3。 |
| 筋骨格症状 | 首のこり、肩の痛み、背中の痛み、腰のだるさ、腕の痛み、指のしびれ | 不適切な座位姿勢と持続的な筋肉の緊張から生じる症状2。 |
| 精神・神経症状 | 頭痛、めまい、いらいら、不安感、食欲不振、睡眠障害、抑うつ状態 | 高度な集中と持続的なストレスによる脳の緊張と自律神経の乱れから生じる症状3。 |
症状の背後にある生理学的メカニズム
効果的な予防策を講じるためには、症状の背後にある生物学的な仕組みを理解する必要があります。
- 毛様体筋の過負荷: 人間の目は自然な状態では遠くを見るようにできています。コンピューター画面のような近くの物体を見るとき、水晶体を厚くして網膜にピントを合わせるために毛様体筋が収縮します。この収縮状態を長時間維持することは、筋肉を絶えず緊張させることになり、疲労、痛み、調節機能の低下を引き起こします9。
- 瞬きの質と量の低下: 通常、人は1分間に15~20回ほど瞬きをして涙液層を均一に広げ、目の表面を潤滑に保ちます。しかし、画面に集中すると、その回数は半分以下にまで減少することがあります3。さらに、その瞬きも不完全(まぶたが完全に閉じない)になりがちで、涙の蒸発を防ぐ油層が適切に供給されず、ドライアイを引き起こします6。
- デジタル画面特有の視覚的ストレス: 紙の上の文字とは異なり、画面上の文字はピクセルで構成されているため、輪郭が不鮮明で背景とのコントラストも低くなりがちです。これにより、視覚系はピントを合わせ続けるためにより多くの努力を強いられます4。また、周囲の照明からのグレア(まぶしさ)や画面への映り込みも「視覚的ノイズ」となり、目の負担を増大させます16。
無視できない国家的負担:罹患率と経済的コスト
この問題は個人の健康だけでなく、企業と社会全体に甚大な経済的負担をもたらしています。厚生労働省の調査では、2004年の時点で既にコンピューターを使用する労働者の78%が身体的な疲労を感じ、そのうち91.6%が「目の疲れや痛み」を訴えていました19。より最近の2023年の調査では、過去1ヶ月間に目の疲れを感じた人は69%に上り、特に50代では76%に達するなど、問題は悪化の一途をたどっています21。
最大の経済的損失は「プレゼンティーズム」と呼ばれる、出勤はしているものの健康問題により生産性が完全に発揮できない状態によってもたらされます22。ある調査では、IT系のオフィスワーカーの93%が目の不調による業務効率の低下を認めています24。Diamond Onlineの分析によれば、この生産性低下による日本の経済損失は年間最大で26兆円にも上ると試算されており25、VDT症候群が個人の健康問題から国家レベルの経済課題へと移行していることを示しています。
厚生労働省が示す公式予防ロードマップ:VDTガイドラインの徹底解剖
深刻化する状況に対応するため、厚生労働省は「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を策定し、企業が従業員の健康を守るための包括的な枠組みを提供しています29。この章では、ガイドラインの要点を解説し、現代の職場環境で実践可能な行動計画へと落とし込みます。
MHLW VDTガイドラインの四つの柱
ガイドラインは、労働者の心身の負担を軽減するため、主に四つの管理領域における具体的な措置を求めています。
- 作業時間管理: 連続作業が疲労の根源であるため、最も重要な対策の一つです。
- 作業環境管理: 物理的な環境は目のストレスに直接影響します。
- VDT機器、椅子、机等の管理: 機器の配置が作業姿勢を決定します。
- 健康管理: 労働者の健康を能動的に維持するための措置です。
ガイドラインの現代的適用:新しい働き方への挑戦
MHLWのガイドラインは包括的ですが、技術や働き方が変化した現代の文脈に合わせて柔軟に解釈・適用する必要があります。特に、ガイドラインの改訂により、対象は従来の「VDT」からノートパソコンやスマートフォンを含む全ての「情報機器」へと拡大されました36。これにより、企業は画一的なルールに従うのではなく、個々の作業状況に応じたリスク評価に基づく対策が求められます。また、テレワークの普及は、オフィス向けに設計された人間工学の原則を家庭の作業環境に適用するという新たな課題を生み出しており、企業には従業員が安全な在宅ワークスペースを構築できるよう、指導や財政的支援を行う責任が生じています34。
包括的アクションプラン:個人の自己防衛術から企業の文化醸成まで
デジタル眼精疲労の克服は、従業員と企業の双方による共同の取り組みを必要とします。この章では、双方の責任を明確にし、具体的な行動計画を提示します。
従業員自身ができる自己防衛ツールキット
従業員は、自身の健康を守る第一線の防御者です。以下の習慣を身につけることが極めて重要です。
- 20-20-20ルール: 国際的な眼科組織が推奨するシンプルで効果的な方法です。20分画面を見たら、20フィート(約6メートル)先を20秒間眺めることで、毛様体筋の緊張をリセットします17。
- 意識的な瞬き: 集中すると瞬きの回数が減るため、意識的に頻繁に、そして深く(上下のまぶたが完全に閉じるように)瞬きをすることが、ドライアイ予防の鍵となります13。
- 温罨法(おんあんぽう)と冷罨法(れいあんぽう): 疲労を感じた際は、温かい蒸しタオルで目を温めると筋肉がリラックスし、涙の油層の質が改善します13。目が充血している場合は、冷たいタオルで冷やすと血管が収縮し、赤みが和らぎます40。
- ライフスタイルの見直し: ビタミンA、B、Cやルテインなど、目に良い栄養素を豊富に含むバランスの取れた食事40、質の高い睡眠13、そして血行を促進する定期的な運動11が、内側から目の健康を支えます。
補助ツールの批判的吟味
市場には多くの対策グッズが存在しますが、その効果は玉石混交です。
- ブルーライトカット眼鏡: 非常に人気がありますが、その有効性を示す質の高い科学的根拠は乏しいのが現状です。日本眼科学会を含む国内外の主要な眼科関連団体は、デジタル眼精疲労の予防・軽減効果は証明されておらず、特に子供への装用は推奨しないとの見解を示しています1243。
- 目薬: ドライアイなどの症状緩和に有効なツールです。頻繁に使用する場合は防腐剤無添加のものを選び、角膜の修復を助けるビタミンA配合の製品は、コンピューター使用者にとって特に推奨されます9。日本では「サンテメディカル12」や「スマイル40プレミアムDX」などが市販されています45。
- コンタクトレンズと眼鏡: 不適切な度数は眼精疲労の一般的な原因です。コンピューター作業用の距離(通常40~70cm)に最適化された度数調整が重要であり、定期的な視力検査が不可欠です9。
雇用主の責任:目に優しい職場環境の構築
個人の努力を持続可能にするためには、企業が制度的・物理的な環境を整える責任があります。
- 人間工学への投資: ちらつきのない(フリッカーフリー)高品質な非光沢ディスプレイ16、昇降式デスク、体格に合わせて細かく調整可能な椅子への投資は、全ての従業員の正しい姿勢を支える最も効果的な手段の一つです16。ノートパソコン使用者には、外付けのキーボード、マウス、そして画面の高さを調整するためのスタンドを支給することが必須です48。
- 方針と文化の徹底: 従業員の自己管理に頼るのではなく、PCに休憩を促すリマインダーアプリを導入したり16、管理職が率先して休憩を奨励したりすることで、休息が生産性のために必要であるという文化を醸成します。
- 教育と環境改善: 定期的に専門家を招いてVDTに関する研修会を実施し42、照度計などを用いて職場環境がMHLWの基準を満たしているか定期的に評価・改善します34。
戦略的必須事項としての眼の健康:「健康経営」の柱とROI
デジタル眼精疲労への対策は、単なる福利厚生や安全配慮義務の遵守に留まりません。それは、企業の競争力を左右する戦略的な経営課題です。特に、日本が国策として推進する「健康経営」の文脈において、従業員の視覚的健康への投資は、測定可能なリターンをもたらす賢明な事業活動となります。
「健康経営」とは何か?
経済産業省が定義する「健康経営」とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです49。従業員の健康を単なるコストではなく、将来の収益を生み出す「投資」と捉え、健康増進を通じて組織全体の活性化と生産性向上、ひいては企業価値の向上を目指す経営手法です51。眼精疲労は、オフィスにおけるプレゼンティーズムやその他の体調不良(肩こり、腰痛、頭痛)の主要因であるため37、この問題に積極的に取り組むことは、健康経営の中核的な実践と言えます。
「健康経営優良法人」認定への道筋
「健康経営優良法人」認定制度は、経済産業省と日本健康会議が共同で、優れた健康経営を実践する企業を顕彰する制度です56。この認定は企業のブランドイメージを向上させ、人材獲得や金融機関からの融資において有利に働くことがあります56。
決定的に重要なのは、2024年度の認定基準における変更点です。この年の改訂で、社会的課題への対応に関する項目が新設され、その中で「眼精疲労」が花粉症などと並んで、企業が取り組むべき具体的な健康課題として名指しされました55。この変更により、眼精疲労対策は「任意」の福利厚生から、企業の経営戦略を評価する上での公式な重要業績評価指標(KPI)へと格上げされたのです。
| 健康経営優良法人の評価項目 | 対応する眼精疲労対策アクション | 調査票における報告・証明方法 |
|---|---|---|
| 1. 経営理念・方針 | 経営トップがVDT症候群を含む職業性疾病への取り組みを宣言する。 | 社内外のウェブサイトへの宣言掲載、年次報告書への記載。 |
| 2. 組織体制 | VDT対策の責任者を任命し、産業医や眼科医と連携する。 | 役割を明記した組織図、専門家との会議議事録。 |
| 3. 制度・施策実行 | VDT研修の実施、人間工学に基づいた備品の提供、ストレッチ体操の導入。 | 研修の資料や写真、備品購入の請求書、体操の実施風景。 |
| 4. 評価・改善 | 年次の健康調査に眼精疲労に関する質問を導入し、健診データを分析する。 | ストレスチェックやアンケートの結果報告、健康データの傾向分析(匿名化)。 |
| 5. 法令遵守・リスクマネジメント | MHLWのVDTガイドラインを遵守し、「眼精疲労」の新基準に対応する。 | ガイドライン遵守のチェックリスト、調査票への具体的な取り組み内容の記述。 |
投資対効果(ROI)の測定
経営層を説得するためには、投資対効果(ROI)の証明が不可欠です。WHOが開発したHPQ(Health and Work Performance Questionnaire)のような科学的に検証された調査ツールを用いて、対策導入前後のプレゼンティーズムによる生産性損失率を測定します。この損失率と平均賃金から経済的損失額を算出し、その削減分を投資のリターンとして提示することができます60。
「新しい椅子とモニターの購入」という予算要求は却下されるかもしれません。しかし、「『健康経営優良法人2025』認定を取得し、ブランド価値と採用競争力を高めるために必須の施策」という予算要求は、説得力のある戦略的ビジネス提案となります。この認定制度は、企業の内部的な停滞を乗り越え、重要なインフラと文化の変革を推進するために必要な正当性と予算的裏付けを提供します。
よくある質問
ブルーライトカット眼鏡は本当に効果がありますか?
在宅勤務(テレワーク)でも会社のVDT対策は適用されますか?
はい、適用されます。労働安全衛生法に基づく企業の安全配慮義務は、従業員が働く場所がオフィスか自宅かにかかわらず発生します。厚生労働省のガイドラインも、テレワーク環境における情報機器作業を対象としています34。企業は、従業員が自宅で安全かつ人間工学的に適切な作業環境を構築できるよう、具体的なガイドラインを提供し、必要に応じて椅子やモニター、その他の備品の購入を補助するなどの支援を行うことが望まれます。
どのような目薬を選べば良いですか?
目薬は症状緩和に有効な手段です。主にドライアイ(目の乾き)の症状を和らげるためには、人工涙液タイプのものが基本となります。頻繁に使用する場合は、角膜への影響を考慮して防腐剤が含まれていない製品を選ぶことが推奨されます。また、長時間のコンピューター作業で傷つきがちな角膜の修復を助けるビタミンA(レチノールパルミチン酸エステル)や、ピント調節機能の改善を助けるビタミンB12(シアノコバラミン)などが配合された製品も有効な選択肢です9。ただし、症状が続く場合は自己判断に頼らず、眼科医に相談することが重要です。
会社の健康経営認定と、私の目の疲れに何の関係があるのですか?
大きな関係があります。2024年度から、「健康経営優良法人」の認定基準に、企業が取り組むべき健康課題として「眼精疲労」が具体的に明記されました55。これは、国が眼精疲労対策を企業の重要な経営課題として公式に認めたことを意味します。あなたの会社がこの認定を目指している場合、従業員の目の疲れを軽減するための施策(例:高品質モニターの導入、休憩の奨励、研修の実施など)を導入することは、認定を取得するための必須要件の一つとなります。つまり、あなたの目の健康を守ることは、会社の経営目標達成に直接貢献することになるのです。
結論
本稿は、デジタル眼精疲労(VDT症候群)が、日本の労働力と経済に静かかつ広範な影響を及ぼす医学的課題であることを体系的に分析しました。これはデジタルトランスフォーメーション時代の避けられない代償ではなく、従業員個人と企業組織の双方による協調的な戦略を通じて管理・解決可能な挑戦です。
主要な結論として、VDT症候群は単なる不快感ではなく、プレゼンティーズムを通じて甚大な経済的損失を生む複雑な医学的症候群であること、政府(MHLW)は明確な予防ロードマップを提供しているものの現場での遵守には乖離があること、そして最も効果的な解決策は、科学的根拠に乏しいハイテク製品よりも、20-20-20ルールのような単純な行動変容や人間工学に基づいた環境介入であることが明らかになりました。特に重要なのは、眼精疲労対策が「健康経営優良法人」認定の公式な評価項目となり、企業の持続的成長のための戦略的必須事項へと昇格したという事実です。
最終的に、従業員の目の健康へ積極的に投資することは、単なる福利厚生の提供を超えた意味を持ちます。それは、持続可能な生産性を構築し、従業員のエンゲージメントとロイヤルティを高め、デジタル化が進む日本経済における企業の長期的な成功を確実にするための、不可欠な要素です。本稿で提案された行動計画を適用することで、企業はリスクとコストを最小限に抑えるだけでなく、トップクラスの雇用主としての地位を固める機会を掴むことができるでしょう。従業員の「視界」に投資することは、まさしく企業自身の未来の「ビジョン」に投資することに他なりません。
免責事項本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言に代わるものではありません。健康に関する懸念や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- VDT症候群とは? 症状、原因、予防法を解説 | アキュビュー® 【公式】. Acuvue. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.acuvue.com/ja-jp/memamori/eye-health/080/
- Munshi S, Varghese A, Dhar-Munshi S. Computer vision syndrome—A common cause of unexplained visual symptoms in the modern era. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.aoa.org/assets/documents/ebo/adult%20eye/415.12munshi.pdf
- 健康の森/VDT症候群. 日本医師会. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.med.or.jp/forest/check/vdt/02.html
- Al-Mohtaseb Z, Schachter S, Shen Lee B, Garlich J, Trattler W. Digital Eye Strain- A Comprehensive Review. Ophthalmol Ther. 2021;10(3 Suppl 1):1-13. doi:10.6084/m9.figshare.14755110. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9434525/
- Coles-Brennan C, Sulley A, Young G. Digital eye strain: prevalence, measurement and amelioration. BMJ Open Ophthalmol. 2019;3(1):e000146. doi:10.1136/bmjophth-2018-000146. Available from: https://bmjophth.bmj.com/content/3/1/e000146
- Computer Vision Syndrome (Digital Eye Strain). EyeWiki. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://eyewiki.org/Computer_Vision_Syndrome_(Digital_Eye_Strain)
- VDT症候群の特徴や症状、治療法について解説! ファストドクター. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://fastdoctor.jp/columns/vdt-syndrome2
- VDT症候群. HOYA株式会社. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.hoya.com/eye/vdt/
- VDT症候群とは?PC・スマホの見過ぎによる心身不調の原因やケア… ライオン株式会社. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://smile.lion.co.jp/column/eye_strain/article03.htm
- スマホなどが引き起こす視力低下対策術. 石坂整形外科クリニック. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://ishizaka-seikei.jp/news/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%8C%E5%BC%95%E3%81%8D%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%99%E8%A6%96%E5%8A%9B%E4%BD%8E%E4%B8%8B%E5%AF%BE%E7%AD%96%E8%A1%93/
- スマホ近視・スマホ老眼の治療・対処法. 恵比寿くぼの眼科. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.ebisu-ganka.com/smartphone/
- ブルーライトとデジタル眼精疲労. たける眼科. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://takeru-eye.com/blog/12082019-bluelight-and-digitaleyestrain/
- スマホの疲れ目を解消したい!疲労の原因と簡単なケア方法. ライオン株式会社. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://smile.lion.co.jp/column/eye_strain/article02.htm
- A S, B S, A C. Computer vision syndrome: a comprehensive literature review. J Ophthalmol Exp Ther. 2024;7(1):11901492. doi:10.37191/maple/jovet.2024.11901492. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11901492/
- Computer vision syndrome: a comprehensive literature review. ResearchGate. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/389678119_Computer_vision_syndrome_a_comprehensive_literature_review
- 【保存版】ディスプレイの疲れ目対策”10選”. EIZO株式会社. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia08/
- Computer vision syndrome. American Optometric Association. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.aoa.org/healthy-eyes/eye-and-vision-conditions/computer-vision-syndrome
- 20~30代でも要注意!「スマホ老眼」はどうすれば改善する?|スマイル. ライオン株式会社. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://smile.lion.co.jp/column/eye_strain/article05.htm
- パソコン作業時の眼精疲労軽減に関する調査実施報告. EIZO株式会社. 2008. Available from: https://www.eizo.co.jp/company/news/2008/files/NR08-013.pdf
- White Paper. EIZO株式会社. 2008. Available from: https://www.eizo.co.jp/products/tech/files/2008/WP08-001.pdf
- 目に関する調査(2023年). 株式会社クロス・マーケティング. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.cross-m.co.jp/report/20231207eye
- 健康経営における損失額とは?プレゼンティーズムで行う健康経営の見える化. GO100. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://go100.jp/column/visualizing-health-management-with-presenteeism/
- 職場における「眼精疲労(目の疲れ)」の予防・対策. OFFICE CARE. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://xn—-1n7a37cg2br21aiw5aerg.com/%E8%81%B7%E5%A0%B4%E3%81%AE%E7%9C%BC%E7%B2%BE%E7%96%B2%E5%8A%B4-%E7%9B%AE%E3%81%AE%E7%96%B2%E3%82%8C%EF%BD%B0%E4%BA%88%E9%98%B2%E5%AF%BE%E7%AD%96
- “IT女子”の目の悩みに関する調査. 株式会社リサ・クリエイティブ・プロダクツ. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.lisalisa50.com/research20150810_14.html
- ビジネスパーソンの蓄積した目の疲労による日本の経済損失は莫大な額に!. Diamond Online. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://diamond.jp/articles/-/145248
- ドライアイによる眼精疲労. 公益社団法人 日本眼科医会. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.gankaikai.or.jp/press/detail2/__icsFiles/afieldfile/2022/06/06/20220606_2.pdf
- 眼精疲労による年間3.5日分の作業ロスを無くす方法を紹介します!. AIG損害保険株式会社. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.aig.co.jp/kokokarakaeru/management/injury-sick/eyehirou01
- 健康の森/VDT症候群. 日本医師会. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.med.or.jp/forest/check/vdt/03.html
- VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて. 厚生労働省. 2019. Available from: https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000188451.pdf
- 「VDT症候群」とは?. 『日本の人事部』. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://jinjibu.jp/keyword/detl/647/
- VDT症候群とは?おもな症状・原因・対策・予防方法を紹介. アスクル. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.askul.co.jp/f/special/product_column/vdt/
- 1. VDT 症候群とは? 2. VDT 作業における労働衛生管理のためのガイドライン. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.kenkomie.or.jp/file/newsletter/k_201903.pdf
- VDT症候群とは?症状や治療法、予防法について解説. Sanpo Navi. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://sanpo-navi.jp/column/vdt-syndrome-prevention/
- 情報機器(VDT)作業における職場での予防・対策. OFFICE CARE. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://xn—-1n7a37cg2br21aiw5aerg.com/vdt-yobou-taisaku
- パソコン作業での疲れ目対策6選. 株式会社ドテヤマビジネス. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.doteyamab.jp/blog/140
- VDTガイドラインを17年ぶりに改正/ 情報機器作業の安全衛生はリスクアセスメントで. 公益社団法人神奈川労務安全衛生協会. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://koshc.jp/archives/2097
- NTN 健康経営レポート. NTN株式会社. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.ntn.co.jp/japan/csr/pdf/ntn_health_report.pdf
- Sheppard AL, Wolffsohn JS. Digital eye strain: prevalence, measurement and amelioration. BMJ Open Ophthalmol. 2018;3(1):e000146. doi:10.1136/bmjophth-2018-000146. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6020759/
- 眼精疲労対策(20-20-20ルール). 古川中央眼科. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.eye-care.or.jp/sittoku/%E7%9C%BC%E7%B2%BE%E7%96%B2%E5%8A%B4%E5%AF%BE%E7%AD%96%EF%BC%8820-20-20%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%89/
- 在宅時間とデスクワークの増加で目の疲れが蓄積!解消と予防のすすめ. Adecco Group. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.adecco.co.jp/useful/work_39
- スマホ老眼時の対処法. メガネスーパー. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.meganesuper.co.jp/content/sumaho-rougan3/
- パソコン作業に要注意!栄養と生活習慣で目の健康を守るコツ. サンポチャート. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://sampo-chart.com/essential-tips-desk-workers-protect-eye-health-nutrition-lifestyle/1849/
- Lawrenson JG, Hull CC, Downie LE. The effect of blue-light blocking spectacle lenses on visual performance, macular health and the sleep-wake cycle: a systematic review of the literature. Ophthalmic Physiol Opt. 2017;37(6):644-654. doi:10.1111/opo.12406. Available from: PMID: 40055942
- García-Ayuso D, Di Pierdomenico J, Valiente-Soriano FJ, et al. Digital eye strain in young screen users: A systematic review. Ophthalmol Ther. 2023;12(3):1413-1435. doi:10.1007/s40123-023-00688-2. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36977430/
- 【薬剤師が解説】眼精疲労目薬売れ筋ランキング15選!長時間のPC作業やゲームでの疲れ目に. くすりの窓口. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.kusurinomadoguchi.com/column/articles/eyestrain-eye-drops-ranking
- 疲れ目を解消!目をいたわる対策とセルフケア. 花王 MyKao. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://my.kao-kirei.com/kurashi-labo/health-beauty/healthcare/048/
- 眼精疲労を有する若年 visual display terminal(VDT)作業者に対する 屈折適正矯正による調節反応と. 日本眼科学会. Available from: https://www.nichigan.or.jp/Portals/0/JJOS_PDF/112_376.pdf
- 【人事・労務向け】VDT症候群とは?【原因と対策を徹底解説】. ポケットセラピスト. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://pocket-therapist.jp/articles/vdt-syndrome/
- 健康経営とは? メリットや企業の取り組み事例を解説. NECソリューションイノベータ. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sp/contents/column/20221209_healthmanagement.html
- 健康経営はなぜ必要?企業が取り組む理由やメリット・デメリットを解説. 心幸グループ. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.shinko-jp.com/column/kenkokeiei_why/
- 健康経営とは?事例やメリット、認定制度を分かりやすく解説|Fem+コラム. Femtech Tokyo. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.femtech-week.jp/hub/ja-jp/blog/article_03.html
- 健康経営とは?意味とメリット、やり方・取り組み例を初心者向け… d’s JOURNAL. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://hr.ds-b.jp/what-is-healthy-company/
- 健康経営で今、もっとも求められているのが VDT作業による目の健康管理!. 視力ケアセンター. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://shiryoku-care.com/healthmanagement/
- 令和5年度 健康経営度調査票 改訂点の背景を知ろうシリーズ⑥ ~生産性低下防止のための取組. Finc for BUSINESS. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://biz.finc.com/blog/22
- 2025年度の健康経営優良法人認定を目指しましょう!申請フロー徹底解説. ワーカーズドクターズ. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.workersdoctors.co.jp/column/knowledge/healthmanagement-certification/
- 健康経営優良法人認定制度. 経済産業省. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
- 「健康経営優良法人2025」認定法人が決定しました. 経済産業省. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250310005/20250310005.html
- 健康経営優良法人とは?メリットや認定基準、取得に活かせる運用のヒントを紹介. OBC360°. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://www.obc.co.jp/360/list/post188
- 健康経営優良法人とは? メリット・認定基準・申請方法をわかりやすく解説. d’s JOURNAL. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://hr.ds-b.jp/kenkoukeiei-yuryouhouzin/
- プレゼンティーズムの損失額は甚大!測定指標と具体的な対策を解説. KIWI GO. [引用日: 2025年7月25日]. Available from: https://kiwi-go.jp/column/presentism-loss/