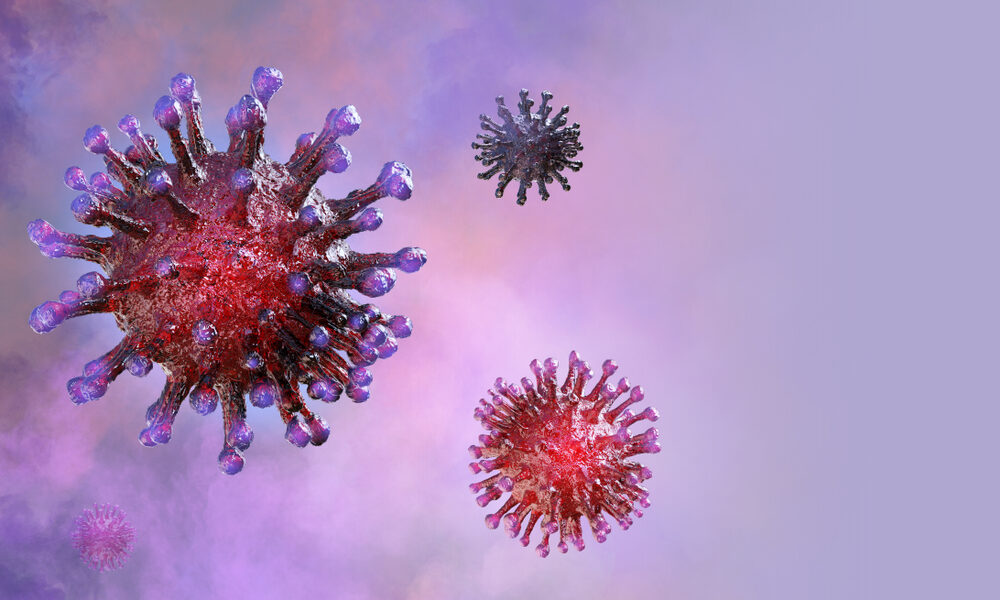本記事の科学的根拠
本記事は、入力された研究報告書に明示的に引用されている、最高品質の医学的証拠にのみ基づいています。以下のリストには、実際に参照された情報源と、提示された医学的指針への直接的な関連性のみが含まれています。
- 世界保健機関(WHO)、米国疾病予防管理センター(CDC): エボラウイルス病、マールブルグ病、狂犬病、デング熱など、世界的な感染症に関する定義、疫学データ、および公衆衛生上の勧告についての記述は、これらの国際的な保健機関が公表したファクトシートやガイドラインに基づいています。7823
- 日本国厚生労働省(MHLW)、国立感染症研究所(NIID): 日本の感染症法に基づく分類、国内でのSFTSや日本脳炎の発生状況、水際対策、および各種疾患に対する公式な診療の手引きに関する情報は、これらの国内規制・研究機関の公式発表および統計データに準拠しています。103536
- 査読付き学術雑誌(例:The Lancet, PubMed Central): ウイルスの病態生理学(サイトカインストームのメカニズムなど)や、治療法・ワクチン開発の最前線に関する専門的な記述は、信頼性の高い査読付き学術論文で発表された研究成果を典拠としています。1920
要点まとめ
- ウイルスの「危険性」は、致死率(個人への脅威)とパンデミックの潜在能力(社会への脅威)という二つの異なる軸で科学的に評価されるべきであり、単純なランキングは誤解を招きます。
- 日本の「感染症法」は、ウイルスの危険度に応じて一類から五類などに分類し、入院勧告や水際対策といった具体的な公衆衛生措置を決定する、私たちの安全を守るための法的基盤です。
- マダニが媒介するSFTS(重症熱性血小板減少症候群)は、日本国内で発生し、致死率が約27-30%と非常に高く、ペットからの感染リスクも報告されている、特に注意すべき脅威です。
- 狂犬病や日本脳炎のように、かつては深刻な脅威であった病気も、予防接種の普及と徹底した公衆衛生対策によって効果的に抑制されており、予防医学の重要性を示しています。
- 全ての情報は、世界保健機関(WHO)、日本の厚生労働省、国立感染症研究所(NIID)などの権威ある機関のデータに基づいており、正確性と信頼性を最優先しています。
ウイルス危険性と正しい理解
「どのウイルスが一番恐ろしいのか」「ニュースで見る致死率の数字はどこまで本当なのか」と不安になったり、扇情的なランキング記事を読んでかえって怖くなってしまった方も多いかもしれません。特にエボラや狂犬病、SFTSといった名前を目にすると、「もし自分や家族がかかったら…」と想像して眠れなくなることもありますよね。本記事が示しているように、ウイルスの危険性は単に「怖そう」「致死率が高そう」といった印象だけで判断すると、かえって大事なポイントを見落としてしまいます。この不安を少しずつほどきながら、「何をどう怖がればよいのか」を冷静に整理していきましょう。
まず大切なのは、「致死率(CFR)」と「どれだけ広がりやすいか」という二つの軸でウイルスの危険性を考えるという、本記事の基本的な考え方をしっかり押さえることです。狂犬病のように発症後の致死率がほぼ100%でも、日本のようにワクチンと検疫が徹底していれば、日常生活のリスクは大きく下げられます。一方、インフルエンザやSARS-CoV-2のように致死率はそれほど高くなくても、広がりやすさゆえに社会全体への影響は非常に大きくなり得ます。こうした「危険性のパラドックス」を、日本の感染症法の分類や具体的な対策とともに体系的に整理しているのが、感染症 完全ガイドです。
次に、「なぜこのウイルスは危険なのか」という原因を、感情ではなく仕組みから理解していきましょう。本記事では、エボラやマールブルグのような出血熱ウイルスが、免疫細胞を攻撃してサイトカインストームを引き起こし、結果として多臓器不全に至るプロセスを丁寧に解説しています。また、狂犬病のように神経を侵してほぼ必ず致死的になるウイルスと、デング熱や日本脳炎のように蚊が媒介するウイルス、SFTSのようにマダニやペットを介して感染するウイルスとでは、危険性の「質」が異なることも重要なポイントです。こうした病態や感染経路の違いを踏まえて、自分や家族がどのタイプのウイルスと向き合う可能性が高いのかを整理する時にも、感染症ごとの症状・検査・治療を俯瞰できる総合ガイドが役立ちます。
具体的な対策の第一歩として、本記事が紹介している日本の感染症法の分類を、もう一度自分の生活に引き寄せて確認してみましょう。一類感染症として位置づけられるエボラやラッサ熱などは、日本国内では「水際」で厳重に管理されている一方、四類感染症に含まれるSFTS、デング熱、日本脳炎などは、国内で実際に患者が発生していることが強調されています。自分が住んでいる地域や、今後旅行・出張で訪れる地域で、どの感染症のリスクが高いのかを知ることが、賢い怖がり方の第一歩です。分類ごとの特徴や、公衆衛生上どのような措置がとられるのかをより詳しく確認したい場合は、感染症法に基づく感染症分類と対策を整理した総合ページをじっくり読むと全体像が見えてきます。
第二のステップとして、「自分が今すぐできる現実的な備え」に視点を移しましょう。本記事が示すように、SFTSは日本国内で致死率が高く、マダニやペットを介した感染が問題になっている一方で、デング熱や日本脳炎は蚊対策やワクチンによってリスクを大きく下げられます。つまり、ニュースで取り上げられる派手なウイルスだけでなく、「自分の生活圏で現実に起こりうるウイルス」に対して、どのような予防策やワクチンが利用できるのかを知ることが、最も実務的な対策になります。こうした身近なウイルスごとの予防・ワクチン・治療の選択肢については、各感染症のリスクと予防策を整理したガイドを併せて確認しておくと安心です。
同時に、インターネット上の「致死率ランキング」や印象的な体験談だけで危険性を判断しないことも大切です。本記事が強調しているように、致死率は医療体制や発見の早さによって大きく変動し、日本のようにワクチンや診療体制が整った国と、そうでない地域では同じウイルスでもリスクの意味が違ってきます。また、ニパウイルスのように、現時点ではワクチンが実用化されていなくても、国際的な研究が進んでいる疾患も少なくありません。こうした最新情報や日本の公衆衛生体制の現状を、感情ではなく事実に基づいて確認したいときには、信頼できる医学情報を集約した感染症の総合解説を基準にすることで、誤情報に振り回されにくくなります。
ウイルスの世界は複雑で、致死率や専門用語だけを見ていると、どうしても「何もかもが怖い」と感じてしまいがちです。しかし、本記事が示しているように、致死率と広がりやすさ、日本の法的分類と公衆衛生体制という軸でもう一度整理し直すと、「どのウイルスをどの程度怖がり、何に備えるべきか」が少しずつ見えてきます。まずは今日から、感情的なランキングではなく、科学的な指標と日本の制度に基づいてウイルスの危険性を理解するという姿勢を持ってみてください。そのうえで、自分や家族の生活にとって現実的なリスクが高い感染症から順番に、落ち着いて情報を確認し、一歩ずつ備えを進めていきましょう。
「ウイルスの危険性」を科学的に定義する
「最も恐ろしいウイルス」という言葉は、人々の感情に訴えかけますが、科学的な議論の出発点としては不適切です。公衆衛生学の観点からウイルスの危険性を評価するためには、客観的な指標に基づいた枠組みが必要です。本稿では、主観的な「恐怖」ではなく、二つの重要な科学的指標を用いてウイルスの脅威を分析します。
致死率(Case Fatality Rate – CFR):個人に対する脅威
致死率(CFR)とは、特定の病気と診断された人々のうち、その病気が原因で死亡した人の割合を示す指標です1。これは、ウイルスに感染した場合の個人の生命に対する直接的な危険度を測るものです。例えば、狂犬病ウイルスは、一度臨床症状が現れると致死率がほぼ100%に達し、既知の感染症の中で最も致死率が高い病気として知られています34。
パンデミックの潜在能力:社会全体への脅威
一方、社会全体に対する脅威は、ウイルスの伝播能力によって決まります。これには、感染経路(空気感染か、接触感染か)、無症状期間中の感染力、そしてワクチンや治療薬といった有効な対抗策の有無などが含まれます。インフルエンザウイルスやSARS-CoV-2は、致死率自体は狂犬病ほど高くありませんが、呼吸器を介して容易に人から人へ伝播する能力を持つため、世界的な大流行(パンデミック)を引き起こし、数百万もの命を奪いました3。
危険性のパラドックス
この二つの指標は、「危険性のパラドックス」として知られる現象を生み出します。個人にとっては極めて致死的(高いCFR)なウイルスでも、伝播しにくければ世界的な公衆衛生上の脅威にはなりにくいのです。逆に、比較的CFRが低いウイルスでも、伝播能力が高ければ、より大規模な災害を引き起こす可能性があります。例えば、平均CFRが約50%であるエボラウイルス8は、主に患者の体液との直接接触によって感染するため9、空気感染するウイルスに比べて封じ込めが比較的容易です。このパラドックスを理解することは、ウイルスの脅威を正確に評価するための第一歩です。
日本の法的枠組み:感染症法による分類
日本国内の読者にとって最も実用的で信頼できる枠組みは、日本政府が定める「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」、通称「感染症法」です。この法律は、感染症をその危険性、伝播力、社会的影響に基づき分類し、それぞれに応じた公衆衛生上の措置を定めています10。本稿では、この法的な分類を構造の基盤とし、各ウイルスの詳細を解説します。
| 分類 | 危険度の定義 | 主な措置 | 代表的なウイルス疾患 |
|---|---|---|---|
| 一類感染症 | 危険性が極めて高い。容易に伝播し、深刻な状態を引き起こしうる。 | 原則入院、就業制限の可能性あり。 | エボラウイルス病、マールブルグ病、ラッサ熱、天然痘。 |
| 二類感染症 | 危険性が高い。伝播の可能性があり、深刻な状態を引き起こしうる。 | 状況に応じ入院勧告、就業制限の可能性あり。 | SARS(COVID-19を除く)、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1, H7N9)。 |
| 三類感染症 | 特定の職業への就業により集団発生を起こしうる。 | 特定の職業への就業制限の可能性あり。 | 主に細菌性疾患(例:コレラ、細菌性赤痢)。 |
| 四類感染症 | 動物、昆虫、または食品を介して伝播する。 | 動物や環境に関する監視と予防措置が必要。 | 狂犬病、デング熱、SFTS、日本脳炎、黄熱。 |
| 五類感染症 | 発生動向の把握と情報提供によるまん延防止が必要。 | 定点把握(強制的な措置なし)。 | 季節性インフルエンザ、麻しん、風しん、手足口病。 |
一類感染症:極めて危険性の高いウイルス
これらは日本の法律上、最高レベルの警戒が求められるウイルスです。その存在は、世界のどこであれ、日本国内における最高レベルの準備と対応体制を必要とします。
フィロウイルス科:ウイルス性出血熱の原型
特徴的な紐状の形状を持つフィロウイルス科には、人類にとって最も恐ろしい病原体とされるエボラとマールブルグが含まれます。
エボラウイルス病 (EVD)
概要:エボラウイルス病は、オルトエボラウイルス属のウイルスによって引き起こされる、重篤でしばしば致死的な疾患です8。1976年に南スーダンとコンゴ民主共和国で同時に発生した二つのアウトブレイクで初めて確認されました8。
病態生理学:エボラウイルスは、表面の糖タンパク質(GP1,2)を介して宿主細胞に侵入し、急速に増殖します19。初期の標的はマクロファージや樹状細胞といった重要な免疫細胞であり20、これらの破壊は免疫系を弱体化させるだけでなく、激しい炎症反応を引き起こします。
「出血熱」の真実:一般的にエボラは恐ろしい出血を伴うイメージがありますが、臨床研究によれば、重篤な出血は症例の50%未満でしか見られません19。そのため、現在の正式名称である「エボラウイルス病」が、病態をより正確に反映しているとされています21。死因の主たるものは失血ではなく、「サイトカインストーム」と呼ばれる現象です。ウイルスが免疫細胞を攻撃すると、大量の炎症性シグナル分子(サイトカイン)が放出され19、この過剰な炎症反応が血管の透過性を高め、血漿の漏出、循環血液量の減少、ショック、そして最終的には多臓器不全を引き起こすのです20。
臨床的特徴と疫学:潜伏期間は2日から21日9。突然の高熱、倦怠感、筋肉痛、頭痛で発症し、その後、嘔吐や下痢などの消化器症状が続きます8。致死率(CFR)は平均約50%ですが、ウイルスの種や医療の質によって25%から90%まで変動します8。感染は、症状のある患者または遺体の血液や体液(尿、便、吐瀉物など)との直接接触(傷のある皮膚や粘膜を介して)によって起こります8。空気感染はしないことが強調されています9。
治療と予防:水分と電解質の補給を中心とした支持療法が極めて重要です。現在、Ervebo(メルク社)とZabdeno/Mvabea(ヤンセン社)の2種類のワクチンが承認されており、アウトブレイク対応で効果的に使用されています8。
マールブルグ病
概要:同じくフィロウイルス科に属するマールブルグウイルスによって引き起こされ、臨床像はエボラに酷似しています23。1967年にドイツのマールブルグとフランクフルト、およびセルビアのベオグラードで、ウガンダから輸入されたアフリカミドリザルを用いた実験室作業に関連して初めて確認されました23。
疫学と治療:CFRも同様に高く、過去のアウトブレイクでは24%から88%に達しました23。自然宿主はオオコウモリの一種であるルーセットオオコウモリと考えられています23。現在、承認されたワクチンや抗ウイルス治療法はありませんが23、研究は活発に進められています。例えば、Sabin Vaccine Instituteはウガンダ、ケニア、米国でワクチン候補の第2相臨床試験を進めており、その進捗が期待されます24。
その他の一類感染症ウイルス
ラッサ熱:アレナウイルス科のラッサウイルスによって引き起こされ、西アフリカの風土病です。マストミス属のネズミの尿や糞で汚染された食物や家庭用品を介して人に感染します7。全体のCFRは約1%ですが、重症で入院した患者では15%以上に上昇します7。抗ウイルス薬リバビリンが、病初期に投与されれば有効な場合があります28。
一類感染症に対する日本の水際対策と国内体制
ウイルスが一類感染症に分類されることは、日本の公衆衛生システムにとって極めて大きな意味を持ちます。これにより、最高レベルの対応措置が発動されます。空港や港の検疫所では、流行地からの渡航者に対して厳格なスクリーニングが実施され30、疑い例は直ちに隔離されます。診断された患者は、陰圧室や高度な感染制御訓練を受けたスタッフを備えた特定の「指定医療機関」で治療を受けなければなりません。国立感染症研究所(NIID)が診断、研究、助言の中心的な役割を担い10、早期発見、隔離、治療を通じて国内でのまん延を阻止する堅固な体制が構築されています。
二類・四類感染症:特に重要な脅威
ここでは、高い危険性を持ち、現代のパンデミックの教訓となったウイルスや、歴史的に重要な意味を持つウイルスを取り上げます。
狂犬病ウイルス:致死率100%と日本での清浄化の物語
脅威:リッサウイルスの一種によって引き起こされ、感染した哺乳類の唾液を介して、通常は咬傷によって伝播します。一度臨床症状が現れると、致死率はほぼ100%であり46、CFRの観点からは最も致死的な感染症です3。
日本の成功物語:日本は世界でも数少ない「狂犬病清浄国」の一つです6。この成果は、1950年に制定された狂犬病予防法に基づく、飼い犬の登録と毎年の予防接種の義務化という、粘り強い公衆衛生努力の賜物です6。
安全は不断の努力の成果:しかし、この安全は決して当たり前のものではありません。日本の動物検疫所は、マイクロチップの装着、複数回のワクチン接種、抗体検査、そして厳格な待機期間など、輸入動物に対して極めて厳しい規則を課しています6。これらの水際対策の存在が、常に存在する再侵入のリスクから国内を守っているのです。世界的に見れば、アジアやアフリカを中心に、狂犬病は今なお年間数万人の命を奪っています3。
高脅威コロナウイルス:SARS-CoV & MERS-CoV
概要:2003年の重症急性呼吸器症候群(SARS)と2012年の中東呼吸器症候群(MERS)は、共に日本で二類感染症に分類されています10。SARSのCFRは約10%、MERSのCFRは約35%に達し10、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)以前に、新しい呼吸器系ウイルスが如何に迅速に世界中に広まりうるかを示す重要な教訓となりました。日本の公式統計によれば、国内でのSARSおよびMERSによる死亡例は報告されておらず33、これは水際対策の有効性を示唆しています。
天然痘:根絶という偉業とバイオテロの懸念
歴史的背景と偉業:CFRが約30%に達し、人類史上数億人を死に至らしめた天然痘は、1980年にWHOによって世界的な根絶が宣言されました2。これは、国際協力とワクチン接種の力を証明する、公衆衛生史上最大の成果です。
残された脅威:自然界からは根絶されたものの、天然痘ウイルスは今なお米国とロシアの二つの高度安全実験施設で保管されています。このため、日本では依然として一類感染症に分類されています10。一般市民がもはや免疫を持たない現在、バイオテロの病原体として悪用されるリスクが理論上存在し、これが最高レベルの警戒が維持される理由です。
日本において特に関連性の高いウイルス
このセクションは、日本国内で現実に発生している、あるいは具体的なリスクをもたらすウイルスに焦点を当てます。
重症熱性血小板減少症候群 (SFTS):日本におけるマダニ由来の最重要脅威
概要:SFTSは、バンダウイルス属のウイルスによって引き起こされるウイルス性出血熱で、主にマダニの咬傷によって感染します35。日本では四類感染症に分類されています10。
国内の疫学:日本での最初の症例は2013年に確認され38、以来、特に西日本の各県を中心に報告数が増加傾向にあります35。国立感染症研究所(NIID)のデータによると、2013年から2025年4月30日までに1,071例が報告されています40。潜伏期間は6日から14日で、発熱、倦怠感、そして血小板と白血球の減少を特徴とします38。日本におけるCFRは推定27-30%と極めて高く35、重大な脅威となっています。
新たな脅威―ペットからの感染:従来、主な感染経路はマダニとされてきましたが、近年、感染した犬や猫から人への感染リスクが明らかになっています。厚生労働省の診療ガイドラインや地方自治体は、特に獣医師やペットの飼い主に対してこのリスクを警告しています35。ペットへの防ダニ剤の使用、体調不良の野良犬猫との接触を避ける、動物と接触した後の手洗いなど、具体的な予防策の実践が強く推奨されます。
治療の進展:治療は主に支持療法ですが、2024年6月には抗ウイルス薬ファビピラビル(アビガン)が日本でSFTSの治療薬として承認されたことは、重要な進歩です36。
| 年 | 全国届出数 | 全国死亡者数 | 主な発生都道府県 |
|---|---|---|---|
| 2013-2024年 | 1,058 (2025年1月31日時点)44 | 184 (報告時点の致死率 約17.4%)44 | 宮崎、山口、愛媛、広島、佐賀 |
| 2025年 | 13 (2025年4月30日時点)40 | (データ更新中) | (データ更新中) |
出典:国立感染症研究所(NIID)感染症発生動向調査の報告データ4044。注意:致死率は初期報告時の死亡者数に基づくものであり、変動する可能性があります。
デング熱:再興する都市型感染症の脅威
概要:蚊が媒介するウイルス感染症で、日本では四類感染症に分類されます10。ほとんどは軽症ですが、重症化することもあります7。
2014年 代々木公園での集団発生:約70年ぶりに国内での感染伝播が確認されたこの出来事は、デング熱がもはや単なる「輸入感染症」ではないことを示す警鐘となりました45。媒介蚊であるヒトスジシマカは日本の広範囲に生息しており、地球温暖化による生息域の北上と、活発な国際交流が相まって、ウイルスの侵入と拡散のリスクは増大しています。予防は、肌の露出を避け、虫除け剤を使用し、水たまりをなくして蚊の発生を防ぐことに尽きます48。
日本脳炎:ワクチンで制御された風土病のリスク
概要と国内状況:同じく蚊が媒介する四類感染症で10、重篤な神経疾患を引き起こす可能性があります。かつては国内で多数の死者を出していましたが、非常に効果的な定期予防接種プログラムにより、現在の年間報告数は10例未満に激減しました45。しかし、ウイルス自体は根絶されたわけではなく、蚊と主な増幅動物であるブタとの間で循環し続けていることが、毎年の調査で確認されています51。症状が出た場合のCFRは20-40%と依然として高く45、子どもたちへの定期接種の遵守が、この病気の再興を防ぐための鍵となります。
| ウイルス名 | ウイルス科 | 主な感染経路 | 潜伏期間 | 致死率 (CFR) | 日本の感染症法分類 | ワクチン・治療薬の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エボラ | フィロ | 体液との直接接触 | 2-21日 | 25-90% (平均~50%) | 一類 | 承認ワクチン2種あり |
| マールブルグ | フィロ | 体液との直接接触 | 2-21日 | 24-88% (平均~50%) | 一類 | なし、開発中 |
| ラッサ | アレナ | ネズミの排泄物との接触 | 2-21日 | 1% (入院時15%+) | 一類 | リバビリン(早期有効) |
| 狂犬病 | ラブド | 感染動物による咬傷 | 1-3ヶ月 | ほぼ100% (発症後) | 四類 | 有効なワクチンあり |
| SARS-CoV | コロナ | 呼吸器 | 2-10日 | ~10% | 二類 | なし |
| MERS-CoV | コロナ | 呼吸器、ラクダとの接触 | 2-14日 | ~35% | 二類 | なし |
| 天然痘 | ポックス | 呼吸器、直接接触 | 7-19日 | ~30% | 一類 | 根絶済み(ワクチンあり) |
| SFTS | フェヌイ | マダニ咬傷、感染動物との接触 | 6-14日 | ~27-30% (日本) | 四類 | ファビピラビル(日本で承認) |
| デング熱 | フラビ | 蚊の刺咬 | 4-10日 | <1% (重症・未治療で10-20%) | 四類 | ワクチン1種あり(限定的)、支持療法 |
| 日本脳炎 | フラビ | 蚊の刺咬 | 5-15日 | 20-40% (有症状例) | 四類 | 有効なワクチンあり |
| ニパ | パラミクソ | コウモリ/ブタとの接触、ヒト-ヒト | 4-14日 | 40-75% | 四類 | なし、開発中 |
出典:WHO, CDC, MHLW, NIIDの情報を基に編集部が統合3710。数値は推定値であり、流行や医療状況により変動します。
よくある質問
最も致死率の高いウイルスは何ですか?
ペットから危険なウイルスに感染することはありますか?
はい、その可能性はあります。特に注意が必要なのは、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)です。SFTSウイルスに感染した犬や猫から、その体液を介して飼い主や獣医療関係者に感染した事例が報告されています35。また、世界的に見れば、犬は狂犬病の主要な感染源です。ペットの健康管理(特にダニ予防)と、動物と接触した後の適切な衛生管理が重要です。
日本は安全なのに、なぜ海外のウイルスを心配する必要があるのですか?
現代のグローバル社会では、人や物が国境を越えて活発に移動するため、いかなる国も感染症の脅威から完全に孤立することはできません。デング熱の国内感染事例が示したように、海外のウイルスが国内に持ち込まれ、定着するリスクは常に存在します45。日本の安全は、空港や港での厳格な検疫(水際対策)や、国内の監視体制といった、公衆衛生システムの不断の努力によって維持されています。海外渡航時の注意や、国内での予防接種の遵守が、この安全を守る上で不可欠です。
結論
ウイルスの脅威を理解する上で最も重要なことは、恐怖に駆られるのではなく、科学的根拠に基づいた知識で武装することです。本稿で詳述したように、ウイルスの「危険性」は致死率という一面的な指標だけでは測れず、その伝播能力や社会への影響を総合的に評価する必要があります。日本の感染症法に基づく分類は、そうした多角的な評価に基づき、私たちの社会を守るための具体的な行動を規定する、合理的かつ強力な枠組みです。
エボラやマールブルグのような致死性の高いウイルスから、SFTSやデング熱のような国内で身近な脅威に至るまで、それぞれのウイルスは異なる課題を提示します。しかし、それらに対する最も効果的な武器は共通しています。それは、正確な情報、徹底した公衆衛生対策、そしてワクチン接種をはじめとする予防医学の恩恵です。狂犬病や日本脳炎の成功事例が示すように、人類は科学の力でこれらの脅威を効果的に制御することが可能です。JAPANESEHEALTH.ORGは、今後も読者の皆様が信頼できる最新かつ正確な情報を提供し続けることをお約束します。ご自身の健康と社会全体の安全を守るため、本稿で得た知識をご活用いただければ幸いです。
免責事項本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言に代わるものではありません。健康上の懸念や治療に関する決定を下す前に、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- ログミーBusiness. 致死率の高い疫病トップ5 その脅威を解説 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://logmi.jp/knowledge_culture/culture/114710
- Kiralia | キラリア. 危険性の高い主な病原体 | 感染症の基礎知識 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://pro.kao.com/jp/kiralia/knowledge/06/
- The Transmission. The deadliest viruses in human history, from COVID to smallpox [Internet]. 2023 Jun 6 [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.unmc.edu/healthsecurity/transmission/2023/06/06/the-deadliest-viruses-in-human-history-from-covid-to-smallpox/
- YouTube. 脳や神経に影響を与えるウイルス性疾患の重症度ランキング [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=B5x5RxnvXXw
- ごみサク. 全世界で年間5万人以上が発症、死亡している致死率100%病とは!? [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.gomisaku.jp/articles/column/rabies/
- ダイヤモンド・オンライン. 【外科医が教える】発症するとほぼ100パーセント死ぬ「恐ろし… [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://diamond.jp/articles/-/328893
- World Health Organization (WHO). Fact sheets [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets
- World Health Organization (WHO). Ebola disease [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-disease
- 福岡県保健環境研究所. エボラ出血熱について [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.fihes.pref.fukuoka.jp/~kikaku/Disease/ebola/ebola_virus.html
- 国立健康危機管理研究機構. 感染症サーベイランス情報のまとめ・評価 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.niid.go.jp/niid/ja/idss.html
- たんの消化器内科・内科. 風邪が新型コロナと同じ5類感染症に?何が変わるの?そもそも風邪とは? [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://tanno-naika.jp/blog/post-358/
- 東京ビジネスクリニック【公式】. 感染症分類の話をしよう [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.businessclinic.tokyo/archives/5840
- 管理薬剤師.com. 指定感染症・新感染症・1~5類感染症 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://kanri.nkdesk.com/hoken/hoken25.php
- 家来るドクター. 感染症の分類や種類を簡単解説|なぜコロナは5類になったの? [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://iekuru-dr.com/blog/kansenshou/
- CareNeTV. 講師情報|忽那 賢志(くつな さとし)大阪大学 大学院医学系研究科 感染制御学 教授 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://carenetv.carenet.com/instructor/detail.php?instructor_id=630
- Wikipedia. 忽那賢志 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%BD%E9%82%A3%E8%B3%A2%E5%BF%97
- 大阪大学医学系研究科・医学部. 忽那 賢志 教授(感染制御学)が着任しました [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.med.osaka-u.ac.jp/archives/26644
- South Dakota Department of Health. SOUTH DAKOTA PUBLIC HEALTH LABORATORY Diseases Fact Sheet – Ebola [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://doh.sd.gov/media/d1adbyw3/ebola_diseases_fact_sheet.pdf
- Jacob ST, Crozier I, Fischer WA 2nd. Ebola Virus Disease. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560579/
- Sharma R, Agarwal M, Gupta M, Somendra S, Saini V. Pathophysiology of Ebola virus infection: Current challenges and future hopes. Microb Pathog. 2020 Oct;147:104437. doi: 10.1016/j.micpath.2020.104437. Epub 2020 Jul 22. PMID: 32711003; PMCID: PMC7443712.
- 厚生労働省検疫所. エボラウイルス病(Ebola virus disease) [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/name48.html
- Bray M, Murphy FA. The Pathogenesis of Ebola Virus Disease. Cell. 2016 Dec 15;167(7):1687-1691. doi: 10.1016/j.cell.2016.11.028. PMID: 27959626.
- World Health Organization (WHO). Marburg virus disease [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/marburg-virus-disease
- Sabin Vaccine Institute. Marburg Vaccine Development Program [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.sabin.org/vaccine-research-and-development/marburg-vaccine-development-program/
- Sabin Vaccine Institute. Sabin Begins Marburg Vaccine Trial in U.S. [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.sabin.org/resources/sabin-begins-marburg-vaccine-trial-in-u-s/
- Sabin Vaccine Institute. A Phase 2 clinical trial is underway in Uganda and Kenya to further evaluate the vaccine’s safety and immunogenicity [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.sabin.org/vaccine-research-and-development/marburg-vaccine-development-program/#:~:text=A%20Phase%202%20clinical%20trial,the%20vaccine’s%20safety%20and%20immunogenicity.
- Clinical Trials Arena. Sabin Vaccine Institute begins trial of vaccine candidate for Marburg virus disease [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.clinicaltrialsarena.com/news/sabin-marburg-vaccine/
- Li S, Sun Z, Meng Q, Yang W, O-U-IL G, Wu Y, et al. Lassa virus glycoprotein complex review: insights into its unique fusion machinery. Biosci Rep. 2022 Feb 28;42(2):BSR20211930. doi: 10.1042/BSR20211930. PMID: 35043825; PMCID: PMC8852335.
- Olayemi A, Oyinloye O, Ojo O, Adeyemi OS. LASSA FEVER: ANOTHER INFECTIOUS MENACE. African Journal of Clinical and Experimental Microbiology. 2008;9(3):144-150.
- 内閣感染症危機管理統括庁. 感染症の発生状況 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.caicm.go.jp/action/data/index.html
- 厚生労働省. 感染症情報 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
- Institut Pasteur. Our fact sheets diseases [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.pasteur.fr/en/medical-center/disease-sheets
- e-Stat 政府統計の総合窓口. 人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡上巻 5-29 感染症による死因(感染症分類)別にみた年次別死亡数及び死亡率(人口10万対) [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003411673
- e-Govデータポータル. 上巻_5-29_感染症による死因(感染症分類)別にみた年次別死亡数及び死亡率(人口10万対) [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://data.e-gov.go.jp/data/dataset/mhlw_20211015_0021/resource/b37372a0-003a-44a5-8c9f-11ea8dd27047
- 国際感染症センター. 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)診療の手引き 2024年版 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://dcc.ncgm.go.jp/prevention/resource/2019SFTS.pdf
- 厚生労働省. 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169522.html
- 福井県医師会. 重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) 診療の手引き [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.fukui.med.or.jp/infuru/sfts-tebiki.pdf
- 岡山県. 『重症熱性血小板減少症候群(SFTS)』に注意しましょう [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.pref.okayama.jp/page/343283.html
- 東京都感染症情報センター. 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) Severe fever with thrombocytopenia syndrome [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/sfts/
- 国立健康危機管理研究機構. 感染症発生動向調査で届出られたSFTS症例の概要(2025年4月30日更新) [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/article/sfts/020/20250523144135.html
- HOKUTO. 重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) 診療の手引き2024年版、 公開 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://hokuto.app/post/WytS0VEwCpLNp8HSqwOc
- 越谷市. 重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) 診療の手引き 2024年版 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/fukushi/hokenjo/kansensho/files/sfts.sinnryounotebiki2024.pdf
- 松山市. 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) 診療の手引き 2024年版 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/iryo/hokenyobo/kansensho/doubutsu/danibaikaikannsenn.files/sftstebiki.pdf
- 国立健康危機管理研究機構. 感染症発生動向調査で届出られたSFTS症例の概要(2025年1月31日更新) [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/article/sfts/020/index.html
- BIKEN. ワクチンの通 vol.17 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.biken.or.jp/upload/wp-content/uploads/2023/07/vaccine_no_michi_vol.17.pdf
- 日本小児科学会. デング熱・チクングニア熱の診療ガイドライン 2015 年 5 月 22 日 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20150727deng.pdf
- 厚生労働省. デング熱診療ガイドライン (第 1 版) [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10906000-Kenkoukyoku-Kekkakukansenshouka/0000057969.pdf
- 国立健康危機管理研究機構. デング熱 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/dengue/010/dengue-info.html
- 厚生労働省検疫所. デング熱(Dengue Fever) [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/name33.html
- 国立感染症研究所. IASR 38(8), 2017【特集】日本脳炎 2007~2016年 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://id-info.jihs.go.jp/niid/ja/je-m/je-iasrtpc/6827-450t.html
- 国立感染症研究所. 日本脳炎 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/je/010/je-intro.html
- 島根県. 日本脳炎 感染症流行予測調査 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www1.pref.shimane.lg.jp/contents/kansen/topics/jpe/i424.htm
- Taylor & Francis Online. Full article: Progress and challenges in Nipah vaccine development and licensure for epidemic preparedness and response [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14760584.2025.2476523?src=
- Pandemic Sciences Institute, University of Oxford. Public health vision led by researchers from Oxford and Bangladesh aims to tackle Nipah virus [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.psi.ox.ac.uk/news-and-opinion/researchers-from-bangladesh-and-oxford-propose-public-health-vision-for-tackling-nipah-virus
- Vax-Before-Travel. Who Sets Nipah Virus Vaccine Research Priorities [Internet]. 2024 Dec 2 [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.vax-before-travel.com/2024/12/02/who-sets-nipah-virus-vaccine-research-priorities
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). About Hantavirus [Internet]. [cited 2025 Jun 23]. Available from: https://www.cdc.gov/hantavirus/about/index.html
- 厚生労働省. 蚊媒介感染症の診療ガイドライン [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/000477538.pdf
- 厚生労働省. 新型コロナウイルス感染症について [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
- 国立健康危機管理研究機構. 感染症発生動向調査週報 [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html