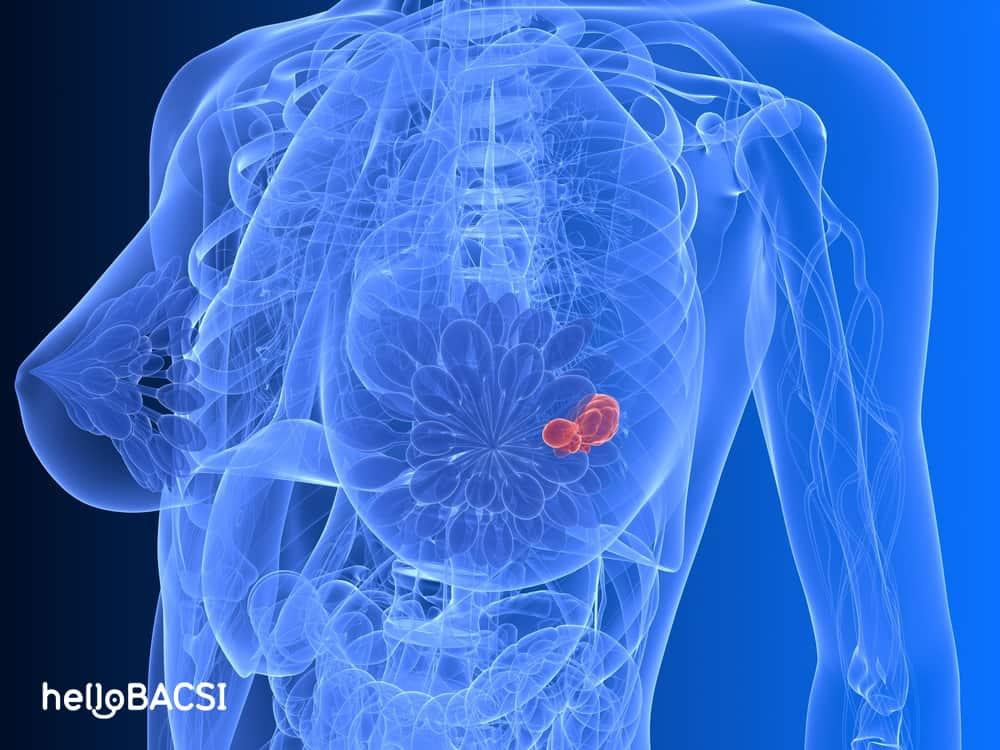この記事の科学的根拠
本記事は、日本の公的機関・学会ガイドラインおよび査読済み論文を含む高品質の情報源に基づき、出典は本文のクリック可能な上付き番号で示しています。
要点まとめ
乳房インプラント交換と長期ケアの指針
「インプラントは一体いつ交換すべきなのか」「BIA-ALCLや破損が怖い」「保険や費用がどのくらいかかるのか分からない」――乳房インプラントと共に生活していると、こうした不安がふと頭をよぎることがあります。しかも多くの人が、その不安を誰にも打ち明けられないまま、一人で抱え込みがちです。まず知っておきたいのは、乳房インプラントは体内に埋め込まれた人工物であり、永久に持つものではないという事実と、それでも適切な情報と定期的な検診があれば、リスクをコントロールしながら付き合っていくことができるという点です。
このガイドでは、「いつ交換が必要になるのか」「どんな合併症に注意すべきか」「日本の医療制度の中でどう備えればよいか」といった不安を、段階的に整理するお手伝いをします。インプラントの問題は、月経・妊娠・産後・更年期・がん検診など、女性の一生の健康の流れの中で考えることも大切です。ライフステージ全体の中で自分のからだの変化や検診のタイミングを俯瞰したいときは、女性の健康ガイド|月経・妊娠・産後・更年期・検診を年齢別に解説も合わせて確認しながら、インプラントとの付き合い方を長期的な視点で捉えてみてください。
インプラントは食品の消費期限のように「◯年で必ずダメになる」ものではなく、時間の経過とともに合併症の確率が高まっていく医療機器です。一般的には10〜20年を目安にリスクが上昇し、被膜拘縮や破損といった問題が起こりやすくなるとされています。被膜拘縮では、インプラントを包む膜が厚く硬くなり、乳房の硬さや変形、痛みにつながることがあります。また、生理食塩水インプラントは破損するとすぐにしぼみますが、シリコーンインプラントは症状が出ない「サイレント・ラプチャー」として進行することも少なくありません。こうした長期経過や日常生活でのケアについては、乳房インプラントによる乳房再建術後の経過とケアでも詳しく整理されており、自分のリスクカーブをイメージするうえで参考になります。
最初の一歩として大切なのは、「今の自分のインプラントがどのような種類で、いつ入れたものか」「乳がん術後の再建なのか、美容目的なのか」といった基本情報を整理し、定期検診の計画を立てることです。日本のガイドラインでは、年1回の専門医による視触診と、約2年に1回の超音波検査またはMRI検査によって、無症候性の破損や被膜拘縮を早期にとらえることが推奨されています。さらに、BIA-ALCLに関しては、手術1年以上経ってから片側だけ急に大きく腫れる「遅発性漿液腫」などのサインを知っておくことが重要です。こうしたリスクや受診の流れは、日本形成外科学会がまとめたBIA-ALCL診療に関する指針でも標準化されていますので、主治医と共有しながらチェックしていきましょう。
次のステップとして、「交換するならどのような方法を選ぶのか」を考える必要があります。インプラントを入れ替えるのか、自家組織再建に切り替えるのかによって、手術時間や身体への負担、見た目や触感の自然さ、将来の再手術の可能性が変わってきます。乳がんや葉状腫瘍の術後再建として保険診療でインプラントを入れた場合、その後に起こった破損や重度の被膜拘縮など医学的に必要な交換・抜去も保険の対象になります。一方、美容目的の豊胸術や自己都合による交換は自由診療となり、費用は全額自己負担です。保険診療の範囲と自己負担の目安を整理するには、健康保険の適用と費用の目安を確認しながら、自分のケースがどこに当てはまるのかを把握しておくと安心です。
そのうえで忘れてはならないのが、「不安だけで衝動的に決めない」という視点です。BIA-ALCLはインプラントをめぐる重大なテーマではありますが、極めてまれな疾患であり、症状のない人に対して予防的な抜去を一律に勧めてはいないという見解も示されています。一方で、明らかな腫れや左右差、しこりなどのサインを放置することも避けなければなりません。インプラント再建そのものの特徴や人工物再建に伴うリスクは、人工物再建についての解説や、インプラント再建手術に特化した患者向け情報であるインプラントを使う乳房再建手術にも整理されています。こうした信頼できる情報をベースに、認定専門医と相談しながら、自分にとって納得できるバランスを探していきましょう。
乳房インプラントの交換や長期的なケアは、「いつか必ず壊れるから怖い」という恐怖だけで向き合う必要はありません。インプラントが永久的なものではないこと、時間とともに被膜拘縮や破損、BIA-ALCLなどのリスクが変化していくこと、日本には保険診療や高額療養費制度といったセーフティネットがあることを理解することで、見通しはぐっとクリアになります。今すぐすべてを決めようとせず、まずは自分の現状とリスクを整理し、次に主治医や専門医に相談し、少しずつ「自分のペース」で選択肢を絞っていけば大丈夫です。一人で抱え込まず、信頼できる情報源と医療者・支援団体を味方につけながら、あなた自身が納得できる形でインプラントとの付き合い方を選んでいきましょう。
第1部 乳房インプラント交換の基礎知識
「このインプラントは、一体いつまで私の体の中にいられるのだろう?」そうした将来への漠然とした不安は、インプラントと共に生活する多くの方が抱える、ごく自然な感情です。実は、インプラントの「耐用年数」という考え方は、食品の消費期限とは全く異なります。科学的には、それは時間と共に変化するリスクの確率曲線として理解されています。これは車のメンテナンススケジュールに似ています。決まった日に壊れるわけではありませんが、定期的に点検することで大きなトラブルを未然に防ぐのと同じです。米国食品医薬品局(FDA)の指摘によると、インプラントを体内に保持する期間が長くなるほど、何らかの合併症を経験し、追加の手術が必要になる可能性が高まることが示されています1。ですから、「いつ期限が切れるのか?」と心配するより、「時間経過とともに変化する自身のリスクを、定期的な検診を通じていかに管理していくか?」という視点に切り替えてみませんか?
一般的にインプラントの耐用年数は10年から20年が一つの目安とされていますが、これは製品の「有効期限」を意味するものではありません2。この期間を過ぎると、後述するような合併症が発生するリスクが統計的に上昇し始めることを示唆しています。インプラントの交換に至る理由は、医学的な問題と、患者さんご自身の希望に基づく選択的なものの二つに大別されます。
交換の主な医学的適応
インプラント交換を必要とする最も一般的な医学的理由は、合併症の発生です。その中でも特に頻度が高いのが「被膜拘縮(ひまくこうしゅく)」です。インプラントが体内に入ると、体の自然な反応としてその周りに薄い膜(被膜)ができます。しかし、この被膜が異常に厚く硬くなり、インプラントを締め付け始めると、乳房が硬くなったり、形が崩れたり、痛みを伴うことがあります34。このような場合には、被膜を取り除き、インプラントを交換する手術が検討されます。
もう一つの主要な理由は「インプラントの破損」です。生理食塩水インプラントは破損すると内容物が体に吸収されて胸がしぼむため、すぐに気づくことができます。一方で、近年のシリコーンゲルインプラントは、破損しても症状が現れない「サイレント・ラプチャー」となることが少なくありません1。この無症候性の破損を早期に発見するため、日本のガイドラインでは、専門家による約2年に1度のMRI検査または超音波検査が推奨されています56。
このセクションの要点
- 乳房インプラントは永久的なものではなく、10~20年を目安に合併症のリスクが上昇します。
- 主な医学的交換理由は「被膜拘縮」と「破損」であり、特にシリコーンインプラントの無症候性破損を発見するために定期的な画像検査が極めて重要です。
第2部 BIA-ALCL:重大な安全性に関する包括的レビュー
近年、乳房インプラントと「がん」との関連性についてのニュースを目にし、深刻な病気ではないかと心を痛めている方もいらっしゃるかもしれません。BIA-ALCLという聞き慣れない病名に、大きな不安を感じるのは当然のことです。しかし、正確な情報を知ることが、漠然とした恐怖を和らげる第一歩となります。科学的には、BIA-ALCLは、乳腺にできる乳がんとは全く異なり、インプラントを包む膜の周りで発生する、体の免疫システムのがんです7。これは、インプラントという「家」そのものではなく、家の周りを警備している「警備員(免疫細胞)」に問題が起きるようなものです。そして、その問題は、表面が滑らかな「警備しやすい家」よりも、表面がザラザラした「警備しにくい家(テクスチャードインプラント)」の周りで起こりやすいことが分かっています8。だからこそ、この病気が非常に稀であるという事実と、万が一に備えて注意すべき特有のサインを冷静に学ぶことが、ご自身を守るための最も確実な行動となります。
日本におけるリスク、症状、診断
世界的なBIA-ALCLの発生率は、テクスチャードインプラントの種類により2,200人から86,000人に1人と幅広く報告されていますが、日本国内での確定診断は2023年9月時点で5例と非常に稀です89。最も一般的な初期症状は「遅発性漿液腫(ちはつせいしょうえきしゅ)」と呼ばれ、手術後1年以上経過してから、片側の乳房が突然大きく腫れる、張りや痛みを感じるといったものです6。診断は、超音波で液体を確認し、それを採取して特殊な病理検査(CD30陽性・ALK陰性)で確定します。この診断プロセスは、日本形成外科学会などの専門学会ガイドラインで標準化されています7。
治療、予後、公的機関の指針
幸いなことに、病変が被膜内に留まっている早期の段階で発見されれば、インプラントと被膜を完全に切除する手術で多くは治癒が期待でき、予後は非常に良好と報告されています7。このことからも、迅速な受診の重要性がわかります。重要な点として、FDAは症状のない患者さんに対して、予防的にテクスチャードインプラントを抜去することは推奨していません10。これは、BIA-ALCLの発生リスクそのものよりも、追加の手術に伴うリスクの方が高いと考えられるためです。
受診の目安と注意すべきサイン
- 手術後1年以上経ってからの、片側乳房の突然の大きな腫れや左右差
- 乳房の持続的な張りや痛み
- 乳房や脇の下のしこり
- 原因不明の皮膚の発疹
第3部 手術の実際とインプラントの選択肢
インプラントを交換する、あるいは新たに入れると決めたとき、どのような手術があり、どんな選択肢があるのか、複雑で分かりにくいと感じることがあります。多くの選択肢があるからこそ、どれが自分に最適なのか迷うのは当然です。ご自身の体とライフプランに合った最良の道を選ぶためには、それぞれの方法の長所と短所を正しく理解することが欠かせません。科学的には、手術のプロセスは、ゼロから空間を作る「二段階再建」と、既存の空間を利用する「交換手術」に大別されます。これは、新しい土地に家を建てるか、既存の家をリフォームするかの違いに似ています。さらに、インプラントという「既製品の家」を選ぶか、自分の組織を使う「オーダーメイドの家(自家組織再建)」を選ぶかという大きな分岐点があります11。まずは、それぞれの選択肢がどのようなもので、ご自身の希望(見た目の自然さ、手術の負担など)とどう合致するのか、一つずつ見ていきましょう。
再建方法の比較
インプラントを用いる方法と、ご自身の体の一部(お腹や背中など)の組織を移植する自家組織再建には、それぞれ利点と欠点があります。
| 再建方法 | 主な利点 | 主な欠点 |
|---|---|---|
| インプラント再建 | ・手術時間が短く、身体への負担が少ない ・組織を採取する傷ができない |
・長期的に交換が必要になる可能性がある ・被膜拘縮や破損、BIA-ALCLのリスクがある ・感触が人工的で、加齢による変化に馴染みにくい |
| 自家組織再建 | ・自分の組織なので温かく自然な感触 ・一度生着すれば半永久的 ・加齢による変化に自然に対応する |
・手術時間が長く、身体への負担が大きい ・組織を採取した部位に傷が残る(ドナーサイト・モービディティ) ・痩せ型の人では十分な組織量を確保できないことがある |
日本国内で利用可能な乳房インプラント
BIA-ALCL問題とそれに伴う一部製品の自主回収を経て、現在日本国内で保険適用されるインプラントの選択肢は変化しています。専門医は、患者さん一人ひとりの体型や希望、そして安全性に関する考え方を総合的に考慮して、最適な製品を選択します。
| 製造販売業者 | 製品シリーズ | 表面性状 | 形状 | 主な特徴・BIA-ALCL関連情報 |
|---|---|---|---|---|
| アラガン・ジャパン合同会社 (AbbVie) | ナトレル Inspiraシリーズ | スムース | ラウンド(おわん型) | BIA-ALCL問題を受け、現在はスムーズタイプのみ供給。テクスチャードタイプの「ナトレル 410」は自主回収済み。 |
| 株式会社グンゼ | Sientra ブレスト・インプラント | スムース マイクロテクスチャード | ラウンド(おわん型) アナトミカル(しずく型) | アラガン社製品の回収後、2020年10月より保険適用。マイクロテクスチャードはBIA-ALCLリスクがマクロテクスチャードより低いとされるがゼロではない。 |
| メンター・ジャパン合同会社 (J&J) | メンター・メモリージェル/シェイプ | スムース テクスチャード | ラウンド(おわん型) アナトミカル(しずく型) | 世界的に主要なブランドの一つ。臨床試験が進行中。 |
| Establishment Labs社 | Motiva | スムーズシルク | ラウンド(おわん型) | 表面はスムーズタイプに分類され、BIA-ALCLのリスクは極めて低いとされる。大規模な国際臨床試験が進行中。 |
自分に合った選択をするために
インプラント再建が適している可能性: 手術の負担を軽くしたい方、体の他の部位に傷をつけたくない方。
自家組織再建が適している可能性: より自然な感触を求める方、将来的な交換手術の可能性を避けたい方で、十分な組織を採取できる方。
第4部 日本の医療制度の活用:費用と保険適用
「再建や交換をしたいけれど、費用が一体いくらかかるのか見当もつかない」という経済的な不安は、治療への一歩をためらわせる大きな壁になり得ます。医療費に関する心配は、誰もが抱える切実な問題です。しかし、日本の医療制度には、患者さんを守るための重要な仕組みが備わっています。この制度の核心は、「治療目的」か「美容目的」かという明確な区分です。乳がん治療の一環としての再建は、社会全体で支えるべき医療と位置づけられ、公的保険が適用されます12。これは、病気という予期せぬ事態に対して、経済的な安全網(セーフティネット)が機能するようなものです。一方で、美容医療は個人の選択とされ、費用は自己負担となります。ご自身の状況がどちらに当てはまるのかを正確に理解し、利用できる制度を知ることが、安心して治療計画を立てるための鍵となります。
保険が適用されるケースとされないケース
日本の公的医療保険が適用されるのは、医学的に必要と判断される治療です。乳がんや葉状腫瘍の術後の乳房再建、遺伝性乳がん(HBOC)のリスク低減手術後の再建、そして、これらの保険適用された再建後のインプラント破損や重度の被膜拘縮といった合併症に対する交換・抜去手術が該当します111213。一方で、美容目的の豊胸術や、その後の自己都合による交換・抜去は保険適用外の自由診療となります。
経済的負担を軽減する「高額療養費制度」
保険適用の手術で医療費が高額になった場合でも、日本の医療保険制度には「高額療養費制度」という重要な仕組みがあります。これは、1ヶ月の医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です14。この制度があるため、最終的な自己負担額は予測可能な範囲に収まり、患者さんが安心して必要な治療を受けるためのセーフティネットとして機能しています15。
このセクションの要点
- 乳がん治療の一環としての再建手術や、それに伴う合併症の治療は公的医療保険の対象です。美容目的の手術は対象外です。
- 保険診療の場合、「高額療養費制度」を利用することで、月々の自己負担額を所得に応じた上限額までに抑えることができます。
第5部 インプラント交換後の生活:長期的なケアと留意点
手術室を出た瞬間がゴールではありません。むしろ、それはご自身の体と生涯にわたって向き合っていく、新たなパートナーシップの始まりです。術後の生活に潜む小さな疑問や注意点を事前に知っておくことは、日々の安心につながります。科学的には、長期的な健康維持の鍵は「継続的なモニタリング」にあります。これは、健康診断を毎年受けるのと同じ考え方です。体に異常がなくても定期的にチェックすることで、問題の芽を早期に摘み取ることができます5。インプラントとの生活も、この長期的な視点を持つことが何よりも大切です。
定期検診と乳がん検診
最も重要なのは、症状がなくても生涯にわたる定期検診を続けることです。日本のガイドラインでは、年に1回の専門医による視触診と、約2年に1回の画像検査(超音波またはMRI)が推奨されています5。また、乳がん検診を受ける際は、インプラントが入っていることを必ず伝えましょう。マンモグラフィは、インプラントを圧迫して破損させるリスクや、インプラントの影で乳腺組織が見えにくくなる問題があります1617。そのため、圧迫の必要がない超音波検査やMRI検査が、より安全で有用な選択肢とされています。
今日から始められること
- 次回の定期検診の予約日を確認し、カレンダーに登録しましょう。
- 乳がん検診の予約をする際は、「インプラントが入っているのですが、どの検査が適していますか?」と事前に電話で相談してみましょう。
第6部 リソースとサポート
一人で情報を集め、決断を下すプロセスは、時に孤独で大きな負担を感じるものです。特に医療に関する選択は、専門的な知識が必要で、どこに相談すればよいか分からなくなることもあります。しかし、あなたは一人ではありません。日本には、同じ経験を持つ仲間と繋がったり、信頼できる専門家を探したりするための、確立されたリソースが存在します。科学的根拠に基づいた情報提供を行う公的機関や、患者さんの視点に立って活動する支援団体は、いわば暗い道を照らす「灯台」のような存在です73。こうしたリソースを積極的に活用することが、納得のいく選択への近道となります。
専門医の探し方と患者支援団体
安全で質の高い医療を受けるためには、適切な資格を持つ医師を選ぶことが極めて重要です。「日本形成外科学会(JSPR)」や「日本美容外科学会(JSAPS)」のウェブサイトでは、認定専門医を検索することができます。また、「NPO法人エンパワリング ブレストキャンサー(E-BeC)」のような患者支援団体は、専門家によるセミナーや患者同士の情報交換の場を提供しており、貴重な情報源となります7376。国の機関である「国立がん研究センター がん情報サービス」も、信頼性の高い基本的な情報を提供しています。
今日から始められること
- お住まいの地域で、JSPRまたはJSAPSの認定専門医がいる医療機関を検索してみましょう。
- E-BeCのウェブサイトを訪れ、次回のオンラインセミナーのテーマや日程を確認してみましょう。
よくある質問
インプラントは何年ごとに交換が必要ですか?
インプラントに明確な「有効期限」はありません。しかし、一般的に10年~20年が経過すると、破損や被膜拘縮などの合併症が起こる確率が統計的に上昇するため、交換を検討することが多くなります2。重要なのは年数ではなく、定期的な検診でインプラントの状態を専門医に確認してもらうことです。
インプラントに明確な「有効期限」はありません。しかし、一般的に10年~20年が経過すると、破損や被膜拘縮などの合併症が起こる確率が統計的に上昇するため、交換を検討することが多くなります2。重要なのは年数ではなく、定期的な検診でインプラントの状態を専門医に確認してもらうことです。
BIA-ALCLの最も一般的な初期症状は何ですか?
インプラントが入っていても乳がん検診は受けられますか?
はい、受けられます。ただし、インプラントがある場合、マンモグラフィは破損のリスクや乳腺組織が写りにくいという問題があります16。そのため、体を圧迫しない超音波(エコー)検査やMRI検査がより安全で推奨される選択肢です。検診を受ける際は、必ずインプラントが入っていることを申告してください。
はい、受けられます。ただし、インプラントがある場合、マンモグラフィは破損のリスクや乳腺組織が写りにくいという問題があります16。そのため、体を圧迫しない超音波(エコー)検査やMRI検査がより安全で推奨される選択肢です。検診を受ける際は、必ずインプラントが入っていることを申告してください。
インプラントの交換手術は保険適用されますか?
結論
乳房インプラントの交換は、単なる外科手術ではなく、ご自身の身体、心理、そして人生設計に深く関わる長期的なプロセスです。インプラントが永久的なものではないという事実の理解から始まり、被膜拘縮や破損、そしてBIA-ALCLという稀ながらも重大なリスクへの対処まで、正確な知識が求められます。特にBIA-ALCLの出現は、患者さんが自身の健康管理に主体的に関わる「参加型医療」への移行を促しました。幸いなことに、日本の医療制度は、乳がん治療の一環としての再建とその後の合併症治療を手厚く保障しています。最終的な意思決定は、信頼できる専門医との十分な対話を通じて、最新の情報に基づき、個々の価値観を反映させることでなされるべきです。本稿が提供した情報が、そのための確かな一助となることを願っています。
免責事項
本コンテンツは一般的な医療情報の提供を目的としており、個別の診断・治療方針を示すものではありません。症状や治療に関する意思決定の前に、必ず医療専門職にご相談ください。
参考文献
- U.S. Food and Drug Administration. What to Know About Breast Implants. [インターネット]. [引用日: 2025-09-17]. https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/what-know-about-breast-implants
- サバイバーシップ. 乳房インプラントによる乳房再建術後の経過とケア. [インターネット]. [引用日: 2025-09-17]. https://survivorship.jp/breast-reconstruction/daily-life/02/index.html
- 日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会 (JOPBS). 人工物再建について. [インターネット]. [引用日: 2025-09-17]. https://jopbs.or.jp/general/saiken/artifact.html
- 乳房再建クリエイト. シリコン・インプラントから発生する現在の問題点について. [インターネット]. [引用日: 2025-09-17]. https://saiken-create.com/about_breast-reconstruction/about_medical-features/current_issues/
- 日本美容外科学会 (JSAPS). 2022年5月 外傷・先天異常に対する乳房再建. [インターネット]. 2022. [引用日: 2025-09-17]. https://www.jsaps.com/docs/info/shiyoukijun_2022rev2.pdf [PDF]
- American Society of Plastic Surgeons (ASPS). Breast Implant Safety. [インターネット]. [引用日: 2025-09-17]. https://www.plasticsurgery.org/patient-safety/breast-implant-safety
- 日本形成外科学会 (JSPR). 乳房インプラント関連未分化大細胞型リンパ腫(BIA-ALCL)診療に関する指針. [インターネット]. [引用日: 2025-09-17]. https://jsprs.or.jp/member/committee/breast-implant-guideline/乳房インプラント関連未分化大細胞型リンパ腫bia-alcl/
- サバイバーシップ. 乳房インプラントに関連する発がんの可能性について. [インターネット]. [引用日: 2025-09-17]. https://survivorship.jp/breast-reconstruction/method/03/index.html
- 厚生労働省. 資料1-2. [インターネット]. [引用日: 2025-09-17]. https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000540930.pdf [PDF]
- American Society of Plastic Surgeons (ASPS). BIA-ALCL Resources Frequently Asked Questions. [インターネット]. [引用日: 2025-09-17]. https://www.plasticsurgery.org/patient-safety/breast-implant-safety/bia-alcl-summary/frequently-asked-questions
- 乳房再建クリエイト. 医学的な特徴について. [インターネット]. [引用日: 2025-09-17]. https://saiken-create.com/about_breast-reconstruction/about_medical-features/
- 乳房再建ナビ. 健康保険の適用と費用の目安. [インターネット]. [引用日: 2025-09-17]. https://nyubo-saiken.com/reconstruction/05_01.html
- 広島市民病院. もっと知りたい乳房再建術. [インターネット]. [引用日: 2025-09-17]. https://www.city-hosp.naka.hiroshima.jp/dl/cancer/260515_03.pdf [PDF]
- AbbVie. がん患者さんに対する医療費助成・支援について. [インターネット]. [引用日: 2025-09-17]. https://blood-cancer.abbvie.co.jp/support_information/cost/
- NPO法人E-BeC. 《第2章》インプラントを使う「乳房再建手術」. [インターネット]. [引用日: 2025-09-17]. https://www.e-bec.com/about/chapter2
- MYCLI【マイクリ】. シリコンバッグ豊胸後の乳がん検診は?3つの注意点を解説. [インターネット]. [引用日: 2025-09-17]. https://mycli.jp/column/1118/
- 無痛MRI乳がん検診. 特徴5 乳房手術後も検査可能な理由. [インターネット]. [引用日: 2025-09-17]. https://www.dwibs-search.com/feature-5/
- QLife. 「E-BeC(エンパワリング ブレストキャンサー)」乳がん患者さんの「乳房再建」への正しい理解を広めたい. [インターネット]. [引用日: 2025-09-17]. https://cancer.qlife.jp/pn/pn001/article20862.html
- PR Times. 【E-BeC】乳房再建手術に関心のある人への意識調査を10年ー2022. [インターネット]. 2022. [引用日: 2025-09-17]. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000081667.html