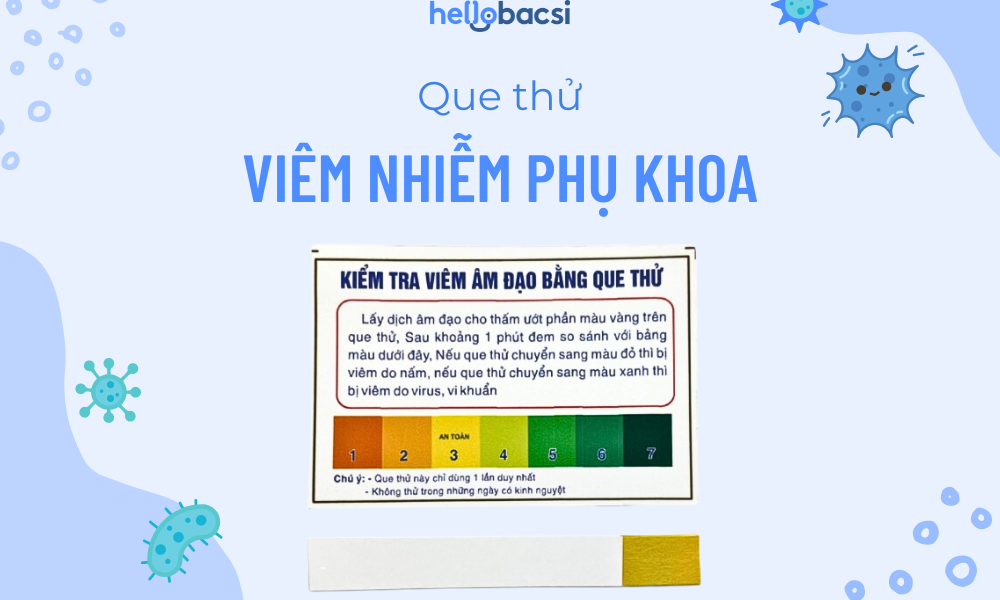この記事の科学的根拠
この記事は、入力された研究報告書に明示的に引用されている最高品質の医学的証拠にのみ基づいています。以下に示すリストは、参照された実際の情報源の一部と、提示された医学的指針との直接的な関連性を示したものです。
- 世界保健機関(WHO)および米国疾病予防管理センター(CDC): 本記事における細菌性腟症、トリコモナス症などの診断基準や標準的な治療法に関する指針は、これらの国際的な保健機関が公表するガイドラインに基づいています12。
- 日本産科婦人科学会(JAOG)および日本性感染症学会(JSTI): 日本国内におけるカンジダ外陰腟炎や各種性感染症の診療ガイドラインは、これらの専門学会が定める指針に準拠しており、本記事の記述の正確性を担保しています34。
- 各種査読済み医学論文: 患者自身が検体を採取する方法(自己採取)の信頼性や、核酸増幅検査(NAATs)の精度に関する記述は、学術雑誌『Journal of Clinical Microbiology』などで発表された複数の臨床研究の結果に基づいています56。
この記事の要点まとめ
- 多くの女性が婦人科受診にためらいを感じており、自宅で使える検査キットはプライバシーを守りながら健康状態を確認できる有効な手段です9。
- 検査キットには大きく分けて2種類あります。「特定の病原体を調べるSTI検査」と「腟内の菌バランス全体を見る膣内フローラ検査」があり、目的によって選ぶべきキットが異なります78。
- キットの精度を判断する上で最も重要なのは、「自己診断」と「自己採取・臨床検査機関での分析」の違いを理解することです。専門機関が分析する後者は、病院での検査とほぼ同等の高い信頼性があります69。
- キットを選ぶ際は、精度(検査方法)の他に、プライバシーへの配慮、結果判明までの速さ、費用、陽性だった場合のサポート体制(アフターフォロー)を総合的に比較することが重要です10。
- 検査結果が陽性であった場合、または強い症状(激しい腹痛や発熱など)がある場合は、自己判断せず、必ず医療機関を受診してください。
婦人科検査キット活用
「おりものの様子がいつもと違う気がする」「かゆみや臭いがつらいけれど、婦人科に行くのは恥ずかしい」と感じながらも、忙しさや抵抗感から受診を先延ばしにしてしまうことはめずらしくありません。自宅で使える検査キットが増えた今、「本当に信頼できるのか」「自分に合ったキットがどれなのか」「陽性だったらどうすればいいのか」と不安が重なり、かえって動けなくなってしまう方も多いでしょう。このガイドは、そうした戸惑いを少しでも軽くし、あなたが安心して一歩を踏み出せるように寄り添うことを目的としています。
まず押さえておきたいのは、検査キットは「病院に行かなくてよい魔法の道具」ではなく、あくまであなたの身体の状態を見える化するための入口だということです。月経や妊娠、更年期、がん検診など、ライフステージごとに変化する女性のからだの特徴を理解しておくと、検査結果の意味もより正確に読み解けます。そうした全体像は、年齢別に女性の健康課題を整理した総合ページで詳しく解説されていますので、長期的な健康管理の視点を持ちたい方は女性の健康ガイドも合わせて確認しておくと安心です。
おりものの色や量の変化、かゆみ、ヒリヒリ感、嫌な臭いといった症状の背景には、細菌性膣症やカンジダ膣炎のような膣内のバランスの乱れから、トリコモナス症などの性感染症まで、さまざまな原因が隠れています。見た目やにおいだけで自己判断すると、「カンジダだと思って市販薬で済ませたが、実は別の感染症だった」といった誤解につながりかねません。デリケートゾーンのかゆみやおりもの異常の代表的な原因や特徴については、医師監修で症状と治し方を整理したデリケートゾーンのかゆみ・おりもの異常の解説で、原因ごとの違いを一度整理しておくと良いでしょう。
自宅用の婦人科系検査キットを賢く使うための第一歩は、「今いちばん心配していることは何か」をはっきりさせることです。具体的な症状があるのか、特定の性行為後の感染が不安なのか、あるいは妊活の一環として腟内環境を確認したいのかによって選ぶべきキットは変わります。そのうえで、説明書をよく読み、自己採取の方法や検査可能な項目、結果が出るまでの日数、陽性時のサポート内容を事前に確認しましょう。自宅での自己観察のポイントや、市販検査キットを使う際の注意点、どのタイミングで病院受診に切り替えるべきかは、自宅でできる膣のセルフチェックガイドが具体的にまとめています。
次のステップとして重要なのは、「どのレベルの検査精度を求めるのか」を意識することです。症状のチェックリストやpH試験紙のみで自己診断するタイプは、目安としては便利ですが、病原体を特定することはできません。一方、自己採取した検体を登録衛生検査所に送り、NAATなどの分子検査で解析するタイプは、医療機関の検査に近い精度が期待できます。自分の不安や状況に合わせて、どこまで詳しく調べるべきかを考えるうえでは、症状・検査方法・費用・膣内フローラ検査などを横断的に整理した膣内感染症検査の完全ガイドを参考にすると、検査の選び方がぐっと整理しやすくなります。
ただし、自宅での検査だけに頼りきるのは危険な場合もあります。強い痛みや発熱、出血を伴うとき、繰り返し同じ症状をくり返すとき、パートナーにも症状が出ているときなどは、キット結果を待つより先に婦人科を受診することが大切です。また、膣内は「腟内フローラ」と呼ばれる菌のバランスで守られているため、自己判断での過度な洗浄や誤ったケアはかえって環境を乱してしまいます。デリケートゾーンケアの科学的な考え方は腟内フローラの解説や、炎症の原因と受診目安をまとめた婦人科の炎症に関するガイドも合わせて確認しておくと安心です。
婦人科系の検査キットは、「恥ずかしさや忙しさから受診を先延ばしにしてしまう」という現実と、「症状を放置したくない」という気持ちのあいだをつないでくれる頼もしいツールです。大切なのは、キットの精度や役割を正しく理解し、自分の目的に合ったものを選んだうえで、結果を今後の行動につなげること。必要なときにはためらわず医療機関に相談するという選択肢も持ちながら、自宅でできる一歩から、あなた自身の健康管理を少しずつ前向きに進めていきましょう。
【2025年最新】専門家が推奨する婦人科系検査キット・クイック比較表
多種多様な検査キットの中から、ご自身の目的に合ったものを迅速に見つけられるよう、JHO編集委員会が信頼性、実績、利用者の評判を基に厳選した製品を比較表にまとめました。詳細なレビューは後述しますが、まずはこの表で全体像を把握してください。
| 製品名 | 価格帯の目安 | 主な検査項目 | どのような方におすすめか | 専門家の評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
| STDチェッカー11 | 3,300円~ | STI全般(淋菌、クラミジア、梅毒、HIV等) | 完全な匿名性を最優先し、多様な検査項目から選びたい方。 | 登録衛生検査所による高精度な検査。プライバシー保護策が徹底しており、郵便局留めも可能。サポート体制も充実。 |
| ルナドクター (FemCHECK)12 | 8,780円~ | STI、細菌性腟症、カンジダ(最大21項目) | 陽性結果が出た場合に、迅速にオンライン診療と処方を受けたい方。 | 検査からオンライン診療、処方までが一体化したサービス。結果判明までのスピードが速い。 |
| ふじメディカル13 | 3,500円~ | STI全般(淋菌、クラミジア等) | コストパフォーマンスと結果の速さのバランスを求める方。 | 長年の実績を持つ老舗。迅速なプロセスと、コンビニや郵便局での受け取りオプションが魅力。 |
| Femcia(フェムシア)7 | 5,478円 | 膣内フローラ(細菌性腟症、カンジダ、善玉菌バランス) | 慢性的なおりものの臭いや状態に悩み、腟内の健康状態を包括的に知りたい方。 | 腟内環境のバランスを詳細なレポートで可視化。自分の体質を理解するのに役立つ。 |
| BELTA(ベルタ)14 | 9,980円 | 膣内フローラ(特に妊活サポートに特化) | 妊娠を計画している、または不妊治療中で、子宮内の環境を最適化したい方。 | 妊活に特化し、栄養士や胚培養士によるサポート体制が整っている点がユニーク。 |
婦人科系感染症の基礎知識:あなたの症状、原因は何?
正しい検査キットを選ぶためには、まずどのような種類の感染症があるのかを理解することが不可欠です。ここでは、女性が経験しやすい代表的な腟の感染症について、医学的知見に基づき解説します。
2.1. 日常で起こりやすい腟のトラブル(非STI)
性交渉の経験がなくても、体の抵抗力の低下や環境の変化によって誰にでも起こりうる感染症です。
| 感染症の種類 | おりものの特徴 | 臭い | かゆみ・痛み | 主な原因 |
|---|---|---|---|---|
| 細菌性腟症 (BV)15 | 水っぽく均一な、灰色がかった白色のおりもの | 生魚のような特有の強い臭い(アミン臭) | かゆみは通常ないか、あっても軽い | 善玉菌(乳酸桿菌)の減少と悪玉菌の増殖による腟内環境の乱れ |
| カンジダ腟炎16 | 白く濁り、カッテージチーズや酒粕、おから状のポロポロしたおりもの | 臭いはほとんどないことが多い | 耐え難いほどの強いかゆみ、灼熱感 | カンジダという常在真菌(カビ)の異常増殖 |
| トリコモナス腟炎 (STI)17 | 泡状で、黄緑色がかった悪臭の強いおりもの | 強い悪臭 | 強いかゆみ、外陰部の刺激感 | トリコモナス原虫という寄生虫による性感染症 |
細菌性腟症(Bacterial Vaginosis – BV)
これは厳密な意味での感染症ではなく、腟内の細菌バランスが崩れた状態(ディスバイオシス)を指します15。健康な腟内は乳酸桿菌(ラクトバチルス)によって酸性に保たれていますが、この善玉菌が減少し、ガードネレラ菌などの様々な嫌気性菌が増殖することで発症します。特徴的なのは、生魚のような臭いを伴う灰色のおりものです17。かゆみは少ないことが多いですが、放置すると他の性感染症にかかる危険性が高まったり、妊娠中の早産のリスクを高めたりすることが知られています1。驚くべきことに、約半数のケースでは症状が現れません18。
カンジダ腟炎(Vaginal Candidiasis)
カンジダは、皮膚や腸内にも存在する常在菌(カビの一種)ですが、ストレス、疲労、抗生物質の使用などで体の抵抗力が落ちた際に異常増殖して症状を引き起こします19。日本人女性の5人に1人が経験するとされるほど一般的な疾患です20。最も特徴的な症状は、外陰部の激しいかゆみと、カッテージチーズやおからに例えられるポロポロとした白いおりものです17。日本では、再発の場合に限り、一部の治療薬が市販薬(OTC医薬品)として薬局で購入可能です21。
2.2. 注意すべき性感染症(STI/STD)
性交渉によって感染する病気で、早期発見・早期治療が非常に重要です。特に、初期段階では無症状のことが多いため、自覚がないままパートナーに感染させてしまったり、病状が進行してしまったりする危険性があります。
- クラミジア感染症: 日本で最も報告数が多い性感染症です22。特に若い女性に多く、無症状のことが大半ですが、放置すると卵管炎などを引き起こし、不妊症や子宮外妊娠の原因となります。
- 淋菌感染症: クラミジアと同様に無症状が多いですが、おりものの増加や不正出血を引き起こすことがあります。咽頭(のど)に感染することもあります。
- トリコモナス腟炎: 上記の表でも触れましたが、これは性感染症に分類されます。感染者の70-85%が無症状とも言われ、自覚のない感染拡大が問題となっています23。治療の際は、パートナーも同時に治療することが鉄則です24。
- 梅毒: 近年、特に若い女性の間で感染者数が急増しており、社会的な問題となっています25。初期症状は性器や口の小さなしこりや潰瘍ですが、痛みがないため見過ごされやすく、治療しないと全身に深刻な影響を及ぼします。
- HIV(エイズ): ヒト免疫不全ウイルスへの感染です。感染初期に風邪のような症状が出ることがありますが、その後は無症状の期間が長く続きます。早期に発見し治療を継続すれば、発症を抑え、通常の生活を送ることが可能です。
2.3. なぜ検査が重要なのか?
これらの感染症を放置することは、単に不快な症状が続くだけではありません。骨盤内炎症性疾患(PID)を引き起こして激しい下腹部痛や発熱の原因となったり、卵管の癒着による不妊症や子宮外妊娠のリスクを高めたりします。また、細菌性腟症や他のSTIは、腟の防御機能を低下させ、HIVなどのより深刻なウイルスに感染するリスクを増大させることが科学的に証明されています1。症状がないから大丈夫、と自己判断せず、不安があれば検査を受けることが、あなた自身の未来と大切なパートナーの健康を守るために極めて重要です。
あなたに最適な検査キットの選び方【専門家による選択ガイド】
「どのキットを選べばいいの?」という疑問に答えるため、JHO編集委員会が3つのステップからなる選択ガイドを作成しました。このステップに従うことで、ご自身の状況に最も合った、信頼できる検査キットを見つけることができます。
ステップ1:目的を明確にする – あなたの主な心配事は何ですか?
まず、あなたがなぜ検査を受けたいのか、その目的をはっきりさせましょう。あなたの悩みに応じて、選ぶべきキットの種類は大きく異なります。
【あなたの悩みは?】選択フローチャート
Q. 主な心配事は何ですか?
A1.「かゆみ、臭い、おりもの異常など、具体的な症状がある」
→ 推奨:細菌性腟症、カンジダ、トリコモナスなどを調べられるキット(例:Femcia, ルナドクター)
A2.「症状はないが、特定の性交渉後に感染が不安」
→ 推奨:クラミジア、淋菌、梅毒、HIVなど主要なSTIを幅広く調べられるキット(例:STDチェッカー, ふじメディカル)
A3.「症状はないが、自分の健康状態を知りたい、または妊娠を考えている」
→ 推奨:善玉菌の割合など、腟内の細菌バランス全体を評価する「膣内フローラ検査」キット(例:BELTA, Femcia)
ステップ2:精度の違いを理解する – 最も重要な比較ポイント
市販の検査キットの「精度」を語る上で、絶対に知っておくべき決定的な違いがあります。それは、「自己採取・検査機関分析型」と「自己診断型」の違いです。
高信頼性(推奨):自己採取・検査機関分析型キット
これは、STDチェッカーやルナドクターなどの主要なキットが採用している方式です10。利用者は自宅で説明書に従って綿棒などで検体(おりものや尿)を採取し、それを郵送します。実際の分析は、国から認可を受けた「登録衛生検査所」の専門家が、核酸増幅検査(NAATs)のような高感度な分子生物学的技術を用いて行います526。複数の大規模な臨床研究により、この方法で患者が自己採取した検体の正確性は、医師がクリニックで採取した検体と同等であることが証明されています69。診断目的で利用するなら、このタイプのキットを選ぶことが絶対条件です。
参考程度:自己診断型キット
これは、利用者が自宅でpH試験紙や症状チェックリストを用いて、その場で自分で結果を判断するタイプのキットです。腟内のpHがアルカリ性に傾いているか(pH > 4.5)などを調べることはできますが、これは細菌性腟症やトリコモナス症を示唆する一つの兆候に過ぎず、両者を区別することはできません27。権威ある医学雑誌BMJに掲載された系統的レビューでは、症状に基づく自己診断の精度は低く(誤診率が50%に達することもある)、日常的な使用を推奨する科学的根拠は乏しいと結論付けられています2829。あくまで健康意識を高めるための初期的なスクリーニングツールと捉えるべきです。
ステップ3:その他の重要な要素を比較検討する
検査方法の次に、以下の4つのポイントを確認しましょう。
- プライバシーへの配慮: 家族や配達員に中身を知られたくない、というニーズに応えるため、各社は様々な工夫を凝らしています。外から中身が分からない無地の梱包はもちろん、「郵便局留め」や「コンビニ受け取り」、「ヤマト運輸営業所留め」が利用できるかを確認しましょう10。STDチェッカーのように、完全に匿名で検査が申し込めるサービスもあります30。
- 結果判明までのスピード: 不安な時間を少しでも短縮するため、スピードは重要な要素です。検体が検査所に到着してから「最短翌日」に結果がわかるサービスもあれば、2〜4日かかるサービスもあります10。注文から結果確認までの全工程にかかる時間を確認しましょう。
- 費用対効果: 価格は単項目で3,000円台から、複数項目をまとめた包括的なセットまで様々です10。単純な価格だけでなく、自分が調べたい項目がすべて含まれているか、1項目あたりのコストはいくらか、といった視点で比較検討することが賢明です。
- 陽性だった場合のサポート体制(アフターフォロー): これは信頼できるサービスを見極める上で非常に重要なポイントです。「検査して終わり」ではなく、陽性結果が出た場合にどうすればよいかを示してくれるかが問われます。多くの優良企業では、無料で電話相談に応じたり、提携している全国の医療機関を紹介してくれたりするサービスを提供しています10。ルナドクターのように、そのままオンライン診療で医師の診察を受け、薬を処方してもらえるサービスもあります12。
【詳細レビュー】目的別・おすすめ婦人科系検査キット10選
ここでは、比較表でご紹介した製品を中心に、それぞれの特徴をより深く掘り下げていきます。
4.1. 性感染症(STI)をしっかり調べたい方向け
STDチェッカー
概要: 性病検査キットの分野で高い知名度と実績を誇るブランド。最大12項目の幅広いSTIに対応し、利用者のニーズに合わせた多様なセットを提供しています。
長所: 最大の強みはプライバシー保護の徹底度。完全匿名での検査が可能で、郵便局留めにも対応しているため、誰にも知られずに検査を完結させたいというニーズに完璧に応えます。検査精度も登録衛生検査所によるNAAT法で非常に高いです。
短所: 他社と比較して、突出した短所は見当たりませんが、サービスがSTI検査に特化しているため、膣内フローラを調べたい場合は別のキットを選ぶ必要があります。
最適な方: プライバシーを何よりも重視する方、多くの項目から自分に必要なものだけを選んで検査したい方。
ルナドクター (FemCHECK)
概要: 検査からオンライン診療、ピルの処方までをシームレスに提供する、新しい形の遠隔医療サービスの一環です。
長所: 検査後のアクションが非常にスムーズ。陽性結果が出た場合、そのままアプリやウェブサイトを通じて医師の診察を受け、必要であれば抗生物質などの処方薬を配送してもらえるため、改めて病院を探して予約する手間が省けます。最大21項目という業界最多クラスの検査項目も魅力です。
短所: 利便性が高い分、単体の検査キットと比較すると価格帯はやや高めに設定されています。
最適な方: 陽性だった場合に、すぐにでも治療を開始したいと考えている方。忙しくて病院に行く時間がない方。
ふじメディカル
概要: 長年の運営実績を持つ、信頼性の高い郵送検査サービスの一つです。
長所: 迅速な対応に定評があり、検体返送から結果判明までがスムーズです。価格設定も比較的リーズナブルで、コストとスピードのバランスが取れています。コンビニ受け取りなど、受け取り方法の選択肢も豊富です。
短所: サポート体制はしっかりしていますが、ルナドクターのようなオンライン診療との直接連携はありません。
最適な方: 信頼できる老舗のサービスで、コストを抑えつつもスピーディーに結果を知りたい方。
4.2. 腟内の健康状態(膣内フローラ)を知りたい方向け
Femcia(フェムシア)
概要: 腟内の細菌バランスに着目した、新しいタイプの検査キット。細菌性腟症やカンジダのリスクレベルだけでなく、善玉菌であるラクトバチルスの割合まで詳細に分析します7。
長所: 検査結果が非常に詳細で分かりやすいレポートとして提供されます。「あなたの腟内はどのタイプ?」といった形で、専門的な内容を視覚的に理解しやすく工夫されています。慢性的なおりものの悩みの原因を探るのに役立ちます。
短所: STIの検査はできないため、性感染症の不安がある場合は別途検査が必要です。
最適な方: 特定の病気だけでなく、自分の体質や腟内環境そのものを理解し、日々のセルフケアに活かしたいと考えている方。
BELTA(ベルタ)
概要: 妊活・妊娠・産後ケアのブランドとして有名なBELTAが提供する、妊活に特化した膣内フローラ検査キットです14。
長所: 腟内だけでなく、子宮内の細菌叢が着床や妊娠維持に重要であるという最新の知見に基づいています8。検査結果に応じて、管理栄養士や胚培養士といった専門家からのアドバイスが受けられるという、手厚いサポート体制が最大の特徴です。
短所: 価格が高めですが、専門家による個別サポートが含まれていることを考慮すれば妥当とも言えます。
最適な方: 妊活中または不妊治療中で、あらゆる角度から妊娠の可能性を高めたいと真剣に考えている方。
よくある質問 (FAQ)
Q1. 自宅用検査キットの精度は本当に信頼できますか?
Q2. 検査結果が陽性だったら、どうすればいいですか?
まず、パニックにならずに落ち着いてください。検査結果が陽性であった場合は、必ず産婦人科や泌尿器科などの医療機関を受診してください。自己判断で放置したり、市販薬で対処しようとしたりしてはいけません。多くの検査キット提供会社は、提携医療機関の紹介や無料の電話相談といったサポートを提供していますので、まずはそちらに連絡してみるのも良いでしょう10。医師の診察を受けて、適切な治療を開始することが最も重要です。
Q3. 検査に健康保険は適用されますか?
いいえ、残念ながら自宅用の郵送検査キットは自費診療となり、健康保険は適用されません。ただし、検査結果が陽性となり、その後の治療のために医療機関を受診した際の診察や処方には、健康保険が適用されるのが一般的です。
Q4. これらのキットは薬局やドラッグストアで買えますか?
ほとんどのSTIや細菌性腟症を調べる検査キットは、プライバシー保護の観点からも、主にオンラインでの販売となります。薬局やドラッグストアで購入できるのは、主に「腟カンジダの再発治療薬(第1類医薬品)」や、妊娠検査薬、排卵日予測検査薬などです31。購入したいキットが決まっている場合は、各メーカーの公式サイトから直接申し込むのが確実です。
Q5. 生理中に検査を受けることはできますか?
いいえ、通常は生理中の検査は避けるべきです。経血が検体に混入すると、正確な検査結果が得られない可能性があるためです。ほとんどの検査キットでは、生理期間を避けて使用するように指示されています。検査を受ける際は、必ず説明書をよく読んで、適切なタイミングで検体を採取してください。
【重要】このような場合は、キットの使用より先に医療機関の受診を
自宅で使える検査キットは非常に便利ですが、万能ではありません。以下のような「危険信号(レッドフラグ)」が見られる場合は、キットの結果を待つのではなく、直ちに産婦人科を受診してください。自己判断は深刻な事態を招く可能性があります。
- 激しい下腹部痛や腰痛、高熱がある場合。(骨盤内炎症性疾患などの可能性があります)
- 妊娠している、またはその可能性がある場合。(妊娠中の感染症は胎児に影響を及ぼすことがあるため、専門医の管理が必須です)
- 不正出血がみられる場合。
- 以前にカンジダと診断され、市販の再発治療薬を使用しても症状が改善しない、またはすぐに再発を繰り返す場合。
- いずれかの検査キットで陽性結果を受け取った場合。(確定診断と治療方針の決定のため)
結論
女性特有のデリケートな悩みは、一人で抱え込みがちです。しかし、科学技術の進歩により、私たちは今、プライバシーを守りながら、自宅で高精度な健康チェックを行うという選択肢を手にしています。本記事で解説したように、重要なのは、数ある検査キットの中から、ご自身の目的と状況を正しく理解し、科学的根拠に基づいた信頼性の高い「自己採取・検査機関分析型」のキットを選ぶことです。そして、検査はゴールではなく、あくまでスタート地点に過ぎません。検査結果を正しく活用し、必要であればためらわずに専門医の助けを求めることが、あなた自身の健康を長期的に守るための最も賢明な行動です。あなたの健康は、あなた自身が主導権を握るべきものです。このガイドが、そのための確かで心強い一歩となることを、JHO編集委員会は心から願っています。
免責事項本記事は、医学的知識の提供を目的としており、専門的な医学的アドバイス、診断、または治療に代わるものではありません。健康上の懸念がある場合、または健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- Bacterial vaginosis [Internet]. World Health Organization (WHO); [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/bacterial-vaginosis
- Trichomoniasis – STI Treatment Guidelines [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention (CDC); [updated 2021 Jul 22; cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/trichomoniasis.htm
- 産婦人科 診療ガイドライン 婦人科外来編 2023 [Internet]. 日本産科婦人科学会; 2023 [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.jsog.or.jp/activity/pdf/gl_fujinka_2023.pdf
- 細菌性腟症 [Internet]. 日本性感染症学会; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://jssti.jp/pdf/guideline2008/02-8.pdf
- Manhart LE, et al. Clinical Validation of the Aptima Bacterial Vaginosis and Aptima Candida/Trichomonas Vaginitis Assays: Results from a Prospective Multicenter Clinical Study. J Clin Microbiol. 2020;58(5):e01643-19. doi:10.1128/jcm.01643-19. Available from: https://journals.asm.org/doi/10.1128/jcm.01643-19
- Jespers V, et al. Vaginitis: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician. 2018 Mar 1;97(5):321-329. Available from: https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/0301/p321.html
- 膣内フローラ検査キット(細菌性膣症・カンジダ等) [Internet]. Femcia; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://femcia.com/itemlist/kit/
- 妊活の鍵?注目が集まる「膣内の菌」を可視化する検査キットを発売 [Internet]. Femtech Press; 2022 Dec 15 [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://femtechpress.jp/26456/
- 女性の2人に1人が婦人科受診を後回しに。PMSや生理中の不調があっても「受診すべきかわからない」「医師に聞きたいことを質問できない」などの課題 | 株式会社ヘルスアンドライツのプレスリリース [Internet]. PR TIMES; 2021 May 26 [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000042562.html
- 女性用 性病検査キットおすすめ6選|即日対応 バレずに最短で結果 … [Internet]. yoku-mite.care; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.yoku-mite.care/qol_post/std-test-kit-woman/
- 女性ができる性病検査キット一覧 性病検査STDチェッカー – STD研究所 [Internet]. STD研究所; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.std-lab.jp/shopping/menu/search-kit.php?sch=woman&sort=2
- 【自宅で完結】郵送性病検査キット|ルナドクター【FemCHECK(フェムチェック)/STDCHECK】 [Internet]. ルナドクター; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://luna-dr.com/femcheck/
- 婦人科・産科|名古屋市緑区の内科、産婦人科 [Internet]. クリニック・ヤマシタ; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://clinic-yamashita.com/gynecology/ (Note: This links to a clinic page, the brand is ふじメディカル but no direct link was provided in the source for the brand itself, so a related contextual link is used.)
- 【公式】ベルタ膣内フローラ検査キット|自宅・WEBで完結 [Internet]. BELTA; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://belta.co.jp/goods/flora_check/
- 細菌性膣炎| プライベートクリニック高田馬場 [Internet]. プライベートクリニック高田馬場; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.private-clinic.jp/female/venereal/bacterial-vaginitis/
- 膣炎・外陰炎 | 名古屋栄・ココカラウィメンズクリニック [Internet]. ココカラウィメンズクリニック; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://cocokara-clinic.com/gynecological_disease/vaginitis_ventilitis/
- 膣炎 |大阪 梅田の内科・婦人科 – 西梅田シティクリニック [Internet]. 西梅田シティクリニック; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://nishiumeda.city-clinic.jp/symptoms/vaginitis/
- 【おりもの異常はこれが原因?】細菌性膣症を解説【約半数で再発 … [Internet]. 予防会; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://yoboukai.co.jp/article/1688
- 腟炎とは?トリコモナス腟炎・カンジダ腟炎・細菌性腟症などの原因、症状チェック法、受診の有無 [Internet]. えびねウィメンズクリニック; 2023 Aug 1 [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://ebine-womens-clinic.com/blog/14646
- 腟カンジダってどんな症状? – メディトリート [Internet]. 大正製薬; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://brand.taisho.co.jp/meditreat/candida/
- 腟外陰部のカンジダ症状に「エンペシドLクリーム」|製品情報 [Internet]. 佐藤製薬; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.empecid.jp/candida/products/cream/
- 性感染症の現状 – 性の健康医学財団 [Internet]. 性の健康医学財団; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.jfshm.org/%E6%80%A7%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%88%E6%80%A7%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%EF%BC%89/%E6%80%A7%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%81%AE%E7%8F%BE%E7%8A%B6/
- About Trichomoniasis [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention (CDC); [updated 2024 Jun 11; cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.cdc.gov/trichomoniasis/about/index.html
- 腟トリコモナス症 [Internet]. 日本性感染症学会; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://jssti.jp/pdf/guideline2008/02-7.pdf
- 【性病】梅毒感染増加 新規感染報告 国立感染症研究所 [Internet]. 食環境衛生研究所; 2024 Sep 2 [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.shokukanken.com/post-21352/
- Gaydos CA, et al. Clinical Evaluation of a New Molecular Test for the Detection of Organisms Causing Vaginitis and Vaginosis. J Clin Microbiol. 2023;61(4):e01748-22. doi:10.1128/jcm.01748-22. Available from: https://journals.asm.org/doi/10.1128/jcm.01748-22
- Evaluation of reliability of self-collected vaginal swabs over physician-collected samples for diagnosis of bacterial vaginosis, candidiasis and trichomoniasis, in a resource-limited setting: A cross-sectional study in India [Internet]. ResearchGate; [published 2019 Aug; cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/335447924_Evaluation_of_reliability_of_self-collected_vaginal_swabs_over_physician-collected_samples_for_diagnosis_of_bacterial_vaginosis_candidiasis_and_trichomoniasis_in_a_resource-limited_setting_A_cross-sec
- Bacterial vaginosis – Diagnosis and treatment [Internet]. Mayo Clinic; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bacterial-vaginosis/diagnosis-treatment/drc-20352285
- Heneghan C, et al. Accuracy of self-diagnosis in conditions commonly managed in primary care: diagnostic accuracy systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2023;13(1):e065748. doi:10.1136/bmjopen-2022-065748. Available from: https://bmjopen.bmj.com/content/13/1/e065748
- Core Concepts – Vaginitis – Self-Study Lessons [Internet]. National STD Curriculum; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.std.uw.edu/go/comprehensive-study/vaginitis/core-concept/all
- 自宅でできる郵送の性病検査キット|あおぞら研究所 [Internet]. あおぞら研究所; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://seibyou.net/
- 【2025年最新版】薬剤師が厳選!膣カンジダに効くドラッグストアで買えるおすすめの市販薬8選|選び方と注意点も解説 [Internet]. ミネイ薬品; [updated 2025 Mar 12; cited 2025 Jul 23]. Available from: https://store.mineiyakuhin.co.jp/blog/1121/
- 自宅で検査ができて料金も安い!性病検査キットのおすすめ8選 [Internet]. asai.clinic; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://asai.clinic/shinsaibashi/column/stdkit/
- 性病検査キット|自宅でできる性感染症(STD)検査の郵送キット|予防会 [Internet]. 予防会; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://yoboukai.co.jp/
- 女性用の性感染症(STD)・性病検査キット一覧 [Internet]. 予防会; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://yoboukai.co.jp/kit?category_id=1
- ロシュ・ダイアグノスティックス、女性の婦人科受診に関するグローバル意識調査を5か国で実施 [Internet]. ロシュ・ダイアグノスティックス日本; 2022 Apr 19 [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.roche-diagnostics.jp/media/releases/2022-4-19
- 女性のがん検診受診率に与える要因の分析 [Internet]. 東京大学; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.pp.u-tokyo.ac.jp/graspp-old/courses/2013/documents/graspp2013-5140331.pdf
- 医療における女性の人権擁護 – 一産婦人科受診に関する実態調査から一 [Internet]. 甲南女子大学; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.i-repository.net/il/user_contents/02/G0000632repository/ktk1999002.pdf
- フェムゾーンケア(デリケートゾーンケア)に関する調査2024 [Internet]. 株式会社アドバンスト・メディカル・ケア; 2024 Sep 10 [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.amcare.co.jp/wp-content/uploads/2024/09/PR_Femcare_survey_amc20240910-1.pdf
- フェムゾーンケア(デリケートゾーンケア)に関する調査2023 [Internet]. ILACY(アイラシイ); [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.ilacy.jp/femcare/post_2023102004.html
- 女性4,582人が回答。8割超が抱えるデリケートゾーン(陰部)のお … [Internet]. 花王株式会社; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.kao.com/jp/femcarelab/enq/result03/
- 「婦人科について」の調査結果~行こう、検診!3月1日~8日は「女性の健康週間」 [Internet]. PR TIMES; 2023 Feb 28 [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000247.000002943.html
- フェムテスト~ラクトバチルス~(膣内フローラチェッカー) [Internet]. 株式会社ビズジーン; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://visgene.com/product/femtest/
- 妊活の鍵?注目が集まる「膣内の菌」を可視化する検査キットを発売 [Internet]. PR TIMES; 2022 Dec 15 [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000070413.html
- Bacterial vaginosis treatment guidelines [Internet]. Melbourne Sexual Health Centre (MSHC); [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.mshc.org.au/health-professionals/treatment-guidelines/bacterial-vaginosis-treatment-guidelines
- 膣炎 – 浅草橋西口クリニックMo [Internet]. 浅草橋西口クリニックMo; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://asakusabashi-mo.jp/urology/vaginal-discharge
- About Bacterial Vaginosis (BV) [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention (CDC); [updated 2022 May 23; cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.cdc.gov/bacterial-vaginosis/about/index.html
- CG-LAB-22 Nucleic Acid Amplification Tests Using Algorithmic Analysis for the Diagnosis of Vaginitis [Internet]. Healthy Blue North Carolina Providers; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://provider.healthybluenc.com/medpolicies/healthybluenc/active/gl_pw_e001870.html
- 外陰炎、腟炎 | 症状、診断・治療方針まで – 今日の臨床サポート [Internet]. 今日の臨床サポート; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://clinicalsup.jp/jpoc/contentpage.aspx?diseaseid=1710
- Bacterial Vaginosis – CDC Diagnosis and Treatment Recommendations [Internet]. The ObG Project; 2016 Oct 16 [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.obgproject.com/2016/10/16/bv-cdc-diagnosis-treatment-recommendations/
- 細菌性腟症 – 22. 女性の健康上の問題 – MSDマニュアル家庭版 [Internet]. MSDマニュアル; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/22-%E5%A5%B3%E6%80%A7%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%B8%8A%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C/%E8%85%9F%E7%82%8E-%E5%AD%90%E5%AE%AE%E9%A0%B8%E7%AE%A1%E7%82%8E-%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E9%AA%A8%E7%9B%A4%E5%86%85%E7%82%8E%E7%97%87%E6%80%A7%E7%96%BE%E6%82%A3/%E7%B4%B0%E8%8F%8C%E6%80%A7%E8%85%9F%E7%97%87
- CQ1-08 カンジダ外陰膣炎の診断と治療は? [Internet]. みどりい医院; [cited 2025 Jul 23]. Available from: http://www.midorii-clinic.jp/img/100917_17.pdf
- 性器カンジダ症 [Internet]. 日本性感染症学会; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://jssti.jp/pdf/guideline2008/02-10.pdf
- くり返す外陰腟カンジダ症の原因は、ある習慣が関係しているかもしれません。 – 性病検査キット [Internet]. 予防会; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://yoboukai.co.jp/article/1461
- 腟カンジダ再発治療薬フレディ®CC1A(日本初!1回で効くタイプ)| ロート製薬: 商品情報サイト [Internet]. ロート製薬; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://jp.rohto.com/flady/fladycc/
- 【オキナゾール®L】腟カンジダの再発治療薬 – 田辺三菱製薬ヘルスケア [Internet]. 田辺三菱製薬; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://hc.mt-pharma.co.jp/site_okinazole/
- CQ1-07 トリコモナス膣炎の診断と治療は? [Internet]. みどりい医院; [cited 2025 Jul 23]. Available from: http://www.midorii-clinic.jp/img/100917_16.pdf
- トリコモナス腟炎の場合、主にどのような治療をしますか? – ユビー [Internet]. Ubie; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://ubie.app/byoki_qa/clinical-questions/h6hn4r9cc
- 症状だけでは性感染症は判断できない!~半数以上の感染者に症状がでないトリコモナス症について~ [Internet]. いだてんクリニック; 2023 Nov 20 [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://idaten.clinic/blog/about-trichomoniasis/
- State of the Art for Diagnosis of Bacterial Vaginosis. PMC. 2023;10446871. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10446871/
- Improving the Diagnosis of Vulvovaginitis: Perspectives to Align … [Internet]. PMC; 2020 Oct 21 [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7591372/
- Accuracy of Vaginal Symptom Self-Diagnosis Algorithms for Deployed Military Women [Internet]. PMC; 2010 Jul 13 [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2902763/
- Accuracy of self- diagnosis in conditions commonly managed in primary care – BMJ Open [Internet]. BMJ Open; 2023 Jan 24 [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/13/1/e065748.full.pdf
- 性感染症に関する特定感染症予防指針の改正に向けた 検討について [Internet]. いわき市; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1747183846004/simple/hyaku.pdf
- lis や嫌気性菌の検出など)が伴えば一層確実である。 む しろBVの実用的でかつ迅速な診断法としては、 膣内容 の鏡検 (グラム染色) 所見と性状検査とを併せた判定法 [Internet]. WAM NET; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.wam.go.jp/wamappl/bb11gs20.nsf/0/3df5daded8d03849492570290009abce/$FILE/s5-8~11.pdf
- 15H05296 研究成果報告書 [Internet]. KAKEN; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://kaken.nii.ac.jp/en/file/KAKENHI-PROJECT-15H05296/15H05296seika.pdf
- 健康な日本人女性の腟内細菌叢を4タイプに分類-北里大ほか … [Internet]. QLifePro; 2025 Apr 18 [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.qlifepro.com/news/20250418/vaginal-microbiota.html
- カンジダ膣炎 – まつなが産科婦人科 福山市 [Internet]. まつなが産科婦人科; [cited 2025 Jul 23]. Available from: http://mybee.or.jp/56
- 【調査結果】デリケートゾーンの悩みと膣内フローラとの関係が明らかに! [Internet]. PR TIMES; 2023 Apr 12 [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000054718.html
- 婦人科 – 医療法人 恵仁会 田中病院 [Internet]. 田中病院; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://www.tanaka-hsp.or.jp/department/gynecology/
- 萎縮性腟炎 | 症状、診断・治療方針まで – 今日の臨床サポート [Internet]. 今日の臨床サポート; [cited 2025 Jul 23]. Available from: https://clinicalsup.jp/jpoc/contentpage.aspx?diseaseid=1761