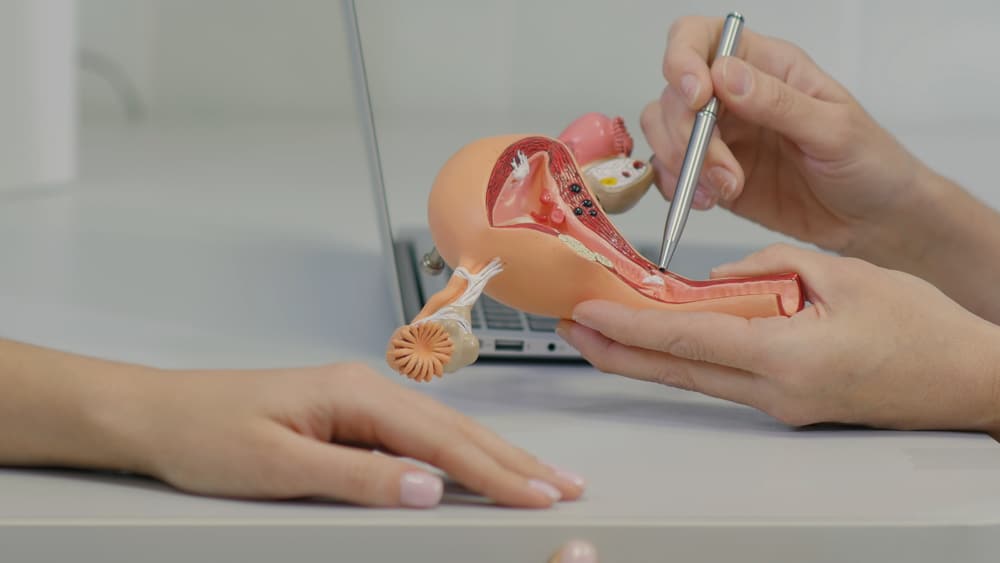この記事の科学的根拠
この記事は、引用元として明示された最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下は、参照された情報源と、提示された医学的指導との直接的な関連性です。
- 公益社団法人 日本産科婦人科学会 (JSOG): 本記事における子宮内膜症、月経困難症、不妊症に関する標準的な診断・治療法に関する記述は、同学会が発行する『産婦人科診療ガイドライン』に基づいています1234。
- 特定非営利活動法人 日本婦人科腫瘍学会 (JSGO): 子宮内膜増殖症および子宮体がんの診断、病期分類、標準治療、妊孕性温存療法に関する推奨事項は、同学会の『子宮体がん治療ガイドライン』を根拠としています578。
- 一般社団法人 日本生殖医学会 (JSRM): 不妊症の原因となる子宮内膜の因子、着床障害、そして生殖補助医療(ART)に関する解説は、同学会の見解および資料を参考にしています910。
- 国立研究開発法人 国立がん研究センター (NCC): 子宮体がんにかかる罹患率や死亡率などの統計データは、同センターのがん情報サービスの公表データに基づいています1213。
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) および Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG): 子宮内膜増殖症や子宮体がんに関する国際的な標準治療や管理指針については、それぞれ米国の産婦人科医会(ACOG)1719および英国の王立産婦人科医会(RCOG)2021が発行するガイドラインを参照し、日本の状況と比較・補完しています。
【重要】本記事は医学的情報の提供を目的としており、自己診断を促すものではありません。気になる症状がある場合は、必ず産婦人科専門医にご相談ください。
要点まとめ
- 子宮内膜は女性ホルモンの影響で周期的に厚さを変え、妊娠に備える重要な組織です。閉経後の内膜の肥厚は注意が必要です。
- 年々ひどくなる月経痛や不妊は「子宮内膜症」の兆候かもしれません。これは生殖年齢女性の約10%に見られる一般的な疾患です4。
- 不正出血、特に閉経後の出血は「子宮体がん」の最も重要な警告信号です。子宮体がんは50代から60代に多く、日本の婦人科がんで最も罹患数が多いがんです13。
- 「子宮内膜異型増殖症」は、子宮体がんの前がん病変であり、診断された時点でがんが併存している可能性もあるため、子宮全摘出術が標準治療とされます26。
- 治療法は疾患、進行度、年齢、そして妊娠希望の有無で大きく異なります。日本の公的保険制度や高額療養費制度を理解し、医師と相談して最適な選択をすることが重要です。
子宮内膜の不調サイン
「たかが生理痛」「年齢のせい」と思い込み、強い月経痛や閉経後の少量出血、不妊の悩みを一人で抱え込んでいませんか。子宮内膜はホルモンの影響で毎月厚さや性質が大きく変化する繊細な組織だからこそ、その小さな変化が将来の健康に関わる重要なサインになることがあります。この記事で説明されているように、年々悪化する生理痛や不正出血、原因のはっきりしない不妊は、放置すべきではない「子宮内膜からのメッセージ」です。不安や恥ずかしさがあっても、あなたの違和感にはきちんと向き合って大丈夫です。
まずは、自分の子宮内膜が「正常な周期的変化」の範囲なのか、それとも病気のサインを示しているのかを冷静に整理することが第一歩です。そのためには、月経周期ごとの厚さの変化、ライフステージ(思春期〜性成熟期〜更年期・閉経後)による違い、そして内膜を評価する検査(経腟超音波・子宮鏡・MRI・生検)について全体像をつかんでおくと安心です。女性の体は月経だけでなく妊娠・出産・更年期と一生を通じて変化していくため、ライフステージごとの基礎知識を押さえておくと、気になる症状が出たときにも判断しやすくなります。こうした全体像は、女性の健康ガイドでライフステージ別に整理されている基礎情報と合わせて確認しておくと、子宮内膜のトラブルをより俯瞰して理解しやすくなります。
子宮内膜のトラブルといっても、その背景にはいくつか代表的な病気があります。生殖年齢の女性で多いのが、子宮の外(卵巣・腹膜など)に内膜と似た組織が増殖する子宮内膜症で、年々悪化する月経痛や性交時痛、不妊の原因として知られています。また、エストロゲンの刺激が長く続くことで内膜が異常に厚くなり、前がん病変になりうる子宮内膜増殖症や、その先に位置づけられる子宮体がんも重要です。さらに、ポリープなどの良性病変や、慢性的な炎症が不正出血や着床障害の原因になることもあります。この記事で触れられているような月経痛・不妊・不正出血が気になる場合には、まずは子宮内膜症について体系的に整理された子宮内膜症のすべてを読み比べながら、自分の症状との共通点を整理してみると理解が深まります。
次のステップとして大切なのは、「内膜が厚いと言われた」「閉経後なのに内膜が肥厚している」といった検査結果を、漠然とした不安のままにせず具体的に確認することです。記事でも説明されているように、閉経後に超音波で5mmを超える内膜肥厚が見つかったり、不正出血を伴う場合には、子宮内膜増殖症や子宮体がんの可能性も視野に入れた精密検査が勧められます。その際、病理診断で「異型」があるかどうかによって、将来のがんリスクや標準治療(子宮全摘出術を含む)が大きく変わる点を理解しておくことが重要です。検査で内膜増殖症を指摘されたり、今後の治療方針について主治医とじっくり相談したいと感じたら、WHO分類や日本のガイドラインに沿って整理された子宮内膜増殖症の全貌を参考にすると、診察室での質問もしやすくなるでしょう。
一方で、症状として最もわかりやすいサインが「不正出血」です。特に記事で強調されているように、閉経後のわずかな出血であっても、量や回数にかかわらず子宮体がんの重要な警告信号になりえます。また、閉経前でも周期が大きく乱れている、生理以外の時期に出血が続く、月経量が急に増えたといった場合には、内膜の病変やホルモン異常など複数の要因が絡んでいる可能性があります。まずは出血のタイミング・量・期間をメモし、どのようなパターンが「要受診のサイン」なのかを知っておくと、受診の目安が明確になります。不正出血という症状自体について整理したいときは、原因と受診のポイントをまとめた不正出血の原因と対策を一緒に確認しておくと安心です。
さらに注意したいのは、「内膜が厚い=すぐにがん」というわけではない一方で、自己判断で様子見を続けることは危険だという点です。実際には、子宮内膜ポリープのように良性の隆起性病変が不正出血や着床障害の原因になっているケースもあり、その多くは子宮鏡下手術で切除することで改善が期待できます。また、がんや前がん病変かどうかを最終的に判断するには、記事でも述べられているように子宮内膜生検による病理診断が不可欠です。どのようなポリープが治療対象になるのか、あるいは生検の目的や流れ・リスクを事前に理解しておきたい場合には、内膜の良性病変を詳しく解説した子宮内膜ポリープのすべてや、具体的な検査手順をまとめた子宮内膜生検の包括的ガイドを読んでおくと、検査や治療への不安が和らぎやすくなります。
子宮内膜は、月経痛・不正出血・不妊といった形で、あなたの体の変化を静かに教えてくれる存在です。我慢や自己判断で時間を過ごすのではなく、「いつもと違う」「説明のつかない症状が続く」と感じた時点で、早めに産婦人科で相談することが、未来の健康と妊よう性、そして生活の質を守る最善の一歩になります。この記事で得た知識を土台に、自分の症状を整理し、必要な検査や治療について医師と対話しながら、一緒に最適な選択肢を探していきましょう。
第1部:子宮内膜の基礎知識 – あなたの体を理解する第一歩
1-1. 子宮内膜とは? – 妊娠を育む奇跡のベッド
子宮内膜とは、子宮の内側を覆っている、厚さが数ミリメートル程度の粘膜組織です。その最大の役割は、受精卵が着床し、成長するための「ベッド」となることです。このベッドは、構造的に二つの層に分かれています。一つは子宮の筋層側にあり、月経では剥がれ落ちない「基底層」、もう一つはその上にあり、毎月ホルモンの影響で増殖と剥離を繰り返す「機能層」です。
1-2. 月経周期と子宮内膜の厚さの変化 – ホルモンのオーケストラ
子宮内膜は、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)という二つの主要な女性ホルモンの影響を受け、その厚さを劇的に変化させます。この周期的な変化を理解することは、ご自身の体のリズムを知る上で非常に重要です。
- 月経期(生理中):厚さ 約2~4mm
妊娠が成立しなかった場合、機能層が剥がれ落ちて血液とともに体外へ排出されます。これが月経です。この時期、子宮内膜は最も薄くなります。 - 増殖期(月経後~排卵前):厚さ 約5~11mm
月経が終わると、卵巣から分泌されるエストロゲンの作用により、基底層から新しい機能層が再生され、増殖を始めます。排卵が近づくにつれて内膜は厚くなり、排卵直前には10mmを超える厚さに達することもあります。 - 分泌期(排卵後~月経前):厚さ 最大16mm程度
排卵後、今度はプロゲステロンの作用が優位になります。これにより内膜はさらに厚く、柔らかくなり、血管や分泌腺が発達します。これは受精卵が着床しやすいように栄養を豊富に蓄えた「ふかふかのベッド」の状態です。
1-3. ライフステージによる変化
子宮内膜の状態は、女性のライフステージによっても変化します。
- 思春期前: ホルモンの分泌がまだ活発でないため、内膜は薄く非活動的な状態です。
- 性成熟期: 上記で説明した周期的な増殖と剥離を毎月繰り返します。
- 更年期・閉経後: 卵巣機能が低下し、ホルモンの分泌が停止するため、内膜は萎縮し薄くなります。日本産科婦人科学会のガイドラインによると、閉経後の内膜の厚さは通常5mm以下とされており、これを超える厚さが超音波検査で見られる場合は、後述する子宮内膜増殖症や子宮体がんなどの疾患の可能性を考慮し、精密検査が必要となることがあります2。
1-4. 子宮内膜を調べる検査
子宮内膜の状態を評価するためには、以下のような検査が行われます。
- 経腟超音波(エコー)検査: 産婦人科で行われる最も基本的な検査です。プローブと呼ばれる細い器具を腟内に挿入し、子宮や卵巣の状態を観察します。子宮内膜の厚さや均一性、子宮筋腫や子宮内膜ポリープの有無などを評価することができます。
- 子宮鏡検査(ヒステロスコピー): 細い内視鏡を子宮口から挿入し、子宮の内部を直接モニターで観察する検査です。超音波検査で疑われた病変を詳細に確認したり、ポリープを切除したり、確定診断のために組織の一部を採取(生検)したりすることができます。
- MRI検査: 磁気を利用して体の断面を撮影する検査です。特にがんが疑われる場合に、その広がり(深達度)やリンパ節への転移の有無など、より詳細な情報を得るために用いられます。
第2部:子宮内膜に関連する主な疾患 – 症状から原因まで
2-1. 子宮内膜症 – 月経痛の陰に潜む病
定義: 子宮内膜またはそれに似た組織が、何らかの原因で子宮の内側以外の場所(例えば卵巣、卵管、腹膜、腸など)で発生し、増殖する疾患です4。これらの組織も月経周期に合わせて増殖と出血を繰り返しますが、体外に排出される出口がないため、炎症や周囲の組織との癒着を引き起こし、様々な痛みの原因となります。
日本の現状: 日本産科婦人科学会によると、子宮内膜症は生殖年齢女性の約10%に存在すると推定されており、非常に身近な病気です4。初経年齢の低下や晩婚化・少子化により、生涯における月経回数が増加したことが、患者数の増加に関連していると考えられています34。
主な症状:
- 痛み: 最も代表的な症状は、年々悪化していく月経痛です。その他にも、月経時以外の下腹部痛や腰痛、性交時痛、排便時痛など、多彩な痛みを引き起こします。
- 不妊: 子宮内膜症を持つ女性の約30%から50%が不妊に悩むと報告されています4。卵管の癒着による卵子のピックアップ障害や、炎症性物質による着床環境の悪化などが原因と考えられています。
代表的な病態: 卵巣に発生した子宮内膜症は、内部に古い血液が溜まって嚢胞(のうほう)を形成し、「卵巣チョコレート嚢胞」と呼ばれます。これは不妊の原因となるだけでなく、まれにがん化する危険性もあるため、定期的な経過観察が重要です。
2-2. 子宮内膜増殖症 – 子宮体がんの前段階となりうる状態
定義: 主にエストロゲン(卵胞ホルモン)の持続的かつ過剰な刺激により、子宮内膜が異常に厚く増殖する状態です。不正出血の主な原因の一つであり、この疾患は細胞に「異型」があるかないかによって、がん化する危険性が全く異なります。
- ① 異型のない子宮内膜増殖症: 細胞にがんを疑わせるような顔つきの変化(異型)がないタイプです。がん化する危険性は低く、英国王立産婦人科医会(RCOG)のガイドラインによれば、20年間でがんへ進行する割合は5%未満とされています21。多くは自然に治癒するか、ホルモン療法によって改善が期待できます。
- ② 子宮内膜異型増殖症: こちらは極めて重要な状態です。細胞に明らかな異型を認めるタイプで、子宮体がんの前がん病変として扱われます。日本婦人科腫瘍学会のガイドラインによると、この状態と診断された時点で、すでに子宮体がんが隠れている(併存している)可能性が17%から52%あると報告されており、放置すると高い確率でがんに進行します26。
リスク因子: 肥満(脂肪組織でエストロゲンが作られるため)、排卵がうまくいかない状態(多嚢胞性卵巣症候群など)、出産経験がないこと、乳がんの治療薬であるタモキシフェンの長期服用などが知られています。
2-3. 子宮体がん(子宮内膜がん) – 閉経後の出血は最重要サイン
定義: 子宮体部の内膜から発生するがんであり、子宮内膜がんとも呼ばれます。そのほとんどは、子宮内膜増殖症と同様にエストロゲンの影響が背景にあると考えられています。
日本の現状: 国立がん研究センターの最新統計によると、2021年に日本で新たに19,071人が子宮体がん(子宮内膜がん)と診断され、婦人科がんの中では最も罹患数が多いがんです13。年齢的には50代から60代に発症のピークがあり、閉経期前後の女性にとって特に注意が必要な疾患です。
最大の危険信号: 最も重要で頻度の高い症状は「不正性器出血」です。特に「閉経後の不正出血」は、量の多少にかかわらず、たとえ一度きりであっても子宮体がんを疑うべき最も重要なサインです12。閉経前であっても、月経不順が続いたり、月経以外の時期に出血したりする場合は注意が必要です。
リスク因子: 子宮内膜異型増殖症の存在が最大のリスクですが、その他にも肥満、糖尿病、高血圧、出産経験がないこと、そして遺伝的要因(リンチ症候群など)が知られています19。
第3部:診断プロセス – 正確な状態把握のために
子宮内膜の疾患が疑われる場合、正確な診断を下すために段階的な検査が行われます。まず問診で症状(出血の時期や量、痛みの程度など)を詳しく聞き、内診で子宮や卵巣の状態を触診します。その後、第1部で述べた経腟超音波検査で内膜の厚さなどを視覚的に評価します。異常が疑われれば、子宮内膜の細胞や組織を採取して、がん細胞や異型細胞の有無を顕微鏡で調べる「組織診」が確定診断のために不可欠です。子宮内膜症が疑われる場合は、血液検査で腫瘍マーカー(CA125など)を測定したり、MRI検査で病巣の広がりを確認したりします。最終的な確定診断や癒着の程度の評価には、腹腔鏡検査が必要となることもあります。
第4部:治療法の徹底解説 – あなたに合った選択肢とは
治療法は、疾患の種類、進行度(ステージ)、年齢、全身の状態、そして何よりも「将来的に妊娠を希望するかどうか(妊孕性温存の希望)」によって大きく異なります。ここでは日本の標準的な治療法を、保険適用の情報と合わせて解説します。
4-1. 子宮内膜症の治療
治療の主な目的は、痛みを和らげて生活の質(QOL)を改善することと、不妊の原因を取り除くことです。
- 薬物療法(ホルモン療法): 痛みの管理が主目的の場合に行われます。エストロゲンの分泌を抑え、子宮内膜症組織の増殖を抑制します。低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬(LEP製剤、いわゆる低用量ピル)や、黄体ホルモン製剤(ジエノゲスト)が第一選択薬として広く用いられます3。これらは長期間の服用が可能で、保険も適用されます30。より強力な偽閉経療法(GnRHアゴニスト)は、骨密度の低下などの副作用があるため、原則として6ヶ月までの短期的な使用に限られます。
- 手術療法: 薬物療法で痛みが改善しない場合や、卵巣チョコレート嚢胞が一定以上の大きさ(一般的に4cm以上)になった場合、あるいは不妊の原因となっていると考えられる場合に検討されます。現在では、体の負担が少ない腹腔鏡下手術が主流です。手術では、病巣の切除や癒着の剥離が行われます。
- 不妊を伴う場合: 薬物療法は排卵を止めてしまうため、妊娠を希望する場合には行われません。不妊治療としては、手術で癒着を剥がして自然妊娠の可能性を高めるか、体外受精などの生殖補助医療(ART)を積極的に検討します。欧州生殖医学会(ESHRE)の最新ガイドラインでも、不妊を伴う子宮内膜症に対する治療戦略が示されています22。
4-2. 子宮内膜増殖症の治療
治療方針は「異型」の有無で全く異なります。
- 異型のない場合: がん化のリスクが低いため、定期的な経過観察が基本となります。不正出血が続く場合や、将来のがん化リスクをさらに低減させたい場合には、黄体ホルモン療法が行われます。この治療には、内服薬のほか、子宮内に薬剤を放出する器具(黄体ホルモン放出IUD、製品名:ミレーナ)が有効とされています。ただし、日本ではミレーナは「過多月経」や「月経困難症」の病名では保険適用となりますが、「子宮内膜増殖症」の治療目的では保険適用外となります(2025年現在)。
- 異型のある場合(子宮内膜異型増殖症): がんが併存している可能性や、将来的に高い確率でがんに進行するリスクがあるため、標準治療は「単純子宮全摘出術」です5。これが、がんのリスクを根治させる最も確実な方法です。妊孕性温存療法: 将来の妊娠を強く希望する若年の患者さんで、厳格な基準(がんが内膜にとどまっていると強く推定されるなど)を満たす場合に限り、選択肢として高用量の黄体ホルモン療法が行われることがあります。これは非常に特殊な治療であり、治療効果が得られた後には、速やかな不妊治療(体外受精など)が推奨されます26。
4-3. 子宮体がんの治療
子宮体がんの治療の基本は手術です。手術によって、がんの進行期(ステージ)を正確に確定し、その後の追加治療の方針を決定します。
- 手術療法: 基本的な術式は「単純子宮全摘出術+両側付属器(卵巣・卵管)切除術」です。多くの場合、骨盤内や傍大動脈のリンパ節に転移がないかを確認するために、リンパ節郭清(またはリンパ節生検)も同時に行われます。
- 低侵襲手術: ごく早期のがん(IA期)と診断された場合には、患者さんの体の負担を軽減するため、腹腔鏡下手術やロボット支援下手術が保険適用で行われています3132。
- 術後療法: 手術で摘出した組織の病理検査の結果、再発のリスクが高いと判断された場合には、再発を予防するために化学療法(抗がん剤)、放射線治療、ホルモン療法、あるいは近年では免疫チェックポイント阻害薬などの薬物療法が追加されます。
【重要】治療にかかる費用と公的保険制度
医療費は大きな不安要素ですが、日本の公的医療保険制度と、高額な医療費の負担を軽減する「高額療養費制度」について理解しておくことが大切です。
| 疾患 | 主な治療法 | 保険適用 | 費用の目安(3割負担) | 高額療養費制度 |
|---|---|---|---|---|
| 子宮内膜症 | 低用量ピル(LEP)/ ジエノゲスト | 〇 | 月3,000~10,000円程度 | 対象外 |
| 子宮内膜症 | 腹腔鏡下手術(嚢胞摘出など) | 〇 | 約15~30万円 | 対象 |
| 異型のない内膜増殖症 | 黄体ホルモン療法(内服) | 〇 | 治療内容による | 対象外 |
| 異型のない内膜増殖症 | ミレーナ挿入 | × (この病名では) | 約4~6万円(自費) | 対象外 |
| 異型のある内膜増殖症 / 子宮体がん | 子宮全摘出術(腹腔鏡/ロボット) | 〇 | 約30~50万円 | 対象 |
| 異型のある内膜増殖症 / 子宮体がん | 子宮全摘出術(開腹) | 〇 | 約25~40万円 | 対象 |
| 子宮体がん | 化学療法・放射線治療 | 〇 | 治療内容による | 対象 |
高額療養費制度とは?
1ヶ月(月の初めから終わりまで)の医療費の自己負担額が、年齢や所得によって定められた上限額を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。例えば、年収が約370~770万円の方の場合、自己負担の上限額は約8万円強となります。手術や化学療法などで高額な医療費が見込まれる場合は、事前にご加入の健康保険組合に限度額適用認定証の申請をしておくと、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。詳しくはご加入の公的医療保険の窓口にご確認ください14。
第5部:妊娠・不妊との深い関わり
子宮内膜は、妊娠の成立に不可欠な役割を果たします。受精卵が着床するためには、子宮内膜が適切な厚さを持ち、受精卵を受け入れる準備が整っている必要があります。この「着床の窓」と呼ばれる最適なタイミングは非常に短いです。子宮内膜に関連する疾患は、この繊細なプロセスに様々な形で影響を与え、不妊の原因となります。
- 菲薄内膜: ホルモンバランスの乱れや血流不全などにより、子宮内膜が十分に厚くならない状態です。着床に必要な厚さ(一般的に8mm以上)に達しない場合、着床障害の原因となることがあります。
- 慢性子宮内膜炎: 子宮内膜に持続的な炎症が起こっている状態です。自覚症状はほとんどありませんが、免疫系の異常を引き起こし、受精卵を異物として攻撃してしまうことで着床を妨げ、不妊や流産の原因となることが知られています。
- 子宮内フローラ: 近年の研究で、子宮内にも細菌叢(フローラ)が存在し、そのバランスが妊娠の成否に関わっていることがわかってきました。ラクトバチルス属の菌が優位な状態が、着床に適した環境であるとされています16。
- 疾患と不妊治療: 子宮内膜症は癒着や炎症で、子宮筋腫やポリープは内膜の変形で着床を妨げます。これらの疾患が不妊の原因と考えられる場合、手術療法や体外受精などの生殖補助医療(ART)が積極的に検討されます。日本生殖医学会からも、不妊症に関する情報が提供されています9。
結論:自分の体と向き合い、適切な医療へ
子宮内膜は、あなたのライフステージや健康状態を映し出す鏡です。月経痛、不正出血、不妊といった悩みは、決して「よくあること」と軽視したり、一人で抱え込んだりするものではありません。この記事を通じてご自身の体への理解を深め、気になる症状があれば、ためらわずに産婦人科の扉を叩いてください。日本の医療制度は、科学的根拠に基づいた標準治療を保険診療で提供しています。専門医との対話を通じて、ご自身にとって最善の道を見つけることができます。早期発見・早期治療が、あなたの未来の健康とQOL(生活の質)を守るための最も確実な一歩となるのです。
よくある質問
子宮内膜が厚いと言われました。がんの可能性は?
超音波検査で「内膜が厚い」と指摘されただけでは、すぐにがんと決まるわけではありません。重要なのは、不正出血などの症状の有無、年齢(閉経前か後か)、そして最終的には組織を採取して調べる「組織診」の結果で判断される「異型」の有無です。閉経後で内膜の厚さが5mmを超える場合や、不正出血がある場合は、がんの可能性も否定できないため、必ず精密検査として組織検査を受ける必要があります2。
チョコレート嚢胞は手術しないとダメですか?
必ずしも全てのチョコレート嚢胞が手術を必要とするわけではありません。治療方針は、嚢胞の大きさ、症状(痛みの強さなど)、年齢、そして妊娠希望の有無を総合的に考慮して決定されます。例えば、嚢胞が比較的小さく(一般的に4cm未満)、痛みが薬でコントロールできている場合は、定期的に経過観察をすることもあります。しかし、嚢胞が大きい場合、痛みが強い場合、あるいは破裂やがん化のリスクが疑われる場合には手術が推奨されます3。
子宮体がん検診は受けた方がいいですか?
現在、日本において、症状のない一般女性を対象とした子宮体ががんの対策型検診(公的な検診)は推奨されていません。これは、有効性を判断する証拠が不十分なためです。しかし、これは「検診を受けなくてよい」という意味ではありません。不正出血(特に閉経後)、月経不順といった何らかの症状がある場合や、肥満、糖尿病、がんの家族歴など、子宮体がんのリスク因子がある方は、積極的に産婦人科を受診し、医師と相談の上で検査を受けることが強く推奨されます12。
免責事項本記事は、医学的知識の普及・啓発を目的とするものであり、専門的な医療アドバイスに代わるものではありません。ご自身の健康状態に関する懸念や、治療に関する決定を下す前には、必ず資格を有する医療専門家にご相談ください。
参考文献
- 公益社団法人 日本産科婦人科学会. Wikipedia. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%94%A3%E7%A7%91%E5%A9%A6%E4%BA%BA%E7%A7%91%E5%AD%A6%E4%BC%9A
- 日本産科婦人科学会, 日本産婦人科医会. 産婦人科 診療ガイドライン―婦人科外来編2020. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://minds.jcqhc.or.jp/common/summary/pdf/c00571.pdf
- 公益社団法人 日本産科婦人科学会. ガイドライン. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://www.jsog.or.jp/medical/410/
- 公益社団法人 日本産科婦人科学会. 子宮内膜症. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://www.jsog.or.jp/citizen/5712/
- 日本婦人科腫瘍学会. 子宮体がん治療ガイドライン 2023年版 第5版. 金原出版; 2023. Available from: https://www.kanehara-shuppan.co.jp/books/detail.html?isbn=9784307301558
- 公益社団法人 日本婦人科腫瘍学会. 子宮頸癌治療ガイドライン2022年版. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://jsgo.or.jp/guideline/keiganguide2022.html
- 日本婦人科腫瘍学会. 子宮体がん治療ガイドライン 2023年版. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00784/
- 公益社団法人 日本婦人科腫瘍学会. 子宮体がん. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://jsgo.or.jp/public/taigan.html
- 一般社団法人日本生殖医学会. 一般のみなさまへ. 2025年6月25日閲覧. Available from: http://www.jsrm.or.jp/public/
- 一般社団法人日本生殖医学会. 2025年6月25日閲覧. Available from: http://www.jsrm.or.jp/
- 日本生殖内分泌学会. 子宮内膜症と不妊症. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://jsre.umin.jp/19_24kan/6-topix1.pdf
- 国立がん研究センター がん情報サービス. 子宮体がん(子宮内膜がん). 2025年6月25日閲覧. Available from: https://ganjoho.jp/public/cancer/corpus_uteri/index.html
- 国立がん研究センター がん情報サービス. がん統計 子宮体部. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/cancer/18_corpus_uteri.html
- 厚生労働省. 医療機能情報提供制度について. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html
- 厚生労働省. 外来(その3). 2025年6月25日閲覧. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000575554.pdf
- 厚生労働科学研究費補助金. 患者さんのための 生殖医療ガイドライン. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202327003B-sonota1.pdf
- The American College of Obstetricians and Gynecologists. FIGO.org. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://www.figo.org/american-college-obstetricians-and-gynecologists
- AAFP. ACOG Updates Guideline on Diagnosis and Treatment of Endometriosis. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2011/0101/p84.html
- Society of Gynecologic Oncology. PRACTICE BULLETIN No. 149: Endometrial Cancer. 2015. PMID: 25798986. Available from: https://www.sgo.org/wp-content/uploads/2015/03/PB-149-Endometrial-Cancer-GJ-w_links-2.pdf
- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Wikipedia. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_College_of_Obstetricians_and_Gynaecologists
- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Management of Endometrial Hyperplasia (Green-top Guideline No. 67). 2016. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/management-of-endometrial-hyperplasia-green-top-guideline-no-67/
- European Society of Human Reproduction and Embryology. ESHRE Guideline: Endometriosis. 2022. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://www.eshre.eu/guideline/endometriosis
- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Endometriosis: Investigation and Management (Green-top Guideline No. 24). 2025年6月25日閲覧. Available from: https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/endometriosis-investigation-and-management-green-top-guideline-no-24/
- World Health Organization (WHO). Sexual and reproductive health and rights. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://www.who.int/health-topics/sexual-and-reproductive-health-and-rights
- World Health Organization (WHO). Sexual health. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://www.who.int/health-topics/sexual-health
- 公益社団法人 日本婦人科腫瘍学会. 子宮体がん治療ガイドライン2023年版. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://jsgo.or.jp/guideline/taiganguide2023.html
- 日本産科婦人科学会. 子宮内膜症取扱い規約 第2部 診療編 第3版. 金原出版; 2021. ISBN: 9784307301466.
- mimiレディースクリニック三越前. 子宮内膜症の全貌: 原因、症状、治療法と管理. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://mimi-lc.com/column/endometriosis/
- torch clinic. 子宮内膜症の治療方法(薬物・手術療法)|症状や妊娠への影響なども解説. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://www.torch.clinic/contents/1901
- アメリカンホーム保険会社. 子宮内膜症とはどんな病気? 保険で備えることはできる?. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://www2.americanhome.co.jp/womens_morph/column/womens-disease/feature-endometriosis.html
- 徳洲会グループ. 産婦人科の病気:子宮体がん. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://www.tokushukai.or.jp/treatment/gynecology/sikyutaigan.php
- 国立がん研究センター がん情報サービス. 子宮体がん(子宮内膜がん) 治療. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://ganjoho.jp/public/cancer/corpus_uteri/treatment.html
- 済生会京都府病院. 子宮体がんについて. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://www.kyoto.saiseikai.or.jp/pickup/2024/03/post-62.html
- 保険市場. 生理痛を我慢していませんか?10代から発症する子宮内膜症. 2025年6月25日閲覧. Available from: https://www.hokende.com/columns/iccyouisseki/female_doctor/005