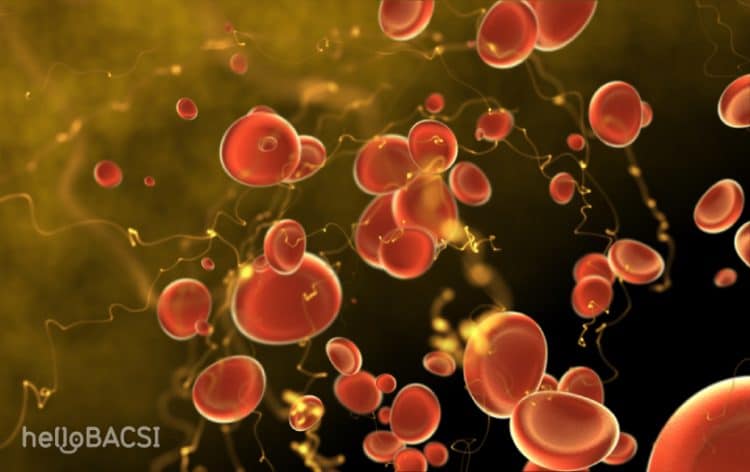この記事の科学的根拠
この記事は、入力された研究報告書に明示的に引用されている最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下のリストには、実際に参照された情報源と、提示された医学的ガイダンスへの直接的な関連性のみが含まれています。
- 日本版敗血症診療ガイドライン2024 (J-SSCG2024): この記事における敗血症の定義、診断基準、および「Hour-1 Bundle」に代表される初期治療に関するガイダンスは、日本集中治療医学会、日本救急医学会、日本感染症学会が合同で作成したこの最新ガイドラインに基づいています61117。
- Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines 2021: 世界的な標準治療との整合性を担保するため、国際的な敗血症ガイドラインを参照し、乳酸値測定や抗菌薬投与、輸液療法などの具体的な治療内容に関する記述の根拠としています1213。
- JAID/JSC 感染症治療ガイドライン 2015 ―尿路感染症・男性性器感染症―: 尿路感染症の分類(単純性・複雑性)、原因菌、および腎盂腎炎から尿路性敗血症への進展過程に関する解説は、日本感染症学会のこのガイドラインに基づいています14。
- 厚生労働省 人口動態統計: 日本国内における敗血症による死亡者数や死亡率に関するすべてのデータは、政府の公式統計から引用しており、問題の深刻さを裏付けています2315。
- 日本敗血症連盟 (Japan Sepsis Alliance): 敗血症に関する一般市民への啓発情報や、「世界敗血症デー」などの活動に関する記述は、この専門家組織の公式情報に基づいています516。
要点まとめ
- 尿路感染症が敗血症につながる:単純な膀胱炎が悪化し、腎臓に感染が及ぶ(腎盂腎炎)と、そこから細菌が血流に入ることで「尿路性敗血症」という命を脅かす状態に発展することがあります1。
- 危険な兆候を知る:高熱や悪寒、意識の混濁(ぼんやりする)、呼吸が速くなる、血圧が低下するといった症状は、単なる風邪や膀胱炎ではない、医療機関への受診を要する緊急事態のサインです17。
- 時間は命:敗血症は一刻を争う医療緊急事態です。治療の開始が1時間遅れるごとに救命率は大幅に低下するため、疑わしい場合は「Hour-1 Bundle」と呼ばれる迅速な初期対応が不可欠です12。
- 特に注意が必要な人々:高齢者、糖尿病患者、尿路に基礎疾患(前立腺肥大や結石など)がある方、免疫力が低下している方は、敗血症を発症する危険性が特に高いです18。
尿路感染症と敗血症
「ただの膀胱炎だと思っていたのに、そこから敗血症になることがある」と聞くと、ご自身や高齢のご家族を思い浮かべて不安になる方も多いのではないでしょうか。排尿時の痛みや頻尿だけでなく、高熱や悪寒、ぐったりした様子が重なると、「このまま放っておいて大丈夫なのか」「救急車を呼ぶべきか」と迷ってしまいます。特に糖尿病や持病を抱えている場合、判断を間違えると取り返しがつかないのではないかという恐怖心も自然な感情です。
この解説では、尿路感染症がどのようなプロセスで敗血症へと進行しうるのか、そしてその危険なサインを一般の方にも分かる言葉で整理し、行動の目安を示します。あわせて、感染が全身に広がったときに血液や臓器で何が起こるのかという「体の中の全体像」を理解しておくと、症状の意味を落ち着いて捉えやすくなります。血液や免疫の異常が全身状態にどう影響するかを俯瞰したい場合には、血液の仕組みと代表的な病気を整理した血液疾患の総合ガイドも参考になります。
尿路感染症は、尿道口から侵入した細菌が膀胱にとどまっている段階(膀胱炎)では局所の症状が中心ですが、そこから尿管をさかのぼって腎臓まで到達すると腎盂腎炎となり、さらに腎臓で増えた細菌が血流に入り込むと全身の免疫反応が暴走して敗血症へ進行します。この段階では「高熱とガタガタ震える悪寒」「息が荒くなる」「血圧が下がってふらつく」「意識がもうろうとする」といった変化が現れやすくなります。こうした全身のサインは、感染症だけでなく血液や臓器の負担が限界に近づいているサインでもあり、その背景には多様な血液疾患や免疫異常が隠れていることもあります。感染が全身の血液や臓器に及んだときの影響を整理して理解しておきたい方は、血液と関連する病気の関係を俯瞰した血液疾患の全体像も役立ちます。
ご自宅でできる最初の一歩は、「いつもの膀胱炎」と「敗血症の入り口」を見分ける視点を持つことです。排尿時痛や頻尿だけでなく、38℃以上の高熱やガタガタ震える悪寒、片側の腰・背中の強い痛みが加わっていないかを意識して確認してみてください。さらに、呼吸が普段より明らかに速い、息苦しくて会話が続かない、妙にぼんやりして返事が遅いといった全身状態の変化があれば、単なる膀胱炎の域を超えている可能性が高くなります。とくに、以前から健康診断などで白血球の値に異常を指摘されている方は、感染に対する体の反応が変化していることもあるため、白血球数の異常が示す意味も踏まえて、早めの受診を意識することが大切です。
次のステップは、「疑ったら迷わず医療へつなぐ具体的な行動」を決めておくことです。尿路感染症の症状に加えて、意識の変化や呼吸の速さ、血圧低下を疑うふらつきなどが見られた場合は、自力で様子を見るのではなく、救急外来の受診や救急車の利用を検討する段階です。その際には「尿路感染症からの敗血症が心配です」とはっきり伝えることで、医療側が速やかに採血や乳酸値の測定、血液培養、早期の抗菌薬投与や点滴などの対応に進みやすくなります。特に、がん治療中で好中球が少ないと言われている方や、免疫や血液に関わる病気を抱えている方では、軽い症状から一気に重症化するリスクが高くなりますので、好中球減少症などの血液疾患を事前に主治医と共有し、緊急時の受診先や連絡方法を確認しておくと安心です。
注意したいのは、「市販薬や以前処方された抗菌薬で様子を見る」ことで受診のタイミングを逃してしまうケースです。発熱が一時的に下がっても、呼吸の速さや意識状態、強い倦怠感が改善しない場合は、感染が全身に広がりつつあるサインかもしれません。また、もともと血が止まりにくい体質や出血傾向を指摘されている方では、敗血症に伴って出血リスクがさらに高まることがあります。鼻血や皮下出血、血尿などが出やすい方は、日頃から血が止まりにくい疾患の特徴も理解し、尿路感染症の治療中や高熱時には早めに医師へ相談するよう心がけてください。
尿路感染症から敗血症に進むかどうかを、完全にご自身だけで見極めることは誰にとっても簡単ではありません。だからこそ、「膀胱炎にしては明らかに様子がおかしい」「普段の風邪よりもずっとつらそうだ」と感じたときの直感を大切にし、早めに医療の手を借りることが命を守る近道になります。感染症のサインと全身状態の変化を冷静に観察しつつ、不安を一人で抱え込まずに、必要なときにはためらわず受診する行動を選びましょう。
第1章:身近な尿路感染症から命を脅かす敗血症へ
多くの人が経験する尿路感染症が、なぜ、そしてどのようにして敗血症という重篤な状態に至るのか。そのメカニズムを理解することは、早期発見の第一歩です。
尿路感染症(UTI)とは?
尿路感染症とは、尿の通り道である「尿路系」(腎臓、尿管、膀胱、尿道)に細菌が侵入し、炎症を起こす病気の総称です19。原因の多くは、腸内に存在する大腸菌などが尿道口から侵入することです20。この感染症は、感染が起きた場所によって大きく二つに分けられます。
- 下部尿路感染症(膀胱炎):感染が膀胱にとどまっている状態で、頻尿(トイレが近い)、排尿時痛、残尿感といった症状が主です22。通常、高熱を伴うことはありません。
- 上部尿路感染症(腎盂腎炎):細菌が尿管を遡って腎臓にまで達した状態です。膀胱炎の症状に加えて、38度以上の高熱、悪寒(寒気と震え)、背中や腰の痛み(特に片側)といった全身症状が現れるのが特徴で、これが尿路性敗血症の直接的な前段階となります1421。
一般市民が理解すべき最も重要な点は、膀胱炎の症状に「高熱」と「腰痛」が加わった場合、それは感染が腎臓にまで広がったサインであり、敗血症に進展する危険性が高い医療的な注意が必要な状態であるということです20。
敗血症とは何か?
敗血症は、感染症そのものではなく、「感染症に対する体の反応が制御不能になり、自らの臓器を傷つけてしまう状態」と定義されています5。体を守るはずの免疫システムが暴走し、侵入した細菌だけでなく、自身の体まで攻撃してしまうのです。この結果、重要な臓器(肺、心臓、腎臓など)の機能が次々と低下し、命に関わる事態に陥ります。
尿路性敗血症へのつながり
腎盂腎炎によって腎臓で増殖した細菌が、血液中に侵入すると(菌血症)、全身でこの免疫の暴走が引き起こされます。これが「尿路性敗血症」であり、敗血症の中でも最も一般的な原因の一つです124。つまり、尿路感染症は、敗血症という全身の火事を引き起こす火種となりうるのです。
第2章:警告サイン:早期認識が行動を変える
敗血症の治療では、一刻も早い対応が予後を大きく左右します。そのためには、一般の人々が「これはただ事ではない」と気づける明確な警告サインを知っておくことが極めて重要です。
医療現場のスクリーニング基準
かつてはqSOFAといった簡易的なツールが用いられていましたが、感度が低く、敗血症患者を見逃す可能性があるため、現在では単独での使用は推奨されていません26。「日本版敗血症診療ガイドライン2024」では、より感度を重視し、見逃しを防ぐために、以下の兆候に基づく迅速な評価を推奨しています17。これらのサインは、一般の方々が救急受診を判断するためのチェックリストとして活用できます。
- 意識の変化:いつもと様子が違う、混乱している、呼びかけへの反応が鈍い、ひどく眠そう。
- 呼吸の異常:呼吸が速い、浅い(1分間に22回以上)、息苦しさを感じる。
- 循環の異常(血圧):血圧がいつもより著しく低い(収縮期血圧が100 mmHg以下)。めまいやふらつきを伴うことがある。
- 体温の異常:38℃以上の高熱、または逆に36℃以下の低体温。
- 脈拍の異常:脈が速い(1分間に90回以上)。
緊急受診を見極めるための症状比較
以下の表は、一般的な膀胱炎の症状と、敗血症の危険性を示唆する緊急のサインを比較したものです。ご自身やご家族の状態を判断する際に役立ててください。
| 症状 | 単純性膀胱炎 | 敗血症の危険サイン(すぐに医療機関へ) |
|---|---|---|
| 排尿痛 | ある | ある |
| 頻尿・残尿感 | ある | ある |
| 発熱 | ない、または微熱 | 高熱(>38°C) または 低体温(<36°C) |
| 悪寒・震え | ない | ある(ガタガタと震えるほどの強い寒気) |
| 腰や背中の痛み | ない | ある(特に片側が痛む) |
| 意識状態 | はっきりしている | 混乱、眠気、めまい、呼びかけに反応しない |
| 呼吸 | 正常 | 速い、息苦しい |
| 全身状態 | 局所的な不快感 | 極度の倦怠感、「死んでしまうかもしれない」と感じるほどの強い消耗感 |
この表は、複雑な診断基準を、一般の方が「いつ行動すべきか」を判断するための、命を救う可能性のあるシンプルなツールへと変換したものです。
第3章:誰がハイリスクか?危険因子を理解する
誰もが尿路感染症にかかる可能性がありますが、そこから敗血症へと進展しやすい「ハイリスク群」が存在します。ご自身や大切な人が当てはまるかを知っておくことは、予防と早期対応に繋がります。
単純性UTIと複雑性UTI
医師は尿路感染症を「単純性」と「複雑性」に分けて考えます。「複雑性尿路感染症」とは、治療が効きにくかったり、敗血症などの重篤な状態に進行する危険性が高かったりする状態を指します28。MSDマニュアルによると、患者が小児や妊婦である場合、尿路に構造的・機能的な異常がある場合、コントロール不良の糖尿病や免疫不全といった併存疾患がある場合、または最近カテーテルなどの器具を尿路に留置した場合、そのUTIは「複雑性」と見なされます14。
ハイリスク群チェックリスト
以下のチェックリストを用いて、ご自身やご家族のリスクを評価してみましょう。
| 危険因子 | リスクが高まる理由 | 自分や家族は? (はい/いいえ) |
|---|---|---|
| 65歳以上 (高齢者) | 免疫機能が低下し、他の健康問題を抱えていることが多い。また、発熱などの典型的な症状が出にくく、意識障害(せん妄)が唯一のサインであることもあり、発見が遅れがちです18。 | |
| 糖尿病 | 高血糖の状態は細菌の増殖を助け、免疫反応を弱らせます18。 | |
| 尿道カテーテルの留置 | 細菌が膀胱へ侵入するための直接的な通り道となります14。 | |
| 腎結石・膀胱結石 | 尿の流れを妨げ、細菌が溜まりやすくなる環境を作ります14。 | |
| 前立腺肥大症 | 膀胱内の尿を完全に出し切れなくなり(残尿)、細菌の温床となります14。 | |
| 免疫抑制状態 | がん治療中の方、ステロイドや免疫抑制剤を使用している方は、体の防御機能が低下しています18。 | |
| 重い尿路感染症の既往歴 | 未解決の根本的な問題(尿路の構造異常など)が存在する可能性を示唆します。 | |
| 妊娠 | 妊娠中の尿路感染症はすべて「複雑性」として扱われ、慎重な管理が必要です18。 |
この表は、読者が自らの状況を積極的に評価し、「なぜ」リスクが高いのかを深く理解するのに役立ちます。ハイリスク群に当てはまる方は、尿路感染症の兆候に対してより一層の注意が必要です。
第4章:病院での対応:尿路性敗血症の診断と治療
敗血症が疑われると、病院では時間との戦いが始まります。ここでは、医療現場で行われる主な検査や治療について解説し、患者さんやご家族の不安を和らげ、治療への理解を深めることを目指します。
「Hour-1 Bundle」:黄金の1時間
敗血症の治療は、最初の1時間(Hour-1 Bundle)に何を行うかが極めて重要です。日本と国際的なガイドラインで推奨されている主な対応は以下の通りです121727。
| 病院での対応 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 乳酸値測定 | 血液検査の一つです。 | 全身の臓器がどれだけストレスを受けているか(酸素不足に陥っているか)を評価します。 |
| 血液培養 | 抗菌薬を投与する前に、通常2か所から採血します。 | 原因となっている細菌を特定し、最も効果的な抗菌薬を見つけ出すためです。 |
| 広域抗菌薬の投与 | 強力な点滴の抗菌薬を直ちに開始します。 | 原因菌が特定される前に、考えられる多くの細菌に効果のある薬で、一刻も早く感染との戦いを始めるためです。 |
| 初期輸液療法 | 大量の点滴(生理食塩水やリンゲル液など)を急速に投与します。 | 低下した血圧を上げ、重要な臓器への血流を確保するためです。 |
| 昇圧薬の使用 | 点滴だけでは血圧が維持できない場合、ノルアドレナリンなどの薬を使用します。 | 生命維持に不可欠な血圧を確保するためです32。 |
| 画像検査 (CT/超音波) | 腎臓の状態を撮影します。 | 尿路閉塞(結石など)がないかを確認します。閉塞があれば、緊急の処置が必要になります。 |
感染巣のコントロールの重要性
尿路性敗血症において、抗菌薬の投与と同じくらい重要なのが「感染巣のコントロール」です30。もし原因が腎結石などによる尿路の閉塞である場合、その詰まりを取り除かない限り、いくら抗菌薬を使っても感染は治まりません。そのため、医師はCTスキャンや超音波検査で閉塞の有無を確認し、もし発見されれば、尿を体外へ排出させるための緊急処置(ドレナージ)を行うことがあります31。
薬剤耐性菌という課題
最初に「広域」抗菌薬が使われるのには理由があります。近年、日本を含む世界中で、通常の抗菌薬が効かない「薬剤耐性菌」が増加しているからです34。例えば、大腸菌の中には、セフェム系という一般的な抗菌薬を分解してしまうESBL産生菌が約25%存在するという報告もあります35。そのため、まずは広範囲の細菌に有効な薬で治療を開始し、数日後に血液培養の結果が判明したら、原因菌に的を絞った最も効果的な抗菌薬に変更します。これを「デ・エスカレーション」と呼び、不要な抗菌薬の使用を減らし、耐性菌のさらなる出現を防ぐための重要な戦略です12。
第5章:予防と行動計画
最善の治療は予防です。ここでは、敗血症のリスクを減らすための日常的な対策と、万が一の際に取るべき具体的な行動計画を提示します。
敗血症を防ぐための尿路感染症予防
以下の科学的根拠に基づいた生活習慣は、尿路感染症の再発を防ぎ、ひいては敗血症のリスクを低減させるのに役立ちます2136。
- 十分な水分摂取を心がける:たくさんの尿を作ることで、細菌を洗い流します。
- 排尿を我慢しない:トイレに行きたいと感じたら、すぐに行く習慣をつけましょう。
- 清潔を保つ:女性は排便後、前から後ろに向かって拭くようにし、腸内細菌が尿道口に付着するのを防ぎます。
- 性交後に排尿する:性的な行為によって尿道口に入り込んだ可能性のある細菌を洗い流します。
- 閉経後の女性:女性ホルモンの低下が感染の一因となることがあるため、医師と相談し、適切な対策を検討することが推奨されます14。
敗血症が疑われる時のあなたの行動計画
もしあなた自身やご家族が、感染症の兆候とともに敗血症の警告サインを示した場合、以下のステップに従って冷静に行動してください。
- 待たないでください。敗血症は時間との勝負です。迷わず行動することが命を救います。
- 救急外来を受診するか、救急車を呼んでください。自家用車での移動中に容態が急変する危険性もあります。ためらわずに119番通報しましょう。
- 懸念をはっきりと伝えてください。医療スタッフに「尿路感染症からの敗血症を心配しています」と具体的に伝えましょう。この一言が、迅速な対応のきっかけになります。
- 症状を具体的に説明してください。特に、この記事で紹介した「警告サイン」(意識の変化、速い呼吸、血圧低下など)を正確に伝えます。
- 危険因子を申告してください。ご自身がハイリスク群(高齢、糖尿病など)に当てはまる場合は、その情報も必ず伝えましょう。
さらなる情報と支援
敗血症に関する正しい知識を広めるため、日本国内でも多くの専門家が活動しています。より詳しい情報や支援が必要な場合は、日本敗血症連盟が運営する公式情報サイト「敗血症.com」をご覧ください5。また、毎年9月13日の「世界敗血症デー」には、各地で啓発活動が行われており、これも社会全体でこの病気に立ち向かう重要な取り組みです1637。
よくある質問
ただの膀胱炎だと思っていましたが、どんな時に敗血症を疑うべきですか?
排尿時痛や頻尿といった膀胱炎の症状に加えて、「38℃以上の高熱」「ガタガタ震えるほどの悪寒」「背中や腰の痛み」のいずれかが出現した場合は、感染が腎臓にまで及んだ腎盂腎炎の可能性が高いです。この状態は敗血症に移行する危険があるため、様子を見ずに速やかに医療機関を受診してください。さらに、「意識がもうろうとする」「呼吸が速く苦しい」「ぐったりして動けない」といった全身状態の悪化が見られれば、敗血症を強く疑い、救急車を呼ぶなど緊急の対応が必要です17。
高齢の家族の様子がいつもと違うのですが、熱はありません。それでも敗血症の可能性はありますか?
はい、可能性は十分にあります。高齢者は免疫反応が若年者と異なるため、敗血症になっても高熱が出ないことが珍しくありません18。むしろ、「急にぼんやりし始めた」「話のつじつまが合わない」「異常に眠そうにしている」といった意識レベルの低下や、「理由もなくそわそわしている」といった急な様子の変化が、敗血症の最初のサインであることがあります。尿路感染症などの感染症がある方で、このような意識の変化が見られた場合は、熱がなくても敗血症を疑い、直ちに医師の診察を受けることが重要です。
病院ではどんな検査をするのですか?時間はかかりますか?
一度敗血症になると、再発しやすいですか?
敗血症の原因となった根本的な問題が解決されていない場合、再発のリスクはあります。例えば、尿路結石や前立腺肥大症など、尿の流れを妨げる要因が残っていると、尿路感染症を繰り返し、再び敗血症に至る可能性があります14。退院後も、医師の指示に従い、基礎疾患の管理をしっかり行い、尿路感染症の予防策を継続することが非常に重要です。
結論
尿路感染症は非常にありふれた病気ですが、それが引き起こす可能性のある敗血症は、一刻を争う医療緊急事態です。この記事を通して明らかになったように、命を救う鍵は「知識」と「行動」にあります。単なる膀胱炎の不快な症状と、腎盂腎炎や敗血症の危険な警告サインとの違いを理解すること。そして、その警告サインに気づいた時に、ためらわずに医療の助けを求めること。この二つが、あなた自身やあなたの大切な人の未来を守る力となります。
あなたの直感を信じてください。もし、ご自身やご家族が感染症の兆候を示し、予想されるよりもはるかに具合が悪そうに見えるなら、すぐに助けを求め、「敗血症」という言葉を口にすることを恐れないでください。この見過ごされがちな危険に、共に向き合っていきましょう。
免責事項この記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言に代わるものではありません。健康上の懸念がある場合や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- Q27:患者さんの救命と社会復帰を支援する敗血症診療. 徳島病院. 2025年6月23日引用. Available from: https://80thbook.tokushima-hosp.jp/specialfeature7/article-72/
- 厚生労働省. 令和4年(2022)人口動態統計(確定数)の概況, 第7表 死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率(人口10万対) [インターネット]. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei22/dl/11_h7.pdf
- 厚生労働省. 平成26年(2014)人口動態統計(確定数)の概況, 第7表 死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率(人口10万対) [インターネット]. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei14/dl/11_h7.pdf
- 敗血症セミナー. 日本集中治療医学会. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.jsicm.org/seminar/sepsis/
- 敗血症情報サイト【敗血症.com】. 日本集中治療医学会. 2025年6月23日引用. Available from: https://xn--ucvv97al2n.com/
- 日本版敗血症診療ガイドライン2024. J-Stage. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsicm/advpub/0/advpub_2400001/_article/-char/ja/
- 敗血症WG. 日本感染症学会. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.kansensho.or.jp/modules/about/index.php?content_id=51
- 理事会役員名簿. 日本感染症学会. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.kansensho.or.jp/modules/about/index.php?content_id=11
- スタッフ紹介. 東京大学泌尿器科. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.imsut-uro.jp/kyoshitsu/staff.html
- PP-953 尿路性敗血症をきたした重症急性腎盂腎炎の検討. J-Stage. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpnjurol/102/2/102_KJ00007188611/_article/-char/ja/
- 「日本版敗血症診療ガイドライン2024 (J-SSCG2024)」正式版 公開のお知らせ. 日本集中治療医学会. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.jsicm.org/news/news241225-J-SSCG2024.html
- Surviving Sepsis Campaign 2021 Adult Guidelines. SCCM. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.sccm.org/survivingsepsiscampaign/guidelines-and-resources/surviving-sepsis-campaign-adult-guidelines
- Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. PubMed. 2025年6月23日引用. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34599691/
- JAID/JSC 感染症治療ガイドライン 2015 ―尿路感染症・男性性器感染症―. 日本感染症学会. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/guideline_JAID-JSC_2015_urinary-tract.pdf
- 人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡 下巻 2 死亡数. e-Stat 政府統計の総合窓口. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/database?page=1&layout=datalist&cycle=7&kikan=00450&toukei=00450011&tstat=000001028897&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053065&result_page=1&second2=1&tclass4val=0&statdisp_id=0003411699
- 世界敗血症デー. 日本敗血症連盟. 2025年6月23日引用. Available from: https://xn--ucvv97al2n.com/gsa/
- 日本版敗血症診療ガイドライン 2024. 日本救急医学会. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.jaam.jp/info/2024/files/bundle.pdf
- 細菌性尿路感染症. MSDマニュアル プロフェッショナル版. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/03-%E6%B3%8C%E5%B0%BF%E5%99%A8%E7%96%BE%E6%82%A3/%E5%B0%BF%E8%B7%AF%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87-uti/%E7%B4%B0%E8%8F%8C%E6%80%A7%E5%B0%BF%E8%B7%AF%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87
- 尿路性器感染症. 広島大学腎泌尿器科学. 2025年6月23日引用. Available from: https://urology.hiroshima-u.ac.jp/medical-treatment/urinary-tract-infection/
- 尿路感染症(膀胱炎、腎盂腎炎). 全国健康保険協会. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/kochi/20140325001/nyourokansen.pdf
- 尿路感染症と発熱. こだいら泌尿器科. 2025年6月23日引用. Available from: https://kodairaurology.jp/%E5%B0%BF%E8%B7%AF%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%81%A8%E7%99%BA%E7%86%B1
- 膀胱炎 (ぼうこうえん)とは. 済生会. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/cystitis/
- 診療内容. 東京大学泌尿器科. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.imsut-uro.jp/shinryo/
- The Urosepsis—A Literature Review. PMC – PubMed Central. 2025年6月23日引用. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8468212/
- Severe Sepsis and Septic Shock. The New England Journal of Medicine. 2025年6月23日引用. Available from: https://anest.ufl.edu/wordpress/files/2021/07/NEJM-Sepsis-Review.pdf
- 【識者の眼】「外来診断訴訟の高リスク:敗血症」徳田安春. Web医事新報. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=19518
- What is new and different in the 2021 Surviving Sepsis Campaign guidelines. PMC. 2025年6月23日引用. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10246868/
- 尿路感染症. ももぞの泌尿器科クリニック. 2025年6月23日引用. Available from: https://momozono-clinic.jp/%E5%B0%BF%E8%B7%AF%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87
- 2023 Update on Sepsis and Septic Shock in Adult Patients: Management in the Emergency Department. PubMed Central. 2025年6月23日引用. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10179263/
- 尿路性敗血症. 日本化学療法学会. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.chemotherapy.or.jp/journal/jjc/05107/051070435.pdf
- 尿路性敗血症. 京都泌尿器科医会. 2025年6月23日引用. Available from: https://kyoto-urology.com/pdf/2024/2024_1001_2.pdf
- 敗血症性ショック. 和歌山県立医科大学. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.wakayama-med.ac.jp/med/eccm/assets/images/library/bed_side/38.pdf
- Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2021. Society of Critical Care Medicine. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.sccm.org/clinical-resources/guidelines/guidelines/surviving-sepsis-guidelines-2021
- 薬剤耐性菌(Antimicrobial resistant bacteria). 日本感染症学会. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.kansensho.or.jp/ref/amr.html
- 薬剤耐性菌対策. 日本環境感染学会. 2025年6月23日引用. Available from: http://www.kankyokansen.org/other/edu_pdf/4-5_01.pdf
- 尿路感染症(UTI)の概要. MSDマニュアル家庭版. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/05-%E8%85%8E%E8%87%93%E3%81%A8%E5%B0%BF%E8%B7%AF%E3%81%AE%E7%97%85%E6%B0%97/%E5%B0%BF%E8%B7%AF%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87-uti/%E5%B0%BF%E8%B7%AF%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87-uti-%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81
- 世界中の敗血症と敗血症による死亡を減らす取り組み. Japan Sepsis Alliance. 2025年6月23日引用. Available from: https://www.nagoya-cu.ac.jp/sdgs-practice/202109001/