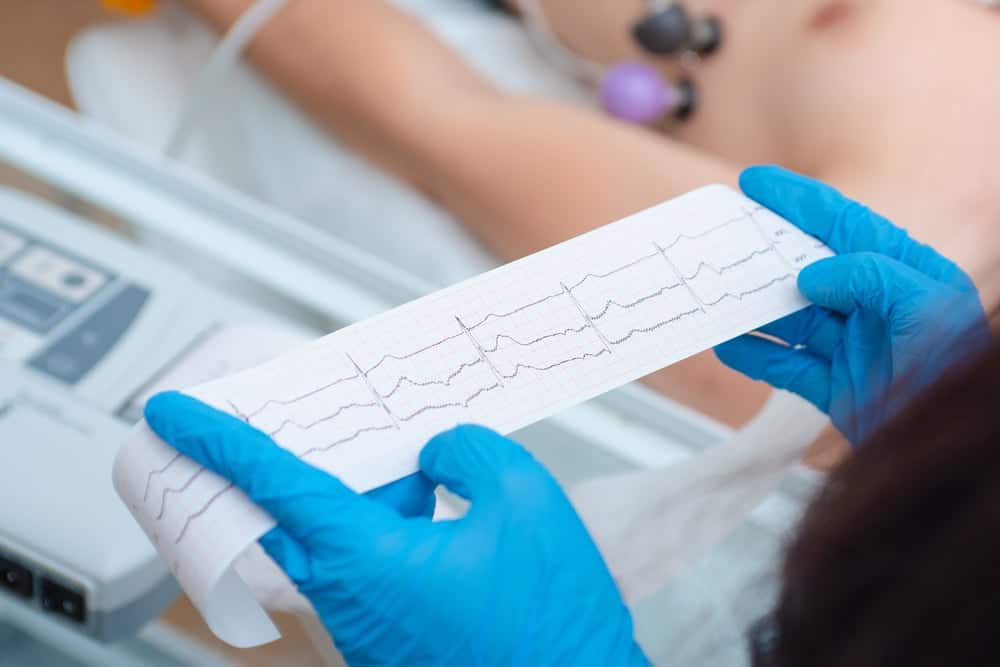医学的監修:
武田 憲彦(たけだ のりひこ)医師、医学博士
東京大学医学部附属病院 循環器内科 教授
この記事の科学的根拠
この記事は、下記に示す最高品質の医学的根拠にのみ基づいて作成されています。以下の一覧には、実際に引用された情報源と、提示された医学的指導との直接的な関連性が含まれています。
- 日本循環器学会/日本不整脈心電学会: 本記事における不整脈の診断、リスク評価、薬物治療、カテーテルアブレーション治療に関する指針は、これらの学会が発行した最新の診療ガイドラインに基づいています7817。
- 米国心臓協会(AHA)/米国心臓病学会(ACC)/心拍リズム協会(HRS): 上室頻拍の管理に関する国際的な標準治療の指針は、これらの組織による共同ガイドラインを参考にしています5。
- 欧州心臓病学会(ESC): 心房細動の管理に関する最新の国際的アプローチ、特にAF-CAREパスウェイの概念は、ESCのガイドラインに基づいています12。
- StatPearls (米国国立医学図書館): 洞性頻脈の基本的な定義や原因に関する記述は、専門家向けの医学文献データベースであるStatPearlsの情報を引用しています4。
要点まとめ
- 安静時の心拍数が毎分100回を超えると「頻脈」と定義され、120回は明らかにこの範囲に含まれます。
- 頻脈には、運動や精神的興奮による「生理的頻脈」と、何らかの疾患が背景にある「病的頻脈」があります。
- 原因は、ストレスや脱水などの生活習慣に起因するものから、貧血や甲状腺機能亢進症、心臓自体の不整脈まで多岐にわたります。
- 胸の痛み、強い息切れ、失神などの「危険な兆候」を伴う場合は、直ちに救急要請が必要です。これらの症状がなくても頻脈が続く場合は、専門医の受診が推奨されます。
- 治療法は原因によって全く異なり、生活習慣の改善、基礎疾患の治療、薬物療法、カテーテルアブレーションなどから最適なものが選択されます。
心拍数120の不安への対処ガイド
「安静にしているのに心拍数が120と言われた」「スマートウォッチを見たら120と表示されていて怖くなった」——そんな経験をすると、多くの方が「このまま放っておいてよいのか」「命にかかわるのではないか」と強い不安を感じます。一方で、運動中や緊張している場面でも同じ120という数字を見ることがあり、「どこまで心配すべきなのか」が分からなくなりがちです。このモヤモヤとした不安に対して、この記事では医学的な視点から「心拍数120」という数字の意味と向き合うための道筋を示しています。
まず理解しておきたいのは、安静時の心拍数が毎分100回を超えると医学的には「頻脈」と定義されるものの、そのすべてが危険というわけではないという点です。本記事では、生理的な頻脈と病的な頻脈の違い、考えられる原因、受診の目安、検査・治療の流れを、ガイドラインに基づいて分かりやすく整理しています。さらに、頻脈が放置された場合に起こりうる脳卒中や心筋梗塞など、心臓・血管全体の病気との関係を広い視点で把握したい場合は、心臓病や血管病の全体像をまとめた心血管疾患の総合ガイドも併せて読むことで、ご自身のリスクをより立体的に理解することができます。
安静時に心拍数が120まで上がる背景には、大きく分けて「一時的な生理的反応」と「何らかの病気に伴う病的頻脈」があります。強いストレスや不安、脱水、睡眠不足、カフェインやアルコールの摂り過ぎ、喫煙などは、交感神経を刺激して一過性に心拍数を押し上げます。一方で、発熱や感染症、貧血、甲状腺機能亢進症、低血糖、自律神経機能障害といった全身の病気、さらには洞性頻脈、発作性上室頻拍、心房細動、心室頻拍などの不整脈が隠れている場合もあります。どの程度の速さや遅さが危険なサインになり得るかについては、危険な心拍数の範囲も参考にしながら、ご自身の状態を整理してみてください。
具体的な対応の第一歩として大切なのは、「本当に安静時に120なのか」「測り方に誤りがないか」を落ち着いて確認することです。椅子に腰掛けて数分間安静にし、そのうえで脈拍計・血圧計・スマートウォッチなどで複数回測定し、いつ・どんな状況で・どれくらいの時間続くのかをメモしておきましょう。同時に、動悸、息切れ、めまい、胸の痛み、失神などの症状の有無も書き添えておくと、受診時の大きな手がかりになります。家庭でできる正しい測定方法や年齢・運動強度ごとの目標心拍数については、心拍数の測り方と正常値のガイドで予習しておくと、数字の意味をより冷静にとらえやすくなります。
次のステップとして重要なのは、「自分の心拍数120が、医学的な基準の中でどの位置づけにあるのか」を把握し、受診のタイミングを判断することです。本記事では、胸の痛み・圧迫感、強い息切れや呼吸困難、意識が遠のく感じや失神、立てないほどのめまいなどを伴う場合は、救急車を含めた緊急受診をためらうべきではないことを強調しています。こうした危険な兆候がなくても、安静時に頻繁に頻脈が続く場合や、糖尿病・高血圧・心臓病などの持病がある場合には、循環器専門医への計画的な受診が推奨されます。日本人のデータに基づく心拍数と血圧の基準値や年代別の平均値については、血圧・心拍数の正常値完全ガイドも確認し、主治医と同じ基準を共有しておくと診察がスムーズになります。
注意していただきたいのは、「心拍数120」という数字だけで自己判断してしまわないことです。たとえ症状が軽くても、頻脈が長期間続けば心臓に負担がかかる可能性があり、特に心房細動のように脳梗塞のリスクを高める不整脈が隠れている場合には、抗凝固薬による脳卒中予防が不可欠になることがあります。また、自己判断で薬を中断したり、市販薬やサプリメントだけで対処しようとすることは避けるべきです。本記事で紹介されているように、日本循環器学会や国際的なガイドラインに沿った診断・治療のプロセスを踏むことで、必要な検査(心電図、血液検査、ホルター心電図、心エコー、心臓電気生理学的検査など)や、生活習慣の見直し・薬物療法・カテーテルアブレーションといった治療法が、個々の原因に合わせて適切に選択されます。
毎分120という心拍数は、必ずしも「今すぐ命に関わる」ことを意味するわけではありませんが、状況によっては体からの重要な警告サインになり得ます。この記事で示されているように、「いつ・どのような場面で・どんな症状を伴って起こるのか」を整理し、必要に応じて専門医の評価を受けることが、ご自身の心臓の健康を守るいちばん確実な第一歩です。不安を一人で抱え込まず、「おかしいな」と感じたときには、早めに医療機関に相談してみてください。
心拍数の基礎知識:正常値と「頻脈」の定義
心拍数120という数字の意味を正確に理解するためには、まず何が「正常」とされるのか、そして医学的に「頻脈(ひんみゃく)」がどのように定義されるのかを知ることが不可欠です。一つの数字に固執するのではなく、心臓血管の生理学的な背景を理解することが、不安を和らげ、適切な判断を下すための第一歩となります。
安静時心拍数の正常範囲
ほとんどの健康な成人において、安静時心拍数(安静にしている状態での心拍数)は、通常1分間に60回から100回の範囲に収まります3。これは、体が特別な労力を必要としない状況で、心臓が効率的に全身へ血液を送り出している状態の指標です。ただし、この数値は個人差が大きいことを理解することが重要です。例えば、日頃からトレーニングを積んでいる運動選手は、心臓のポンプ機能がより効率的であるため、安静時心拍数が60回未満になることも珍しくありません。逆に、加齢に伴い心拍数はわずかに上昇する傾向があります3。また、特に若年層で見られる呼吸性洞性不整脈は、息を吸うと心拍数が少し速くなり、吐くと遅くなるという生理的な現象であり、病的なものではありません3。
「頻脈」とは何か?
医学的に「頻脈」とは、安静時の心拍数が毎分100回を超える状態と定義されています3。したがって、心拍数120回という測定値は、明確にこの頻脈のカテゴリに分類されます。医師が「頻脈」という言葉を用いるとき、それは患者の心拍が安静時の正常範囲の上限を超えて速くなっている状態を指します。
生理的頻脈と病的頻脈の重要な違い
ここが、読者の皆様の不安を解消するための最も重要な分岐点です。すべての頻脈が病気の兆候というわけではありません。
- 生理的頻脈(せいりてきひんみゃく): 激しい運動、精神的な興奮、極度のストレス、あるいは痛みを感じている時などに心拍数が120回を超えるのは、全く正常な身体の反応です1。これは、交感神経系がカテコールアミン(アドレナリンなど)を放出し、体の酸素やエネルギー需要の増加に対応するために心臓の拍動を速める、適切な適応反応です。ストレスの原因がなくなれば、心拍数は自然に正常範囲へと戻っていきます。
- 病的頻脈(びょうてきひんみゃく): 本記事が主眼を置くのは、安静にしているにもかかわらず、また明らかな誘因がないにもかかわらず頻脈が起こる場合、あるいはめまい、息切れ、胸痛といった他の症状を伴う場合です1。このような状況は、精査を必要とする何らかの医学的問題が背景にある可能性を示唆します。この明確な分類により、運動後に心拍を測定した読者は自身の状況が正常であると認識して安心でき、一方で原因不明の頻脈に悩む読者はさらに深く情報を読み進めるべきだと理解できます。
安静時でも心拍数120?考えられる10の潜在的原因
安静時に心拍数が120回に達する場合、それは体が何らかの状態にあることを示す重要な信号かもしれません。考えられる原因を包括的かつ分かりやすく提示することは、この記事の中核をなす情報です。このセクションは、臨床医が診断を下すプロセスを模倣し、最も一般的で調整可能な原因から始め、徐々により専門的で深刻な病状へと進むように構成されています。このアプローチは、読者が論理的に情報を追跡し、過度な不安を軽減するのに役立ちます。
一時的な要因と生活習慣
これらは最も頻繁に見られ、かつ自分で調整可能な原因です。
- ストレスと不安: 急性または慢性の心理的ストレスは、カテコールアミン(アドレナリンなど)の放出を引き起こし、心拍数を自然に増加させます4。
- 脱水: 体内の水分が不足すると、血液の総量が減少します。心拍出量と血圧を維持するため、心臓は代償的に速く拍動する必要が生じます4。
- 睡眠不足: 質の悪い、あるいは不十分な睡眠は、自律神経系のバランスを乱し、基礎心拍数を上昇させることがあります。
- カフェインやアルコールの過剰摂取: これらは心臓の電気伝導系に直接影響を与え、頻脈を引き起こす可能性のある刺激物です。
- 喫煙: タバコに含まれるニコチンは強力な刺激物であり、心拍数と血圧を上昇させます。
心臓以外の病気(全身性の原因)
頻脈は、心臓以外の臓器の疾患の一症状として現れることがあります。
- 発熱・感染症: 体が発熱すると代謝が亢進し、心臓はそれに応えるためにより速く拍動します。特に敗血症では、頻脈は最も早期の重要な警告サインの一つです4。
- 貧血: 血液中のヘモグロビン濃度が低いと、血液の酸素運搬能力が低下します。組織に十分な酸素を供給するため、心臓はより多くの仕事をし、速く拍動する必要があるのです2。
- 甲状腺機能亢進症: 甲状腺が過剰に活動すると、甲状腺ホルモンが過剰に産生され、心拍数を含む全身の代謝が加速します。これは患者さんがしばしば懸念される重要な鑑別診断の一つです2。
- 低血糖: 特に糖尿病(とうにょうびょう)の治療に関連して起こりうる副作用です。血糖値が下がりすぎると、体はアドレナリンを放出して反応し、震え、冷や汗、そして動悸などの症状を引き起こします3。
- 自律神経機能障害: 他の原因が除外された後に考慮される診断です。体位性頻脈症候群(POTS)のように、横になったり座ったりした状態から立ち上がると心拍数が急激に増加する状態などが含まれます2。
心臓自体の問題(不整脈)
これらは最も深刻な原因群であり、専門医による評価が必要です。
- 洞性頻脈: 最も一般的な頻脈で、心臓の自然なペースメーカーである洞結節が、正常より速いペースで電気信号を送る状態です。これは生理的な場合もあれば、不適切な場合(原発性の疾患)もあります4。
- 発作性上室頻拍(PSVT): 心臓の上部(心房)に「電気的なショート回路」が生じることで起こります。突然始まり、突然止まる非常に速い脈が特徴で、多くの場合、生命を脅かすものではありません。日本のガイドラインによれば、心電図上、幅の狭いQRS波(QRS幅 < 120ミリ秒)を特徴とします5。
- 心房細動・心房粗動: 心房が不規則に、かつ速く興奮する不整脈です。ここで強調すべき最も重要な点は、心房細動の最大のリスクは頻脈そのものではなく、心臓内に血栓(血の塊)が形成され、それが脳に飛んで脳梗塞(のうこうそく)を引き起こす危険性にあるということです8。これは極めて重要な公衆衛生上のメッセージです。
- 心室頻拍(VT): より重篤な不整脈で、心臓の下部(心室)から発生します。生命を脅かす可能性があり、緊急の医療介入を必要とします4。
いつ受診すべきか?タイミングと「危険な兆候」
いつ医療機関を受診すべきかについて、明確で実行可能な指針を提供することは、医療情報記事が提供できる最も価値のあるサービスの一つです。緊急性の高い状況と、予定を組んで受診すべき状況を明確に区別することで、読者は混乱の中でも賢明な判断を下すことができます。
救急車を呼ぶ、または直ちに救急外来を受診すべき症状
心拍数120回の頻脈が、以下のいずれかの症状を伴う場合、それは医学的な緊急事態である可能性があり、即時の対応が必要です。
- 胸の痛み・圧迫感: 心筋が十分な酸素を受け取れていない状態(心筋虚血)のサインかもしれず、心筋梗塞につながる可能性があります。
- 強い息切れ・呼吸困難: 心臓が効率的に血液を送り出せず、肺に水分がうっ滞している(心不全)ことを示唆します。
- 意識が遠のく感じ・失神した: 失神は極めて重要な危険信号です。危険な不整脈により、脳への血流が著しく低下した可能性を示します。特に心臓病の既往がある患者さんでは、非常に深刻に受け止めるべき症状です7。
- めまいがひどく、立てない: 失神と同様に、血圧が不安定になっている兆候です。
早めに循環器専門医の診察を受けるべき症状
上記の緊急症状はないものの、以下のような状況がみられる場合は、循環器専門医への受診を計画することが強く推奨されます。
- 安静時に頻繁に頻脈が起こる:明らかな理由なく、頻繁に動悸を感じる場合1。
- 「脈が飛ぶ」「不規則に打つ」といった動悸の感覚:このような感覚(どうき)は、期外収縮や心房細動などの不整脈の兆候である可能性があります3。
- 頻脈が軽い息切れや倦怠感を伴う:症状が軽度であっても、心臓に負担がかかっていることを示している可能性があります。
- 危険因子がある:糖尿病、高血圧、心臓病などの既往がある場合、頻脈はより慎重に評価されるべきです3。
表:受診準備のためのチェックリスト
医師との対話をより効率的にするために、準備ツールを提供することは非常に有益です。以下の表は、患者さんの不安を軽減するだけでなく、医師が重要な情報を効率的に収集する手助けとなり、この記事が患者さんの実際の体験に寄り添っていることを示します。
| チェック項目 | メモしておくこと |
|---|---|
| いつから? | 例:1ヶ月前から、昨日から |
| どんな時に? | 例:安静時、立ち上がった時、食後 |
| どのくらい続く? | 例:数秒で治まる、30分以上続く |
| 頻度は? | 例:毎日、週に1回程度 |
| 他の症状は? | 動悸、息切れ、めまい、胸痛、失神の有無 |
| きっかけは? | ストレス、カフェイン、睡眠不足など |
| 持病や服用中の薬は? | 高血圧、糖尿病、甲状腺疾患など。サプリメントも含む |
病院での検査の流れ:原因を特定するために
診断プロセスを明確に説明することは、未知への恐怖を和らげ、診断が体系的かつ論理的なプロセスであるという信頼を築きます。このセクションの構成は、日本循環器学会(JCS)の「不整脈の診断とリスク評価に関するガイドライン」などで推奨される標準的な臨床手順に沿っています7。このような権威あるガイドラインへの明確な言及は、内容が高い専門基準に基づいていることを示す強力なE-E-A-T(専門性・経験・権威性・信頼性)のシグナルとなります。
問診と身体診察
最初にして最も重要なステップは、医師と患者さんとの対話です。医師は、前のセクションの「チェックリスト」にある項目に基づき、症状について詳しく質問します。その後、聴診器で心臓の音を聴き、心雑音やリズムの異常がないかを確認するなどの身体診察を行います。
基本的な検査
これらは全体像を把握するために最初に行われる検査です。
- 12誘導心電図: 最も重要で不可欠な検査です。12の異なる角度から心臓の電気活動を記録します。これにより、心拍のリズムが整っているか、QRS波(心室の興奮を示す波形)が狭いか広いかなどを判断し、不整脈診断の第一歩とします6。
- 血液検査: 貧血(血球数算定)、甲状腺の問題(甲状腺ホルモン測定)、心拍に影響を与えうる電解質(カリウム、マグネシウム)の不均衡など、心臓以外の原因を調べるために行われます2。
- 胸部X線写真: 心臓の大きさや形を評価し、症状の原因となりうる肺の問題を発見するのに役立ちます。
不整脈を捉えるための追加検査
不整脈は一過性の場合が多いため、より長時間のモニタリング検査が必要となることがよくあります。
- ホルター心電図: 携帯可能な心電図記録装置を24時間(またはそれ以上)装着します。これにより、1日中のすべての心拍を記録し、12誘導心電図では捉えきれない非定常的な不整脈を検出できます7。
- イベントレコーダー: 症状の頻度がさらに低い場合に使用します。症状を感じた時に患者さん自身が装置を作動させ、その時点での心電図を記録します。
心臓の構造と機能を確認する検査
- 心エコー図検査(心臓超音波検査): 心臓の非侵襲的な超音波検査です。心臓の部屋、弁、心筋の詳細な画像を提供します。心臓のポンプ機能(左室駆出率 – LVEFで測定)の評価、弁膜症や心筋症の発見に不可欠です。これは、特に心房細動患者の評価において、クラスI(必須)の推奨事項とされています7。
専門的な精密検査
- 心臓電気生理学的検査(EPS): 複雑な不整脈の診断における「ゴールドスタンダード(最も信頼性の高い基準)」とされています。細いカテーテルを血管から心臓内に挿入し、内部から電気信号を記録したり、心臓を刺激して不整脈を誘発したりします。EPSは不整脈のメカニズムと発生部位を正確に特定するのに役立ち、しばしばカテーテルアブレーション治療の直前に行われます。これは、上室頻拍の種類を鑑別するためにクラスIの推奨となっています7。
治療法の概観:原因に基づいたアプローチ
「心拍数120」に対する単一の治療法は存在しない、という点を強調することが重要です。治療は、診断プロセスを経て特定された根本的な原因に完全に依存します。このセクションでは、主要な治療戦略の概要を提供し、読者に情報を提供することを目的としますが、具体的な医療アドバイスではありません。日本の治療ガイドラインと国際的なガイドラインとの違いや整合性について言及することは、深い専門性を示す重要なポイントです。
生活習慣の改善と基礎疾患の治療
これが最初で最も基本的なアプローチです。頻脈の原因が生活習慣(ストレス、脱水、カフェインなど)や心臓以外の病気(貧血、甲状腺機能亢進症など)であると特定された場合、治療の主眼はこれらの根本的な問題を解決することに置かれます4。例えば、鉄剤の補充による貧血の治療や、薬による甲状腺機能の正常化は、多くの場合、頻脈を解消します。このアプローチは、欧州心臓病学会(ESC)が提唱するAF-CAREパスウェイにおける「C」(併存疾患と危険因子の管理)の原則にも合致しています12。
不整脈に対する薬物療法
不整脈が主な原因である場合、薬物療法が第一選択となることがよくあります。
- レートコントロール(心拍数調節): たとえ不規則なリズムが続いていても、心拍数を許容範囲内(通常は安静時110回/分未満)に遅くすることで、症状を緩和し、頻脈による心不全を防ぐことを目的とします。β遮断薬やカルシウム拮抗薬などが一般的に使用されます5。これは心房細動管理の主要な目標です。
- リズムコントロール(洞調律維持): 異常なリズムを正常な洞調律に戻し、それを維持することを目指します。これは抗不整脈薬によって行われます。
カテーテルアブレーション治療
これは、多くの種類の不整脈、特に発作性上室頻拍や心房細動を根治させうる低侵襲性の治療手技です11。医師はカテーテルを心臓内に進め、高周波や冷凍エネルギーを用いて、異常な電気信号の原因となっている微小な組織を焼灼または冷凍凝固します。日本のガイドラインと国際ガイドラインの両方で、症状のある患者に対する第一選択の治療法としてしばしば位置づけられており、高い有効性と低い合併症リスクを誇ります14。
心房細動における脳卒中予防
これは極めて重要であり、強く強調されなければならない項目です。心房細動の最も危険な側面は、動悸症状ではなく、虚血性脳卒中のリスクが約5倍に高まることです。
- リスク評価: 医師はCHADS₂スコアやCHA₂DS₂-VAScスコアのようなリスク評価尺度を用いて、患者の年間脳卒中リスクを算出し、血液をサラサラにする薬が必要かどうかを判断します。日本のガイドラインでは、CHADS₂スコアが優先的に用いられることがあります15。
- 抗凝固薬: 脳卒中を予防するため、リスク因子を持つほとんどの心房細動患者には抗凝固薬(血液をサラサラにする薬)が必須です。直接経口抗凝固薬(DOACs)は、ワルファリンと比較して同等以上の有効性、より高い安全性、少ない相互作用のため、現在では優先的に使用されています9。抗血小板薬(アスピリンなど)は、心房細動における脳卒中予防には推奨されないことを強調する必要があります。
深い専門性を示す一つのポイントは、日本のガイドラインが国内の人口に合わせて調整されていることを認識することです。日本循環器学会/日本不整脈心電学会(JCS/JHRS)のガイドラインは、使用可能な薬剤、用量、および人口特性の違いから、欧米の臨床試験やガイドラインが必ずしも日本の患者に直接適用できるわけではないことを強調しています17。したがって、「治療方針は、日本循環器学会のガイドラインを基本としながら、国際的な標準(AHA、ESCなど)も参照し、個々の患者さんにとって最適な決定が下されます。日本のガイドラインは、日本人の体格や臨床データを考慮しているため、特に重要です」と明記することが望ましいでしょう。
よくある質問
運動中に心拍数が120になるのは普通ですか?
はい、全く正常です。運動中は、筋肉への酸素供給を増やすために心臓が速く拍動するのは自然な生理的反応です。心拍数の上限は年齢によって異なりますが、健康な成人にとって運動中の心拍数120は通常、安全な範囲内です。
不安やパニック発作で心拍数が120になることはありますか?
はい、非常によくあります。強い不安やパニック発作は、体の「闘争・逃走反応」を引き起こし、アドレナリンが放出されることで心拍数が急激に上昇します4。発作が落ち着けば、心拍数も通常は正常に戻ります。ただし、症状が頻繁であったり、他の身体疾患との区別がつかない場合は、専門医に相談することが重要です。
甲状腺の問題で心拍数は速くなりますか?
はい、その通りです。甲状腺機能亢進症は、頻脈の一般的な原因の一つです2。甲状腺ホルモンが過剰になると、全身の代謝が活発になり、心拍数が上昇します。原因不明の頻脈がある場合、医師は通常、血液検査で甲状腺機能をチェックします。
心房細動と診断されたら、一生薬を飲み続けなければなりませんか?
必ずしもそうとは限りませんが、多くの場合、長期的な管理が必要です。特に、脳卒中予防のための抗凝固薬は、リスクがある限り継続することが極めて重要です9。カテーテルアブレーション治療によって不整脈が根治した場合は、薬を中止できる可能性もありますが、その判断は主治医と慎重に相談して行う必要があります。
結論
要約すると、毎分120回の心拍数は、必ずしも危険な兆候ではありませんが、それが安静時に起こる場合や、気になる症状を伴う場合には、決して無視すべきではありません。それは、運動やストレスに対する正常な生理的反応であるかもしれませんが、同時に、貧血や脱水といった調整可能な問題から、専門家の介入を必要とする複雑な心臓の不整脈まで、さまざまな医学的状態の早期警告信号である可能性も秘めています。インターネットの情報に基づいて自己診断することは、不必要な不安を生んだり、治療における危険な遅延を招いたりする可能性があります。原因を確実に特定し、適切なケアを受ける唯一の方法は、専門知識を持つ医師による包括的な医学的評価を受けることです。単純な心電図から専門的な精密検査に至るまで、現代の診断ツールは、医師が問題を正確に突き止め、個人に合わせた治療計画を立てることを可能にします。ご自身の体の信号に耳を傾け、不安を感じた際には専門家の助言を求めることをためらわないこと。それが、ご自身の心臓の健康を守るための、最も重要で確実な第一歩です。
免責事項本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的アドバイスを構成するものではありません。健康に関する懸念や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- 120回以上の心拍数は頻脈!?|頻脈の原因と検査・治療|京都市南区 いいだ内科クリニック. [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.kuroyanagi-iida.com/tachycardia/
- 少し動いただけで脈が120について | 医師に聞けるQ&Aサイト – アスクドクターズ. [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.askdoctors.jp/open/lp?query=%E5%B0%91%E3%81%97%E5%8B%95%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%A7%E8%84%88%E3%81%8C120
- 心拍数が100を超えた – みんなの家庭の医学 WEB版. [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://kateinoigaku.jp/qa/8332
- José EM, Armagan D. Sinus Tachycardia. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553128/
- Page RL, Joglar JA, Caldwell MA, Calkins H, Conti JB, Deal BJ, et al. 2015 ACC/AHA/HRS Guideline for the Management of Adult Patients With Supraventricular Tachycardia. Circulation. 2016;133:e506–e574. Available from: https://professional.heart.org/en/science-news/-/media/028ddd505f514ea2b3a4e74bb72e3557.ashx
- 頻拍 | 症状、診断・治療方針まで – 今日の臨床サポート. [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://clinicalsup.jp/jpoc/contentpage.aspx?diseaseid=785
- 日本循環器学会/日本不整脈心電学会. 不整脈の診断とリスク評価に関するガイドライン(2022年改訂版). [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/03/JCS2022_Takase.pdf
- 日本循環器学会より 2020 年改訂版不整脈薬物治療ガイドラインが発行された。 – 日本集中治療医学会. [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.jsicm.org/commitee/ccu/pdf/02jsy2.pdf
- 心房細動の治療 – 不整脈. [インターネット]. 第一三共株式会社. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://med2.daiichisankyo-ep.co.jp/cardiology/knowledge/files/arrhythmia/ar6.pdf
- Page RL, Joglar JA, Caldwell MA, Calkins H, Conti JB, Deal BJ, et al. 2015 ACC/AHA/HRS Guideline for the Management of Adult Patients With Supraventricular Tachycardia: Executive Summary. J Am Coll Cardiol. 2016;67(13):1575-1623. Available from: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/cir.0000000000000310?doi=10.1161/CIR.0000000000000310
- Chhabra L, Goyal A, Benham MD. Supraventricular Tachycardia. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6964177/
- Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomström-Lundqvist C, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. European Heart Journal. 2024. Available from: https://www.acc.org/Latest-in-Cardiology/ten-points-to-remember/2024/09/17/04/05/2024-ESC-guidelines-for-AF-esc-2024
- Comments on the 2024 ESC guidelines for the management of atrial fibrillation. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2024. Available from: https://www.revespcardiol.org/en-comments-on-the-esc-guidelines-for-the-articulo-S1885585724003384
- 日本循環器学会の循環器病ガイドラインがアップデートされました. [インターネット]. 斉藤内科クリニック. 2024年3月8日. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://clinicsaito.com/2024/03/08/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%BE%AA%E7%92%B0%E5%99%A8%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E3%81%AE%E5%BE%AA%E7%92%B0%E5%99%A8%E7%97%85%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%8C%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97/
- The 2024 European Society of Cardiology Atrial Fibrillation Guidelines: a new paradigm shift or a storm in a teacup?. J Transl Intern Med. 2024 Mar 21;12(1):1-5. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11865665/
- 2020 年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン 心房細動に関するまとめ. [インターネット]. Dobashin-Medical. 2020年2月2日. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://dobashin.exblog.jp/240182742/
- 日本循環器学会/日本不整脈心電学会. 不整脈薬物治療ガイドライン(2020年改訂版). [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: http://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/01/JCS2020_Ono.pdf
- 武田憲彦 – Wikipedia. [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E6%86%B2%E5%BD%A6
- 循環器内科 – 小室 一成 こむろ いっせい 先生 – メディカルノート. [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://medicalnote.jp/doctors/191113-001-QJ
- 夛田浩 医師(ただひろし)|ドクターズガイド – 時事メディカル. [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://medical.jiji.com/doctor/2226
- 武田 憲彦 | 東京大学. [インターネット]. [引用日: 2025年6月23日]. Available from: https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/people/people100632.html