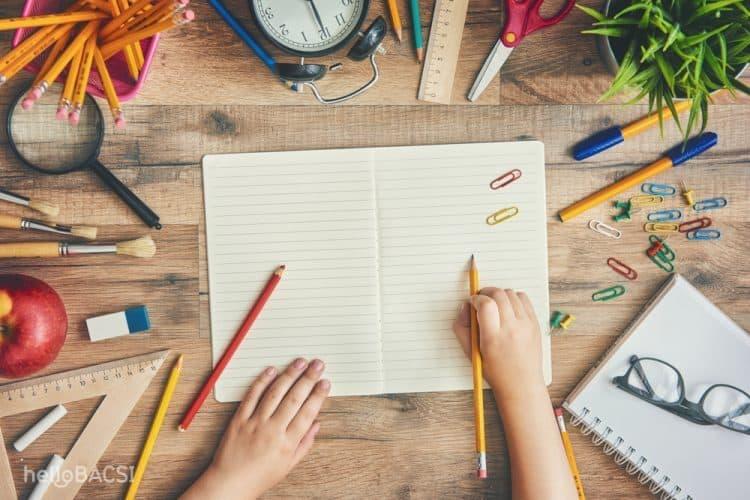この記事の科学的根拠
この記事は、入力された研究報告書で明示的に引用されている最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下の一覧には、実際に参照された情報源と、提示された医学的指針への直接的な関連性のみが含まれています。
- ユニセフ (UNICEF): この記事における子どもの幸福度に関する国際比較の指針は、情報源資料で引用されているユニセフ発行の報告書に基づいています123。
- 文部科学省 (MEXT): 不登校、いじめ、自殺に関する国内の統計データと分析は、文部科学省の公式調査報告書に基づいています910111214212740。
- 厚生労働省 (MHLW): 精神疾患に関する患者数の推移と精神科医療の実態調査は、厚生労働省のデータおよび研究報告に基づいています1516。
- 国立成育医療研究センター (NCCHD): 新型コロナウイルス感染症禍における子どものストレス反応に関するデータは、国立成育医療研究センターの調査に基づいています17。
- 内閣府: 若者の自己肯定感に関する国際比較データは、内閣府が実施した調査に基づいています2022。
- 前野隆司教授 (慶應義塾大学): 幸福の4つの因子に関する理論的枠組みは、前野隆司教授の研究に基づいています3844474849。
- 学術研究論文: 学業ストレス、精神的健康、自己肯定感、非認知能力などに関する具体的な知見は、PubMed Central (PMC) やFrontiers、ResearchGateなどの査読付き学術雑誌に掲載された複数の研究に基づいています6783233345070。
要点まとめ
- 日本の子どもは身体的健康や学業成績で世界トップクラスですが、精神的幸福度は先進38カ国中37位と極端に低い状況です13。
- この nghịch lý (逆説) の根源には、子どもの価値を点数や偏差値で測る「成績至上主義」があり、5つの深刻な代償(精神的健康の悪化、低い自己肯定感、内発的動機付けの消滅、家庭の機能不全、未来を生き抜く力の欠如)を生んでいます。
- 不登校の児童生徒数は過去最多の約30万人に達し、若者の自殺やいじめも高水準で推移しており、これらは構造的な圧力による共通の症状と考えられます913。
- 解決策として、目標を「点数」から「ウェルビーイング(幸福)」へと転換する必要があります。具体的には、「成長マインドセット」の育成、非認知能力の涵養、家庭を「安全基地」にすること、そして成功の定義を多様化させることが有効です。
- 親や教育者は、結果ではなく努力の過程を褒め、失敗を学びの機会と捉え、子どもの内なる好奇心を育むことで、真に幸福で強靭な次世代を育てることができます。
成績至上主義から幸福へ
日本の子どもは「点数は高いのに心は疲れている」という逆説に直面しています。毎日の宿題、模試、順位の比較……その圧は、子どもの自己価値を「成果=自分」と結びつけ、息苦しさや不安を生みます。もしあなたが「うちの子の笑顔が減った」「学ぶ喜びが消えてきた」と感じているなら、それは親として当然の心配です。ここでは、同じ悩みを抱える保護者のために、今すぐできる実践的な手立てをまとめます。
このガイドは、点数に偏った視点から子どものウェルビーイングへ視点を移すための道しるべです。まずは全体像をつかみ、何を優先し、どこから整えるかを明確にしましょう。発熱や発達、メンタルを含む小児の課題を横断的に見渡せる小児科の総合ガイドも併せて確認すると、家庭での判断と行動がぶれません。
成績至上主義が子どもの心を蝕む主要因は「条件付きの価値感」と「外発的動機への過剰依存」です。結果でしか認められない経験が重なると、点数が自己価値の代理になり、失敗恐怖が強まります。そのときまず回復させたいのは“自分は結果と切り離して大切にされている”という核の感覚です。年齢に応じた関わり方の全体像は、自己肯定感を育むアプローチが役立ちます。
最初の一歩は「褒め方の転換」です。才能や結果ではなく、過程・工夫・粘りを具体語で承認します。例えば「最後まで手順を見直していたね」「解けなかった後に別の方法を試したのが良かった」。この関わりは失敗を学びに変え、挑戦回避を減らします。言葉がけの原則は、子どものやる気の育て方に整理されています。
次に、点数化しにくい「非認知能力(共感・協調・ねばり・自己制御)」の土台づくりを生活へ落とし込みます。家事の役割、協働の遊び、感情の言語化、少し背伸びした課題――こうした反復が、折れにくい自己を形づくります。家庭で実践できる具体的な方法は、ソーシャルスキルの伸ばし方を参考に設計できます。
注意点もあります。叱責や比較は“条件付きの愛”として伝わり、自己価値を傷つけます。指導は「行動」だけに焦点をあて、人格から切り離してフィードバックしましょう。日々のしつけを見直す視点は、しつけの9原則を。もし気分の落ち込みや無気力、希死念慮など「病気のサイン」を疑う場合は、専門的評価につながる目安を早めに確認してください。
点数は子どもの価値そのものではありません。今日から「過程を認める言葉がけ」「非認知の土台づくり」「人格と行動を分けたフィードバック」を、できる一つから始めましょう。小さな一歩が、学びの喜びと心の強さを取り戻す最短ルートです。あなたの伴走が、子どもの未来をしなやかにします。
第一部:成績至上主義の重い代償:臨床的・社会的診断
第一の代償:精神的健康の蝕み ― ストレス、不安、うつ病の「流行」
成績至上主義に特徴的な絶え間ない学業のプレッシャーは、子どもや青年にとって慢性的な心理社会的ストレス要因として機能します。臨床的な観点から、この長期にわたるストレスは、精神的健康における潜在的な素因を誘発または悪化させる可能性があります。このメカニズムは「ストレス脆弱性モデル」で明確に説明されています6。個人が生物学的または心理的な脆弱性を元々持っている場合、継続的な学業プレッシャーが最終的な引き金となり、全般性不安障害、パニック障害、大うつ病性障害といった臨床的な状態に陥らせることがあります。国際的な研究でも、学業プレッシャーが青年期の抑うつ症状の重要な予測因子であることが確認されています7。
日本におけるこの危機の規模は、公式な統計データによって明確に示されています。これらの指標を総合的に見ると、期待という重圧の下で苦しむ世代の憂慮すべき姿が浮かび上がります。
- 不登校: この問題は国家的な危機となっています。文部科学省(MEXT)のデータによると、小中学生の不登校者数は10年連続で増加し、2022年度には前年比22.1%増の299,048人という過去最多を記録しました9。これは中学生の17人に1人が不登校であることを意味します10。より最近の調査では、この数字は346,000人にまで増加しており、この憂慮すべき傾向が鈍化していないことを示唆しています1112。
- 若者の自殺: 悲劇的なことに、このプレッシャーは時に究極的な結末を招きます。2022年、小中高生の自殺者数は512人に達し、1980年の統計開始以来、最多を記録しました13。この数字は2023年には411人にわずかに減少したものの、依然として憂慮すべき高水準であり、一部の若者が直面している絶望を痛切に物語っています9。
- いじめと暴力: 熾烈な競争環境は、有害な社会環境を生み出すこともあります。認知されたいじめの件数は2022年に過去最多の681,948件に急増し、その後の報告では732,568件にまで増加し続けています914。特筆すべきは、サイバーいじめが着実に増加しており、子どもたちの社会的相互作用の変化を反映している点です14。
- 精神疾患の診断: 厚生労働省(MHLW)のデータは、精神疾患、特にストレス関連障害や気分障害で治療を受ける外来患者数が著しく増加していることを示しています15。全国の児童精神科クリニックでの調査では、診断の大部分が発達障害(多くはストレスによって悪化する)およびストレスや不安に関連する障害であることが示されています1316。
これらの指標は、個別の問題として捉えるべきではありません。不登校、いじめ、若者の自殺が同時に、かつ記録的なレベルで増加していることは、共通の根本原因を示唆しています。「受験戦争」によって煽られる構造的な圧力が、若者全体の集団に対する慢性的なストレス要因として作用しているように見えます。このストレスは、子どもによって異なる形で現れます。すなわち、引きこもり(不登校)、攻撃性(いじめ)、あるいは絶望(自殺)です。したがって、いじめ対策プログラムのような単一の症状のみを対象とした介入では不十分です。これらの問題が育つ土壌を作り出した、根底にある構造的な圧力を解決する必要があります。
| 指標 | 最新データ/統計 | 出典 |
|---|---|---|
| 精神的幸福度の国際順位 | 38カ国中37位 | ユニセフ1 |
| 生活満足度(15歳) | 62%(最低水準グループ) | ユニセフ1 |
| 不登校の児童生徒数(小・中学校) | 299,048人(2022年、10年連続増加) | 文部科学省9 |
| 若者の自殺者数(小〜高校) | 411人(2022年) | 文部科学省/警察庁9 |
| 認知されたいじめの件数 | 681,948件(2022年、過去最多) | 文部科学省9 |
| 子どものストレス反応の割合(コロナ禍) | 76%が少なくとも1つの症状を報告 | 国立成育医療研究センター17 |
第二の代償:自信の nghịch lý (逆説) ― 高い能力と低い自己肯定感の育成
成績至上主義がもたらす、最も巧妙かつ破壊的な心理的影響の一つは、自己の核となる二つの概念、すなわち自己効力感と自己肯定感の間に生み出す不均衡です。自己効力感とは、特定の課題を遂行する能力に対する信念、つまり「私はこの数学の問題を解ける」という感覚です18。日本の教育システムは、反復練習と達成を重視するため、この能力の構築に長けています。
しかし、自己肯定感ははるかに深い概念です。それは、達成とは無関係な、本来備わっている自己の価値感覚、つまり「私の点数がどうであれ、私は価値のある人間だ」という感覚です5。自己肯定感は、無条件の愛と受容を通じて育まれます。親や教師からの承認が、良い点数、高い順位、名門校への合格といった結果に左右されるように見えると、子どもは危険なメッセージを内面化します。それは、自分の価値は生来のものではなく、達成を通じて獲得しなければならないものだというメッセージです1819。これにより、外部からの承認に依存する、脆い自己感覚が形成されます。
日本の若者におけるこの自己肯定感の欠如の証拠は明らかです。内閣府が実施した国際比較調査では、日本の若者は欧米諸国の同世代に比べて、自己満足度や自己肯定感が著しく低いことが一貫して示されています2021。ある調査では、「自分に満足している」日本の若者はわずか45.1%であり、他国での70〜80%以上という数値と比較して驚くほど低いものでした22。ベネッセと東京大学の共同研究は、さらに憂慮すべき傾向を示しています。全体的な自己肯定感はわずかに改善しているかもしれない一方で、「失敗から立ち直る力」― 回復力の重要な指標 ― は低下しているのです23。
高い自己効力感と低い自己肯定感の間のこの不均衡は、心理学者が「脆い高達成者」と呼ぶ性格類型を生み出します。これらの個人は、成功のルールが明確に定義されている学校のような構造化された環境では優れた能力を発揮するかもしれません。しかし、現実世界での失敗、曖昧さ、または批判に直面すると、心理的に崩壊しやすいのです。外部からの承認(称賛、高得点、昇進)がなければ、彼らは頼るべき内的な価値の源を持っていません。この脆さは、なぜ高達成者であっても、うつ病や不安に苦しむことがあるのかを説明します18。また、なぜ「受験戦争」のプレッシャーが生存の脅威のように感じられるのかも説明します。なぜなら、彼らにとって、試験の失敗は単なる悪い結果ではなく、自己価値全体の破滅を意味するからです。
第三の代償:内発的動機付けの消滅 ― 学びが労働になるとき
子どもは生まれながらにして、探求し、学び、周囲の世界を理解しようとする自然な好奇心、つまり内発的動機付けを持っています。しかし、成績至上主義は、点数、順位、親の承認といった外的な動機付けに過度に依存することで、この貴重な動機を組織的に破壊します24。本来楽しい発見の旅であるべき学びが、報酬を得るため、あるいは罰を避けるために完了しなければならない骨の折れる仕事、つまり労働へと変貌してしまうのです。
教育システム、特に試験においては、答えに至る深い思考プロセスを評価するよりも、「正解」を迅速に見つけ出すことが優先されがちです26。これは子どもたちに、目標は理解ではなくパフォーマンスであることを教えます。その結果、彼らは試験を乗り切るための丸暗記といった表面的な学習戦略を発達させ、目標(点数)が達成されるとすぐにその知識を忘れてしまうことがよくあります。
さらに、結果を重視する文化に深く根付いた失敗への恐れは、子どもたちが知的な危険を冒すことをためらわせます。彼らは、難しい科目や創造的な問題解決法を避ける傾向があります。なぜなら、これらの道はすぐに正解にたどり着かない可能性があり、したがって自分の点数を危険にさらす可能性があるからです26。外的な報酬のために常に成果を出すよう求められるプレッシャーは、燃え尽き症候群や学習意欲の喪失につながる確実な処方箋です。これは、日本の不登校の主要な原因の一つとして特定されている「無気力・不安」の問題に直接寄与しています2728。
本質的に、成績至上主義は、学習を促進しようとする試みの中で、実際には長期的には効果の低い学習者を生み出しているのです。脳の報酬回路が事実上再配線されます。喜びは、理解の「アハ体験」の瞬間からではなく、紙に書かれた高い点数を見ることからもたらされるようになります。最終的な結果は、標準化されたテストでは優秀かもしれないが、知的好奇心、創造性、そして生涯学習への愛情を欠いた世代の生徒です。これらは、21世紀の成功と幸福に本当に必要なスキルなのです。
第四の代償:家庭という細胞の蝕み ― 安全基地から圧力鍋へ
健全な発達において、家庭は「安全基地」としての役割を果たします。それは、子どもたちが外の世界の試練の後に慰めと再充電のために戻ることができる、無条件の精神的支援を提供する避難所です5。しかし、成績至上主義の圧力の下で、家庭はしばしば「圧力鍋」と化し、学業プレッシャーの最前線となります。
親は、しばしば多大な社会的圧力と子どもの将来への不安に苛まれ、無意識のうちに精神的な養育者ではなく、成績の監視者になってしまうことがあります29。家族の会話は、「宿題やったの?」や「テストの点数どうだった?」といった質問にますます集中し、「今日学校で楽しかった?」や「今どんな気持ち?」といった会話は後回しになります。子どもを友人と比較したり、悪い点数を厳しく批判したり、努力を無視して結果だけに集中したりする親の行動は、すべて緊張と不安に満ちた家庭環境を作り出す一因となります193031。
この影響に関する科学的証拠は明らかです。ある重要な多層的研究は、家庭からの圧力を、青年期の精神的健康に関連する最も重要な学業ストレス源として特定し、その影響は友人や教育システム自体の圧力よりも大きいことを示しました32。これは、子どもの健康における家庭の力学の中心的な役割を示唆しています。
これは悲劇的な悪循環です。親は悪役ではありません。彼らはしばしば、自身も耐えている社会的圧力を伝達する導管なのです。最近のメタ分析では、親のストレスと彼ら自身の幸福度との間に有意な負の相関(r=-0.40)が見つかりました。つまり、親がストレスを感じるほど、彼ら自身の幸福度は低くなるのです3334。このストレスが子どもに「伝染」することは避けられません29。子どもがプレッシャーと不安を感じると、彼らの精神的健康は悪化し、学校での成績が振るわないと、それがさらに親の不安とストレスを増大させ、圧力を強めることになります。この悪循環は親子関係を破壊し、家を安全な避難所からストレスの源へと変えてしまいます。この連鎖を断ち切るには、親と子の両方を支援することが必要です。
第五の代償:未来を生き抜くスキルの放置 ― 「脆いエリート」世代の創出
試験の点数や順位といった、測定可能な認知的達成への狭く執拗な集中は、他の重要な能力群、すなわち非認知能力の組織的な放置につながっています35。これらのスキルには、回復力(レジリエンス)、粘り強さ(グリット)、共感、協調性、創造性、自己抑制といった性格特性や社会情動的能力が含まれます3637。
人工知能(AI)によって日常的な認知的作業がますます自動化される、急速に変化する世界において、長期的な成功と幸福を決定するのは、まさにこれらの非認知能力です38。それらは、適応し、革新し、意味のある人間関係を築く能力の基盤であり、機械によっては代替できないスキルです。
日本の若者におけるこれらのスキルの欠如の証拠は明らかです。ユニセフのデータは、日本の高い学業成績を認めつつも、友人作りの容易さといった「社会的スキル」では最下位に近いことを示しています2。国内の調査では、日本の親は非認知能力の重要性を認識しているものの、現在の教育システムではそれらを効果的に育むのに不十分だと感じていることが示されています3539。いじめを含む友人関係の問題の増加は、必須の社会的・情動的スキルの欠如の直接的な証拠です940。
成績至上主義は、本質的に近視眼的な戦略です。狭い尺度(試験の点数)に最適化することで、現代の生活や仕事の複雑さに対して十分な準備ができていない個人を生み出します。ゼロサムの教育システムにおいて、試験対策や丸暗記に費やされる時間と資源は、他の活動から奪われた時間と資源です。構造化されていない遊び、協調的なプロジェクト、チームスポーツ、芸術、自然体験活動といった、非認知能力を育む活動は、脇に追いやられます41。その結果、回復力、協調性、創造性に関連する心理的な「筋肉」は鍛えられません。結果として、私たちは「脆いエリート」の世代を生み出す可能性があります。彼らは試験には合格できるかもしれませんが、人生の挑戦を乗り越えるのに苦労します。これが究極の nghịch lý (逆説) です。学業的な「成功」の追求が、最終的には人生における真の成功に必要な要素を損なうのです42。
第二部:新たな道筋:幸福で強靭な子どもを育むための根拠に基づく行動計画
基本原則:目標を点数からウェルビーイングへの転換
成績至上主義によって引き起こされた危機に対処するためには、根本的なパラダイムシフトが必要です。私たちは、子育てと教育の主要な目標を、高い点数を達成することから、包括的なウェルビーイング(幸福)を育むことへと転換しなければなりません。ウェルビーイングとは単なる幸福感ではありません。それは心理的、社会的、情動的に健やかに成長している状態であり、成功した子ども時代の真の尺度です444546。
この概念を行動に移すために、慶應義塾大学の前野隆司教授が提唱する「幸福の4つの因子」は、親や教育者にとって実践的で根拠に基づいた枠組みを提供します。この枠組みは、幸福な人生の4つの柱を特定しています474849。
- 「やってみよう!」因子(自己実現と成長): 目的意識、個人の成長、そして意味のある目標を追求する意欲を育む。
- 「ありがとう!」因子(つながりと感謝): ポジティブな人間関係、所属感、他者への感謝の気持ちを築く。
- 「なんとかなる!」因子(前向きと楽観): 回復力、楽観主義、そして挑戦の中にポジティブな側面を見出す能力を育む。
- 「ありのままに!」因子(独立と自分らしさ): 自己肯定感、自己受容、そして比較に振り回されず、ありのままの人生を生きる勇気を育む。
前野教授の枠組みは、単なる抽象的な理論ではありません。それは、第一部で診断された問題に対する直接的かつ対称的な解決策を提供します。各幸福因子は、成績至上主義の「代償」の一つに対する解毒剤として機能します。「ありのままに!」因子は、比較によって引き起こされる自己肯定感の低下に直接対抗します。「やってみよう!」因子は、消えかかった内発的動機付けを再燃させます。「なんとかなる!」因子は、失敗に立ち向かうために必要な回復力を築きます。そして、「ありがとう!」因子は、競争によって蝕まれた社会的なつながりを再構築します。この枠組みを意識的に適用することで、親や教育者は、成果を管理することから、積極的に幸福を育むことへと焦点を移すことができます。
行動領域1:成長マインドセットの育成 ― プロセスを褒める力
成績至上主義の悪影響に対抗するための、最も強力かつ即効性のある介入の一つは、子どもを褒める方法を変えることです。核となる原則は、固定的な特性や結果を褒めること(「頭がいいね」「A評価、すごいね!」)から、プロセス、努力、戦略を褒めること(「一生懸命取り組んでいたのを見ていたよ」「行き詰まったときに別の方法を試したのが独創的だったね!」)へと移行することです。
この言葉遣いの変化は、単なる些細な変更ではありません。それは、努力と挑戦に対する子どもの関係全体を再構築します。私たちが知性(固定的な特性)を褒めるとき、私たちは無意識のうちに、成功は生来のものであるというメッセージを送っています。これは、子どもたちが自分の「知性のなさ」を露呈させる可能性のある挑戦を恐れるようにさせます。対照的に、私たちがプロセス(制御可能な要素)を褒めるとき、私たちは子どもに、成功は努力と学びから来ることを教えます。これは、「成長マインドセット」― 能力は献身と努力を通じて伸ばすことができるという信念 ― を育むのです5051。
実践ガイド:
- 努力と粘り強さを褒める: 「あの問題は難しかったのに、諦めなかったね。その粘り強さを本当に誇りに思うよ。」5253
- 戦略と選択を褒める: 「宿題を始める前にノートを見直すことに決めたのは、とても良い戦略だったね。」54
- 改善と学びを褒める: 「漢字の書き方がすごく上達したのに気づいたよ。練習の成果が出ているね。」55
同様に、失敗を再定義することが重要です。失敗は断罪ではなく、貴重な情報源として捉えるべきです。失望で反応する代わりに、親は建設的な対話を導くことができます。まず、子どもの感情を認めます。「この結果にがっかりしているんだね。」5758。次に、学びに移行します。「面白いね。この間違いは何を教えてくれているんだろう?次に活かすために、ここから何を学べるかな?」5459。このアプローチは、失敗を恐ろしい経験から、学習プロセスの正常で必要な一部へと変え、回復力と粘り強さを直接的に築き上げます。
行動領域2:非認知能力の体系的な育成 ― 人格の土台
非認知能力は、生まれつきの特性でも、任意の「ソフトスキル」でもありません。それらは、家庭と学校の両方で意図的に教え、育むことができる、そしてそうすべき必須の能力です356061。それらは人格の基盤を形成し、人生における成功と幸福の強力な予測因子です62。これらのスキルを実践する機会を提供する意図的な環境を作ることは、計画的な行動です。
家庭向け実践ガイド:
- 意味のある家事: 食卓の準備、洗濯物をたたむ、ペットの世話など、年齢に応じた家事を子どもに任せます。これらの仕事は、責任感、粘り強さ、そして集団に貢献することの重要性を教えます。子どもが仕事をやり遂げ、「ありがとう」と言われることで、貢献の価値を学び、自己肯定感を築きます6263。
- 遊びと創造性: 構造化されていない創造的な遊びの時間を確保します。レゴブロックで遊んだり、絵を描いたり、ごっこ遊びをしたりすることは、創造性、問題解決能力、協調性、共感を育む強力なツールです436465。
- 野外活動と体験: 身体活動や自然の中での体験を奨励します。研究によると、キャンプ、ハイキング、公園での遊びといった活動は、自己肯定感、身体的・精神的健康と正の相関があります4166。
- コミュニケーションと共感: 日常の会話や読み聞かせを、感情、視点、社会的な状況について話し合う機会として活用します。「その登場人物はどんな気持ちだと思う?」といった質問を投げかけることで、共感と情動的知性を育むことができます6267。
学校への提言:
- プロジェクトベース学習と協調学習: 個人的な丸暗記から、チームで協力し、コミュニケーションを取り、交渉し、複雑な問題を共同で解決する必要がある協調的なプロジェクトへと、焦点の一部を移します60。
- 芸術とスポーツの統合: 芸術とスポーツを副教科ではなく、創造性、規律、チームワーク、回復力を育むための必須領域として認識します42。
- 社会的・情動的学習 (SEL): 自己認識、自己管理、社会的認識、人間関係スキル、責任ある意思決定といったスキルを明確に教えるための構造化されたSELプログラムを実施します70。
行動領域3:「安全基地」の再構築 ― 無条件の自己肯定感を育む親の役割
子どもの自己肯定感は、絶え間ない賞賛によってではなく、一貫した受容によって築かれます。「安全基地」は、危険を冒す能力や回復力を含む、他のすべての発達が起こるための基盤です68。核となる原則は、子どもの価値をその行動や成績から切り離すことです。基本的なメッセージは常に、「あなたのことは愛している。あなたの行動は好きではないかもしれないけれど、あなたへの愛は変わらず無条件だよ」でなければなりません69。
実践的戦略:
- 積極的傾聴と感情の承認: 子どもが失望、怒り、悲しみを表現したとき、すぐに判断したり解決策を提示したりする衝動に抵抗します。最初のステップは、彼らの感情を認めることです。「そのテストのことで、本当にがっかりしているみたいだね」といった簡単な言葉は、子どもに自分の感情が正当であり、聞いてもらえていることを示します55。
- 無条件の愛情: 愛情表現は、達成に依存するべきではありません。抱擁、「愛しているよ」という言葉、そして一緒に過ごす質の高い時間は、良い点数や良い行動の報酬としてではなく、自由に与えられるべきです5。
- 失敗しても安全な環境を作る: 失敗が人格的な大惨事ではないことを子どもに示します。これを行う強力な方法の一つは、あなた自身の失敗とそこから学んだことを共有することです5373。子どもが失敗したときは、非難ではなく、慰め、そして学ぶことに焦点を当てます。
- 行動とアイデンティティの分離: 言葉遣いは重要です。「あなたは悪い子だ」と言う代わりに、「それは良くない行動だったね」と言います。前者の表現は子どものアイデンティティを攻撃しますが、後者は行動のみを批判し、子どもの核となる価値は損なわれません6871。
子どもが悪い点数を持ち帰ったとき、「安全基地」の反応は「圧力鍋」の反応とは根本的に異なります。圧力鍋の反応は、「これは何だ?またお父さん(お母さん)をがっかりさせたな。」です。これは子どもに、愛は条件付きであり、失敗は危険であると教えます。安全基地の反応は、「あら、この点数で悲しい思いをしているんだね。こっちにおいで、抱きしめてあげる。気持ちが落ち着いたら、何が起こったのか話して、次は違う計画を立てられるか一緒に考えてみようか。」です2972。吸収されるメッセージは、「たとえ失敗しても、自分は愛されている。失敗は解決すべき問題であって、人格的な大惨事ではない」というものです。この安全な基盤は、子どもたちが成長に必要な危険を冒すことを可能にします7475。
行動領域4:成功の定義を広げる ― 多様な道を尊重する
成績至上主義は、成功を狭く定義するシステムの中で繁栄します。それは、良い高校から名門大学へ、そして大企業での安定したキャリアへと続く一本の直線的な道です。この単一の道だけを称賛することで、私たちは大部分の子どもたちを失敗感に陥らせています。より健康的で現実的なアプローチは、才能の多様性と意味のある人生への多様な道を認め、尊重することです。
実践ガイド:
- 情熱の奨励と支援: 学業以外の趣味や興味を積極的に奨励し、支援します。スポーツ、芸術、音楽、プログラミング、ボランティア活動など、これらは気を散らすものではなく、自信、スキル、喜びを築くための重要な領域です24。子どもが情熱を注ぐ分野で優れているとき、その自信は学業を含む人生の他の領域にも広がる可能性があります。
- 代替選択肢の検討: 主流のシステムの圧力によって深刻な影響を受けている子どもたち、例えば深刻な不安や長期的な不登校に苦しむ子どもたちにとって、代替の学習環境が存在し、それが有効で命を救う選択肢となりうることを認識することが重要です。フリースクールなどの代替教育機関は、しばしばより小規模で支援的な環境と、困難を抱える生徒のニーズによりよく応えることができる柔軟なカリキュラムを提供します767778。それらは、教育への再エンゲージメントと自信の再構築への道筋を提供することができます。
- 包括的なキャリア教育: 大学進学だけに焦点を当てるのではなく、学校や家庭は、さまざまなキャリアパスやライフスタイルへの早期かつ広範な接触を提供すべきです。これには、職人技、起業、創造的な分野、非営利セクターでの役割などが含まれます7980。これにより、子どもたちは社会に貢献し、充実した人生を送るための多くの方法があることを知ることができます。
才能の多様性を尊重することは、より人道的であるだけでなく、21世紀の複雑な経済においてより現実的です。子どもが芸術的な才能を示す一方で数学が苦手な場合、成績至上主義の反応は芸術を軽視し、数学への圧力を強めることです。新しい道筋の反応は、芸術的な才能を貴重な贈り物として称賛し、同時に数学のサポートを提供することです45。後者のアプローチは、子どもの価値を認め、自己肯定感を築き、自分の課題に取り組むための回復力を与える可能性があります。
結論と行動喚起
本稿は、日本における成績至上主義がもたらす5つの潜在的かつ深刻な代償を診断しました。それは、精神的健康の蝕み、低い自己肯定感を持つ「脆い高達成者」世代の育成、内発的学習意欲の消滅、家庭の安全基地から圧力鍋への変質、そして未来に不可欠な非認知能力の放置です。これらの代償は個別の問題ではなく、子どもの包括的な幸福よりも狭い達成指標を優先する、見当違いの価値体系の関連症状です。
しかし、明確な診断は効果的な治療への道を開きます。新たな道筋は、考え方の根本的な転換、すなわち点数の追求から幸福の育成への転換を必要とします。本稿では、この転換を実現するための4つの根拠に基づく行動領域を概説しました。(1)プロセスの称賛を通じて成長マインドセットを育むこと、(2)非認知能力を体系的に育成すること、(3)家庭を無条件の受容の「安全基地」として再構築すること、そして(4)成功の定義を広げ、多様な道を尊重することです。
以下の表は、親や教育者のためのこの実践的な転換を要約したものです。
| 領域 | 成績至上主義のアプローチ(避けるべき) | ウェルビーイングのアプローチ(推奨) | 主要な参考文献 |
|---|---|---|---|
| 褒め方とフィードバック | 「頭がいいね!」(結果・才能を褒める) | 「一生懸命頑張って諦めなかったね!」(過程・努力を褒める) | 54 |
| 失敗への対処 | 「なぜ間違えたの?がっかりだ。」(批判、羞恥心を与える) | 「大丈夫。この失敗から何が学べるかな?また挑戦しよう。」(正常化、学びに焦点を当てる) | 44 |
| 学習動機 | 「勉強しないと良い学校に入れないよ。」(外的な圧力) | 「何に興味がある?一緒に調べてみよう。」(内なる好奇心を育む) | 24 |
| 家庭の目標 | 主な目標は高い点数と良い順位。 | 主な目標は幸福で、強靭で、親切な子どもを育てること。 | 72 |
| 成功の定義 | 狭い一本道:名門大学と安定したキャリア。 | 多くの道:芸術、スポーツ、職人技など多様な才能を尊重する。 | 5 |
この転換は容易な課題ではありません。日本の次世代のために成功を再定義するためには、親、教育者、そして政策立案者による共同の努力が必要です。最終的な目標は、高達成の子どもを育てることではなく、幸福で、強靭で、全人格的な若者を育てることです。彼らは、試験を乗り越えるだけでなく、世界で健やかに成長し、意味のある貢献をするための装備を備えています。子どもたちの健康と幸福、そして日本社会そのものの未来は、この転換にかかっています。
免責事項この記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言を構成するものではありません。健康に関する懸念や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- 子どもたちに影響する世界 – 日本ユニセフ. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.unicef.or.jp/library/pdf/labo_rc16j.pdf
- ユニセフ報告書「レポートカード16」 先進国の子どもの幸福度をランキング 日本の子どもに関する結果. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.unicef.or.jp/report/20200902.html
- 第130回 2020年日本の子どもの幸福度 38カ国中「身体的健康」は1位、「精神的幸福度」は37位. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.nissay.co.jp/enjoy/keizai/130.html
- 【小学校受験】子どものメンタルを保つために親がするべきこと – oriori. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://ori-ori.jp/2004045
- 学歴だけでは測れない子どもの発達…人間力を育むために欠かせない3つの要素とは – nobico. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://family.php.co.jp/2025/06/19/post_33360/
- Academic Pressure and Psychological Imbalance in High School … [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11724657/
- Associations Between Academic Stress, Mental Distress, Academic Self-Disclosure to Parents and School Engagement in Hong Kong – PMC. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9344061/
- Family and Academic Stress and Their Impact on Students’ Depression Level and Academic Performance – PMC – PubMed Central. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9243415/
- 令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上 … – こども家庭庁. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5aa667da-fe7f-4ea9-9ee2-7510121e6751/2d6548bb/20231016_councils_ijime-kaigi_dai2_01.pdf
- 小中学生の不登校は過去最多の約30万人に 数字だけを見て終わりにせず、教師や保護者ができることは? – EdTechZine(エドテックジン). [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://edtechzine.jp/article/detail/10197
- 不登校の小中学生、過去最多の34.6万人 文科省調べ – こどもとIT – インプレス. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://edu.watch.impress.co.jp/docs/news/1636116.html
- 【解説記事】[2025年最新情報]文科省調査で過去最多の34万超え。不登校児童生徒の現状と、今ある支援を紹介 – メガホン. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://megaphone.school-voice-pj.org/2025/05/post-2265/
- 子どものメンタルヘルス の現状とEBPM. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_seisaku_suishin/ebpm_meeting/siryou2.pdf
- 令和5年度児童生徒の問題行動・ 不登校等生徒指導上の諸課題に 関する調査結果の概要. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/34f031ee-2de2-4655-878f-34a8bac23a6d/d1152397/20241108_councils_ijime-kaigi_34f031ee_01.pdf
- 精神疾患を有する総患者数の推移 – 厚生労働省. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000940708.pdf
- 児童・思春期精神疾患の診療実態把握と 連携推進のための研究 令和 3 年度 総括・分担研究 – 厚生労働科学研究成果データベース. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/download_pdf/2021/202118024A.pdf
- コロナ×こどもアンケート第5回調査 報告書. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.ncchd.go.jp/center/activity/covid19_kodomo/report/CxC5_repo_20210525.pdf
- 高学歴なのに生きづらさを抱える人……心のバランスを崩したわけ … [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://allabout.co.jp/gm/gc/486928/
- 知らないとヤバい!テスト結果が悪い時にやってはいけない保護者のNG言動. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.seisekiup.net/column/study/2155/
- 若者の自己肯定感、国際比較で最低水準…子ども・若者白書 – リセマム. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://resemom.jp/article/2019/06/19/51090.html
- 参考資料2 自己肯定感を高め – 文部科学省. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo14/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/07/11/1388011_11_1.pdf
- 特集 1 日本の若者意識の現状~国際比較からみえてくるもの. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.aiina.jp/uploaded/attachment/2291.pdf
- 子どもの生活と学びに関する 親子調査2015-2018. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://csrda.iss.u-tokyo.ac.jp/oyakopanel_digest.pdf
- 子どもに「学歴」と「自分らしい生き方」の両方を手にしてほしい親が知りたいこと. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://diamond.jp/articles/-/327329
- The Psychological Impact of Parental Pressure on Kids and Teens | Relational Psych. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.relationalpsych.group/articles/the-psychological-impact-of-parental-pressure-on-kids-and-teens
- 成績至上主義の逆を行け。子どもを伸ばす3つの問いかけ、対話で得られる7つの力. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://kodomo-manabi-labo.net/series-hajime-mieno-vts-08
- 令和5年度文部科学省調査「不登校の理由」いじめが前回から6.6倍に増加 – note. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://note.com/yui_homeschool/n/n94cb738a3b25
- 不登校の現状とは?(文部科学省 2024年データから). [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://toco.mom/current-state-of-school-absence-in-japan-mext-2024-data/
- 受験生の親必見!ストレス対策ガイド~親の言動に子どもはストレスを感じています~. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://sanyokai-clinic.com/kokoro/7523/
- 【成績が悪い中学生の親向け】NG行動6選とおすすめ行動を解説 – スプリックス. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://sprix.inc/media/2022/08/00024/
- 進学校に通う子どもが落ちこぼれに…成績を上げるために親がしてはいけないこと&すべきこと. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://todai-connect.com/2024/05/11/%E9%80%B2%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%AB%E9%80%9A%E3%81%86%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%8C%E8%90%BD%E3%81%A1%E3%81%93%E3%81%BC%E3%82%8C%E3%81%AB%E6%88%90%E7%B8%BE%E3%82%92%E4%B8%8A%E3%81%92-2/
- Academic Stress and Adolescents Mental Health: A Multilevel … [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33424005/
- (PDF) Parental Stress and Well-Being: A Meta-analysis – ResearchGate. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/389682869_Parental_Stress_and_Well-Being_A_Meta-analysis
- Parental Stress and Well-Being: A Meta-analysis – PMC. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12162691/
- 「非認知能力」についての意識調査 | イー・ラーニング研究所のプレスリリース. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://kyodonewsprwire.jp/release/202412272353
- 「非認知能力」の低下が顕著に。コロナ禍で受ける子どもへの影響 – ベネッセ教育情報. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://benesse.jp/kyouiku/202108/20210808-2.html
- 非認知能力とは – 名古屋市緑区のプリスクール SukuSuku English Preschool 浦里. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://sukusuku-ep.com/what-is-non-cognitive-ability/
- 2020年、大人が「幸せ」に生きる社会をどうつくるか――慶大・前野隆司教授に聞く. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.sustainablebrands.jp/news/1195445/
- 「非認知能力」を知っている親は6割、コミュニケーション能力育成に高い関心 イー・ラーニング研究所調査 – こどもとIT. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://edu.watch.impress.co.jp/docs/news/1635395.html
- 文部科学省委託事業 不登校の要因分析に関する調査研究 報告書. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.mext.go.jp/content/20240322-mxt_jidou02-000028870_02.pdf
- 20年にわたる追跡調査で判明! 将来の収入にも影響する、小学生が“通塾や受験勉強以外”にすべき体験 – All About ニュース. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://news.allabout.co.jp/articles/o/63013/
- 将来の学歴・経済力を決定づける「子ども時代の能力」とは? – ダイヤモンド・オンライン. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://diamond.jp/articles/-/339085
- 非認知能力の育て方7選!子どもの力を育てるために親ができること – プロクラ. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.programming-cloud.com/column/children/2023-12-05/
- 【親子のウェルビーイング教育】子どもの幸福度を高める4つの「幸せ習慣」とは – FQ Kids. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://fqkids.jp/23632/
- 子どものウェルビーイングを1週間で高める方法|幸福度と学びの関係 – FQ Kids. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://fqkids.jp/30004/
- 「ウェルビーイングの向上」とは?【知っておきたい教育用語】. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://kyoiku.sho.jp/383945/
- ウェルビーイングとは?研究者・前野隆司教授に聞く幸せな生き方 … [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2023/97725/social_contributions
- ウェルビーイングの4つの因子とは?職場や今すぐ実践できる幸せへのヒント | SUGUME Note. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://medicarelight.jp/sugume-note/well-being/4-factors/
- 幸せをつかむ4つの方法. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://lab.sdm.keio.ac.jp/maenolab/children/about.html
- Influence of perceived parental views of failure on … – Frontiers. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2025.1532332/full
- 【言葉1つで変わる】子供が劇的に変わる成長マインドセットの育て方 – タサカログ. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://tasaka.musicsyrup.net/change-the-mind-growth-mindset/
- 親ができる「子どものやり抜く力(グリット)」を引き出す育て方 – 天神. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.tenjin.cc/education/pre/grit/
- 「すぐにあきらめる子」を「最後まで頑張る子」に変える親のひと言。忍耐力は失敗体験で育つ!. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://kodomo-manabi-labo.net/nintairyoku-up
- しなやかマインドセットと硬直マインドセットって? – アデック知力育成教室. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://adecc.jp/columns/maind88880-1
- 子どもの自己肯定感を高めるために大人ができる10のこと – 横須賀バイリンガルスクール. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://ybschool.jp/column/afterschool_blog/24883/
- 子どもの才能を伸ばすには?「効果的な親の言葉」チェックリスト – nobico. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://family.php.co.jp/2024/02/06/post_14450/
- 第3回:やり抜く力を育てる声のかけ方について – 個別指導塾AQ学院. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://manabi-life.co.jp/howto-study/howto-3/
- グロースマインドセットとは?子どもの可能性を最大限に引き出す方法 – 【教育ピックス】. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://x-ship.jp/media/growth_mindset/
- 子どもの失敗に親はどう対応する?失敗を恐れずに挑戦できる子に育てるコツ. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://conobas.net/blog/education/8707/
- 非認知能力を育む教育とは?学校現場での実践方法とその重要性 – すらら. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://surala.jp/school/column/4822/
- 社会情緒的(非認知)能力の発達と環境に関する研究 – 国立教育政策研究所. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.nier.go.jp/05_kenkyu_seika/pdf_seika/r05/r060424-02_honbun.pdf
- 【非認知能力を高める方法】家庭で親が子どもにできることを5つ紹介 – X-Ship(クロス・シップ). [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://x-ship.jp/media/noncognitive_home/
- 非認知能力の伸ばし方とは? 子どもに必要な力を育む家庭での実践法5選【専門家に聞く】. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://kodomo-manabi-labo.net/hininchinouryoku-expert
- 子どもの「非認知能力」|忍耐力・社会性・感情コントロール…などを養う「子育て方法」とは〔専門家の解説〕 – コクリコ. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://cocreco.kodansha.co.jp/cocreco/general/study/XOm3S
- 非認知能力とは?高い人の特徴や伸ばし方、鍛える遊びを紹介. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://junior.litalico.jp/column/article/136/
- 【幼児期におすすめ】家庭で手軽に真似できる非認知能力の育て方を9つ紹介します。 – 天神. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.tenjin.cc/education/pre/how-to-grow-eq/
- 【非認知能力】鍛える遊び13選|ポイントや高める必要性を解説 | comotto – NTTドコモ. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://comotto.docomo.ne.jp/column/00000009-2/
- 子どもの「自己肯定感」を高めるには?子どもが幸せな気持ちで生きていくために – 学研教室. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.889100.com/column/column047.html
- 【文部科学省推奨】子どもの自己肯定感を高める方法やコツ、気を付けることを解説 | comotto. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://comotto.docomo.ne.jp/column/00000035-2/
- Nurturing positive mental health and wellbeing in educational settings – the PRICES model – PMC. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10834646/
- 子どもの「考える力」を育てるには?親の声かけのポイントと効果的なツールを解説. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://np-labo.com/archives/episode/202312kiji-02
- 子供を幸せにするには、まず親自身が幸せになることが大切?. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: http://www.youzi-kyouiku.jp/14850982325858
- カーリングペアレントが奪う「失敗体験」。子どもが “安心して失敗できる” 親とは?. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://kodomo-manabi-labo.net/failure-growth
- 「間違えるのが怖い子」への親の接し方とは?失敗を受け止める力を育む方法 – SHINGA FARM. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.shinga-farm.com/parenting/kids-who-are-afraid-of-making-mistakes/
- てぃ先生が見つけた!失敗を恐れて行動できない子のチャレンジ精神を育てる2つの方法. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://diamond.jp/articles/-/309532
- The Students Alternative Schools Serve – Urban Institute. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.urban.org/sites/default/files/2022-07/2022%2007%2024_Alternative%20Schools_finalized.pdf
- Alternative Schools and the Students They Serve: Perceptions of State Directors of Special Education – Institute on Community Integration. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://ici.umn.edu/products/prb/141/
- Full article: The complex and contradictory nature of alternative education provision. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2024.2413208
- 日本の受験戦争に突入すべきかChatGPTに聞いてみた|A&A World Traveler – note. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://note.com/qphoney/n/n93958823bbe2
- 学校法人ワオ未来学園/《コロナ禍教育支援》大学受験コーチング. [インターネット]. [引用日: 2025年7月29日]. Available from: https://voix.jp/edu/news/14926/