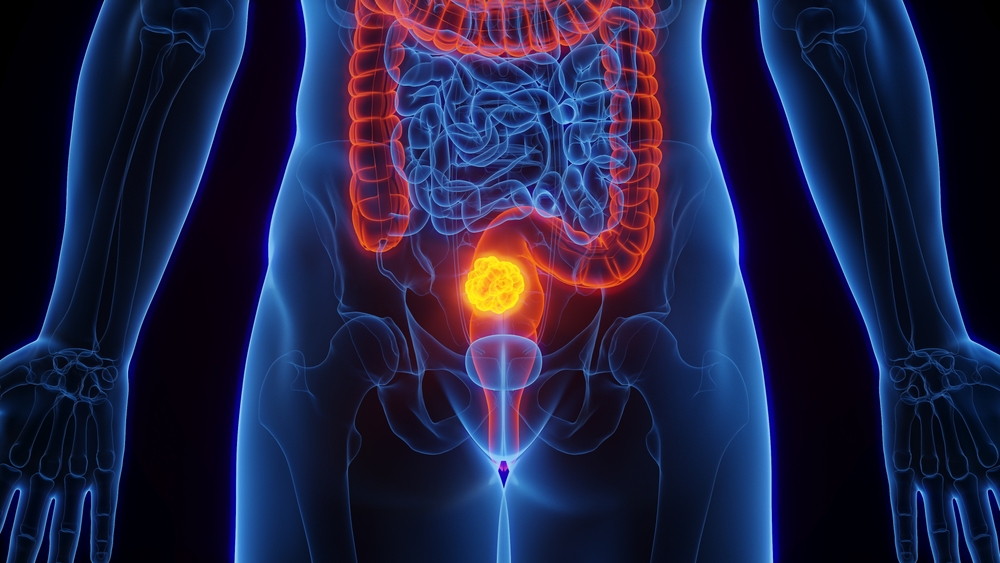この記事の科学的根拠
本記事は、入力された研究報告書で明示的に引用されている最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下に、参照された実際の情報源の一部と、提示された医学的指導との直接的な関連性を示します。
- 日本大腸癌研究会 (JSCCR): 本記事における日本の標準治療、手術手技、化学療法、放射線療法、そして生物学的指標(バイオマーカー)に関する指針は、同研究会が発行した「大腸癌治療ガイドライン 医師用 2024年版」に基づいています1。
- 国立がん研究センター がん情報サービス (Ganjoho.jp): 日本国内の発生率や病期(ステージ)別生存率など、すべての統計データは、日本の公式ながん情報源である同サービスの公開データに基づいています2。
- 欧州臨床腫瘍学会 (ESMO): 術前補助療法などの治療選択肢に関する世界的な視点と欧州の標準治療は、同学会が発行した直腸がんに関する臨床実践ガイドラインを参考にしています3。
- 米国国立がん研究所 (NCI): TNM分類による病期診断やセカンドオピニオンに関する情報は、同研究所が提供する医療専門家向け情報を基に解説しています4。
要点まとめ
- 直腸がんは早期発見が極めて重要であり、初期段階であれば内視鏡治療などで根治が期待できます。
- 治療法は、病期(ステージ)、がんの発生部位、そしてMSIやRAS/BRAFといった生物学的指標(バイオマーカー)に基づき、個々の患者様に最適化された「個別化医療」が行われます。
- 日本の直腸がん治療は、日本大腸癌研究会(JSCCR)が発行する「大腸癌治療ガイドライン2024年版」1が標準治療の基盤となります。
- 近年では、肛門温存手術の技術向上に加え、進行・再発例に対しても免疫療法などの新しい薬物療法が登場し、治療選択の幅が広がっています。
直腸がん治療と検査
直腸がんと告げられた瞬間、多くの方が「肛門は残せるのか」「どの治療を選べばよいのか」「再発したらどうしよう」といった不安に押しつぶされそうになります。とくに血便や排便習慣の変化が続きながらも、痔だと思い込み受診が遅れた経験があると、後悔や自責の念も重なりやすいものです。この小さなガイドでは、そのような思いを抱えるあなたに寄り添いながら、直腸がんの症状・診断・治療の流れを落ち着いて整理できるようお手伝いします。
“`
まず知っておきたいのは、直腸がんはステージ0やIといった早期で見つかれば、内視鏡治療や肛門温存手術によって根治を目指せる可能性が高いという事実です。一方で、ステージIIIやIVまで進行すると、手術に加えて化学放射線療法や薬物療法を組み合わせた集学的治療が必要になります。本記事で整理されている情報に加え、がん全体の仕組みや検診・治療法の位置づけを俯瞰できるがん・腫瘍疾患の総合ガイドも合わせて読むことで、ご自身の状況をより冷静に理解しやすくなるはずです。
直腸がんの多くは、大腸の粘膜にできたポリープ(腺腫)が何年もかけてがん化していく「腺腫–がん連続説」に沿って進行すると考えられています。赤肉・加工肉のとり過ぎ、飲酒、喫煙、運動不足、肥満といった生活習慣に加え、家族性大腸腺腫症やリンチ症候群のような遺伝性腫瘍症候群があるとリスクはさらに高まります。こうした背景と、大腸ポリープの段階で介入する重要性については、ポリープから大腸がんへの移行と早期発見のポイントをまとめた大腸ポリープと大腸がんの予防で、直腸がん予防の観点からも詳しく確認できます。
実際に血便や便通の変化、残便感などの症状が続いた場合、最初の一歩として重要なのは「痔かもしれない」と自己判断せず、消化器内科・大腸肛門外科で直腸指診と大腸内視鏡検査を受けることです。そこで見つかった病変が粘膜内〜粘膜下層にとどまりリンパ節転移のリスクが低いステージ0〜Iであれば、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)など負担の少ない治療で根治を目指せるケースも少なくありません。日本におけるステージI大腸がんの治療方針や5年相対生存率、治療後の生活のイメージは、大腸がんステージ1の詳細ガイドを通して具体的にイメージしやすくなるでしょう。
一方で、ステージII・IIIの直腸がんでは、直腸間膜全切除術(TME)を中心とした手術と、術前化学放射線療法や術後補助化学療法を組み合わせるかどうかが重要な検討ポイントになります。その際、骨盤内の詳細な解剖と腫瘍の深達度、リンパ節転移の有無を評価するMRIに加え、胸腹部CTで遠隔転移の有無を確認することが欠かせません。日常の健康診断などで行われる腹部超音波(エコー)は、肝臓など一部の臓器には有用である一方、直腸を含む大腸がんの拾い上げには限界があることも理解しておく必要があります。腹部エコーで分かること・分からないことと、本当に受けるべき検査の選び方については、超音波検査と大腸がん検査の解説で補うことができます。
さらに進行したステージIVや再発直腸がんでは、FOLFOXやCAPEOXなどの化学療法に加えて、RAS/BRAF変異やMSI-Highといったバイオマーカーを踏まえた分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬の組み合わせが検討されます。とはいえ、治療のゴールは「がんを小さくすること」だけではなく、排便・排尿・性機能、そして人工肛門(ストーマ)を含む生活の質(QOL)をどう守るかという視点も欠かせません。手術後の頻便や便失禁、排尿障害、性機能障害などについては、主治医だけでなくストーマ外来やリハビリスタッフと連携しながら、時間をかけて対策を重ねていくことで、少しずつ自分らしい生活を取り戻していくことが可能です。
直腸がんと向き合う旅路は決して平坦ではありませんが、「血便を放置しない」「検診や内視鏡で早期に見つける」「自分のステージと治療選択肢を理解したうえで納得して決断する」という三つの軸を押さえることで、不安の中にも確かな道筋が見えてきます。一人で抱え込まず、本記事や関連ガイドを手がかりに、信頼できる医療チームと対話を重ねながら、一歩ずつ自分にとって最善の選択をしていきましょう。
“`
直腸がんとは?日本の現状と基本情報
直腸がんは、大腸の一部である直腸(肛門から約15〜20cmの腸管)に発生する悪性腫瘍です。大腸がん全体の中で、結腸がんに次いで多く見られます。消化された食べ物の最終的な通り道である直腸の機能は、便を一時的に溜め、体外へ排出することです。この部位にがんが発生すると、排便機能に直接的な影響を及ぼす可能性があるため、治療においては機能温存が重要な課題となります5。
日本における直腸がんの最新統計
国立がん研究センターが運営する「がん情報サービス」の最新データによると、大腸がん(結腸がんと直腸がんを含む)は、日本で最も罹患数が多いがんの一つです2。2019年の統計では、約15万5千人が新たに大腸がんと診断されており、部位別に見ると男女ともに上位に位置しています。死亡数においても、大腸がんは肺がんに次いで高く、年間約5万7千人以上が亡くなっており、国民の健康にとって重大な課題であることが示されています2。この傾向は、世界の先進国における動向とも一致しており、食生活の欧米化などが要因の一つとして指摘されています6。
【セルフチェック】直腸がんの症状:血便や便の変化は危険信号か?
直腸がんの症状は、がんの進行度や発生部位によって異なります。特に初期段階では自覚症状がほとんどない場合も多く、それが発見の遅れにつながることも少なくありません。しかし、いくつかの特徴的な兆候に注意を払うことで、早期発見の可能性を高めることができます。
初期症状と進行後の症状
最も多く見られる初期症状は血便です7。便に血が混じる、便の表面に血が付着する、排便後にトイレットペーパーに血が付くといった形で見られます。直腸は肛門に近いため、出血した血液が新鮮な赤色であることが多いのが特徴です。その他、以下のような症状が現れることがあります8。
- 便通の変化:下痢と便秘を繰り返す、便が細くなる(便柱細少)。
- 残便感:排便後も便が残っているような感覚が続く。
- 腹痛やしぶり腹:お腹の痛みや、便意があるのに出ない状態。
がんが進行すると、腫瘍が大きくなることで腸管が狭くなり(狭窄)、便秘の悪化、腹部膨満感、嘔吐などの腸閉塞症状を引き起こすことがあります。また、がんが周囲の臓器に浸潤すると、腰や骨盤周辺の痛み、膀胱への影響による頻尿などをきたすこともあります9。
なぜ痔と間違えやすいのか?専門医受診の重要性
血便は痔(特にいぼ痔)の代表的な症状でもあるため、「痔だろう」と自己判断してしまい、受診が遅れるケースが後を絶ちません10。しかし、両者を見分けることは専門家でなければ困難です。がんの発見が遅れると治療の選択肢が限られ、治癒率も低下します。血便や排便習慣の変化など、少しでも気になる症状があれば、決して放置せず、消化器内科や肛門科などの専門医を受診することが極めて重要です。
直腸がんの原因とリスク要因
直腸がんの発生には、遺伝的要因と環境的要因(特に生活習慣)が複雑に関与していると考えられています。リスク要因を理解し、可能な範囲で対策を講じることが予防につながります。
生活習慣と遺伝的要因
厚生労働省は、科学的根拠に基づくがん予防として「5+1のリスク」を掲げており、その多くが大腸がんのリスクにも関連しています11。
- 食生活:赤肉(牛、豚、羊など)や加工肉(ハム、ソーセージなど)の過剰摂取は、大腸がんのリスクを高めることが確実視されています。一方、食物繊維の豊富な野菜や果物の摂取はリスクを低下させる可能性があります。
- 飲酒:アルコールの摂取量が多いほど、リスクは高まります。
- 喫煙:喫煙は多くのがんのリスク要因であり、大腸がんも例外ではありません。
- 肥満:過体重や肥満は、大腸がんのリスクを上げることが指摘されています。
- 運動不足:定期的な身体活動は、リスクを低下させる効果があります。
また、遺伝的要因も重要です。家族に大腸がんの既往歴がある場合、リスクは高まります。特に、リンチ症候群や家族性大腸腺腫症(FAP)といった遺伝性腫瘍症候群の家系では、若年で発症するリスクが著しく高いため、専門的なカウンセリングや定期的な精密検査が不可欠です12。
【ステージ分類】病期ごとの特徴と5年生存率
直腸がんの治療方針を決定する上で最も重要なのが、がんの進行度を示す「病期(ステージ)」です。病期は、がんの深達度(T因子)、リンパ節転移の有無(N因子)、遠隔転移の有無(M因子)を組み合わせたTNM分類に基づいて、0期からIV期まで分類されます4。
ステージ0期からIV期までのTNM分類解説
- ステージ0:がんが粘膜の最も浅い層にとどまっている状態。転移の可能性はほとんどありません。
- ステージI:がんが粘膜下層または固有筋層までにとどまっている状態。
- ステージII:がんが固有筋層を越えて腸管壁の外まで達しているが、リンパ節転移はない状態。
- ステージIII:がんの深達度にかかわらず、所属リンパ節に転移が見られる状態。
- ステージIV:肝臓、肺、腹膜など、直腸から離れた臓器への遠隔転移が見られる状態。
【データで見る】日本のステージ別5年生存率
治療成績の指標として用いられる「5年相対生存率」は、がんと診断された人が5年後に生存している割合を、日本人全体の5年後の生存率と比較したものです。国立がん研究センターの最新の統計データによると、日本の大腸がん(結腸・直腸)のステージ別5年相対生存率は以下の通りです。これはあくまで統計的な平均値であり、個々の患者様の予後を示すものではありませんが、早期発見の重要性を明確に示しています13。
| 病期(ステージ) | 5年相対生存率 |
|---|---|
| I期 | 95.1% |
| II期 | 88.9% |
| III期 | 77.9% |
| IV期 | 18.7% |
| 出典: 国立がん研究センター がん情報サービス「院内がん登録生存率集計」13 | |
直腸がんの精密検査と診断プロセス
直腸がんが疑われた場合、診断を確定し、正確な病期を決定するために、段階的に精密検査が行われます。このプロセスは、最適な治療計画を立てるための根幹となります。
確定診断までの流れ
一般的な診断プロセスは以下の通りです。まず、問診と直腸指診で肛門や直腸下部に異常がないかを確認します。その後、診断を確定するために大腸内視鏡検査(コロノスコピー)が行われます。この検査では、肛門から内視鏡を挿入し、大腸全体の粘膜を直接観察します。疑わしい病変が見つかった場合、その組織の一部を採取(生検)し、病理検査でがん細胞の有無を確定します14。
MRI検査の重要性:治療方針を左右する
直腸がんの診断が確定すると、治療方針決定のために正確な病期診断が必要になります。特に骨盤内の解剖学的構造が複雑な直腸がんでは、MRI(磁気共鳴画像法)検査が極めて重要な役割を果たします。MRIは、がんが直腸壁のどの深さまで達しているか(深達度)、周囲のリンパ節への転移があるか、そして直腸間膜(直腸を支える膜)との位置関係などを詳細に評価できます。これにより、手術で切除すべき範囲や、術前治療(化学放射線療法など)の必要性を判断するための重要な情報が得られます4。その他、胸部から骨盤部までのCT検査で、肝臓や肺などへの遠隔転移の有無も評価します。
バイオマーカー検査(MSI、RAS、BRAF)とは?
近年のがん治療では、がん細胞が持つ遺伝子の特徴(バイオマーカー)を調べ、治療薬の効果を予測する「個別化医療」が主流となっています。「大腸癌治療ガイドライン2024年版」でも、特定の状況下でこれらの検査が推奨されています15。
- MSI検査:マイクロサテライト不安定性(MSI-High)と呼ばれる特徴を持つがんは、免疫チェックポイント阻害薬の効果が期待できます。
- RAS遺伝子検査:RAS遺伝子(KRAS、NRAS)に変異があると、抗EGFR抗体薬(セツキシマブ、パニツムマブなど)の効果が見込めないため、治療薬選択の必須検査となります。
- BRAF遺伝子検査:BRAF V600E変異は予後不良因子と関連し、特定の分子標的薬の適応を判断するために検査されます。
これらの検査は、特に進行・再発がんの薬物療法を選択する際に不可欠な情報を提供します。
【治療法の最前線】JSCCRガイドライン2024年版に基づく標準治療
直腸がんの治療は、内視鏡治療、手術、放射線治療、薬物療法(化学療法、分子標的薬、免疫療法)を組み合わせた「集学的治療」が基本です。治療方針は、日本大腸癌研究会(JSCCR)のガイドラインに基づき、専門家チームによって慎重に決定されます1。
治療方針を決める3つの柱:ステージ、がんの位置、バイオマーカー
最適な治療法は、主に以下の3つの要素によって決まります。
- 病期(ステージ):がんの進行度が治療の根幹を決定します。
- がんの位置:肛門からの距離によって、手術の難易度や肛門を温存できる可能性が変わります。
- バイオマーカー:薬物療法の効果を予測し、最適な薬剤を選択するために重要です。
早期がん(ステージ0・I)の治療:内視鏡治療が中心
がんが粘膜内または粘膜下層の浅い部分にとどまり、リンパ節転移の可能性が極めて低い早期がんでは、体への負担が少ない内視鏡的切除が第一選択となります16。内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)などの技術を用いて、お腹を切開することなくがんを切除できます。ただし、切除した組織の病理検査の結果、がんが深く浸潤していたり、リンパ管への侵入が見られたりした場合には、追加で外科手術が必要となることがあります。
進行がん(ステージII・III)の治療:手術と集学的治療
がんが直腸の壁を越えて広がり、リンパ節転移の可能性があるステージII・IIIでは、手術が治療の中心となります。手術と、放射線治療や化学療法を組み合わせることで、再発率を低下させ、治癒率の向上を目指します。
手術:直腸間膜全切除術(TME)と肛門温存手術
現在、直腸がん手術の標準術式は直腸間膜全切除術(TME)です。これは、直腸とその周囲のリンパ節を含む脂肪組織(直腸間膜)を一つの膜で包み込むように切除する手技で、局所再発率を劇的に低下させました17。
患者様が最も懸念する肛門温存については、がんの位置が重要になります。肛門から非常に近い場所にがんがある場合を除き、多くの場合で肛門括約筋を温存し、永久的な人工肛門(ストーマ)を回避することが可能です。腹腔鏡手術やロボット支援手術といった低侵襲手術の普及も、より精密な操作を可能にし、機能温存に貢献しています。
術前補助療法(Neoadjuvant Therapy)の役割と選択
特に進行した下部直腸がんでは、手術前に化学療法や放射線治療を行う術前補助療法が標準的です。これにより、がんを小さくして切除しやすくし、肛門温存の可能性を高め、局所再発のリスクを低減する効果が期待できます1。
世界的には、術前・術後のすべての化学療法を手術前に集中的に行うTotal Neoadjuvant Therapy (TNT)という戦略が注目されています。TNTは、がんが完全に消失する割合(病理学的完全奏功、pCR)を高め、生存期間を改善する可能性が示唆されています18。JSCCRガイドライン2024年版では、TNTはまだ確立された標準治療とは位置づけられていませんが、有望な治療選択肢として臨床研究が進められています19。この点は、欧州のESMOガイドラインなどがより積極的にTNTを推奨している点との違いであり、国内外の動向を注視する必要があります3。
術後補助化学療法
手術でがんを完全に取り除いた後も、目に見えない微小ながん細胞が体内に残っている可能性がある場合、再発を予防する目的で術後補助化学療法が行われます。JSCCRガイドライン2024年版では、ステージIIIおよび再発リスクの高いステージIIの患者様に対して、FOLFOX療法やCAPEOX療法などの化学療法が推奨されています1。
転移・再発がん(ステージIV)の治療:薬物療法と個別化医療
遠隔転移があるステージIVや、治療後に再発した場合には、薬物療法が治療の中心となります。目標は、がんの進行を制御し、症状を緩和し、生活の質(QOL)を維持しながら生存期間を延長することです。
治療は、従来の化学療法に加え、がん細胞の特定の分子を狙い撃ちする分子標的薬や、自己の免疫力を利用してがんを攻撃する免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせます。前述のバイオマーカー検査の結果に基づき、JSCCRガイドライン2024年版では、MSI-Highの腫瘍に対してペンブロリズマブの使用が推奨されるなど20、個々の患者様に最適な薬剤が選択されます。
手術後のQOL(生活の質)と後遺症対策
直腸がんの治療は、がんを治すことだけでなく、治療後の生活の質(QOL)をいかに維持するかも非常に重要です。特に手術後は、様々な後遺症と向き合う必要があります。
排便・排尿・性機能障害との向き合い方
直腸の切除により、便を溜める機能が低下し、頻繁な便意や便失禁などの排便障害が起こることがあります。また、直腸の周囲には排尿や性機能に関わる神経が密集しているため、手術の影響で排尿障害や性機能障害(勃起不全など)が生じることもあります5。これらの後遺症は、患者様のQOLに深刻な影響を与えかねません。多くの専門病院では、医師、看護師、理学療法士などが連携し、食事指導、骨盤底筋体操、薬物療法、そして精神的なサポートを通じて、これらの問題に多角的にアプローチしています21。
人工肛門(ストーマ)との生活:ケアと精神的サポート
がんの位置によっては、永久的な人工肛門(ストーマ)が必要になる場合があります。ストーマを造設することは、多くの患者様にとって大きな精神的負担となりますが、適切なケアと管理方法を学ぶことで、手術前と変わらない社会生活を送ることが可能です。専門のストーマ外来では、皮膚・排泄ケア認定看護師が装具の選択やスキンケア、日常生活の注意点についてきめ細やかな指導を行い、患者様が自信を持って生活できるよう支援しています17。
直腸がんの予防と検診
直腸がんのリスクを低減するためには、生活習慣の改善と定期的な検診が両輪となります。
厚生労働省が推奨するがん予防法
厚生労働省は、科学的根拠に基づき、がん予防のために以下の生活習慣を推奨しています11。
- 禁煙:タバコを吸わない。
- 節酒:飲酒は適量を守る。
- 食生活:塩分を控え、野菜や果物を多く摂り、バランスの取れた食事を心がける。
- 身体活動:日常生活の中で身体を動かす機会を増やす。
- 適正体重の維持:太りすぎず、痩せすぎないように体重を管理する。
これらの健康的な生活習慣は、直腸がんだけでなく、多くのがんや生活習慣病の予防につながります22。
定期検診の重要性と受診の目安
症状がない段階でがんを発見するために、がん検診は極めて有効です。日本では、40歳以上の男女を対象に、便潜血検査による大腸がん検診が推奨されています23。これは、便に混じった微量の血液を検出する簡単な検査です。陽性となった場合は、精密検査として大腸内視鏡検査を受けることが推奨されます。定期的に検診を受けることで、がんやその前段階であるポリープを早期に発見し、治療につなげることができます。
よくある質問
直腸がんの治療で名医や良い病院を見つけるには?
良い治療を受けるためには、病院選びが重要です。一つの指標として、国が指定する「がん診療連携拠点病院」24があります。これらの病院は、専門的ながん医療を提供する体制が整っており、手術、放射線治療、薬物療法を組み合わせた集学的治療を専門家チームで提供しています。また、各病院のウェブサイトで、消化器外科や腫瘍内科の医師の実績(年間手術件数など)や専門分野を確認することも参考になります。日本大腸肛門病学会などの専門学会のウェブサイトで専門医を探すことも可能です。
セカンドオピニオンはどのように受ければよいですか?
セカンドオピニオンとは、主治医以外の医師に治療方針に関する意見を求めることです。診断や治療方針に納得し、安心して治療に臨むために非常に重要です。希望する場合は、まず主治医にその旨を伝え、紹介状(診療情報提供書)や画像データなどの資料を提供してもらいます。多くの「がん診療連携拠点病院」にはセカンドオピニオン外来が設置されています。費用は自費診療となりますが、納得のいく治療選択のために積極的に活用することが推奨されます4。
結論
直腸がんの治療は、この10年で大きく進歩しました。TMEのような標準手術手技の確立、腹腔鏡やロボット支援手術といった低侵襲技術の発展、そしてバイオマーカーに基づく個別化された薬物療法の登場により、治療成績は着実に向上しています。特に、日本の治療は「大腸癌治療ガイドライン2024年版」1という強固な科学的根拠に基づいており、世界最高水準の医療が提供されています。
本記事で解説したように、直腸がんはもはや不治の病ではありません。しかし、その治療は複雑であり、多くの情報の中から自分にとって最善の道を見つけ出すことは容易ではありません。大切なことは、血便などのサインを見逃さず早期に専門医を受診すること、そして診断された際には、信頼できる情報源を基に主治医と十分に話し合い、納得のいく治療を選択することです。JapaneseHealth.orgは、皆様がこの困難な道のりを歩む上での確かな羅針盤となるべく、今後も正確で信頼性の高い情報を提供し続けることをお約束します。
免責事項本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言に代わるものではありません。健康に関する懸念がある場合、またはご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- 大腸癌研究会. 大腸癌治療ガイドライン 医師用 2024年版. 東京: 金原出版; 2024. https://www.jsccr.jp/public/guideline20240130.pdf
- 国立がん研究センターがん情報サービス. がん統計. [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://ganjoho.jp/public/cancer/colon/index.html
- ESMO. ESMO Clinical Practice Guideline: Localised Rectal Cancer. [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://www.esmo.org/guidelines/esmo-clinical-practice-guideline-localised-rectal-cancer
- National Cancer Institute. Rectal Cancer Treatment (PDQ®)–Patient Version. [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://www.cancer.gov/types/colorectal/patient/rectal-treatment-pdq
- がん研有明病院. 診療科の特徴|直腸がん集学的治療センター. [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://www.jfcr.or.jp/hospital/department/clinic/disease/gastro/rectum/feature.html
- Araghi M, Soerjomataram I, Bardot A, et al. Epidemiology of colorectal cancer: incidence, mortality, survival, and risk factors. PMC. [インターネット]. 2019 [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6791134/
- 株式会社cellcloud. 直腸がんの症状・前兆とは?ステージ別の病状や早期発見に… [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://micro-ctc.cellcloud.co.jp/column/rectal-cancer_symptoms
- サリバテック. 大腸がんの症状|初期症状や気づいたきっかけ、主な原因を解説. [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://sc.salivatech.co.jp/magazine/colorectal-cancer_earlysigns/
- JR東京総合病院. 大腸がんの症状・治療について. [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://www.jreast.co.jp/hospital/info/certified_cancertreatment/big5cancers3.html
- SBI損害保険株式会社. こんな症状が出てきたら、がんの可能性?がんの初期症状を見逃してはいけない. [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://www.sbisonpo.co.jp/gan/column/column34.html
- 厚生労働省. がん予防. [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059490_00004.html
- Mayo Clinic. Rectal cancer – Symptoms and causes. [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rectal-cancer/symptoms-causes/syc-20352884
- MEDLEY. 大腸がんの統計①:ステージ1,2,3,4の生存率、転移した時の生存率. [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://medley.life/diseases/54b69fbd6ef4587502f19991/details/knowledge/prognosis/
- National Cancer Institute. Rectal Cancer Treatment (PDQ®)–Health Professional Version. [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://www.cancer.gov/types/colorectal/hp/rectal-treatment-pdq
- HOKUTO. 大腸癌治療ガイドラインが改訂!薬物療法の要点を解説 -周術期療法編-. [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://hokuto.app/post/bzxTjRWvt5XEE3TxHmJ3
- 株式会社プレメディ. 直腸がんに対する手術:どんな治療?合併症は?術後の生活は… [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://www.premedi.co.jp/%E3%81%8A%E5%8C%BB%E8%80%85%E3%81%95%E3%82%93%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/h01046/
- 大阪国際がんセンター. 直腸がんセンター. [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://oici.jp/hospital/department/chokuchogancenter/
- Karahan SN, Gorgun E. Modern rectal cancer management: A review of total neoadjuvant therapy and current practices. Am J Surg. 2024 Dec 13:S0002-9610(24)00650-6. doi: 10.1016/j.amjsurg.2024.116145. Epub ahead of print. PMID: 39706107. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39706107/
- ケアネット. 「大腸癌治療ガイドライン」、主な改訂ポイントを紹介/日本癌治療学会. [インターネット]. 2024 [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://www.carenet.com/news/general/carenet/59576
- HOKUTO. 大腸癌治療ガイドラインが改訂!薬物療法の要点を解説 -遠隔転移再発編-. [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://hokuto.app/post/rL4q0qVzflD9XGQR2COg
- Mayo Clinic. Rectal cancer – Care at Mayo Clinic. [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rectal-cancer/care-at-mayo-clinic/mac-20352891
- 国立がん研究センターがん情報サービス. 科学的根拠に基づくがん予防. [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/evidence_based.html
- Sanpo Navi. 2023年度から開始された「第4期がん対策推進基本計画」の要点を紹介. [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://sanpo-navi.jp/column/basic-cancer-control-law/
- 国立がん研究センターがん情報サービス. 大腸がん(結腸がん・直腸がん). [インターネット]. [引用日: 2025年7月24日]. Available from: https://ganjoho.jp/public/cancer/colon/treatment.html