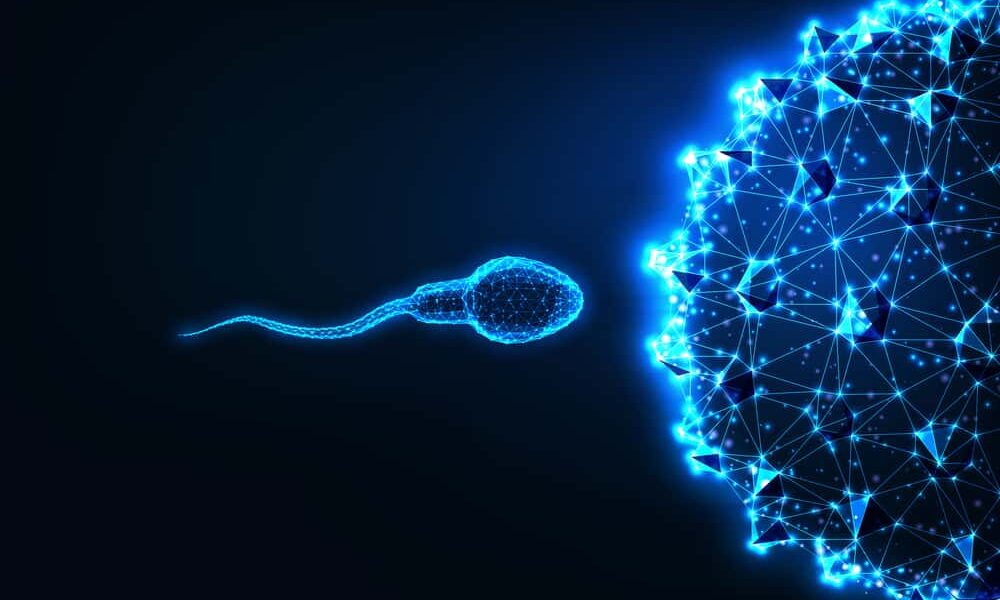「精子の数が少ない(乏精子症)」と診断され、深い不安と多くの疑問を抱えていらっしゃるかもしれません。「もう自然妊娠は望めないのだろうか」「どのような治療法があるのか」「費用はどれくらいかかるのか」。そのお気持ちは、決して特別なことではありません。日本の夫婦の約4.4組に1組が不妊の検査や治療を経験しており1、その原因の約半数には男性側にも何らかの要因が関わっていると報告されています2。つまり、あなたは一人ではないのです。この記事では、その不安を希望に変えるための、正確で信頼できる情報を提供します。本稿は、世界的な基準であるWHO(世界保健機関)の最新マニュアル3と、日本の男性不妊治療に新たな道標を打ち立てた画期的な**『男性不妊症診療ガイドライン 2024年版』**2に完全準拠しています。ご自身の精液検査の結果を正しく理解する方法から、考えられる原因、科学的根拠に基づく具体的な治療選択肢、そして2022年から大きく変わった保険適用の詳細まで、専門的な知見を分かりやすく解説します。この記事を読み終える頃には、ご自身の状況を客観的に把握し、パートナーや医師と前向きな次の一歩を踏み出すための知識が身についているはずです。
この記事の科学的根拠
この記事は、入力された研究報告書に明示的に引用されている最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下は、参照された実際の情報源と、提示された医学的指導との直接的な関連性を含むリストです。
- 日本泌尿器科学会(JUA)『男性不妊症診療ガイドライン 2024年版』: この記事における治療法の推奨(例:精索静脈瘤手術、薬物療法)に関する指導は、日本の男性不妊治療の標準を示すこの画期的なガイドラインに基づいています。
- 世界保健機関(WHO)『ヒト精液検査・処理マニュアル第6版』: 精液検査の基準値や解釈に関する記述は、世界的な標準とされるこのマニュアルに基づいています。
- 米国泌尿器科学会(AUA)/米国生殖医学会(ASRM)ガイドライン: 日本のガイドラインを補完する情報として、国際的な診断・治療アプローチに関する知見を引用しています。
- 各種学術論文・調査報告: 提示された統計データ(例:日本の不妊治療経験率、ART出生児の割合)や、特定の治療法の有効性に関するメタアナリシスなどの科学的研究結果は、個別に引用された論文に基づいています。
要点まとめ
- 乏精子症(精子濃度が1600万/mL未満)と診断されても、必ずしも自然妊娠が不可能というわけではありません。精液所見は変動するため、複数回の検査が必要です。
- 2024年に日本初の『男性不妊症診療ガイドライン』が発行され、治療方針の新たな基準が示されました。
- 治療可能な原因として最も多い「精索静脈瘤」に対する手術は、ガイドラインで強く推奨(グレードA)されており、保険も適用されます。
- 薬物療法や人工授精、顕微授精などの多くの治療法が、2022年から公的医療保険の対象となり、経済的負担が軽減されています。
- 不妊治療はカップルの問題であり、治療の成功には女性パートナーの年齢が大きく関わるため、早期の共同での意思決定が重要です。
「精子が少ない」と言われた方へ — まずは精液検査の結果を正しく理解する
精液検査の結果を受け取った際、多くの数字が並び、その一つ一つに一喜一憂してしまうかもしれません。しかし、まず知っておくべき最も重要なことは、精液所見は体調やストレス、検査前の禁欲期間などによって大きく変動するということです4。そのため、米国泌尿器科学会(AUA)のガイドラインでは、通常2回以上の検査を行い、総合的に評価することが推奨されています4。一度の結果だけで悲観する必要は全くありません。
世界基準で見る:WHO第6版(2021年)の基準値
現在、世界の医療機関で標準的に用いられているのが、2021年に改訂されたWHO(世界保健機関)の『ヒト精液検査・処理マニュアル第6版』です3。このマニュアルが提供する基準値は、妊娠可能な男性集団を集め、その中で下位5%にあたる数値を「基準値」として設定したものです。これは、絶対的な「正常/異常」の境界線(カットオフ値)ではなく、さらなる精密検査を検討すべきかどうかの「決定限界(decision limits)」として捉えるべきだとWHOは強調しています5。つまり、これらの数値を下回っていても、直ちに妊娠不可能と判断されるわけではないのです。また、第6版では単なる精子濃度だけでなく、射精1回あたりの総精子数がより重視されるようになっています3。
| パラメータ(項目) | WHO 2021年基準値 下限5パーセンタイル | 分かりやすい解説 |
|---|---|---|
| 精液量 | 1.4 mL | 1回の射精で排出される精液の総量です。この量と精子濃度を掛け合わせることで、総精子数が計算されます3。 |
| 精子濃度 | 16 × 10⁶/mL (1600万/mL) | 精液1mLあたりに含まれる精子の数です。この数値を下回る状態が「乏精子症」と呼ばれます6。 |
| 総精子数 | 39 × 10⁶ (3900万) | 1回の射精に含まれる精子の総数です。WHOは濃度だけでなく、この総数を重視しています3。 |
| 総運動率 | 42% | 前進運動をしている精子と、その場で動いている精子を合わせた割合です。 |
| 前進運動率 | 30% | まっすぐ、または大きな円を描いて活発に前進している精子の割合です。卵子に到達するために重要です。 |
| 精子正常形態率 | (基準値なし) ※ | 頭部、中片部、尾部の形が正常な精子の割合です。第6版では特定の基準値は設けられていません。 |
| 精子生存率 | (基準値なし) ※ | 動いていない精子のうち、生きている精子の割合です。総運動率が低い場合に特に重要な検査となります7。 |
※WHO第6版では、正常形態率と生存率について、以前の版のような集団ベースの下限基準値は設定されていません。評価は各検査室の基準や臨床的状況に応じて行われます。 出典: 3
なぜ精子が少ないのか?考えられる原因の全体像
乏精子症の原因は多岐にわたります。専門医は問診、身体診察、血液検査などを通じて原因を特定していきますが、主な原因は以下のように分類されます。原因を正しく理解することは、適切な治療法を選択するための第一歩です。
- 造精機能障害: 日本の男性不妊において最も一般的な原因で、全体の82.4%を占めます2。これは、精子を造る機能そのものに問題がある状態です。
- 精路通過障害: 精子は作られているものの、その通り道(精路)が閉塞しているために精液中に出てこられない状態です6。
- 性機能障害: 勃起障害(ED)や、射精はするものの精液が膀胱に逆流してしまう逆行性射精などが原因となることがあります2。
- 生活習慣・環境要因: 日常の習慣が精子の質や量に影響を与える可能性も指摘されています。これらは改善可能な要因であり、治療の基本となります。
| 要因 | 精子への潜在的影響 | 推奨される対策 |
|---|---|---|
| 喫煙 | 精液所見の悪化、精子のDNA損傷を引き起こす酸化ストレスの増加9。 | 禁煙が強く推奨されます。 |
| 過度の飲酒 | 精液量の減少、精子形態の悪化の可能性9。 | 過剰摂取を避け、適度な量に留めるべきです。 |
| 肥満 (BMI高値) | 精液量や総精子数の減少傾向10。ホルモンバランスの乱れにも繋がります。 | 適度な運動とバランスの取れた食事による体重管理が重要です。 |
| ストレス | 前進運動率の低下との関連性が示唆されています9。 | リラクゼーション、十分な睡眠、趣味などでストレスを管理することが望ましいです。 |
| 食事 | 加工肉やトランス脂肪酸は質の低下に関連。抗酸化物質(ビタミンC, E)、亜鉛、オメガ3脂肪酸などは質の向上に寄与する可能性9。 | バランスの取れた食事を基本とし、野菜、果物、魚を積極的に摂取し、加工食品を避けることが推奨されます。 |
| 高温環境 | サウナ、長風呂、膝上でのPC使用などは精巣の温度を上昇させ、精子形成に悪影響を与える可能性があります11。 | 精巣を高温に晒す習慣は避けるべきです。 |
| 長時間の座位 | 精巣周辺の温度上昇や血流悪化につながる可能性があります10。 | 定期的に立ち上がって体を動かすことが推奨されます。 |
妊娠に向けた具体的な治療法:2024年最新ガイドラインと保険適用
ここからは、乏精子症に対する具体的な治療選択肢を、最新の科学的根拠と保険適用の情報と共に解説します。2024年に日本泌尿器科学会から発表された『男性不妊症診療ガイドライン』2は、各治療法がどの程度推奨されるかを「推奨グレード」として明確に示しており、治療選択の大きな助けとなります。さらに、2022年4月から多くの不妊治療が保険適用となり12、患者の経済的負担が大きく軽減されました。これらの情報を統合し、段階的に治療法を見ていきましょう。
Step 0: 生活習慣の改善
全ての治療の基礎となるのが、前述の表2に示した生活習慣の見直しです。JUAガイドラインでも、喫煙や肥満などの危険因子を持つ患者に対してカウンセリングを行うことは条件付きで推奨されています(推奨度C)4。すぐに始められることであり、精子の状態改善だけでなく、全体的な健康増進にも繋がります。
Step 1: 薬物療法
特定の状態の患者さんには、薬物による治療が有効な場合があります。
- クロミフェンクエン酸塩: テストステロン値が低い特発性乏精子症に対して用いられる内服薬です。脳に働きかけて精子形成を促すホルモンの分泌を刺激します。JUAガイドラインでは推奨度B(行うことを勧める)とされています2。複数の研究を統合したメタアナリシスでも、精子濃度や運動率の改善効果が示されています13。ただし、もともとは女性の排卵誘発剤であり、男性への使用は適応外使用(オフラベル)となりますが、特定の条件下で保険適用が認められています14。
- ゴナドトロピン療法 (hCG/FSH注射): 脳下垂体の機能低下により、精子形成に必要なホルモンが分泌されない「低ゴナドトロピン性性腺機能低下症」が原因の場合、このホルモンを直接注射で補充する治療が非常に効果的です。JUAガイドラインでは推奨度A(強く勧める)とされています2。また、特発性乏精子症に対しても、FSH製剤の投与が、特に高用量で有効性を示唆するメタアナリシスも報告されています15。
- 抗酸化サプリメント: コエンザイムQ10、L-カルニチン、ビタミンC・Eなどは、精子を損傷させる「酸化ストレス」から守る目的で経験的に用いられることがあります。JUAガイドラインでは、そのエビデンスはまだ限定的であるとして推奨度C(行ってもよい)とされていますが2、多くの研究をまとめたアンブレラレビューでは、抗酸化療法が精液の各種パラメータを有意に改善するという中等度のエビデンスが示されています16。これらは自費診療となります。
- 漢方薬: 補中益気湯などが日本では経験的に用いられることがありますが、日本生殖医学会のQ&Aでは、現時点で明確な統計的有効性は示されていないとされています11。一部のクリニックで自費診療として提供されています17。
Step 2: 手術療法
原因が特定でき、外科的に改善が見込める場合には手術が選択されます。
- 精索静脈瘤手術: 触診で確認できる(触知可能な)精索静脈瘤は、手術によって精液所見が改善し、自然妊娠率や生殖補助医療の成績が向上する可能性があるため、JUAガイドラインで強く推奨されています(推奨度A)218。これは、乏精子症に対する治療の中で最も科学的根拠が確立されたものの一つです。顕微鏡下で行う低位結紮術が標準的な方法で、保険適用となります19。
Step 3: 生殖補助医療 (ART)
上記の治療が適さない、あるいは効果が見られなかった場合、または重度の乏精子症の場合には、生殖補助医療(ART: Assisted Reproductive Technology)が次のステップとなります。
| 治療法 | 対象となる状態 | JUAガイドライン推奨度 | 保険適用の状況 | 簡単な説明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 薬物療法 | クロミフェンクエン酸塩 | 低テストステロンを伴う乏精子症 | B (行うことを勧める) | 保険適用 (条件あり) | 脳下垂体に働きかけ、精子を作るホルモンの分泌を促す内服薬2。 |
| ゴナドトロピン療法 (hCG/FSH注射) | 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 | A (強く勧める) | 保険適用 | 精子形成に直接必要なホルモンを注射で補充する、非常に効果的な治療2。 | |
| 抗酸化サプリメント | 特発性男性不妊症 | C (行ってもよい) | 自費診療 | 精子を酸化ストレスから守る目的で、コエンザイムQ10などが経験的に用いられる2。 | |
| 手術療法 | 精索静脈瘤手術 | 触知可能な精索静脈瘤 | A (強く勧める) | 保険適用 | 精巣の血流を改善し、精子の質を向上させることを目的とした手術2。 |
| 生殖補助医療 | 人工授精 (AIH) | 軽度~中等度の乏精子症 | B (行うことを勧める) | 保険適用 | 運動性の良い精子を調整し、排卵のタイミングで直接子宮内に注入する方法20。 |
| 顕微授精 (ICSI) | 重度の乏精子症、手術で採取した精子を使用する場合 | B (行うことを勧める) | 保険適用 | 1個の精子を直接卵子の中に注入して受精させる高度な技術6。 |
出典: JUAガイドライン推奨度2; 保険適用状況12; 説明20, 6
一般不妊治療から高度生殖医療へ
治療は一般的に、身体への負担が少ないものから段階的に進める「ステップアップ」方式が取られます。
- 人工授精 (AIH): 運動良好な精子を洗浄・濃縮し、排卵のタイミングに合わせてカテーテルで直接子宮内に注入する方法です。軽度から中等度の乏精子症で、女性側に大きな問題がない場合にまず試みられます6。保険適用となります20。
- 体外受精 (IVF) / 顕微授精 (ICSI): 人工授精で結果が出ない場合や、重度の乏精子症、精索静脈瘤手術後も精液所見の改善が乏しい場合には、より高度な生殖医療へと進みます。
- 体外受精(IVF): 採取した卵子に精子をふりかけて、自然に近い形で受精させる方法です。
- 顕微授精(ICSI): 重度の乏精子症に対する標準治療であり、顕微鏡下で1個の精子を選び出し、細い針で直接卵子の中に注入します6。たとえごく僅かでも精子がいれば、受精の可能性があります。精巣から直接精子を回収する手術(TESE)で得られた精子を用いる際にも必須の技術です。
- 無精子症の場合 (TESE): 精液中に全く精子が見られない「無精子症」と診断された場合でも、精巣内で精子が作られていれば、精巣の組織を一部採取する手術(精巣内精子採取術; TESE)によって精子を回収できる可能性があります。特に、顕微鏡を用いて精子が存在する可能性の高い精細管を見つけ出す「顕微鏡下精巣内精子採取術(micro-TESE)」は、JUAガイドラインでも強く推奨されています(グレードA)2。
治療成功率と女性の年齢:カップルで考えること
ここで極めて重要な点に触れなければなりません。それは、不妊治療、特に生殖補助医療(ART)の成功率は、女性パートナーの年齢に大きく影響されるという現実です。男性不妊の治療に専念している間にも、時間は経過していきます。厚生労働省の調査によると、ARTによる1回の胚移植あたりの妊娠率は、30歳では約42%ですが、35歳で約38%、40歳では約27%へと低下し、42歳では20%を下回ります21。男性側の治療と並行して、あるいは男性治療が長期にわたる可能性がある場合は特に、カップル全体として最適な治療戦略を立てることが不可欠です。不妊症は「カップルの問題」であるという認識4を持ち、時機を逸することなく、お二人で専門医と相談することが強く勧められます。
あなたは一人ではない:日本の男性不妊の「いま」
不妊や乏精子症の問題を一人で抱え込み、社会から孤立しているように感じる必要はありません。データは、これが多くの人々が直面している共通の課題であることを示しています。
- 有病率: 不妊症に悩むカップルのうち、約半数(48%)に男性側の要因が関与しているとされています2。
- 治療経験者: 日本では、夫婦の4.4組に1組が不妊の検査や治療の経験があります1。これは決して珍しいことではありません。
- ARTによる出生: 2022年には、日本で生まれた赤ちゃんの約10人に1人が生殖補助医療(ART)によって誕生しています22。ARTは特別な治療ではなく、一般的な選択肢となりつつあります。
- 仕事との両立: 不妊治療と仕事の両立は大きな課題です。治療経験者のうち26%以上が「両立が困難だった」と回答し、11%が実際に離職しています22。これは個人の問題だけでなく、社会全体で支えるべき課題です。
さらに詳しく知りたい方へ:標準的な精液検査を超えた高度な診断法
標準的な検査で原因が特定できない場合や、反復流産、ART不成功例などでは、より詳細な検査が検討されることがあります。
- 精子DNA断片化(SDF)検査: 精子が持つ遺伝情報(DNA)の損傷度合いを調べる検査です。DNAの損傷率が高いと、受精率や妊娠率の低下、流産率の上昇に関わると考えられています。WHO第6版でも「拡張検査」の一つとして追加され3、AUAガイドラインでも反復流産などの症例で考慮される可能性が示唆されています4。有望な検査ですが、日常的な診療における有用性や基準値についてはまだ標準化されておらず、自費診療となります7。
- ホルモン検査・遺伝子検査: 重度の乏精子症(例:精子濃度500万/mL未満)や無精子症の場合、原因を特定するために血液検査でホルモン値(FSH, LH, テストステロンなど)を測定したり、染色体異常やY染色体微小欠失の有無を調べたりすることが、ガイドラインで推奨されています2。
希望の未来:最新治療法への一瞥
男性不妊治療の分野は、日進月歩で研究が進んでいます。ここでは、将来的な可能性として研究されている技術を、過度な期待を抱かせないよう、責任ある形でご紹介します。これらはまだ研究段階であり、標準治療ではないことをご理解ください。
- 幹細胞治療: 精子を造り出す元となる細胞(精原幹細胞)を再生させることを目指す研究です。まだ動物実験の段階ですが、将来的には造精機能障害に対する根本的な治療法となる可能性があります2324。
- 遺伝子治療: 遺伝的な欠陥が原因である場合に、その遺伝子を修復する治療法です。不妊治療への応用はまだ非常に実験的な段階にあります25。
- AIと先進技術: 人工知能(AI)を用いて顕微授精(ICSI)の際に最も良好な精子を選別する技術や、手術(micro-TESE)の際に精子が存在する場所をより正確に見つけるための画像技術などが探求されています26。
よくある質問
1回の検査で精子が少ないと言われました。もう自然妊娠は無理ですか?
いいえ、決してそうとは限りません。前述の通り、精液所見は一度の検査だけでは判断できず、体調によって大きく変動します4。まずは日を改めて2回以上の検査を受けることが重要です。また、WHOの基準値は絶対的なものではなく、基準値を下回っていても自然妊娠するカップルはたくさんいます。まずは落ち着いて、専門医と相談し、正確な状態を把握することから始めましょう。
治療すれば、精子の数は必ず正常値に戻りますか?
治療法とその効果は、乏精子症の原因によって大きく異なります。例えば、精索静脈瘤の手術やホルモン補充療法のように、原因が明確で効果的な治療法が確立されている場合は、精液所見が大幅に改善する可能性があります2。一方で、原因が特定できない特発性の場合、薬物療法などの効果には個人差があります。必ずしも全ての人が正常値に戻るわけではありませんが、治療によって生殖補助医療の成績が向上するなど、妊娠の可能性を高めることは期待できます。
妻は問題ないのですが、私だけが治療を受ければいいですか?
不妊は「カップルの問題」です。たとえ男性側に明らかな原因が見つかったとしても、治療方針を決める際には必ず女性側の状態、特に年齢を考慮する必要があります21。男性側の治療に時間をかけている間に女性の妊孕性(妊娠する力)が低下してしまっては、元も子もありません。お二人で一緒に情報を共有し、婦人科と泌尿器科の医師と連携しながら、カップルにとって最適な治療計画を立てていくことが最も重要です。
どの病院・クリニックに行けばいいですか?
結論
乏精子症という診断は、大きな衝撃と不安をもたらすものです。しかし、この記事で見てきたように、それは決して妊娠への道を閉ざすものではありません。2024年の最新ガイドラインの登場と保険適用の拡大により、日本の男性不妊治療は新たな時代を迎えました。科学的根拠に基づいた明確な治療の道筋が示され、多くのカップルがよりアクセスしやすい形で高度な医療を受けられる環境が整いつつあります。重要なのは、不正確な情報に惑わされず、ご自身の状態を正しく理解し、信頼できる専門家と共に歩むことです。不妊はカップルで乗り越えるべき課題です。この記事で得た知識を武器に、ぜひパートナーと手を取り合って、専門医の扉を叩いてみてください。その一歩が、あなたの望む未来へと繋がる、最も確かな道となるはずです。
免責事項本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言に代わるものではありません。健康上の懸念や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- 不妊治療、社会全体で理解を深めましょう – 政府広報オンライン. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.gov-online.go.jp/article/202309/entry-7862.html
- Iwatsuki S, Tsujimura A, et al. Summary of the Clinical Practice Guidelines for Male Infertility by the Japanese Urological Association With the Support of the Japan Society for Reproductive Medicine. J Urol. 2024. doi:10.1097/JU.0000000000004122. PubMed. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40459122/
- Esteves SC, Zini A, et al. Sixth edition of the World Health Organization laboratory manual of semen analysis. Andrologia. 2023;55(11):e14852. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/20905998.2023.2298048
- Schlegel PN, Sigman M, et al. Diagnosis and treatment of infertility in men: AUA/ASRM guideline part I. Fertil Steril. 2021;115(1):54-61. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/diagnosis-and-treatment-of-infertility-in-men-auaasrm-guideline-part-i-2020/
- Agarwal A, Baskaran S, et al. The Sixth Edition of the WHO Manual for Human Semen Analysis: A Critical Review and SWOT Analysis. Life (Basel). 2021;11(12):1368. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8706130/
- 日本生殖医学会. 患者さんのための 生殖医療ガイドライン. 厚生労働省科学研究費補助金(成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)「性分化・生殖機能異常に関するエビデンスに基づいた診療体制の構築」研究班; 2023. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202327003B-sonota1.pdf
- Calik G, Gunes S. Sixth edition of the World Health Organization laboratory manual of semen analysis: a critical overview. J Reprod Infertil. 2024;25(2):97-106. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10929669/
- 日本生殖医学会. 生殖医療ガイドライン2021. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://ginzarepro.jp/column/medicine_guidelines_2021/
- Schlegel PN, Sigman M, et al. Updates to Male Infertility: AUA/ASRM Guideline (2024). J Urol. 2024. doi:10.1097/JU.0000000000004180. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.auajournals.org/doi/10.1097/JU.0000000000004180
- エスセットクリニック. 精子が少ない…その原因と対処法とは?. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://sset-clinic.com/guide/seisi_sukunai/
- 一般社団法人日本生殖医学会. 生殖医療Q&A(旧 不妊症Q&A). [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: http://www.jsrm.or.jp/public/funinsho_qa15.html
- こども家庭庁. 不妊治療が保険適用されています。. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/bef0ee9a-c14d-4203-b02b-051adf80f495/cf3a6623/20230401_policies_boshihoken_funin_01.pdf
- Borg M, Daniels M, et al. Male Factor Infertility and Clomiphene Citrate: A Meta-Analysis. Uro. 2023;3(3):237-245. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37559276/
- 永尾 光一. 男性不妊症に対する保険適用と実情. 産婦人科の実際. 2023;72(5):549-555. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.18888/sp.0000002549
- Santi D, De Vincentis S, et al. FSH dosage effect on conventional sperm parameters: a meta-analysis of randomized controlled studies. Andrology. 2019;7(5):565-575. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31274479/
- Alahmar AT, Hamoda AF, et al. Current treatment for male infertility: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses of randomized controlled trials. BMC Urol. 2024;24(1):207. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11614172/
- 後楽堂薬局. 男性不妊と漢方について. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://kanpo-tokyo.net/advice/%E7%94%B7%E6%80%A7%E4%B8%8D%E5%A6%8A%E3%81%AE%E6%BC%A2%E6%96%B9%E5%AF%BE%E5%87%A6%E6%B3%95/
- Iwatsuki S, Tsujimura A, et al. Summary of the Clinical Practice Guidelines for Male Infertility by the Japanese Urological Association With the Support of the Japan Society for Reproductive Medicine. ResearchGate. 2024. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/392373484_Summary_of_the_Clinical_Practice_Guidelines_for_Male_Infertility_by_the_Japanese_Urological_Association_With_the_Support_of_the_Japan_Society_for_Reproductive_Medicine
- 順天堂大学医学部附属順天堂医院 泌尿器科. 男性妊活外来. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://hosp.juntendo.ac.jp/clinic/department/hinyo/male.html
- ケアノート. 2022年4月からの不妊治療の保険適用条件、内容、厚生労働省Q&A. [インターネット]. 2022. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://carenote.jp/202204huninchiryo/
- 厚生労働省. 不妊治療の実態に関する調査研究 最終報告書. 2021. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/000766912.pdf
- 厚生労働省. 令和7年3月 不妊治療と仕事の両立のために. 2022. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001073887.pdf
- Shrestha A, Kc K, et al. Stem Cell Therapy for Oligospermia: Revolutionary Treatment Approach. Viezec. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.viezec.com/oligospermia-stem-cell-therapy-india/
- Gencell. Treatment of Oligospermia (Low Sperm Count) with Stem Cells. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.gencell.com.ua/en/low-sperm-count-oligospermia
- Immune Deficiency Foundation. Gene therapy. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://primaryimmune.org/understanding-primary-immunodeficiency/treatment/gene-therapy
- Bala G, Pathak R, et al. Future of Male Infertility Evaluation and Treatment: Brief Review of Emerging Technology. World J Mens Health. 2022;40(3):407-420. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/362265454_Future_of_Male_Infertility_Evaluation_and_Treatment_Brief_Review_of_Emerging_Technology
- 辻村 晃. 2024年 男性不妊治療に新時代到来! ~日本初の男性不妊症診療ガイドラインを読み解く~. メディカル・データ・ビジョン株式会社セミナー. 2024. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://www.mids.jp/kouen/files/20240206.pdf
- メンズファーティリティクリニック東京. 東京品川区の男性不妊治療専門クリニック. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://mens-funin.com/
- 銀座リプロ外科. 精子の数が少ない原因と治療法を解説. [インターネット]. [引用日: 2025年6月30日]. Available from: https://ginzarepro.jp/column/low-sperm-count-causes/