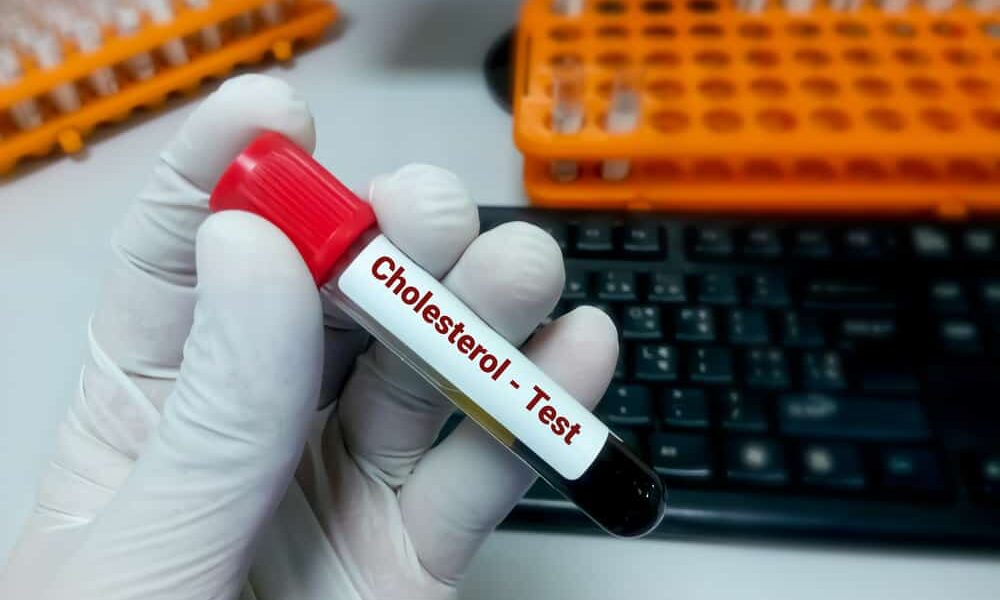この記事の科学的根拠
この記事は、JHO編集委員会が信頼できると判断した、最高品質の医学的根拠にのみ基づいて作成されています。本文中のすべての主張、統計、推奨事項は、以下に示す具体的な情報源に由来しており、読者の皆様がその典拠を確認できるようになっています。
- 日本動脈硬化学会 (JAS): 本記事における脂質異常症の診断基準、管理目標値、食事療法(The Japan Diet)、および薬物治療に関する中核的な推奨事項は、同学会が発行した「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」および「動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症診療ガイド2023年版」に完全に基づいています56。
- 久山町研究 (九州大学): 日本人における動脈硬化性疾患の危険性評価に用いられる「久山町研究スコア」に関する解説は、60年以上にわたるこの世界的に著名な疫学研究の成果に基づいています101139。
- 厚生労働省 (MHLW): 日本国内の脂質異常症の有病率に関する統計データは、厚生労働省が実施する「国民健康・栄養調査」の最新の公開情報に基づいています2627。
- 国際的な医学会・機関: 米国心臓協会(AHA)や米国国立コレステロール教育プログラム(NCEP)などの国際的なガイドラインからの知見を参考に、日本の基準との比較分析を行っています212224。
要点まとめ
- コレステロールは生命維持に必須ですが、量とバランスが崩れると動脈硬化の危険性を高めます。特にLDL(悪玉)とHDL(善玉)の均衡が重要です。
- 脂質異常症の診断は、日本動脈硬化学会の最新ガイドライン5に基づき、LDL、HDL、中性脂肪、non-HDLコレステロールの値で判断されます。
- 治療目標は画一的ではなく、日本人のデータに基づいた「久山町研究スコア」1011で個々の動脈硬化の危険性を評価し、それに応じて設定されます。
- 主な原因は飽和脂肪酸の多い食事や運動不足などの生活習慣ですが、遺伝的な要因(家族性高コレステロール血症など)も存在します113。
- 対策の基本は食事療法と運動療法です。特にJASが推奨する日本食ベースの食事「The Japan Diet」3435は有効性が示されています。
- 生活習慣の改善で目標を達成できない場合、スタチン薬37をはじめとする薬物治療が検討されます。
- sdLDL(超悪玉コレステロール)9やLp(a)73など、より進んだ危険性評価指標も存在し、個別の病状に応じて考慮されることがあります。
コレステロール高値と言われた後の対処ガイド
健康診断の結果で総コレステロールやLDLコレステロールの横に「↑」が付いていたり、「脂質異常症の疑い」というコメントを見て、不安や戸惑いを感じているかもしれません。「今すぐ薬が必要なのか」「放っておくと心筋梗塞や脳梗塞になるのでは」と、頭の中でさまざまなシナリオがよぎる方も多いでしょう。特に自覚症状がない場合、「本当に治療が必要なのか」が分かりにくく、誰に何を相談すればよいのか迷ってしまいがちです。まずは、その不安を一人で抱え込む必要はないということを知っておいてください。
“`
この記事で触れられているように、日本動脈硬化学会の最新ガイドラインでは、単なる数値の高低だけでなく、将来の心血管イベントリスクに基づいてコレステロールの管理を考えることが重要だとされています。ここでは、その考え方を踏まえながら、「検査結果をどう読むか」「何から始めればよいか」を整理していきます。心臓や血管の病気全体とのつながりを俯瞰して理解したい場合は、心血管疾患全般を体系的にまとめた心血管疾患の総合ガイドも合わせて参考にすると、現在の自分の位置づけが見えやすくなります。
まず押さえておきたいのは、「診断基準」と「治療開始の目安」は別物であるという点です。LDLコレステロールやnon-HDLコレステロールが一定値を超えると脂質異常症と診断されますが、それだけで直ちに薬が必要という意味ではありません。年齢、喫煙、血圧、血糖、既往歴などを含め、久山町研究スコアのような日本人データに基づく指標で総合的にリスク評価を行い、その結果に応じて管理目標値が決まります。こうした「脂質異常症とは何か」「どのくらいのリスクがあるのか」を体系的に理解したいときは、動脈硬化による合併症リスクまで丁寧に解説している脂質異常症(高脂血症)完全ガイドを読むと、検査結果の意味がぐっとクリアになります。
次の一歩として、多くの方に共通する「第一選択の対策」が食事と生活習慣の見直しです。JASが推奨するThe Japan Dietに沿って、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を減らし、魚・大豆製品・野菜・海藻・未精製穀類を増やすことは、LDL低下と中性脂肪改善の双方に役立ちます。また、体重管理や飲酒の見直し、適度な運動を組み合わせることで、HDLを保ちながら全体のバランスを整えることができます。具体的に「何をどれくらい食べればいいのか」「コンビニや外食でどう選べばいいのか」といった実践的な工夫は、JASの考え方を踏まえて献立例まで提示している脂質異常症の食事療法 完全ガイドを参考にすると、日常生活に落とし込みやすくなるでしょう。
一定期間しっかりと生活改善に取り組んでも目標値に届かない場合や、心筋梗塞・脳梗塞の既往、家族性高コレステロール血症などで初診時からリスクが高いと判断される場合には、薬物治療が検討されます。スタチンを中心とした薬は、LDLコレステロールを大きく下げる一方で、「飲み始めたら一生やめられないのでは」「筋肉痛などの副作用が怖い」と不安になる方も少なくありません。実際には、用量調整や薬剤の変更、他剤との併用など、ガイドラインに沿った柔軟な選択肢が用意されています。薬をどう位置づけ、どのように主治医と相談していけばよいかは、スタチンから最新治療までを網羅した脂質異常症の薬物療法を読むと、より安心して判断できるはずです。
一方で、「痩せているから自分は大丈夫」「サプリを飲んでいるから検査値は気にしなくていい」といった誤解は要注意です。痩せていても内臓脂肪型肥満や遺伝的素因でコレステロールが高い方は珍しくなく、サプリメントはあくまで補助的な位置づけであって、医薬品や生活習慣の改善を置き換えるものではありません。また、短期間で極端な食事制限を行うと、かえって体調を崩すこともあります。安全で現実的なステップで血中脂質を下げていきたい場合は、6週間という具体的な期間を区切って11の実践策を示している脂質管理の基本をヒントに、「続けられるやり方」を一緒に探してみてください。
コレステロールの数値に矢印が付いていても、それは必ずしも「すぐに重大な病気になる」という宣告ではなく、「今から生活と治療を整えれば、将来のリスクを大きく減らせる」というサインでもあります。検査結果の意味を理解し、自分のリスクレベルを知り、できるところから一つずつ対策を始めていけば、数字は少しずつでも確実に変わっていきます。今回の結果をきっかけに、この記事や関連ガイドを手がかりにしながら、主治医と協力して、ご自身に合ったペースでコレステロール管理に取り組んでいきましょう。
“`
第1章:コレステロールの基本:敵か味方か?
「コレステロール」と聞くと、多くの人が健康に悪いものという印象を持つかもしれません。しかし、コレステロールは本来、私たちの体にとって不可欠な物質です。問題となるのは、その「量」と「質」、そして「バランス」なのです。
1.1. コレステロールの必須の役割
コレステロールは脂質の一種で、体内に約100~150グラム存在します。その主な役割は極めて重要で、国立循環器病研究センターによると、全身の約37兆個の細胞を包む「細胞膜」の構成成分となるほか、食物の消化吸収を助ける「胆汁酸」や、体の調子を整える「各種ホルモン」(副腎皮質ホルモン、性ホルモンなど)の原料としても利用されます30。このように、コレステロールは生命を維持するために決して欠かすことのできない物質なのです。体内のコレステロールの約70~80%は肝臓などで合成され、残りの20~30%が食事から摂取されます。
1.2. 血液中の輸送隊:善玉(HDL)、悪玉(LDL)、中性脂肪(TG)
コレステロールは脂質であるため、血液(主成分は水)に溶けることができません。そのため、血液中を移動する際には、「リポタンパク質」というカプセルのような粒子に乗って運ばれます。このリポタンパク質の種類によって、コレステロールは「善玉」「悪玉」などと呼ばれます。
- LDL(低密度リポタンパク質)コレステロール: 「悪玉コレステロール」として知られています。その役割は、肝臓で作られたコレステロールを全身の細胞に届けることです。しかし、血中でLDLコレステロールが過剰になると、血管の壁に蓄積し、酸化されることで動脈硬化を引き起こす原因となります5051。
- HDL(高密度リポタンパク質)コレステロール: 「善玉コレステロール」と呼ばれます。HDLは、全身の余分なコレステロールを回収し、肝臓に戻す働き(逆コレステロール転送系)を担っています52。これにより動脈硬化の進行を防ぐため、善玉と称されます。
- 中性脂肪(トリグリセリド、TG): 体のエネルギー源として貯蔵される脂質です。過剰になると肥満の原因となるだけでなく、HDLコレステロールを減少させ、LDLコレステロールを小型化(後述のsdLDL)させるなど、間接的に動脈硬化を促進します53。
健康な血管を保つためには、これらの脂質のバランスが非常に重要になります。
第2章:健康診断の結果を正しく読み解く【JAS 2022/2023年版ガイドライン】
健康診断で渡される結果表には、さまざまな脂質関連の項目が並んでいます。ここでは、日本動脈硬化学会が「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」で定めた、脂質異常症の診断基準について詳しく解説します56。
2.1.【重要表1】脂質異常症の診断基準
同学会は、将来の動脈硬化性疾患(心筋梗塞や脳梗塞など)の危険性を早期に発見し、介入するためのスクリーニング(ふるい分け)基準として、以下の数値を定めています。特に注目すべきは、non-HDLコレステロールが必須項目として位置づけられた点です。これは、総コレステロールから善玉のHDLコレステロールを引いた値で、動脈硬化を引き起こす可能性のある全てのコレステロールの総量を示します。
| 脂質異常症のタイプ | 基準値 (mg/dL) |
|---|---|
| 高LDLコレステロール血症 | 140 mg/dL 以上 |
| 境界域高LDLコレステロール血症 | 120~139 mg/dL |
| 低HDLコレステロール血症 | 40 mg/dL 未満 |
| 高トリグリセリド(中性脂肪)血症 | 150 mg/dL 以上 |
| 高non-HDLコレステロール血症 | 170 mg/dL 以上 |
| 境界域高non-HDLコレステロール血症 | 150~169 mg/dL |
出典: 日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」5を基に作成。随時採血の場合は、高トリグリセリド血症の基準が175mg/dL以上となります。
2.2. 注意:「診断基準」は「治療開始基準」ではない
ここで非常に重要な点があります。上記の診断基準は、あくまで「脂質異常症という状態にある」ことを示すスクリーニングのための基準であり、この数値を超えたからといって、直ちに薬物治療が必要になるわけではありません10。これは、ご自身の体の状態を知り、生活習慣を見直す、あるいはより詳細な危険性評価に進むための「出発点」と捉えるべきです。実際の治療方針は、次の章で解説する個々人の危険性評価に基づいて決定されます。
第3章:あなたの危険性は?「久山町研究スコア」による最新リスク評価
脂質異常症の管理目標は、すべての人に同じ数値が適用されるわけではありません。最新のガイドラインでは、個々人が持つ他の危険因子を総合的に評価し、将来の心筋梗塞や脳梗塞の発症危険性に応じて、管理目標値を設定します。その評価に用いられるのが、「久山町研究スコア」です11。
3.1. 日本が誇る60年以上の疫学研究「久山町研究」
「久山町研究」とは、福岡県糟屋郡久山町の住民を対象に、九州大学が1961年から継続して行っている疫学調査です3940。この研究は、日本人の生活習慣病の実態や危険因子を長期間にわたって追跡調査してきた、世界的に見ても極めて貴重なデータを提供しています。その信頼性の高さから、日本の医療政策や診療ガイドライン策定に大きな影響を与えてきました。
3.2. なぜ吹田スコアから変更されたのか?
以前のガイドラインでは「吹田スコア」という評価法が用いられていました。しかし、2022年版ガイドラインから「久山町研究スコア」が採用されました56。その最大の理由は、久山町研究スコアが、日本人に多いとされる脳梗塞(特にアテローム血栓性脳梗塞)の発症危険性も評価に含んでおり、より日本の医療の実情に即した評価が可能であると判断されたためです11。これにより、個々の患者さんに対して、より精度の高い危険性評価と、それに基づいた適切な治療目標の設定が可能になりました。
3.3.【重要表2】危険性区分別の脂質管理目標値
久山町研究スコアを用いて、年齢、性別、喫煙、血圧、血糖値、HDLコレステロール値などから個人の危険性を「低・中・高」の3段階に分類します。そして、その危険性区分に応じて、目指すべきLDLコレステロール(またはnon-HDLコレステロール)の管理目標値が設定されます。心筋梗塞などの既往がある方は「二次予防」として、最も厳しい管理が求められます。
| 危険性区分 | LDL-C 管理目標値 (mg/dL) | non-HDL-C 管理目標値 (mg/dL) |
|---|---|---|
| 二次予防 (冠動脈疾患の既往) |
< 70 | < 100 |
| 高危険性群 | < 100 | < 130 |
| 中危険性群 | < 120 | < 150 |
| 低危険性群 | < 140 | < 170 |
出典: 日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」56を基に作成。糖尿病、慢性腎臓病、末梢動脈疾患などの併存疾患によっても危険性分類は変わります。
第4章:コレステロール値が高くなる主な原因
コレステロール値が基準を超える原因は一つではありません。生活習慣と遺伝的要因が複雑に関与しています。
4.1. 食生活と生活習慣
最も一般的で、かつ改善の余地が大きいのが生活習慣です。主な要因として以下が挙げられます12。
- 食事: 肉の脂身、バター、生クリームなどに多く含まれる「飽和脂肪酸」や、洋菓子や加工食品に含まれる「トランス脂肪酸」の過剰摂取は、LDLコレステロールを上昇させる最大の要因です。
- 運動不足: 運動不足はHDL(善玉)コレステロールを減少させ、中性脂肪を増加させる傾向があります。
- 肥満: 特に内臓脂肪型の肥満は、脂質代謝異常と密接に関連しています。
- 喫煙: 喫煙はHDLコレステロールを著しく減少させ、血管を傷つけ、LDLコレステロールの酸化を促進し、動脈硬化を強力に進行させます。
- 過度の飲酒: アルコールの過剰摂取は中性脂肪を著しく増加させます。
- その他: ストレスや、甲状腺機能低下症、腎臓病などの他の疾患が原因となることもあります。
4.2. 遺伝的要因:家族性高コレステロール血症(FH)
生活習慣に問題がないにもかかわらず、著しくコレステロール値が高い場合、遺伝的な要因を考慮する必要があります。その代表が「家族性高コレステロール血症(FH)」です13。FHは、LDLコレステロールを細胞内に取り込むための「LDL受容体」の遺伝子に変異があるために起こる疾患で、生まれつき血液中のLDLコレステロールが非常に高くなります。日本人では200~500人に1人の割合で存在すると推定されています59。FHの患者さんは若いうちから動脈硬化が進行しやすく、早期に心筋梗塞などを発症する危険性が高いため、早期発見と強力な薬物治療が不可欠です。未治療の状態でLDLコレステロール値が180mg/dL以上である場合や、家族にも同様にコレステロールが高い人がいる場合は、専門医への相談が強く推奨されます。難治性家族性高コレステロール血症患者会などの団体は、患者への情報提供や支援活動を行っています1415。
第5章:食事で改善する【JAS推奨「The Japan Diet」】
脂質異常症の治療の基本は、薬物治療の前に、まず生活習慣の改善、特に食事療法から始めることです。日本動脈硬化学会は、これまでの研究成果を基に、日本人の食文化に適した健康的な食事スタイルとして「The Japan Diet」を提唱しています343536。
5.1.【重要表3】「The Japan Diet」の基本
これは、欧米の食事療法をそのまま持ち込むのではなく、日本の伝統的な食生活の長所を活かし、科学的根拠に基づいて構築された食事法です。その基本構成は以下の通りです。
| 積極的に摂るべき食品 | 控えるべき食品 |
|---|---|
| • 魚(特に青魚:EPA・DHA源) • 大豆・大豆製品(豆腐、納豆など) • 野菜(緑黄色野菜を含む) • 海藻 • きのこ • 未精製穀類(玄米、全粒粉パンなど) • 牛乳・乳製品 |
• 肉の脂身 • 加工肉(ソーセージ、ベーコン) • バター、ラード • 鶏卵(特に卵黄) • 砂糖、果糖を多く含む菓子・飲料 • 精製された穀物(白米、白いパン) |
出典: 日本動脈硬化学会「The Japan Diet 食生活を見直しましょう」3560を基に作成。減塩も重要なポイントです。
5.2. 科学的根拠のある注目成分
「The Japan Diet」で推奨される食品には、脂質代謝を改善する成分が豊富に含まれています。
- EPA・DHA(エイコサペンタエン酸・ドコサヘキサエン酸): イワシ、サバ、アジなどの青魚に豊富に含まれるオメガ3系脂肪酸です。中性脂肪を低下させる効果が確立しているほか、炎症抑制や血栓予防など、多角的に動脈硬化を防ぐ作用が数多くの研究で示されています454661。
- 大豆タンパク質・イソフラボン: 豆腐や納豆などの大豆製品に含まれ、血中のLDLコレステロールを低下させる効果が報告されています6263。
- 緑茶カテキン: 緑茶に含まれるポリフェノールの一種です。複数の研究を統合したメタ解析において、カテキンが総コレステロールとLDLコレステロールを有意に低下させることが示されています44。これは、コレステロールの吸収を阻害する作用や、LDLの酸化を防ぐ作用によるものと考えられています6465。
第6章:薬物治療が必要な場合
食事療法や運動療法を3~6ヶ月続けても脂質の管理目標が達成できない場合や、危険性が非常に高いと判断された場合には、薬物治療が検討されます。
6.1.【重要表4】日本の主要なスタチン薬
脂質異常症の治療薬として、最も基本的かつ中心的な役割を果たすのが「スタチン」です。スタチンは、肝臓でのコレステロール合成に関わる重要な酵素(HMG-CoA還元酵素)の働きを阻害することで、血液中のLDLコレステロールを強力に低下させます。日本国内では、効果の強さによって「標準スタチン」と「強力スタチン」に分類されています373866。
| 分類 | 一般名(主な商品名) |
|---|---|
| 強力スタチン (Strong Statin) |
アトルバスタチン(リピトール) ロスバスタチン(クレストール) ピタバスタチン(リバロ) |
| 標準スタチン (Standard Statin) |
プラバスタチン(メバロチン) シンバスタチン(リポバス) フルバスタチン(ローコール) |
出典: つくば医療コンソーシアム「HMG-CoA還元酵素阻害剤(スタチン)フォーミュラリ」37等を基に作成。
6.2. スタチン以外の選択肢
スタチンで効果が不十分な場合や、副作用で使用できない場合には、他の作用機序を持つ薬が併用または代替として用いられます。
- エゼチミブ: 小腸にあるコレステロールトランスポーターを阻害し、食事由来および胆汁由来のコレステロールの吸収を抑える薬です。スタチンと併用することで、LDLコレステロールをさらに15~20%低下させる高い効果が期待できます6768。
- PCSK9阻害薬: LDL受容体を分解するPCSK9というタンパク質の働きを阻害する注射薬です。スタチンやエゼチミブでも管理目標を達成できない重症のFH患者さんなどに用いられ、LDLコレステロールを約60%と劇的に低下させます。
- フィブラート系薬: 主に中性脂肪を低下させ、HDLコレステロールを増加させる効果があります。中性脂肪が特に高い場合に用いられます。
6.3. 副作用が心配な方へ:スタチン不耐への対処法
スタチンの副作用として最も知られているのが、筋肉痛や筋肉の脱力感などの筋肉に関連する症状です。頻度は高くありませんが、もし服用中にこのような症状が現れた場合は、自己判断で中止せず、必ず主治医に相談してください。日本動脈硬化学会は「スタチン不耐に関する診療指針」69を公開しており、医師は原因を特定し、減量、他剤への変更、隔日投与などの対処法を検討します71。副作用を恐れて必要な治療を中断してしまうことが、最も避けるべき事態です。
第7章:【より深く知りたい方へ】先進的危険性マーカー
通常の健康診断では測定されませんが、より詳細な動脈硬化の危険性を評価するために、以下のような先進的な脂質マーカーが臨床で用いられることがあります。
7.1. 超悪玉コレステロール「small dense LDL (sdLDL)」
同じLDLコレステロールの中でも、粒子が小さく密度の高い「small dense LDL(sdLDL)」は、血管壁に入り込みやすく、酸化されやすいため、「超悪玉コレステロール」と呼ばれています972。通常のLDLコレステロール値が基準範囲内でも、sdLDLが高い場合は動脈硬化の危険性が高いと考えられています。特に中性脂肪が高い方や、メタボリックシンドロームの方で高値になりやすいことが知られています。
7.2. 遺伝で決まる危険因子「リポタンパク(a) [Lp(a)]」
リポタンパク(a)(Lp(a))は、LDLにアポタンパク(a)という特殊なタンパク質が結合したリポタンパク質です73。その血中濃度は主に遺伝によって決まり、食事や運動などの生活習慣ではほとんど変化しません74。Lp(a)高値は、冠動脈疾患や脳梗塞、大動脈弁狭窄症の独立した危険因子であることが数多くの研究で証明されており75、日本動脈硬化学会も、特に若年で動脈硬化性疾患を発症した場合や、家族歴がある場合などに一度は測定することを推奨しています。
よくある質問
Q1: 痩せているのにコレステロールが高いのはなぜですか?
A1: 体型に関わらずコレステロール値が高くなることは珍しくありません。主な原因として、①見た目は痩せていても内臓脂肪が多い「隠れ肥満」、②飽和脂肪酸(肉の脂身やバターなど)の摂取量が多い食生活、③遺伝的要因(家族性高コレステロール血症など)、④極端な糖質制限による脂質摂取の増加、などが考えられます1。体重だけでなく、食事内容や家族の病歴を見直すことが重要です。
Q2: 高齢者(75歳以上)でも治療は必要ですか?
Q3: コレステロールを下げるサプリメントは効果がありますか?
A3: 特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品の中には、コレステロールの吸収を抑える、あるいは血中コレステロールを低下させるといった表示が許可されている製品があります。例えば、植物ステロール、キトサン、大豆タンパク質などが知られています。これらはあくまで食事療法を補助するものであり、医薬品のような強力な効果は期待できません。利用する際は、その効果と安全性を十分に理解し、治療の基本である食事療法や運動療法をおろそかにしないことが大切です。薬物治療中の方は、摂取前に必ず主治医や薬剤師に相談してください。
結論
コレステロール値は、単なる数字の羅列ではなく、あなたの未来の健康状態を映し出す重要な鏡です。健康診断で指摘された高い数値は、これまでの生活習慣を見直し、より健康的な未来への舵を切るための貴重なきっかけとなります。本記事で解説したように、最新の日本のガイドラインでは、画一的な基準ではなく、個々の危険性に応じたきめ細やかな管理が推奨されています。ご自身の数値を正しく理解し、まずは「The Japan Diet」のような実践しやすい食事改善から始めてみてください。そして、不安や疑問があれば一人で抱え込まず、必ずかかりつけの医師や専門医に相談してください。専門家と手を取り合って、あなたに合った対策を粘り強く続けることが、動脈硬化を防ぎ、健康長寿を実現するための最も確実な道筋となるでしょう。
免責事項本記事は、信頼できる医学情報に基づいて作成されていますが、読者個人の状態に対する専門的な医学的アドバイスを提供するものではありません。健康に関するいかなる懸念や、治療に関する決定を下す前には、必ず資格を有する医療専門家にご相談ください。
参考文献
- 梅田シティクリニック. 健康診断でLDLコレステロール値が高いと言われた・・・原因と対策 … [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://umeda-cityclinic.com/column/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E8%A8%BA%E6%96%AD%E3%81%A7ldl%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%80%A4%E3%81%8C%E9%AB%98%E3%81%84%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%9F/
- 味の素株式会社. LDL(悪玉)コレステロールが高い原因は?生活習慣のポイントを解説 | 未来献立®︎ コラム [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/rd/miraikondate/column/article_007/
- 厚生労働省. 特定健診・保健指導について [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000099071.pdf
- 厚生労働省. 特定健診・特定保健指導について [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html
- 日本動脈硬化学会. ガイドライン【日本動脈硬化学会】 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.j-athero.org/jp/publications/guideline/
- 日本心臓財団. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン・エッセンス | | 循環器病の治療に関するガイドライン・エッセンス [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.jhf.or.jp/pro/a%26s_info/guideline/post_2.html
- 大正製薬. LDL(悪玉)コレステロール値を下げる食べ物・飲み物 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://brand.taisho.co.jp/contents/livita/242/
- しぎょう循環器内科・内科・皮膚科・アレルギー科. LDL(悪玉コレステロール)だけ高く困っていませんか?どうやったら下がるか?ほっていて危険はないのか?専門医が解説します。 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://shigyo-medical.com/info/ldl%EF%BC%88%E6%82%AA%E7%8E%89%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%AB%EF%BC%89%E3%81%A0%E3%81%91%E9%AB%98%E3%81%8F%E5%9B%B0%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%9B/
- 武田病院グループ. 30.悪玉コレステロールは本当に全部悪いの? [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.takedahp.or.jp/ijinkai/blog/2024/10/03/post-703/
- CareNet.com. 寄せられた疑問に答える、脂質異常症診療ガイド2023発刊/日本 … [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.carenet.com/news/general/carenet/56974
- HOKUTO. 【久山町スコア】2022年版で新採用!動脈硬化性疾患予防ガイドライン [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://hokuto.app/post/J0cyFUG47xREzRa6SAtr
- Growbase. 特定保健指導対象者を選定する基準とは?項目を詳しく解説! [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://hss.wellcoms.jp/blog/n0090
- 生活習慣病オンライン. 脂質異常症の診断基準 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.sageru.jp/ldl/knowledge/criterion.html
- 難治性家族性高コレステロール血症患者会. 難治性家族性高コレステロール血症患者会 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://ldl-apheresis.com/
- 難治性家族性高コレステロール血症患者会. 患者会の活動紹介 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: http://ldl-apheresis.com/page8.html
- 日本動脈硬化学会. 追悼 難治性家族性高コレステロール血症患者会前代表 栗山幸生様 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.j-athero.org/jp/20231222-2/
- 日本動脈硬化学会. 役員・委員会名簿 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.j-athero.org/jp/outline/yakuin/
- 日本医学会. No.86 日本動脈硬化学会 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://jams.med.or.jp/members-s/86.html
- 日本動脈硬化学会. 一般社団法人日本動脈硬化学会 各委員会委員一覧 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.j-athero.org/jp/wp-content/uploads/outline/pdf/iinkai/iinkai.pdf
- Arai H, et al. Japan Atherosclerosis Society (JAS) Guidelines for Prevention of Atherosclerotic Cardiovascular Diseases 2022. J Atheroscler Thromb. 2023;30(Special_Issue):1-103. doi: 10.5551/jat.ED200. PMID: 38123343. [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38123343/
- American Heart Association. What Your Cholesterol Levels Mean [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/about-cholesterol/what-your-cholesterol-levels-mean
- Virani SS, et al. 2023 AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA Guideline for the Management of Patients With Chronic Coronary Disease. Circulation. 2023;148(9):e9-e119. doi: 10.1161/CIR.0000000000001168. [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001168
- Virani SS, et al. 2023 AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA Guideline for the Management of Patients With Chronic Coronary Disease: A Report of the American Heart Association/American College of Cardiology Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2023;82(9):833-947. doi: 10.1016/j.jacc.2023.04.015. [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIR.0000000000001168
- National Heart, Lung, and Blood Institute. ATP III Guidelines At-A-Glance Quick Desk Reference [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/atglance.pdf
- HMSA. ATP III Guidelines At-a-Glance [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://prc.hmsa.com/s/article/ATP-III-Guidelines-At-a-Glance
- National Institute of Health and Nutrition. Annual changes in current data|Health Japan 21 (the second term) Analysis and Assessment Project [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.nibiohn.go.jp/eiken/kenkounippon21/en/kenkounippon21/genjouchi.html
- 生活習慣病オンライン. 総コレステロール値が240mg/dL以上は、男性10.1%、女性23.1 … [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://seikatsusyukanbyo.com/statistics/2024/010820.php
- Japan Atherosclerosis Society. Guidelines [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.j-athero.org/jp/en/guidelines/
- Japan Atherosclerosis Society. TOP PAGE [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.j-athero.org/jp/english/
- 国立循環器病研究センター. 脂質異常症|病気について [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.ncvc.go.jp/hospital/pub/knowledge/disease/dyslipidemia/
- 東京大学医学部附属病院 国際検診センター. センターについて [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.intl-pvntmed-uth.jp/contents/about.html
- 東京大学医学部附属病院 予防医学センター. 東京大学医学部附属病院 予防医学センター [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.todai-yobouigaku-dock.jp/
- ハイメディック・東大病院コース. ハイメディック・東大病院コース [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.himedic.jp/course/todai.html
- 日本生活習慣病予防協会. 動脈硬化を予防・改善するための食事スタイル 日本動脈硬化学会の「The Japan Diet」 | ニュース [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://himan.jp/news/2020/000391.html
- 日本動脈硬化学会. The Japan Diet 食生活を見直しましょう [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.j-athero.org/jp/general/9_japandiet/
- 日本動脈硬化学会. 動脈硬化を知る×動脈硬化を予防する食事 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.j-athero.org/jp/wp-content/uploads/general/pdf/The_Japan_Diet.pdf
- つくば医療コンソーシアム. HMG-CoA還元酵素阻害剤(スタチン)フォーミュラリ Ver.1 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.xn--y8jybwb572vjpd47vth9d.jp/pdf/%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%81%B0%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%80%80%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%81%E3%83%B3%20%E7%B5%B1%E5%90%88%E7%89%88.pdf
- 薬剤師国家試験対策.com. 日本で使われているスタチン [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://be89314.com/column10.html
- 認知症ねっと. 久山町研究とは?~認知症の追跡調査 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://info.ninchisho.net/mci/k140
- Kiyotake K, et al. Epidemiology of Stroke in a General Japanese Population: The Hisayama Study. J Atheroscler Thromb. 2023;30(7):851-866. doi: 10.5551/jat.RV22004. [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jat/30/7/30_RV22004/_html/-char/en
- The Hisayama Study. Trends in cardiovascular diseases and diabetes mellitus|The Hisayama Study [インターネット]. Kyushu University; [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.hisayama.med.kyushu-u.ac.jp/en/cardiova/
- Murakami K, et al. Data Resource Profile: The Japan National Health and Nutrition Survey (NHNS). Int J Epidemiol. 2015;44(6):1842-8. doi: 10.1093/ije/dyv210. [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://academic.oup.com/ije/article/44/6/1842/2572514
- Grundy SM, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol. Circulation. 2019;139(25):e1082-e1143. doi: 10.1161/CIR.0000000000000625. [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/cir.0000000000000625
- Kim A, et al. Green tea catechins decrease total and low-density lipoprotein cholesterol: a systematic review and meta-analysis. J Am Diet Assoc. 2011;111(11):1720-9. doi: 10.1016/j.jada.2011.08.009. PMID: 22027055. [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22027055/
- Mason RP, et al. Emerging Mechanisms of Cardiovascular Protection for the Omega-3 Fatty Acid Eicosapentaenoic Acid. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2020;40(5):1135-1147. doi: 10.1161/ATVBAHA.119.313346. PMID: 32212849. [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32212849/
- Mason RP, et al. Emerging Mechanisms of Cardiovascular Protection for the Omega-3 Fatty Acid Eicosapentaenoic Acid. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2020;40(5):1135-1147. [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7176343/
- 厚生労働省. 第4期特定健診・特定保健指導の見直しについて [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001160411.pdf
- e-ヘルスネット(厚生労働省). 特定健康診査の検査項目 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/metabolic/m-04-005.html
- 生活向上WEB. 総コレステロール | 検査データの読み方 | 治験ボランティア募集と健康情報発信サイト [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: http://www.seikatsu-kojo.jp/health/rinken/tc
- SALUS CLINIC. 総コレステロールが高いとどうなる? ~脂質異常症との関連や原因 … [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://salusclinic.jp/column/lifestyle-related-diseases/article-68/
- Soppert J, et al. Pathophysiology and treatment of atherosclerosis: Current view and future perspective on lipoprotein modification treatment. J Mol Cell Cardiol. 2017;109:95-108. [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5355390/
- Pirillo A, et al. LDL-cholesterol versus HDL-cholesterol in the atherosclerotic plaque: inflammatory resolution versus thrombotic chaos. Cardiovasc Res. 2012;95(3):271-3. doi: 10.1093/cvr/cvs178. PMID: 22548566. [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22548566/
- e-ヘルスネット(厚生労働省). 脂質異常症 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/metabolic/m-05-004.html
- Rosenson RS, et al. HDLs and the pathogenesis of atherosclerosis. Nat Rev Cardiol. 2018;15(4):195-207. doi: 10.1038/nrcardio.2018.1. PMID: 29561322. [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29561322/
- 健康長寿ネット. 高齢者の脂質異常症の診断 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/shishitsuijoushou/shindan.html
- CareNet.com. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版、主な改訂点5つ/日本動脈硬化学会 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.carenet.com/news/general/carenet/54680
- アークレイ クリニックサポート. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン5年ぶり改訂、糖尿病など近年の日本の問題をカバー [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://arkrayclinicsupport.com/blog-of114/
- Viatris e Channel. 脂質異常症治療の基礎知識 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.viatris-e-channel.com/viatris/healthylife/pdf/UAR51N007B.pdf
- 国立循環器病研究センター. 診療科等の概要家族性高コレステロール血症 (Familial Hypercholesterolemia: FH)について [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.ncvc.go.jp/hospital/section/genome/genomesupport/fhyperchol/
- himan.jp. 動脈硬化を予防・改善するための食事スタイル 日本動脈硬化学会の「The Japan Diet」 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://himan.jp/news/2020/000391.html#:~:text=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8B%95%E8%84%88%E7%A1%AC%E5%8C%96%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E3%81%AF,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%80%82
- Weitz D, et al. New Insights into Mechanisms of Action for Omega-3 Fatty Acids in Atherothrombotic Cardiovascular Disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2019;39(1):e1-e13. [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6330561/
- Velasquez MT, Bhathena SJ. Effect of soy proteins and isoflavones on lipid metabolism and involved gene expression. J Nutr Biochem. 2007;18(11):711-23. doi: 10.1016/j.jnutbio.2007.08.003. PMID: 17981741. [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17981741/
- Serna R, et al. Effects of Soy Protein Containing of Isoflavones and Isoflavones Extract on Plasma Lipid Profile in Postmenopausal Women as a Potential Prevention Factor in Cardiovascular Diseases. Nutrients. 2021;13(8):2824. [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8398438/
- Bursill CA, et al. A green tea extract lowers plasma cholesterol by inhibiting cholesterol synthesis and upregulating the LDL receptor in the cholesterol-fed rabbit. Atherosclerosis. 2007;193(1):23-30. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2006.08.033. PMID: 16970948. [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16970948/
- Suzuki-Sugihara N, et al. Green tea catechins prevent low-density lipoprotein oxidation via their accumulation in low-density lipoprotein particles in humans. Br J Nutr. 2016;115(2):225-33. doi: 10.1017/S000711451500438X. PMID: 26773777. [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26773777/
- 山形県病院薬剤師会. HMG-CoA還元酵素阻害剤(スタチン)のフロー図 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.ypa21.or.jp/pdf/formularyinfo05.pdf
- 神戸きしだクリニック. エゼチミブ(ゼチーア) – 代謝疾患治療薬 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://kobe-kishida-clinic.com/metabolism/metabolism-medicine/ezetimibe/
- クリニックフォア. エゼチミブで脂質吸収抑制・コレステロール管理ガイド|オンライン診療で簡単スタート [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://jrsandaaga.com/diet_column/ezetimibe/
- 日本動脈硬化学会. スタチン不耐に関する診療指針 2018 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.j-athero.org/jp/wp-content/uploads/publications/pdf/statin_intolerance_2018.pdf
- 日本動脈硬化学会. 脂質異常症診療のQ&A [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.j-athero.org/jp/publications/si_qanda/
- U.S. Department of Veterans Affairs. Management of Statin Intolerance Clinician Factsheet IB 10-1695 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.pbm.va.gov/PBM/AcademicDetailingService/Documents/508/10-1695_Dyslipidemia_Provider_StatinIntolerance_P97132.pdf
- 有楽橋クリニック. small dense LDL(超悪玉コレステロール)測定について [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://yurakubashi.com/blog/677
- SRL総合検査案内. リポプロテイン(a) [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://test-directory.srl.info/akiruno/test/detail/005680200
- シスメックス プライマリケア. リポ蛋白(a [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://primary-care.sysmex.co.jp/speed-search/detail.php?pk=152
- LSIメディエンス. リポ蛋白(a)[Lp(a)]|脂質|生化学検査|WEB総合検査案内|臨床検査 [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://data.medience.co.jp/guide/guide-01070030.html
- 日本医師会. かかりつけ医のための 適正処方の手引き [インターネット]. [2025年7月25日参照]. Available from: https://www.med.or.jp/dl-med/chiiki/tebiki/R0201_shohou_tebiki4.pdf