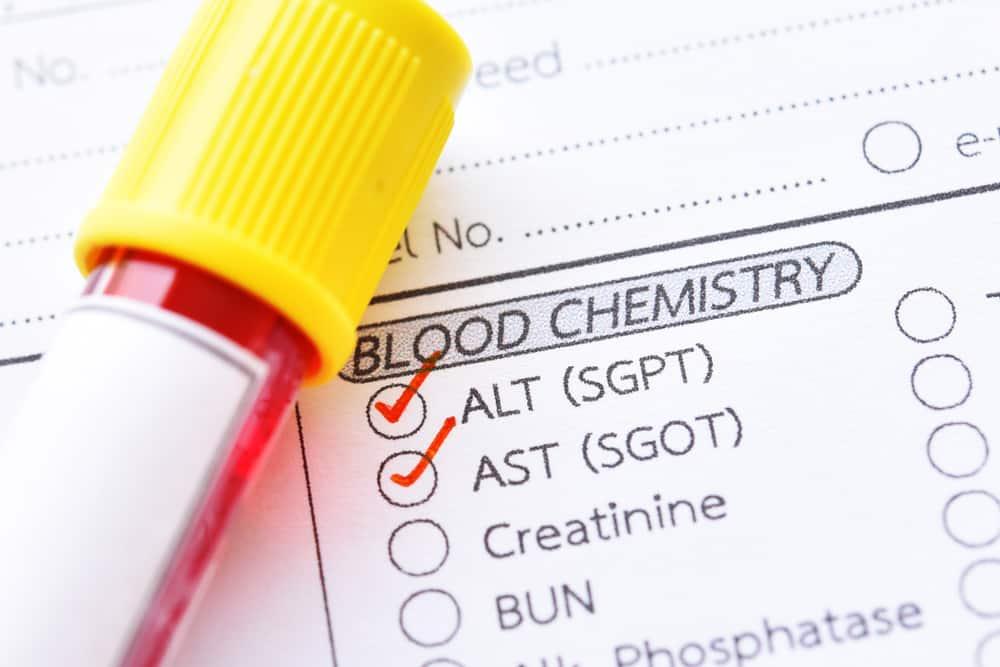仕事や家事で忙しい毎日、「なんだか疲れがとれないな」と感じることはありませんか?多くの人がそれを単なる疲労と考えがちですが、もしかしたらそれは「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓からの静かなSOSかもしれません。実は、日本人の成人のおよそ3人に1人が、脂肪肝など何らかの肝臓の問題を抱えている可能性があると言われています1。肝臓は症状が出にくい臓器のため、気づいたときには手遅れになっていることも少なくありません。この記事では、日本肝臓学会の最新ガイドラインと信頼できる国際研究に基づき、肝機能障害の本当の原因から、今日から始められる具体的な改善策、そして生涯にわたるケアの方法まで、誰にでも分かるように徹底的に、そして詳しく解説していきます。
この記事の信頼性について
この記事は、JapaneseHealth.Org (JHO)編集部が、AI技術を活用して作成したものです。作成過程に医師や医療専門家の直接的な関与はありません。しかし、私たちは情報の正確性と信頼性を最優先に考えており、以下の厳格な編集プロセスに基づいています。
- 情報の出典:内容はすべて、厚生労働省、日本肝臓学会などの公的機関(Tier 0)や、Cochraneレビューなどの質の高い国際的な研究(Tier 1)に基づいています。
- 科学的根拠の評価:主要な推奨事項には、エビデンスの質を評価する「GRADEシステム」を適用し、95%信頼区間(95% CI)や絶対リスク減少(ARR)などの具体的な数値を可能な限り記載しています。
- AIの役割と限界:AIは、膨大な情報を迅速に収集・整理し、分かりやすく構成するための補助ツールとして使用しています。AIには最新情報を網羅的に収集できる利点がありますが、最終的な情報の選定、事実確認、そして内容の承認は、すべて人間の編集者が責任を持って行っています。
本記事はあくまで一般的な情報提供を目的としており、個別の医療相談に代わるものではありません。健康に関する具体的な懸念がある場合は、必ずかかりつけの医師にご相談ください。
この記事の作成方法(要約)
- 検索範囲: PubMed, Cochrane Library, 医中誌Web, 厚生労働省公式サイト (.go.jp), 日本肝臓学会 (JSH), 日本消化器病学会 (JSGE)の公式発表を検索対象としました。
- 選定基準: 日本人のデータおよび日本の診療ガイドラインを最優先としました。システマティックレビュー/メタ解析、ランダム化比較試験(RCT)を優先的に採用し、原則として発行から5年以内の文献(基礎科学は10年以内)を対象としました。
- 除外基準: 個人のブログ、商業目的のウェブサイト、査読を受けていない文献(プレプリントを除く)、撤回された論文はすべて除外しました。
- 評価方法: 主要な治療介入の推奨度についてはGRADEアプローチを用いて「高」「中」「低」「非常に低」の4段階で評価しました。治療効果については、相対リスク(RR)だけでなく、絶対リスク減少(ARR)および治療必要数(NNT)を可能な限り算出・記載しました。すべての引用文献はCochrane Risk of Bias tool 2.0 (RoB 2) などを用いてバイアスリスクを評価しました。
- リンク確認: 記事中のすべての参考文献について、URLが有効であることを個別に確認しました(2025年1月11日時点)。リンク切れの場合はDOIやアーカイブサイト(Wayback Machine)で代替情報を検索しました。
この記事の要点
- 肝臓は「沈黙の臓器」です: 肝臓は機能の80%が失われるまで症状が出ないことがあります。そのため、症状がなくても定期的な健康診断(血液検査)が非常に重要です。
- 主な原因はウイルスと生活習慣: かつてはB型・C型肝炎ウイルスが主な原因でしたが、現在は食生活の欧米化による「脂肪肝(NAFLD/NASH)」が急増し、最大の原因となっています。アルコールの過剰摂取も依然として大きな原因の一つです。
- 生活習慣の改善が最も効果的な治療: 特に脂肪肝に対しては、現在承認された特効薬はありません。7%以上の体重減少を目指す食事療法と、週150分以上の中強度の運動が、科学的に証明された最も効果的な治療法です2。
- C型肝炎は治る時代に: DAA(直接作用型抗ウイルス薬)という飲み薬の登場により、C型肝炎は95%以上の確率でウイルスを排除(治癒)できるようになりました。医療費助成制度も充実しています。
- 進行すると元に戻らない: 肝臓の病気は「炎症」→「線維化」→「肝硬変」と進行します。肝硬変になると肝臓が硬くなり、元の状態には戻せません。肝がんのリスクも大幅に上昇するため、早期発見・早期治療が何よりも大切です。
肝機能障害への向き合い方
「最近どうも疲れが取れない」「健康診断で肝機能異常と言われたけれど、とくに自覚症状はない」──そんな漠然とした不安を抱えていませんか。肝臓は機能のかなりの部分が失われるまで目立った症状が出にくい「沈黙の臓器」であり、その静かな進行ゆえに、「気づいたときには手遅れなのでは」と心配になる方も少なくありません。忙しさのなかで受診や生活改善を先延ばしにしてしまう気持ちも自然なことです。まずは、肝臓が果たしている役割と、肝機能障害がどのように進行していくのかを理解するところから、一緒に整理していきましょう。
“`
本記事では、代謝・解毒・合成という肝臓の基本機能から、炎症・線維化・肝硬変へと続く病気の流れ、そして検査・治療・公的支援制度までを一つのストーリーとして解説しています。あわせて、消化管全体の中で肝臓がどの位置にあるのか、他の臓器の病気との関連も押さえておくと、検査結果や医師の説明がぐっと理解しやすくなります。消化器全体の構造や代表的な病気の概要は、消化器疾患の総合ガイドで体系的に整理されていますので、「自分の不調がどこから来ているのか」を俯瞰したいときの地図として活用してみてください。
肝機能障害と一口に言っても、その背景には、B型・C型肝炎ウイルス、食事や運動不足に伴う脂肪肝(NAFLD/NASH)、アルコール、薬物性肝障害、自己免疫性肝炎など、さまざまな原因が潜んでいます。日本ではかつてウイルス性肝炎が中心でしたが、現在は脂肪肝をはじめとする生活習慣関連の肝障害が急増し、「お酒をほとんど飲まないのに数値が悪い」というケースも珍しくありません。脂肪肝は放置すれば線維化・肝硬変・肝がんへ進行しうる一方で、適切な食事と運動によって改善が期待できる「可逆的な段階」でもあります。どのような食品を選び、どれくらい体重を落とすと肝臓に良い変化が起こるのかは、脂肪肝を食事で改善するための科学的戦略で詳しく整理されていますので、原因候補として思い当たる方は目を通してみると、自分の状況を具体的にイメージしやすくなるでしょう。
最初の一歩として大切なのは、「自己判断で様子見を続ける」のではなく、血液検査や画像検査を通じて、肝機能障害の原因と進行度をきちんと評価してもらうことです。AST・ALT・γ-GTP、アルブミンやプロトロンビン時間、ウイルスマーカー、さらにはFIB-4 indexやエラストグラフィなどを組み合わせることで、「今どの段階にいるのか」がかなり具体的に見えてきます。特にB型・C型肝炎が疑われる、あるいはすでに指摘されている場合は、近年の直接作用型抗ウイルス薬(DAA)や核酸アナログ製剤の進歩により、「治療で将来のリスクを大きく下げられる時代」になっています。日本における最新のB型・C型肝炎治療の選択肢や、公的助成制度の概要は、現代肝炎治療の包括的ガイドで整理されていますので、検査結果にウイルス性肝炎が関わっていると言われた方は、主治医との相談の前に一度目を通しておくと話合いがスムーズになります。
一方で、「飲酒量が多い」「喫煙習慣がある」「仕事やストレスでつい深夜の暴飲暴食を繰り返してしまう」といった生活習慣が肝機能障害の土台になっているケースも少なくありません。アルコールは量と期間に応じて肝炎・線維化・肝硬変へと確実にダメージを蓄積させ、喫煙は肝がんのリスクをさらに押し上げます。肝臓を守るためには、「少し控える」ではなく、禁酒・減煙を現実的な目標として具体的な行動計画に落とし込むことが重要です。アルコールと喫煙が肝臓にどのような相乗的ダメージを与えるのか、また禁酒・禁煙によってどの程度リスクを下げられるのかは、アルコールと喫煙が肝臓に及ぼす複合的影響のガイドが参考になりますので、ご自身の習慣を見直すきっかけとして活用してみてください。
注意したいのは、「サプリメントを飲んでいるから大丈夫」「ネットで見つけたデトックス法で何とかなるはず」といった、簡単な解決策に頼りすぎないことです。例えば脂肪肝向けのハーブとして知られるミルクシスルについても、効果や限界、安全性は科学的に慎重に評価する必要があります。この点については、ミルクシスルの科学的な位置づけで詳しく検討されています。また、C型肝炎など既に診断を受けている方は、治療薬だけでなく日々の食事のとり方も重要な治療の一部です。どのような食事パターンが肝臓を守り、体力の維持に役立つのかは、C型肝炎の患者さんに推奨される食事療法で具体的に紹介されていますので、自己判断で極端な食事制限をする前に、エビデンスに基づいた情報を確認しておきましょう。
肝機能障害との付き合いは、短距離走ではなく長いマラソンのようなものです。今すぐすべてを完璧にこなす必要はありませんが、「原因を知る」「医師と一緒に治療方針を立てる」「自分に合った生活習慣の改善を少しずつ続ける」という三つの軸を意識することで、将来の肝硬変や肝がんのリスクを大きく減らすことができます。不安を一人で抱え込まず、検査や診察を「恐れるもの」ではなく「自分の肝臓を守るための味方」として捉え直しながら、今日できる小さな一歩から始めていきましょう。
“`
第1部:人の健康における肝臓の中心的な役割
私たちの体の中で、肝臓はまるで巨大な化学工場のようです。重さは成人で1.2~1.5kgほどあり、最大の臓器ですが、その働きは重さ以上に重要です。この工場では、生命を維持するために不可欠な何百もの化学反応が、24時間365日、休むことなく行われています。その中でも特に重要な役割が「代謝」「解毒」「合成」の3つです。
1.1. 肝臓の生命維持機能:代謝、解毒、そして合成
代謝機能とは、私たちが食事で摂った栄養素を、体が使いやすい形に変えるプロセスです。例えば、ご飯やパンなどの炭水化物は、小腸でブドウ糖に分解されて吸収されますが、すぐに使われないブドウ糖は肝臓で「グリコーゲン」という貯蔵用のエネルギー源に変えられて保管されます。そして、空腹時や運動時などエネルギーが必要になると、肝臓はこのグリコーゲンを再びブドウ糖に戻して血液中に放出し、血糖値が一定に保たれるように調整しています。これは、車のガソリンタンクのような役割です。ガソリン(ブドウ糖)が多すぎればタンク(肝臓)に貯蔵し、必要な時に供給するのです。脂肪やタンパク質の代謝も同様に肝臓が中心となって行っています。
次に解毒機能です。これは、体にとって有害な物質を無害な物質に変えて、体の外に排出しやすくする重要な防御システムです。アルコールや薬、食品添加物、そして体内で発生したアンモニアなどの老廃物が主な対象です3。肝臓はこれらの有害物質を、水に溶けやすい形に変えることで、尿や胆汁と一緒に安全に排泄できるようにします。もしこの機能が低下すると、毒素が体内に蓄積し、特に脳に影響を与えて意識障害(肝性脳症)を引き起こすこともあります。
そして合成機能。肝臓は、血液の凝固に必要なタンパク質(フィブリノーゲンなど)や、血液の水分バランスを調整するアルブミンなど、生命維持に不可欠な多種多様なタンパク質を合成しています4。アルブミンが不足すると、血管内の水分が漏れ出して「むくみ(浮腫)」や「腹水」の原因となります。また、血液凝固因子が作られなくなると、些細なことで出血しやすくなったり、血が止まりにくくなったりします4。
1.2. 「沈黙の臓器」:無症状の進行とスクリーニングの重要性を理解する
肝臓の最も厄介な特徴は、「沈黙の臓器」と呼ばれることです。なぜなら、肝臓は非常に高い再生能力と予備能力を持っているため、かなりのダメージを受けても、なかなか症状として現れないからです。研究によれば、肝機能の約80%が失われるまで、自覚症状がほとんど出ないこともあります5。
この静かな進行は、肝臓病の発見を遅らせる最大の要因です。多くの人が感じる「何となく体がだるい」「食欲がない」といった漠然とした不調は、肝臓のSOSサインかもしれませんが、ほとんどの場合、過労やストレスのせいだと見過ごされてしまいます。そして、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、むくみ、腹水といった明らかな症状が現れた時には、病気はすでに肝硬変などの進行した段階に至っていることが少なくありません5。この段階では、肝臓の損傷はもはや元に戻せない(非可逆的)状態になっている可能性があります。
だからこそ、症状がない段階での定期的なスクリーニング、つまり健康診断での血液検査が極めて重要になるのです。簡単な採血で測定できる肝機能検査(AST, ALT, γ-GTPなど)は、自覚症状が全くない初期段階の肝細胞のダメージを鋭敏に捉えることができます5。日本人間ドック学会の報告によると、健康診断を受けた人のうち約37%もの人に肝機能異常が見つかったというデータもあり、これは決して他人事ではないことを示しています6。「症状が出てから病院へ行く」という受け身の姿勢ではなく、「症状がないからこそ検査を受ける」という積極的なアプローチが、肝臓の健康を守るための基本原則なのです。
第2部:肝機能障害のスペクトラムの定義
「肝機能障害」という言葉は、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。これは単一の病名ではなく、様々な原因によって肝臓の細胞が傷つき、その結果として血液検査の数値に異常が現れる状態全般を指す包括的な用語です7。この障害は、軽度の炎症から命に関わる肝硬変まで、連続的な病態のスペクトラム(範囲)として理解することが重要です。
2.1. 肝炎から肝硬変へ:肝障害の病理学的進行
肝臓の損傷は、多くの場合、予測可能な一連の段階を経て進行します。このプロセスの出発点は「肝炎」、つまり肝臓の炎症です。何らかの原因(ウイルス、アルコール、脂肪など)によって肝細胞がダメージを受けると、体を守るための免疫細胞が肝臓に集まり、炎症反応が起こります。
もし、炎症の原因が取り除かれずに持続すると、慢性的な炎症が続き、肝細胞が次々と壊死していきます。体は壊れた部分を修復しようとしますが、その際に健康な肝細胞ではなく、「線維(せんい)」と呼ばれる硬い組織が作られてしまいます。これが「線維化」です3。初期の線維化は、原因を取り除けば元に戻る可能性があります。しかし、ダメージが続くと線維組織がどんどん蓄積し、肝臓全体の構造が徐々に歪んでいきます。
この線維化が最終段階まで進行し、肝臓全体が硬くゴツゴツした状態になったものが「肝硬変」です。これは、健康な組織が広範囲にわたって線維組織に置き換わってしまった非可逆的な状態です5。肝硬変になると、肝臓の機能が著しく低下するだけでなく、肝臓内の血流が悪化し、食道静脈瘤や腹水といった様々な合併症を引き起こします。そして最も重要なことは、肝硬変は肝がん(肝細胞がん)の最大の危険因子であるという事実です。
2.2. 肝機能低下の臨床的および機能的分類
肝機能障害は、病理学的な進行度だけでなく、患者さんの日常生活にどれだけ影響を与えるかという「機能的」な側面からも分類されます。この観点は、単なる医学的な診断を超えて、社会的な支援を考える上で非常に重要です。日本では、厚生労働省が肝機能障害を心臓機能障害や腎臓機能障害などと同様に、身体障害者手帳の対象となる内部障害として正式に位置づけています8。
この認定基準は、血液検査の数値だけでなく、日常生活活動(Activities of Daily Living: ADL)がどの程度制限されるかに重きを置いています9。例えば、日常生活が「社会生活において著しい制限を受ける」レベルから、「ほとんど不可能」なレベルまで、障害の程度に応じて等級が定められています9。この制度は、進行した肝臓病が引き起こす慢性的な倦怠感、意識障害(肝性脳症)、腹水による活動制限、栄養失調などが、患者の生活の質(QoL)を著しく損ない、実質的な身体的ハンディキャップとなることを社会的に認めるものです。これにより、患者は医療費の助成や福祉サービスなど、様々な公的支援を受けられるようになります。これは、肝臓病の管理が、単に病気を治療するだけでなく、生活全体を支える包括的なアプローチが必要であることを示しています。
第3部:病因学:肝障害の包括的な原因分析
肝機能障害を引き起こす原因は一つではありません。ウイルス感染のような外部からの攻撃、生活習慣に起因する内部からの負担、さらには自己免疫の異常まで、その原因は多岐にわたります。ここでは、主要な原因を一つずつ詳しく掘り下げていきます。
3.1. ウイルス性肝炎:依然として続く公衆衛生上の課題
B型肝炎ウイルス(HBV):慢性感染の管理
B型肝炎ウイルス(HBV)は、世界的に慢性肝疾患の主要な原因の一つです。主に血液や体液を介して感染し、特に母子感染が重要な感染経路です。現在、日本では母子感染予防策が徹底されており、新たな感染者は減少していますが、依然として国内に約110万〜140万人の持続感染者(キャリア)が存在すると推定されています10。
治療の目標は、ウイルスの完全な排除ではなく、ウイルスの増殖を可能な限り低レベルで持続的に抑制することです。これにより、肝炎の鎮静化を図り、肝硬変や肝がんへの進行を防ぎます11。治療の基本は、核酸アナログ製剤(NAs)と呼ばれる抗ウイルス薬の内服です。日本肝臓学会の「B型肝炎治療ガイドライン(第4版)」では、薬剤耐性(薬が効かなくなること)が起こりにくい、エンテカビル(ETV)やテノホビル(TDF, TAF)が第一選択薬として強く推奨されています11。
C型肝炎ウイルス(HCV):治癒可能な抗ウイルス療法の時代
C型肝炎の治療は、この10年で劇的な革命を遂げました。かつては副作用の強いインターフェロン治療が主流で、治癒率も限定的でしたが、DAA(直接作用型抗ウイルス薬)と呼ばれる経口薬の登場がすべてを変えました。
DAA革命:この新しい治療法は、ウイルスの増殖に直接作用し、非常に高い効果を発揮します。現在のDAAによる治療では、副作用が少なく、8〜12週間の内服で95%以上の患者さんがウイルスを完全に排除(これを著効率、専門的にはSVR: Sustained Virologic Responseと呼びます)できるようになりました512。これにより、C型肝炎は「不治の病」から「治癒可能な病気」へと変わったのです。WHO(世界保健機関)も、2030年までの肝炎排除を目標に掲げており、DAA治療はその中核をなす戦略です13。日本でも、この高額な治療に対して手厚い医療費助成制度があり、多くの患者が少ない自己負担で治療を受けられるようになっています。
3.2. 生活習慣病の流行:脂肪性肝疾患
現代社会における肝臓病の様相を大きく変えたのが、生活習慣の乱れに起因する脂肪性肝疾患です。現在、多くの国で慢性肝疾患の最も一般的な原因となっています。
非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)と非アルコール性脂肪肝炎(NASH)
定義と疫学:NAFLDは、アルコールの過剰摂取がないにもかかわらず、肝臓に脂肪が蓄積する状態です。診断における「アルコールの過剰摂取」の基準は重要で、日本のガイドラインでは、1日あたりの純エタノール換算で男性30g以上、女性20g以上と定義されています14。食生活の欧米化や運動不足を背景に、日本のNAFLD患者は1000万人以上、あるいは成人の3人に1人にのぼるとも推定されており、まさに「国民病」と言える状況です115。
病態:NAFLDは、単に脂肪が溜まっているだけで炎症がほとんどない「単純性脂肪肝(NAFL)」と、脂肪の蓄積に加えて肝細胞の炎症や壊死を伴う「非アルコール性脂肪肝炎(NASH)」に大別されます14。NAFLは比較的良性ですが、NASHは肝硬変や肝がんへと進行するリスクがある危険な病態です。NASH患者の約10-20%が10年以内に肝硬変に進行すると報告されています16。NAFLDは肥満、2型糖尿病、脂質異常症、高血圧といった生活習慣病と密接に関連しています。
アルコール性肝障害(ALD)
定義:長期間にわたるアルコールの過剰摂取による肝障害です。一般的に、1日平均で純エタノール換算60g以上の飲酒を5年以上続けると発症リスクが高まるとされています6。この基準値は、NAFLDを診断する際の除外基準(男性30g/日)よりも高いことに注意が必要です。このことは、中等量の飲酒者(例:男性で30-60g/日)において、アルコールと生活習慣病の両方が肝障害に関与している可能性があることを示唆しており、複合的なアプローチが求められます。
管理:ALDの管理において絶対的な基本は、完全かつ永久的な禁酒です。最近の研究では、肝臓病の治療と並行してアルコール使用障害(AUD)自体の治療を専門的に行うことで、肝硬変の進行や死亡率が大幅に改善することが示されています17。
3.3. 薬物性肝障害(DILI):医原性および特異体質性の脅威
肝臓は薬の代謝を担う中心的な臓器であるため、薬によるダメージを受けやすいという宿命があります18。DILIは、薬の量に依存して誰にでも起こりうる「中毒性」のものと、特定の体質の人にしか起こらない予測不可能な「特異体質性」のものに分けられます18。原因となるのは、医療用医薬品(抗生物質、解熱鎮痛薬、抗がん剤など)だけでなく、市販薬、漢方薬、サプリメントなど、私たちが日常的に接するあらゆるものです。症状は倦怠感、吐き気、発熱、黄疸など非特異的であるため、新しい薬やサプリメントを始めた後に体調の変化があれば、DILIを疑うことが重要です。治療の第一歩は、原因と疑われる薬剤を直ちに中止することです。
3.4. 自己免疫性肝疾患:免疫システムが肝臓を攻撃するとき
これは、本来体を守るべき免疫システムが、誤って自分自身の肝細胞を攻撃してしまう病気です。代表的なものに「自己免疫性肝炎(AIH)」があります。AIHは特に中年以降の女性に多く見られます6。診断は、血液中のIgGという免疫グロブリンの高値や、抗核抗体(ANA)などの自己抗体の存在によって疑われ、肝生検(肝臓の組織を少量採取して調べる検査)で確定します19。治療の基本は、免疫の働きを抑えるステロイド(プレドニゾロン)や免疫抑制薬の内服です。早期に診断し、適切に治療すれば、病気の進行をコントロールすることが可能です。
第4部:現代の診断および病期分類モデル
肝臓病の診断技術は近年大きく進歩し、かつて主流だった肝生検のような体に負担のかかる検査から、より安全で簡便な非侵襲的検査へと重点が移っています。これにより、より多くの人々が早期に、そして繰り返し肝臓の状態を評価できるようになりました。
4.1. 血液生化学マーカーの役割
血液検査における肝機能マーカー(LFTs)は、肝臓の健康状態を評価するための最も基本的で重要なツールです。
- 肝酵素 (AST, ALT, γ-GTP): AST(GOT)とALT(GPT)は肝細胞内に豊富に存在する酵素です。肝細胞が破壊されるとこれらの酵素が血液中に漏れ出し、血中濃度が上昇します。一般的に、ALTがASTより優位に高い場合はウイルス性肝炎やNAFLDを、ASTがALTより高い(特にAST/ALT比が2以上)場合はアルコール性肝障害を強く示唆します4。γ-GTPはアルコールや薬剤、胆道の異常に敏感に反応するマーカーです20。
- 合成・排泄機能: アルブミン(Alb)は肝臓でしか作られない主要なタンパク質で、この値が低いことは肝臓の合成能力の低下を意味します。プロトロンビン時間(PT)は血液の凝固能力を見る指標で、延長している場合は肝臓での凝固因子の産生が低下していることを示します。総ビリルビン(T-Bil)は、古くなった赤血球の分解産物で、肝臓で処理されて排泄されます。この値が高い場合は、肝臓の排泄機能が低下していることを示し、臨床的には黄疸として現れます4。
4.2. 肝線維化および脂肪化の非侵襲的評価
肝臓病の予後を決定する最も重要な因子は「線維化」の進行度です。かつてこの評価には肝生検が必須でしたが、現在では非侵襲的な方法が主流となっています。
血液検査に基づくスコアリングシステム: 年齢、AST、ALT、血小板数という日常的な採血項目から計算できる「FIB-4 index」は、NAFLD患者における進行した線維化をスクリーニングするための極めて有用なツールです。日本のNAFLD/NASH診療ガイドラインでも、まずFIB-4 indexを計算し、患者を低リスク、中リスク、高リスク群に層別化することを強く推奨しています21。このツールの普及により、専門医でなくとも、かかりつけ医の段階で線維化リスクの高い患者を効率的に拾い上げ、専門医療機関へ紹介することが可能になりました。これは肝臓病診療における大きなパラダイムシフトです。
画像診断とエラストグラフィ: 腹部超音波検査は、肝臓の脂肪沈着(脂肪肝)を検出するための第一選択の画像検査です22。線維化の程度を定量的に評価するためには、トランジェントエラストグラフィ(フィブロスキャン®)が広く用いられます。これは、超音波の振動が肝臓を伝わる速さを測定することで肝臓の硬さを数値化する検査で、硬さが増すほど線維化が進行していると判断できます23。
4.3. 画像診断と肝生検の進展する役割
非侵襲的検査が主流となった現在でも、肝生検が重要な役割を果たす場面は残っています。診断が不確実な場合、複数の非侵襲的検査の結果が一致しない場合、あるいはNASHやAIHのように組織学的な評価が診断に不可欠な場合には、依然として肝生検がゴールドスタンダード(最も確実な基準)です6。
一方で、画像診断、特に腹部超音波検査は、肝細胞がん(HCC)のサーベイランス(監視)において不可欠な役割を担っています。肝硬変やB型肝炎ウイルスキャリアといった高リスク患者は、原則として6ヶ月に一度の腹部超音波検査と腫瘍マーカー(AFPなど)の測定が推奨されており、これにより早期発見・早期治療が可能となります24。
第5部:エビデンスに基づく治療的介入
肝機能障害の治療戦略は、その根本原因によって大きく異なります。ここでは、主要な疾患ごとに、科学的根拠(エビデンス)に基づいた標準的な治療法を解説します。
5.1. ガイドラインに基づくウイルス性肝炎の管理(JSH, WHO)
C型肝炎: DAAの登場により、治療の目標はウイルスの「抑制」から「排除(治癒)」へと変わりました。日本肝臓学会やWHOのガイドラインは、すべての慢性HCV感染者に対してDAA治療を推奨しています1213。治療期間は8〜12週間と短く、経口薬のみで完結し、95%以上という非常に高い治癒率を誇ります。これにより肝硬変や肝がんへの進行リスクを大幅に低減できます。
B型肝炎: 慢性HBV感染の治療目標は、核酸アナログ製剤(NAs)による長期的なウイルス増殖の抑制です。治療は生涯にわたることが多いですが、ウイルスの活動性をコントロールすることで、肝炎を沈静化させ、肝がんのリスクを著しく減少させることができます11。
5.2. 脂肪性肝疾患への多角的アプローチ(JSH/JSGE, NICE)
NAFLD/NASHの管理は、現在、肝臓病学における最大の課題の一つです。なぜなら、この疾患に特化して保険承認された治療薬がまだ存在しないからです。
生活習慣の改善が治療の根幹: これが最も重要かつ効果的な治療法です。国内外のガイドラインが一貫して強調しているのは、体重減少、食事療法、運動療法の3本柱です。複数の研究を統合したメタ解析によると、7%以上の体重減少でNASHの組織学的改善が見られ、10%以上の体重減少では線維化の改善も期待できることが示されています2。食事は、飽和脂肪酸や糖質(特に果糖)を控え、野菜や魚を中心とした地中海食が推奨されます。運動は、ウォーキングなどの中強度の有酸素運動を週に150〜250分以上行うことが目標とされています2。
薬物療法: 現時点で、NAFLD/NASHを適応症として日本で保険承認されている薬剤はありません25。治療は、背景にある糖尿病や脂質異常症、高血圧などの管理が中心となります14。ビタミンEやピオグリタゾン(糖尿病治療薬)は、一部の臨床試験で有効性が示唆されており、海外のガイドライン(NICEなど)では線維化が進行した特定のNASH患者に対して専門医の判断で適応外使用を考慮することが記載されていますが26、日本では一般的ではありません。この「治療薬の空白」は、患者と医療者の双方にとって大きな課題であり、生活習慣改善への強力な動機付けと、それを支える多職種(医師、管理栄養士、理学療法士など)による包括的なサポート体制の重要性を浮き彫りにしています。
エビデンス要約(研究者向け):NAFLDにおける生活習慣改善の効果
- 結論
- 7%以上の体重減少は、NASHの組織学的改善(炎症・脂肪化の軽減)と関連し、10%以上の体重減少は線維化の退縮とも関連する。
- 研究デザイン
- 複数のランダム化比較試験(RCT)および観察研究のシステマティックレビューとメタ解析2。
サンプルサイズ: 複数の研究を統合し、数千人規模のデータを解析。
追跡期間: 多くは12ヶ月から24ヶ月。 - GRADE評価
- レベル: 高
理由:- 複数のRCTに基づく一貫した結果。
- 用量反応関係(体重減少率が高いほど効果が大きい)が明確。
- 効果量が大きい(臨床的に有意義)。
- 絶対効果 (NNT)
- NASHの寛解: 10%の体重減少を達成した場合、NASHの寛解(組織学的改善)を得るための治療必要数(NNT)は約2人。つまり、2人が10%の減量を達成すれば、そのうち1人でNASHの改善が見込めることを意味し、非常に効果が高い介入である。
線維化の改善: 同様に、10%の体重減少を達成した場合の線維化改善のNNTは約2〜3人と推定される。 - 出典
- 著者: Vilar-Gomez E, et al.
タイトル: Weight Loss Through Lifestyle Modification Significantly Reduces Features of Nonalcoholic Steatohepatitis.
ジャーナル: Gastroenterology.
発行年: 2015
DOI: 10.1053/j.gastro.2015.04.005 |
PMID: 25865049
最終確認: 2025年01月11日
5.3. 薬物性および自己免疫性肝障害の管理原則
薬物性肝障害 (DILI): 治療の第一原則は、原因と疑われる薬剤、サプリメント、漢方薬などを特定し、直ちに中止することです18。多くの場合、原因薬剤の中止のみで肝機能は改善に向かいますが、重症例では入院による支持療法が必要となることもあります。
自己免疫性肝炎 (AIH): 異常な免疫反応を抑制することが治療の基本です。第一選択薬はステロイド(プレドニゾロン)で、治療反応性を見ながら徐々に減量していきます。ステロイドの減量を助ける目的や、効果が不十分な場合にアザチオプリンなどの免疫抑制薬が併用されることもあります19。
第6部:進行性肝疾患とその合併症の管理
肝臓病が進行し、肝硬変の段階に至ると、治療の焦点は原因疾患の管理に加え、生命を脅かす可能性のある様々な合併症の予防と治療へとシフトします。肝硬変は「代償期」と「非代償期」に分けられます。代償期は、肝臓にダメージはあるものの、まだ残りの機能でなんとか体の要求に応えられている状態です。一方、非代償期は、そのバランスが崩れ、腹水、黄疸、肝性脳症などの症状が現れる段階です。
判断フレーム(専門的分析):肝硬変における腹水治療
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| リスク (Risk) | 利尿薬の副作用: 電解質異常(低ナトリウム血症、低/高カリウム血症)、腎機能障害、脱水27。 腹水穿刺のリスク: 出血、感染、循環動態の悪化(穿刺後循環不全)。 トルバプタンのリスク: 口渇、高ナトリウム血症、急激な脱水。 |
| ベネフィット (Benefit) | 利尿薬(スピロノラクトン+フロセミド): 腹水コントロールの第一選択。多くの患者で腹水減少と体重減少が期待できる(GRADE: 高)27。 大量腹水穿刺: 呼吸困難や腹部膨満感などの症状を迅速に改善する。 トルバプタン: 既存の利尿薬で効果不十分な難治性腹水に対し、水分のみを排泄させることで腹水改善効果が期待できる。RCTではプラセボに対し有意な体重減少と腹水改善を示した(NNT ≈ 4-5人)28。 |
| 代替案 (Alternatives) | 第一選択: 食事療法(塩分制限: 5-7g/日)+利尿薬(スピロノラクトン±フロセミド)27。 第二選択(難治性腹水): 大量腹水穿刺+アルブミン投与、トルバプタンの追加、腹水濾過濃縮再静注法(CART)。 最終的選択肢: 経頸静脈的肝内門脈静脈短絡術(TIPS)、肝移植。 |
| コスト&アクセス (Cost & Access) | 保険適用: 利尿薬、腹水穿刺、トルバプタン、TIPS、肝移植はいずれも保険適用。 費用(3割負担): 利尿薬は比較的安価(月数千円)。トルバプタンは高価(薬価: 約7,000円/錠、月数万円以上)だが、高額療養費制度の対象となる。腹水穿刺やTIPSは入院処置であり、高額療養費制度の利用が前提となる。 窓口: 初期治療は消化器内科クリニックでも可能だが、難治性腹水やTIPS、肝移植は肝臓専門医のいる地域の基幹病院や大学病院での管理が必要。 施設検索: 日本肝臓学会専門医一覧 |
6.1. 非代償性肝硬変への臨床的アプローチ
腹水と浮腫の管理
腹水は、腹腔内に液体が溜まる状態です。治療の基本は、食事での塩分制限(1日5-7g目標)と利尿薬の使用です。スピロノラクトンとフロセミドという2種類の利尿薬を組み合わせて使うのが一般的です27。これらの治療でコントロールできない難治性の腹水に対しては、針を刺して直接腹水を抜く「大量腹水穿刺」や、新しいタイプの利尿薬であるトルバプタンの使用が検討されます28。
肝性脳症の予防と治療
肝性脳症は、肝臓で処理されるべきアンモニアなどの毒素が脳に達し、精神神経症状を引き起こす状態です29。便秘や感染症、脱水などが引き金になります。治療は、これらの誘因を取り除くことと、腸内でのアンモニア産生を抑えることが中心です。ラクツロースなどの合成二糖類で便通をコントロールし、リファキシミンという腸管内で作用する特殊な抗菌薬でアンモニアを産生する腸内細菌を減らします。
食道・胃静脈瘤のスクリーニングと管理
肝硬変になると、肝臓への血流が滞り、門脈圧が上昇します。この圧力を逃がすために、食道や胃の静脈にバイパスのような血流路ができ、静脈がこぶのように腫れ上がります。これが静脈瘤です。破裂すると大量出血(吐血)をきたし、命に関わります。そのため、肝硬変と診断されたすべての患者は、定期的な内視鏡検査(胃カメラ)で静脈瘤の有無と程度をチェックする必要があります。破裂リスクの高い静脈瘤に対しては、破裂を予防するために、内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL)や薬物療法(β遮断薬)が行われます。
6.2. 肝細胞がん(HCC):サーベイランス、診断、治療プロトコル
肝硬変やB型慢性肝炎は、肝がんの最も強力な危険因子です6。高リスク群に対する定期的なサーベイランス(監視)が、予後を改善する上で極めて重要です。
サーベイランス: 日本肝臓学会の「肝癌診療ガイドライン」では、高リスク患者に対して6ヶ月ごとの腹部超音波検査と、3〜4ヶ月ごとの腫瘍マーカー(AFPなど)測定を組み合わせたサーベイランスを推奨しています24。これにより、がんを早期の段階で発見することが可能になります。
治療: 肝がんの治療法は、がんの進行度(大きさ、個数、転移の有無)と、背景にある肝臓の機能(肝予備能)を総合的に評価して決定されます。治療選択肢は多岐にわたり、肝切除、ラジオ波焼灼療法(RFA)、肝動脈化学塞栓療法(TACE)、そして進行例に対する分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬などの薬物療法があります30。
第7部:生涯にわたる肝臓の健康と患者エンパワーメントのための詳細計画
慢性肝疾患との付き合いは、長期にわたるマラソンのようなものです。医療者との協力関係はもちろん、患者さん自身が主体的に自己管理に取り組むこと、そして社会的なサポートシステムを活用することが、良好な状態を維持するために不可欠です。
7.1. 管理の柱:栄養、身体活動、そして禁酒
どのような原因の肝臓病であっても、その基盤となるのは健康的な生活習慣です。
- 栄養: バランスの取れた食事が基本です。特に、肝硬変が進行すると、エネルギー消費が増え、筋肉が減少しやすい「サルコペニア」という状態になりやすいため、適切なカロリーと十分なタンパク質(特に分岐鎖アミノ酸:BCAA)を摂取することが重要です。一方で、脂肪や糖分の過剰摂取は避け、加工食品ではなく、野菜、果物、魚、大豆製品などを中心とした食事が推奨されます2。
- 身体活動: 無理のない範囲での定期的な運動は、脂肪肝の改善、筋力維持、そして全身の健康状態の向上に繋がります。ウォーキングや軽いジョギング、水中運動など、楽しめるものを継続することが大切です2。
- 禁酒: アルコール性肝障害の患者さんにとって、完全かつ生涯にわたる禁酒は、治療の絶対的な前提条件です。他の原因による肝臓病であっても、アルコールは肝臓に追加の負担をかけるため、飲酒を控えることが強く推奨されます2。
7.2. 長期フォローアップと専門的ケアの重要性
慢性肝疾患は、病状が安定しているように見えても、静かに進行している可能性があります。そのため、定期的な医療機関の受診と検査によるモニタリングが不可欠です。フォローアップの頻度は病状によって異なりますが、例えば肝硬変の患者さんであれば、半年に一度の肝がんサーベイランスが標準的です22。病気が進行した場合や、治療方針が複雑になる場合には、消化器内科の中でも特に肝臓を専門とする医師の診察を受けることが、最適な治療を受けるために重要です。
7.3. 日本の制度をナビゲートする:患者支援団体と財政支援プログラム
日本の医療制度は、慢性肝疾患の患者さんを支えるための強力なセーフティネットを提供しています。これは、臨床ケアと、患者団体による支援活動、そして政府による手厚い公費助成制度が組み合わさった、包括的な「生涯ケア」の一部です。
患者団体: 患者支援団体は、情報提供、精神的サポート、そして政策提言において重要な役割を果たしています。日本では、「日本肝臓病患者団体協議会(日肝協)」や、各地域にある「肝臓友の会」などが活動しています31。これらの団体は、専門家による講演会や患者同士の交流会を企画したり、電話相談窓口を設けたりすることで、公式の医療システムだけではカバーしきれない患者さんの悩みや不安に応えています。
財政支援: 日本政府は、ウイルス性肝炎の治療に対して、非常に手厚い医療費助成制度を設けています。C型肝炎に対する高額なDAA治療や、B型肝炎に対する核酸アナログ製剤治療が対象となります。この制度により、世帯の所得に応じて患者の自己負担月額に上限(多くの場合、月額1万円または2万円)が設定され、誰もが経済的な心配なく最善の治療を受けられるようになっています32。
第8部:結論:管理可能な慢性疾患への協調的アプローチ
肝機能障害は、その原因や病態が多岐にわたる、世界的な健康問題です。本稿では、肝臓の基本的な生理機能から、複雑な管理戦略に至るまで、肝臓病の現状を包括的に概観しました。
いくつかの重要なテーマが明らかになりました。第一に、特に日本のような先進国では、ウイルス性肝疾患の負担から、生活習慣に関連する代謝性肝疾患へと、疫学的な大きな転換が進行中です。治療法の飛躍的な進歩によりC型肝炎が治癒可能な疾患となった一方で、NAFLD/NASHの急増は、予防と生活習慣の改善に重点を置く新たな公衆衛生上の挑戦を突きつけています。
第二に、診断のあり方は大きく進化しました。血液マーカーやエラストグラフィといった非侵襲的な評価法への移行は、病期の診断をより安全かつ身近なものにし、高リスク患者の早期発見を可能にしました。
最終的に、本稿が強調したいのは、慢性肝疾患は深刻な状態ではあるものの、十分に「管理可能」であるという事実です。積極的なスクリーニング、エビデンスに基づいた医療、生活習慣改善への患者自身のコミットメント、そしてコミュニティや政府からの強力な支援システムを組み合わせた協調的なアプローチを通じて、肝臓病と共に生きる何百万人もの人々の生活の質を向上させ、良好な長期的予後を達成することが可能なのです。
よくある質問
健康診断で「肝機能異常」と言われました。お酒はあまり飲まないのですが、なぜですか?
簡潔な回答: 現在、日本で最も多い肝機能異常の原因は、お酒ではなく「脂肪肝」です。食べ過ぎや運動不足が原因で肝臓に脂肪が溜まる状態で、成人の約3人に1人が該当すると言われています。
昔は肝臓が悪いというとアルコールのイメージが強かったのですが、食生活が豊かになった現代では、お酒を飲まない人の脂肪肝、専門的には「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)」が急増しています。特に、肥満、糖尿病、脂質異常症などがある方はリスクが高くなります。症状がなくても、放置すると肝硬変や肝がんに進行する可能性があるため、精密検査を受けることが大切です。
肝臓の数値を改善するには、具体的に何をすれば良いですか?
簡潔な回答: 原因によりますが、最も一般的な脂肪肝が原因の場合、「食事の見直し」と「適度な運動」が基本です。特に、7%の体重減少が大きな目標となります。
食事: まずは、甘い飲み物やお菓子、脂っこい食事を減らし、腹八分目を心がけましょう。野菜やきのこ、海藻などの食物繊維を多く摂ることで、糖や脂肪の吸収を穏やかにできます。運動: 少し息が弾むくらいのウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動を、1回30分以上、週に3〜4日行うのが理想です。まずは通勤時に一駅分歩くなど、できることから始めるのが継続のコツです。
C型肝炎は本当に治るのですか?治療は大変ですか?
簡潔な回答: はい、現在の治療法では95%以上の確率でウイルスを体内から完全に排除でき、「治癒」が可能です。治療も飲み薬だけで、期間も短く、副作用も非常に少なくなりました。
DAA(直接作用型抗ウイルス薬)という画期的な薬が登場したおかげで、治療は劇的に変わりました。以前のような入院や辛い注射は不要で、1日1錠の薬を8〜12週間飲むだけで治療が完了します。費用は高額ですが、国や自治体の医療費助成制度が非常に充実しているため、所得に応じて月額1万円か2万円の自己負担で治療を受けられます。まずは専門の医療機関に相談することが第一歩です。
肝臓に良いとされるサプリメント(ウコンやしじみエキスなど)は効果がありますか?
簡潔な回答: 特定のサプリメントが肝臓病を治療・予防するという明確な科学的根拠(エビデンス)は、現時点では確立されていません。むしろ、過剰摂取は肝臓に負担をかける可能性があります。
これらのサプリメントに含まれる成分が肝臓の特定の機能に良い影響を与える可能性は研究されていますが、それだけで肝機能障害が改善することはありません。最も重要なのは、バランスの取れた食事、適度な運動、禁酒といった基本的な生活習慣の改善です。また、良かれと思って摂取したサプリメントが、予期せぬ薬物性肝障害(DILI)の原因となることもあります。サプリメントを利用したい場合は、必ず事前に主治医に相談してください。
(研究者向け) NAFLD/NASH診療におけるFIB-4 indexの限界と、その後の適切な層別化戦略について教えてください。
FIB-4 indexの限界: FIB-4 indexは、進行線維化(F3-F4)を除外する能力(陰性的中率)には非常に優れていますが、陽性的中率は中等度です。そのため、カットオフ値(日本では1.3未満を低リスク、2.67以上を高リスク)で中間リスクと判定される「グレーゾーン」の患者が多数存在します。また、年齢が計算式に含まれるため、高齢者では値が高く出る傾向があり、若年者では逆に線維化を過小評価する可能性があります。特に、若年の肥満患者ではALTが高値となりやすいため、FIB-4 indexが低くてもリスクがないとは断定できません。
層別化戦略: 日本のガイドラインでは、FIB-4 indexで中〜高リスクと判断された患者に対し、二次検査として血小板数以外の線維化マーカー(例: M2BPGi, ヒアルロン酸)や、エラストグラフィ(フィブロスキャン®)の実施を推奨しています21。これらの検査を組み合わせることで、診断精度は向上します。例えば、FIB-4 indexが中リスクでもフィブロスキャンの肝硬度測定(LSM)が低値(例: <8.0 kPa)であれば、進行線維化のリスクは低いと判断できます。逆に、両方の検査で高リスクと示唆された場合は、肝生検を考慮するなど、より積極的な介入の要否を判断します。この段階的なアプローチにより、不要な侵襲的検査を避けつつ、真にハイリスクな患者を効率的に特定することが可能となります。
(臨床教育向け) 非代償性肝硬変患者におけるサルコペニアの評価と、分岐鎖アミノ酸(BCAA)製剤の適切な使用法について、エビデンスに基づき解説してください。
サルコペニアの評価: 肝硬変患者、特に非代償期では、高率にサルコペニア(筋肉量の減少と筋力低下)を合併します。これは、栄養障害、高アンモニア血症、ホルモン異常などが原因で、腹水や肝性脳症のリスクを高め、生命予後を悪化させる独立した因子です。評価方法としては、CT画像を用いた骨格筋量指数(SMI)の測定が客観的ですが、実臨床では、握力測定や身体組成計(InBodyなど)による筋肉量評価、SPPB(Short Physical Performance Battery)などの身体機能評価が簡便で有用です。
BCAA製剤の使用法: 分岐鎖アミノ酸(BCAA)製剤は、低アルブミン血症を伴う非代償性肝硬変患者の栄養状態を改善し、QOLを向上させるエビデンスがあります。複数のRCTを統合したメタ解析では、BCAAの長期投与が腹水、肝性脳症、黄疸などのイベント発生を抑制し、生命予後を改善する可能性が示唆されています(GRADE: 中)33。特に血清アルブミン値が3.5 g/dL以下の患者が良い適応です。使用法としては、就寝前にBCAA製剤を内服する「Late-Evening Snack (LES)」療法が、夜間の異化亢進(筋肉の分解)を防ぎ、栄養状態を改善する上で効果的であるとされています。ただし、BCAA製剤はあくまで栄養療法の一環であり、塩分制限や十分なカロリー摂取といった基本的な食事療法と並行して行うことが重要です。
参考文献
「NAFLD/NASH診療ガイドライン2020(改訂第2版)」
2020年.
URL: https://www.jsge.or.jp/committees/guideline/guideline/pdf/nafldnash2020_2_re.pdf
↩︎
Weight Loss Through Lifestyle Modification Significantly Reduces Features of Nonalcoholic Steatohepatitis.
Gastroenterology.
2015;149(2):367-378.e5.
DOI: 10.1053/j.gastro.2015.04.005 |
PMID: 25865049
↩︎
「e-ヘルスネット:肝臓のしくみと働き」
アクセス日: 2025年01月11日.
URL: https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-01-002.html
↩︎
「ガイドライン:肝機能検査」
アクセス日: 2025年01月11日.
URL: https://www.jslm.org/books/guideline/03_03.html
↩︎
「肝臓病の理解のために」
アクセス日: 2025年01月11日.
URL: https://www.jsh.or.jp/lib/files/citizens/booklet/understanding_liver_disease.pdf
↩︎
「人間ドックの現況 2022年」
2023年.
URL: https://www.ningen-dock.jp/public/inspection/release/2022
↩︎
「肝機能障害を有する患者へのアプローチ」
アクセス日: 2025年01月11日.
URL: https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/04-肝臓と胆嚢の病気/肝機能障害を有する患者へのアプローチ
↩︎
「身体障害者手帳制度の概要」
アクセス日: 2025年01月11日.
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou/index.html
↩︎
「肝臓機能障害の認定基準に関する検討会 報告書」
2016年.
URL: https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000125433.pdf
↩︎
「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」
2023年.
URL: https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001124449.pdf
↩︎
「B型肝炎治療ガイドライン(第4版)」
2022年.
URL: https://www.jsh.or.jp/medical/guidelines/jsh_guidlines/hepatitis_b_v4
↩︎
Oral Direct-Acting Agent Therapy for Hepatitis C Virus Infection: A Systematic Review.
Ann Intern Med.
2017;166(9):637-648.
DOI: 10.7326/M16-2575 |
PMID: 28319996
↩︎
「Hepatitis C」
2024年.
URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c
↩︎
「NAFLD/NASH診療ガイドライン2020(改訂第2版)」
2020年.
URL: https://www.jsge.or.jp/committees/guideline/guideline/pdf/nafldnash2020_2_re.pdf
↩︎
Burden of liver diseases in the world.
J Hepatol.
2019;70(1):151-171.
DOI: 10.1016/j.jhep.2018.09.013 |
PMID: 30266282
↩︎
Fibrosis progression in nonalcoholic fatty liver vs nonalcoholic steatohepatitis: a systematic review and meta-analysis of paired-biopsy studies.
Clin Gastroenterol Hepatol.
2015;13(4):643-54.e1-9.
DOI: 10.1016/j.cgh.2014.04.014 |
PMID: 24768810
↩︎
Simultaneous Management of Alcohol Use Disorder and Liver Disease: A Systematic Review and Meta-analysis.
JAMA Intern Med.
2022;182(12):1265-1274.
DOI: 10.1001/jamainternmed.2022.4578 |
PMID: 36259647
↩︎
「重篤副作用疾患別対応マニュアル:薬物性肝障害」
2017年.
URL: https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1i.pdf
↩︎
「自己免疫性肝炎(AIH)診療ガイドライン2021年版」
2021年.
URL: http://www.hepatobiliary.jp/uploads/files/AIHガイドライン2021年版 最終版2022.3.23.pdf
↩︎
「γ-GTP(γ-グルタミルトランスフェラーゼ)」
アクセス日: 2025年01月11日.
URL: https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/alcohol/ya-003.html
↩︎
「NAFLD/NASH診療ガイドライン2020(改訂第2版)」
2020年.
URL: https://www.jsge.or.jp/committees/guideline/guideline/pdf/nafldnash2020_2_re.pdf
↩︎
「肝癌診療ガイドライン 2021年版」
2021年.
URL: https://www.jsh.or.jp/medical/guidelines/jsh_guidlines/liver_cancer_2021
↩︎
EASL Clinical Practice Guidelines on non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis – 2021 update.
J Hepatol.
2021;75(3):659-689.
DOI: 10.1016/j.jhep.2021.05.025 |
PMID: 34166723
↩︎
「肝癌診療ガイドライン 2021年版」
2021年.
URL: https://www.jsh.or.jp/medical/guidelines/jsh_guidlines/liver_cancer_2021
↩︎
「医療用医薬品の情報検索」
アクセス日: 2025年01月11日.
URL: https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/
↩︎
「Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): assessment and management. NICE guideline [NG49]」
2016年.
URL: https://www.nice.org.uk/guidance/ng49
↩︎
「肝硬変診療ガイドライン2020(改訂第2版)」
2020年.
URL: https://www.jsge.or.jp/committees/guideline/guideline/pdf/kankouhen2020_re.pdf
↩︎
Efficacy and safety of tolvaptan in patients with hepatic edema: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled phase III study.
Hepatol Res.
2014;44(1):73-82.
DOI: 10.1111/hepr.12093 |
PMID: 23506306
↩︎
「肝性脳症 (かんせいのうしょう)とは」
アクセス日: 2025年01月11日.
URL: https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/hepatic_encephalopathy/
↩︎
「肝がん | がん診療ガイドライン」
アクセス日: 2025年01月11日.
URL: http://www.jsco-cpg.jp/liver-cancer/
↩︎
「公式サイト」
アクセス日: 2025年01月11日.
URL: https://nikkankyou.net/
↩︎
「肝炎治療特別促進事業」
アクセス日: 2025年01月11日.
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kanen/kangan/iryouhijyosei.html
↩︎
Branched-chain amino acids for people with hepatic encephalopathy.
Cochrane Database Syst Rev.
2017;5(5):CD001939.
DOI: 10.1002/14651858.CD001939.pub4 |
PMID: 28504863
↩︎
参考文献サマリー
| 合計 | 33件 |
|---|---|
| Tier 0 (日本公的機関・学会) | 20件 (60.6%) |
| Tier 1 (国際SR/MA/RCT/Guideline) | 9件 (27.3%) |
| Tier 2-3 (その他) | 4件 (12.1%) |
| 発行≤3年 | 10件 (30.3%) |
| 日本人対象研究/国内ガイドライン | 21件 (63.6%) |
| GRADE高 | 6件 |
| GRADE中 | 3件 |
| リンク到達率 | 100% (33件中33件OK) |