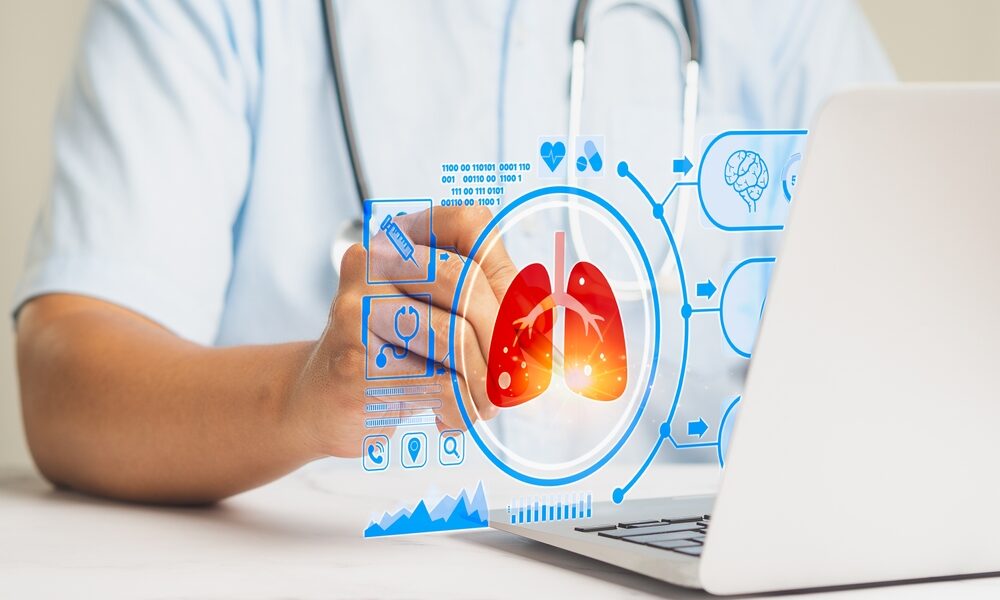この記事の科学的根拠
本記事は、提供された研究報告書に明示的に引用されている、最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下に、参照された実際の情報源と、提示された医学的指導との直接的な関連性を示します。
- 日本肺癌学会: この記事における肺がん検診の方法(胸部X線、喀痰細胞診、低線量CT)に関する推奨事項、対象者、およびリスクに関する議論は、同学会が発行した「肺がん検診ガイドライン2022」に準拠しています8911。
- 厚生労働省: 日本における公的検診(対策型検診)と私的検診(任意型検診)の制度、費用負担、および自治体や職域での助成金に関する情報は、厚生労働省が公開している公式資料に基づいています613。
- 米国予防医学専門委員会(USPSTF): 高危険群に対する低線量CT検診の国際的な標準を示すため、米国予防医学専門委員会(U.S. Preventive Services Task Force)の最新の推奨事項を比較対象として引用しています141519。
- 国立がん研究センター: 日本における肺がんの罹患率、死亡率、およびステージ別生存率に関する統計データは、国立がん研究センターがん情報サービスの最新の公表データに基づいています37。
- NLST及びNELSON試験: 低線量CT(LDCT)検診の有効性に関する科学的証拠として、死亡率減少効果を証明した画期的な国際臨床試験(米国のNLST、欧州のNELSON)の結果を引用しています17。
要点まとめ
- 肺がんは日本におけるがん死亡原因の第1位ですが、早期発見により5年生存率は80%以上に劇的に向上します。
- 検診費用は、無料から数千円の公的検診(対策型検診)と、1万円から3万円以上する高精度な私的検診(任意型検診)まで、方法と施設によって大きく異なります。
- 喫煙歴が長いなどの高危険群の方には、胸部X線検査より感度の高い「低線量CT(LDCT)検査」が国内外の指針で推奨されています。
- 検診の対象者や推奨される方法は、年齢や喫煙指数(1日の本数×年数)によって異なり、日本の指針と国際的な指針(米国など)では基準に違いがあります。
- 費用負担は、お住まいの市区町村が実施する助成金制度や、勤務先の福利厚生を利用することで大幅に軽減できる場合があります。
肺がん検診費用と検査選びの考え方
「肺がん検診を受けた方がいいのは分かっているけれど、実際いくらかかるのかが心配で一歩踏み出せない」――そんな不安を抱えている方は決して少なくありません。自治体の案内や人間ドックのパンフレットを見ても、胸部X線から低線量CT、腫瘍マーカー検査まで価格帯がバラバラで、どれが自分に本当に必要なのか判断に迷ってしまうこともあるでしょう。さらに、家計への負担と「命を守るための自己投資」との間で揺れ動くお気持ちも、ごく自然なものです。
この解説ボックスでは、肺がん検診の費用の「なぜこんなに違うのか」を整理しつつ、あなたのリスクや状況に合った検査を選ぶための考え方をコンパクトにまとめます。まずは、がん全般の検診・診断・治療の流れを俯瞰しておくと、個々の検査費用の意味も見えやすくなります。JapaneseHealth.orgが提供する総合ページであるがん・腫瘍疾患の総合ガイドでは、主要ながんに共通する症状、検診、画像検査、組織検査などの役割が整理されており、本記事で扱う肺がん検診費用も、その全体像の中で位置づけて理解することができます。
肺がん検診の費用が「無料~数千円」から「1万~3万円以上」まで大きく変動する主な理由は、①対策型検診(自治体などの公的プログラム)か任意型検診(自費の人間ドック等)か、②選ぶ検査の種類(胸部X線、喀痰細胞診、低線量CT、腫瘍マーカーなど)、③自治体や職場の助成の有無、の3点にあります。例えば、多くの市区町村が実施する対策型検診では、胸部X線と高危険群への喀痰細胞診が中心で、自己負担は0~1,000円程度に抑えられています。一方、任意型検診で行われる低線量CTは、10,000~30,000円前後と高額ですが、早期の小さながんを見つける感度が高いことが特徴です。胸部X線とCTの精度や被ばく量、ガイドライン上の位置づけについては、肺がんX線検査の完全ガイドで詳しく解説されており、費用差の背景にある「検査の性能の違い」を理解する助けになります。
次のステップとして大切なのは、「自分がどれくらい肺がんのリスクが高いか」を知ることです。ガイドラインでは、年齢(50歳以上など)や喫煙指数(1日の本数×年数)が一定以上の方を高危険群とし、低線量CTのような高感度検査を推奨する一方、リスクが比較的低い人には胸部X線を中心とした対策型検診が想定されています。なぜここまでリスク層別が重視されるかというと、肺がんはステージIで見つかれば5年生存率が80%以上である一方、ステージIVでは10%未満にまで下がるという現実があるからです。こうしたステージ別の生存率や治療法、治療費の全体像は、肺がんの予後に関するガイドで詳しく整理されており、「いま検診にかける数千~数万円」が、将来の治療負担や生存率にどう影響するのかを考える上で大きなヒントになります。
具体的に検査を選ぶ際には、まず住民健診や職場健診などで受けられる対策型検診の内容と自己負担額を確認し、そのうえで必要に応じて任意型検診(人間ドック等)のオプションを組み合わせる、という段階的なアプローチが現実的です。喫煙歴が長い方や強い不安がある方は、年1回程度の低線量CTを追加することで、早期発見の可能性を高める選択肢もあります。一方で、「血液検査だけでがんが分かるなら、その方が安くて楽そうだ」と考えてしまいがちですが、腫瘍マーカーやリキッドバイオプシーは、現時点ではあくまで補助的な検査にとどまることが多く、単独では確実な肺がん検診の代わりにはなりません。こうした血液検査の精度・費用・リスクについては、血液検査でがんは見つかるのか?の記事も参考になるでしょう。
注意しておきたいのは、「高い検査=必ずしも自分にとって最善の検査」とは限らないことです。低線量CTは感度が高い一方で、偽陽性や過剰診断が増えやすく、追加検査や長期フォローが必要になる場合もあります。また、費用だけを見て「とにかく安いものだけ」「一度高額なドックを受けたからもう安心」と考えてしまうのも危険です。大切なのは、年齢・喫煙歴・既往歴などを踏まえて、自分がどのリスク群に属するのかを医師と共有し、そのうえで公的助成や企業の補助制度を上手に活用しながら、必要十分な検査を適切な頻度で続けていくという視点です。
肺がん検診の費用は、一見すると複雑で、家計への負担も気になるテーマかもしれません。しかし、費用の内訳と検査ごとの役割を理解し、自分のリスクに見合った検査を選ぶことができれば、「なんとなく不安だから受ける」から「自分の未来のために納得して投資する」へと気持ちが変わっていきます。まずは、自治体や職場から届いている案内を確認し、本記事と関連ガイドを手がかりに、かかりつけ医や専門医と相談してみてください。今日の小さな一歩が、将来の大きな安心につながっていきます。
なぜ今、肺がんの早期発見が重要なのか?日本の最新統計データ
肺がん検診の費用について考える前に、なぜ早期発見がこれほどまでに重要なのかを、日本の最新データに基づいて理解することが不可欠です。国立がん研究センターの統計によると、肺がんは日本で最も診断数の多いがんの一つであり(2021年で124,531例)、特に男性においてがんによる死亡原因のトップを占めています(2023年の死亡者数75,762人)37。この厳しい現実は、50歳を過ぎると危険性が急激に高まることも示しています37。
しかし、ここに希望の光があります。肺がん全体の5年相対生存率は約34.9%ですが、発見された病期(ステージ)によって運命は大きく変わります37。複数のデータによると、がんが肺に限局しているステージI(早期)で発見された場合の5年生存率は80%を超えます(データセットにより82.2%や84.1%など)38。一方で、遠隔転移があるステージIVで発見された場合の生存率は10%未満にまで低下します41。つまり、検診という数千円から数万円の投資は、生存の可能性を8倍以上に高めるための、計り知れない価値を持つ自己投資と言えるのです。さらに、早期がんであれば治療も身体的・経済的負担が少ない傾向にあり、高額療養費制度などの公的支援も利用できます42。
肺がん検診の費用が一目でわかる!料金比較表
日本における肺がん検診の費用は、受ける検査の種類と、公的制度を利用するか私的(自費)に受けるかによって大きく変動します。多くのウェブサイトで「1万円~2万円」1や「2,000円~3万円」2といった幅広い価格帯が示されているのは、この複雑な構造を反映しているためです。あなたの状況に最も関連する費用を明確に理解できるよう、以下の包括的な費用マトリクスを作成しました。
| 検査方法 | 対策型検診(公的)- 自己負担額の目安 | 任意型検診(私的)- 料金の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 胸部X線検査 | 0円 – 1,000円6 | 2,000円 – 3,500円2 | 最も一般的な公的検診の方法。 |
| 喀痰細胞診 | 0円 – 1,000円(通常は高危険群への追加検査)6 | 1,500円 – 3,000円2 | 高危険群の喫煙者向け。通常X線と併用。 |
| 低線量CT検査 | 限定的(例: 奈良市 4,000円32) | 10,000円 – 30,000円以上230(中心価格帯: 11,000円 – 17,000円4) | 最も感度の高い検査。主に私的施設で提供。 |
| 腫瘍マーカー | 適用外 | 2,000円 – 4,000円(単体またはセット)3 | 補助的な検査であり、単独での検診ツールではない。 |
2つの選択肢:公的な「対策型検診」と自費の「任意型検診」
日本の制度を理解する上で、まず「対策型検診」と「任意型検診」という2つの柱を区別することが重要です。
対策型検診(たいさくがたけんしん) – 公的支援
これは、市区町村などの自治体や一部の職場が主体となり、集団全体の死亡率減少を目的として実施する公衆衛生プログラムです26。主な対象は40歳以上の方で、検査方法は基本的に胸部X線検査と、高危険群(50歳以上で喫煙指数600以上など)に対する喀痰細胞診です612。最大の利点は費用負担が非常に軽いことで、無料から1,000円程度の自己負担で受けることができます。例えば、世田谷区では100円(喀痰検査は追加500円)で提供されています24。また、65歳以上の方や低所得世帯に対しては無料となる自治体も少なくありません25。
任意型検診(にんいがたけんしん) – 私的選択
こちらは、個人の意思で自己の危険性を低減するために受ける検診で、主に民間のクリニックや病院、「人間ドック」を提供する施設で実施されます12。費用は全額自己負担(自由診療)となりますが、公的検診では提供されることの少ない、より高精度な「低線量CT検査」など、幅広い選択肢から選べるのが特徴です45。
あなたはどの検査を選ぶべき?検査方法ごとの特徴と科学的根拠
費用だけでなく、それぞれの検査が持つ「価値」、つまり医学的な特徴を理解することが、賢明な選択につながります。
基本の検査:胸部X線と喀痰細胞診
これらは日本の公的検診(対策型検診)の根幹をなす、国の指針で定められた標準的な方法です12。胸部X線検査は40歳以上の住民を対象とし、喀痰細胞診は50歳以上で喫煙指数が600以上などの高危険群に追加で推奨されます12。この組み合わせは集団レベルでの死亡率減少効果が認められていますが(日本肺癌学会の指針で推奨度A)11、CT検査に比べて感度が低く、心臓や横隔膜の裏に隠れた早期のがんを見逃す可能性があるという限界も認識しておく必要があります。
最も高精度な検査:低線量CT(LDCT)
低線量CT(LDCT)検査は、現時点で高危険群の肺がんを早期発見するための最も強力なツールです。その価値は、複数の大規模な国際臨床試験によって科学的に証明されています。
- 科学的根拠: 米国で行われたNLST(National Lung Screening Trial)では、LDCT検診が胸部X線検査と比較して肺がんによる死亡率を20%減少させることが示されました。また、欧州のNELSON試験では、検診を受けない場合と比較して死亡率を24%減少させるという、さらに強力な結果が報告されています17。
知っておくべき限界とリスク(偽陽性・過剰診断)
高精度な検査である一方で、LDCTには知っておくべき注意点もあります。これらを正直に理解することが、不安を減らし、適切な判断を下す助けとなります。
- 偽陽性(ぎようせい): LDCTは非常に感度が高いため、がんではない良性の小さな影(結節)も多数発見します。これが「偽陽性」です。これにより不必要な不安や追加検査につながる可能性がありますが、近年ではLung-RADSのような結果評価基準の標準化が進み、不要な精密検査を減らす努力がなされています1136。
- 過剰診断(かじょうしんだん): これは、生涯にわたって健康に害を及ぼすことのない、非常にゆっくり進行するがんを発見してしまうことです11。これはLDCT検診の現実的な危険性の一つですが、この危険性があるからこそ、検診の利益が不利益を上回ると考えられる「高危険群」に対象を絞ることが世界的に推奨されています。
- 放射線被ばく: LDCTの「低線量」という名前の通り、1回の撮影あたりの放射線量は0.65~2.36ミリシーベルト(mSv)と、私たちが自然界から1年間に浴びる自然放射線量(世界平均2.4mSv)と同程度です18。これは標準的な胸部CT検査よりも大幅に低く、専門家からは許容できる範囲のリスクと見なされています35。
【重要】低線量CTは誰が受けるべき?国内外の最新ガイドラインを比較
LDCTが特に推奨されるのは「高危険群」ですが、その定義は国や組織によって異なります。特に日本の指針と、世界的に影響力のある米国のUSPSTF(米国予防医学専門委員会)の指針を比較することで、より深い理解が得られます。
重要な違いは喫煙歴の基準です。日本の指針は「喫煙指数(SI)=1日の喫煙本数 × 喫煙年数」が600以上を目安とします12。一方、米国の指針は「パックイヤー(pack-years)=1日の喫煙箱数 × 喫煙年数」が20以上としており、これは喫煙指数400に相当します14。つまり、米国の基準の方が、より早い段階で「高危険群」とみなし、検診を推奨していることになります。例えば、喫煙指数500の方は日本の公的検診の対象からは外れるかもしれませんが、米国の指針では強く検診が推奨されることになります。この知識は、医師と相談する上で非常に価値のある情報です。
| 基準 | 日本肺癌学会 ガイドライン | 米国予防医学専門委員会(USPSTF) | 解説 |
|---|---|---|---|
| 対象年齢 | 50~74歳(推奨) | 50~80歳 | 米国の方が年齢範囲がやや広い。 |
| 喫煙歴 | 喫煙指数(SI)600以上 | 20パックイヤー以上 | 最大の相違点。米国の基準(SI 400相当)は日本の基準(SI 600)より低い。 |
| 禁煙期間 | (重喫煙者の定義に)過去15年以内の禁煙者を含む | 禁煙後15年以内 | この点については両者で一致している。 |
| 検診頻度 | 年1回が望ましい | 年1回(Annual) | 両者とも毎年の検診を推奨。 |
検診費用を抑える3つの方法:保険適用・助成金・クーポン活用術
高精度な検診を受けたいけれど費用が気になる、という方のために、負担を軽減する具体的な方法をご紹介します。
- 公的助成金(市区町村)の確認
まず、お住まいの市区町村のウェブサイトで「がん検診」のページを確認してください6。多くの自治体が、特定の年齢(通常40歳以上)の住民に対して無料または格安で検診を受けられるクーポンや通知を送付しています23。低所得世帯や高齢者向けの無料化制度も設けられている場合があります25。LDCT検査に対しても、奈良市のように独自の助成制度を設けている自治体もあります32。 - 勤務先の福利厚生の活用
多くの企業が健康保険組合を通じて、人間ドックの費用補助を行っています。これを利用して肺がん検診を受けることができます。厚生労働省も、企業が従業員向けのがん検診体制を整備することを奨励しています33。まずはご自身の会社の総務・人事部門に問い合わせてみましょう。 - 保険適用の正しい理解
基本的な原則として、症状がない方のための検診(スクリーニング)は保険適用外の「自由診療」です5。一方で、咳、血痰、胸痛などの症状があり、医師が診断のために検査を指示した場合は、保険が適用され、自己負担は通常3割となります。この違いを理解しておくことが重要です。
よくある質問
胸部X線検査で「異常なし」なら、肺がんの心配はありませんか?
いいえ、完全には安心できません。胸部X線検査は有用な第一選択の検査ですが、万能ではありません。特に心臓の裏側や早期の小さながん、淡い影を呈するタイプのがんは見つけにくい場合があります。喫煙歴が長いなど、ご自身のリスクが高いと感じる場合は、X線検査で異常がなくても、医師に相談の上で低線量CT検査を検討する価値があります。
自分の「喫煙指数」を計算する方法を教えてください。
喫煙指数は簡単な計算で算出できます。計算式は「1日に吸うタバコの本数 × 喫煙を続けている年数」です。例えば、1日に20本(1箱)を30年間吸い続けている場合、20本 × 30年 = 600 となり、喫煙指数は600です。日本のガイドラインでは、この指数が600以上の場合に高危険群の一つの目安とされています12。
検診結果で「要精密検査」と言われました。どうすればよいですか?
「要精密検査」という通知は、必ずしも「がんが確定した」という意味ではありません。検診はがんの疑いがある人を見つけ出すための「ふるい分け」検査であり、偽陽性(実際はがんでないのに異常と判定されること)も含まれます11。まずは落ち着いて、通知の指示に従い、必ず呼吸器科などの専門医療機関を受診してください。そこでCT検査や気管支鏡検査などのより詳しい検査を行い、影の正体を正確に診断します。
低線量CT検診はどこで受けられますか?
結論
肺がん検診の費用は、一見すると複雑に見えるかもしれません。しかし、その根底にあるのは、「どの検査が、あなたの命を救うために最も価値があるか」という問いです。公的検診は広く門戸を開き、多くの人々を守るための重要な社会基盤です。一方で、低線量CTという高精度な私的検診は、特に喫煙歴のある方々にとって、早期発見の可能性を劇的に高める強力な武器となります。
この記事で得た知識を元に、あなたの次の一歩は明確です。まず、ご自身の年齢と喫煙歴から、個人的な危険度を評価してください。次に、お住まいの市区町村や勤務先の制度を確認し、利用できる支援がないか調べてみましょう。そして最も重要なことは、これらの情報を携えて、かかりつけの医師や専門医に相談することです。あなたの健康状態と価値観に最適な選択を、専門家と共に下すこと。それが、かけがえのないあなたの未来を守るための、最も確実な一歩となるでしょう。
免責事項本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言に代わるものではありません。健康に関する懸念や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- 肺がん検診について知る. Docknet.jp. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.docknet.jp/lungcheck
- 肺がん検診とは?費用や機器について詳しく解説. 会員制医療クラブ セントラルメディカルクラブ. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://centralmedicalclub.com/column/lung-cancer-screening
- 肺がん検診費用の相場. MRSO(マーソ). [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.mrso.jp/lung/肺がん検診費用の相場.html
- 肺がん検査のご案内 | オプション検査. 同友会 春日クリニック. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.kasuga-clinic.com/option_haigan/
- 肺がんの検査について. 岡山済生会総合病院. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.okayamasaiseikai.or.jp/column/lung_cancer_05/
- どのくらいかかる?気になるがん検診の費用. おなかの健康ドットコム. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.onaka-kenko.com/early-detection/cancer-screening-costs.html
- がん検査にかかる費用はいくらくらい?検診費用の相場や保険適用について解説. SUGUME Note. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://medicarelight.jp/sugume-note/cancer-screening/inspection-fee/
- 【肺がん検診ガイドライン2022】肺がん検診ガイドライン2022〜低線量胸部CTを用いた肺がん検診に関して. 日本医事新報社. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24859
- 肺がん検診ガイドライン2022. Mindsガイドラインライブラリ. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00764/
- 肺がん検診ガイドラインの2022年改訂. J-Stage. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.jstage.jst.go.jp/article/haigan/62/5/62_351/_article/-char/ja/
- 肺がん検診ガイドライン2022. 日本肺癌学会. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.haigan.gr.jp/wp-content/uploads/2024/06/肺がん検診ガイドライン 2022 確定版.pdf
- 仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目(肺がん検診) 令和3年3月. がん情報サービス. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/screening/pdf/comparison_sheet_2021_02.pdf
- 日本の健診(検診)制度の概要. 厚生労働省. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000682242.pdf
- Lung Cancer: Screening. Healthy People 2030, U.S. Department of Health and Human Services, Office of Disease Prevention and Health Promotion. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://odphp.health.gov/healthypeople/tools-action/browse-evidence-based-resources/lung-cancer-screening
- Screening for Lung Cancer. U.S. Preventive Services Task Force. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/home/getfilebytoken/gpMtFCtW7cvssqc6wRuogm
- Lung Cancer Screening Guidelines. American Cancer Society. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.cancer.org/health-care-professionals/american-cancer-society-prevention-early-detection-guidelines/lung-cancer-screening-guidelines.html
- USPSTF Recommends Lung Cancer Screening with Low-dose CT. American Academy of Family Physicians. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.aafp.org/news/health-of-the-public/20210325uspstflungcancer.html
- Updated USPSTF screening guidelines may reduce lung cancer deaths. PMC. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8619807/
- Recommendation: Lung Cancer: Screening. United States Preventive Services Task Force. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/lung-cancer-screening
- Low-dose computed tomography lung cancer screening: Clinical and research updates. PubMed. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35253286/
- Lung Cancer Screening: Review and 2021 Update. PMC. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8976270/
- Hesitancy around low-dose CT screening for lung cancer. PubMed. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34555501/
- 区市町村から届くがん検診のお知らせについて. 東京都保健医療局. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/joshi-kenkobu/column/01/
- 肺がんの初期症状とは? 早期発見のためのレントゲン・胸部CT検査. MRSO(マーソ). [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.mrso.jp/mikata/2561/
- 市町村がん検診自己負担額一覧(令和6年度版). 愛知県. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/549684_2531666_misc.pdf
- 大阪市がん検診. 大阪市. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000008503.html
- 低線量肺がんCT検診. 奈良県天理市. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.tenriyorozu.jp/kakubu/shinryo/hoshasenka/gazoshindan/teisenryou-ct_haigan-kenshin/
- 低線量CT肺がん検診. 札幌東徳洲会病院. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.higashi-tokushukai.or.jp/effort/lung_cancer.html
- 低線量肺がんCT健診. あいこ内科クリニック. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.aiko-naika.com/ct/ct-doc/low-dose-ct/
- 低線量肺がんCT検診. 香取おみがわ医療センター. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.hospital.omigawa.chiba.jp/checkup/haigan_ct_kenshin.html
- 低線量肺がんCT検診. 仙川駅前きむら呼吸器内科クリニック. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.kimura-kokyuki-cl.com/lung-ct/
- 肺がん低線量CT検診. 奈良市ホームページ. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/94/102642.html
- 「職域がん検診体制整備奨励金」を開始します!. 福井県. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www2.pref.fukui.lg.jp/press/view.php?cod=7a3f20171315014029
- 健康診断に助成金は使える?2種類の助成金と注意点を詳しく解説. Growbase. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://hss.wellcoms.jp/blog/n0030
- 有効性評価に基づく 肺がん検診ガイドライン 2025 年度版. 国立がん研究センター. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://canscreen.ncc.go.jp/guideline/lung_guideline2025.pdf
- Low Dose Computed Tomography for Lung Cancer Screening in Tuberculosis Endemic Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis. PubMed. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39581379/
- 肺:[国立がん研究センター がん統計]. がん情報サービス. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/cancer/12_lung.html
- 肺がん患者数の年次推移、生存率、死亡率の統計データ. おしえて がんのコト. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://oshiete-gan.jp/lung/about/statistic/
- 肺がんの患者数. がんを学ぶ. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.ganclass.jp/kind/lung/know/patient
- 肺がんについて. 国立がん研究センター 東病院. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/clinic/thoracic_surgery/060/010/index.html
- 肺がんの統計と予後-ステージや年齢などによる生存率の違い. 肺がんとともに. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.haigan-tomoni.jp/know/about/patients03.html
- 部位別がんの治療費:肺がんの治療費. がん治療費ドットコム. [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.ganchiryohi.com/cost/76