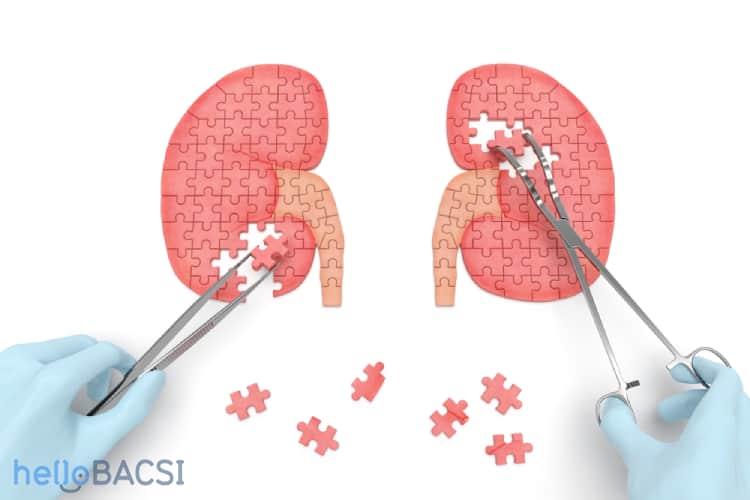この記事の科学的根拠
この記事は、入力された研究報告書で明示的に引用された最高品質の医学的エビデンスにのみ基づいています。以下に、参照された実際の情報源と、提示された医学的指導との直接的な関連性を示します。
- 世界腎臓病予後改善推進機構 (KDIGO): 本記事における慢性腎臓病(CKD)の全般的な管理戦略、特にSGLT2阻害薬の役割や患者中心のケアに関する推奨は、KDIGOが発行した最新の診療ガイドラインに基づいています13。
- 日本腎臓学会 (JSN): 日本の医療現場に即した血圧目標や貧血管理など、より具体的な治療法の推奨は、日本腎臓学会の「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023」を根拠としています12。
- 日本透析医学会 (JSDT): 日本国内の透析患者数、平均年齢、原因疾患などの正確な統計データは、同学会が毎年発表している「わが国の慢性透析療法の現況」から引用しており、問題の規模と緊急性を示しています7。
- 日本慢性腎臓病データベース (J-CKD-DB): SGLT2阻害薬などの治療法が日本の患者に与える実際の効果に関する「リアルワールドエビデンス」は、この全国規模のデータベースから得られた研究成果に基づいています8。
- 腎臓病SDM推進協会: 本記事の中核をなす「協働意思決定(SDM)」の概念とその重要性は、同協会の活動と理念を参考にしています5。
要点まとめ
- 腎不全治療は、単に治療法を列挙する時代から、患者様自身の価値観を基に医療者と協働で最善の道を選ぶ「協働意思決定(SDM)」の時代へと移行しています56。
- SGLT2阻害薬やミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(フィネレノン)などの新しい薬物療法は、腎機能の低下を遅らせ、透析導入を回避または遅延させる大きな希望となっています13。
- 腎代替療法には、血液透析(HD)、腹膜透析(PD)、腎移植の3つの主要な選択肢があり、それぞれ生活様式や価値観に与える影響が大きく異なります134。
- 治療の選択は終着点ではなく、栄養指導、適切な運動、そして心のケアを通じて、治療後の生活の質(QOL)を豊かにすることが極めて重要です。
- 日本の研究機関では腎臓の再生や修復に関する基礎研究が進行中であり、将来的にはさらに新しい治療選択肢が期待されています11。
腎不全治療の選び方ガイド
「腎不全」「透析」と告げられた瞬間、これからの生活や仕事、家族との時間がどうなってしまうのか、不安で胸が締めつけられているかもしれません。eGFR や G4・G5 といった聞き慣れない数値、新しい薬の名前、血液透析・腹膜透析・腎移植という選択肢が一度に提示されると、「自分には何が一番いいのか」冷静に考える余裕がなくなってしまいます。その戸惑いや怖さは、とても自然なものです。一つひとつ整理しながら、自分らしい選択を見つけていきましょう。
この解説ボックスでは、腎不全と診断されたあとに「何から考えればよいか」「どのように治療法を選んでいけばよいか」を、できるだけわかりやすく道筋としてまとめます。まずは、腎臓と尿路全体のしくみや代表的な病気を俯瞰しておくと、主治医の説明がぐっと理解しやすくなります。全体像を整理したいときは、腎臓や尿路の働き、検査、症状、治療法を一つにまとめた総合ページである腎臓と尿路の病気 完全ガイドをあわせて読みながら、自分の状態を位置づけてみてください。
腎不全に至る背景には、日本では糖尿病性腎症や慢性糸球体腎炎、腎硬化症といった生活習慣病・慢性腎臓病(CKD)が大きく関わっています。KDIGO や日本腎臓学会のガイドラインでは、eGFR と尿アルブミン量によって G1〜G5 のステージ分類を行い、G5 は末期腎不全として腎代替療法の検討が必要な段階とされています。ご自身が今どのステージにいるのか、進行スピードは速いのか遅いのかを理解することが、治療選択の出発点です。特に早い段階での対策を整理したいときは、G1〜G3 の時期に現れやすい変化と向き合うための視点がまとめられた初期の腎不全の解説も参考になります。
治療の第一歩は、「いま残っている腎機能をできるだけ長く守る」保存的療法を徹底することです。血圧や血糖の管理、SGLT2 阻害薬やフィネレノンなど腎保護効果が示された薬の適切な使用、そして塩分・たんぱく質・カリウム・リンの量をステージに合わせて調整する食事療法が柱になります。無理のない有酸素運動を続けることも、心血管リスクと腎機能の両方を守る助けになります。こうした生活面の工夫を体系的に押さえたいときは、腎臓を長く守るための具体的な予防策をまとめた腎臓を守るためのガイドを一緒に確認すると、日常生活で取り組むべきポイントが整理しやすくなります。
それでも eGFR が 15 未満に近づき、むくみや息切れ、食欲低下などの症状が強くなってきたら、血液透析・腹膜透析・腎移植といった腎代替療法を具体的に検討する時期に入ります。それぞれの治療には、通院頻度や時間的拘束、食事制限、自己管理の負担度など、日常生活への影響が大きく異なります。本記事で紹介されている SDM(協働意思決定)の考え方に沿って、ご自身の価値観や人生設計を医療チームと共有しながら、一番納得できる選択肢を選んでいきましょう。治療開始のタイミングを見逃さないためには、症状や検査値から読み取れる危険信号を整理した慢性腎不全の重要な兆候も合わせてチェックしておくと安心です。
一方で、「クレアチニンが少し高いだけだから」「まだ透析ではないから」と自己判断で通院間隔を延ばしたり、薬や食事制限を勝手に緩めてしまうと、気づかないうちに腎機能低下が加速することがあります。むくみや息切れ、尿の量や色の変化、泡立ちといった身体からのサインを軽く見ず、早めに主治医へ共有することが大切です。特に、eGFR の変化やたんぱく尿といった「腎機能低下のサイン」を整理した腎機能低下のサインや、ステージごとの食事の工夫をまとめた腎臓病患者のための食事ガイドを活用しながら、「無理のない自己管理」と「早めの受診」のバランスを意識していきましょう。
腎不全の治療は、もはや「どの透析を選ぶか」だけではなく、「自分はどう生きたいのか」を医療者と共に考えながら決めていく時代になっています。新しい薬物療法や、保存的療法と腎代替療法を組み合わせた柔軟な戦略によって、以前よりもずっと多くの「選択肢」と「希望」が生まれています。今回の記事やここで紹介した関連ページをきっかけに、ご自身の疑問や不安を書き出し、主治医や医療チーム、ご家族とじっくり話し合ってみてください。あなたのペースで、一歩ずつ納得のいく治療計画を形にしていきましょう。
第1章:あなたの腎臓を理解する-腎不全の原因とステージ
腎臓は、血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として排泄するだけでなく、血圧の調整、赤血球の産生促進、骨の健康維持など、生命維持に不可欠な多様な機能を担っています。腎不全とは、これらの機能が慢性的に低下した状態(慢性腎臓病、CKD)が進行した結果を指します。
日本透析医学会の統計によれば、慢性腎不全に至る原因疾患の第一位は糖尿病性腎症(39.5%)、次いで慢性糸球体腎炎、腎硬化症と続きます7。これは、生活習慣病である糖尿病や高血圧の管理が、腎臓を守る上でいかに重要であるかを示しています。
慢性腎臓病の重症度は、腎機能の指標である推算糸球体ろ過量(eGFR)と、腎障害の指標である尿中アルブミン排泄量に基づいて、国際的なKDIGOガイドラインおよび日本のJSNガイドラインによりステージ分類されます1213。このステージ分類は、治療方針を決定する上で重要な指標となります。
| ステージ | eGFR (mL/分/1.73m²) | 腎機能の状態 |
|---|---|---|
| G1 | 90以上 | 正常または高値 |
| G2 | 60~89 | 軽度低下 |
| G3a | 45~59 | 軽度~中等度低下 |
| G3b | 30~44 | 中等度~高度低下 |
| G4 | 15~29 | 高度低下 |
| G5 | 15未満 | 末期腎不全(ESKD) |
ご自身のステージを正確に把握し、早期から適切な対策を講じることが、腎機能の維持と良好な予後につながります。
第2章:治療選択の核心「協働意思決定(SDM)」とは?
かつての医療では、医師が最善と判断した治療法を患者が受け入れる、という形が一般的でした。しかし、腎不全のように生涯にわたる管理が必要で、治療法が患者様の生活様式、価値観、人生設計に深く影響を及ぼす疾患においては、新しいアプローチが求められます。
それが「協働意思決定(Shared Decision Making – SDM)」です4。SDMとは、医師や看護師、栄養士などの医療専門家チームが、最新かつ最良の医学的根拠(エビデンス)を分かりやすく提供し、それに対して患者様とご家族がご自身の価値観、希望、生活状況を伝え、対話を重ねることで、全員が納得できる最善の治療方針を「共に」決定していく過程を指します56。
例えば、「旅行が好きで、できるだけ自由な時間を確保したい」という価値観を持つ方と、「自宅で過ごす時間を大切にし、通院の負担を減らしたい」という方では、最適な治療法は自ずと異なります。SDMは、こうした個々の「物語」を医療の中心に据えることで、治療への満足度を高め、より良い療養生活を実現することを目指します。日本でも腎臓病SDM推進協会などの団体が設立され、この先進的なアプローチの普及が積極的に進められています5。
第3章:腎機能の維持を目指す-保存的療法と最新薬物療法
末期腎不全への進行を可能な限り遅らせ、透析や移植を回避することを目指す「保存的療法」は、CKD治療の根幹です。特に近年の薬物療法の進歩は、この分野に革命をもたらしました。
3.1. 生活習慣の改善:食事と運動
食事療法は、腎臓への負担を軽減するための基本です。日本腎臓学会のガイドラインでは、ステージに応じた塩分(1日6g未満を推奨)、タンパク質、カリウム、リンの摂取制限が推奨されています3134。これらは専門的な知識を要するため、必ず医師や管理栄養士の指導のもとで行うことが重要です。
運動療法もまた、筋力維持、心血管疾患の危険性低下、生活の質の向上に有効であることが示されています32。ウォーキングなどの有酸素運動が推奨されますが、個々の病状に合わせた運動計画を立てるため、主治医への相談が不可欠です。
3.2. 薬物療法の最前線:SGLT2阻害薬とその他の新薬
薬物療法の分野では、画期的な進歩が続いています。中でも特筆すべきは「SGLT2阻害薬」です。元々は血糖降下薬として開発されましたが、その後の大規模臨床試験で、糖尿病の有無にかかわらず、CKD患者の腎機能低下を抑制し、心不全などの心血管イベントを減少させることが証明されました13。この強力な腎保護作用は、KDIGOやJSNの最新ガイドラインでも高く評価され、CKD治療の標準薬の一つとして位置づけられています1213。さらに、J-CKD-DBのような日本の大規模データベースを用いた研究でも、日本人患者における有効性が確認されており、その信頼性は非常に高いものとなっています81718。
その他、非ステロイド性ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(フィネレノンなど)も、炎症や線維化を抑えることで腎保護効果を発揮することが示され、新たな治療選択肢として期待されています。
3.3. 腎性貧血との戦い:HIF-PH阻害薬の登場
腎機能が低下すると、赤血球の産生を促すホルモン(エリスロポエチン)が不足し、腎性貧血が起こります。従来は注射剤(ESA製剤)による治療が中心でしたが、近年「HIF-PH阻害薬」という経口薬が登場しました。これは、体が本来持つ低酸素応答メカニズムを活性化させることで、内因性のエリスロポエチン産生を促す新しい作用機序の薬です。東京大学の南学正臣教授らの研究によってもその有効性と安全性が示されており、注射の負担を軽減し、患者の生活の質を改善する選択肢として注目されています1024。
第4章:腎代替療法-透析と腎移植の詳細な比較
保存的療法を行っても腎機能の低下が進行し、末期腎不全(ステージG5)に至った場合、生命を維持するために腎臓の機能を代替する治療(腎代替療法)が必要となります。主な選択肢は「血液透析」「腹膜透析」「腎移植」の3つです。SDMの精神に基づき、それぞれの特徴を客観的に比較検討することが重要です。
4.1. 血液透析(HD):特徴、スケジュール、生活への影響
血液透析は、腕に作成したシャント(動脈と静脈をつなぎ合わせた太い血管)から血液を体外に取り出し、ダイアライザー(人工腎臓)と呼ばれる装置で老廃物や余分な水分を除去した後、再び体内に戻す方法です1。日本では最も広く行われている治療法で、通常は週に3回、1回あたり4~5時間かけて医療機関で行われます。医療スタッフが治療を管理するため安心感が高い一方、通院による時間的・身体的拘束が大きい点が特徴です。
4.2. 腹膜透析(PD):在宅治療の利点と注意点
腹膜透析は、患者様自身の腹腔(お腹の中)にある腹膜を利用して血液を浄化する方法です3。お腹に留置したカテーテルを通して透析液を腹腔内に入れ、一定時間留置することで、腹膜を介して老廃物や水分が透析液に移動します。その後、その透析液を排出します。この交換作業は、主に自宅や職場で患者様自身またはご家族が行います。通院は月1~2回程度で済むため、時間的制約が少なく、社会生活との両立がしやすいという大きな利点があります。しかし、自己管理が徹底して求められ、腹膜炎などの感染症には常に注意が必要です。
4.3. 腎移植:最も自由度の高い選択肢とその現実
腎移植は、他者から提供された健康な腎臓を体内に移植することで、腎機能を回復させる根治療法です4。ご家族などから提供される「生体腎移植」と、亡くなられた方から提供される「献腎移植」があります。移植が成功すれば、透析から完全に解放され、食事制限も大幅に緩和されるなど、最も自由度の高い生活を送ることが可能です。しかし、大きな外科手術が必要であること、移植後は拒絶反応を抑えるために免疫抑制薬を生涯にわたり服用し続けなければならないこと、そしてドナー不足という厳しい現実があります。
4.3.1. あなたに合った選択は?比較表で考える
以下の表は、各治療法の一般的な特徴をまとめたものです。ご自身のライフスタイルや価値観と照らし合わせながら、主治医と相談する際の参考にしてください。
| 項目 | 血液透析 (HD) | 腹膜透析 (PD) | 腎移植 |
|---|---|---|---|
| 治療場所 | 医療機関 | 自宅・職場 | (術後安定すれば)日常生活 |
| 時間的拘束 | 週3回、1回4-5時間の通院 | 毎日数回の自己交換(1回30分程度) | 毎日の服薬、定期的な通院 |
| 食事・水分制限 | 比較的厳しい | 比較的緩やか | 大幅に緩和 |
| 自己管理の責任 | シャント管理、食事・体重管理 | 交換操作、感染対策(最も高い) | 服薬管理、感染対策 |
| 主な危険性 | シャントトラブル、血圧変動 | 腹膜炎、カテーテル出口部感染 | 拒絶反応、感染症、免疫抑制薬の副作用 |
| 旅行・社会生活 | 旅行透析の手配が必要 | 透析液の運搬が必要だが比較的自由 | 最も自由度が高い |
第5章:治療後の生活を豊かにする-食事、運動、心のケア
どの治療法を選択しても、それが人生の終わりではありません。むしろ、新しい生活の始まりです。治療を受けながら、いかにして心豊かに、自分らしく生きていくかが重要になります。
5.1. 専門家による栄養指導
治療法によって食事制限の内容は異なります。専門の管理栄養士による個別指導を受けることで、栄養バランスを保ちながら、食事を楽しむ工夫を学ぶことができます。
5.2. 無理のない運動の継続
体力の維持・向上は、合併症の予防や精神的な健康にもつながります。医師や理学療法士と相談し、ご自身の状態に合った安全な運動を継続することが推奨されます。
5.3. 心の健康と社会的サポート
慢性疾患との共存は、時に不安や孤独感をもたらします。こうした精神的な負担について医療スタッフに相談することに加え、同じ病を持つ仲間とつながることも大きな力になります。日本では、全国腎臓病協議会(全腎協)20やNPO法人 日本腎臓病協会(JKA)19といった患者会が活発に活動しています。これらの団体は、情報提供、電話相談、交流会の開催などを通じて、患者様とご家族を力強く支援しています1427。JKAが提供する「CKD手帳」のような自己管理ツールも、治療への主体的な参加を助けます19。
第6章:腎臓治療の未来-日本の研究室から世界へ
腎臓治療の未来は、希望に満ちています。日本の研究室からも、世界をリードする画期的な研究成果が次々と生まれています。例えば、京都大学の柳田素子教授の研究グループは、急性腎障害(AKI)から慢性腎臓病(CKD)へ移行するメカニズムを解明し、腎臓が持つ自己修復能力を高めることで、線維化(腎臓が硬くなる現象)を抑制する新たな治療戦略の可能性を示しています11。
こうした基礎研究の積み重ねが、将来的には「腎臓を再生させる」「傷ついた腎臓を修復する」といった、現在の治療の枠組みを根底から変えるような新しい治療法の開発につながる可能性があります。科学の進歩は、腎不全と共に生きる人々の未来を、より明るいものにし続けています。
よくある質問
腎不全と診断されたら、必ず透析が必要になりますか?
新しい薬(SGLT2阻害薬など)は、どんな人でも使えますか?
SGLT2阻害薬は、糖尿病の有無にかかわらず多くの慢性腎臓病患者様で腎保護効果が認められていますが、全ての患者様に使用できるわけではありません。腎機能が極度に低下している場合(末期腎不全など)や、特定の病状をお持ちの方には適さないことがあります。また、HIF-PH阻害薬なども同様に、使用には適応基準があります。これらの新しい薬の使用については、必ず腎臓専門医が患者様一人ひとりの状態を総合的に評価して、その適応を判断します。
治療の選択について、誰に相談すればよいですか?
結論
腎不全の治療は、かつての暗いイメージを払拭し、希望に満ちた新時代を迎えています。腎機能の維持を目指す革新的な薬物療法の登場、そして患者様が治療の主役となる「協働意思決定(SDM)」という考え方の浸透が、その大きな原動力です。腎代替療法においても、血液透析、腹膜透析、腎移植という多様な選択肢があり、それぞれの利点・欠点を理解した上で、ご自身の人生設計に最も合致する方法を選ぶことができます。
この記事で提供された情報が、皆様にとっての「最初の対話のきっかけ」となることを願っています。ぜひ、ここで得た知識や疑問点を整理し、主治医、医療チーム、そしてご家族と共に、あなたにとって最善の治療計画を築き上げてください。未来は、あなたの主体的な選択の中にあります。
免責事項この記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言に代わるものではありません。健康に関する懸念や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- 旭化成. 家族の誰かに透析治療が必要になったら. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.asahi-kasei.co.jp/medical/personal/basic/special_1.html
- 協和キリン. 薬物療法について|知ろう。ふせごう。慢性腎臓病(CKD). [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.kyowakirin.co.jp/ckd/prevention/pre4.html
- キッセイ薬品工業株式会社. 腎臓の働き~透析療法とは? | 透析について考える. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.kissei.co.jp/dialysis/about_dialysis/cure.html
- 日機装株式会社. 大切な “腎臓”の基礎知識。腎臓の位置、腎臓の働きや病気の種類. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://bright.nikkiso.co.jp/article/medical/kidney-1
- 腎臓病SDM推進協会. 慢性腎臓病とSDM – 糖尿病リソースガイド. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://dm-rg.net/ckdsdm
- 日本透析医会. 腎代替療法における Shared Decision Making(SDM). [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.touseki-ikai.or.jp/htm/05_publish/dld_doc_public/37-1/37-1-3.pdf
- 日本透析医学会. わが国の慢性透析療法の現況(2023年12月31日現在). 日本透析医学会雑誌. 2024;57(12):543-591. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsdt/57/12/57_543/_article/-char/ja
- Okada H, et al. J-CKD-DB: a nationwide multicentre electronic health record-based chronic kidney disease database in Japan. Sci Rep. 2020;10(1):7831. doi: 10.1038/s41598-020-64123-z. Available from: https://www.researchgate.net/publication/341048808_J-CKD-DB_a_nationwide_multicentre_electronic_health_record-based_chronic_kidney_disease_database_in_Japan
- Okada H, et al. J-CKD-DB: a nationwide multicentre electronic health record-based chronic kidney disease database in Japan. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/261691/1/s41598-020-64123-z.pdf
- Sugahara M, Tanaka T, Nangaku M, et al. Prolyl hydroxylase domain inhibitor protects against metabolic disorders and associated kidney disease in Tsukuba-hypo-Ins2-Akita diabetic mice. J Am Soc Nephrol. 2020;31(4):761-776. doi: 10.1681/ASN.2019070685. PMID: 31953299.
- Yamamoto S, et al. Spatiotemporal ATP dynamics during acute kidney injury predicts renal prognosis. J Am Soc Nephrol. 2021;32(1):117-132. doi: 10.1681/ASN.2020050580. PMID: 33046558.
- 日本腎臓学会. エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.carenet.com/news/general/carenet/56794
- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://kdigo.org/guidelines/ckd-evaluation-and-management/
- 全国腎臓病協議会. 主な活動内容 | 全腎協について. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.zjk.or.jp/about/activities/
- 東京新橋透析クリニック. 全国10万人が集まる透析患者の会「腎友会」とは. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.toseki.tokyo/blog/about-jinyuukai/
- National Kidney Foundation. KDOQI US Commentary on the KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://kdigo.org/wp-content/uploads/2025/01/KDOQI-Commentary_KDIGO-2024-CKD-Guideline.pdf
- 東京大学医学部附属病院. 腎保護作用が最も強い SGLT2 阻害薬は? -薬剤間の薬効差を比較-. [インターネット]. 2022. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.h.u-tokyo.ac.jp/press/__icsFiles/afieldfile/2022/08/09/release_20220809_1.pdf
- 東京大学医学部附属病院. SGLT2 阻害薬の腎保護効果は BMI に影響される?. [インターネット]. 2025. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.h.u-tokyo.ac.jp/press/__icsFiles/afieldfile/2025/01/30/release_20250203-2.pdf
- NPO法人 日本腎臓病協会. NPO法人 日本腎臓病協会 | Japan Kidney Association. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://j-ka.or.jp/
- 一般社団法人 全国腎臓病協議会. 一般社団法人 全国腎臓病協議会(全腎協). [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.zjk.or.jp/
- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). CKD Evaluation and Management. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://kdigo.org/guidelines/ckd-evaluation-and-management/
- 東京医学社. エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン 2023. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.tokyo-igakusha.co.jp/b/show/b/1632.html
- J-CKD-Database. 研究成果. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://j-ckd-db.jp/results/
- 東京カレッジ. NANGAKU Masaomi. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.tc.u-tokyo.ac.jp/en/members/3060/
- Moriyama T, et al. Prognosis in IgA nephropathy: 30-year analysis of 1,012 patients at a single center in Japan. PLoS One. 2014;9(3):e91756. doi: 10.1371/journal.pone.0091756. PMID: 24658533.
- PLoS One. Prognosis in IgA Nephropathy: 30-Year Analysis of 1012 Patients at a Single Center in Japan. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0091756
- NPO法人 東京腎臓病協議会. 患者会の活動. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.toujin.jp/html/kanja.htm
- 全国腎臓病協議会. 全国の患者会(腎友会). [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.zjk.or.jp/jinyuukai/
- 日本腎臓学会. JKA の活動報告. 日本腎臓学会誌. 2019;61(8):1155-1159. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://jsn.or.jp/journal/document/61_8/1155-1159.pdf
- 医学書院. 慢性腎臓病患者とともにすすめるSDM実践テキスト. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/108778
- 東京医学社. 食事療法を中心とした腎不全治療 改訂第3版. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.tokyo-igakusha.co.jp/b/show/b/200.html
- JR札幌病院. 慢性腎臓病. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://hospital.jrhokkaido.co.jp/treatment/%E6%85%A2%E6%80%A7%E8%85%8E%E8%87%93%E7%97%85/
- 沢井製薬. もはや「国民病」の慢性腎臓病……予防と改善に有効なのは、実は運動!. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://kenko.sawai.co.jp/prevention/202208.html
- 日本調剤. 腎臓は健康維持に欠かせない臓器!慢性腎臓病について学ぼう【栄養だより2023年3月号】. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.nicho.co.jp/column/20230301_c1/
- 厚生労働省. 慢性腎臓病(CKD)の重症化予防. [インターネット]. [2025年7月18日引用]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316478.pdf