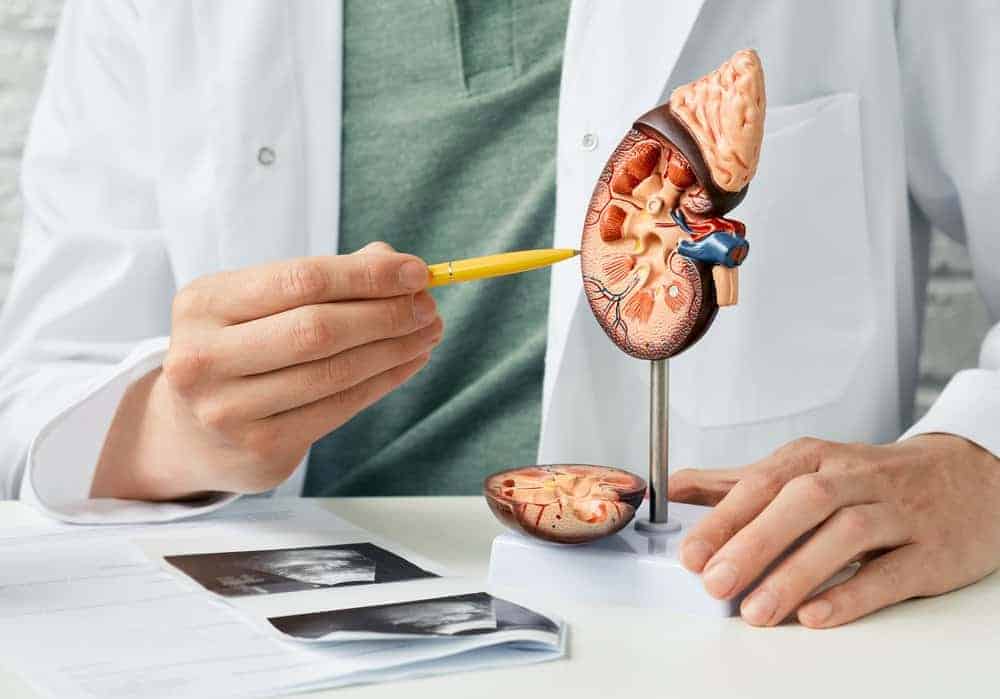この記事の科学的根拠
この記事は、入力された研究報告書に明示的に引用されている最高品質の医学的根拠にのみ基づいて作成されています。以下は、実際に参照された情報源とその医学的指導との直接的な関連性を示したリストです。
- 日本腎臓学会(JSN): この記事における標準的な治療勧告、血圧目標、および各病期における薬剤の役割に関する指針は、日本腎臓学会が発行した「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023」に基づいています1。
- KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes): 国際的な視点と最新の治療法に関する記述は、国際的権威であるKDIGOの「2024年版CKD評価・管理臨床実践ガイドライン」を参考にしています2。
- DAPA-CKD試験 (NEJM): SGLT2阻害薬ダパグリフロジン(フォシーガ)が糖尿病の有無にかかわらず腎機能低下リスクを大幅に減少させるという記述は、The New England Journal of Medicineに掲載されたDAPA-CKD試験の結果に基づいています3。
- EMPA-KIDNEY試験 (NEJM): SGLT2阻害薬エンパグリフロジン(ジャディアンス)の幅広いCKD患者に対する腎保護効果は、EMPA-KIDNEY共同研究グループによる試験結果に基づいています4。
- FIDELIO-DKD試験 (NEJM): 非ステロイド性MRAフィネレノン(ケレンディア)が2型糖尿病を合併するCKDの進行を遅らせるという証拠は、FIDELIO-DKD試験の結果に基づいています5。
- FLOW試験 (NEJM): GLP-1受容体作動薬セマグルチドが腎疾患イベントのリスクを著しく低下させるという画期的な知見は、FLOW試験の結果に基づいています6。
- 厚生労働省 (MHLW) & 日本透析医学会 (JSDT): 日本におけるCKDと透析治療の現状に関する統計データは、これらの公的機関の年次報告書から引用しています7。
要点まとめ
- CKD治療は、かつての進行をただ見守る時代から、SGLT2阻害薬、非ステロイド性MRA、GLP-1受容体作動薬といった新薬により、積極的に腎機能低下を抑制し、透析を遅らせる新時代へと突入しました。
- SGLT2阻害薬は、今や糖尿病の有無を問わず、幅広いCKD患者様に使用される「腎保護のエース」であり、腎不全進行や心血管死のリスクを大幅に低下させることが証明されています3,4。
- 非ステロイド性MRA(フィネレノン)は、腎臓の「炎症」と「線維化」を抑えるという新しい機序で、特に2型糖尿病を合併するCKD患者様の腎臓と心臓を保護します5。
- 治療の成功は、新薬だけに頼るのではなく、血圧を管理するRAS阻害薬などの基本薬、そして減塩を中心とした食事療法という「両輪」をしっかりと回すことが不可欠です。
- 自身の病状を正しく理解し、医師と積極的に対話することが、最適な治療法を見つける鍵です。特に「シックデイ」の対応や市販薬(特に痛み止め)の自己判断での使用には注意が必要です。
CKD治療薬に迷ったときの指針
「慢性腎臓病と言われてから、薬の名前や数値が頭の中でぐるぐるしている」「SGLT2阻害薬やフィネレノン、GLP-1受容体作動薬など新しい薬がたくさん出てきて、何が自分に必要なのか分からない」――そんな不安や混乱を抱えたまま、次の受診日を迎えようとしていませんか。将来の透析や生活への影響を考えると、治療を一つ一つ自分で理解しておきたいという思いはごく自然なものです。その一方で、インターネット上の情報が多すぎて、かえって判断に迷ってしまう方も少なくありません。
このボックスでは、現在主治医から提案されている治療方針や、新しく勧められた薬の位置づけを整理し、「自分の腎臓を守るために今なにを優先すべきか」を一緒に確認していきます。まずは、慢性腎臓病が腎臓と尿路全体の病気の中でどのような位置づけにあるのかを押さえておくと、検査や治療の意味が見えやすくなります。腎炎、腎結石、前立腺の病気なども含めた全体像は、腎臓・尿路疾患を体系的に整理した腎臓と尿路の病気 完全ガイドを併せて読むことで、ご自身のCKDが「今どこにいるのか」をより立体的に把握しやすくなります。
慢性腎臓病(CKD)は、eGFRと尿アルブミン(蛋白尿)の2つでステージ分類され、G1〜G5とA1〜A3の組み合わせで将来の腎不全・心血管イベントのリスクが評価されます。日本では成人の7〜8人に1人がCKDを抱えていると推定され、「沈黙の国民病」と呼ばれるほど自覚症状の乏しい病気です。そのため、検診のたびに少しずつ悪化しているのに気づかれず、G3b以降になってから初めて治療の重要性を意識する方も少なくありません。CKDの背景には高血圧や糖尿病、加齢、生活習慣など複数の要因が絡み合っており、どのステージでどの程度のリスクにいるのかを理解することが、薬物療法を含む全体の戦略を立てる出発点になります。こうしたCKD全体像や予防・診断・治療の流れを体系的に押さえたい場合は、慢性腎臓病(CKD)の予防・診断・治療をまとめた解説を参考にすると、主治医の説明がぐっと理解しやすくなるでしょう。
そのうえで、治療薬を選ぶ最初のステップは、「いま自分がどのステージにいて、どの合併症がどこまで進んでいるのか」を主治医と共有することです。診察では、クレアチニンやeGFRだけでなく、尿アルブミン、血圧、血糖、脂質、貧血やカリウムの値など、薬の選択に直結する検査結果を一つ一つ確認してみてください。SGLT2阻害薬やフィネレノン、GLP-1受容体作動薬は、いずれも「誰にでも同じように飲めばよい薬」ではなく、糖尿病の有無、カリウム値、心血管リスクなどによって適応が変わります。そもそものCKDの症状や進行リスク、従来から使われてきたRAS阻害薬や降圧薬との位置づけを整理するには、慢性腎不全の症状と対策を整理した記事を読みながら、自分の治療がどこまで標準的な土台を踏まえたものなのか確認しておくと安心です。
次のステップとして大切なのは、「自分のステージに合った現実的な治療計画」を主治医と一緒に描くことです。例えばCKDステージ3では、多くの患者さんでSGLT2阻害薬とRAS阻害薬による腎保護が治療の中核となり、そこに血圧管理やスタチンによる心血管予防、場合によってはフィネレノンやGLP-1受容体作動薬が追加されます。同時に、運動量や体重、フレイルの有無、公的助成制度の活用なども含めて総合的に考える必要があります。「どの薬をいつから始めるのか」「どのタイミングで用量を調整するのか」といった具体的な相談をするときは、CKDステージ3の治療と公的助成を詳しく解説した記事を参考にしながら、自分に合った治療の「ロードマップ」をイメージしておくと話し合いがスムーズになります。
さらに、どんなに優れた新薬であっても、塩分やたんぱく質のとり方など日々の食事療法が土台として整っていなければ、本来の効果を十分に引き出すことはできません。また、シックデイ(発熱・下痢・嘔吐などで食事や水分がとれない日)には、一時的に中止すべき薬があり、NSAIDs系の市販の痛み止めは腎機能を急激に悪化させることがあるため、自己判断での連用は非常に危険です。「薬だけ」「食事だけ」に偏らず、両輪としてバランスを取るためには、減塩やたんぱく質制限を含めた具体的な実践方法を、慢性腎臓病の食事療法ガイドで押さえておくと、治療薬の効果をより長く安定して保ちやすくなります。
CKD治療は、かつてのように「悪くなるのを見守るだけ」の時代から、SGLT2阻害薬、非ステロイド性MRA、GLP-1受容体作動薬といった新しい選択肢を組み合わせて、積極的に進行を遅らせる時代へと大きく変わりました。その一方で、薬の数も情報量も増えたからこそ、「自分のステージ」「合併症」「生活背景」に合った治療を一緒に選んでくれる医療チームとの対話がますます重要になっています。この記事で整理したポイントを手がかりに、次の受診ではぜひ気になる薬の名前や不安な点をメモにして持参し、主治医と納得のいくまで話し合ってみてください。それが、腎臓を長く守りながら、日々の生活の質をあきらめないための一歩になります。
第1章:慢性腎臓病(CKD)とは?日本の現状と向き合う
治療について知る前に、まずはご自身の病気がどのような状態なのか、そして日本全体でどのような課題となっているのかを理解することが重要です。
1.1. CKDの定義とステージ分類:あなたの現在地を知る
慢性腎臓病(CKD)とは、腎臓の障害(蛋白尿など)や、腎機能の低下が3ヶ月以上続く状態を指します。ご自身の病状を正確に把握するため、治療は「ステージ分類」に基づいて行われます。この分類は、腎臓がどれくらい老廃物を濾過できているかを示すeGFR(推算糸球体濾過量)と、腎臓からの蛋白の漏れを示す尿アルブミン値の2つの指標で決まります。日本腎臓学会および国際的なKDIGOガイドラインで標準的に用いられているこの分類を理解することは、治療への第一歩です1,2。
- Gステージ(eGFRによる分類):
- G1: eGFR 90以上(正常または高値)
- G2: eGFR 60~89(軽度低下)
- G3a: eGFR 45~59(軽度~中等度低下)
- G3b: eGFR 30~44(中等度~高度低下)
- G4: eGFR 15~29(高度低下)
- G5: eGFR 15未満(末期腎不全)
- Aステージ(尿アルブミン/蛋白による分類):
- A1: 正常(アルブミン尿 30mg/gCr未満)
- A2: 微量アルブミン尿(30~299mg/gCr)
- A3: 顕性アルブミン尿(300mg/gCr以上)
これらの組み合わせで、現在の腎臓の状態と将来の腎不全進行や心血管疾患のリスクが評価され、治療方針が決定されます。
1.2. 日本におけるCKDの深刻な現状と国の目標
CKDは単なる個人の病気ではなく、日本の医療全体における極めて重要な課題です。厚生労働省および日本透析医学会の公式統計データによると、2020年末時点で、日本の慢性透析患者数は約34万7千人に達しています7。この状況を受け、国は2028年までに新規透析導入患者数を年間35,000人以下に減らすという明確な目標を掲げています7。この国家目標は、透析に至る前の段階、つまりCKDの早期発見と効果的な治療によって進行を食い止めることがいかに重要であるかを浮き彫りにしています。
第2章:CKD薬物療法の新時代:透析を遅らせる「3本の矢」
かつてCKDの治療選択肢は限られていましたが、ここ数年で状況は一変しました。3つの新しいカテゴリーの薬剤が登場し、CKD治療に革命をもたらしています。これらは、単に症状を管理するだけでなく、腎臓と心臓そのものを保護し、病気の進行を積極的に遅らせる「攻めの治療」を可能にしました。
2.1. SGLT2阻害薬:糖尿病の有無を問わない「腎保護のエース」
SGLT2阻害薬は、もはや単なる糖尿病治療薬ではありません。今や、糖尿病のないCKD患者様を含む幅広い層に対して強力な腎保護・心保護効果を発揮する基幹薬として位置づけられています。この薬は、尿中に糖を排出させることで血糖値を下げるだけでなく、腎臓内の圧力を下げるなど複数の機序により、腎臓への負担を軽減します。
この変革を決定づけたのが、DAPA-CKD試験です。この画期的な臨床試験では、SGLT2阻害薬の一つであるダパグリフロジン(商品名:フォシーガ)がプラセボ(偽薬)と比較して、腎機能の50%以上の持続的低下、末期腎不全への進行、腎臓または心血管系の原因による死亡のリスクを、全体で39%も有意に低下させることが示されました3。驚くべきことに、この絶大な効果は患者様が糖尿病であるか否かにかかわらず一貫して見られました。その後、EMPA-KIDNEY試験も同様に、別のSGLT2阻害薬であるエンパグリフロジン(商品名:ジャディアンス)が、より広い範囲のCKD患者様に対して腎保護効果を持つことを裏付けています4。
さらに、日本国内の研究からも興味深い知見が得られています。2025年に発表された東京大学の研究では、SGLT2阻害薬の腎保護効果は特にBMI(体格指数)が高い患者様でより顕著になる可能性が示唆されました8。これは、個々の患者様の状態に合わせた治療選択の重要性を示すものであり、日本の臨床現場において非常に有用な情報です。
2.2. 非ステロイド性MRA(フィネレノン):炎症と線維化を抑える新戦略
CKDの進行には、高血圧や高血糖による負担だけでなく、腎臓内部で起こる慢性的な「炎症」と、それが原因で腎臓組織が硬くなる「線維化」が深く関わっています。非ステロイド性ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)であるフィネレノン(商品名:ケレンディア)は、まさにこの炎症と線維化という、従来とは異なるメカニズムに働きかけることで腎臓を保護する、全く新しい選択肢です。
その有効性は、FIDELIO-DKD試験によって確立されました。この試験では、2型糖尿病を合併するCKD患者様において、フィネレノンを標準治療に追加することで、腎不全への進行や心血管イベントのリスクを有意に抑制することが証明されました5。日本では現在、「2型糖尿病を合併する慢性腎臓病」の治療薬として承認されており9, 10、SGLT2阻害薬とは異なる角度から腎臓を守る重要な一手となっています。
2.3. GLP-1受容体作動薬:心腎連関への新たなアプローチ
GLP-1受容体作動薬は、血糖降下作用に加え、体重減少効果、そして強力な心血管保護効果を併せ持つことで知られてきました。そして近年、腎臓に対する保護効果も明確になり、特に2型糖尿病を合併するCKD患者様における重要な治療選択肢として注目されています。
その地位を不動のものとしたのが、2024年に発表された画期的なFLOW試験です。この試験では、セマグルチド(注射剤のオゼンピック®や経口剤のリベルサス®が知られる)が、プラセボと比較して腎疾患の進行、主要な心血管イベント、および全死亡のリスクを全体で24%も低下させることが示されました6。この結果は、心臓と腎臓が密接に関連する「心腎連関」という概念を体現するものであり、この領域における新たな標準治療となる可能性を示唆しています。
第3章:CKD治療の基盤となる重要薬
新薬の登場は目覚ましいものがありますが、それだけでCKD治療が完結するわけではありません。長年にわたり使用されてきた基本的な治療薬も、依然としてCKD管理において不可欠な屋台骨としての役割を担っています。
3.1. RAS系阻害薬(ACE阻害薬/ARB):血圧管理と尿蛋白減少の基本
レニン・アンジオテンシン系(RAS)阻害薬、具体的にはACE阻害薬やARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)は、CKD治療の土台となる薬剤です。これらの薬は、血圧をコントロールするだけでなく、腎臓のフィルター(糸球体)にかかる圧力を直接下げ、腎臓を傷つける原因となる尿蛋白を減少させます。多くの場合、CKD治療における第一選択薬として処方されます。
日本腎臓学会のガイドラインでは、蛋白尿のあるCKD患者様の降圧目標は、診察室血圧で130/80 mmHg未満と明確に定められており、この目標達成のためにRAS阻害薬が中心的な役割を果たします1。
3.2. 脂質異常症治療薬(スタチン系など):心血管イベントを防ぐために
CKD患者様は、腎機能が正常な人と比べて心筋梗塞や脳卒中といった心血管イベントを発症する危険性が非常に高いことが知られています。そのため、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を管理する脂質異常症治療薬、特にスタチン系の薬剤による治療は、腎臓を守ることと同じくらい重要です。
国際的なKDIGOガイドラインでは、50歳以上のほとんどのCKD患者様にスタチンまたはスタチン/エゼチミブ併用療法を推奨しており、これは心血管疾患のリスクを低減するための標準的なアプローチとなっています2。
第4章:合併症を管理し、生活の質(QOL)を保つ薬
CKDの治療は、eGFRやクレアチニンといった数値を追うだけではありません。病気の進行に伴って現れる、貧血や骨の問題といった辛い合併症を適切に管理し、日々の生活の質(Quality of Life)を維持することも極めて重要です。
- 腎性貧血: 腎臓は赤血球を作るホルモン(エリスロポエチン)を産生するため、機能が低下すると貧血になります。だるさや息切れの原因となるこの合併症に対し、ESA製剤(注射薬)やHIF-PH阻害薬(経口薬)による治療が行われます1。
- 高カリウム血症: 腎機能が低下すると、体内のカリウムを十分に排泄できなくなり、血中濃度が上昇します。重篤な不整脈の原因となるため、食事でのカリウム制限に加え、カリウム吸着薬による管理が必要になることがあります1。
- CKD-MBD(ミネラル骨代謝異常): カルシウムやリンのバランスが崩れ、骨がもろくなったり、血管にカルシウムが沈着(石灰化)したりする合併症です。リン吸着薬や活性型ビタミンD製剤を用いて、これらのミネラルバランスを管理します1。
- 代謝性アシドーシス: 体が酸性に傾く状態で、進行すると骨や筋肉に悪影響を及ぼします。重炭酸ナトリウム(重曹)などを内服して、体の酸塩基平衡を補正します1。
第5章:患者が主治医と相談すべきこと:治療薬の選び方と注意点
あなたは治療の受け手であると同時に、主体的な参加者です。正しい知識を持つことで、主治医との対話がより深まり、ご自身にとって最適な治療法を共に見つけることができます。
5.1. 【重要】治療薬選択のポイントをまとめた比較表
最新の主要な治療薬について、その特徴を理解することは非常に重要です。以下の表は、主治医と治療方針を相談する際の参考としてご活用ください。
| 特徴 | SGLT2阻害薬 | 非ステロイド性MRA | GLP-1受容体作動薬 |
|---|---|---|---|
| 主な作用機序 | 尿中への糖排泄促進、糸球体内圧低下 | 炎症・線維化の抑制 | インスリン分泌促進、食欲抑制、心血管保護 |
| 主な対象(日本) | CKD(2型糖尿病の有無を問わず)、心不全 | 2型糖尿病を合併するCKD | 2型糖尿病 |
| 根拠となる主な臨床試験 | DAPA-CKD3, EMPA-KIDNEY4 | FIDELIO-DKD5, FIGARO-DKD | FLOW6 |
| 主な効果 | 強力な腎・心保護 | 腎・心保護 | 腎・心保護、体重減少、血糖改善 |
| 注意すべき主な副作用 | 尿路・性器感染症、脱水、ケトアシドーシス | 高カリウム血症 | 消化器症状(吐き気、下痢など) |
5.2. シックデイ(体調の悪い日)の服薬注意
発熱、下痢、嘔吐などで食事がとれない「シックデイ」には、脱水や腎機能の急激な悪化を防ぐため、一時的に中止すべき薬があります。これはご自身の命を守るための非常に重要な知識です。必ず事前に主治医に確認し、どのような場合にどの薬を休むべきか、具体的な指示を受けておきましょう。
日本腎臓学会のガイドラインなどに基づき、一般的にシックデイに中止を検討すべき薬剤には以下のようなものがあります1,11:
- 降圧薬(特にRAS阻害薬、利尿薬)
- SGLT2阻害薬
- 糖尿病治療薬(特にメトホルミン、SU薬)
- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)
5.3. 避けるべき市販薬(特に痛み止め)
自己判断での市販薬の使用には、特に注意が必要です。中でも、ロキソプロフェン(ロキソニン®など)やイブプロフェンなどの非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は、腎臓への血流を低下させ、腎機能を急激に悪化させる可能性があるため、自己判断での長期連用は非常に危険です12。頭痛や関節痛などで痛み止めが必要な場合は、まず主治医に相談してください。比較的腎臓への影響が少ないとされるアセトアミノフェン(カロナール®など)の使用を検討することが推奨されます。
よくある質問
Q1: クレアチニン値を直接下げる薬はありますか?
残念ながら、現時点では一度傷ついてしまった腎臓の機能を回復させ、クレアチニン値を直接的に下げることを目的とした薬は存在しません13。しかし、最も重要なのは、これ以上腎機能が悪化する速度を緩やかにすることです。本記事で紹介したSGLT2阻害薬などの腎保護薬は、まさにその目的のために開発された非常に効果的な治療法であり、将来の透析導入を遅らせ、あるいは回避することを目指します。
残念ながら、現時点では一度傷ついてしまった腎臓の機能を回復させ、クレアチニン値を直接的に下げることを目的とした薬は存在しません13。しかし、最も重要なのは、これ以上腎機能が悪化する速度を緩やかにすることです。本記事で紹介したSGLT2阻害薬などの腎保護薬は、まさにその目的のために開発された非常に効果的な治療法であり、将来の透析導入を遅らせ、あるいは回避することを目指します。
Q2: 新しい薬は高価ですか?医療費のサポートはありますか?
新しい薬は薬価が高い傾向にありますが、日本には患者様の経済的負担を軽減するための優れた公的支援制度があります。月々の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額が支給される「高額療養費制度」や、指定された難病や障害に対する「医療費助成制度」などです。これらの制度が利用できるかどうかは、ご自身の所得や病状によって異なりますので、まずは主治医や病院の医療ソーシャルワーカー、または加入している健康保険組合にご相談ください。
新しい薬は薬価が高い傾向にありますが、日本には患者様の経済的負担を軽減するための優れた公的支援制度があります。月々の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた額が支給される「高額療養費制度」や、指定された難病や障害に対する「医療費助成制度」などです。これらの制度が利用できるかどうかは、ご自身の所得や病状によって異なりますので、まずは主治医や病院の医療ソーシャルワーカー、または加入している健康保険組合にご相談ください。
Q3: 食事療法と薬物療法、どちらが重要ですか?
これは非常によくある質問ですが、答えは「どちらも同じくらい重要」です。食事療法と薬物療法は、CKD治療における車の両輪のような関係です。減塩やたんぱく質制限といった食事療法は、腎臓への日常的な負担を減らすための土台となります。薬物療法は、その土台の上でさらに強力な保護効果を発揮し、病気の進行を抑制します。どちらか一方が欠けても、治療はうまくいきません。両方を根気よく続けることが、ご自身の腎臓を長く守るための最良の道筋となります14。
これは非常によくある質問ですが、答えは「どちらも同じくらい重要」です。食事療法と薬物療法は、CKD治療における車の両輪のような関係です。減塩やたんぱく質制限といった食事療法は、腎臓への日常的な負担を減らすための土台となります。薬物療法は、その土台の上でさらに強力な保護効果を発揮し、病気の進行を抑制します。どちらか一方が欠けても、治療はうまくいきません。両方を根気よく続けることが、ご自身の腎臓を長く守るための最良の道筋となります14。
結論
慢性腎臓病(CKD)の治療は、間違いなく新時代を迎えました。かつては防ぐ手立てが少なかった腎機能の低下に対し、今や私たちはSGLT2阻害薬、非ステロイド性MRA、GLP-1受容体作動薬といった強力な武器を手にしています。これらの薬は、科学的根拠に裏付けられた確かな力で、透析導入を遅らせ、心臓を守り、患者様の未来に新たな光を灯しています。
しかし、最も重要なのは、これらの薬をただ服用することではありません。ご自身の病状と治療の選択肢を正しく理解し、食事療法や生活習慣の改善に取り組み、そして何よりも主治医とオープンにコミュニケーションをとって、納得のいく治療法を一緒に見つけていくことです。この記事で得られた知識が、そのための確かな一歩となり、あなたが希望を持って、主治医と共に力強く歩んでいくための一助となることを、JHO編集部一同、心から願っています。
免責事項この記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的アドバイスを構成するものではありません。健康上の懸念がある場合、またはご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- 日本腎臓学会編. エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023. 東京医学社; 2023. Available from: https://minds.jcqhc.or.jp/summary/c00779/
- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. 2024. Available from: https://kdigo.org/guidelines/ckd-evaluation-and-management/
- Heerspink HJL, Stefánsson BV, Correa-Rotter R, et al. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. N Engl J Med. 2020;383(15):1436-1446. doi:10.1056/NEJMoa2024816. Available from: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2024816
- The EMPA-KIDNEY Collaborative Group. Empagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. N Engl J Med. 2023;388(2):117-127. doi:10.1056/NEJMoa2204233. Available from: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2204233
- Bakris GL, Agarwal R, Anker SD, et al. Finerenone and Chronic Kidney Disease Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2020;383(23):2219-2229. doi:10.1056/NEJMoa2025845. Available from: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2025845
- Perkovic V, Tuttle KR, Rossing P, et al. Semaglutide and Kidney Disease Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2024. doi:10.1056/NEJMoa2403347. Available from: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2403347
- 厚生労働省. 腎疾患対策の取組について. 2022. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/001005972.pdf
- University of Tokyo. Press Release: SGLT2 阻害薬の腎保護効果は BMI に影響される?. 2025. Available from: https://www.h.u-tokyo.ac.jp/press/__icsFiles/afieldfile/2025/01/30/release_20250203-2.pdf
- Wellbeing Naika Clinic. CKD治療薬 ケレンディア(フィネレノン®)長期処方解禁. Available from: https://wellbeingnaika.com/finerenone/
- 桂川さいとう内科循環器クリニック. フィネレノン:新しい心不全、腎不全治療薬. 2024. Available from: https://clinicsaito.com/2024/10/24/フィネレノン:心不全・腎不全治療の新しい治療/
- たかぎファミリークリニック. ブログ. Available from: https://www.takagi-family-clinic.com/blog/
- 赤垣クリニック. 腎臓が悪い方が気を付ける薬とは?. Available from: https://akagaki-clinic.jp/blog/腎臓が悪い方が気を付ける薬とは?/
- 赤羽もり内科・腎臓内科. クレアチニンを下げる薬はある?腎機能が低下したときの治療薬. Available from: https://akabanejinzonaika.com/drug
- じんラボ. 慢性腎臓病(CKD)の食事療法での皆さんの愚痴や悩み. Available from: https://www.jinlab.jp/dietarylife/wk_grumble.html