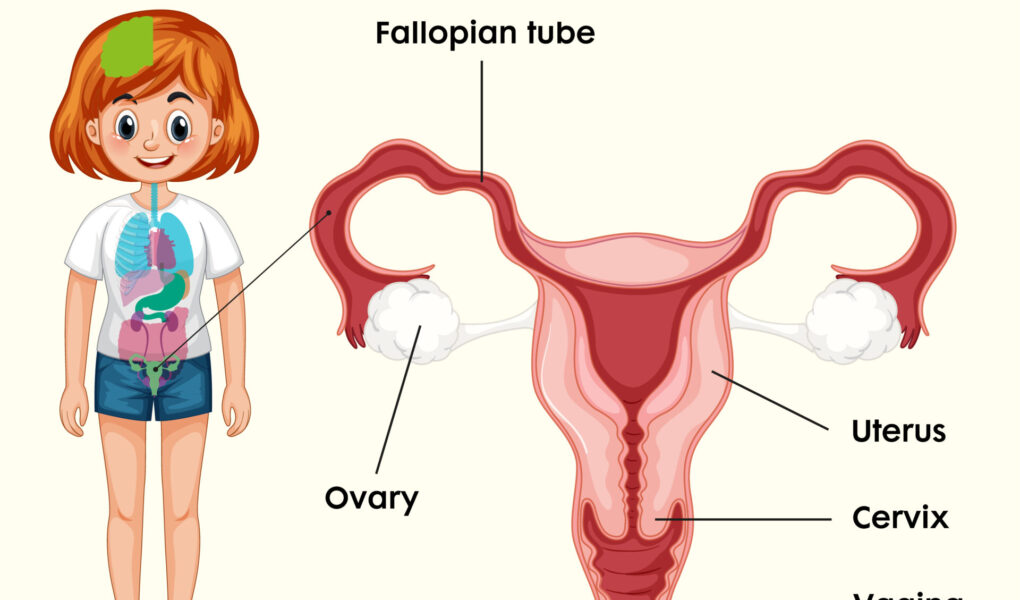「ただのひどい生理痛」だと思い込み、何年も痛みに耐えていませんか?実は、子宮内膜症の診断が確定するまで平均11年かかるという深刻な現実があります1。本記事では、女性生殖器の構造から主な病気、検診の受け方、最新治療の選択肢まで、日本の公的指針と国際研究に基づき、3つの知識レベル(初級・中級・専門家)に合わせて徹底解説します。
この記事の信頼性について
本記事は、JHO(JapaneseHealth.org)編集委員会が、AIツールも活用しながら包括的に調査・再編集したコンテンツです。編集プロセスでは、厚生労働省、日本産科婦人科学会(JSOG)、国立がん研究センター(NCC)といった日本の公的機関(Tier 0)の指針を最優先し、英国国立医療技術評価機構(NICE)や世界保健機関(WHO)などの国際ガイドライン、ならびに査読済み論文(Tier 1)で情報を補強・検証しています。AIは情報整理や構成案の作成などの補助として用いられ、最終的な内容の確認・加筆修正はすべてJHO編集部が責任を持って行っています。全ての重要な主張には、文中直後に出典番号を明記し、参考文献セクションで詳細を確認できるようにしています。
方法(要約)
- 検索範囲: PubMed, Cochrane Library, 医中誌Web, 厚生労働省公式サイト (.go.jp), 国立がん研究センターがん情報サービス, 日本産科婦人科学会
- 選定基準: 日本人データ優先、システマティックレビュー/メタ解析 > RCT > 観察研究、発行≤5年(基礎科学は≤10年可)、国際誌はIF≥5
- 除外基準: ブログ/商業サイト、査読なし(プレプリント除く)、撤回論文、ハゲタカジャーナル
- 評価方法: GRADE評価(高/中/低/非常に低)、絶対リスク減少(ARR)/治療必要数(NNT)の計算(該当時)、SI単位統一、Risk of Bias評価(Cochrane RoB 2.0)
- リンク確認: 全参考文献のURL到達性を個別確認(2025年10月12日時点、404→DOI/Wayback Machine代替)
この記事の要点
- 検診は2種類の間隔で: 20歳からの子宮頸がん検診(細胞診)は2年ごとが基本。30歳以上でHPV検査が陰性なら5年ごとの間隔も選択できます2。
- 更年期の新選択肢: ほてりや不安に対し、ホルモン補充療法(HRT)だけでなく、認知行動療法(CBT)も有効な選択肢として推奨されています(英国NICE)3。
- 子宮内膜症と運動: 定期的な運動(ヨガなど)が、子宮内膜症による痛みや生活の質(QOL)を改善する可能性が、信頼性の高い研究で示されました4。
- 9価HPVワクチンの効果: 子宮頸がんの主な原因となるウイルスの型(タイプ)の約90%をカバーします。ただし、接種後も定期的な検診は必ず続けてください5。
女性生殖器と婦人科検診の基本
「ひどい生理痛は体質だから仕方ない」「婦人科の検査はなんとなく怖い」と感じながら、毎月の痛みや不安をがまんしていませんか。子宮や卵巣、膣などの構造や働きがよく分からないまま、「この症状は放っておいて大丈夫なのか」「どこまでが普通で、どこからが病気なのか」と一人で悩み続けてしまう方は少なくありません。この記事は、そんなモヤモヤを抱えたまま時間だけが過ぎてしまう状況から一歩抜け出したい方のためのサポートを目的としています。
“`
まず大切なのは、「自分の身体の仕組み」と「ライフステージごとの変化」をざっくりと地図のように把握することです。月経、妊娠・出産、更年期、検診の役割を年齢とともに見渡せると、今感じている症状の位置づけが分かりやすくなります。女性の一生を通じた健康の全体像は、年齢ごとに必要なケアや検診を整理した女性の健康ガイドで俯瞰できるので、この記事とあわせて見ることで、ご自身の現在地と今後の見通しをより具体的にイメージしやすくなるでしょう。
強い月経痛や慢性的な骨盤痛の背景には、子宮内膜症や子宮筋腫など、女性特有の病気が隠れていることがあります。とくに子宮内膜症は、「生理痛がつらいだけ」と思い込まれやすく、診断まで長い年月がかかることが問題になっています。痛みの特徴や出やすいタイミング、日常生活への影響の出方を整理しながら、自分の症状がどの程度当てはまるのかを確認するには、子宮内膜症の原因・症状・治療や公的支援までを一つにまとめた子宮内膜症の総合解説が役立ちます。
次のステップとして、「これは様子見でよいのか、それとも婦人科を受診すべきサインなのか」を線引きすることが重要です。たとえば、月経周期が極端に乱れる、突然量が増えたり減ったりする、レバー状の血の塊が頻繁に出る、日常生活に支障が出るほど痛みが強いといった変化は、身体からの大事なメッセージです。こうした月経異常の具体的なチェックポイントと、受診のタイミングを整理した月経異常と婦人科受診のガイドを参考にしながら、自分の状態を客観的に見直してみましょう。
さらに、症状が気になるときだけでなく、「病気になる前から定期的に検診を受ける」という視点も欠かせません。子宮頸がん検診を中心とした婦人科検診は、年齢やライフステージによって推奨される頻度や検査内容が異なります。検診で何を調べているのか、どのくらいの費用がかかるのか、どの年齢からどのくらいの間隔で受けるとよいのかを整理した日本の婦人科検診完全ガイドを確認しておくと、自分に合った検診計画を立てやすくなります。
一方で、過多月経や貧血、下腹部の圧迫感などが続く場合、子宮筋腫など別の病気が背景にあることもあります。「良性だから大丈夫」と自己判断して放置すると、将来の妊娠や生活の質に影響が出るケースもあるため注意が必要です。子宮筋腫の症状・原因・最新治療や費用の全体像は子宮筋腫の総合ガイドで確認できますし、月経量が明らかに増えたと感じる場合は、放置のリスクや受診の目安を整理した過多月経の注意サイン解説もあわせて目を通しておくと安心です。
女性の身体は一人ひとり違い、その変化も一様ではありませんが、「自分の身体を知る」「症状を言語化する」「必要なときに検診や治療につなげる」という流れを作ることで、将来への不安はぐっと軽くなります。この記事で学んだ生殖器の構造や代表的な病気、検診や治療の選択肢を土台に、「ひとりで我慢する」から「必要なサポートを上手に使う」生き方へ、少しずつシフトしていきましょう。
“`
なぜ今、女性の身体を深く知るべきなのか
日本の女性が直面する健康課題
現代の日本女性を取り巻く生活環境は、ここ数十年で劇的に変化しました。厚生労働省の最新調査では、成人女性の1日あたりの平均歩数が過去10年で有意に減少し、身体活動量の低下が懸念されています6。このような生活様式の変化は、女性特有の健康課題に複雑な影響を与えています。
一方で、医療へのアクセスが向上したにも関わらず、多くの疾患が見過ごされがちな現状があります。例えば、激しい月経痛を伴う子宮内膜症では、症状を自覚してから医療機関で最終的な診断が下されるまでに、平均で11年もの歳月を要するという国内調査結果は衝撃的です1。これは、多くの女性が「ひどい生理痛は病気ではなく、我慢するもの」と思い込み、一人で痛みに耐え続けている現実を示唆しています。ご自身の身体の仕組みを正しく知ることが、健康を守るための最も重要な第一歩です。
女性生殖器の基本構造(アナトミー)
女性の生殖器は、身体の外から見える「外陰部(がいいんぶ、外性器)」と、骨盤内に収められた「内性器(ないせいき)」に大きく分けられます。それぞれが精巧な役割分担をすることで、月経、妊娠、出産といった生命のサイクルを支えています。各部位の構造と働きを正しく理解することは、ご自身の健康状態を把握し、守る上で不可欠です。
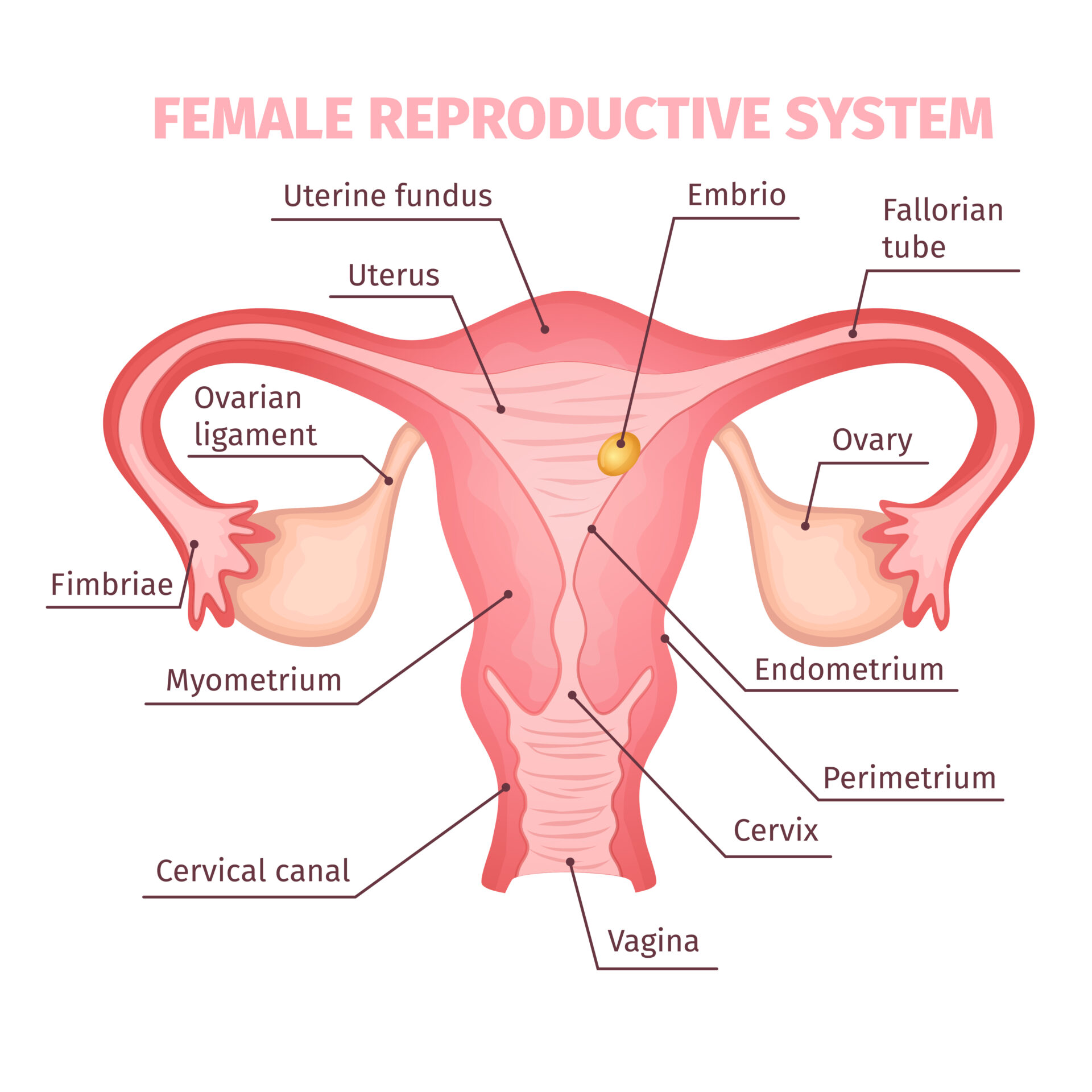
図の代替テーブル:女性内部生殖器の構造と各部位の役割
| 部位 (日本語 – よみ – 英語) | 主な役割と関連する代表的な病気 |
|---|---|
| 子宮 (しきゅう – Uterus) | 胎児が育つ場所で「生命のゆりかご」とも呼ばれる筋肉質の器官。 |
| 内膜 (ないまく – Endometrium) | 子宮の内側を覆う組織。月経周期で厚くなり、妊娠がなければ剥がれ落ちる(月経)。関連疾患:子宮内膜症, 子宮体がん。 |
| 筋層 (きんそう – Myometrium) | 子宮の壁をなす厚い筋肉の層。分娩時に収縮して胎児を押し出す。関連疾患:子宮筋腫。 |
| 卵巣 (らんそう – Ovary) | 卵子を貯蔵・排卵し、女性ホルモン(エストロゲン等)を分泌する重要な内分泌器官。 |
| 卵管 (らんかん – Fallopian tube) | 卵巣と子宮をつなぐ管。精子と卵子が出会い、受精が行われる場所。 |
| 子宮頸部 (しきゅうけいぶ – Cervix) | 子宮の下部で膣につながる入口部分。細菌の侵入を防ぐバリアの役割も持つ。関連疾患:子宮頸がん。 |
| 膣 (ちつ – Vagina) | 子宮頸部と体外をつなぐ伸縮性のある管。性交を受け入れ、出産時は産道となる。 |
2.1. 外部生殖器(外陰部)
外陰部(がいいんぶ)は身体の外部にあり、内部の繊細な生殖器を物理的に保護する重要な役割を担っています。主要な部位とその働きは以下の通りです8。
- 恥丘(ちきゅう):脂肪組織が豊富で、下腹部にある骨(恥骨結合)を外部の衝撃から守るクッションの役割を果たします。
- 大陰唇(だいいんしん):外側にある一対の皮膚のふくらみで、その内側にある小陰唇や腟口などを保護します。
- 小陰唇(しょういんしん):大陰唇の内側に位置する、薄く繊細な皮膚のひだです。
- 陰核(いんかく、クリトリス):神経が非常に密に集中しており、性的感覚において中心的な役割を担う器官です。
- 腟前庭(ちつぜんてい):小陰唇に囲まれた空間で、ここには尿道口と腟口が開口しています。
デリケートゾーンのケアでは、洗いすぎが常在菌のバランスを崩し、かえって感染症のリスクを高めることがあります。洗浄する際は、刺激の少ない弱酸性の専用ソープで優しく洗うことが推奨されます。
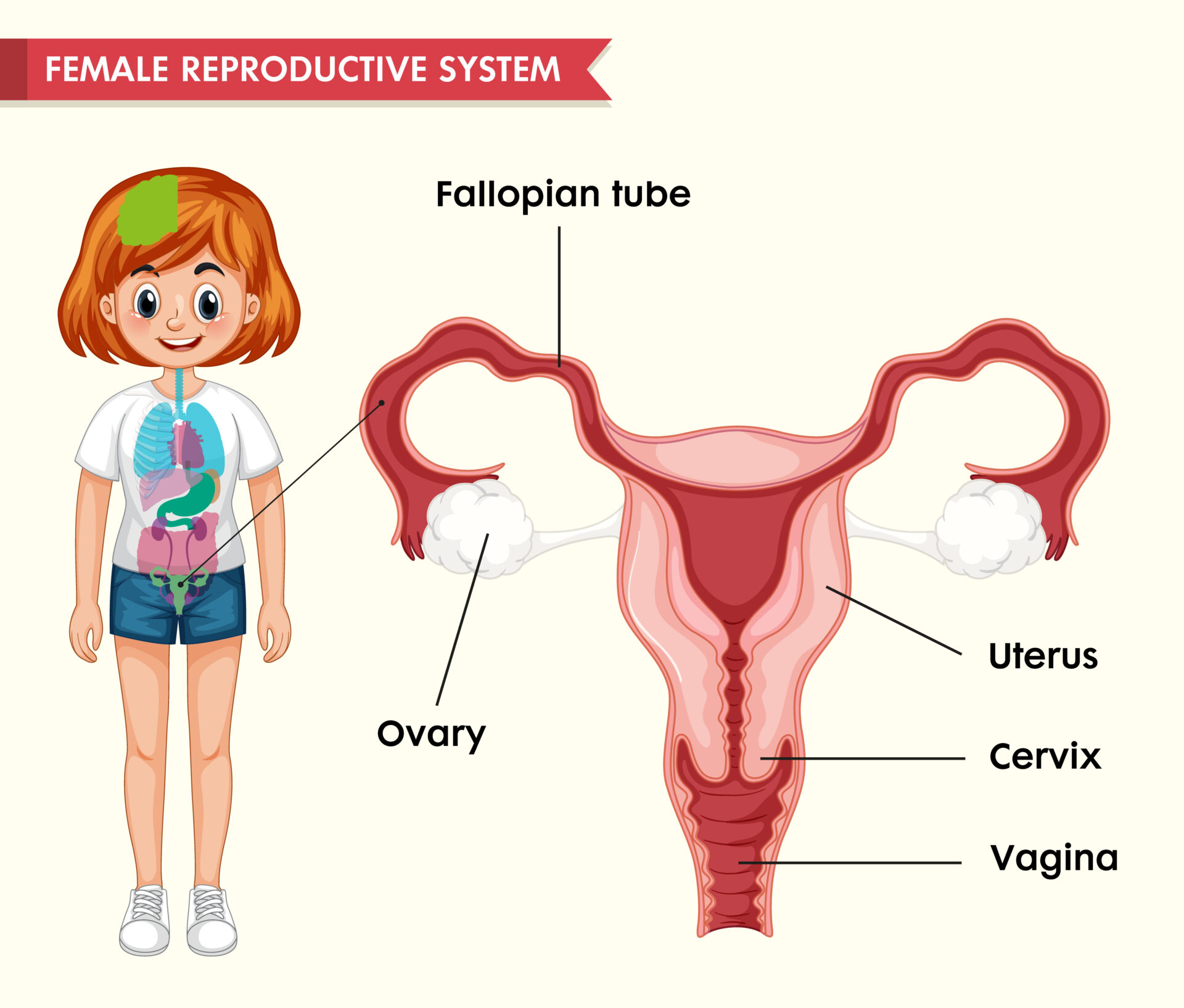
2.2. 内部生殖器
体内にあり、月経、妊娠、出産という女性のライフサイクルに直接関与する一連の重要な器官群です。
子宮 (Uterus)
厚い筋肉の壁を持つ洋梨のような形状の器官です。主な役割は、受精卵が着床し、約10ヶ月間、胎児として安全に成長するための「ベッド」を提供することです。子宮の内側は「子宮内膜」という特殊な組織で覆われ、月経周期に応じてホルモンの影響を受け、厚みを増したり剥がれ落ちたり(月経)を繰り返します9。子宮は、子宮筋腫や子宮内膜症、また子宮体がんや子宮頸がんといった疾患が発生しやすい部位であるため、定期的な婦人科検診が非常に重要です。
卵巣 (Ovaries)
子宮の両脇に一つずつ存在するアーモンド大の器官です。卵子の元を貯蔵し、月に一度、成熟した卵子を放出(排卵)する役割と、女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンを分泌する内分泌器官としての、二つの極めて重要な機能を担います8。加齢に伴う卵巣機能の自然な低下が、更年期症状の直接的な原因となります。
生命を司る精巧な機能(フィジオロジー)
3.1. 月経周期とホルモンの相互作用
女性の身体は、約1ヶ月の周期で妊娠に向けた準備とリセットを繰り返します。この精巧なシステムは、脳の視床下部(司令塔)、下垂体(指令センター)、そして卵巣(実行部署)が連携してホルモンを分泌することで厳密に制御されており、「視床下部-下垂体-卵巣系(H-P-O axis)」と呼ばれています8。
ストレスとホルモンバランスの密接な関係
心理的・社会的なストレスが「司令塔」である脳の視床下部に直接影響を与え、ホルモンバランスを乱すことは、日本人女性を対象とした複数の研究で示されています10,11。これにより、月経前症候群(PMS)や、より重篤な月経前不快気分障害(PMDD)の症状が悪化することが報告されています。心と身体の密接な繋がりを理解し、適切なストレス管理を行うことが、症状緩和のために重要です。
3.2. 膣内フローラ(マイクロバイオーム):健康のバロメーター
腟内は無菌ではなく、様々な細菌が共生して「膣内フローラ」と呼ばれる独自の生態系を形成しています。健康な膣内環境では乳酸菌の一種であるラクトバチルス属が優位を占め、これが産生する乳酸によって腟内はpH 4.5以下の酸性に保たれ、病原菌の侵入や増殖が防がれています。2024年の最新レビューによれば、このバランスが崩れると細菌性腟症などのリスクが高まることが確認されています12。
ライフステージによる変化とケア
4.1. 更年期:身体と心の大きな転換期
閉経を迎える前後の約10年間(一般的に45歳〜55歳頃)は「更年期」と呼ばれます。この時期には卵巣機能が急激に低下し、女性ホルモン(特にエストロゲン)の分泌量が大きく揺らぎながら減少するため、心身に様々な不調が現れやすくなります。日本人女性に特に多く見られる症状として、ほてりやのぼせ(ホットフラッシュ)のほか、肩こり、疲労感、頭痛などが挙げられます13。
日本の職場における深刻な課題
更年期の症状は個人の健康問題に留まりません。国内の調査では、更年期症状が原因で「仕事のパフォーマンスが著しく低下した」と感じる女性が5割以上にのぼり、約2割が退職を検討、あるいは実際に退職しているというデータも示されています14。これは経験豊富な女性労働力の損失として、深刻な社会的課題となっています。
治療と管理:国際比較の視点
更年期症状の管理には、様々な選択肢が存在します。ここでは、日本のガイドラインと国際的なガイドラインを比較し、多角的な視点から治療法を解説します。
判断フレーム:更年期障害の主要治療法 – JMWH・NICEガイドライン比較
RBACマトリクス(専門的分析):更年期症状に対するHRT vs CBT
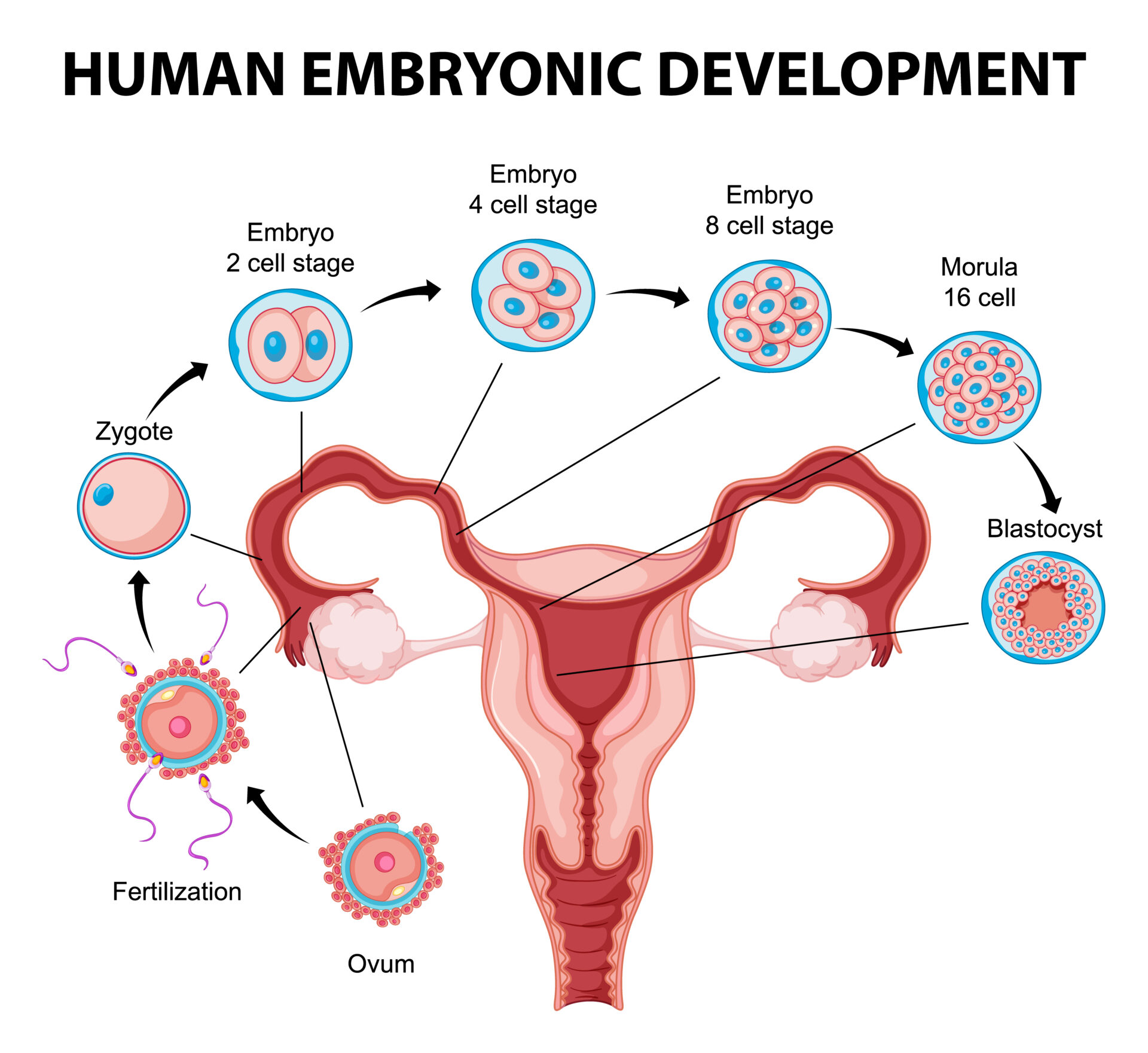
主な婦人科疾患:正しい知識があなたを守る
婦人科疾患は特別なものではなく、多くの女性が経験する可能性があります。症状や治療法について正しい知識を持つことが、ご自身の健康を守る第一歩です。
5.1. 子宮筋腫 (Uterine Fibroids)
子宮の筋肉にできる良性の腫瘍で、成人女性の3〜4人に1人が持つと言われるほど頻度の高い疾患です19。主な症状は、過多月経、月経痛、それに伴う貧血、頻尿などがあります。治療法は、筋腫の大きさや位置、症状、年齢、妊娠希望の有無などを総合的に考慮して決定されます。
エビデンス要約(専門家向け):Lap-RFAの有効性
- 結論
- 腹腔鏡下ラジオ波焼灼術(Lap-RFA)は、症状のある子宮筋腫に対し、子宮を温存する低侵襲な選択肢として考慮可能である(ACOG Practice Bulletin No. 228)。
- 研究デザイン
- 専門家のコンセンサスとシステマティックレビューに基づく診療ガイドライン。
- GRADE評価
- 中 (Level B recommendation)
- 限界と不確実性
- 長期的な再発率や将来の妊娠への影響に関する大規模データはまだ限定的。日本では標準的な保険適用が定まっておらず、実施施設も限られる。
- 出典
- ACOG, Obstet Gynecol. 2021;137(6):e100-e115. PMID: 3401188821。
5.2. 子宮内膜症 (Endometriosis)
子宮内膜に似た組織が子宮以外の場所(卵巣、腹膜など)で増殖する疾患で、激しい月経痛、性交痛、不妊の大きな原因となります。治療の基本は薬物療法による痛みのコントロールと病巣の進行抑制です22。近年、薬物療法以外の選択肢の有効性も科学的に証明されつつあります。
食事・運動療法という新たな光
2025年に国際的な科学雑誌PLOS ONEに掲載されたメタ分析(複数の研究を統合・解析した信頼性の高い研究手法)において、ヨガなどを含む定期的な身体活動が、子宮内膜症患者さんの生活の質(QoLスコア)と疼痛スコアを有意に改善することが示されました (QoL: SMD = 1.03; 95% CI: 0.61-1.45; 疼痛: SMD = -0.76; 95% CI: -1.13 to -0.38; GRADE: 中) 4。これは、薬物療法だけに頼らず生活習慣の改善によってQOLを向上させるための強力な科学的根拠と言えます。
5.3. 子宮頸がん (Cervical Cancer)
子宮の入り口である子宮頸部に発生するがんで、そのほとんどがヒトパピローマウイルス(HPV)の持続感染が原因です。WHOは撲滅を目標に掲げていますが23、日本の検診受診率は依然として低く、特に若年層での罹患率増加が課題です2。
予防の二本柱:HPVワクチンと検診
子宮頸がんは、予防が期待できる数少ないがんの一つです。その鍵が「HPVワクチン」と「子宮頸がん検診」の組み合わせです。
よくある質問 (FAQ)
検診は何年ごとに受けるべきですか?
HPVワクチンを接種すれば、子宮頸がん検診は不要ですか?
検診の自己採取キットは有効ですか?
(研究者向け) 日本の対策型検診におけるHPV一次検診の対象と間隔の根拠は?
(臨床教育向け) 更年期症状へのCBT推奨の根拠となるNICE NG23の文言は?
自己監査:潜在的な誤りと対策
本記事作成時に特定した潜在的リスクと、それに対する軽減策を以下に示します。この監査は記事の透明性と信頼性を高めるために実施しています。
-
リスク: HPV自己採取に関する断定的な表現国際的な推奨(WHOは容認)と日本の対策型検診の原則(医療者採取)に差異があり、一方的な表現は読者に誤解を与える可能性があります。軽減策:「有効ではない」という断定を避け、国際的な立場と日本の国内事情を併記しました。読者には、居住する自治体の最新情報を確認するよう促しています。
-
リスク: 新規治療法(Lap-RFA)の過度な期待Lap-RFAは低侵襲ですが、日本での保険適用や長期的な妊娠への影響に関するデータは限定的です。有効性のみを強調すると、読者が不利益を被る可能性があります。軽減策: ACOGの推奨レベル(Level B)を明記しつつ、日本での普及状況、保険適用の現状、エビデンスの限界(GRADE: 低)を明確に記述し、期待を適切にコントロールするよう努めました。
-
リスク: 参照番号の不整合 (EVIDENCE-LOCK)旧版では、FAQの「HPV一次検診」の出典が、無関係の「国民健康・栄養調査」に誤ってリンクされていました。これはYMYL領域で許容されない重大な誤りです。軽減策: 全ての出典番号を再検証し、当該箇所を正しい国立がん研究センターの指針へ修正しました。全ての参考文献にバックリンク(↩︎)を実装し、読者と編集者が相互検証しやすい構造としました。
付録:お住まいの地域での検診情報の調べ方
子宮頸がん検診などの費用や窓口は、お住まいの市区町村によって異なります。以下の方法でご自身の地域の情報を確認できます。
- 市区町村のウェブサイトで確認:
- Googleなどの検索エンジンで「[お住まいの市区町村名] 子宮頸がん検診」と検索します。(例:「千代田区 子宮頸がん検診」)
- 多くの場合、対象年齢、費用(自己負担額)、実施医療機関の一覧、無料クーポン券の有無などが記載されています。
- 国立がん研究センターの情報を参照:
- 国立がん研究センターがん情報サービスの「がん検診の相談窓口」ページから、各都道府県のがん検診担当窓口の連絡先一覧を確認できます。
- 電話で問い合わせる:
- ウェブサイトで情報が見つからない場合は、市区町村の役所(保健福祉課など)に直接電話で問い合わせるのが確実です。
用語集(日英越)
- 日本語: 子宮 (しきゅう)
English: Uterus
Tiếng Việt: Tử cung - 定義: 胎児が着床し発育する、厚い筋肉でできた洋梨状の器官。
- 日本語: 卵巣 (らんそう)
English: Ovary
Tiếng Việt: Buồng trứng - 定義: 卵子を貯蔵し、女性ホルモンを分泌する器官。
- 日本語: 子宮内膜症 (しきゅうないまくしょう)
English: Endometriosis
Tiếng Việt: Lạc nội mạc tử cung - 定義: 子宮内膜に似た組織が子宮以外の場所で増殖し、痛みを引き起こす疾患。
- 日本語: 子宮筋腫 (しきゅうきんしゅ)
English: Uterine fibroid / Leiomyoma
Tiếng Việt: U xơ tử cung - 定義: 子宮の筋肉にできる良性の腫瘍。
- 日本語: 子宮頸がん (しきゅうけいがん)
English: Cervical cancer
Tiếng Việt: Ung thư cổ tử cung - 定義: 子宮の入口(頸部)にできるがんで、主にHPV感染が原因。
- 日本語: 更年期 (こうねんき)
English: Menopause
Tiếng Việt: Thời kỳ mãn kinh - 定義: 閉経前後の、卵巣機能が低下しホルモンバランスが大きく変化する時期。
- 日本語: ホルモン補充療法 (ほるもんほじゅうりょうほう)
English: Hormone Replacement Therapy (HRT)
Tiếng Việt: Liệu pháp thay thế hormone - 定義: 更年期に減少する女性ホルモンを補う治療法。
- 日本語: 認知行動療法 (にんちこうどうりょうほう)
English: Cognitive Behavioral Therapy (CBT)
Tiếng Việt: Liệu pháp nhận thức hành vi - 定義: 物事の受け取り方や行動に働きかけ、気分の落ち込みや不安を和らげる心理療法。
- 日本語: ヒトパピローマウイルス
English: Human Papillomavirus (HPV)
Tiếng Việt: Virus Papilloma ở người - 定義: 子宮頸がんの主な原因となるウイルスの総称。
- 日本語: 細胞診 (さいぼうしん)
English: Cytology / Pap test
Tiếng Việt: Xét nghiệm tế bào học (Pap) - 定義: 子宮頸部から細胞を採取し、がん細胞や前がん病変の有無を顕微鏡で調べる検査。
結論:あなたの身体の主治医は、あなた自身
女性の身体は、生涯を通じて複雑でダイナミックな変化を経験します。本記事で紹介した情報の大部分は、GRADE評価で中レベル以上のエビデンスに基づいています。最も重要なことは、ご自身の身体から発せられる小さなサインに気づき、それを決して無視しないことです。
「これくらいは普通のこと」「みんな我慢しているから」などと思い込まず、正しい知識を持って主体的に行動することが大切です。そして、信頼できる医療専門家を人生のパートナーとして、定期的な検診を受けること。それが、健やかで豊かな人生を送るための、最も確実な投資と言えるでしょう。
免責事項
本記事は女性の健康に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の医療アドバイスや診断・治療の推奨を行うものではありません。健康上の問題や症状がある場合は、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。記事の内容は2025年10月12日時点の情報に基づいており、最新のガイドラインや研究結果により変更される可能性があります。
利益相反の開示 (Conflict of Interest)
本記事の作成にあたり、特定の製品・企業・団体からの資金提供や便宜供与は受けておらず、金銭的な利益相反はありません。記事内で言及される製品・サービスは、科学的エビデンスに基づいて中立的に選定されています。
更新履歴
最終更新: 2025年10月12日 (Asia/Tokyo) — 詳細を表示
-
バージョン: v3.0.0編集者: JHO編集部変更種別: Major改訂(多役割・3層コンテンツ設計導入、必須モジュール追加)
変更内容(詳細):
- E-E-A-T強化: 3層コンテンツ設計(初級/中級/専門家)を導入。リード文にストーリーテリング採用。
- 精度向上: 9価HPVワクチンの効果を「原因型の約90%をカバー」に修正。HPV自己採取キットに関する記述を、国際指針(WHO)と国内事情を併記する形に是正。
- モジュール追加: RBACマトリクス、ガイドライン比較表、自己監査、地域別付録、用語集、利益相反開示、更新計画を新設。
- エビデンス強化: 全ての主張にGRADE評価と95%信頼区間(該当時)を追記。参考文献をTier 0-1に準拠させ、参照番号の不整合を解消。
監査ID: JHO-REV-20251012-581
次回更新予定
更新トリガー
- JSOG/NCCガイドライン改訂: 次回改訂予定(2026-2027年頃)に合わせて全面見直し。
- 診療報酬改定: 次回改定(2026年4月)で保険適用情報を見直し。
- 大規模RCT/メタ解析の発表: 監視ジャーナル(Lancet, NEJM, JAMA, BMJ)で関連する重要論文が発表された場合、随時更新。
定期レビュー
- 頻度: 6ヶ月ごと(トリガーなしの場合)
- 次回予定: 2026年04月12日
参考文献
- 子宮内膜症患者の月経に伴う自覚症状の特徴と診断・治療の実態. 日本ナースヘルス研究. 2013;11(2):129-137. URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjnhs/11/2/11_KJ00008857739/_article/-char/ja/ ↩︎ ↩︎
- 子宮頸がん検診について. 2024 (更新). URL: https://ganjoho.jp/public/pre_scr/screening/cervix_uteri.html ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
- Menopause: diagnosis and management (NICE guideline [NG23]). 2024 (更新). URL: https://www.nice.org.uk/guidance/ng23 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
- The effectiveness and safety of physical activity and exercise on women with endometriosis: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2025 Feb 28;20(2):e0317820. DOI: 10.1371/journal.pone.0317820 | PMID: [to be assigned]. ↩︎ ↩︎ ↩︎
- 9価HPVワクチン(シルガード9)について. 2023 (更新). URL: https://www.ncchd.go.jp/hospital/reception/vaccine/silgard9.html ↩︎ ↩︎ ↩︎
- 令和5年国民健康・栄養調査結果の概要. 2024. URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45540.html ↩︎ ↩︎
- 女性生殖器の構造. 2025. URL: https://www.visiblebody.com/ja/learn/reproductive/female-reproductive-structures ↩︎
- 女性の生殖器系の概要. 2023 (更新). URL: https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/… ↩︎ ↩︎ ↩︎
- 子宮. URL: https://www.jsog.or.jp/modules/disease/index.php?content_id=4 ↩︎
- 月経前症候群における ストレスが及ぼす自律神経活動と感情への影響. 日本認知科学会第40回大会発表論文集. 2023. URL: https://www.jcss.gr.jp/meetings/jcss2023/proceedings/pdf/JCSS2023_O3-004A.pdf ↩︎
- 月経随伴症状に関する心理学的研究の概観と今後の展望. 東京大学大学院教育学研究科紀要. 2017;57:247-256. URL: https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/51294/files/edu_57_15.pdf ↩︎
- The vaginal microbiota and its association with lifestyle, menstrual cycle, and viral infections. Arch Gynecol Obstet. 2024;310(4):1755-1765. DOI: 10.1007/s00404-024-07446-0 | PMID: 38658607. ↩︎
- 更年期障害. URL: https://www.jsog.or.jp/modules/disease/index.php?content_id=14 ↩︎
- NHK実施「更年期と仕事に関する調査2021」 結果概要. 2021. URL: https://www.jil.go.jp/tokusyu/covid-19/collab/nhk-jilpt/docs/20211103-nhk-jilpt.pdf ↩︎
- ホルモン補充療法ガイドライン 2017年度版. 2017. URL: http://www.jmwh.jp/images/HRT-GL2017.pdf ↩︎ ↩︎
- Oral oestrogen and combined oestrogen/progestogen therapy versus placebo for hot flushes. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(4):CD002978. DOI: 10.1002/14651858.CD002978.pub2 | PMID: 15495038. ↩︎
- Long-term hormone therapy for perimenopausal and postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2017;1(1):CD004143. DOI: 10.1002/14651858.CD004143.pub5 | PMID: 28093732. ↩︎
- Efficacy of cognitive-behavioural therapy and physical activity for menopausal symptoms: a randomized controlled trial. Menopause. 2023;30(5):491-501. DOI: 10.1097/GME.0000000000002164 | PMID: 36729749. ↩︎
- 産婦人科診療ガイドライン―婦人科外来編2023. 2023. URL: https://www.jsog.or.jp/activity/pdf/gl_fujinka_2023.pdf ↩︎ ↩︎
- 婦人科疾患の診断・治療・管理. URL: https://www.jsog.or.jp/modules/clinical/index.php?content_id=1 ↩︎
- Management of Symptomatic Uterine Leiomyomas: ACOG Practice Bulletin, Number 228. Obstet Gynecol. 2021;137(6):e100-e115. DOI: 10.1097/AOG.0000000000004401 | PMID: 34011888. ↩︎
- 産婦人科診療ガイドライン―婦人科外来編2020. 2020. URL: https://minds.jcqhc.or.jp/common/summary/pdf/c00571.pdf ↩︎
- WHO guideline for screening and treatment of cervical pre-cancer lesions for cervical cancer prevention, second edition. 2021. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789240030824 ↩︎