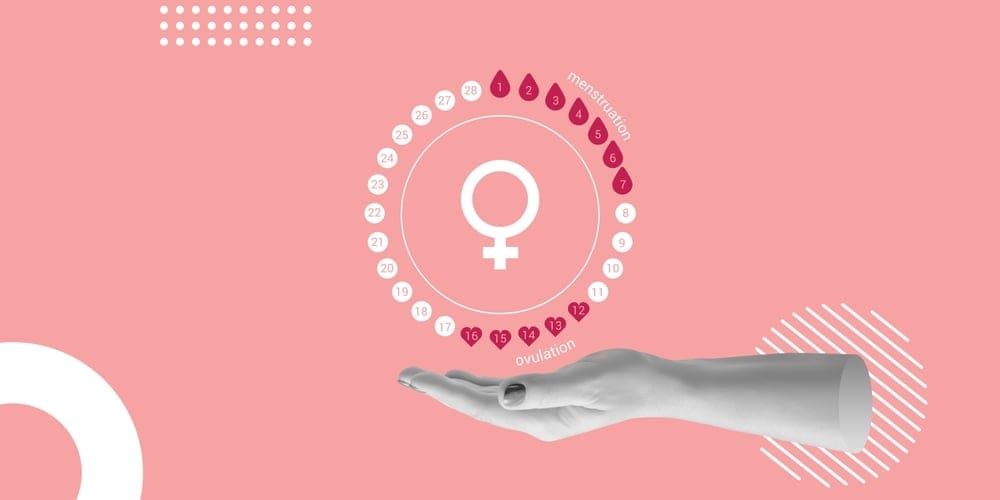この記事の科学的根拠
この記事は、下記に示す最高品質の医学的根拠にのみ基づいて作成されています。本文中の推奨事項は、すべてこれらの出典元の指針や研究結果に依拠するものです。
- 世界保健機関(WHO): この記事における避妊法の有効性(一般的な使用における失敗率)に関する記述は、世界保健機関(WHO)が公表した大規模なデータに基づいています927。
- 日本産科婦人科学会(JSOG): 緊急避妊薬の服用方法、効果、そして服用後のフォローアップに関する指針は、日本産科婦人科学会が定める「緊急避妊法の適正使用に関する指針」に準拠しています23。
- 大阪大学の研究: 日本の職場におけるストレスと月経不順の関連性についての分析は、大阪大学の研究チームが発表した論文データを基にしています15。
- 米国産科婦人科学会(ACOG): 妊娠可能期間(Fertile Window)の定義や、月経周期を健康の指標と見なす考え方は、米国産科婦人科学会(ACOG)の見解を参考にしています828。
要点まとめ
- 生理予定日3日前の性行為で妊娠する可能性は低いですが、ゼロではありません。排卵日がストレスや体調によってずれる可能性があるためです1。
- 妊娠の可能性は、「精子の生存期間(最大5日間)」、「卵子の寿命(約12~24時間)」、そして「排卵日の予測不可能性」という3つの生物学的要因によって決まります36。
- 特に日本の女性は、職場での高いストレスが月経不順のリスクを高めるという研究結果があり、カレンダー通りの予測が難しい場合があります15。
- 万が一、妊娠の不安がある場合は、72時間以内に緊急避妊薬(アフターピル)を服用することが有効な選択肢となります。日本では医師の診察が必要です23。
- 将来の安心のためには、失敗率の高い「リズム法」や「膣外射精」に頼るのではなく、低用量ピルやIUD(子宮内避妊具)など、より確実な避妊法について産婦人科医に相談することが推奨されます9。
生理直前の妊娠不安対策
「生理予定日直前の性行為なら安全なはず」と思っていたのに、あとから妊娠の可能性が頭をよぎり、不安で眠れない…そんなお気持ちになっていませんか。カレンダーアプリの表示と実際の体の反応が違うかもしれない、と気づいた瞬間、急に自分の体が信じられなくなることもあります。この記事で紹介されているように、排卵はストレスや体調でずれることがあり、「絶対安全」とは言い切れないからこそ、そのモヤモヤはとても自然な反応です。一人で自分を責めるのではなく、「不確実さ」とどう付き合うかを一緒に整理していきましょう。
まず大切なのは、「生理予定日数日前=安全日」という思い込みを手放し、精子の寿命や卵子の生存時間、そして排卵日のブレといった基本的な仕組みを冷静に理解することです。本記事が示すように、精子は最長5日程度生きる一方で、排卵はストレス社会の日本では特にずれやすく、予定日直前でも理論上妊娠は起こり得ます。性的な健康全体の中で今回の不安を位置づけ直したいときは、性教育から避妊、性感染症、妊娠、LGBTQ+までを体系的に整理した性的健康 完全ガイド|性教育・避妊・性感染症・妊娠・性機能障害・LGBTQ+もあわせて読んでみると、全体像が掴みやすくなります。
妊娠の可能性がゼロと言い切れない背景には、「精子は数日間生きる」「卵子の寿命はごく短い」「排卵日は毎周期少しずつずれる」という3つの不確実性があります。この記事でも解説されているように、膣外射精や「浅い性交」だから安全というわけではなく、腟内に射精がなくても粘液中の精子が子宮頸管から子宮・卵管へ到達し得ます。この点をより具体的なケースで知りたい場合は、膣外射精や軽い性行為でも妊娠が起こり得る仕組みとリスク、そして現実的な避妊の選び方まで詳しくまとめた膣外射精(外出し)や浅い性交で妊娠する?確率とリスク、正しい避妊法を産婦人科医が徹底解説が参考になります。
「今回は大丈夫だったのか」をできるだけ早く判断したいとき、この記事が紹介するように、性行為から72時間以内であれば緊急避妊薬(アフターピル)という選択肢があります。排卵前であれば排卵そのものを遅らせることで妊娠リスクを下げられる一方、すでに妊娠が成立している場合には効果がないことも理解しておきましょう。日本では必ず医師の診察と処方が必要で、オンライン診療を含め入手ルートや費用にも幅があります。こうした「緊急対応」の全体像を整理したいときは、アフターピルの種類・値段・副作用・安全な入手方法までを網羅的にまとめた緊急避妊の全て:アフターピルの種類、値段、安全な入手方法から副作用まで徹底解説を合わせて確認すると、次の一歩が決めやすくなります。
一度「生理直前だけど大丈夫かな?」と不安を経験すると、毎月同じ思いをしたくないと感じる方が多いはずです。この記事が指摘するように、リズム法や「なんとなく安全日」という感覚に頼るのではなく、日常的に確実性の高い避妊法を取り入れることで、そもそもの不安を大きく減らすことができます。たとえば、低用量ピルは排卵そのものをコントロールし、アフターピルは「もしものとき」のバックアップとして位置づけることが可能です。両者の効果・副作用・費用・入手経路などを具体的に比較した情報は、低用量ピル・アフターピル徹底比較:効果・副作用・費用(保険適用/自費)と日本での全入手方法【2025年最新】で詳しく整理されています。
一方で、「薬に頼らない避妊」を選びたくなる気持ちも自然ですが、この記事が示すWHOのデータのように、リズム法や膣外射精は現実の使われ方では決して失敗率が低くありません。「安全日」や「外出しだから平気」というメッセージだけが一人歩きすると、今回のような不安が繰り返されてしまいます。コンドームの限界も含め、日本で選べる避妊法の全体像とそれぞれの長所・短所を客観的に知っておくことは、パートナーとの話し合いにも大きな助けになります。そのためには、コンドーム・ピル・IUD・緊急避妊までを俯瞰して解説した日本の避妊完全ガイド:コンドームの限界、ピル・IUDの真実から緊急避妊まで徹底解説も役立つでしょう。
今回の不安は、「自分の体や避妊について、もっと知っておきたかった」という気づきでもあります。生理予定日直前の性行為が「絶対安全」ではないことを正しく理解しつつ、緊急避妊という選択肢や、今後のためのより確実な避妊法を知ることで、同じ不安を少しずつ減らしていくことができます。完璧である必要はありませんが、「なんとなく大丈夫だろう」から一歩進んで、自分の心と体を守る選択を少しずつ積み重ねていきましょう。
結論から先に:なぜ「絶対安全」ではないのか?
多くの方が最も知りたい点からお伝えします。結論として、生理予定日3日前の性行為で妊娠する可能性は低いものの、決してゼロではありません1。このわずかながら存在する可能性が、多くの方の不安の種となっています。では、なぜ「絶対」と言い切れないのでしょうか。その理由は、女性の体がいかに繊細で、予測通りにはいかないことがあるか、という点に集約されます。
医学的な最大の根拠は、「排卵のタイミングは、ご自身の体調やストレスなど、様々な要因で変動することがあるため」です2。カレンダーアプリや過去の周期から「この日あたりが排卵日のはず」と予測していても、その月の仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、睡眠不足といった要因が、ホルモンバランスに影響を与え、排卵が数日遅れることは決して珍しいことではないのです。この「排卵のずれ」こそが、「安全日」という概念を不確かなものにする核心的な理由です。
妊娠の可能性を左右する「不確実性の3つの柱」
妊娠が成立するかどうかは、単純な日付計算ではなく、3つの生命の法則に基づいています。この3つを理解することが、誤解を解く第一歩です。
- 精子の生存能力: 性行為によって女性の体内に射精された精子は、子宮頸管粘液などに保護され、最大で5日間も生存し、受精能力を保つことができます34。つまり、性行為から5日後に排卵が起こったとしても、体内で待機していた精子によって受精する可能性があるのです。
- 卵子の限られた寿命: 一方、排卵された後の卵子が受精できる時間は非常に短く、わずか12時間から24時間程度です6。この短い時間内に精子と出会わなければ、卵子は受精能力を失います。
- 排卵日の予測不可能性: これが最も重要な要素です。前述の通り、排卵日は固定されていません。たとえ毎月順調に来ている人でも、ある月の排卵日が数日ずれることは十分に起こり得ます1。生理予定日3日前に性行為があったとしても、もしその周期の排卵が大幅に遅れ、性行為の4日後(つまり生理予定日の翌日)に排卵が起きた場合、体内で生存していた精子がその卵子と受精する条件が整ってしまうのです。
この3つの要素が組み合わさることで、「計算上の安全日」が、実際には妊娠可能な「危険日」に変わりうるという現実が生まれます。これが、専門家が「安全日」という言葉を使わず、「妊娠の可能性が低い時期」と表現する理由です。
妊娠の科学:本当の「妊娠可能期間」を理解する
「安全日」という考え方から一歩進んで、医学的に正確な「妊娠可能期間(Fertile Window)」について理解を深めましょう。これは、あなた自身の体を守り、将来の計画を立てる上で非常に重要な知識です。
生命のタイムライン:精子と卵子の旅
妊娠に至るプロセスは、精子と卵子、二つの細胞の壮大な旅です。
- 精子の旅: 射精された数億個の精子のうち、ごく一部の精鋭だけが子宮頸管を通り抜け、子宮、そして卵管へとたどり着きます4。この過酷な道のりを生き延びた精子は、卵管の中で卵子が来るのを待ち構えます。その待機可能時間が、前述の通り最大5日間です3。
- 卵子の旅: 月に一度、卵巣から成熟した一つの卵子が腹腔内に放出されます。これが排卵です。卵子は卵管采に捉えられて卵管内へと進み、そこで精子との出会いを待ちます。しかし、その受精可能な時間はわずか12~24時間しかありません6。
これらの時間差を考慮すると、米国産科婦人科学会(ACOG)などが定義する「妊娠可能期間」とは、排卵日の5日前から排卵日当日までのおよそ6日間となります812。妊娠はこの期間内の性行為によってのみ成立するのです。
「教科書通り」の28日周期と現実のギャップ
多くの方が学校で習うのは、月経開始日を1日目とし、14日目に排卵が起こるという「28日周期モデル」です。この理想的なモデルでは、妊娠可能期間は9日目から14日目にあたります。これは基礎を理解する上で役立ちます。
しかし、これはあくまで理想化されたモデルです。ジョンズ・ホプキンス大学医学部などの専門機関が示すように、正常な月経周期は21日から35日の範囲と広く、多くの女性がこの範囲に当てはまります12。さらに重要なのは、同じ人物であっても、月ごとの周期の長さは変動しうるという事実です14。周期が35日だった翌月に、25日になることもあります。この変動性が、「計算」だけに頼ることの危険性を物語っています。
表1:妊娠に関わる重要な期間
| 要素 | 生存・持続期間 | 情報源 |
|---|---|---|
| 女性の体内での精子 | 最大5日間 | Mayo Clinic11, Johns Hopkins Medicine12 |
| 排卵後の卵子 | 12~24時間 | Mayo Clinic6, BabyCenter7 |
| 結果としての妊娠可能期間 | 約6日間 | ACOG8, Johns Hopkins Medicine12 |
決定的な要因:あなたの月経周期が予測不能な理由(特に日本において)
なぜ、これほどまでに月経周期は変動するのでしょうか。その答えは、私たちの心と体が密接に連携していることにあります。特に、現代の日本社会に特有の要因が、この予測不可能性をさらに高めている可能性があります。
ストレスとホルモンの関係:日本の現実
毎日のお仕事や人間関係でストレスを感じることは、決して珍しいことではありません。そして、そのストレスがあなたの月経周期に直接影響を与えている可能性があるのです。これは単なる感覚的な話ではなく、科学的なデータによって裏付けられています。
大阪大学の研究チームによる注目すべき報告があります。日本の女性従業員を対象としたこの研究では、職場での心理的・身体的ストレスが高いグループは、ストレスが低いグループに比べて月経不順の発生リスクが2.2倍も高いことが明らかにされました15。これは、日本の労働環境が女性のホルモンバランスに具体的な影響を及ぼしていることを示す強力な証拠です。実際に、国の調査でも、特に30代から50代の女性は男性よりも高いストレスレベルを報告している傾向があります17。
では、なぜストレスが月経周期を乱すのでしょうか。その仕組みは、脳の視床下部から始まります。強いストレスを感じると、体は「HPA軸」と呼ばれるストレス応答システムを活性化させます。このHPA軸の活動が過剰になると、月経周期をコントロールする「HPO軸」(視床下部-下垂体-卵巣系)の正常な働きを妨げてしまうのです2。具体的には、排卵に不可欠な黄体形成ホルモン(LH)や卵胞刺激ホルモン(FSH)の分泌が抑制されたり、タイミングがずれたりします。その結果、排卵が遅延し、妊娠可能期間が予期せぬ時期に移動してしまうのです。
カレンダーアプリと「リズム法」の落とし穴
現在、多くの方が月経周期の管理にスマートフォンアプリを利用しています。これらのアプリは非常に便利ですが、その限界を理解しておくことが重要です。ほとんどのアプリは、過去の周期データの平均値を基に未来の排卵日を予測する、いわば現代版の「リズム法(荻野式)」です1。これらの方法は、周期が毎月ほぼ一定であることを前提としています。
しかし、前述の通り、その月の予期せぬストレスによって排卵が遅れた場合、アプリはそれを予測できません。アプリは過去のデータしか見ておらず、「今月、あなたが大きなストレスを抱えている」という事実を知る術はないのです。これが、アプリの予測だけに頼ることの危険性です。
世界保健機関(WHO)のデータは、この点を明確に示しています。カレンダー(リズム法)に基づく避妊法の「一般的な使用」における年間失敗率(妊娠率)は12~15%にも上ります。また、多くの人が頼りがちな膣外射精に至っては、失敗率は20%です9。これは、5人に1人が1年間のうちに妊娠する計算となり、信頼性の高い避妊法とは到底言えません。この事実は、より確実な方法を検討する必要性を示唆しています。
今すぐできること:不安なあなたが取るべき行動
もし、この記事を読んで「もしかしたら」と不安に感じている方がいらっしゃいましたら、冷静に行動することが大切です。ここでは、日本国内で利用可能な、事実に基づいた具体的な選択肢をご紹介します。これは、非難されるべきことではなく、ご自身の体を守るための正当な医療的選択です。
日本の緊急避妊薬(アフターピル):事実に基づくガイド
緊急避妊薬(Emergency Contraception, EC)は、避妊に失敗した、あるいは避妊なしの性行為後に妊娠を防ぐために使用される医薬品です。日本では「アフターピル」という名称で知られています。
- 作用の仕組み: 日本で標準的に用いられるレボノルゲストレル(LNG)錠の主な作用は、排卵を抑制または遅延させることです23。これにより、精子が卵子と出会う機会をなくします。ここで非常に重要なのは、緊急避妊薬は受精卵の着床を阻害する「堕胎薬」ではないという点です。すでに妊娠が成立している場合には効果がありません。
- 有効性と服用タイミング: 日本産科婦人科学会(JSOG)の指針では、避妊なしの性行為後72時間(3日)以内にLNG 1.5mgを1錠服用することが推奨されています23。服用は早ければ早いほど効果が高まります。公式な承認は72時間以内ですが、120時間後まで一定の効果が期待できるとの報告もあります。ただし、時間経過とともに効果は低下します24。
- 副作用について: 服用後に副作用が現れることがあります。日本の臨床データによれば、主な副作用として悪心(吐き気)、頭痛、不正子宮出血などが報告されていますが、重篤な副作用は稀です23。特に、現在主流のLNG法では、過去の方法に比べて悪心の発現率は3.6%と低いことが示されており、過度な心配は不要です24。
実践ステップ:日本での緊急避妊薬の入手方法
緊急避妊薬は、行動への障壁を低くするため、入手方法を具体的に知っておくことが安心につながります。
- 医師の診察が必須: 日本では、緊急避妊薬は市販されておらず、必ず医師の診察・処方が必要です25。
- 受診先: 産婦人科を受診するのが最も一般的ですが、内科や救急外来など他の診療科でも処方してもらえる場合があります25。近年では、オンライン診療に対応している医療機関も増えており、自宅からでも診察を受け、薬を郵送してもらうことが可能です。
- 問診で聞かれること: 診察では、最終月経日、月経周期、そして問題の性行為があった日時などを質問されます。事前にメモしておくとスムーズです。多くの場合、緊急避妊薬の処方に際して内診が必須となることはありません25。
- 費用: 緊急避妊薬の処方は、病気の治療ではないため健康保険は適用されず、自費診療となります。費用は医療機関によって異なりますが、おおむね10,000円から20,000円程度が目安です26。
服用後と妊娠検査のタイミング
薬を服用した後も、体の変化を注意深く観察することが大切です。
- 消退出血について: 服用後、数日から3週間以内に、月経のような出血(消退出血)が起こることが多いです。JSOGの指針によると、次の月経は予定日の±2日以内に来る場合が80%以上、7日以内に来る場合が95%以上とされています23。ただし、周期がずれることもあります。
- 妊娠検査のタイミング: もし、予定された月経が7日以上遅れる場合や、出血量が普段より著しく少ない場合は、妊娠の可能性を考慮し、市販の妊娠検査薬を使用してください24。また、より確実な結果を得るためには、性行為から3週間後を目安に検査を行うことが推奨されます26。
- 再受診: 処方を受けた医療機関を3週間後くらいに再受診し、確実に避妊が成功したかを確認することが望ましいとされています25。
長期的な計画:安心のための確実な避妊法を選ぶ
緊急避妊はあくまで緊急時の対応です。毎回「大丈夫だろうか」と心配する日々から卒業し、ご自身のライフプランと健康を主体的に管理するために、より信頼性の高い避妊法について考えることは非常に重要です。
「たぶん大丈夫」からの卒業:エビデンスに基づく避妊法の比較
避妊法の選択にあたっては、世界保健機関(WHO)が提唱する「理想的な使用(Perfect Use)」と「一般的な使用(Typical Use)」という二つの指標を知ることが役立ちます9。理想的な使用とは、毎回指示通り完璧に使った場合の失敗率、一般的な使用とは、飲み忘れや使い方の間違いなど、現実世界で起こりうるミスを含めた失敗率を指します。後者の「一般的な使用」における失敗率こそが、私たちが注目すべき現実的な数値です。
表2:避妊法の有効性:「理想的な使用」と「一般的な使用」の比較
| 避妊法 | 一般的な使用での年間妊娠率 | 理想的な使用での年間妊娠率 | 日本の読者へのポイント |
|---|---|---|---|
| 避妊なし | 85% | – | – |
| 膣外射精 | 20% | 4% | 信頼性が低い方法と認識すべきです。 |
| 男性用コンドーム | 13% | 2% | 性感染症予防には有効ですが、避妊の失敗率は比較的高めです。 |
| リズム法/オギノ式 | 12-15% | 5% (SDM) | ストレス等で周期が乱れやすいため推奨されません。 |
| 低用量ピル | 7% | 0.3% | 毎日の服用が必要ですが、正しく使えば非常に効果的です。 |
| IUD (子宮内避妊具) | 0.1 – 0.8% | 0.1 – 0.6% | 一度装着すれば数年間効果が持続し、失敗率は極めて低いです。 |
| 出典: 世界保健機関(WHO)のデータを基に調整9 | |||
この表が示すように、膣外射精やリズム法といった方法の「一般的な使用」における失敗率は驚くほど高く、これらに頼ることは大きな危険性を伴います。一方で、低用量ピルやIUD(子宮内避妊具)は、極めて低い失敗率を誇ります。これらの方法は、毎日の不安から解放され、安心して生活を送るための強力な選択肢となり得ます。
あなたの健康のパートナー:産婦人科での相談
どの避妊法が自分に最も合っているかを知るために、ぜひ一度、産婦人科を受診して専門家と相談することをお勧めします。産婦人科は、問題が起きてから行く場所ではなく、あなたの健康と幸福を長期的にサポートしてくれるパートナーです。米国産科婦人科学会(ACOG)が月経を「第5のバイタルサイン」と位置づけているように、月経や避妊に関する相談は、健康管理の非常に重要な一部です28。医師は、あなたの健康状態、ライフスタイル、そして将来の希望などを総合的に考慮し、最適な選択肢を一緒に考えてくれます27。
よくある質問
生理の直前なら、本当に安全ではないのですか?
はい、安全とは断言できません。可能性は非常に低いですが、稀に排卵が大幅に遅れることがあります。ストレスや体調の変化が原因で、生理予定日間近に排卵が起こり、それより前にあった性行為の精子で受精する理論的な可能性は排除できないためです2。
カレンダーアプリの「妊娠可能性が低い日」という表示は信じられますか?
参考程度に留めるべきです。アプリの予測は過去のデータの平均に基づいているため、その月の突発的な排卵の遅れを予測することはできません1。特にストレスが多いなど、周期が乱れる要因がある場合は、アプリの予測の信頼性はさらに低下します。
緊急避妊薬は体に悪いと聞きましたが、本当ですか?
ピルやIUDは副作用が心配です。
どのような医薬品や医療器具にも利点と欠点があります。低用量ピルには吐き気や頭痛などの初期の副作用や、稀に血栓症のリスクがあります。IUDには装着時の痛みや不正出血の可能性があります。しかし、これらの副作用は全ての人に起こるわけではなく、多くは時間と共に軽快します。最も重要なのは、産婦人科医と十分に相談し、ご自身の健康状態や体質に合った方法を選択することです。医師は、利点と危険性を丁寧に説明し、あなたが安心して決断できるようサポートしてくれます27。
[mwai_chatbot id=”default”]
結論
「生理予定日3日前」の性行為における妊娠の可能性は、医学的に見れば低いですが、ゼロではありません。この不確実性の根源は、女性の月経周期が、特にストレス社会である日本において、予測通りに機能するとは限らないという生物学的な事実にあります。カレンダーアプリや旧来のリズム法に頼ることは、時に意図しない結果を招く危険性をはらんでいます。
この記事を通じて私たちが最も伝えたいことは、正確な知識こそが、あなたを不要な不安から解放し、ご自身の体を主体的にコントロールする力になる、ということです。万が一の際には、緊急避妊薬という安全で有効な選択肢があることを知っておくこと。そして、より長期的には、信頼性の高い避妊法について専門家である産婦人科医に相談し、「たぶん大丈夫」という曖昧な状態から卒業すること。それが、心身ともに健康で、自分らしい人生を歩むための確かな一歩となるでしょう。
免責事項本記事は情報提供を目的としたものであり、専門的な医学的アドバイスに代わるものではありません。健康に関する懸念や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- Rhythm method for natural family planning. Mayo Clinic [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/rhythm-method/about/pac-20390918
- A Systematic Review of The Association Between Adulthood and Psychological Stress on Menstrual Cycle Irregularity. International Journal of Pharmaceutical Sciences [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://www.ijpsjournal.com/article/A+Systematic+Review+of+The+Association+Between+Adulthood+and+Psychological+Stress+on+Menstrual+Cycle+Irregularity++
- How Long do Sperm Live: Sperm Life Cycle & Survival Rate. Natural Cycles [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://www.naturalcycles.com/cyclematters/the-truth-about-sperm-survival-how-long-do-sperm-live
- Sperm transport in the female reproductive tract. Human Reproduction Update. 2006;12(1):23-37. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://academic.oup.com/humupd/article/12/1/23/607817
- Insights into the role of cervical mucus and vaginal pH in unexplained infertility. Medical Express. 2017;4. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://www.scielo.br/j/medical/a/qjRg5mV765Dvs5tYjCtBwyC/
- Ovulation signs: When is conception most likely?. Mayo Clinic [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/expert-answers/ovulation-signs/faq-20058000
- Ovulation calculator: Predict your fertile window. BabyCenter [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://www.babycenter.com/getting-pregnant/ovulation/ovulation-calculator
- Safe Period: How to Time Sex to Prevent Pregnancy. Healthline [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://www.healthline.com/health/womens-health/safe-period
- Mechanisms of action and effectiveness of contraceptive methods. World Health Organization [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/reproductive-health/contraception-family-planning/mechanisms-of-action-and-effectiveness-of-contraception-methods.pdf?sfvrsn=e39a69c2_1
- Sperm transport in the female reproductive tract. Human Reproduction Update [インターネット]. 2006;12(1):23-37. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://academic.oup.com/humupd/article-abstract/12/1/23/607817
- How to get pregnant. Mayo Clinic [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/how-to-get-pregnant/art-20047611
- Calculating Your Monthly Fertility Window. Johns Hopkins Medicine [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/calculating-your-monthly-fertility-window
- Fertility evaluation of infertile women: a committee opinion (2021). American Society for Reproductive Medicine [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/fertility-evaluation-of-infertile-women-a-committee-opinion-2021/
- When Are You Most Likely to Conceive? An Expert Explains ‘Fertile Windows’. Sigourney Health [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://simhcottumwa.org/when-are-you-most-likely-to-conceive-an-expert-explains-fertile-windows/
- 職場での心身のストレス反応は月経不順の発生リスクを高める. 大阪大学 [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2025/20250424_3
- 女性の月経不順リスクに職場の心身ストレスが影響 ストレスチェック活用により女性の健康を支援. 特定健診・特定保健指導.jp [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2025/013874.php
- どんなことに悩みやストレスを感じる?. 生命保険文化センター [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://www.jili.or.jp/lifeplan/rich/9870.html
- 各世代における悩みやストレスの原因の可視化. 法政大学 [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://cdgakkai.ws.hosei.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/10/19-1-05.pdf
- Bloody stressed! A systematic review of the associations between …. PubMed [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38950686/
- HPA axis activity across the menstrual cycle – a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. ResearchGate [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://www.researchgate.net/publication/360681718_HPA_axis_activity_across_the_menstrual_cycle_-_a_systematic_review_and_meta-analysis_of_longitudinal_studies
- Correlation of perceived stress with monthly cyclical changes in the female body. PMC [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10771141/
- Natural Family Planning. AAFP [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2012/1115/p924.html
- 緊急避妊法の適正使用に関する指針. 公益社団法人 日本産科婦人科学会 [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://www.jsog.or.jp/activity/pdf/kinkyuhinin_shishin_H28.pdf
- 緊急避妊法の適正使用に関する指針(令和7年改訂版). 日本産科婦人科学会 [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://www.jsog.or.jp/news/pdf/kinkyuhinin_shishin202504.pdf
- WHO緊急避妊薬の安全性に関するファクトシート. 緊急避妊.jp [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://kinkyuhinin.jp/emergency-contraceptives/
- 緊急避妊について. 日本産婦人科医会 [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://www.jaog.or.jp/qa/youth/jyosei200122/
- Family planning/contraception methods. World Health Organization [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception
- Fertility Awareness-Based Methods for Family Planning and Women’s Health: Impact of an Online Elective. STFM Journals [インターネット]. [2025年6月30日引用]. 入手先: https://journals.stfm.org/familymedicine/2024/july-august/duane-0387/