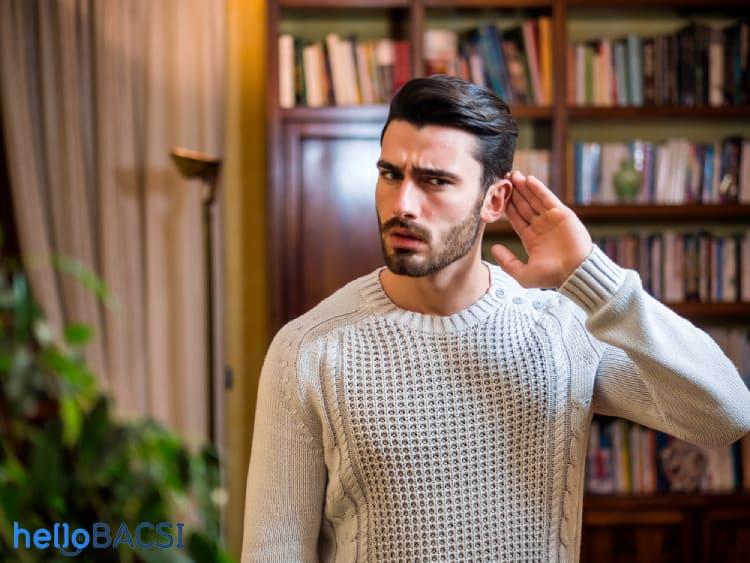医学監修:
菅原 一真(すがはら かずま)医師
山口大学大学院医学系研究科 耳鼻咽喉科学講座 教授
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 専門医・指導医、騒音性難聴担当医、補聴器相談医
専門は中耳手術、人工内耳手術、難聴・感染症の薬物治療、内耳保護機構の研究。若者の聴力低下問題にも深い知見を持つ。
researchmapで詳細を確認する
この記事の科学的根拠
本記事は、引用元として明記された最高品質の医学的根拠にのみ基づいて作成されています。以下は、本記事で提示される医学的指導の根拠となる主要な情報源とその関連性です。
- BMJ Global Health誌のメタアナリシス: 本記事における「世界の若者10億人以上が難聴リスクにある」という問題の深刻性に関する記述は、この大規模なメタアナリシスに基づいています1。
- 世界保健機関(WHO)「世界聴覚報告書」: 安全な音量や時間に関する国際的な推奨事項は、この包括的な報告書を根拠としています2。
- The Lancet Regional Health誌の研究: 「日本の若年層で聴力が低下している」という国内の状況に関する記述は、約16万人の日本人データを分析したこの画期的な研究に基づいています3。
- The Lancet誌の委員会報告: 「難聴が認知症の最大のリスク因子である」という極めて重要な指摘は、認知症予防に関するこの影響力の大きい報告書に基づいています4。
- 厚生労働省「騒音障害防止のためのガイドライン」: 職場における騒音基準など、日本国内の公的な基準に関する解説は、このガイドラインを引用しています5。
要点まとめ
- 世界の若者の半数近く(11億人以上)が、イヤホンの不適切な使用により聴力低下の危険に晒されています12。日本でも40歳以下の若者の聴力悪化が確認されています3。
- イヤホン難聴は、内耳の「有毛細胞」が物理的な音圧で破壊されることで起こります。この細胞は一度壊れると再生しないため、聴力は基本的に元に戻りません6。
- 中年期の難聴は、認知症の予防可能な最大のリスク因子(寄与率8%)であることが、国際的な研究で示されています4。若いうちからの聴力ケアは、将来の認知機能維持に直結します。
- 予防の鍵は「音量と時間」の管理です。WHOは「80デシベル(走行中の電車内程度)の音量で、週40時間以内」を推奨しています7。スマートフォンの音量は60%以下が目安です8。
- 「会話が聞き取りにくい」「耳鳴りが続く」などの症状があれば、放置せずに耳鼻咽喉科を受診することが重要です。早期の対応が、あなたの未来の聴力を守ります。
若者の聴力を守るための重要ガイド
毎日イヤホンを使っていると、「将来、本当に耳が聞こえなくなるのではないか」と不安に感じることはありませんか。一度失った聴力は戻らないという事実は、音楽を楽しむ若者にとって深刻な懸念事項です。
聴力の低下を防ぎ、将来にわたって健やかな「聞こえ」を維持するためには、耳の構造や機能全体を理解することが第一歩です。まずは、耳鼻咽喉科疾患の完全ガイドで、耳の健康に関する基礎知識を確認しておきましょう。
イヤホンによる難聴だけでなく、耳のトラブルは多岐にわたります。年齢を問わず注意すべき耳の病気について知ることで、子供から大人まで気をつけるべき耳の病気を早期に発見し、適切な対策を講じることが可能になります。
聴力低下の初期サインとして最も注意すべきなのが「耳鳴り」です。もし静かな場所で「キーン」という音が聞こえたら、それは耳からのSOSかもしれません。耳鳴りの原因と対策を詳しく知り、症状を放置しないようにしましょう。
また、記事内で触れられている「不適切な耳掃除」も聴力リスクの一つです。自己流のケアで耳を傷つけないよう、安全で正しい耳掃除の方法を実践し、外耳道を健康に保つことが重要です。
イヤホンの長時間使用は、難聴だけでなく外耳炎などの痛みを引き起こすこともあります。もし耳に痛みを感じた場合は、無理に使用を続けず、耳の痛みの原因と対処法を確認し、早めに耳を休ませることが大切です。
未来の自分のために、今の聴力を守る行動を起こしましょう。適切な音量管理と定期的な休息、そして正しい知識が、一生涯続くコミュニケーションの架け橋となります。
第1章:若者の聴力低下、その深刻な実態とは? – 最新データで見る日本の現状
1.1. 「イヤホン世代」が直面する世界的な課題
若者の聴力低下は、もはや個人的な問題ではなく、世界的な公衆衛生上の課題として認識されています。2022年に権威ある医学雑誌『BMJ Global Health』に掲載されたメタアナリシス(複数の研究データを統合・分析した信頼性の高い研究)では、衝撃的な事実が明らかになりました。世界の12歳から34歳までの若者のうち、24%が個人的音響機器(イヤホンやヘッドホン)を危険なレベルの音量で使用しており、実に48%がライブハウスなどの大音量の娯楽施設に頻繁に通っていることが示されたのです1。この結果から、研究者たちは「世界で10億人以上の若者が、回復不能な聴力低下を招く可能性のある危険な聴取習慣を持っている」と結論付けています。これは、将来的に多くの人々がコミュニケーションの困難や生活の質の低下に直面することを示唆しており、世界保健機関(WHO)もこの状況に強い警鐘を鳴らしています2。
1.2. 日本国内の状況:気づかぬうちに進行するリスク
この問題は、決して海外だけの話ではありません。2021年、国立病院機構東京医療センターの研究チームが、国際的な医学雑誌『The Lancet Regional Health – Western Pacific』に、日本人における重要な研究結果を発表しました3。この研究では、約16万人にのぼる日本の労働者の健康診断データを分析したところ、特に40歳以下の若年層において、会話には直接影響しにくい高音域(4000ヘルツ)の聴力が、過去10年間で有意に悪化していることが判明したのです9。この高音域の聴力低下は、騒音性難聴の初期症状の典型であり、イヤホンの長時間使用との関連が強く疑われています。実際に、新潟医療福祉大学が行った調査では、日本の大学生の97%がイヤホンを使用していると回答しており10、この問題がいかに私たちの生活に密着しているかが分かります。この深刻な状況を受け、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会は、ACジャパンと共同で俳優の近藤真彦氏を起用した啓発キャンペーンを開始するなど、社会全体でこの問題に取り組む動きが始まっています11。
第2章:なぜ聞こえにくくなるのか?- 聴力低下を招く2大要因
2.1.【生活習慣編】日常に潜む6つの危険な習慣
若者の聴力低下は、多くの場合、日々の生活習慣にその原因が潜んでいます。科学的根拠に基づき、特に注意すべき6つの習慣を解説します。
- イヤホン・ヘッドホンの大音量・長時間使用(音響性難聴): これが若者の聴力低下における最大の原因です。耳の奥にある蝸牛(かぎゅう)という器官には、音を感じ取るための「有毛細胞」という非常に繊細な細胞が並んでいます。大きな音は、この有毛細胞に物理的な衝撃を与え、傷つけ、やがては破壊してしまいます。重要なのは、この有毛細胞は一度壊れると二度と再生しないということです612。これが、音響性難聴が「予防こそがすべて」と言われる所以です。
- 騒音環境への暴露: ライブハウスやクラブ、パチンコ店、あるいは工事現場などの大きな音に晒されることも、イヤホンと同様に有毛細胞を損傷させます13。ここで一つの基準となるのが、厚生労働省が定める「騒音障害防止のためのガイドライン」です5。このガイドラインでは、職場において85デシベル以上の音環境は健康障害のリスクがあるとされ、事業者に対策を義務付けています。ライブハウスでは100デシベルを超えることも珍しくなく、これは極めて危険なレベルと言えます。
- 喫煙: 喫煙は、全身の血流に悪影響を及ぼします。ニコチンによる血管収縮と、一酸化炭素による血液中の酸素運搬能力の低下は、音を感じ取るために大量の酸素を必要とする繊細な内耳の血流を著しく悪化させ、有毛細胞にダメージを与える可能性があります。
- 過度の飲酒: 大量のアルコールは、内耳の有毛細胞や、音の情報を処理する脳の中枢神経系に対して、直接的な毒性を持つ可能性が指摘されています。
- 不適切な耳掃除: 綿棒などを耳の奥深くまで入れすぎる行為は、外耳道を傷つけたり、耳垢を鼓膜の方へ押し込んでしまったりする危険性があります。耳掃除は、耳の入り口付近を優しく拭う程度で十分とされています。
- ストレス・生活習慣の乱れ: 特に若年の女性に多く見られる「急性低音障害型感音難聴」は、ストレスや疲労、睡眠不足が引き金となることがあります14。これは、内耳のリンパ液の圧力バランスが崩れることで起こると考えられています。
2.2.【医学的要因編】注意すべき病気と身体の状態
生活習慣だけでなく、特定の病気が聴力低下の原因となることもあります。若年層でも発症の可能性がある、注意すべき代表的な疾患を理解しておくことが重要です。
- 突発性難聴: 何の前触れもなく、突然片耳(稀に両耳)が聞こえなくなる病気です。原因はまだ完全には解明されていませんが、ウイルス感染や内耳の血流障害などが考えられています。早期治療が非常に重要です15。
- 中耳炎: 特に、治療が長引いたり、繰り返したりする慢性中耳炎では、炎症が内耳にまで及び、聴力に影響を与えることがあります。
- 聴神経腫瘍: 音の情報を脳に伝える聴神経にできる良性の腫瘍です。通常は片耳の難聴がゆっくりと進行するのが特徴で、耳鳴りやめまいを伴うこともあります。
- メニエール病: 回転性のめまい、耳鳴り、そして変動する聴力低下を繰り返す病気です。内耳のリンパ水腫(水ぶくれ)が原因とされています。
- 全身性の疾患: 糖尿病や高血圧、腎機能障害といった全身の病気は、全身の血管にダメージを与えます。内耳の血管は特に細く繊細なため、これらの病気によって血流が悪化し、聴力低下の間接的な原因となることがあります。
第3章:あなたの耳は大丈夫?- 専門家が教えるセルフチェックリスト
聴力低下はゆっくりと進行するため、自分ではなかなか気づきにくいものです。以下の専門家が推奨するチェックリストを使って、ご自身の「聞こえ」の状態を客観的に評価してみましょう1617。3つ以上当てはまる場合は、一度専門医への相談を検討することをお勧めします。
聴力低下の危険サイン・セルフチェック
- 会話中、相手の言葉を何度も聞き返すことが増えた。
- 家族や友人から「テレビの音量が大きい」と指摘される。
- 電話での会話が聞き取りにくいと感じる。
- 騒がしい場所(レストラン、駅、人混みなど)では、特に会話の内容が分かりにくい。
- 後ろから声をかけられても気づかないことがある。
- 耳鳴り(キーン、ジーといった音)がすることがある。
- 耳が詰まったような感じ(耳閉感)が続くことがある。
- 以前より高い音(電子レンジの音など)が聞こえにくくなった気がする。
- 音楽を聴いていても、歌詞がはっきりと聞き取れないことがある。
- 自分の話し声が大きいと人から言われたことがある。
補足情報: さらに、ウェブ上には簡易的に聴力をチェックできるツールも存在します18。これらは自身の聞こえの状態に関心を持つ良いきっかけになります。ただし、これらのツールはあくまでスクリーニング(ふるい分け)であり、正確な診断を下すものではありません。正確な聴力の状態を知るためには、必ず耳鼻咽喉科で精密な聴力検査を受ける必要があります。
第4章:聴力を守り、未来を変える – 今日からできる予防と対策のすべて
音響性難聴は一度進行すると回復が困難ですが、幸いなことに、正しい知識を持って行動すれば、そのリスクを大幅に減らすことが可能です。今日から実践できる、科学的根拠に基づいた予防策を具体的にご紹介します。
4.1. 基本原則:WHOと専門家が推奨する「音量と時間」のルール
聴力保護の最も重要で基本的な原則は、「どれくらいの音量で、どれくらいの時間聴くか」を管理することです。世界保健機関(WHO)は、国際電気通信連合(ITU)との共同で、安全な聴取のための具体的な基準を推奨しています。それは、「平均音量80デシベルで、1週間の合計聴取時間を40時間以内」に抑えるというルールです7。80デシベルとは、走行中の電車内や騒々しいカフェくらいの音量です。多くのスマートフォンの最大音量は100デシベルを超えるため、音量を常に60%以下に保つことが、この基準を守るための現実的な目安となります8。
さらに、音量と安全な時間の関係を示す「3デシベルルール」を覚えておくと非常に有用です。これは、音量が3デシベル上がるごとに、安全に聴ける時間は半分になるという法則です19。つまり、83デシベルなら週20時間、86デシベルなら週10時間が上限となります。少し音量を上げることが、リスクを急激に高めることを理解しましょう。また、連続して聴き続けることも耳への負担を増やします。「1時間聴いたら10分は耳を休ませる」といった、定期的な休憩を習慣づけることも極めて重要です6。
4.2. 予防策①:イヤホン・ヘッドホンの賢い選び方と使い方
使用する機器の選択や使い方を工夫することで、より安全に音楽などを楽しむことができます。
- ノイズキャンセリング機能の活用: 周囲が騒がしいと、つい音量を上げてしまいがちです。ノイズキャンセリング機能付きのイヤホンやヘッドホンは、周囲の騒音を効果的に打ち消してくれるため、結果として再生音量を上げすぎずに済みます。特に電車やバス、カフェなど、騒がしい環境で音楽を聴くことが多い人には、聴力保護の観点から非常に有効な選択肢です12。
- 遮音性の高いイヤホンの選択: 耳の穴にしっかりフィットするカナル型(耳栓型)のイヤホンは、物理的に外部の音を遮断する効果(パッシブノイズキャンセリング)が高いです。これにより、小さな音量でも音楽に集中しやすくなります。
- スマートフォンの機能活用: 最近のスマートフォンには、聴力を保護するための便利な機能が搭載されています。例えば、iPhoneの「ヘルスケア」アプリでは、ヘッドホンの音量を自動で記録し、一定期間の平均音量がWHOの推奨値を超えると通知してくれたり、大きすぎる音量を自動的に低減してくれたりする機能があります。こうした機能を積極的に活用し、自身の聴取習慣を客観的に把握・管理することが推奨されます。
4.3. 予防策②:聴覚をサポートする栄養と生活習慣
健康な聴覚を維持するためには、耳だけでなく、全身の健康状態を良好に保つことが不可欠です。特に、バランスの取れた食事と質の高い睡眠は、内耳の健康を支える上で重要な役割を果たします。
- 聴覚をサポートする栄養素: 内耳の血流や神経機能を正常に保つために役立つとされる栄養素があります。例えば、神経の機能を維持するビタミンB群(特にビタミンB12)、有毛細胞の代謝に関わる亜鉛、神経の興奮を抑える働きのあるマグネシウムなどが挙げられます20。これらの栄養素は、豚肉、レバー、魚介類、ナッツ、緑黄色野菜などに多く含まれています。ただし、最も重要な注意点として、これらの栄養素を特定のサプリメントで摂取すれば難聴が治るわけではありません。あくまで健康な聴覚機能を維持するための補助的な役割であり、基本は様々な食材から栄養を摂る、バランスの取れた食事です。
- 十分な睡眠とストレス管理: 睡眠不足や過度のストレスは、自律神経の乱れや血流の悪化を引き起こし、内耳に悪影響を与える可能性があります。質の高い睡眠を十分にとることは、日中のダメージから有毛細胞が回復するのを助けると考えられています。自分なりのリラックス法を見つけ、心身の健康を保つことも、大切な聴力を守ることに繋がります。
4.4. 急性期の対応:もし急に聞こえにくくなったら?
突発性難聴のように、ある日突然、耳が聞こえにくくなることがあります。このような急性期の聴力低下は、時間との勝負です。一般的に、「治療のゴールデンタイムは発症から1週間以内、遅くとも2週間以内」と言われています15。主な治療法としてステロイド剤の内服や点滴が行われ、早期に治療を開始することで、聴力が回復する可能性が高まります。「少し様子を見よう」と自己判断せず、「おかしい」と感じたら、その日のうちにでも直ちに耳鼻咽喉科を受診してください。迅速な行動が、あなたの聴力の運命を分ける可能性があるのです。
第5章:【重要】難聴と認知症 – 日本の未来に関わる深刻な関係
この章では、本記事で最もお伝えしたい重要な事実、すなわち「難聴と認知症」の深刻な関係について解説します。これは、超高齢社会を迎えた日本に住む私たち全員にとって、決して無視できない問題です。
2020年、世界で最も権威ある医学雑誌の一つである『The Lancet』の国際委員会が、認知症に関する画期的な報告を発表しました4。この報告では、認知症の全症例のうち約40%は、生活習慣の改善などによって予防が可能である12のリスク因子によって引き起こされると結論付けました。そして、その12の因子の中で、「中年期(40〜65歳)の難聴」が、単独で8%と、最大のリスク因子であることを科学的に突き止めたのです。これは、高血圧(5%)や肥満(1%)、喫煙(5%)といった他のよく知られたリスク因子を上回る、驚くべき結果でした。
なぜ難聴が認知症に繋がるのでしょうか。その仕組みとして、難聴によって脳に届く音の刺激が慢性的に減少することが、脳の萎縮や認知機能の低下を招くという仮説が有力です21。また、会話が聞き取りにくくなることで、他者とのコミュニケーションを避け、社会的に孤立しがちになることも、うつ病や認知機能低下の引き金になると考えられています。
この国際的な動向を受け、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会も「難聴が認知症やうつ病の発生に深く関係している」という事実を重く受け止め、大森孝一理事長(当時)のメッセージなどを通じて、国民への積極的な啓発活動を行っています22。結論として、若いうちからの聴力ケアは、単に「よく聞こえる」という現在の生活の質を保つためだけではありません。それは、将来のあなたの認知機能を守り、健康で自立した人生を長く送るための、極めて重要な「未来への自己投資」なのです。
第6章:専門医への相談 – いつ、どこで、何を相談すべきか
6.1. 受診のタイミング
この記事を読んで、ご自身の聞こえに少しでも不安を感じたなら、専門家への相談をためらう必要はありません。以下のような場合は、受診を強く推奨します。
- 第3章の「聴力低下の危険サイン・セルフチェック」で3つ以上当てはまった場合。
- 3日以上続く、原因不明の耳鳴りや耳が詰まった感じ(耳閉感)がある場合15。
- 急に片耳または両耳が聞こえにくくなった場合(これは救急疾患です。直ちに受診してください)。
6.2. どこへ行くべきか?
聴覚に関する問題の専門家は、「耳鼻咽喉科(じびいんこうか)」または「耳鼻咽喉科・頭頸部外科(とうけいぶげか)」の医師です。お近くのクリニックや病院を受診してください。さらに、補聴器の装用を検討するなど、より専門的な相談が必要となった場合に備え、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が認定する「補聴器相談医」という資格を持つ医師がいることを知っておくとよいでしょう。この資格を持つ医師のリストは、同学会のウェブサイトで公開されており、地域ごとに検索することができます。これは、信頼できる専門家を見つけるための非常に有用な情報源です23。
6.3. 聴力検査とは?
病院での聴力検査と聞くと、少し身構えてしまうかもしれませんが、痛みなどは全く伴わない簡単な検査です。主に2種類の検査が行われます。
- 純音聴力検査: ヘッドホンを着け、防音室の中で「ピー」や「ボー」といった様々な高さの音が聞こえたらボタンを押す検査です。これにより、どの周波数の音がどのくらいの大きさまで聞こえるかを調べます。
- 語音明瞭度検査: 「あ」や「き」といった言葉がどの程度正確に聞き取れるかを調べる検査です。これにより、聴力低下が日常生活のコミュニケーションにどの程度影響しているかを評価します。
これらの検査は、通常数十分程度で終了します。ご自身の聴力の状態を正確に把握するための、非常に重要な第一歩です。
よくある質問
Q1. イヤホン難聴は一度なったら、もう治らないのですか?
A: 残念ながら、大きな音によって内耳の有毛細胞が一度破壊されてしまった場合、現在の医学ではそれを再生させることはできず、聴力は元に戻りません6。これが「音響性難聴は予防が最も重要」と言われる最大の理由です。ただし、突発性難聴のように急激に発症した場合など、原因によっては発症直後の急性期にステロイド治療などで改善する可能性もゼロではありません。いずれにせよ、早期の受診が鍵となります。
Q2. ノイズキャンセリングイヤホンなら、いくら使っても安全ですか?
A: いいえ、安全とは限りません。ノイズキャンセリング機能は、周囲の騒音を効果的に低減してくれるため、結果として音楽などのボリュームを上げすぎずに済むという点で、難聴予防に「役立ちます」。しかし、ノイズキャンセリング機能付きのイヤホン自体を大音量で長時間使用すれば、耳へのダメージは通常のイヤホンと何ら変わりません。あくまで「適切な音量で聴く」という大原則を守るための、非常に有用な補助機能と考えるべきです。
Q3. 子どものイヤホン使用で、特に気をつけるべきことは何ですか?
A: 子どもの耳は解剖学的にも大人よりデリケートであるため、より一層の注意が必要です。WHOは、子どもに対しては大人よりも厳しい安全基準、すなわち「平均音量75デシベルで週40時間まで」を推奨しています2。保護者の方が、スマートフォンのペアレンタルコントロール機能や音量制限機能を積極的に活用し、子どもが安全な音量で楽しめる環境を整えてあげることが非常に重要です。
結論
若者の聴力低下は、イヤホンやヘッドホンが普及した現代社会が抱える、静かで、しかし非常に深刻な問題です。それは、単に音が聞こえにくくなるだけでなく、コミュニケーションの障壁を生み、社会的な孤立を招き、さらには将来の認知症のリスクをも高める可能性があります4。しかし、この記事で解説してきたように、その原因の多くは日々の生活習慣にあり、正しい知識を持って行動することで、リスクは大幅に低減できます。「80デシベル・週40時間」というWHOの推奨ルールを守り、適切な音量と休憩を心がけること。それが、あなたの未来を守るための最もシンプルで強力な方法です。あなたの「聞こえ」は、人との繋がりを育み、音楽を楽しみ、世界を感じるための、かけがえのない一生の財産です。この記事を読んで少しでも不安を感じたなら、どうか一人で悩まず、お近くの耳鼻咽喉科専門医に相談してください。早期の行動が、あなたの豊かで健康な未来を守ることに繋がります。
免責事項本記事で提供する情報は、一般的な情報提供を目的としたものであり、医師の診断や治療に代わるものではありません。聴覚に関する健康上の問題については、必ず耳鼻咽喉科の専門医にご相談ください。本記事の情報を用いて行う一切の行為について、JAPANESEHEALTH.ORGは何ら責任を負うものではありません。
参考文献
- Freedman M, et al. Prevalence and global estimates of unsafe listening practices in adolescents and young adults: a systematic review and meta-analysis. BMJ Glob Health. 2022;7(11):e010501. doi:10.1136/bmjgh-2022-010501. Available from: https://gh.bmj.com/content/7/11/e010501
- World Health Organization. World report on hearing. 2021 [インターネット]. Geneva: World Health Organization; 2021 [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789240020481
- Fujii M, et al. Secular trends in hearing loss in 40-year-old and younger Japanese employees from 2009 to 2018: A retrospective study. Lancet Reg Health West Pac. 2021;10:100159. doi:10.1016/j.lanwpc.2021.100159. Available from: https://www.thelancet.com/journals/lanwpc/article/PIIS2666-6065(21)00062-8/fulltext
- Livingston G, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413-446. doi:10.1016/S0140-6736(20)30367-6. Available from: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30367-6/fulltext
- 厚生労働省. 騒音障害防止のためのガイドライン [インターネット]. 東京: 厚生労働省; 2023 [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32018.html
- 社会福祉法人 恩賜財団 済生会. その習慣、耳の劣化を早めてませんか? 「ヘッドホン・イヤホン難聴」に要注意! [インターネット]. 東京: 済生会; [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.saiseikai.or.jp/medical/column/headphones-hearing-loss/
- 茨城産業保健総合支援センター. 騒音性難聴に関わる [インターネット]. 茨城: 茨城産業保健総合支援センター; 2024 [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://ibarakis.johas.go.jp/2024/wp-content/uploads/2024/07/souon_20240522c.pdf
- よし耳鼻咽喉科. 【若者に急増中】イヤホンのせいで耳は悪くなる!防ぐためにできることも詳しくご紹介 [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.yoshijibika.com/archives/32427
- FNNプライムオンライン. 40代以下の聴力が最大20歳“老化”…原因はイヤホン使用? 今からできる対策を耳鼻科医に聞いた [インターネット]. 2021 [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.fnn.jp/articles/-/164025?display=full
- 新潟医療福祉大学. 若年者におけるイヤホンまたはヘッドホンの使用実態と聴力に関する調査. 新潟市医師会報. 2020 [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.niigatashi-ishikai.or.jp/newsletter/academic/202005253843.html
- 日本医師会. 特別寄稿 難聴の早期発見のため耳鼻咽喉科受診勧奨にご協力を. 日医on-line. [インターネット]. 2024 [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011853.html
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会. ヘッドホン・イヤホン難聴 [インターネット]. 東京: 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会; [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://owned.jibika.or.jp/headphone
- 東洋経済オンライン. 【イヤホン難聴】音楽聴きっぱなしで若者に急増 WHOも警鐘を… [インターネット]. 2022 [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://toyokeizai.net/articles/-/621317?display=b
- Olive Union. 20代で耳が遠いと感じる原因は?低音障害型感音難聴の症状や対処方法も解説 [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.oliveunion.com/jp/blog/tinnitus/20dai_mimigatooi/
- 岩佐耳鼻咽喉科. 若年性難聴 [インターネット]. 東京: 岩佐耳鼻咽喉科; [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://iwasa-jibika.jp/disease/young_hearing-loss.html
- 特定非営利活動法人 日本成人病予防協会. スマホ難聴 ~新しい生活様式~ 生活習慣病を予防する [インターネット]. 東京: 日本成人病予防協会; 2021 [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.japa.org/tips/kkj_2110/
- ソフトバンクニュース. 気づかぬうちに難聴に? 「ヘッドホン・イヤホン難聴」の初期症状などを耳鼻咽喉科医に聞いた [インターネット]. 2023 [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20230530_02
- シャープ. 聴力検査のアプリはある?聞こえを簡単にチェックする方法 | メディカルリスニングプラグ [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://jp.sharp/mlp/column/021/
- 兵庫県耳鼻咽喉科医会. 騒音障害防止のためのガイドライン [インターネット]. 兵庫: 兵庫県耳鼻咽喉科医会; 2021 [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.jibika.hyogo.med.or.jp/wp-content/uploads/2021/11/%E9%A8%92%E9%9F%B3%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%80%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B47%E6%9C%88%E3%80%80%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E8%80%B3%E9%BC%BB%E7%A7%91%E5%8C%BB%E4%BC%9A%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E6%8E%B2%E8%BC%89%E7%94%A8.pdf
- 湧永製薬株式会社. イヤホン難聴 [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.wakunaga.co.jp/health_info/%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E9%9B%A3%E8%81%B4
- メガネのカワチ. 『難聴と認知症の関係』NHK『ガッテン!』を参考に! [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://i-love-megane.jp/hearing_blog/archives/1099
- CareNet.com. 加齢性難聴予防に「聴こえ8030運動」を推進/耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 [インターネット]. 2024 [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.carenet.com/news/general/carenet/59694
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会. 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 [インターネット]. 東京: 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会; [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.jibika.or.jp/