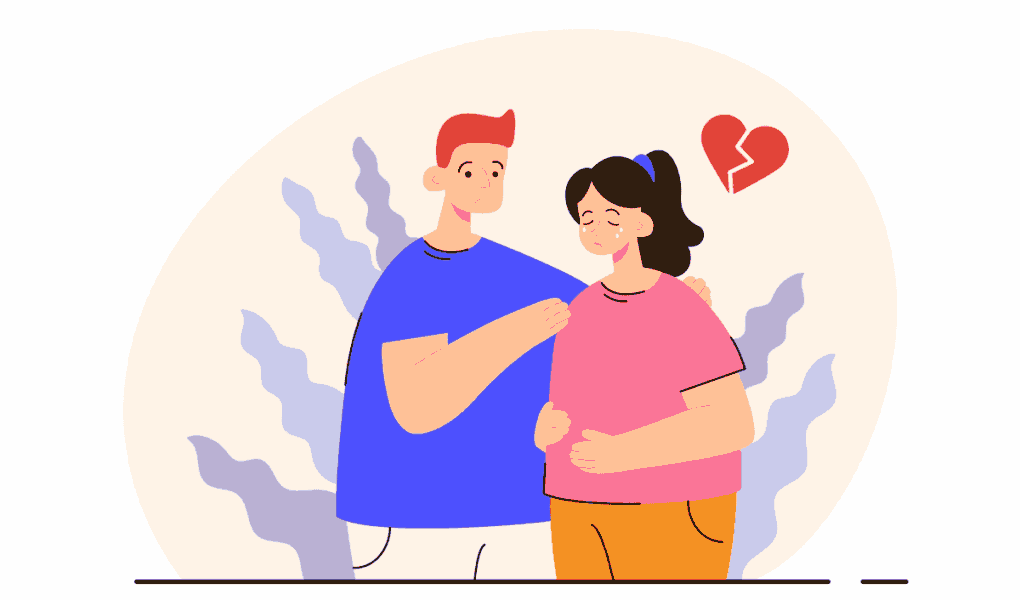この記事の科学的根拠
この記事は、インプットされた研究報告書に明記されている最高品質の医学的根拠にのみ基づいています。以下に示すリストは、実際に参照された情報源と、提示された医学的ガイダンスへの直接的な関連性を示したものです。
- e-Gov(日本政府): 本記事における死産の法的定義(妊娠12週以降)および死産届の義務に関する記述は、e-Gov法令検索に掲載されている「死産の届出に関する規程」に基づいています2。
- 日本産科婦人科学会 (JSOG) / 日本不育症学会 (JSRM): 2025年から適用される「不育症」の新しい定義に関する記述は、両学会の公式発表に基づいています1。これは、次回の妊娠に向けた最新の医学的視点を提供するものです。
- ACOG (米国産科婦人科学会) / SMFM (米国母体胎児医学会): 死産の原因、診断、医学的管理に関する国際的な標準治療の解説は、ACOGおよびSMFMが発表した診療コンセンサスに基づいています10。
- RCOG (英国王立産婦人科医会): 後期死産における分娩誘発、心理的サポート、家族の選択権の尊重に関する記述は、RCOGのグリーン・トップ・ガイドラインに基づいています11。
- 国立成育医療研究センター (NCCHD): 日本におけるグリーフケア(悲嘆ケア)の原則に関する解説は、NCCHDが作成した「子どもを亡くした家族への支援の手引き」に基づいています13。
- Hori, M., et al. (BMC Pregnancy and Childbirth): 日本の死産の現状と統計に関するデータ(南日本における20年間の傾向)は、2024年に発表されたこの疫学研究に基づいています8。
要点まとめ
- 日本では、法律上「死産」は妊娠12週以降と定義され、死産届の提出が義務付けられます。一方、医学的には妊娠22週以降を指すことが多く、二つの定義が存在します。
- 死産の原因は多岐にわたり、胎児側、胎盤・臍帯、母体側の要因がありますが、半数近くは原因不明です。原因究明のための検査は、次の妊娠への重要な情報となり得ます。
- 最も重要な兆候は「胎動の減少・消失」です。その他、出血や腹痛など、いつもと違う変化を感じたら、すぐに医療機関に連絡することが不可欠です。
- 死産後は、7日以内に「死産届」を役所に提出する行政手続きが必要です。この手続きについて事前に知っておくことで、精神的負担を軽減できます。
- 悲しみや辛さを乗り越えるために、専門的なグリーフケアや、同じ経験をした人々が集うサポート団体が日本には存在します。一人で抱え込まず、支援を求めることが大切です。
死産を経験したら
大切な赤ちゃんをおなかの中で亡くされたという現実は、言葉にできないほどの喪失感と混乱をもたらします。「なぜ自分に」「何を先にすればいいのか」という思いが強くても当然ですし、手続きや医療の説明を聞くだけでもつらいと感じるのは自然な反応です。このガイドでは、そのつらさを前提に、少しずつ進められる順番で整理してお伝えします。
まず知っておいてほしいのは、日本の制度や医療には、死産を経験したご家族を支えるためのルールと選択肢が用意されているということです。全体像をつかむには、妊娠・出産・手術・検査といった周辺情報をまとめた産婦人科の総合ガイドを起点にしておくと、後で必要になったときに関連する手続きや検査の位置づけを確認しやすくなります。
死産と診断されるとき、多くの場合は超音波で心拍が確認できないことが決定的な根拠になります。妊娠後期でも胎動が急に減る、出血や腹部の違和感が続くといった「いつもと違うサイン」があったら、自己判断をせずにすぐ受診し、画像で状況を確かめることが重要です。こうした検査の進み方や日本での標準的な見方は妊娠中の超音波検査の基本知識でもう一度確認しておくと、医師の説明が理解しやすくなります。
診断がついた直後は、心のつらさと同時に「子宮を安全に回復させる」「感染を防ぐ」「体力を落としすぎない」という医学的な段取りを整える必要があります。薬剤での誘発や処置のあとは、安静のとり方や出血の目安、入浴・外出を再開するタイミングを日本の基準に沿って確認してください。こうした“妊娠を終えたあとのケア”の考え方は人工妊娠中絶後のケアと共通する点が多く、出血量や痛みが想定より強いときの受診目安もここで補えます。
少し落ち着いてきたら、次の妊娠を見据えて身体を戻す段階に入ります。急がずに、まずは栄養を取りやすい形で補い、鉄分や葉酸など次の妊娠でも必要になる栄養素を整えると「また妊娠しても大丈夫かもしれない」という実感が持てます。食べ方の工夫や日本で手に入りやすい食材のヒントは流産を経験されたあなたへの食事ガイドが応用しやすく、パートナーと共有する際の説明材料にもなります。
また、今回の死産の背景に高血圧・糖尿病・胆汁うっ滞など妊娠中の合併症が関わっていた可能性がある場合は、次回の妊娠前にそれらをできるだけ整えておくことが再発リスクを下げます。とくに高血圧関連は胎盤の血流に影響しやすいため、基礎疾患がある人や年齢が高めの人は妊娠高血圧症候群の予防のポイントを産科医と一緒に確認しておくと安心です。
いまは「前と同じように妊娠を喜べるだろうか」と感じていても、身体を整え、手続きと医療の見通しを付け、周囲に支えてもらうことで少しずつ前に進めます。かかった医療機関や自治体の相談窓口を遠慮なく頼りながら、ご自身のペースで回復に向かってください。あなたの悲しみは正当なものであり、一歩ずつ進めば必ず次の選択が見えてきます。
1. 死産とは:知っておくべき二つの定義
「死産」という言葉は、非常に重く、辛い響きを持ちます。この言葉を理解する上で、まず知っておくべきなのは、日本には「法律上の定義」と「医学上の定義」という、二つの異なる捉え方があるという事実です。この違いを明確に理解することは、ご自身がおかれた状況を正確に把握し、必要な手続きを進める上で極めて重要です。
1.1. 法律上の定義:妊娠12週以降
日本の法律、具体的には厚生労働省が定める「死産の届出に関する規程」において、「死産」とは「妊娠満12週以後の死児の出産」と定義されています2。ここでの「死児」とは、出産後に心臓の拍動、随意筋の運動、呼吸のいずれも認めないものを指します。この定義の最も重要な点は、妊娠12週(12週0日)以降に赤ちゃんがお腹の中で亡くなった場合、それが自然な流産であっても、人工的な中絶であっても、法律上はすべて「死産」として扱われるということです。この法律上の定義は、純粋に医学的な問題だけでなく、社会的な義務を伴います。具体的には、死産から7日以内に、お住まいの市区町村役場へ「死産届」を提出する義務が生じます。そして、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、火葬を行う必要も出てきます2, 3。この行政手続きは、悲しみの最中にあるご家族にとって大きな負担となり得ますが、法律で定められた重要な責務です。
1.2. 医学・周産期医療における定義:妊娠22週以降
一方で、医学、特に周産期医療の分野では、一般的に「死産」は妊娠22週以降の胎児死亡を指します。この「妊娠22週」という時期は、赤ちゃんの「生存限界(viability)」、つまり、もし生まれた場合に現代の医療技術をもってすれば、生存できる可能性が出てくる境界線と考えられています。そのため、国の保健統計や国際的な周産期死亡率の比較分析など、医学的なデータを扱う際には、この妊娠22週以降を「死産」として集計することが標準的です10, 11。妊娠12週から21週までの間の胎児死亡は「後期流産」と呼ばれ、医学的には区別されます。この二つの定義の違いを知っておくことは、医師からの説明を理解し、統計データなどを目にした際の混乱を避けるために非常に役立ちます。
2. 日本における死産の現状と統計
お子さんを亡くすという経験は、計り知れないほどの孤独感を伴います。しかし、あなただけがこの悲しみを経験しているわけではありません。日本の周産期医療は世界最高水準にあり、周産期死亡率(妊娠22週以降の死産と生後1週未満の早期新生児死亡を合わせた率)は極めて低い国の一つですが、それでも毎年、数千ものご家族が死産という辛い現実に直面しています9。厚生労働省の人口動態統計によると、日本の死産率は長期的に減少傾向にありますが、依然としてゼロではありません12。より具体的な状況を明らかにしたのが、日本の南九州地方で2001年から2020年までの20年間にわたる大規模なデータを解析した堀氏らの研究です。この研究によれば、この地域での1,000出産あたりの死産率は、2001年の3.98から2020年には2.20へと著しく減少したことが示されました8。この改善は、日本の産科医療全体の質の向上を反映しています。しかし、同研究は同時に新たな課題も浮き彫りにしました。胎児機能不全や常位胎盤早期剥離といった原因による死産が減少する一方で、臍帯(へその緒)の異常に関連する死産の割合が増加傾向にあったのです。さらに注目すべきは、死産の原因を特定するために最も有効とされる胎児剖検(解剖)の実施率が、調査期間全体でわずか25.9%と低水準にとどまっていた点です8。これは、米国産科婦人科学会(ACOG)などが強く推奨する剖検実施率よりも低い数値であり、原因がわからないまま次の妊娠への不安を抱えるご家族が多い可能性を示唆しています。このデータは、死産が決して稀な出来事ではなく、その原因究明と予防に向けた継続的な努力が社会全体で必要とされていることを物語っています。
3. 死産の主な原因
「なぜ、私たちの赤ちゃんが…」これは、死産を経験したすべての親が抱く、最も痛切な問いです。しかし、残念ながら、現代の医学をもってしても、死産の約半数は明確な原因が特定できない「原因不明」であるのが現状です10。原因が分からないことは、自分を責める気持ちにつながりやすく、ご家族をさらに苦しめることがあります。しかし、原因の多くは誰のせいでもなく、予測や予防が困難な偶発的な出来事であることを理解することが重要です。ここでは、現在わかっている主な原因を体系的に解説します。
3.1. 胎児側の要因
赤ちゃん自身の側に、発育を続けることが困難になる問題が存在する場合があります。米国産科婦人科学会(ACOG)の報告によれば、死産の8%から13%に染色体異常が関与しているとされています10。これにはダウン症候群(21トリソミー)、18トリソミー、13トリソミーなどが含まれます。また、心臓や脳などの重要な臓器に重篤な構造的奇形(先天性疾患)がある場合も、胎内での生存が困難になることがあります。さらに、サイトメガロウイルス(CMV)やパルボウイルスB19といった感染症が母親から胎児へ垂直感染することも、死産の原因となり得ます。
3.2. 胎盤・臍帯の異常
胎盤と臍帯(へその緒)は、赤ちゃんに酸素と栄養を届ける「命綱」です。この部分に異常が生じると、胎児の生命に直接的な影響を及ぼします。死産の原因として最も多いグループの一つであり、特に常位胎盤早期剥離(胎盤が赤ちゃんが生まれる前に子宮の壁から剥がれてしまう状態)は、死産全体の10%から20%を占める重大な原因です10。その他にも、胎盤の機能が低下し、赤ちゃんが十分に成長できなくなる胎盤機能不全や、臍帯がねじれたり、結び目(真結節)ができたり、圧迫されたりして血流が途絶えてしまう臍帯の異常も、突然の死産を引き起こす原因となります。
3.3. 母体側の要因
お母さん自身の健康状態が、妊娠の経過に大きく影響することもあります。特に、妊娠前から持っている糖尿病や高血圧症などの慢性疾患が十分に管理されていない場合、死産のリスクは著しく高まります10, 18。また、抗リン脂質抗体症候群(APS)に代表される自己免疫疾患は、胎盤内に血栓(血の塊)を作りやすくし、胎児への血流を妨げることで死産の原因となります。妊娠中に発症する合併症、例えば重度の妊娠高血圧症候群(かつての妊娠中毒症)や、妊娠性肝内胆汁うっ滞症なども、胎児環境を悪化させ、リスクを高めることが知られています。
4. 注意すべき兆候と症状
全ての死産を予防することは不可能ですが、赤ちゃんの危険を知らせるサインに早期に気づき、迅速に行動することで救える命があるかもしれません。妊婦さんとそのご家族が知っておくべき最も重要な兆候は、「胎動の変化」です。
胎動は、お腹の赤ちゃんが元気であることの証です。多くの妊婦さんは妊娠20週前後で胎動を感じ始め、妊娠28週以降は、赤ちゃん独自のリズムで力強い動きを感じるようになります。死産の最も一般的で重要な前兆は、この胎動が明らかに少なくなる、弱くなる、あるいは全く感じられなくなる「胎動の減少・消失」です11, 18。
「今日は静かだな」と感じる程度でも、普段の赤ちゃんの様子と比べて明らかに動きが少ない、いつもなら動いている時間帯に全く動かないなど、少しでも不安を感じたら、自己判断で様子を見ることは絶対に避けてください。すぐに産科の医療機関に電話し、指示を仰ぐことが極めて重要です。
その他、注意すべき症状には以下のようなものがあります。
- けいれんや激しい腹痛
- 性器からの出血
- 破水(水っぽいおりものが流れ出る)
これらの症状が必ずしも死産を意味するわけではありませんが、いずれも緊急の医学的評価が必要なサインです。ためらわずに、昼夜を問わず、かかりつけの医療機関に連絡してください。
5. 診断と医学的な対応
医療機関で死産の疑いが持たれた場合、医師はまず超音波検査(エコー検査)を行い、赤ちゃんの心臓の拍動を確認します。この検査で心拍が確認できない場合に、死産の診断が確定されます。これは、ご家族にとって人生で最も辛い瞬間の一つです。医療スタッフは、ご家族がこの事実を受け止めるための時間とプライベートな空間を提供してくれます。診断後の医学的な対応は、ご家族の心身の状態と意向を最大限に尊重しながら進められます。
5.1. 分娩方法の選択肢
診断が確定した後、赤ちゃんを体外に出すための方法について、医師と話し合います。選択肢は主に以下の3つです。
- 分娩誘発 (Inducing labor): これは最も一般的に推奨される方法です。薬剤を用いて人工的に陣痛を起こし、経腟分娩を行います。この方法の利点は、ご家族が精神的な準備を整え、お産の日時をある程度計画できることです。米国産科婦人科学会(ACOG)のコンセンサスでも、多くの状況で推奨されています10。
- 待機的管理 (Expectant management): 自然に陣痛が始まるのを待つという選択肢です。多くの場合、診断から3週間以内に自然な陣痛が起こるとされています。しかし、待機期間が長引くと、母体に感染症のリスクが生じたり、精神的な負担が増大したりする可能性があります。
- 帝王切開 (Caesarean birth): 母体側に特別な医学的理由(例えば前置胎盤など)がない限り、死産のために帝王切開が行われることは稀です。経腟分娩に比べて母体への身体的負担やリスクが大きく、将来の妊娠にも影響を与える可能性があるため、通常は避けられます10。
どの方法を選択するかは、医師からの十分な情報提供のもと、ご家族の希望を基に決定されます。
5.2. 死因究明のための検査
なぜ赤ちゃんが亡くなったのかを知ることは、ご家族が「自分のせいではなかった」と理解し、罪悪感から解放される助けとなることがあります。また、原因を特定することは、次の妊娠を考える上での非常に重要な医学的情報を提供します。検査を行うかどうかは、完全に ご家族の任意であり、その権利は尊重されます。英国王立産婦人科医会(RCOG)のガイドラインでも、家族の意思決定支援の重要性が強調されています11。主な検査には以下のようなものがあります。
| 検査名 | 目的 | 国際的な推奨 (ACOG/RCOG) | 日本での状況 |
|---|---|---|---|
| 胎児剖検(Autopsy) | 赤ちゃんの体を詳細に調べ、先天性の疾患や構造異常、感染の有無などを確認する。 | 最も多くの情報が得られるため、強く推奨される10。 | 実施率は低い(約25.9%)8。文化的背景や説明不足が影響している可能性がある。 |
| 胎盤・臍帯の病理検査 | 胎盤や臍帯に感染の兆候、血栓、構造的な問題がないかを調べる。 | 必須。剖検を希望しない場合でも実施すべきとされる10。 | 剖検よりは高いが(約54.8%)8、まだ100%ではない。 |
| 遺伝学的検査 | 赤ちゃんの染色体を分析し、遺伝的な異常がないかを確認する。 | 強く推奨される。通常、胎盤や皮膚の組織から検体を採取する10。 | 実施可能だが、施設や家族の同意による。 |
| 母体の血液検査 | 糖尿病、甲状腺疾患、抗リン脂質抗体症候群(APS)など、母体の隠れた病気を調べる。 | 必須。治療可能なリスク因子を特定するのに役立つ。 | 標準的なケアの一環として行われる。 |
6. 死産後の手続きと利用できる支援
赤ちゃんとのお別れの直後、ご家族は深い悲しみの中で、現実的な手続きにも向き合わなければなりません。このセクションは、日本の文脈において非常に実践的で重要な情報を提供します。必要な手続きと、利用できる心の支援について知ることは、混乱した状況下での大きな助けとなります。
6.1. 行政手続き:死産届と火葬許可
前述の通り、日本の法律では妊娠12週以降の死産があった場合、行政への届出が義務付けられています2。悲しみの淵にいるご家族にとって、これは非常に酷な作業に感じられるかもしれませんが、避けては通れない手続きです。以下にその流れを具体的に示します。
- 死産証書(死胎検案書)の受領: まず、分娩に立ち会った医師または助産師から「死産証書(または死胎検案書)」を受け取ります。これは、死産の事実を医学的に証明する公的な書類です。
- 死産届の記入: 死産証書の右半分が「死産届」の様式になっています。届出義務者(通常は父、それができない場合は母)が必要事項を記入します。
- 役所への提出: 記入した死産届を、死産があった日から7日以内に、届出人の所在地、または死産があった場所の市区町村役場の戸籍担当窓口に提出します4。この届出により、戸籍には記載されませんが、死産台帳に記録が残ります。
- 死胎火葬許可証の受領: 死産届を提出すると、役所から「死胎火葬許可証」が交付されます。この許可証がなければ、赤ちゃんを火葬することができません。この許可証をもって、火葬場の手配を進めることになります。
自治体によっては、この一連の手続きをまとめたガイドブックを用意している場合もあります(例:大阪市4、藤沢市17)。
6.2. 心のケア:グリーフケアとサポート団体
死産後の心の痛みは、言葉では言い尽くせないほど深く、長く続くものです。この悲嘆(グリーフ)のプロセスは、人それぞれであり、正常な反応です。大切なのは、一人で抱え込まず、適切な支援につながることです。「グリーフケア」とは、このような喪失体験をした人々が、悲しみを乗り越え、再び穏やかな日常を取り戻せるように支える専門的なケアを指します。国立成育医療研究センター(NCCHD)が発行した手引きによると、効果的なグリーフケアには、敬意をもって話を聞くこと、悲嘆の反応が自然なものであると肯定すること、無理強いせずに感情の表出を支えることなどが含まれます13。幸いなことに、日本には、同じ痛みを知る当事者や専門家によるサポート団体が数多く存在します。これらの団体は、電話相談、オンラインコミュニティ、分かち合いの会などを通じて、ご家族が孤立しないように支えています。
| 団体名 | ウェブサイト | 主な対象とサービス |
|---|---|---|
| ポコズママの会 | https://pocosmama.jp/ | 流産・死産を経験した家族を支援。オンラインコミュニティの運営、お話会の開催、情報提供などを行う6。 |
| SIDS家族の会 | https://www.sids.gr.jp/ | SIDS(乳幼児突然死症候群)に加え、流産・死産で子どもを亡くした家族も支援。電話相談や全国での分かち合いの会を実施5。 |
| 天使の保護者ルカの会 | https://waiskt.org/ | 聖路加国際大学が運営母体。周産期に子どもを亡くした家族のための分かち合いの会や個別相談を提供している。 |
| NPO法人 周産期グリーフサポート・Nagomi | https://pls-nagomi.or.jp/ | 周産期の子どもとの死別(ペリネイタル・ロス)の啓発、支援団体の連携、ベビーのためのドレスや資料の提供などを行う。 |
大阪府など、自治体レベルでも支援情報が集約されています19。
7. リスクの軽減と次の妊娠に向けて
一度死産を経験すると、次の妊娠に対して大きな不安を抱くのは当然のことです。しかし、適切な知識と準備を持つことで、多くのご家族が健康な赤ちゃんを授かっています。
7.1. 妊娠前・妊娠中の予防策
全ての死産が予防可能ではありませんが、リスクを少しでも減らすためにできることがあります。国際的なガイドラインでは、以下のような対策が推奨されています10, 18。
- 妊娠前の健康管理: 妊娠を計画する段階で、持病(糖尿病、高血圧、甲状腺疾患など)があれば、主治医と相談し、最良の状態にコントロールしておく。
- 健康的な生活習慣: 禁煙、禁酒、違法薬物の不使用は絶対です。バランスの取れた食事と適度な運動を心がけ、適切な体重を維持することも重要です。
- 葉酸の摂取: 妊娠前から推奨量の葉酸をサプリメントで摂取することは、赤ちゃんの神経管閉鎖障害のリスクを減らすことが知られています。
- 定期的な妊婦健診: 妊婦健診をきちんと受けることは、母子双方の健康状態をチェックし、問題を早期に発見するために不可欠です。
- 胎動のモニタリング: 妊娠後期(28週以降)になったら、毎日赤ちゃんの胎動に注意を払い、普段との違いを感じたらすぐに医療機関に連絡する習慣をつけましょう。
7.2. 不育症としての考え方と相談
もし、今回が初めての妊娠喪失ではない場合、より専門的なアプローチが必要になるかもしれません。この分野において、日本産科婦人科学会(JSOG)と日本不育症学会(JSRM)は、重要な一歩を踏み出しました。2025年に発刊される新しい用語集から、「不育症」の定義が「2回以上の流産・死産を繰り返した場合」へと変更されることが決定したのです1。これは、これまでの「3回以上」という基準から緩和され、より早期からの検査や治療介入を可能にすることを目的としています。
もしあなたがこの新しい定義に当てはまる場合、つまり過去に流産や死産を合わせて2回以上経験している場合は、「不育症」を専門とする医師への相談を検討する価値があります。不育症の検査では、血液凝固異常(抗リン脂質抗体症候群など)、夫婦の染色体異常、子宮の形態異常などを調べ、原因に応じた治療を行うことで、次の妊娠での出産成功率を高めることが期待できます。
よくある質問
死産を経験すると、次の妊娠がしにくくなりますか?
ほとんどの場合、一度の死産がその後のあなたの妊娠する能力(妊孕性)に直接影響を与えることはありません。多くの女性が、死産後に健康な赤ちゃんを妊娠・出産しています。ただし、死産の原因が母体の健康問題(例えば、治療が必要な抗リン脂質抗体症候群など)や、繰り返される可能性のある遺伝的問題であった場合は、次の妊娠の前に専門家によるカウンセリングや治療が非常に重要になります。ACOGのコンセンサスでも、原因に応じた次回の妊娠管理の重要性が指摘されています10。
次の妊娠を試みるまで、どれくらい待つべきですか?
この問いに対して、すべての人に当てはまる唯一の答えはありません。身体的な回復という点では、数回の月経周期を経れば、子宮は次の妊娠の準備が整うことが多いです。しかし、それと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが、心と感情の回復です。悲しみを乗り越え、精神的に次の妊娠と向き合う準備ができたと感じるまで、焦る必要は全くありません。国際的なガイドラインでも、カップルが十分に悲しむための時間をとり、自分たちのペースで決断することが推奨されています。主治医やパートナーと率直に話し合い、ご自身たちのタイミングを大切にしてください。
夫/パートナーが、私ほど悲しんでいないように見えます。これは普通のことですか?
はい、それはごく普通であり、非常によくあることです。人々は、悲しみに対して様々な方法で向き合います。一般的に、女性は感情を言葉にして表出する傾向がありますが、男性は悲しみを内に秘め、仕事に没頭するなど、異なる形で表現することがあります。重要なのは、お互いの悲しみの表現方法が違うことを理解し、尊重し合うことです。コミュニケーションを閉ざさず、「あなたは悲しくないの?」と責めるのではなく、「私は今こう感じている」と自分の気持ちを正直に伝えることが大切です。カップルでカウンセリングを受けることも、お互いの理解を深めるのに非常に役立ちます。
結論
死産は、親にとって最も辛い経験の一つです。この記事では、その医学的な側面から、日本特有の行政手続き、そして心のケアに至るまで、包括的な情報を提供することを目指しました。重要なのは、この悲劇的な出来事に直面したとき、正しい知識を身につけ、次に何をすべきかを理解し、そして何よりも一人で抱え込まないことです。日本には、あなたを支えるための医療専門家、カウンセラー、そして同じ経験を持つ仲間のコミュニティが存在します。医師や助産師とオープンに話し合い、ためらうことなく心理的なサポートを求めてください。この長く困難な道のりにおいて、あなたは決して一人ではないことを、どうか忘れないでください。
免責事項本記事で提供される情報は、一般的な知識提供のみを目的としており、専門的な医学的アドバイス、診断、または治療に代わるものではありません。健康に関する問題や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- 日本産科婦人科学会, 日本不育症学会. 2025年発刊 日本産科婦人科学会用語集に掲載されました [インターネット]. 2025 [引用日: 2025年7月21日]. Available from: http://jpn-rpl.jp/2025/06/10/2025%E5%B9%B4%E7%99%BA%E5%88%8A-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%94%A3%E7%A7%91%E5%A9%A6%E4%BA%BA%E7%A7%91%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E7%94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86%E3%81%AB%E6%8E%B2%E8%BC%89%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE/
- e-Gov法令検索. 昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000100042
- 株式会社りゅうきゅう. 死産・流産の違いとは?何か月から火葬?死産・流産・中絶の赤ちゃんの処置や手続きは? [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.ryuukyuu.co.jp/column/stillbirthormiscarriage0804/
- 大阪市. 死産届 (…>ご不幸>戸籍などの届出) [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369833.html
- NPO法人 SIDS家族の会. ホーム [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.sids.gr.jp/
- ポコズママの会. 団体概要 | 流産・死産経験者で作るポコズママの会 [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://pocosmama.jp/about/outline/
- 日本産婦人科医会. 5.後期流産の処置 [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.jaog.or.jp/note/5%EF%BC%8E%E5%BE%8C%E6%9C%9F%E6%B5%81%E7%94%A3%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%BD%AE/
- Hori M, Umazume T, Kouno Y, et al. Trends in the causes of stillbirths over 20 years in Southern Japan. BMC Pregnancy Childbirth. 2024;24(1):443. doi:10.1186/s12884-024-06403-4. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12135317/
- Fujiwara T, Hata A, Sago H. Trends in perinatal mortality and its risk factors in Japan: Analysis of vital registration data, 1979–2010. PLoS One. 2017;12(4):e0176326. doi:10.1371/journal.pone.0176326. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5404230/
- American College of Obstetricians and Gynecologists; Society for Maternal-Fetal Medicine. ACOG SMFM Obstetric Care Consensus #10: Management of Stillbirth. Obstet Gynecol. 2020;135(3):e110-e132. Available from: https://publications.smfm.org/publications/322-acog-smfm-obstetric-care-consensus-10-management-of/
- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Care of late intrauterine fetal death and stillbirth (Green-top Guideline No. 55). RCOG; 2025. PMID: 39467688. Available from: https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/care-of-late-intrauterine-fetal-death-and-stillbirth-green-top-guideline-no-55/
- Ministry of Health, Labour and Welfare. Outline of Vital Statistics in JAPAN [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.mhlw.go.jp/english/database/db-hw/outline/index.html
- 国立成育医療研究センター, キャンサースキャン. 子どもを亡くした家族への支援の手引き [インターネット]. 2022 [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://cancerscan.jp/wp-content/uploads/2022/03/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D.pdf
- 繁殖成績向上のために、特に白子対策について [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.e-jasv.com/gijutu_pdf/hanshoku_06_murata.pdf
- 乳用牛の流産、受精卵の胚死滅について ~流産の要因、予防と管理 [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.milknet-labo.co.jp/blog/others/411/
- 異常産・流産の原因となる – 常病 – 疾病と対策 – 日本養豚開業獣医師協会(JASV) [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.e-jasv.com/gijutu_pdf/hanshoku_19_nakamura.pdf
- 藤沢市. 流産・死産を経験された方へ [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/oyako/ninshin/ryuuzan.html
- Cleveland Clinic. Stillbirth [Internet]. [cited 2025 Jul 21]. Available from: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9685-stillbirth
- 大阪府. 流産・死産等でお子さまを亡くされたご家族への支援について [インターネット]. [引用日: 2025年7月21日]. Available from: https://www.pref.osaka.lg.jp/o100040/kenkozukuri/boshi/ryuzan.html