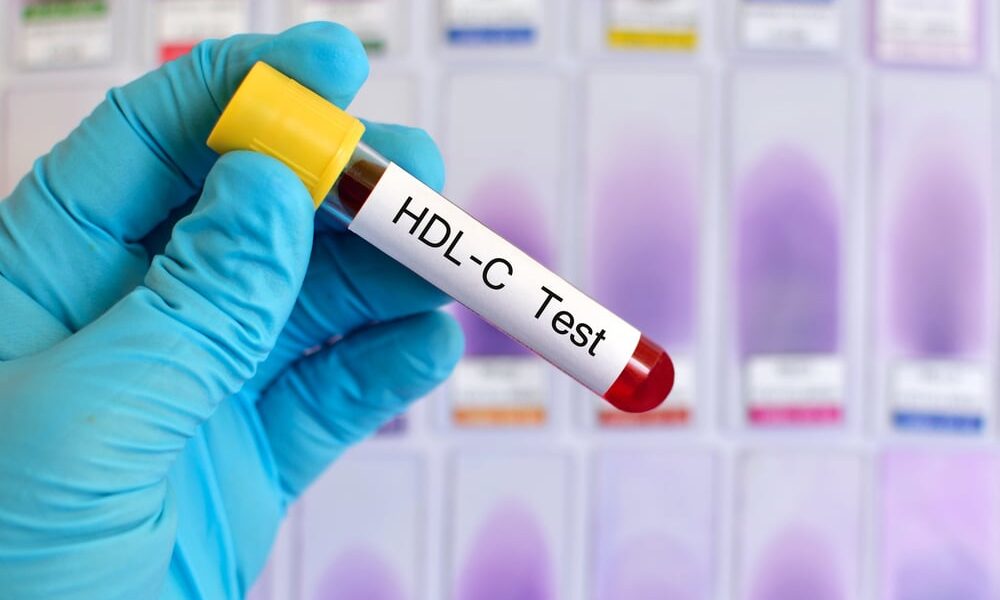健康診断、特に年に一度の特定健診の結果を見て、「HDLコレステロール」の数値に一喜一憂した経験はありませんか。「善玉コレステロール」として知られるこの数値は、低いと問題であると広く認識されていますが、その一方で「高ければ高いほど良い」というわけではない、という複雑な側面も近年の研究で明らかになってきました。厚生労働省の令和5年(2023年)「国民健康・栄養調査」によると、non-HDLコレステロールの平均値は男性で139.0 mg/dL、女性で143.5 mg/dLとなっており、脂質管理は多くの日本人にとって決して他人事ではありません15。本記事では、2022年に発表された最新の日本の診療ガイドラインと、近年の国際的な科学研究に基づいて、HDLコレステロールに関する疑問と不安をできるだけ網羅的に解説します。基準値の正しい理解から、数値が低い場合・高すぎる場合のそれぞれのリスク、そして科学的根拠に基づいた具体的な改善策まで、日本の生活者の視点に立って丁寧に整理していきます。
この記事の科学的根拠と編集方針
本記事は、JHO(JapaneseHealth.org)編集委員会が、厚生労働省や日本の専門学会、査読付き論文などの信頼できる情報に基づいて作成しました。国内外の公的ガイドラインやレビュー論文をもとに、一般の読者にも分かりやすい形で情報を整理しています(一部の情報の整理にはAIツールも活用していますが、内容の確認と最終的な判断はすべてJHO編集部が行っています)。提示されている医学的な指針や数値は、下記の情報源に由来するものです。
- 日本動脈硬化学会 (JAS): 本記事における脂質異常症の診断基準(HDLコレステロール40mg/dL未満など)、管理目標値、および生活習慣改善の推奨は、同学会発行の「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」に基づいています111224。
- 厚生労働省 (MHLW): 日本国内における脂質異常症の有病率やnon-HDLコレステロールの平均値に関する統計データは、厚生労働省の「国民健康・栄養調査」などを引用しています15。
- 国立循環器病研究センター (NCVC): 脂質異常症の病態や原因、動脈硬化との関係に関する基礎的な解説は、同センターの公式情報を参考にしています1617。
- 国際的な学術論文 (メタアナリシス及びレビュー論文): HDLコレステロール値が極端に高い場合の逆説的リスク(U字型リスクカーブ)や、HDLの「機能(コレステロール引き抜き能)」に関する最先端の知見は、「Frontiers in Cardiovascular Medicine」7やPubMedに索引されている複数の査読付き論文に基づいています8910。
- 米国心臓協会 (AHA) / 米国国立心肺血液研究所 (NHLBI): 生活習慣改善に関する国際的な推奨事項や、HDLコレステロール値の歴史的な分類については、これらの国際的権威機関のガイドラインを参考にし、日本の基準が国際標準と整合していることを確認しています1922。
要点まとめ
- HDLコレステロールは「善玉」と呼ばれ、血管壁の余分なコレステロールを回収する重要な役割を担います。
- 日本の公式な診断基準では、HDLコレステロール値が40mg/dL未満の場合、「低HDLコレステロール血症」と診断され、動脈硬化のリスクが高まります11。
- 近年の研究では、HDLコレステロール値が極端に高い場合(例:90〜100mg/dL以上)も、死亡率の上昇と関連する「U字型リスク」の可能性が指摘されています7。
- HDLは単純な「量」だけでなく、コレステロールを回収する能力である「質(コレステロール引き抜き能)」も重要視されるようになっています925。
- 脂質管理では、HDLだけでなくLDLコレステロールやnon-HDLコレステロール、中性脂肪などを総合的に評価することが重要です124。
- 改善には、有酸素運動、禁煙、適切な食事が不可欠です。特に不飽和脂肪酸の摂取やトランス脂肪酸の制限が推奨されます242829。
- 健康診断の結果は「良い・悪い」を一人で判断せず、基準値やご自身の他の病気・家族歴も踏まえて、医療機関で相談しながら活用することが大切です。
第1部:HDLコレステロールの基礎知識
HDLコレステロール(善玉コレステロール)とは?
HDLコレステロール(高比重リポタンパク質コレステロール)は、一般に「善玉コレステロール」として知られています。その主な役割は、体内のさまざまな組織、特に動脈の血管壁に蓄積した余分なコレステロールを回収し、肝臓へ運び戻すことです。このプロセスは「リバースコレステロールトランスポート(コレステロール逆転送系)」と呼ばれ、血管をきれいに保つための重要な機能です1626。
コレステロール自体に「善悪」があるわけではなく、それを運ぶリポタンパク質(LDL、HDLなど)の種類によって、体内での働き方が変わります。HDLは、動脈硬化の原因となるプラーク(粥腫)の蓄積を防ぐ方向に働くため、「善玉」と呼ばれているのです。一方でLDLコレステロールは、必要以上に多い状態が長く続くと血管壁に沈着し、動脈硬化を進める方向に働くため「悪玉」と呼ばれます17。
HDLコレステロールの基準値と年齢・性別による違い
日本動脈硬化学会のガイドラインでは、HDLコレステロールが40mg/dL未満の場合に「低HDLコレステロール血症」とされます1124。一方、「何mg/dL以上なら絶対に安心」といった一律の上限や「理想値」が定められているわけではありません。一般に、40mg/dL以上であれば動脈硬化リスクの評価において大きなマイナス要因にはなりにくく、50〜60mg/dL前後であれば心血管リスクの観点から望ましい範囲とされることが多いと考えられています2122。
また、HDLコレステロールの値は、性別や年齢、体格、喫煙・飲酒習慣、身体活動量などによっても変化します。例えば、一般的に女性は男性よりもHDLコレステロール値が高い傾向にあり、閉経後に変化がみられることも知られています14。同じ「50mg/dL」という値でも、人によって意味合いがやや異なる場合があるため、自分の背景や他の検査値も含めて医療者と一緒に評価することが重要です。
なぜHDLコレステロール検査が重要なのか?動脈硬化との深刻な関係
HDLコレステロールの値が低い状態(低HDLコレステロール血症)は、動脈硬化の独立した危険因子です217。HDLが少ないと、血管壁にたまったLDLコレステロール(悪玉コレステロール)を効率よく回収できなくなり、結果としてLDLコレステロールが血管壁に酸化などの変性を起こしながら蓄積しやすくなります。この蓄積物がプラークとなり、血管の内側を狭くし、弾力性を失わせるのが動脈硬化です。
動脈硬化が進行すると、血栓が形成されやすくなり、心臓の血管が詰まれば心筋梗塞、脳の血管が詰まれば脳卒中(脳梗塞)といった、生命を脅かす深刻な疾患を引き起こす危険性が高まります。日本を含む多くの国で、心筋梗塞や脳卒中は主要な死因・要介護原因となっており、その背景に脂質異常症が関わっていることはよく知られています1623。したがって、HDLコレステロールの値を適切な範囲に保つことは、これらの疾患を予防するうえで非常に重要なポイントなのです。
HDLとLDL・non-HDLコレステロールのバランス
脂質の検査結果を見るとき、多くの方が「HDLの値」だけに注目しがちですが、実際にはLDLコレステロールやnon-HDLコレステロール、中性脂肪(トリグリセリド)などとのバランスが重要です。non-HDLコレステロールとは、「総コレステロール − HDLコレステロール」で計算される値で、LDLを含む、動脈硬化に関わる「悪玉側」のリポタンパク質をまとめて反映した指標です1。
HDLがある程度高くても、LDLやnon-HDLコレステロールが大きく上回っている場合には、動脈硬化リスクはなお高いままということも少なくありません。逆に、LDLやnon-HDLがしっかりコントロールされており、HDLも40mg/dL以上であれば、全体としては比較的良好な脂質バランスと言えるケースもあります。検査結果を「1つの数字」だけで判断せず、組み合わせで見ることが大切です。
第2部:検査結果の正しい読み方【日本動脈硬化学会2022年版ガイドライン完全準拠】
脂質異常症の診断基準:日本の公式基準を理解する
脂質異常症の診断は、空腹時に採血した血液中の脂質濃度に基づいて行われます(最近では、状況によっては非空腹時の値も活用されることがあります)。日本動脈硬化学会が2022年に発表した最新のガイドラインでは、以下の基準値が定められています。この基準は、日本の医療現場で広く用いられている公式なものです111324。ご自身の健康診断の結果と見比べて、どの項目に当てはまるかを確認することが第一歩です。
| 脂質項目 | 基準値 (mg/dL) | 診断名 |
|---|---|---|
| LDLコレステロール (悪玉) | 140以上 | 高LDLコレステロール血症 |
| 120~139 | 境界域高LDLコレステロール血症 | |
| HDLコレステロール (善玉) | 40未満 | 低HDLコレステロール血症 |
| トリグリセリド (中性脂肪) | 150以上 (空腹時) | 高トリグリセリド血症 |
| Non-HDLコレステロール | 170以上 | 高non-HDLコレステロール血症 |
| 150~169 | 境界域高non-HDLコレステロール血症 |
特に注目すべきは、特定健診などでもリスク評価に用いられる「non-HDLコレステロール」です。これは総コレステロールからHDLコレステロールを引いた値で、動脈硬化を引き起こすすべての悪玉リポタンパク質の量を反映しており、LDLコレステロールだけでは捉えきれないリスクをより正確に反映する指標とされています124。
検査結果をどう読み解くか:自分のパターンを整理する
実際の健診結果では、「LDLは少し高いがHDLも高め」「HDLだけが低い」「中性脂肪も含めて全体的に高め」など、さまざまなパターンがあります。例えば、
- LDL 140mg/dL以上、HDL 40mg/dL未満、中性脂肪150mg/dL以上のように、複数の項目が基準値を超えている場合
- LDLやnon-HDLは基準値内だが、HDLだけが40mg/dL未満と低い場合
- HDLは高めだが、non-HDLコレステロールが170mg/dL以上と高い場合
などでは、リスクの内容や対策の優先順位が変わってきます。健診結果の用紙には「要経過観察」「要受診」などのコメントが付くことがありますが、「そこまで悪くないから大丈夫だろう」と自己判断せず、必ず一度は医療機関で説明を受けることをおすすめします。とくに糖尿病や高血圧、喫煙歴、家族歴(若くして心筋梗塞を起こした家族がいるなど)がある場合には、同じ検査値でもリスクが高く評価されることがあります19。
低HDLコレステロール血症:基準値「40mg/dL未満」が意味する重大なリスク
上記の基準表に示されている通り、HDLコレステロール値が40mg/dL未満である状態は「低HDLコレステロール血症」と診断されます11。これは、血管の「掃除屋」が不足している状態を意味し、他の脂質の値(LDLコレステロールや中性脂肪)が正常範囲内であっても、心血管疾患のリスクが有意に高まることが知られています。
歴史的に見ても、米国のNCEP-ATP IIIガイドライン(2002年)では、HDLコレステロールが40mg/dL未満は「低い」、60mg/dL以上は「高い(望ましい)」と分類されており、この基準は国際的にも広く認識されています2122。日本のガイドラインでも、HDLが40mg/dL未満の場合には、ほかの危険因子の有無にかかわらず動脈硬化リスクを評価する際の重要なポイントとして位置づけられています24。
【最重要】HDLコレステロールのパラドックス:「高すぎる」ことの隠れたリスクとは?
これまで「HDLは高いほど良い」と信じられてきましたが、この常識を見直す必要があることを示唆する知見が近年次々と報告されています。これが「HDLのパラドックス」または「U字型リスクカーブ」と呼ばれる現象です。2023年前後に発表された複数の研究やメタアナリシスによると、HDLコレステロール値と死亡リスクの関係は直線的ではなく、U字型のカーブを描くことが示唆されています78。つまり、低すぎるのが危険なのはもちろんですが、極端に高すぎる場合(例えば90mg/dLや100mg/dLを超えるようなレベル)も、全死亡リスクや心血管疾患による死亡リスクが逆に上昇する可能性があるのです。
この現象の背景には、いくつかの原因が考えられています。一つは、コレステリルエステル転送蛋白(CETP)の欠損症など、遺伝的な要因によってHDLコレステロールが異常に高値となる場合です。この場合、HDL粒子が正常に機能していない「機能不全HDL」である可能性が指摘されています3。また、過度の飲酒など生活習慣に関連した要因が関与している可能性を示す報告もあります78。
したがって、単にHDLコレステロールの値が高いことを喜ぶのではなく、特に100mg/dLを超えるような異常高値の場合は、その背景にある原因や全体的なリスクプロフィールについて、医師と相談することが重要です。現時点のガイドラインでは「HDLが高いから下げる治療をする」という考え方は一般的ではありませんが、「なぜ高いのか」を確認することは、将来のリスクを見逃さないために大切な視点です。
HDLの「量」から「質」へ:最新科学が注目する「コレステロール引き抜き能(CEC)」
HDL研究の最前線では、健康診断で測定されるHDLコレステロールの「濃度(量)」だけでなく、その「機能(質)」こそが重要であるという考え方が主流になりつつあります。その質の指標として最も注目されているのが「コレステロール引き抜き能(Cholesterol Efflux Capacity, CEC)」です925。
CECとは、HDL粒子が血管壁の細胞(マクロファージなど)からどれだけ効率よくコレステロールを抜き取って回収できるか、という能力を直接測定したものです。複数の先進的な研究により、このCECの値が、従来のHDLコレステロール濃度よりも心血管イベントの発生をより強く予測する可能性があることが示されています810。つまり、HDLの数が多くても(高濃度でも)、個々のHDL粒子が「怠け者」であれば血管保護作用は弱く、逆に数が少なくても(低濃度でも)「働き者」であれば保護作用は強い、という可能性を示唆しています。
現時点ではCECは研究レベルの検査であり、一般的な健康診断や日常診療で測定されるものではありません。しかし、「HDLの値だけでは語りきれない部分がある」という視点は、今後の治療戦略の見直しにもつながる重要なテーマです。今のところ、私たちが日常生活のなかでできることは、ガイドラインに沿った生活習慣の改善やLDL・non-HDLコレステロールの管理を通じて、HDLの「量」と「質」の両方をできるだけ良い状態に保つことだと言えるでしょう。
どのくらいの頻度で検査を受ければよい?
日本では、40〜74歳を対象とした特定健診などで、年1回の脂質検査が行われることが一般的です15。一方で、すでに脂質異常症と診断されている方、糖尿病や高血圧、慢性腎臓病などの合併症がある方、心筋梗塞や脳卒中の既往がある方では、より短い間隔で検査が行われることもあります。
適切な検査頻度は、年齢や既往歴、現在の治療状況によって変わります。健診で「要精密検査」「要医療」と書かれていたり、薬を飲み始めた直後・変更した直後などは、医師の指示に従って再検査のタイミングを決めることが大切です。「前回より少し悪くなっている気がする」「家族に心筋梗塞になった人がいて心配」など、不安があるときも、早めに相談してみましょう。
第3部:HDLコレステロール値を改善するための具体的戦略
HDLコレステロール値の改善は、まずは生活習慣の見直しが基本となります。日本動脈硬化学会や米国心臓協会(AHA)などの国内外の権威機関は、科学的根拠に基づいた具体的な方法を推奨しています2429。ここでは、「何をどこから始めればよいか」をイメージしやすいように整理して紹介します。
1. 食事療法:科学的根拠に基づく食べ物の選び方
食事はHDLコレステロール値だけでなく、LDLや中性脂肪、体重などにも大きな影響を与えます。完璧を目指す必要はありませんが、次のポイントを少しずつ取り入れていくことで、脂質全体のバランスを整えやすくなります428。
- トランス脂肪酸を避ける: マーガリン、ショートニング、それらを使用したパン、洋菓子、揚げ物などに含まれるトランス脂肪酸は、HDLコレステロールを低下させ、LDLコレステロールを増加させる最も避けるべき脂肪です28。食品表示に「ショートニング」「加工油脂」などと書かれているものは取りすぎに注意しましょう。
- 飽和脂肪酸を控える: 肉の脂身、バター、ラードなどの動物性脂肪に多い飽和脂肪酸の過剰摂取は控えめにしましょう。脂身の少ない肉を選ぶ、揚げ物より蒸し料理や煮物を選ぶなど、日々の小さな工夫が積み重なります。
- 不飽和脂肪酸を積極的に摂る:
- 一価不飽和脂肪酸: オリーブオイル、アボカド、ナッツ類に多く含まれ、LDLコレステロールを下げつつHDLコレステロールの改善にも役立つとされています。
- 多価不飽和脂肪酸 (オメガ3系): サバ、イワシ、サンマなどの青魚に豊富なDHAやEPAが代表的で、心血管疾患リスクの低減効果が報告されています。
- 水溶性食物繊維を増やす: 玄米や麦などの全粒穀物、海藻、きのこ類、野菜、果物に豊富な水溶性食物繊維は、コレステロールの吸収を穏やかにし、non-HDLコレステロールの低下にも役立ちます。
- 砂糖や精製された炭水化物を摂りすぎない: 清涼飲料水、菓子パン、白パン、白米のとり過ぎは、中性脂肪の上昇を通じてHDLを下げる方向に働くことがあります。
- 日本食の活用: 魚介類、大豆製品(豆腐、納豆)、野菜、海藻を中心とした伝統的な日本食は、上記の条件を満たしやすく、脂質管理に非常に有用です4。毎食すべてを変える必要はなく、「1日1回は魚料理を取り入れる」「週に数回は大豆製品を主菜にする」といった現実的な目標から始めてみましょう。
2. 運動療法:最も効果的な運動の種類と頻度
定期的な運動は、HDLコレステロールを上昇させるうえで非常に効果的です。とくに推奨されるのは有酸素運動です26。厚生労働省やAHAは、中等度の強度の有酸素運動(早歩き、ジョギング、サイクリング、水泳など)を週に合計150分以上行うことを推奨しています29。これを1回30分、週5日といった形に分けても構いません。
「中等度の強度」とは、少し息が弾むが会話はなんとか続けられる程度の運動をイメージすると分かりやすいでしょう。いきなり激しい運動を始める必要はなく、
- エレベーターではなく階段を使う
- 一駅分歩く・自転車に乗る
- 休日に少し長めの散歩をする
といった身近な工夫から始めることでも、長期的には大きな差につながります。心臓病や関節の病気などをお持ちの方は、無理のない範囲や始め方について、主治医に相談してから取り組みましょう。
3. その他の生活習慣の改善:禁煙と節度ある飲酒
- 禁煙: 喫煙はHDLコレステロールを低下させる最大の要因の一つです。禁煙は、HDLを改善するための最も確実で効果的な方法の一つであり、心筋梗塞や脳卒中、がんなどのリスク低下にも直結します。禁煙後、数週間から数ヶ月でHDLコレステロール値の改善が見られると報告されています4。一人での禁煙が難しい場合は、禁煙外来や保険適用の禁煙補助薬なども活用できます。
- 節度ある飲酒: 適量のアルコール摂取はHDLコレステロールをわずかに上昇させる可能性が示唆されていますが、その効果は限定的であり、「HDLを上げるためにお酒を飲む」ことは推奨されません。日本人男性であれば1日あたり日本酒1合、ビール中瓶1本、ワイン2杯程度が目安とされますが、心疾患や肝臓病をお持ちの方、薬を服用している方ではより厳しい制限が必要な場合もあります。過度の飲酒は中性脂肪を著しく増加させ、他の健康問題も引き起こすため、厳に慎むべきです。
4. 体重管理・睡眠・ストレスケア
HDLコレステロールは、体重や内臓脂肪、睡眠の質、ストレスとも深く関わっています。肥満やメタボリックシンドロームでは、HDLが低く、中性脂肪が高いパターンがよくみられます1415。
- 急激な減量ではなく、半年〜1年かけて3〜5%程度の体重減少を目標にする
- 夜更かしや睡眠不足を避け、睡眠時間とリズムを整える
- ストレスが強い場合には、趣味や運動、相談窓口の利用などで「一人で抱え込まない」工夫をする
といった取り組みは、HDLコレステロールだけでなく、血圧や血糖などの改善にもつながります。職場や家庭の事情から生活を大きく変えるのが難しい場合も、できる範囲で少しずつ続けることが大切です。
5. 薬物療法が必要な場合
上記の生活習慣の改善を最大限行っても、遺伝的な要因などにより脂質の値が目標に達しない場合があります。特に、心筋梗塞などの既往がある方や、糖尿病、高血圧などの他の危険因子を多く持つハイリスクな方では、薬物療法が検討されます1619。スタチン系薬剤やフィブラート系薬剤などが用いられますが、これらは必ず医師の診断と処方の下で使用されるべきものです。
かつては、HDLコレステロールを直接上昇させる薬剤の開発も盛んに行われていましたが、現時点では「HDLを上げること自体」を目標とした治療によって心血管イベントが確実に減ると証明された薬剤は多くありません。そのため、ガイドラインでは、LDLコレステロールやnon-HDLコレステロールなど全体のリスクを下げることに重点が置かれています24。自己判断で薬を始めたり中断したりすることは絶対に避け、疑問点があれば遠慮なく主治医に相談しましょう。
6. 受診のタイミングと医療機関で相談できること
次のような場合には、早めに医療機関を受診して相談することをおすすめします。
- 健康診断で「要精密検査」「要医療」と書かれている
- HDLコレステロールが40mg/dL未満、あるいは反対に100mg/dLを超えるような値が続いている
- LDLコレステロールやnon-HDLコレステロールも高く、家族に心筋梗塞や脳卒中になった方がいる
- 糖尿病、高血圧、慢性腎臓病など、他の生活習慣病を複数抱えている
受診時には、健診結果の用紙を持参し、
- 自分のリスクが全体としてどのくらいなのか
- 生活習慣で優先的に変えたほうがよい点はどこか
- 薬物療法が必要かどうか、必要な場合のメリットとデメリット
といった点を一緒に整理してもらうとよいでしょう。「こんなことで受診してもいいのかな」と迷う必要はありません。不安や疑問があるときこそ、医療機関を活用していただきたいタイミングです。
よくある質問
サプリメントでHDLコレステロールは上がりますか?
DHA/EPAやナイアシン(ビタミンB3)などの一部の成分は、HDLコレステロールを上昇させる効果が報告されています。しかし、その効果は限定的であり、サプリメントだけで脂質異常症を治療することはできません。特にナイアシンは、医師の監督なしに高用量で摂取すると副作用のリスクがあるため注意が必要です。
基本はあくまで食事や運動などの生活習慣の改善であり、サプリメントは不足しがちな栄養素を補う「補助的な存在」と考えるのが安全です。使用を検討する場合は、現在服用している薬との飲み合わせも含めて、必ずかかりつけ医や薬剤師に相談してください。
HDLコレステロールだけが低いのですが、問題ありますか?
はい、問題があります。LDLコレステロールや中性脂肪の値が正常でも、HDLコレステロール値が40mg/dL未満の場合は「低HDLコレステロール血症」と診断され、独立した動脈硬化の危険因子となります11。これは「脂質異常症」の一つです。
血管のコレステロールを回収する力が弱い状態ですので、放置せずに運動や禁煙、体重管理などの生活習慣改善に積極的に取り組むことが強く推奨されます。すでに他の生活習慣病(糖尿病、高血圧など)がある場合や、家族に心筋梗塞・脳卒中の人がいる場合は、早めに医療機関で総合的なリスク評価を受けると安心です。
HDLコレステロールが高すぎる(例:120mg/dL)と言われました。放置しても大丈夫ですか?
HDLコレステロールの目標値はどのくらいを目指せばよいですか?
現時点の日本のガイドラインでは、「HDLコレステロールを何mg/dL以上にする」といった治療目標値は設定されていません24。一方で、40mg/dL未満は明らかなリスクとして位置づけられており、この値を上回ることが重要な目安となります。
一般的には、HDLが40mg/dL以上であり、かつLDLコレステロールやnon-HDLコレステロールがガイドラインで推奨される範囲にコントロールされていることが望ましいとされています1924。そのうえで、「たばこを吸わない」「運動習慣を持つ」「適正体重を維持する」など、全体として心血管リスクを下げる生活を続けていくことが大切です。具体的な目標値や優先順位は、年齢や持病によっても変わるため、主治医と相談しながら決めると安心です。
生活習慣を変えたら、どのくらいでHDLコレステロールは変化しますか?
個人差は大きいものの、禁煙や運動習慣の改善、減量などに取り組むと、数週間〜数ヶ月の単位でHDLコレステロールを含む脂質プロフィールの変化が見られることがあります429。ただし、「すぐに劇的に上がる」というよりは、じわじわと少しずつ改善していくケースが多いと考えられます。
大切なのは、「短期間で数値を下げる・上げる」ことだけを目標にするのではなく、長く続けられる生活習慣を身につけることです。3ヶ月〜半年ごとの検査結果を参考にしながら、無理のないペースで生活を整えていきましょう。なかなか改善しない場合も、自分を責めず、医師や管理栄養士などと相談しながら、できる工夫を一緒に見つけていくことが大切です。
結論
HDLコレステロールは、私たちの健康状態を映し出す重要な指標ですが、その解釈は決して単純ではありません。「低い」のは明確な危険信号ですが、「高ければ高いほど良い」というかつての常識は見直されつつあり、極端な高値や、見かけの数値の裏にある「質」の問題にも目が向けられるようになってきました。
最も重要なことは、健康診断の結果を放置せず、日本動脈硬化学会の最新ガイドライン24や厚生労働省などの科学的根拠に基づいた正しい知識を持つことです。そして、ご自身の数値を多角的に理解し、食事、運動、禁煙、体重管理といった具体的な生活習慣の改善につなげていくことが、心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気を防ぐための現実的で確かな一歩になります。
一人でインターネット情報を検索していると、「何が本当に正しいのか」「自分にはどれが当てはまるのか」が分からなくなってしまうことも少なくありません。不安や疑問があれば、かかりつけの医師や専門の医療機関に相談し、自分に合った管理方針を一緒に考えていきましょう。その際、本記事の内容が、医師と話し合うときの「準備」として少しでも役立てば幸いです。
免責事項 本記事は情報提供のみを目的としており、専門的な医学的助言を構成するものではありません。健康に関する懸念や、ご自身の健康や治療に関する決定を下す前には、必ず資格のある医療専門家にご相談ください。
参考文献
- 糖尿病ネットワーク. 見逃したくない検査値「non-HDLコレステロール」 糖尿病の治療は脂質管理も大切 [インターネット]. 2019 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://dm-net.co.jp/calendar/2019/029798.php
- 株式会社ケアプロ. HDLコレステロールとは?低くなるとどうなる?基準値を保つための習慣って? [インターネット]. 2024 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://carepro.co.jp/preventive/corporation/archives/7220/
- 株式会社ロッテ. HDLコレステロール値が高いとどうなる?健康への影響や原因を解説 [インターネット]. 2025 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://mediage.lotte.co.jp/post/321
- 医療法人社団 実正会. 【医師監修】善玉・HDLコレステロールとは?基準値と増やす食べ物・飲み物 [インターネット]. 2023 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/health-care/12820
- 株式会社ファルコバイオシステムズ. HDLコレステロール – 臨床検査案内 [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.falco.co.jp/rinsyo/detail/060068.html
- ソニー損保. コレステロールについて正しく知ろう【LDLとHDL】 [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.sonysonpo.co.jp/md/i_hch010.html
- Madsen CM, Varbo A, Nordestgaard BG. Association between extremely high-density lipoprotein cholesterol and risk of infectious disease. Front Cardiovasc Med. 2023;10:1201107. doi:10.3389/fcvm.2023.1201107
- Wang Y, He Z, Zhang J, Li T, Wang W, Liu Y. Association between the High-density Lipoprotein Cholesterol Efflux Capacity and the Long-term Prognosis in Patients with Coronary Artery Disease: A Meta-analysis. Chin Med J (Engl). 2024;137(8):969-976. doi:10.1097/CM9.0000000000003014
- Rosenson RS, Brewer HB Jr, Davidson WS, Fayad ZA, Fuster V, Goldstein J, et al. Cholesterol efflux and atheroprotection: advancing the concept of a guideline. Circulation. 2012;125(15):1905-19. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.111.066589
- Khera AV, Demler OV, Adelman SJ, Collins HL, Glynn RJ, Ridker PM, et al. Cholesterol Efflux Capacity, High-Density Lipoprotein Particle Number, and Incident Cardiovascular Events: An Analysis From the JUPITER Trial (Justification for the Use of Statins in Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin). Circulation. 2017;135(25):2494-2504. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.025678
- 浦安やなぎ通り診療所. 脂質異常症 (動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版において) [インターネット]. 2022 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://urayasu-yanagi.com/blog/%E8%84%82%E8%B3%AA%E7%95%B0%E5%B8%B8%E7%97%87%EF%BC%88%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E4%B8%AD%E6%80%A7%E8%84%82%E8%82%AA%E3%81%8C%E9%AB%98%E3%81%84%E6%96%B9-2/
- 荒井 秀典. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版の概要と,健診におけるコレステロール管理の留意点. 日本総合健診医学会誌. 2024;52(2):353-359. Available from: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhep/52/2/52_353/_article/-char/ja
- 生活習慣病オンライン. 脂質異常症の診断基準 [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.sageru.jp/ldl/knowledge/criterion.html
- 日本高血圧学会. 『よくわかる高血圧と循環器病の予防と管理 第二版 追補』 [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.jpnsh.jp/sidousi/files/addendum_book07.pdf
- 日本生活習慣病予防協会. 総コレステロール値が 240mg/dL以上は、男性 10.1%、女性 23.1%。non-HDLコレステロール平均値は、男性 139.0 mg/dL、女性 143.5 mg/dL 令和 5年(2023)「国民健康・栄養調査」の結果より [インターネット]. 2024 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://seikatsusyukanbyo.com/statistics/2024/010820.php
- 国立循環器病研究センター. 脂質異常症|国立循環器病研究センター冠疾患科 [インターネット]. 2022 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.ncvc.go.jp/coronary2/risk/dyslipidemia/index.html
- 国立循環器病研究センター. 脂質異常症|病気について|循環器病について知る|患者の皆様へ [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.ncvc.go.jp/hospital/pub/knowledge/disease/dyslipidemia/
- American Heart Association. My LDL Cholesterol Guide [インターネット]. 2019 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.heart.org/-/media/Files/Health-Topics/Cholesterol/My-LDL-Cholesterol-Guide.pdf
- American College of Cardiology. 2018 Guideline on the Management of Blood Cholesterol [インターネット]. 2018 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.acc.org/~/media/Non-Clinical/Files-PDFs-Excel-MS-Word-etc/Guidelines/2018/Guidelines-Made-Simple-Tool-2018-Cholesterol.pdf
- MedlinePlus. LDL: The “Bad” Cholesterol [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://medlineplus.gov/ldlthebadcholesterol.html
- National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation. 2002;106(25):3143-421.
- National Heart, Lung, and Blood Institute. ATP III Guidelines At-A-Glance Quick Desk Reference [インターネット]. 2002 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/atglance.pdf
- Cui, X., et al. Serum Cholesterol Levels and Risk of Cardiovascular Death: A Systematic Review and a Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(14):8272. doi:10.3390/ijerph19148272
- 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版 [インターネット]. 2022 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.j-athero.org/jp/jas_gl2022/
- de la Llera-Moya M, Asztalos BF, Koral D, Hembry AG, Rothblat GH. From HDL-cholesterol to HDL-function: cholesterol efflux capacity determinants. Curr Opin Lipidol. 2019;30(1):57-65. doi:10.1097/MOL.0000000000000569
- 厚生労働省. 脂質異常症 | e-ヘルスネット [インターネット]. 2019 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/metabolic/m-05-004.html
- 道北医療福祉センター. 動脈硬化性疾患予防ガイドラインが改訂されました~適切な血中脂質管理を目指して [インターネット]. 2022 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.do-yukai.com/medical/157.html
- MedlinePlus. How to Lower Cholesterol with Diet [インターネット]. [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://medlineplus.gov/howtolowercholesterolwithdiet.html
- American Heart Association. Life’s Essential 8 – How to Control Cholesterol Fact Sheet [インターネット]. 2022 [引用日: 2025年7月19日]. Available from: https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-lifestyle/lifes-essential-8/how-to-control-cholesterol-fact-sheet
: