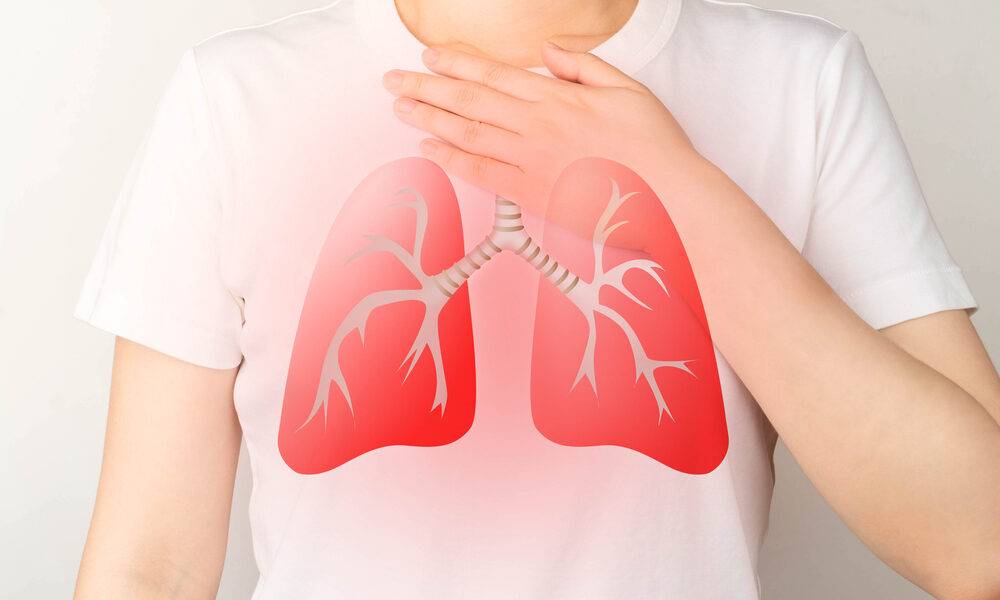胸水は、肺の外側にある胸膜腔(きょうまくくう)という空間に液体が異常にたまる状態です。原因は心不全から感染症、がんまで多岐にわたります。Light基準などを含む検査で原因を正確に見きわめ、原因疾患の治療と胸水の排出を組み合わせて対処することが重要です。息切れや胸の痛みが続く場合は、早めに専門医の診察を受けることをお勧めします。
本記事はJHO編集部がAIを活用して編集・検証しました。外部の医師・専門家の関与はありません。国内の公的機関、主要な学会のガイドライン、査読付き学術論文など、一次情報源としての信頼性が高い情報を優先して参照しています。すべての事実に関する主張の直後には、出典を示す脚注を配置しています。また、リンクの到達可能性や情報の鮮度も定期的に確認し、必要に応じて内容を更新しています。
この記事の要点
- 胸水は肺を包む胸膜腔への液体の異常貯留であり、原因の鑑別(滲出性か漏出性か)が治療方針を決定する上で最も重要です。
- 初期鑑別の基盤となるLight基準は、感度98%、特異度83%と非常に有用な指標です。
- 胸腔穿刺は超音波ガイド下で行うことで合併症を低減できますが、一度に1,000~1,500mLを超える急速な排液は再膨張性肺水腫のリスクに注意が必要です。
- 再発性の悪性胸水に対しては、留置胸腔カテーテル(IPC)による在宅管理やタルクを用いた胸膜癒着術が重要な選択肢となります。
- 息切れや胸痛などの症状が現れた場合は自己判断せず、速やかに呼吸器専門医のいる医療機関を受診することが推奨されます。
胸水の不安を解消する:原因解明と治療への道
突然の息苦しさや胸の痛みを感じたとき、「もしかして肺に水がたまっているのでは?」と不安になるのは当然のことです。特に、横になると息が苦しい、咳が止まらないといった症状は、日常生活に大きな影を落とし、深刻な病気が隠れているのではないかという恐怖心を煽ります。
これらの症状は、体が発する重要なサインです。呼吸器全体の仕組みや疾患の全体像を把握することで、ご自身の症状を客観的に見つめ直すことができます。まずは、呼吸器疾患完全ガイドを参照し、胸水がどのような位置づけにあるのかを確認してみてください。
胸水がたまる原因は一つではありません。心不全による水分の漏出や、感染症・がんによる炎症など、その背景は多岐にわたります。なぜご自身の肺に水がたまってしまったのか、そのメカニズムと原因疾患について理解を深めるために、胸水貯留の原因とメカニズムに関する詳細な解説をご覧ください。
診断の第一歩は、画像検査によって「水」の存在と状態を正確に把握することです。特に胸部レントゲン検査は、初期診断において非常に重要な役割を果たします。胸水におけるX線検査の役割を知ることで、検査に対する不安を和らげ、医師の説明をより深く理解できるようになります。
治療方針が決まれば、具体的な対処が始まります。医療機関での治療に加え、ご自宅での過ごし方や症状を和らげるための工夫も大切です。入院治療だけでなく、効果的な胸水治療と在宅ケアについて学ぶことで、療養生活の質を高めることができます。
特に注意が必要なのは、一度改善しても再び胸水がたまる「再発」のリスクです。がん性胸水などの場合、再発を繰り返すことがあります。どのような場合に再発しやすいのか、またその予防策はあるのか、胸水の再発と対策についての知識を持っておくことは、長期的な病気との付き合いにおいて非常に重要です。
胸水は原因に応じた適切な治療を行えば、症状をコントロールできる病態です。息切れや痛みを我慢せず、早めに専門医に相談してください。正しい知識と適切なケアが、あなたの呼吸を楽にし、安心した生活を取り戻すための鍵となります。
1. 胸水とは何か? ― 肺の外側に水がたまる状態
胸水とは、専門的には胸膜腔(きょうまくくう)と呼ばれる、肺を覆う膜(臓側胸膜)と胸壁の内側を覆う膜(壁側胸膜)との間のスペースに、液体が異常に貯留した状態を指します。12
1.1. 胸水の定義と正常な胸水の役割
実は、健康な人の胸膜腔にも、ごく少量の液体(正常胸水、約10~20mL)が存在します。1この液体は、私たちが呼吸をする際に肺が胸壁に対してスムーズに膨らんだり縮んだりするための「潤滑油」としての重要な役割を果たしています。1胸水は、この液体の産生と吸収のバランスが何らかの原因で崩れ、異常に量が増加してしまった病的状態なのです。
1.2. 胸水と肺水腫の違い ― 水がたまる場所が異なる
「肺に水がたまる」という表現は、しばしば「胸水」と「肺水腫(はいすいしゅ)」を指すことがあり混同されがちですが、これらは液体がたまる場所が根本的に異なります。34胸水が肺の“外側”(胸膜腔)にたまるのに対し、肺水腫は肺の“内側”、つまり酸素と二酸化炭素のガス交換を行う肺胞(はいほう)という小さな袋の中に液体があふれ出た状態です。34症状や治療法も異なるため、両者を正確に鑑別することが治療の第一歩として極めて重要です。
| 特徴 | 胸水 (Pleural Effusion) | 肺水腫 (Pulmonary Edema) |
|---|---|---|
| 水がたまる場所 | 胸膜腔(肺と胸壁の間) | 肺胞(肺の内部) |
| 主な原因 | がん、感染症、心不全、肝硬変など52 | 心不全(特に左心不全)、腎不全など4 |
| 主な症状 | 呼吸困難、胸の圧迫感、乾いた咳1 | 急激な呼吸困難、ピンク色の泡のような痰、喘鳴4 |
| 治療の方向性 | 原因疾患の治療、胸水の排出(ドレナージ) | 利尿薬、酸素投与、心機能のサポート |
2. 胸水が生じる主な原因 ― なぜ水がたまるのか?
胸水が生じる原因を特定するため、医学的にはまず胸水をその性状によって「漏出性(ろうしゅつせい)」と「滲出性(しんしゅつせい)」の二つに分類します。126この分類は、数ある原因の中から真の原因を絞り込むための、非常に重要な第一歩となります。
2.1. 胸水の分類:漏出性胸水と滲出性胸水
この分類は主に、胸水に含まれるタンパク質の濃度に基づいて行われます。6簡単に言うと、漏出性胸水はタンパク質が少なくサラサラした液体で、胸膜自体は健康であるものの、全身の体液バランスの異常が原因で生じます。一方、滲出性胸水はタンパク質が多くドロドロした液体で、胸膜自体の炎症や病変が直接的な原因となります。12この鑑別のために、後述するLight基準(Light’s criteria)という指標が世界的に用いられています。
2.2. 漏出性胸水の主な原因疾患
漏出性胸水は、血管内の圧力(静水圧)が上昇するか、血液中に水分を保持する力(膠質浸透圧)が低下することで、血管から液体成分が胸膜腔へ漏れ出して生じます。2主な原因疾患は以下の通りです。
- うっ血性心不全: 心臓のポンプ機能が低下し、体内の血液が滞る(うっ血する)ことで血管内の圧力が上昇し、液体が胸膜腔に漏れ出します。12日本の高齢化に伴い、心不全を原因とする胸水患者は増加傾向にあります。7
- 肝硬変: 肝臓の機能が著しく低下すると、血液中の主要なタンパク質であるアルブミンの産生が減少します。アルブミンは血管内に水分を保持する働きがあるため、これが低下すると水分が血管外に漏れやすくなります。12
- 腎不全(特にネフローゼ症候群): 腎臓から大量のタンパク質が尿中に失われ、低アルブミン血症となることで、肝硬変と同様のメカニズムで胸水が生じます。32
- 低アルブミン血症: 上記以外にも、重度の栄養失調などが原因で血中のアルブミンが低下し、胸水を引き起こすことがあります。3
2.3. 滲出性胸水の主な原因疾患
滲出性胸水は、胸膜そのものが炎症や腫瘍によって障害され、血管の壁の透過性が高まることで、タンパク質や細胞成分を多く含む液体が漏れ出して生じます。2原因は極めて多岐にわたります。
- 感染症:
- 悪性腫瘍(がん):
- がん性胸膜炎: 肺がんや乳がん、悪性リンパ腫などが胸膜に転移(胸膜播種)したり、がんがリンパの流れを塞いだりすることで胸水が生じます。52
- 悪性中皮腫: 胸膜自体から発生するがんで、アスベスト(石綿)への職業的あるいは環境的曝露が主な原因とされます。8
日本における傾向:日本呼吸器学会の報告によると、国内の胸膜炎の原因としてはがん性胸膜炎と結核性胸膜炎が多く、全体の約60~70%を占めるとされています。5また、アスベスト曝露歴は悪性中皮腫を疑う上で極めて重要な情報です。 - その他: 膠原病(関節リウマチなど)、肺血栓塞栓症、外傷、腹部疾患(膵炎など)も原因となり得ます。152
3. 胸水の症状 ― こんなサインに要注意
胸水の症状は、貯留する液体の量、たまる速さ、そして原因疾患によって様々です。少量のうちは無症状のこともありますが、量が増えるにつれて肺が圧迫され、特徴的なサインが現れます。
3.1. 代表的な自覚症状
- 息切れ(呼吸困難): 最も一般的で重要な症状です。胸水が肺を圧迫し、十分に膨らめなくなることで起こります。10はじめは階段や坂道での息切れ(労作時呼吸困難)として現れ、量が増えると安静時にも息苦しさを感じるようになります。
- 胸痛: 特に深呼吸や咳をした際にズキッとする鋭い痛み(胸膜性胸痛)を感じることがあります。これは、炎症を起こした胸膜が呼吸のたびにこすれるために生じます。9
- 咳: 痰を伴わない乾いた咳(乾性咳嗽)が続くことが多いです。
- その他の全身症状: 原因疾患によっては、発熱、体重減少、全身の倦怠感などを伴うことがあります。1患者報告アウトカム(PROM)に関する研究でも、呼吸困難がQOL(生活の質)に最も大きな影響を与える症状であることが示されています。11
受診の目安
以下のような症状がある場合は、自己判断せずに速やかに呼吸器専門の医療機関を受診してください。12
- 今すぐ受診:新規の胸痛、高熱、急な呼吸困難。
- 数日内に受診:労作時の息切れ、乾いた咳、体重減少が続く場合。
- 専門医へ相談:悪性腫瘍の既往歴がある、あるいはアスベスト曝露の可能性がある場合。
3.2. 他覚的所見(医師が診察で気づくこと)
医師が診察(聴診や打診)を行うと、以下のような所見が認められることがあります。
- 呼吸音の減弱・消失: 胸水がたまっている側の胸部では、聴診器を当てても肺の音が聞こえにくくなります。132
- 打診での濁音: 胸部を指で叩くと、正常な肺では太鼓のような共鳴音がしますが、液体がたまっている部分は鈍い音(濁音)になります。1314
3.3. 原因疾患に伴う症状
胸水の症状に加え、原因となっている病気特有の症状が同時に現れることも診断の重要な手がかりです。例えば、心不全では足のむくみ(下肢浮腫)、肝硬変では黄疸や腹水、感染症では高熱や膿性の痰、がんでは長引く咳や血痰、急な体重減少などが挙げられます。1
4. 胸水の診断 ― 原因を特定するための検査
胸水の診断では、まず胸水の存在を画像で確認し、次にその原因を特定するために胸水を採取して分析することが重要です。そのため、段階的に様々な検査が行われます。
4.1. 問診と身体診察
診断の第一歩は、患者さんから症状や病歴を詳しく伺うことです。いつからどのような症状があるか、過去の病歴(心臓病、肝臓病、がん、結核など)、職業歴(アスベスト曝露の可能性)、服用中の薬などを詳細に確認します。15その後、前述の聴診や打診で胸水を示唆する所見を確認します。
4.2. 画像検査
画像検査は、胸水の有無、量、広がりを客観的に評価するために不可欠です。
4.2.1. 胸部X線撮影 (レントゲン)
最も基本的で重要な検査です。192胸水はX線を通しにくいため、たまっている部分は白く写ります。通常は鋭角である肋骨と横隔膜の角(肋骨横隔膜角)が鈍くなり、量が増えると三日月状の陰影が見られます。
4.2.2. 胸部超音波検査 (エコー)
X線では分かりにくい少量の胸水の検出や、胸水の性状(サラサラか、隔壁があるかなど)の評価に非常に優れています。15162また、放射線被ばくがなく、リアルタイムに観察できるため、後述する胸腔穿刺を安全に行うためのガイドとして極めて重要な役割を果たします。超音波ガイドにより、気胸などの合併症が減少し、穿刺の成功率が向上することが複数の研究で示されています。17
4.2.3. 胸部CTスキャン
胸水の詳細な評価に加え、肺、胸膜、縦隔などの状態を断層写真で詳しく観察できるため、原因疾患の特定に非常に有用です。1218特に、肺がんなどの腫瘍性病変や肺血栓塞栓症の診断には欠かせません。
4.3. 胸水検査(胸腔穿刺)
画像検査で胸水が確認された場合、原因を特定するために、注射針を刺して胸水を直接採取する「胸腔穿刺(きょうくうせんし)」が行われます。
4.3.1. 胸腔穿刺の目的と手技
胸腔穿刺は、①診断(採取した胸水の分析)と、②治療(多量の胸水を抜いて呼吸困難を和らげる)の二つの目的で行われます。1152現在は超音波ガイド下で安全な穿刺部位を確認しながら行うのが標準的です。局所麻酔をするため痛みは軽微ですが、気胸(肺に穴が開く)や出血などの合併症リスクを伴います。1217
4.3.2. 胸水の生化学検査とLight基準
胸水が「漏出性」か「滲出性」かを鑑別するため、世界標準の指標であるLight基準(Light’s criteria)が用いられます。121519これは胸水と血液中のタンパク質とLDH(乳酸脱水素酵素)の値を比較するもので、感度約98%、特異度約83%と非常に信頼性が高い基準です。19
- 胸水タンパク質/血清タンパク質 比 > 0.5
- 胸水LDH/血清LDH 比 > 0.6
- 胸水LDH値 > 血清LDH基準上限の2/3
上記の3項目のうち1つでも満たせば「滲出性胸水」と判断されます。
4.3.3. 胸水の細胞学的検査(細胞診)
採取した胸水を顕微鏡で観察し、悪性細胞(がん細胞)の有無を調べます。がん性胸水の確定診断に不可欠な検査です。156リンパ球が多ければ結核やがん、好中球が多ければ細菌感染など、細胞の種類も原因のヒントになります。156
4.3.4. その他の胸水検査
原因に応じて、さらに詳細な検査が行われます。例えば、結核性胸膜炎が疑われる場合はADA(アデノシンデアミナーゼ)という酵素の値が非常に参考になり、国内の報告では40 U/L前後が診断の一助となることがあります(施設基準に依存)。1520
4.4. 胸膜生検
胸水検査を行っても診断が確定しない場合、特にがんや結核が強く疑われる際には、胸膜の組織そのものを採取して調べる「胸膜生検(きょうまくせいけん)」が行われます。11520局所麻酔下で胸腔鏡という内視鏡を用いて行う方法が、診断率が高く広く行われています。
5. 胸水の治療法 ― 症状緩和と原因へのアプローチ
胸水の治療は、二つの大きな柱で成り立っています。一つは胸水がたまる根本原因となっている病気を治療すること(原因療法)、もう一つはたまった胸水を取り除いて息苦しさなどの症状を和らげること(対症療法)です。1210これらは多くの場合、並行して進められます。
5.1. 原因疾患に対する治療(原因療法)
最も根本的な治療は、胸水を引き起こしている原因疾患をコントロールすることです。
- 感染症(肺炎、膿胸、結核など): 原因菌に対し、効果的な抗菌薬や抗結核薬を投与します。521
- 悪性腫瘍(がん性胸水): がんの種類に応じ、化学療法(抗がん剤)、分子標的治療、免疫療法などが行われます。51622
- 心不全: 利尿薬で体内の余分な水分を排出させるとともに、心臓の負担を軽くする薬を使用します。32塩分・水分制限も非常に重要です。
- 肝硬変・腎不全: 利尿薬や食事療法(塩分制限など)で体液バランスを管理します。12
5.2. 胸水除去(ドレナージ)
呼吸困難などの症状が強い場合、原因治療と並行して、たまった胸水を体外へ排出する処置が行われます。
5.2.1. 胸腔穿刺(治療的穿刺)
診断時と同様に針を刺して胸水を吸引除去し、症状を速やかに緩和します。1162
5.2.2. 胸腔ドレナージと胸膜癒着術
繰り返し貯留する胸水(特にがん性胸水)には、胸に細いチューブ(ドレーン)を留置し、持続的に排液します。12その後、ドレーンからタルクなどの薬剤を注入し、肺と胸壁を癒着させて胸水がたまるスペースを閉鎖する胸膜癒着術を行うことがあります。3122
5.2.3. 留置胸腔カテーテル(IPC)と在宅管理
近年、特に再発性悪性胸水の管理で重要性が増しているのが留置胸腔カテーテル(IPC: Indwelling Pleural Catheter)です。1624柔らかいカテーテルを体内に留置し、退院後は自宅で患者さん自身やご家族が定期的に排液できるようにするシステムです。25頻繁な通院や入院を避けられ、QOL(生活の質)の維持に大きく貢献します。1624
最新の動向(BTS 2023ガイドライン)
英国胸部疾患学会(BTS)の2023年ガイドラインでは、IPCとタルク胸膜癒着術の使い分けについて言及しています。IPCは特に肺が十分に広がらない(被包化肺)症例や、在宅での管理を希望する患者さんにとって良い選択肢です。また、IPCからの排液を毎日少量ずつ行う(daily drainage)ことで、自然に胸膜癒着が起こる確率が高まる可能性も示唆されています。26
5.3. 外科的治療と補助療法
薬剤が効かない難治性の膿胸や、一部の悪性中皮腫などでは、胸腔鏡や開胸による手術が検討されることがあります。225これらと並行し、症状緩和のために酸素吸入、鎮痛薬、呼吸リハビリテーション、栄養管理なども行われます。
6. 胸水の治療期間と回復の見通し(予後)
治療期間と回復の見通し(予後)は、胸水の原因、重症度、治療への反応性、患者さんご本人の年齢や全身状態など、多くの要因によって大きく異なります。
- 急性疾患が原因の場合(肺炎など): 適切な抗菌薬治療により、数週間から数ヶ月で改善することが多いです。ただし、膿胸に至ると治療は長期化します。
- 慢性疾患が原因の場合(心不全など): 基礎疾患のコントロールが主体となり、生涯にわたる長期的な管理が必要となることが少なくありません。
- 悪性腫瘍(がん)が原因の場合: がん性胸水は進行がんの兆候であり、一般的に予後は厳しいとされます。5海外の報告では生存期間の中央値は3~12ヶ月とされていますが1622、これはあくまで平均的なデータです。近年の分子標的薬や免疫療法の進歩により、予後が改善するケースも増えています。治療の目標は、症状を緩和し、患者さんのQOLをできる限り高く維持することが中心となります。
7. 胸水が続く場合のリスクと合併症
胸水が慢性的に貯留すると、胸膜が厚く硬くなり肺の膨らみを妨げる「胸膜肥厚」や、肺が硬い膜で覆われて膨らめなくなる「被包化肺(ひほうかはい)」といった合併症を引き起こすリスクがあります。1これらの合併症は呼吸機能を著しく低下させる可能性があるため、早期診断と適切な介入が重要です。
8. 日常生活でのケアとセルフマネジメント
胸水の治療中や退院後の生活では、病状を安定させ、再発を防ぐための自己管理が大切です。
- 栄養管理と食事療法: 体力を保つため、バランスの取れた食事が基本です。1原因疾患によっては、医師や管理栄養士の指導のもと、塩分制限(心不全、腎不全など)や水分制限が必要になります。1
- 呼吸訓練・理学療法: 状態が安定したら、医師や理学療法士の指導のもと、口すぼめ呼吸や腹式呼吸といった呼吸訓練や、軽い運動を行うことが呼吸機能の維持・改善に繋がります。
- 感染予防: 感染症は胸水の増悪因子となります。手洗いやうがい、人混みを避けるなどの基本的な感染対策を徹底しましょう。
- 症状変化の早期発見: 息切れの悪化、咳の増加、発熱など、体調の変化に気づいたら、自己判断せずに早めに主治医に相談することが非常に重要です。
健康に関する注意事項
- この記事で提供される情報は、一般的な知識の提供を目的としており、個別の医学的アドバイスに代わるものではありません。
- 息切れ、胸痛、持続する咳などの症状がある場合は、自己判断せず、必ず速やかに医療機関を受診し、医師の診断と治療を受けてください。
よくある質問 (FAQ)
胸水と肺水腫の違いは?
胸水は肺の外側(胸膜腔)に、肺水腫は肺の内側(肺胞)に液体が貯留する点で根本的に異なります。原因や症状、治療法も異なるため、正確な鑑別が重要です。
Light基準とは?
胸水が「滲出性」か「漏出性」かを3つの条件で判定する世界的な指標です。3項目のうち1つ以上を満たせば滲出性と判断され、その感度は約98%、特異度は約83%とされています。
どの症状なら受診すべきですか?
これまでにない胸の痛み、発熱、急な息切れなどがある場合は、すぐに呼吸器専門の医療機関を受診してください。また、安静にしていても息苦しい、咳が続く、体重が減るといった場合も早めの受診が推奨されます。
胸腔穿刺は安全ですか?
超音波ガイド下で行うことで、気胸(肺に穴が開く)などの合併症のリスクが大幅に減少し、安全性が向上します。複数の研究で、超音波ガイドが安全性と成功率を改善させることが示唆されています。17
高齢者で注意すべき点は?
高齢者では複数の病気を抱えていることが多く、症状が典型的でない場合があります。また、多くの薬を服用していることによる影響も考慮が必要です。侵襲的な検査や治療は、全身の状態やご本人の意思を尊重し、慎重に検討されます。
結論
胸水は、それ自体が病気なのではなく、体の中で起きている何らかの異常を知らせる重要なサインです。その原因は心不全のような慢性疾患から、肺炎のような急性感染症、そして悪性腫瘍まで、極めて多岐にわたります。したがって、単に「肺の水を抜く」だけでなく、なぜ水がたまったのか、その根本原因を正確に診断し、原因に応じた適切な治療を行うことが何よりも重要です。息切れや胸の痛みなど、気になる症状があれば、決して放置することなく、専門医に相談してください。正しい知識を得て、ご自身の状態を理解し、主体的に治療に参加することが、より良い未来への第一歩となります。
免責事項:この記事は医学的アドバイスに代わるものではなく、症状がある場合は専門家にご相談ください。
参考文献
- 国立病院機構 近畿中央呼吸器センター. 胸水. https://kcmc.hosp.go.jp/shinryo/kyousui.html. 参照 2025-10-08. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
- MSDマニュアル プロフェッショナル版. 胸水. https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/05-pulmonary-disorders/mediastinal-and-pleural-disorders/pleural-effusion. 参照 2025-10-08. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
- 同仁会クリニック. 高齢者の肺に水がたまった場合の余命とは? 胸水と肺水腫の違いも…. https://dojin.clinic/column/4914/. 参照 2025-10-08. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
- 公益財団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット. 高齢者の胸水・肺水腫. https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/rounensei/kyousui.html. 参照 2025-10-08. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
- 日本呼吸器学会. G-01 胸膜炎 – G. 胸膜疾患. https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/g/g-01.html. 参照 2025-10-08. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
- Nickson C. Pleural Fluid Analysis. Life in the Fast Lane. 2020. https://litfl.com/pleural-fluid-analysis/. Accessed Oct 8, 2025. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
- 厚生労働省. 入院・外来医療等の調査・評価分科会 これまでの検討結果 【別添】資料編②. https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001161691.pdf. 参照 2025-10-08. ↩︎
- 厚生労働省. 表1-1 労災保険法に基づく保険給付の石綿による疾病別請求・決定状況. e-Stat. https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040150098&fileKind=2. 参照 2025-10-08. ↩︎
- 厚生労働省. 重篤副作用疾患別対応マニュアル 薬剤性胸膜炎. https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1b45.pdf. 参照 2025-10-08. ↩︎ ↩︎ ↩︎
- Merck Manual Consumer Version. Pleural Effusion. https://www.merckmanuals.com/home/lung-and-airway-disorders/pleural-and-mediastinal-disorders/pleural-effusion. Accessed Oct 8, 2025. ↩︎ ↩︎
- Mishra EK, et al. Patient-Reported Outcomes in Pleural Effusions: A Systematic Review. Cureus. 2024;16(1):e52927. doi:10.7759/cureus.52927. ↩︎
- 日本呼吸器学会. Q25. 胸部エックス線画像で異常があり、胸水がたまっていると言われました。. https://www.jrs.or.jp/citizen/faq/q25.html. 参照 2025-10-08. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
- 西条すこやか内科. 胸に水が溜まる(胸水). https://saijo-sukoyaka-clinic.com/blog/pleural-effusion/. 参照 2025-10-08. ↩︎ ↩︎
- Dev SP, Nici MW, et al. Pleural Effusion. In: The Rational Clinical Examination: Evidence-Based Clinical Diagnosis. McGraw-Hill; 2009. ↩︎
- Karkhanis VS, Joshi JM. Pleural Effusion. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448189/. Accessed Oct 8, 2025. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
- Psallidas I, et al. Management of Malignant Pleural Effusion in 2024: A Definitive and Unified Global Approach. JCO Oncology Practice. 2024. doi:10.1200/OP.24.00925. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
- Gordon CE, et al. Ultrasound-guided thoracentesis. Chest. 2010;137(4):817-824. doi:10.1378/chest.09-1763. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
- Ghattas C, et al. Non-Malignant Pleural Effusions: A Narrative Review of Classification, Diagnosis, and Management. Medicina (Kaunas). 2024;60(3):443. doi:10.3390/medicina60030443. ↩︎
- Heffner JE, Brown LK, Barbieri CA. Diagnostic value of tests that discriminate between exudative and transudative pleural effusions. Chest. 1997;111(4):970-980. doi:10.1378/chest.111.4.970. ↩︎ ↩︎
- 鈴木 純子, 他. 当院における胸腔鏡下胸膜生検で診断した結核性胸膜炎12例の臨床的検討. 北里医学. 2022;52(1):1-5. doi:10.5691/kitasatoigaku.52.1. ↩︎ ↩︎ ↩︎
- 日本感染症学会, 日本化学療法学会. JAID/JSC 感染症治療ガイドライン―呼吸器感染症. 2016. https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/guideline_jaid_jsc.pdf. 参照 2025-10-08. ↩︎
- Porcel JM, Fiszman S. Malignant Pleural Effusion: Diagnosis and Treatment—Up-to-Date Perspective. Cancers (Basel). 2024;16(11):507. doi:10.3390/cancers16110507. ↩︎ ↩︎
- PDQ® Adult Treatment Editorial Board. Malignant Pleural Effusion Treatment (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries [Internet]. Bethesda (MD): National Cancer Institute (US); 2002-. https://www.cancer.gov/types/lung/hp/malignant-pleural-effusion-treatment-pdq. Accessed Oct 8, 2025. ↩︎ ↩︎
- Reddy C, et al. Management strategies for recurrent pleural effusion: a clinical practice review. AME Med J. 2023;8:14. doi:10.21037/amj-22-68. ↩︎ ↩︎ ↩︎
- 日本緩和医療学会. がん患者の呼吸器症状の緩和に関するガイドライン(2011年版). https://www.jspm.ne.jp/files/guideline/respira_2011/04_01.pdf. 参照 2025-10-08. ↩︎ ↩︎
- Roberts ME, et al. British Thoracic Society Guideline for pleural disease. Thorax. 2023;78(Suppl 3):s1-s42. doi:10.1136/thorax-2023-220302. ↩︎
更新履歴
最終更新:2025年10月08日(Asia/Tokyo) ― 詳細を表示
-
日付:2025年10月08日(Asia/Tokyo)編集者:JHO編集部変更種別:P0, P1, P2 (包括的レビューに基づく全面改訂)対象範囲:記事全体変更内容(要約):参照情報の統一・修正、定量的データ(Light基準の感度/特異度、ADA参考値等)の追加、最新ガイドライン(BTS 2023)の要点反映、可読性向上のための段落分割、FAQセクションの新設、およびE-E-A-T強化のための構成変更を実施しました。根拠:JP-ADAPT v4.4J 準拠総合レビュー理由:EVIDENCE-LOCK/Japan-fit/最新情報の反映引用・単位:SI単位・母集団補正なしリンクチェック:OK品質確認:編集部で再校し、出典とリンク到達性を再確認しました。監査ID:JHO-REV-20251008-842